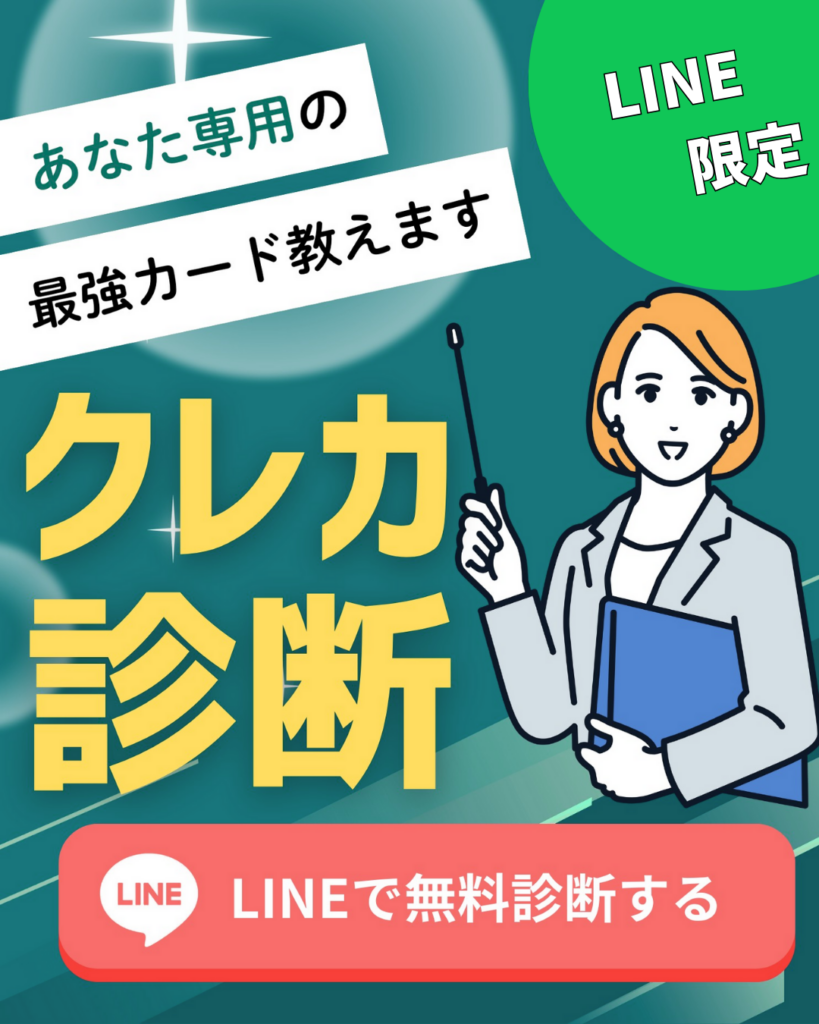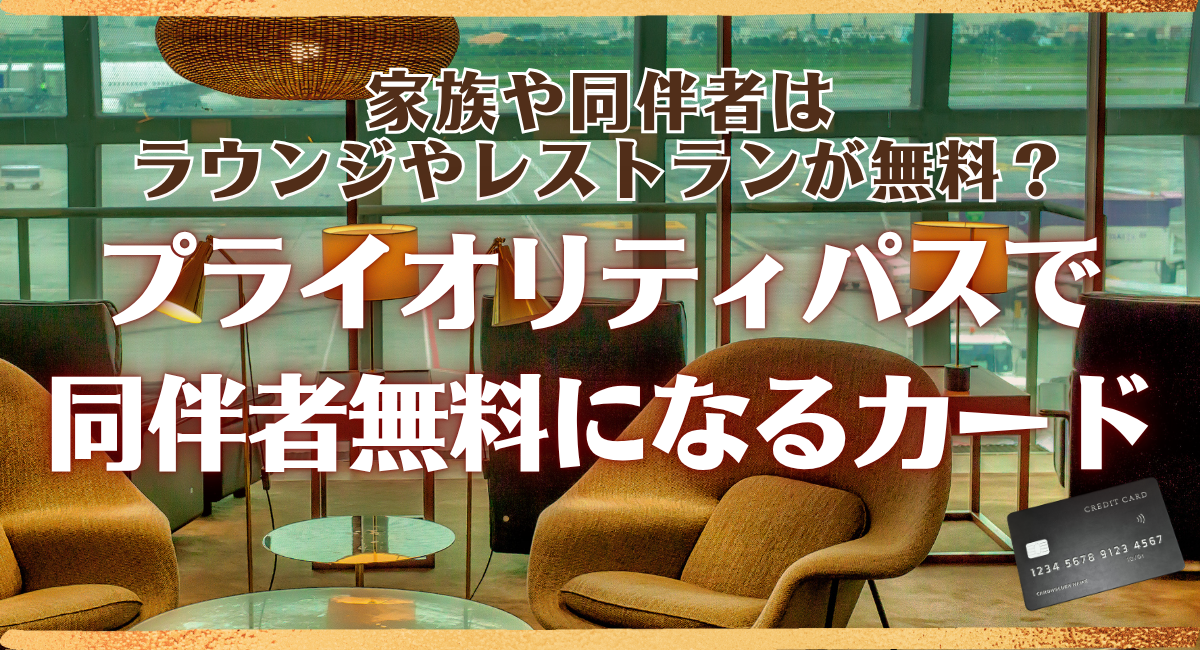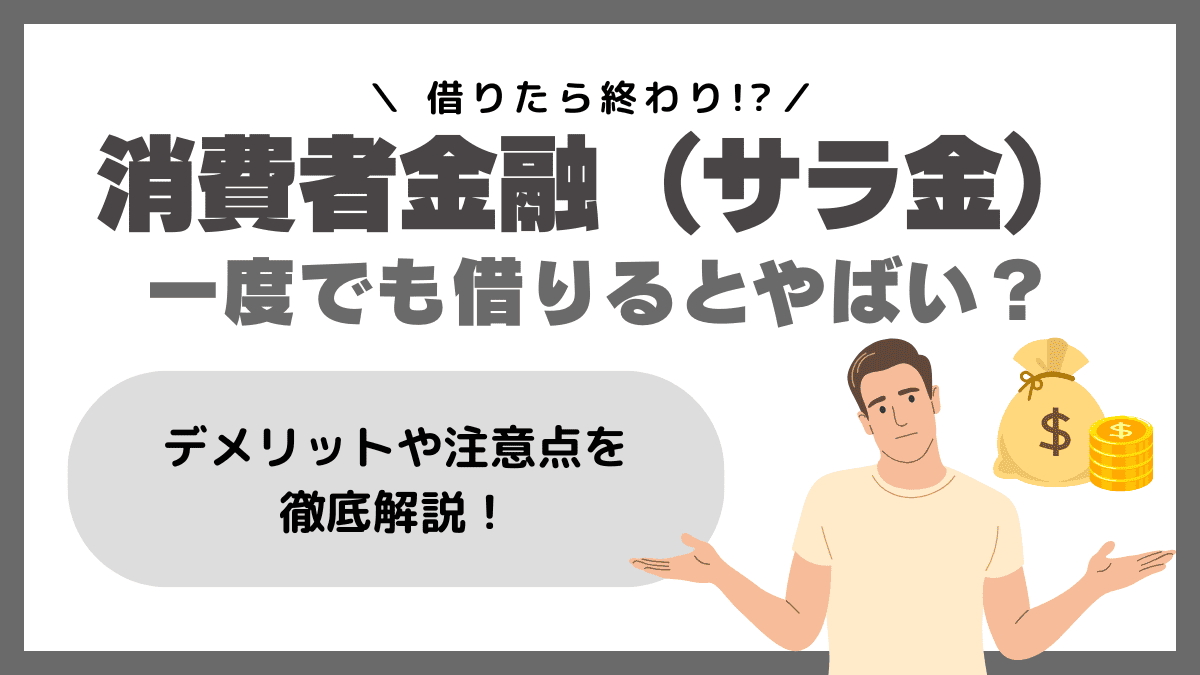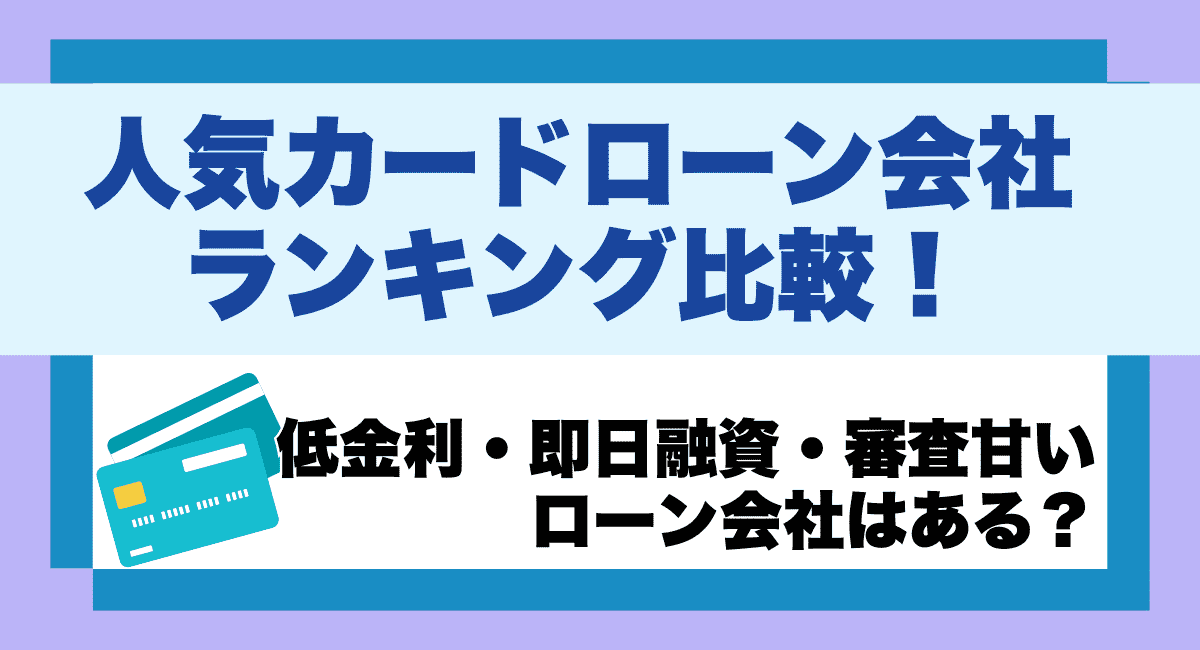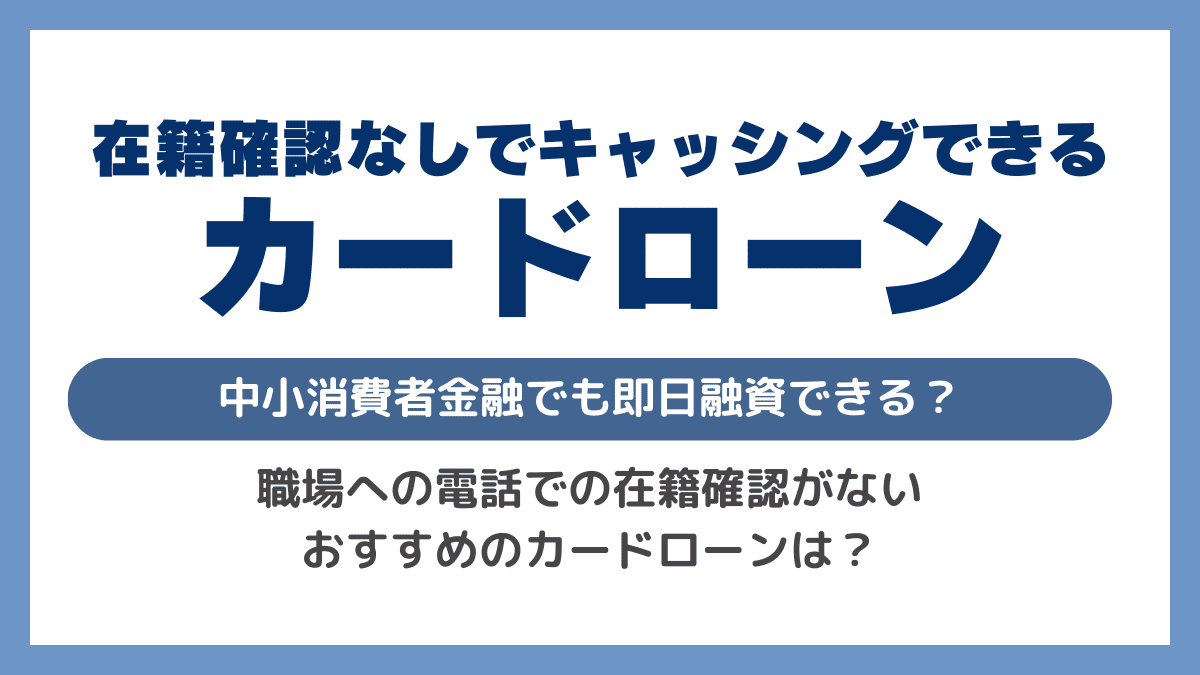ねじれ国会とは、衆議院と参議院で多数派の政党が異なることで、国会の意思決定がスムーズに進まなくなる状態を指します。
法案が通りづらくなったり、政治の混乱が長引いたりする一方で、与党の独断を防ぎ多様な意見を反映しやすくなる側面もあります。
ニュースで耳にする機会が多いものの、仕組みや影響について正確に理解している人は少なくありません。
ねじれ国会の意味や背景、実際に起きた事例までを解説していきます。
【まずは選挙の仕組みをおさらい!】
・衆議院と参議院の違いは?任期・人数・役割・なぜ2つあるのかを小学生にもわかりやすく簡単に解説!
・与党と野党の違いは?それぞれの役割や衆議院・参議院選挙との関係をわかりやすく解説!
・出口調査とは何か・意味あるのか簡単に解説!当選確実の仕組みや速報がはずれたことはないのか徹底調査
目次
ねじれ国会とは何?定義と概要を解説
ねじれ国会とは、衆議院と参議院で多数派の政党が違う状態のことをいいます。
これが起こると、法律や予算などの重要な決定がスムーズに進みにくくなるのです。
そもそも日本の国会は「二院制」といって、衆議院と参議院という2つの議会があります。
衆議院は任期が4年で解散があり、参議院は6年任期で3年ごとに半数が改選されます。
このしくみの違いによって、選挙のタイミングや国民の判断がずれて、片方では与党が多数、もう片方では野党が多数というようなねじれが起こるのです。
実際、ねじれ国会の状態では、与党だけで法案を通すことができないため、他の政党と話し合いながら進める必要が出てきます。
これが政治のスピードを遅らせる原因になる一方で、一つの政党の意見だけで物事が決まらないという点では、慎重な議論を促す良い面もあります。
つまり、ねじれ国会とは「国会が2つに分かれていることで、政治にブレーキとアクセルの両方がかかるような状態」といえるのです。
ねじれ国会はなぜ起こる?
ねじれ国会は、衆議院と参議院で多数派が分かれることで生まれます。
これは「選挙のタイミング」と「有権者の意識の違い」という2つの要因によって引き起こされるのです。
衆参それぞれの選挙制度や任期が変わってくるため、国民の政権に対する評価が変わるタイミングもずれがちです。
また、有権者が参議院選挙では衆議院とは違う視点で投票することも、ねじれを生む一因になります。
この章では、そうした背景を解説していきますので、「なぜ起こるのか」がきちんと理解できます。
選挙のタイミングが異なっていてその時々で政権に対する評価が変わるから
ねじれ国会が起こる大きな理由の一つは、衆議院と参議院の選挙が別々のタイミングで行われることにあります。
衆議院は解散があるため政権交代のたびに選挙があり、参議院は3年ごとに半分ずつ改選される仕組みです。
このズレがあるため、たとえば衆議院選挙で与党が勝っても、その後に参議院選挙があれば、政権への評価が変わって野党が勝つということがよくあります。
選挙のたびに国民の意見や社会の空気も変化するため、どちらか一方でしか多数を取れない状態=ねじれ国会が生まれやすくなるのです。
制度上のズレと、有権者の評価の変化が重なることで、ねじれが自然に発生してしまうというわけです。
有権者の衆議院と参議院に対する投票意識が違ってくるから
もう一つの理由は、有権者が衆議院選挙と参議院選挙に対して「投票の意味合い」を変えて考えていることです。
衆議院選挙は「この政党に国のかじ取りを任せたい」という、いわば政権選びの場です。
一方、参議院選挙はすでにできた政権がしっかり働いているかを「チェックする」役割が強くなります。
そのため、「衆議院では与党を選んだけど、参議院ではあえて野党に入れてバランスを取りたい」と考える人も少なくありません。
このように、同じ有権者でも選挙ごとに異なる視点で投票するため、結果として衆参の多数派が食い違い、ねじれ国会が生まれやすくなるのです。
ねじれ国会によるメリットは?一番は与党の暴走を防ぐことができる点
ねじれ国会には、「政治が停滞する」というイメージがありますが、実は民主主義にとって大事な役割も果たしています。
最大のメリットは、与党が一方的に物事を決めるのを防ぎ、バランスの取れた政治を保てることです。
この章では、ねじれ国会によって得られる3つのプラス面を解説していきます。
「本当に悪いことばかりなの?」と疑問を持つ方にこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。
抑制や均衡といった二院制のメリットが大いに発揮される
ねじれ国会の最大のメリットは、与党が暴走しないよう「政治にブレーキがかかる」ことです。
本来、国会が衆議院と参議院の二つに分かれているのは、物事を慎重に決めるため。これを「抑制と均衡(チェック&バランス)」といいます。
ねじれ国会のときは、衆議院だけで決めたことでも、参議院でストップがかかる可能性が高くなります。
その結果、与党が強引に法案を通すことが難しくなり、多くの意見を取り入れた形で再調整せざるをえません。
もちろん政治のスピードは落ちるかもしれませんが、それによって一方的な政策が通りにくくなるという意味では、民主主義を守る「安全装置」として機能していると言えるでしょう。
野党の発言力が増し議論が活性化する
ねじれ国会では、野党の存在感が一気に高まります。
というのも、参議院で野党が多数を占めていると、与党が単独では法案を通すことができず、野党と真剣に話し合う必要があるからです。
その結果、国会ではさまざまな視点がぶつかり合い、より深くて多面的な議論が行われるようになります。
これはまさに、国会が「言論の府」としての役割をしっかり果たしている状態とも言えます。
与党と野党がきちんと議論し合うことで、国民にとってよりよい法案や制度が生まれる確率も高くなるのです。
政治に多様な声が届きやすくなるという意味では、ねじれ国会は“無駄”どころか、必要な摩擦とも言えるかもしれません。
さまざまな国民の意見を幅広く反映させることができる
ねじれ国会が生まれるということは、国民の意見が一枚岩ではなく、多様であることの表れでもあります。
衆議院と参議院で投票先が違うというのは、それぞれの場面で国民が別の判断をしているということです。
それによって国会の中に幅広い意見が入りやすくなり、少数派や特定の地域の声も無視されにくくなります。
特に、参議院は全国区や地方区を含む構成のため、地域ごとの課題や少数意見が通りやすくなる側面もあります。
ねじれた状態だからこそ、与党以外の考え方も無視できなくなり、多様な価値観が政策に活かされるのです。
ねじれ国会によって生じる影響・デメリット
ねじれ国会にはメリットもありますが、現実にはさまざまなデメリットも発生します。
最大の問題は、与党と野党の意見がぶつかってしまい、法案がスムーズに通らなくなることです。
その結果、政治が停滞したり、対立が激しくなったりして、国民の生活に関わる決定が先送りされる事態も起きかねません。
この章では、ねじれ国会がもたらす3つの主な悪影響について、わかりやすく整理して解説します。
法案がなかなか通らなくなってしまう
ねじれ国会の最も深刻な影響の一つが、「法案が通りにくくなること」です。
衆議院と参議院で多数派の政党が違うと、衆議院で可決された法案が参議院で否決されることがあります。
もちろん憲法59条には、衆議院の再可決で法案を成立させる手続きもありますが、これは現実には簡単ではありません。
予算案や条約の承認のように「参議院の同意が必要なもの」も多く、スムーズな政治運営に大きな影響を及ぼします。
その結果、重要な政策が後回しになり、国民生活にも悪影響が出る恐れがあります。
与野党の対立が激化し政治が不安定になってしまう
ねじれ国会になると、与党と野党の間の緊張が高まり、対立が激しくなる傾向があります。
特に、参議院で野党が主導権を持つと、政権の動きにブレーキをかける力が強まり、政策の実現が難しくなることがあります。
そうなると、与党側も「どうにか通したい」と強行的な姿勢を見せ、野党側はそれに反発する、という悪循環に陥りやすいのです。
こうした状態が続くと、国会が“議論の場”ではなく“対立の場”として機能してしまい、政策どころではなくなるという不安定さが生じます。
国民の政治に対する不信感が強まってしまう
政治がなかなか動かない状態が続くと、国民の中には「また国会でモメてるのか」「どうせ何も決まらない」とあきらめる声が増えてきます。
これが、ねじれ国会のもう一つの大きなデメリット、「政治不信」の悪化です。
議論が長引くこと自体は悪いことではありませんが、それが結果的に何も決まらないという状況につながると、信頼は失われていきます。
特に、災害対策や景気対策のようなスピードが求められる場面で足踏みしてしまうと、「政治は私たちの生活を守ってくれない」と感じてしまう人も多いでしょう。
政治が国民の期待に応えられない状態が続けば、投票率の低下や無関心にもつながり、民主主義の根幹が揺らいでしまいます。
ねじれ国会は最近いつ起こったか紹介
ねじれ国会は「たまにしか起きない特別な状態」と思われがちですが、実は近年でもたびたび発生しています。
その理由をより理解するためには、「いつ、どんな状況でねじれが起こったのか」を具体的に知ることが重要です。
特に1998年・2007年・2010年の参議院選挙では、与党が参議院で過半数を失い、国会のねじれが生じました。
それぞれの状況で、政権の支持率や社会の空気がどう影響したのかも含めて確認しておくと、ねじれ国会の背景がぐっとわかりやすくなります。
1998年7月の参議院議員選挙
1998年の参議院選挙では、当時の与党・自民党が大きく議席を減らし、ねじれ国会が初めて本格的に生まれました。
背景には、当時の橋本内閣による消費税の引き上げ(3%→5%)や景気の低迷、金融危機など、国民生活への不安がありました。
その影響で、有権者の「政権への不満」が選挙に強く表れ、自民党は単独過半数を失います。
この結果、自民党は野党だった自由党(小沢一郎氏が率いていた)と連立を組むことで、かろうじて政治の安定を図りました。
この選挙は、ねじれ国会の「はじまり」とも言える重要な出来事で、以後の選挙でもねじれが起きやすくなる前例となったのです。
2007年7月の 参議院議員選挙
2007年の参院選は、当時の安倍政権にとって大きな転機となりました。
この選挙の直前、年金記録漏れ問題(いわゆる「消えた年金」)が発覚し、政府への信頼が大きく揺らぎました。
さらに、閣僚の失言や相次ぐスキャンダルも影響し、自民党に対する批判が強まっていました。
その結果、民主党が自民党を大きく上回る議席を獲得し、参議院では野党が多数派となる「ねじれ国会」が成立します。
このねじれによって法案審議が難航し、安倍首相はわずか1年で辞任に追い込まれました。
選挙結果が政権そのものを揺るがすほどのインパクトを持つことを、まざまざと見せた例と言えるでしょう。
2010年7月の 参議院議員選挙
2010年の参議院選挙では、与党である民主党が大きく議席を減らし、再びねじれ国会が生まれました。
この選挙のきっかけとなったのは、鳩山由紀夫首相の辞任と、それに続いて就任した菅直人首相による突然の「消費税率引き上げ」発言です。
この発言が国民に「増税ありきの政治」という印象を与え、民主党の支持率が急落しました。
結果、民主党は単独での参議院過半数を失い、野党との協力なしには法案が通らない状態になりました。
このねじれ状態が長期化し、以降の民主党政権(特に野田政権)では重要法案が次々と停滞しました。
結果的に政権交代(2012年)への流れを強めることになります。
「ねじれ」が政権の体力を削り、政治の主導権を失わせた象徴的な選挙となりました。
ねじれ国会はどうしたら解消するのか解説
ねじれ国会は自然に解消されるものではなく、意図的な対応が必要です。
その主な方法は「衆議院の解散総選挙」か「他党との連立」の2つです。
なぜなら、参議院の構成はすぐに変えられないため、衆議院側で状況を動かすか、協力体制を築くしかないからです。
どちらの方法にもメリット・デメリットがあるため、状況によって最適な選択が求められます。
この章では、それぞれの対応方法について、仕組みや現実的な影響をわかりやすく解説していきます。
衆議院の解散総選挙を行う
ねじれ国会を解消するもっとも直接的な方法は、衆議院を解散して総選挙を行うことです。
参議院は任期が決まっていてすぐに解散できないため、構成を変えるには衆議院を動かすしかありません。
選挙によって国民の意見をもう一度問い、衆議院で与党が圧倒的多数を取ることができれば、参議院の反対を乗り越えて法案を通す力を持てるようになります。
ただし、選挙には費用や時間がかかり、与党にとっては勝敗が読めないリスクもあります。
他党と連立を組む
もう一つの方法は、他党と連立を組んで参議院でも安定多数を確保することです。
ねじれ国会では与党が単独で法案を通せないため、協力関係を築くことでスムーズな政治運営を目指します。
たとえば1999年には、自民党が公明党や保守党と連立を組み、ねじれ状態を解消しました。
この方法のメリットは、選挙を行わずに比較的早く安定を取り戻せる点です。
しかし、連立を組むためには、政策のすり合わせや譲歩も必要になるため、与党が本当にやりたいことが制限されるリスクもあります。
とはいえ、「多数派をつくるために意見をすり合わせる」という行為自体が、民主主義の基本であり、国会の健全な運営にもつながるといえるでしょう。
ねじれ国会についてのよくある質問
ねじれ国会に関する疑問は多く、ニュースでよく耳にするものの、制度的なしくみや影響までは詳しく知らないという人も多いのではないでしょうか。
この章では、「法案は通りづらくなるの?」「衆議院の優越ってなに?」「海外にもあるの?」など、読者が感じがちな素朴な疑問に答えていきます。
ここを読めば、ねじれ国会の全体像がよりはっきりと見えてくるはずです。
ねじれ国会時の法案成立率はどう変わる?
ねじれ国会になると、法案の成立率は明らかに下がる傾向があります。
理由は、衆議院で可決された法案が、参議院で否決されたり棚ざらしにされたりするからです。
たとえば、通常時の法案成立率は平均で80〜90%程度と高い水準にありますが、2010年〜2012年の民主党政権下では成立率が50%台まで落ち込んだこともあります。
成立率が下がると、重要な法律が進まず、社会の制度や支援が追いつかない事態も起こり得ます。
ただし、すべてがマイナスとは限らず、拙速な法案にブレーキをかける役割もあるため、一概に「悪」とも言い切れません。
ねじれ国会はどうしてニュースでよく取り上げられるの?
ねじれ国会は政治の流れを左右する大きな出来事なので、ニュースでも頻繁に取り上げられます。
その理由は、与党が法案をスムーズに通せなくなることで、政権運営が大きく揺らぐからです。
実際、2007年の参院選後のねじれでは、安倍首相がわずか1年で辞任に追い込まれました。
このように、ねじれは政治の“非常事態”ともいえる状態であり、国民の生活に直結するため、報道の注目度も自然と高くなるのです。
ねじれ国会と衆議院優越ってどう関係しているの?
ねじれ国会の中でよく出てくるキーワードの一つが「衆議院の優越」です。
これは日本国憲法によって定められた仕組みで、衆議院の決定が参議院よりも強い効力を持つ場合があるというものです(憲法59条など)。
ねじれ国会のとき、法案が参議院で否決されても、衆議院で3分の2以上の賛成があれば再可決が可能です。
この制度は、政治の完全な行き詰まりを防ぐ「最後の切り札」ですが、使うにはハードルが高く、与党の力だけでは届かないことも多いため、万能ではありません。
海外でもねじれ国会のような制度はあるの?
日本と同じく二院制を採用している国は世界にもいくつかあり、その中でもアメリカは日本のねじれ国会に近い状況がよく見られます。
たとえば、アメリカでは下院と上院で別々に選挙が行われるため、大統領の所属政党と異なる政党が議会の一部を支配するケースが珍しくありません。
その結果、法律の成立や予算の可決が思うように進まず、政権が足止めを食うこともあります。
ただし、アメリカでは大統領が行政のトップとして強い権限を持ち、議会と独立して行動できる点が日本とは大きく異なります。
一方、日本のような議院内閣制では、国会のねじれが内閣の動きに直結するため、政権全体が立ち往生する可能性が高くなります。
つまり、日本のねじれ国会は「制度のつくりそのものが弱点になりやすい」構造になっていると言えるのです。
ねじれ国会が長引くと国民生活にはどんな影響がある?
ねじれ国会が長引くと、政治の意思決定が遅れ、国民の生活にもじわじわと影響が出てきます。
例として、子育て支援や最低賃金の引き上げといった政策が議論ばかりで実行されず、現場に必要な支援が届かないといったことが起こり得ます。
また、災害時の緊急対応予算が通りにくくなると、復興や支援が遅れるおそれもあります。
政治の停滞は、じかに財布や暮らしに関わってくる問題なのです。
だからこそ、ねじれ国会が単なる政治用語ではなく、「私たちの日常にも影響するリアルなテーマ」であることを、多くの人に知ってもらう必要があると考えます。
まとめ
ねじれ国会とは、衆議院と参議院で多数派の政党が異なる状態のことで、政治の意思決定に大きな影響を及ぼします。
二院制の仕組みにより、与党の暴走を防ぐというメリットがある一方で、法案が通りにくくなったり、政権運営が不安定になったりするというデメリットもあります。
ねじれは主に選挙のタイミングや有権者の投票意識の違いから生じ、過去にもたびたび発生してきました。
衆議院の解散総選挙や他党との連立によって解消が図られることもありますが、長期化すれば国民生活にも悪影響を与えるおそれがあります。
そのため、制度の正しい理解と、冷静で柔軟な対応が重要となります。
この記事を書いた人
エレビスタ ライター
エレビスタは「もっと"もっとも"を作る」をミッションに掲げ、太陽光発電投資売買サービス「SOLSEL」の運営をはじめとする「エネルギー×Tech」事業や、アドテクノロジー・メディアなどを駆使したwebマーケティング事業を展開しています。
エレビスタは「もっと"もっとも"を作る」をミッションに掲げ、太陽光発電投資売買サービス「SOLSEL」の運営をはじめとする「エネルギー×Tech」事業や、アドテクノロジー・メディアなどを駆使したwebマーケティング事業を展開しています。