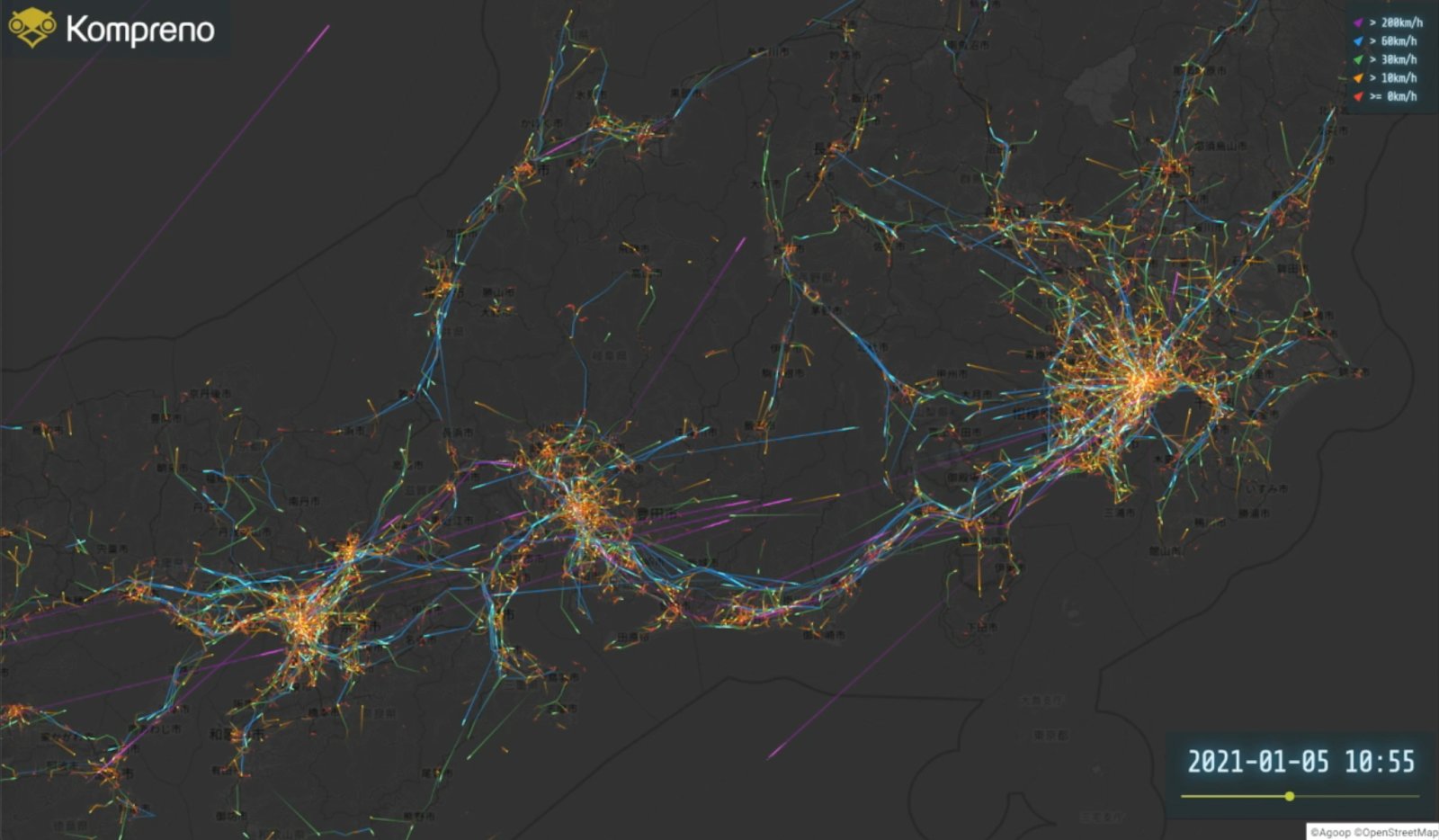株式会社ダイビック 代表取締役 野呂浩良さん インタビュー

野呂浩良
大学卒業後、小売業販売職、法人営業職を経て、29歳で業界未経験からプログラミング技術を習得。IT業界へ飛び込むことに。すべてのペインはテクノロジーで解決できると信じ、日常生活のあらゆる無駄を排除すべく12年間、欠かさず毎日ストップウォッチで生活をモニタリング。そこでのヒントを活かして、最短期間でスキルを習得できるエンジニアスクールを創業。今では、年間100人以上のエンジニアリング未経験の生徒が相談に訪れる、行列のできるアドバイザーとしても有名。「逆境からいつでも未来は切り拓ける」をモットーに、場所や経験による格差をなくすべく、「世界にIT教育と雇用機会を広げる」ことを掲げ、国内外に活動の幅を広げる。最近ではラテンアメリカ、アフリカでのITエンジニア独立支援にも力を入れる、日本で唯一の人材である。
目次
introduction
IT業界未経験でも、ITスキルを学びキャリア転換を目指せるプログラミングスクール「ディープロ(DPro)」を運営する株式会社ダイビック。
日本国内だけでなく、アフリカでもITスキルを提供し、どんな人でもテクノロジーを学び、活躍する機会が得られる社会を目指しています。
今回は、代表取締役の野呂浩良さんに、アフリカでの取り組みを中心に、企業理念について、事業内容や目指す世界などについてお話をうかがいました。
日本でも世界でも新しい分野に挑戦する機会を作りたい
–はじめに、株式会社ダイビックのご紹介をお願いします。
野呂さん:
株式会社ダイビックは、オンラインプログラミングスクールとして2015年4月に創業しました。
主な事業は、IT業界での経験がない人がスキルを身につけ、システムエンジニアやプログラマーにキャリア転換するためのスクール「ディープロ(DPro)」の運営です。
現在はそれに加えて、企業でのDXやリスキングなどの研修事業、システム開発の受託開発なども手掛けています。
また、どんな人でもチャレンジできる世界を目指せるように、アフリカでもエンジニア養成を行っています。

–では、御社の理念についてお聞かせいただけますか。
野呂さん:
私は、どんな状況や環境にあったとしても、いろいろなことに挑戦する機会が持てる社会を作りたいと思い、「すべての人が、テクノロジーを武器にして活躍できる社会をつくる」を理念として掲げています。
日本では、今や転職は当たり前です。それでも、30歳を過ぎて今までのキャリアと全く違った職種への転職や、40歳過ぎてからの転職は、まだまだ難しいのが現状です。
特にITやAIなど、どんどん新しく発展する分野に挑戦したくても、あきらめてしまう人も多くいると思うんです。そんな状況を変え、何歳からでも、どんな背景があっても挑戦できる機会があり、仕事に繋げられるような道を作りたいと思っています。
そして事業に取り組む中で、この理念は、SDGsの掲げる目標と重なる部分があることに気がつきました。
現在は特に、目標4「質の高い教育をみんなに」、目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」この2つを意識して事業に取り組んでいます。
弊社の理念とSDGsへの考えに基づいて、アフリカなどの途上国でも同様に、新しい分野に挑戦する機会を得られる社会にしたいと考えています。
物語の偉人のようにかっこよく社会を良くする活動がしたい!
–アフリカには以前から興味を持っていたのですか。
野呂さん:
興味はあったのですが、全く違う分野でした。
私は生き物が好きで、動物などのTV番組をよく見ていました。すると、高い確率でアフリカが出てくるんです。それでいつか行ってみたいと思っていました。
もう一つ、子どもの頃に野口英世やシュバイツァーなどの偉人伝が好きでよく読んでいました。ここにもガーナやガボンというアフリカの国が出てきていたんです。この時に読んだ本に出てくる主人公たちの生き方が、すごくかっこいいと思い、ずっと心に残っていました。
この思いが、社会を良くするような活動をしたいという、私の取り組みの根底にあると思います。
–ここからは、アフリカで展開されているエンジニア養成を中心にお話をうかがいたいと思います。まず、アフリカで事業を行うようになった経緯を教えてください。
野呂さん:
最初に、会社を立ち上げたきっかけから話しますね。
私は創業前、仕事をしながら経営を体系的に学ぶために、グロービス経営大学院に通っていたのですが、そこでの経験が会社設立のきっかけとなりました。
同級生には起業を目指す人たちが大勢いました。その人たちと話をする中で、「こんなものを作りたいんだけど、プログラマーやシステムエンジニアがいないから作れない」という話をたくさん聞いていました。
私は、大学院に通う以前、全く経験がないところからIT業界に転職した経験があるんです。とても大変でしたが、ゼロから学んでスキルを身につけました。ですから、同級生の話を聞き、「人がいなくてできないのなら、自分がすればいいんじゃないか」と思ったんです。
それで、「自分でできる方法を教えてあげるから、やってみたら」と声をかけ、セミナーのような形で勉強会を開きました。すると、たくさんの人たちが来てくれたんです。
《大学院時代》

この時に、「プログラミングを教えることは、夢に近づく機会を提供したり、人生の価値を上げたりするようなサポートができるとても面白い仕事だ」と思ったことが起業につながりました。この経験が現在の弊社の理念にも繋がっていると思います。
そして起業後、セミナー受講を検討する人向けの事前講座の時に、自己紹介で自分の夢を毎回話していたんです。「これからIT業界は、未経験の方でも仕事につけるようになる。日本だけでなく、いつかは発展途上のアフリカで事業展開するのが夢だ」と必ず話していました。
そして2017年、アフリカに関連のある会社に勤めている受講生が、ルワンダで子ども向けのIT教育に取り組んでいるNPOに紹介してくれ、間接的な接点ができました。
それが、アフリカでプログラミングを教える第一歩になりました。
日本でもアフリカでもITのスキルを学び就職への道を切り開く
–では、アフリカで最初にプログラミングを教えた後、どのように事業を展開したのか教えてください。
野呂さん:
最初にプログラミングを教えたのは、ルワンダで現地の施設を借り、現地への往復のフライト含めて5日程の短い期間でした。
その後、準備期間を経て、2019年にクラウドファンディングで資金を集め、プロジェクトとして約半年間、プログラミングスクールを開催しました。
《ルワンダでのスクールの様子》


この実績をもとに、現在は2つの事業を進めています。1つ目が、IT系の大学と提携して提供している大学生への寄付講座です。
この寄付講座は、現地の大学や生徒からはお金はもらわず、経済産業省からの予算で運営しています。
海外産業人材育成協会(AOTS)を通して、経済産業省のODA予算(開発途上国の経済社会開発支援を目的とした政府開発援助のための予算)を申請し、寄付活動に充てています。弊社は、この予算を管理運営し、教育・学習機会の提供、インターンシップの機会・雇用機会を提供しています。
生徒は、各国のIT系の大学の在校生が中心で、弊社が運営している日本の学校の教材を英語やフランス語に翻訳したものをオンライン上で学習します。
講義もオンラインツールを使って現地で受講してもらい、提出物は、弊社のルワンダ人の現地スタッフが採点・評価などすべて行います。
卒業後は、インターンシップの機会を提供したり、弊社のスタッフとして働いてもらったりする方もいますし、期間限定の日本企業のプロジェクトに関わる方、現地企業に就職する方もいます。
《大学での授業の様子》

–もう一つの事業はどのようなものですか。
野呂さん:
もう一つは、民間企業と提携している事業です。現地の民間企業と契約を締結して、日本では私たちが直接日本人の受講生に教えているように、 現地スタッフが現地の受講生に、有料あるいは無料で講座を提供しています。
有料の場合は学校としてきちんと運営する。
無料の場合は、卒業後の仕事を斡旋したり、学校内の仕事をやってもらうことで、 経営が成り立つようにするビジネスモデルです。 弊社は教材の提供と講師の教育をし、生徒への授業は現地企業が行います。
これはすでに実績があり、ベナンで長年パートナーを結んでいる企業や、ケニアやモザンビーク、モンゴルなどにもビジネスパートナーがいます。
《ビジネスパートナーの方々》


–これらの事業に取り組むうえで大事にしていることなどはありますか。
野呂さん:
日本、アフリカに関わらず、弊社のプログラムを受講する方たちは、ただスキルを勉強したいわけではなく、それを使って仕事を得ることを目的にしています。仕事を得て、こんな人生を歩んでいきたいという希望を持っています。
ですから、仕事を得て、そこできちんと活躍してもらわないと意味がないんです。
教材や講座を提供するだけではだめなんです。「今のままでは仕事では通用しないですよ」など厳しいことも言わないといけない。
特にアフリカでは、大学を卒業しても就職することは厳しいという現実があります。卒業から就職までに3年くらいかかるのが通常です。就職するまで、アルバイトをしたり、インターンシップを何回も受けたりするようです。
これは、そもそも「企業の数が多くないこと」、「企業が成長していないこと」が背景にあると思います。主産業が、農業の国がほとんどで、しかも家族経営の農家ばかりです。企業でも人を多く雇うのは難しく、新卒採用もなく、欠員補充くらいなんです。
しかし、こんな状況の中でも、ITを使って事業を伸ばしたい企業はある程度ありますから、弊社のスクールで勉強した方たちには、IT業界での就職の機会をつかんでもらうことが重要だと考えサポートしています。
日本の社会課題を解決することでアフリカや日本の人材利用につながる
–今まで事業に取り組んできて、成果は感じられますか。
野呂さん:
はい。この活動を始めて7年になりますが、日本の企業に就職する方が出てきたことが一番実感している成果です。
スキルはもちろんですが、弊社が提供する講座を最後まできちんと終了し、真面目にコツコツと続けてきたことが評価されたのだと思います。このような才能と適性を持った人がいて、きちんと働けるということが証明でき、今後に続く道につながると思うと、効果を実感しますね。
また、弊社内の効果ですと、ルワンダのスタッフが、日本人受講生の課題評価や質問対応などを担当するようになったことです。
プログラミングの世界では共通語は英語ですから、そこは問題ありません。
今は、AIなども発達し、翻訳も以前よりは簡単になったので、日本語ですべて対応できるようになりました。
この結果を見ると、アフリカの課題を解決したいと思って始めた取り組みですが、日本での少子高齢化社会での労働力不足など、国内の課題解決にも繋がるのではないかと考えています。
アフリカ人、日本人に雇用の機会を作るには、やはり日本の企業、社会の課題解決に役立つ事業をすることが重要だと考えています。日本の企業・社会に役に立つためにITを使う。そのITスキルに日本人とアフリカ人がともに取り組んでいくことが必要だと思うんです。
今後は、日本の社会の役に立つようなことにも積極的に参加していきたいですし、人材の受け皿をたくさん作る努力も必要だと考えています。
–では、アフリカだけでなく、他にも取り組んでいる事業などあれば教えてください。
野呂さん:
現在日本で展開しているスクールでのユニークな取り組みをご紹介します。
日本のスクールの生徒たちが取り組んでいる、卒業課題です。
日本の地方には、IT化がまったく進まない、人手が足りない、DXをする人材がいないなど様々な悩みを抱える企業や自治体がたくさんあります。
そんな地方へ行き、企業や地場産業などのIT化をお手伝いするということを卒業課題にしています。これは日本の中でも新しい取り組みだと思います。
例を一つ上げますね。
山梨県の富士吉田市は、かつて機織り産業が非常に盛んで、世界的な大手ブランドに服の生地を提供するほど有名だったそうです。大量生産というよりは、丁寧に品質の高い生地を作る土地で、工場・染物屋、問屋などが多くありました。しかし、ここ30年くらいは知名度もなくなり、衰退していました。そして、人材も予算もないのでIT化もされてなく、まだアナログですべての作業をしていました。
スクールでは、この織物産業をIT化することを学生たちの卒業課題にしました。
地元の企業と協業し、在庫管理、ECサイトでの販売、ホームページで注文を受ける、お客様とのコミュニケーションのツールなどを作る作業などを手掛けました。もちろん生徒たちは無償で取り組みます。
《卒業課題の取り組み》


企業の方に喜んでいただいたことはもちろん、学生にとっては実務経験になるので、就職活動に直結します。
このように、IT化したい企業や自治体は数多くあるので、日本人だけでなく、アフリカなどの人材の活躍の場になる可能性は大きいと思いますし、社会課題を解決できるのではないかと考えています。
–それでは、最後に今後どのように事業を展開していくのか、展望をお聞かせください。
野呂さん:
現在の日本は、失われた30年などと言われ、人口も減少し、成長しない社会が当たり前になっています。しかし世界を見ると、人口も若者も増え、経済成長しているんです。
日本は殻に閉じこもってしまっているようですよね。
私は、世界と積極的につながり、海外のマーケットに挑戦していけば、もっとお金を稼ぐこともできると考えています。
ですから、日本のノウハウを使った新しいものを世界の人たちと一緒に作っていく、まだ発展途上だけれど、そこのビジネスを日本と繋げていく。閉じこもっているだけでなく、いい形で仲間と一緒に繋がり、次の挑戦の機会があると思える世界にしたいと考えています。
特に若い人たちには、そんな社会を作る挑戦を一緒にしてほしいと思います。
そして、アフリカの仕事やITと言えばダイビックと認識してもらえるように、弊社の活動が、人材育成と雇用の創出につながる存在になりたいと考えています。
–今後の取り組みがとても楽しみですね。本日はありがとうございました。
DPro公式サイト:https://diveintocode.jp/sdgs
この記事を書いた人
中島卯月 ライター
フリーランスのライターをしています。以前は、電機メーカーや飲食店での勤務、化粧品の卸、販売店の経営、エステティシャンなどいろいろな経歴があります。駐在員の家族として通算約10年、アメリカでの生活もしており、その間に出産や子育ても経験しています。皆様の“読みたい!”記事が書ければ嬉しく思います。
フリーランスのライターをしています。以前は、電機メーカーや飲食店での勤務、化粧品の卸、販売店の経営、エステティシャンなどいろいろな経歴があります。駐在員の家族として通算約10年、アメリカでの生活もしており、その間に出産や子育ても経験しています。皆様の“読みたい!”記事が書ければ嬉しく思います。