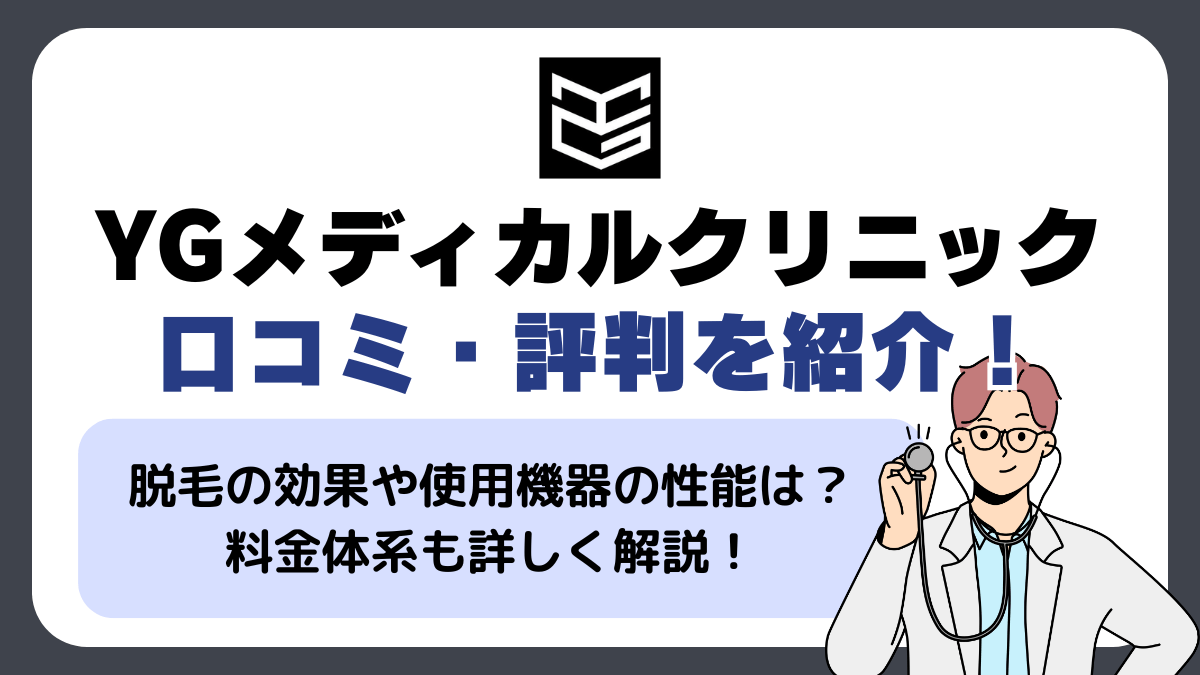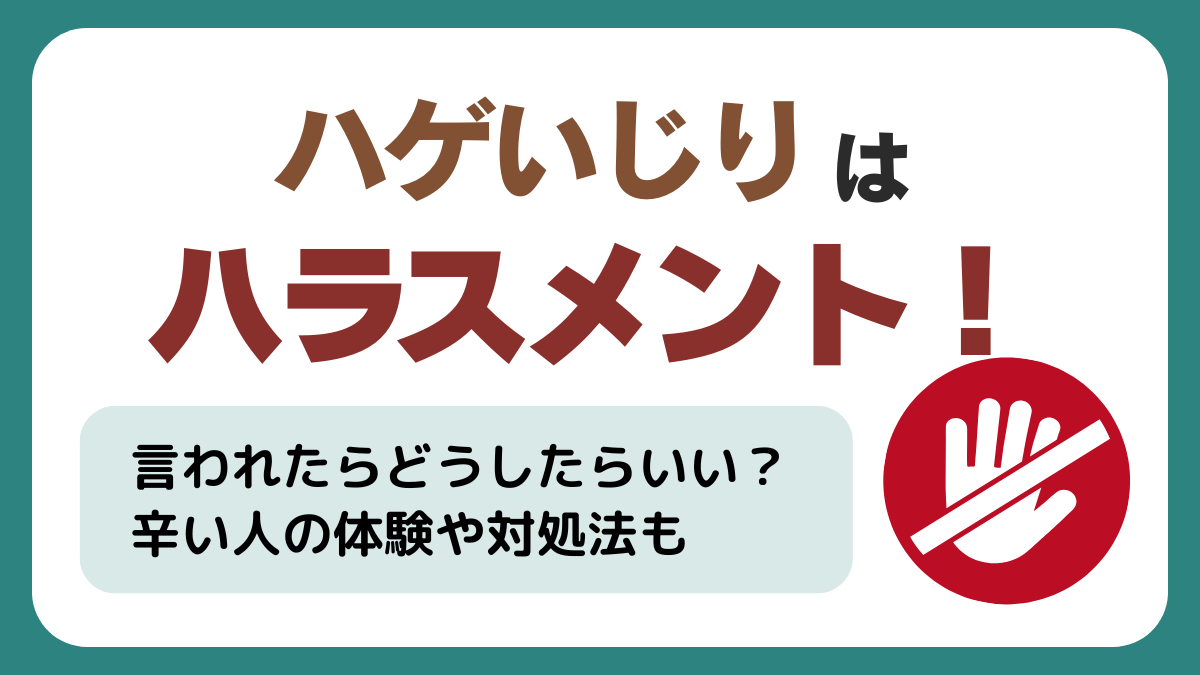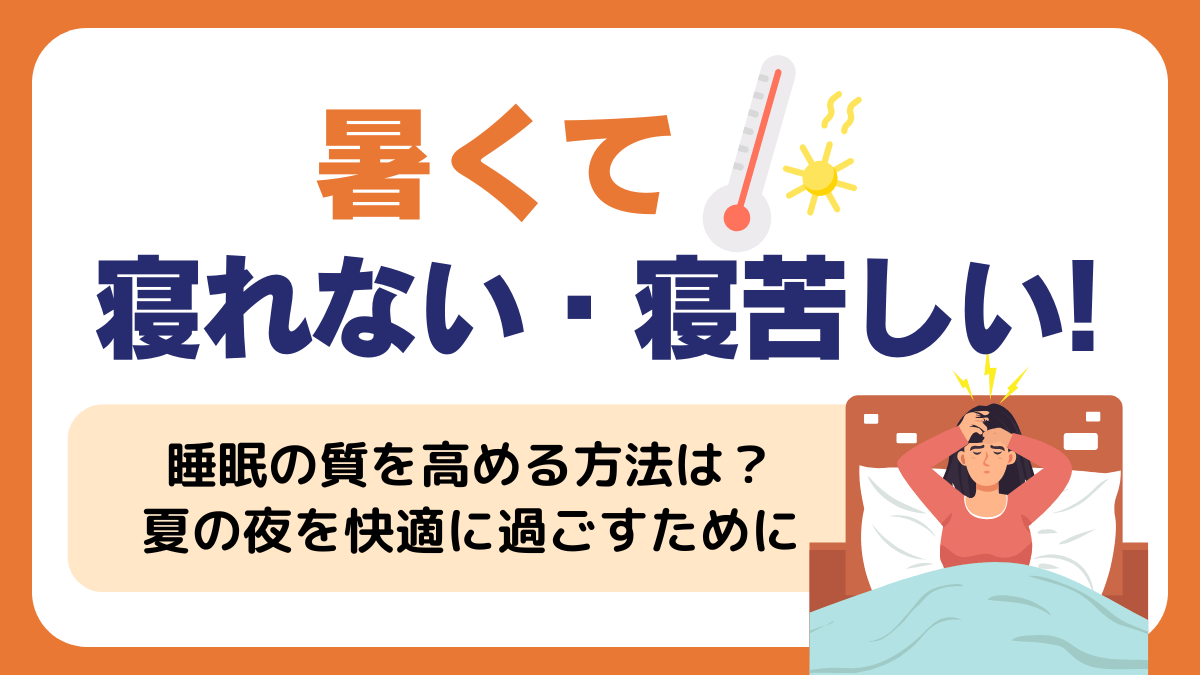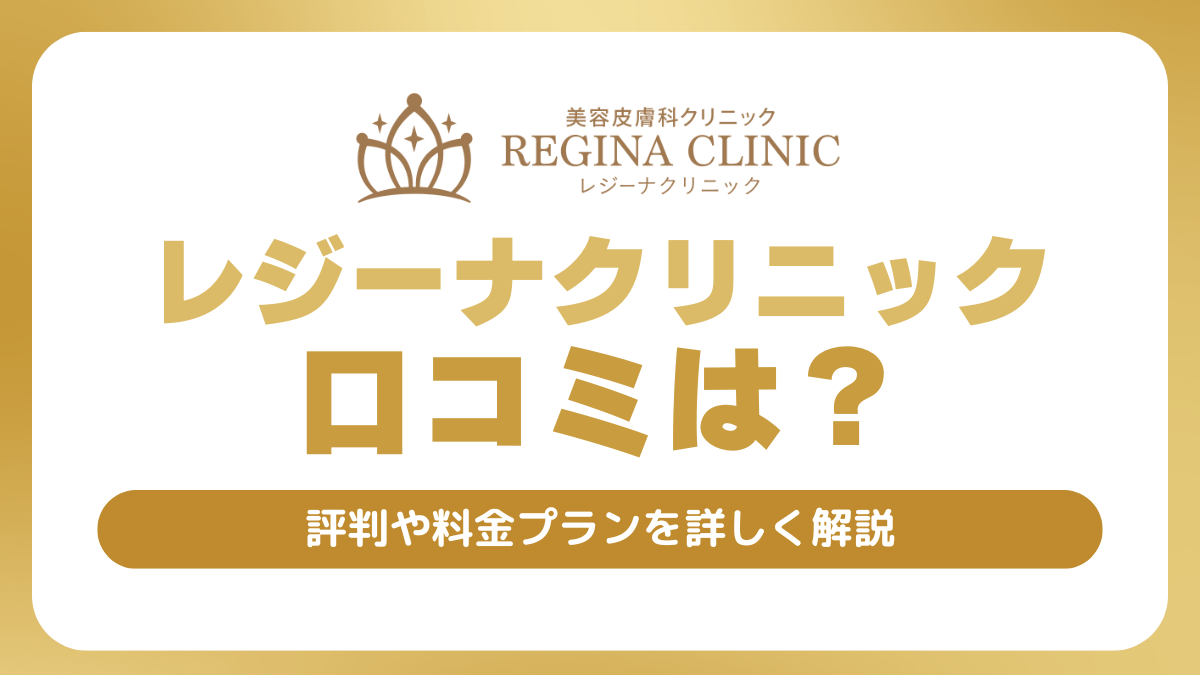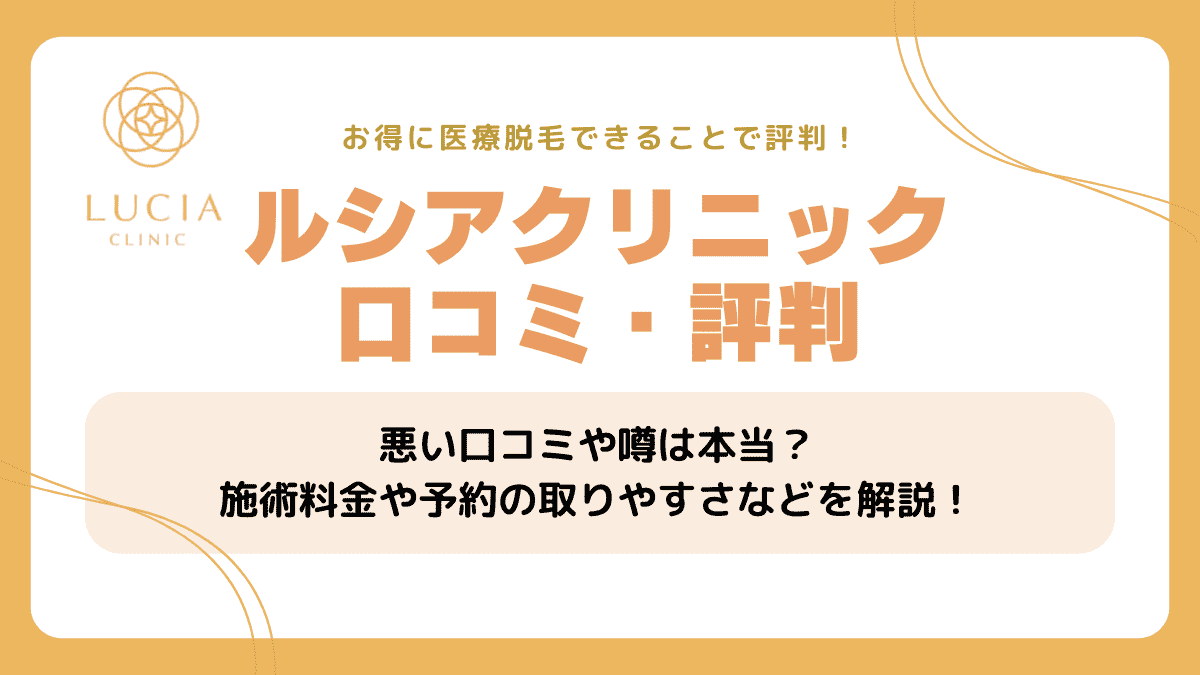近年、XR(クロスリアリティ)市場への注目が高まっており、市場規模は2025年に1兆円を超えると予想されています。
これまでXR(クロスリアリティ)は、ゲームや映像などエンターテイメント分野を中心に活用されてきました。そしてXR市場は、現在導入されている分野だけではなく、医療や製造・物流などにも広がりをみせています。
本記事では、さまざまな分野で導入が始まっているXRが、注目されている理由や抱えている課題についてまとめました。まずは、XRとは何かを知りましょう。
目次
XRとは?クロスリアリティについて簡単に解説
XR(Extended Reality)とは、現実世界と仮想世界を融合し、暮らしや仕事などさまざまな作業の効率化・迅速化を図る画像処理技術です。最先端技術 「VR」「AR」「MR」「SR」の総称であり、「クロスリアリティ」とも呼ばれています。XRのXは「未知数」を、Extendedは「拡張」を意味し、「XR元年」と言われる2016年から普及し始めました。
XRが何かを理解したところで、続いてはVR・AR・MR・SRについて詳しく見ていきましょう。
XR(クロスリアリティ)の種類とそれぞれの意味
VR・AR・MR・SRには、下記のような特徴があります。
VR(Virtual Reality:仮想現実)
「仮想現実」と呼ばれるVRは、コンピュータやインターネット上に人間が入り込み、何かを作ったり見たりできる技術です。人が立ち入れない危険な場所にある機械を、遠隔操作できる「テレプレゼンス」の技術(※)をもとに誕生しました。
身近なものに、VRゲームがあります。専用の装置を装着すると、VR空間を自由自在に動き回れるため、自身がゲームの世界にいるような感覚を味わえるのです。近年はVR空間を活用し、音楽イベントや撮影会なども開催されています。
AR(Augmented Reality:拡張現実)
「拡張現実」であるARは、コンピュータによってつくり出したものを現実世界に重ね合わせ、価値を生み出す技術です。身近な例としては、スマートフォンゲームが挙げられます。多くの方がプレイした『ポケモンGO』もこの一つです。
何の変哲もない風景をスマートフォン越しに見ると、キャラクターがその場にいるような感覚を味わえます。その他にもARは、カメラアプリや動画共有サービスなどのフィルター機能としても活用されています。
MR(Mixed Reality:複合現実)
「複合現実」を意味するMRは、ARを発展させた技術です。「VRとARの中間を示す言葉」として、1994年に大阪大学の岸野名誉教授らによって定義されました。ARのように、現実世界に仮想世界を重ね合わせるだけではなく、本当に実在しているかのような演出を可能にします。さらに、デジタル映像の操作や誰かと一緒に仮想空間内で作業も行えるのです。
そのため、AR以上に現実に近い仮想空間を体感できます。例えば、ARを活用したスマートフォンゲームのキャラクターは正面のみの映像となりますが、MRの場合は、360度好きな角度からキャラクターを自由に確認できるのです。
SR(Substitutional Reality:代替現実)
「代替現実」と言われるSRは、過去に起こった現実の映像を実世界に重ね合わせることで過去の体験を追体験できる技術です。
視覚だけではなく、他の聴覚や触覚といった五感を組み合わせることでよりリアルな体験ができるとされています。
実用化には時間がかかりますが、心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの治療に活用することが期待されています。
ここまでは、VR・AR・MR・SRについて説明しました。続いては、XRが注目されている理由を確認していきます。
メタバースとは、インターネット上の仮想空間を示し、オンライン上での交流の場やマインクラフトなどのゲーム空間のことを示します。
メタバースは仮想の「場所」を表すのに対して、XRは仮想の空間を実現するための「技術」を表します。
XR(クロスリアリティ)が注目されている理由5選
XR(クロスリアリティ)が注目されている理由は、下記の4つです。
デバイスやソフトの進化
以前の仮想世界は、映像の解像度が低く粗さが目立ちました。そのため、現実世界と仮想世界のギャップが大きかったと言えます。しかし近年は、高画質や立体的な音響設備・人と同じ視野を再現するなど、急速な技術発展が起きています。
これにより、現実世界と仮想世界のギャップが大幅に縮まりました。さらに、機械の軽量化や小型化によって利便性も向上したことで、利用する場面が増えたことも理由の1つです。
5Gによる通信環境の進化
5Gとは別名「第5世代移動通信システム」と言い、日本では2020年3月から使用が開始されました。
主な特徴として
- 高速大容量
- 多数同時接続
- 超低遅延
などが挙げられます。
これまで主要とされていた4Gと比べると、遅延・速度・容量・汎用性の面で大きく進化しており、ビデオ会議や仮想現実など、ビデオテクノロジーの増加にも対応しています。そのため、VR(仮想現実)を含むXRの普及を促進しているのです。
「モノ消費」から「コト消費」の時代へ
2017年頃から人々は、物を買う「モノ消費」より、体験を買う「コト消費」に重きを置き始めました。
例えば、
- 好きなアーティストのCDを購入して聴くのではなく、コンサートに行って生の歌声や演奏を聴く
- お店でケーキを購入するのではなく、ケーキのキットを購入し子どもと一緒に作る
などが挙げられます。
そして、2020年に起こった新型コロナウイルスの影響により、モノ消費からコト消費への消費行動の移行が加速していきました。現実世界で集客することが難しくなり、VRのような仮想世界で集客しようとする会社が増えていったのです。
リモートコミュニケーションの普及
新型コロナウイルスの影響はそれだけではありません。
感染症の拡大を抑えるために、外出が制限され、リモートワークが推奨されるようになりました。
それだけでなく、オンラインセミナー、オンラインイベントなども普及し、リモートコミュニケーションが活発になりました。
XRはリモートコミュニケーションを円滑に進められる側面を持つため、XRの需要は高まりました。
SDGsの目標達成に貢献する
2015年に開催された国連総会にて、全加盟国が賛同して採択されたSDGs。17の目標と169のターゲットが設定されており、2030年までに達成を目指す国際目標です。このSDGsの目標達成に、XR技術が貢献する可能性があります。
例えば、SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」。この目標は、健康にまつわる内容が掲げられています。
現在医療分野では、VRを活用したメンタルヘルスケアプログラムの開発が進められています。その他にも、がん治療専用のVRアプリやMRを駆使した3次元のオンライン診療などの導入も始まりました。つまり、XR技術によって医療が発達することで「すべての人に健康と福祉を」の達成にもつながるのです。
現在は医療だけではなく、ほかの分野でもXRは導入されているため、SDGs目標3以外の達成にも貢献するでしょう。
このように、さまざまな理由から注目が集まるXRですが、いくつかの課題やリスクも抱えています。
XR(クロスリアリティ)が抱える課題やリスク
XR(クロスリアリティ)が抱える課題やリスクは、大きく分けて下記の4つです。
個人情報の管理
XR(クロスリアリティ)は没入型技術であり、
- 人の感情
- 判断
- 反応
- 個人を決定づける特性や情報
など、私的な内容を簡単に入手できます。
そのため、「悪意のある第三者がXRを使い、これ等の情報を手に入れた際の危険性」を考え、対策を行わなければいけません。XRを利用する際は、「どのような方法で個人情報を管理するか」にも注意しましょう。
フェイクエクスペリエンスにつながる可能性も
フェイクエクスペリエンスとは、機器やサービス・組織などの対象物と関わる中で生じる、印象や認識を偽装・粉飾することです。
例えば、A国とB国が戦争を行っている地域に仮想体験を通して行けるとします。戦地の悲惨な状況を見て、私たちはさまざまな感情を抱き、意見を持つでしょう。しかし、その仮想空間自体が、どちらかの国が有利になるように戦地の状況を偽装・粉飾していたとしたらどうなるでしょうか。
当然ですが、何も知らずに仮想体験を行った人は嘘の情報を信じてしまいます。正しい情報が届かなくなり、戦争の悪化にもつながりかねません。このようにXR(クロスリアリティ)は、使い方によって人や国に悪影響を及ぼす危険性があるのです。
著作権問題
XR(クロスリアリティ)を活用する際に問題となるものが「著作権」です。
例えば、VRchat(※)。仮想空間を歩いていると、漫画やアニメのキャラクターをかたどったアバターと出会う機会も少なくありません。アバターだけではなく、著作権を持つ建物やアニメの世界観をそのまま使用している空間も見かけます。
この場合、許可を得ていないものは当然著作権の侵害に当たるため、違法行為として対処されます。しかし、なかには判断が難しいケースもあり、取り締まる範囲の線引きが難しい点があることも事実です。
トラブルへの対処が難しい
先述した著作権問題と同様に、XR(クロスリアリティ)を利用するうえで人格や所有権など、さまざまなトラブルが起きています。
例えば、仮想世界で交流していると一方的にアバターを攻撃される、または、侮辱的な言動を受けるなどが挙げられます。このようなトラブルの発生は、珍しいことではありません。操作しているのは人間ではあるものの、仮想世界やアバターという特殊な条件下での交流のため、誰かに危害を加えることに対して抵抗感が薄くなっていると考えられます。
その他にも、ハラスメント行為や迷惑行為などが発生していますが、
- どの程度の被害で、どの法律を使い訴えるべきなのか判断が難しい
- 現時点では、仮想空間内のトラブルに対する判例が少ない
- 現在ある法律では裁くことが難しいトラブルもある
などの問題によって、解決が難しいケースも少なくありません。
急速に発展しているXR市場ですが、トラブルを防ぐためにも対処法や法整備に力を入れる必要があります。
XR(クロスリアリティ)技術の活用事例
XR(クロスリアリティ)の課題を理解したところで、ここからは導入事例を見ていきます。
【順天堂大学大学院】3次元オンライン診療システム
順天堂大学大学院では、服部信孝教授・大山彦光准教授・関本智子非常勤助教らの医学研究科神経学研究グループによって、3次元オンライン診療システムが開発されました。
「Holomedicine(ホロメディスン)」と名付けられた診療システムは、患者の3次元動作情報を離れた場所にいる医師のHMD(※)へ投影。その後、受け取った情報を基に医師が診察を行います。不要な感染リスクの軽減や、病院へ行けない患者への負担軽減につながることが期待されます。
また、遠隔医療が普及することで医療格差の改善も期待されます。
【株式会社杉孝】VRによって進化する安全教育
近年、現場では足場からの墜落事故が増加傾向にあり、その理由の1つに、「危険に対する感受性の低下」が挙げられています。
この問題を解決するために株式会社杉孝では、キヤノンITソリューションズ株式会社が構築した「プラント現場での飛来落下災害の加害者体験シミュレータ」を採用。VRを使い、災害によって不安定になった足場を再現しました。これにより、安全でリアリティのあるトレーニングを行えます。さらにシミュレーターと実際の足場や手すりを組み合わせることによって、危険感受性を高めることにもつながったそうです。
【株式会社楽天球団】プロ野球球団監修のトレーニングシステム
2017年から株式会社NTTデータは、VR技術を活用したトレーニングシステムの提供を開始しました。監修には株式会社楽天球団が関わっており、東北楽天ゴールデンイーグルスがファーストユーザーとして使用しています。
このシステムでは、バッターがピッチャーの投げる球を仮想体験でき、本番でのパフォーマンス向上を目指します。HMDを装着することでバッターボックスにいる状態を味わえ、本番さながらの状態で練習を行えるのです。また、相手選手の投球動作や軌跡を繰り返し確認できるため、特徴も掴みやすく、攻略方法の習得にも役立っています。
【NTTドコモ】ARショッピングとゲーム体験
NTTドコモでは、自社開発の「ARクラウド技術」とARクラウド用のコンテンツ作成を簡単にする開発ツールを使い、実証実験を行いました。この実証実験では、実店舗と仮想世界を融合させ、新たなショッピング体験を目指すことが狙いです。
専用のタブレットやMRグラス越しに周囲を見ると、ARコンテンツが出現し、自身が仮想世界に入り込んだ感覚になります。ゲーム要素も含まれているため、アトラクションとしても楽しめるでしょう。また、地図や周囲の交通機関の情報・体験者に合わせた広告表示など、実用性の面でも優れています。
XR(クロスリアリティ)に関するよくある質問
ここでは、XR(クロスリアリティ)に関するよくある質問について紹介します。
XRとは具体的にどんな技術のこと?
XR(クロスリアリティ)とは、VR(仮想現実)・AR(拡張現実)・MR(複合現実)など、現実とデジタルを融合させる技術の総称です。たとえば、仮想空間の中で製品を試したり、現実の風景に情報を重ねたりする体験が該当します。
これらの技術を統合して、より没入感のある体験や効率的な情報提示を可能にするのがXRです。教育・医療・製造業・観光など多分野で活用が広がっています。
VR・AR・MRとXRの違いは?
VRは完全に仮想の空間を体験する技術、ARは現実の風景にデジタル情報を重ねる技術、MRは仮想と現実の情報をリアルタイムで相互作用させる技術です。XRはこれらの総称で、目的や状況に応じてVR・AR・MRの要素を柔軟に活用する概念です。
つまりXRは、これら3つを含む「拡張された現実のすべて」を表す言葉であり、技術の発展に伴い今後さらに広範囲な意味で使われる可能性があります。
XRはどんな分野で活用されているの?
XRは教育・医療・建設・製造業・観光・エンタメなど、多くの分野で活用されています。たとえば医療では手術のシミュレーションに、建設業では設計の可視化に使われています。
教育現場では仮想体験によって理解を深め、観光ではARを使って史跡を当時の姿で再現するといった事例もあります。現実の制約を超えて体験や操作が可能になるため、さまざまな業界の効率化と革新を支えています。
XRを使った教育や医療のメリットは?
教育では、実際の体験が難しい環境や出来事を仮想で再現でき、子どもたちの理解や関心を深めます。理科の実験や歴史の再現、職業体験などへの応用も可能です。
医療では、手術前のシミュレーションや遠隔診療での補助、リハビリ支援に活用されています。特に安全性やコストの面で現場の負担を減らし、実践的なスキルの習得をサポートする点が大きなメリットです。
XRはSDGsにどのように貢献できるの?
XRは、SDGsのさまざまな目標達成に役立つテクノロジーです。たとえば、遠隔地でも教育や医療支援を受けられることで「目標4:質の高い教育をみんなに」や「目標3:すべての人に健康を」に貢献します。
また、都市計画や災害訓練における活用は「目標11:住み続けられるまちづくり」にもつながります。XRは、情報の「体験的な理解」を促すことで、行動変容や意識改革を支援する力を持っています。
XR(クロスリアリティ)とSDGsの関係
XR(クロスリアリティ)とSDGsの関係は、テクノロジーによって持続可能な社会づくりを支援する点で深く結びついています。XRは、VR(仮想現実)・AR(拡張現実)・MR(複合現実)といった現実と仮想を融合させる技術の総称で、教育、産業、防災、環境啓発など多方面でSDGsの目標達成に寄与します。
たとえば、遠隔地でも質の高い教育を提供できるXRは「目標4:質の高い教育をみんなに」に貢献します。また、建設や製造現場での仮想訓練や設計シミュレーションは「目標9:産業と技術革新の基盤をつくろう」を支援します。
さらに、気候変動の影響を仮想体験で伝えることで「目標13:気候変動に具体的な対策を」の意識を高めたり、住民参加型の街づくりにも活用され「目標11:住み続けられるまちづくりを」にもつながります。
このようにXRは、課題の「見える化」と体験による理解促進を通じて、SDGsの行動を促す有効なツールとして注目されています。
まとめ
急速な成長を見せるXR市場。仮想世界という非現実的な空間の中で、今まで不可能とされてきたことが可能になりつつあります。「実際に行かないとできない体験ができるようになる」、「病院に行けない人も遠隔で診察を受けられる」など、私たちの暮らしに少しずつ浸透し始めているのです。
法整備や個人情報の問題・トラブルへの対処法など課題は残っているものの、これから少しずつ解消されていくでしょう。今後、課題を解決しながらXR技術が広まることで、地球上に暮らすすべての人に優しい世界に近づき、SDGsの目標達成にもつながります。
そのためにも私たち個人は、ルールやマナーを守りXR技術を利用していきましょう。
〈参考文献〉
仮想空間とVR|株式会社 往来 著
SDGs(持続可能な開発目標)|蟹江憲史 著
Digital Reality(XR)|越智 隆之 著
この記事を書いた人
スペースシップアース編集部 ライター
スペースシップアース編集部です!
スペースシップアース編集部です!