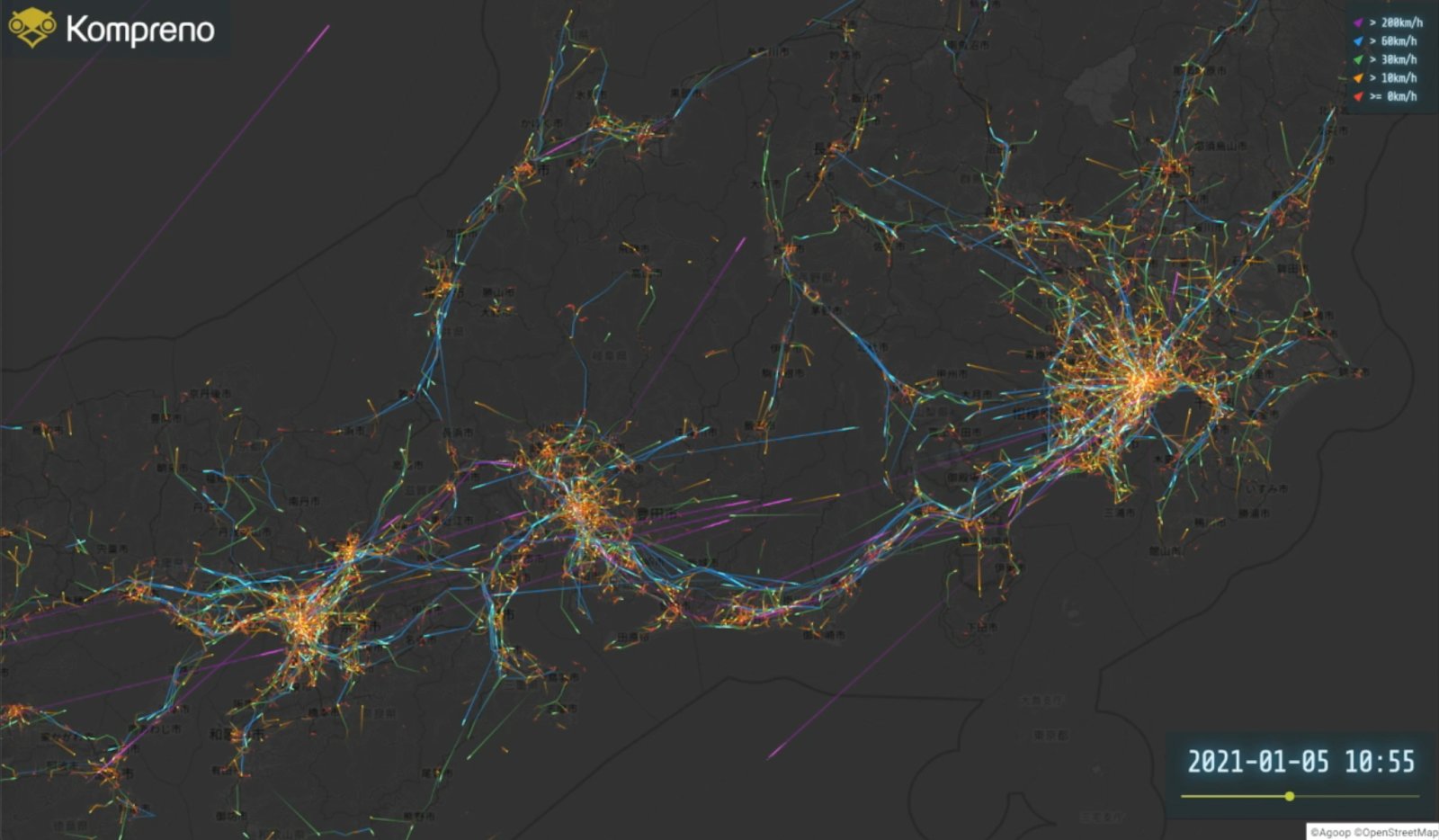NPO法人フォレシア 代表理事 佐藤高輝さん インタビュー

NPO法人フォレシア代表理事 佐藤高輝
27歳から不妊治療を始め、体外受精で2人の子どもを授かる。その経験から2017年にNPO法人フォレシアを設立。
全国の企業向けに不妊治療と仕事の両立に係る制度設計等の伴走支援、専門家や大学と連携した両立相談窓口、健康相談窓口の提供を行っている。
また、職域における女性の健康課題の解決と不妊症予防における研究を自治体や医師、大学と共に行う。
目次
introduction
日本は海外の国と比べて、不妊治療を受けている人の数が多く、「不妊治療大国」と言われていることをご存じでしょうか。
自分の周りにも、知らないだけで不妊治療を受けている人がいるかもしれません。そんな社会で暮らしていくために、私達が知っておきたい不妊治療の知識と現状。
今回は、「将来、不妊症で悩む方を減らしたい」と活動するNPO法人フォレシアの代表理事、佐藤高輝さんにお話を伺いました。
子どもを望むすべての方に納得出来る選択を
–はじめに、NPO法人フォレシアのご紹介をお願いします。
佐藤さん:
フォレシアは、2017年に不妊治療と仕事の両立を支援することを目的に立ち上げたNPO法人です。
「子どもを望むすべての人に、納得できる選択を」を理念に掲げ活動しています。
日本では、不妊治療や検査を受けたことがある、または現在受けているカップルは約4.4組に1組とされています。
しかし、治療を続けたいのに仕事との両立が難しく退職を余儀なくされる場合や、治療費の負担が大きく、治療を断念、子どもを持つことを諦めざるを得ない状況が多くあります。このような苦悩を抱えている方々が大勢いるのが現状です。
仕事や経済的負担、地域格差などの問題で、納得のいかないまま子どもを諦めなければならない社会課題を解決したいと考えています。
その中で現在、大きく分けて2つの取り組みをしています。
ひとつは、不妊治療について悩んでいる方をサポートする事業です。
企業向けに不妊治療を理解するための研修や啓発、オンラインでの相談窓口などを医師と連携して行っています。
もう一つは、将来に向けて、不妊症の患者さんを減らしていくための事業です。
自治体と連携して、企業の健康診断の際にプレコンセプションケア健診をしています。
これは採血により、不妊症予防や安全な妊娠出産のため、妊娠前からの治療の有効性が知られるおよそ13項目を追加で検査するものです。例えば葉酸やビタミンD、性感染症の有無などです。それらを職域健診で受けることができ、さらに地域の産婦人科医からオンライン上で説明をうけることも可能となるものです。
《大学でのプレコンセプション教育の様子》

–なぜ佐藤さんは、不妊治療支援のNPO法人を立ち上げようと思われたのですか。
佐藤さん:
私自身が不妊治療の経験をしたことが、フォレシアを立ち上げたきっかけです。
24歳で結婚したんですが、なかなか子どもが授からず、27歳の時に不妊治療を始めました。ちょうど、会社を退職してエクステリアの会社を立ち上げたときで、プライベートの時間ができ、病院を受診しました。
結果的に体外受精で二人の子どもを授かりました。でも、まさか自分が不妊治療や体外受精を経験するとは思っていませんでしたね。
不妊治療では、どうしても生物学的に女性の体への負担が大きいんです。それで、長女が生まれた時に、「この子が大人になる未来でも、この状況が変わらないのは大変なことだ」と思ったのと同時に、不妊治療における今の問題・課題がなくなるようにしたいと考えフォレシアを立ち上げました。
不妊症の要因の一つは低い生殖リテラシー
–立ち上げの際は、苦労されたことはありましたか。
佐藤さん:
そうですね、最初に事業の内容を分かってもらうのが大変でしたね。
不妊治療は2022年に保険適用の対象になり、今でこそ「フェムテック」という言葉も認知されつつあります。しかし、立ち上げたころは不妊治療自体があまり認識されていませんでした。「不妊治療と、仕事の両立ってどういうこと?しかも男性が?」という反応が多かったんです。確かに、どう考えても怪しすぎますよね(笑)
ですから、個人事業主の届け出を出したその足で、秋田県庁に行き、担当の人に話をして県庁の中のコワーキングスペースに事務所を借りました。最初から県庁の中にきちんと事務所を構え、役所の方達と話をし、県と意見交換をしながら事業の実績を積みました。
現在は、上場企業や日本全国の自治体などに事業提供し、一緒に進められるようになりましたが、ここまで来るにはやはり時間がかかりましたね。
–次に、日本での不妊治療の現状や、課題などについてお聞かせいただけますか。
佐藤さん:
「ICMART、生殖補助医療技術監視国際委員会」が2016年に出したレポートによると、日本で行なわれている不妊治療の数は、調査した世界60か国中で、一番多いという結果が出ています。しかし、1回の採卵あたりの出産率は最下位です。
生殖補助医療技術監視国際委員会世界報告書:生殖補助医療2008年、2009年、2010年† |人間の生殖 |オックスフォードアカデミック (oup.com)
つまり、多くの方が不妊治療(体外受精)しているにもかかわらず、子どもが授からないということです。
この原因の一つは、日本ではきちんとした「生殖教育」や「包括的性教育」がされずにきたことだと考えています。
「包括的性教育」とは、性にまつわる様々な要素を含む教育で、生殖・性行動のリスク・性に関する疾病等だけでなく、「人権」をベースにウェルビーイングの実現などの観点が重視されています。一言でいうと、性的同意、性の多様性、ジェンダー平等、コミュニケーションなどを体系的に学ぶ教育とされています。
日本では、包括的性教育も生殖教育もその水準は、先進国の中ではだんとつ最下位です。
日本で行われる不妊治療の数は、治療を受ける人の年齢が上がるとともに増えています。不妊治療は30代後半から40代で行うのが当たり前と思われていますが、実はそれでは遅いことがわかっています。諸外国では、治療を受ける人数は35歳以降40代にかけて減少しています。
十分な教育を受けていないために、不妊症についての知識が乏しく、その結果、ケアが遅れます。そのため、不妊治療が高度化し、仕事との両立が難しくなり、離職を余儀なくされるという悪循環が生まれています。
また、月経困難症も不妊の要因ですが、ピルの服用が予防につながることについて、日本ではまだ認識が不足しています。「ピル」イコール「避妊」という意味でとらえられることも多いんです。
このように妊娠に対する知識不足や、間違った認識が不妊治療での出生率の低さに繋がっていると思います。
「プレコン健診」で変えたい不妊治療の未来
–このような現状を変えるため、どのような取り組みをされているのでしょうか。
佐藤さん:
今一番注力しているのが、プレコンセプションケアの健康診断「プレコン健診」です。
コンセプション(Conception)は受胎という意味で、プレコンセプションケア(Preconception care)とは、将来妊娠を考えるすべての人が自分達の体の状態を知り、健康や生活に向き合うことです。
知識がなく正しい選択ができないために、不妊に繋がってしまうという大元の原因をなくす事業として、小学生から20代前半の社会人の方達を対象に教育機会を創るとともに、健診事業を自治体や大学と連携しながら進めています。
現在は、企業の健康診断の中に「プレコン健診」を取り入れ、希望する女性社員が不妊症予防や安全な妊娠出産のため、妊娠前からの治療の有効性が知られる追加検査を受けられるようにしています。
令和5年、フォレシアは経済産業省の「フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金」に採択され、プレコン健診の受診システムを作り、大規模な健診が受けられるようにしました。他にも様々な自治体で取り入れられています。
https://www.femtech-projects.jp/project/40.html
《フェムテック等サポートサービス実証事業費 経産省補助金報告会の様子》

具体的な健診の流れですが、自治体が主体となり「プレコン健診」を希望する企業を取りまとめて実施します。
企業健診時に、希望者には多めに採血をしてもらい、血液検査でチェックを行います。内容は「貧血検査」「Fe・フェリチン」「葉酸」「ビタミンD」「梅毒」などおよそ13項目で、結果はオンラインで通知され、必要に応じて医師との面談や、相談もできます。
例えば愛媛県の場合であれば、愛媛大学の産婦人科の先生方が協力してくれています。
–実際に健診を受けた方々から、お話をお聞きになったことはありますか。
佐藤さん:
この健診を受けると、現在の自分の体の状態を把握するのに繋がります。
例えば葉酸やビタミンDなど、妊娠にとても大事な栄養素などが欠乏しているとか、梅毒やクラミジアなどの性感染症の有無、月経困難症や多嚢胞性卵巣症候群の疑いなどの発見に寄与出来ると考えています。
また、このような検査を自身で受けようとすると、仕事をしながら通院をしなくてはならず、非常にハードルが高いのが現状です。そのため、検査を受けた方の多くが満足されていて、感謝の言葉をいただくこともあります。
例えば、「検査のおかげで早期に治療ができ、手術でなく投薬だけで済んで本当に助かりました。」や「早期の治療で仕事を辞めずにすみました。」などです。
思いもしなかった病気が見つかり、早期治療につながったと聞くこともあります。
最初に「プレコン健診」を始めた秋田県では、健診1年後にアンケートを取りました。妊娠された方が何人かいて、この方たちは「プレコン健診に影響をうけましたか?」との問いに、「100%影響を受けた」と答えています。妊娠を考えている方には非常に有効なのではないかと思います。
また、将来の妊娠の可能性を考えて卵子の凍結保存を考える方や、まだ子どもは考えていなかったけれど、早めに妊娠を考えたほうが良いと知り、行動をとる方もいます。
「もっと早く知りたかった」という言葉を私たちは何度も聴いていました。そのため、その言葉を無くせるように環境整備を進めていきたいと思います。
不妊治療は社会の課題として知っておくべき知識
–他にも注力されている事業はありますか。
佐藤さん:
はい、これもプレコンセプションケアの領域ではありますが、子ども達への教育にも力を入れています。
生理用ナプキンを教材として使おうと取り組んでいます。
生理用ナプキンを学校のトイレの個室に置くのですが、これは支援ではなく、あくまでもナプキンを教材とした教育です。
トイレットペーパーはトイレに置いてあるのに、どうしてナプキンはないのか。そこに置いてあるのが当たり前という認識に徐々に変わっていくようになれば、性に関する意識も変わるのではないかと思います。
加えて現在、工業高校の「メカクラブ」の女子生徒に、ナプキンを入れるディスペンサーを作ってもらおうと動いています。
生徒が自分たちで使いやすいものを考えて、自分たちで作る。それを自分たちの学校に置くことで、県内の他の学校にも広めていこうと考えています。
–では、この記事を読んでいる読者の方々に何かアドバイスがありましたらお願いします。
佐藤さん:
不妊治療は、当事者でなければ「じぶんごと」にするのが難しい領域だと思います。
ただ、今の日本にあるのは、自分がその立場になったときに、「もっと早く知りたかった」とおっしゃる方たちが非常に多いという事実です。
早い段階で不妊症がわかれば、その後の行動が選べますが、遅れると選択肢が無くなってしまうこともあります。そのため、出来るだけ早く知り、自分でどうするのか選んでほしいと思います。
また、子どもは持たないと考えている方達には届きにくい領域かもしれません。しかし、社会では夫婦全体の4.4組に1組は不妊治療を受けています。
自分が働くチームの中にも不妊治療を受けている人がいるかもしれません。自分が子どもを持つ持たないではなく、月経や妊娠、不妊などに関しての知識は、周りと一緒に仕事をしていくうえで、必ず知っておかなければならない知識です。
最近は、男性管理職の方々の研修への参加率が高くなってきていますが、もちろん男性も知っておくべきことです。
管理職ならばなおのこと、きちんと知識をもったうえで、皆が公平に仕事ができる環境を提供することが大切だと考えています。
「国立成育医療研究センター」のサイトにも、プレコンセプションケアについて詳しく載っていますので、参考にしてください。
プレコンセプションケアセンター | 国立成育医療研究センター
–最後に、今後どのように事業を展開するのか、展望をお聞かせください。
佐藤さん:
「プレコン健診」を当たり前に受けられるようにしたいと考えています。
3年前に始めて、やっと多くの自治体から問い合わせをいただくことができました。将来は、健診を受けたいと思ったときに、いつでも受けられる機会を全国に作りたいと思います。
–本日は貴重なお話をありがとうございました。
NPO法人フォレシア公式サイト:https://forecia-japan.com/
この記事を書いた人
中島卯月 ライター
フリーランスのライターをしています。以前は、電機メーカーや飲食店での勤務、化粧品の卸、販売店の経営、エステティシャンなどいろいろな経歴があります。駐在員の家族として通算約10年、アメリカでの生活もしており、その間に出産や子育ても経験しています。皆様の“読みたい!”記事が書ければ嬉しく思います。
フリーランスのライターをしています。以前は、電機メーカーや飲食店での勤務、化粧品の卸、販売店の経営、エステティシャンなどいろいろな経歴があります。駐在員の家族として通算約10年、アメリカでの生活もしており、その間に出産や子育ても経験しています。皆様の“読みたい!”記事が書ければ嬉しく思います。