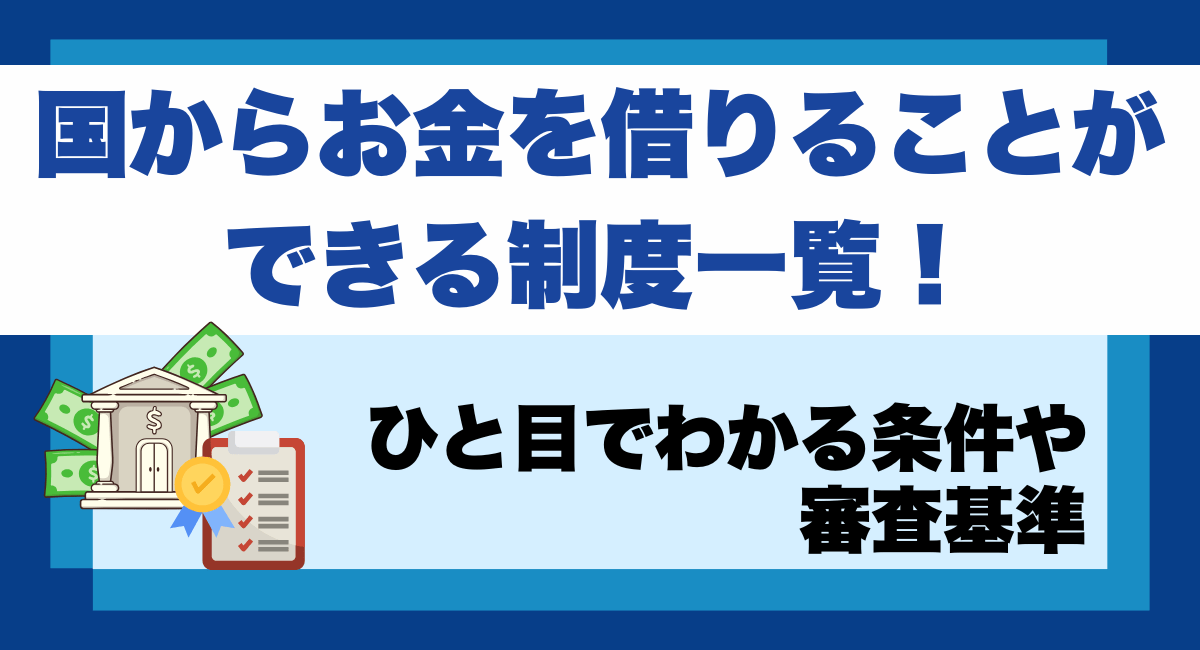
国からお金を借りる制度は、生活の困難や資金繰りに直面したとき、頼れる選択肢のひとつです。
収入が不安定な個人や創業間もない個人事業主にとって、銀行などの民間融資が難しい状況でも、国の制度なら低金利・無担保での資金調達が可能なケースがあります。
生活費や教育費、事業資金など、用途によって多様な支援策が整備されており、自分の状況に適した制度を見つけやすいのも特徴です。
ただし、制度ごとに審査や条件、手続きの流れは異なります。
そのため、まずはそれぞれの制度の特徴を正しく理解し、自分に必要な制度が何なのかを見極めることが大切です。
目次
国からお金を借りるとは?公的融資の仕組みを解説
国からお金を借りるとは、政府や自治体が提供する公的融資制度を使い、生活や事業のサポートを受けることを指します。
これらの制度は、営利を目的とせず、生活困窮者や起業家、個人事業主など、民間の金融機関からの借入が難しい人たちを対象に設計されています。
公的融資の主な特徴は、低金利や無担保・無保証での貸付が可能である点です。
たとえば、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」は、創業初期の事業者を対象に、無担保・無保証での融資を提供しています。
また、返済期間も長期に設定され負担も少ないです 。
さらには、特定の状況に応じた支援制度もあります。
これらの制度は、生活費の補填や教育資金の確保、住宅の確保など、さまざまな目的で活用できます。

最大365日と無利息期間の長さが優れている消費者金融です!
原則勤務先への在籍確認も実施しておらず、書類で審査可能。
事前に返済額や総額をシミュレーションすることもできます。
レイクの詳細はこちら>>
個人が国からお金を借りる方法を紹介
個人が国からお金を借りる場合、状況次第で使える制度が複数あります。
それぞれ生活費や教育費、住居費など、目的に合わせて選べるのが特徴です。
制度ごとの条件や使い道を知っておくことで、自分に合ったサポートを受けやすくなります。
生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度は、生活に困っている世帯が必要な資金を確保し、自立を目指すことをサポートする制度です。
対象となるのは、収入が一定基準以下の低所得世帯、高齢者世帯、障害者世帯、ひとり親家庭などで、それぞれの家庭状況によって複数の資金プランがあります。
制度の中で最も即時性が高いのが「緊急小口資金」で、急な出費に無利子で対応できます。
失業や収入減によって継続的な生活が難しい場合には「総合支援資金」が活用され、最長12か月の生活費が貸し付けられます。
子どもの学費や通学費に備えるには「教育支援資金」が効果的で、在学中は返済が猶予される仕組みです。
また、「福祉資金」は高齢者や障害者のための介護機器購入や住宅改修に対応し、「住宅支援資金」は住まいの安定が厳しい家庭に向けた家賃補助制度です。
どれも無担保で申し込める上、条件次第では返済が免除される場合もあります。申請の際は市区町村の社会福祉協議会が窓口です。
緊急小口資金
急な出費や一時的な収入減により、日々の生活費に困っている人を支援するのが「緊急小口資金」です。
この制度は、突発的な支出で生活が立ち行かなくなった際に、無利子で必要な資金を一時的に借りられる仕組みで、特に単身高齢者世帯や低所得世帯などにとって心強い味方となっています。
失業や病気、災害、給与の支払い遅延などによって収入が途絶えた、あるいは大幅に減少した人が対象です。
貸付限度額は最大10万円ですが、特に新型コロナウイルスの影響を受けた世帯などには20万円までの貸付が認められる特例も存在しました(※現在は終了)。
返済は原則1年以内で、返済開始までには猶予期間が設けられるため、すぐに返さなければならないという不安を軽減できます。
申請は居住地の市区町村にある社会福祉協議会が窓口となり、本人確認書類や必要に応じた証明書類の提出が求められます。
この制度は返済義務はありますが、無利子である点や審査が比較的簡易なことから、短期的な資金不足に対する迅速な支援策として、とても効果的です。
総合支援資金
失業や収入の大幅な減少によって生活費の確保が困難になった世帯をサポートするのが「総合支援資金」です。
この制度は、比較的長期にわたって安定的な生活が見込めない状況にある場合に使われるもので、数か月にわたって生活を下支えする役割を果たします。
対象となるのは、原則として低所得者世帯や失業者であり、生活再建に向けた計画の策定と併せて使われるケースが多いです。
貸付の内訳は、基本的に月額15万円以内(単身世帯)または20万円以内(2人以上世帯)の生活支援費を原則3か月間貸し付けるもので、状況によって最大12か月まで延長されることがあります。
無利子での貸付であり、返済は据え置き期間後に始まります。
さらに、返済免除の制度も一部用意されており、特定の条件を満たすことで返済が不要となる場合もあります。
特定の条件とは、たとえば就職が決定し、一定期間継続して勤務した際などです。
申請の流れは、まず居住地の社会福祉協議会に相談し、必要書類を提出した上で、家計の状況や支援の必要性について面談を受けることから始まります。
教育支援資金
教育支援資金は、家庭の経済的事情により進学や修学が難しい子どもたちを支えるための貸付制度です。
高等学校や大学、専門学校などへの進学に必要な学費を無利子または低利子で貸し付けることで、教育の機会均等を保障することを目的としています。
対象は主に低所得者世帯であり、保護者の収入状況により支援の可否が判断されます。
貸付の内容は「修学支度費」と「就学支援費」の2種類です。
修学支度費は入学時に必要な費用で、上限は50万円程度です。
就学支援費は毎月の授業料や通学にかかる費用で、大学生であれば月額最大6万5千円程度まで貸し付けを受けられます。
貸付期間は在学期間中とされ、卒業後に返済が開始される仕組みです。
申請にあたっては、進学予定の学校からの証明書類や家計状況の申告などが求められます。
申し込みは地域の社会福祉協議会が窓口となっており、在学中の貸付に関する相談にも対応しています。
福祉資金
福祉資金は、障害のある方や高齢者が日常生活を快適に送るために必要な費用を支援する制度です。
介護や福祉に関わる出費は思いのほか大きく、急な対応が求められることも多いため、経済的な負担を和らげる目的で設けられています。
対象となるのは、高齢者世帯、障害者世帯、またはそれに準ずる特別なサポートが必要な世帯です。
この制度では、車椅子の購入、手すりの取り付け、浴室やトイレの改修などの住宅設備工事、または介護用品の購入といった用途が想定されています。
貸付額は最大で580万円までとされており、使う目的によって金額が変動します。
償還期間は原則として20年以内で、条件を満たすことで無利子での貸付も可能です。
必要に応じて、補助金との併用も考えられます。
申請の際は、利用目的を明記した計画書や見積書、福祉機関からの推薦書などが必要です。
住宅支援資金
住宅支援資金は、安定した住居を確保できない状態にある人々が自立を目指す際に使える制度です。
特に、ひとり親家庭や収入が極端に少ない世帯にとって、家賃の負担は生活再建の大きな障害となりやすいため、その負担を軽減することを目的としています。
住まいの安定が、就労や子育て、教育などあらゆる生活基盤の土台になるという考え方がベースになっています。
この資金では、民間賃貸住宅の家賃相当分が貸付対象となり、貸付額の上限は月額4万円、期間は最長で12か月です。
なお、児童扶養手当を受けているひとり親世帯などは、条件を満たすと返済が免除されることもあります。
また、支援にあたっては、単なる資金提供だけでなく、住居の選定や就労支援との併用など、生活全体の安定を図る取り組みがセットで行われることが特徴です。
申し込みはお住まいの地域の社会福祉協議会を通じて行い、申請時には収入や家賃、住居の状況などに関する詳しい書類を出す必要があります。
教育一般貸付
教育一般貸付は、「国の教育ローン」として知られる制度で、日本政策金融公庫が実施しています。
対象は、子どもを中学卒業後に高校・専門学校・大学などに進学させる保護者であり、一定の年収以下の世帯が使えます。
この貸付制度の特徴は、入学金や授業料、教材費、通学にかかる交通費、さらには下宿のための費用など、教育に関する幅広い支出が対象になる点です。
1人あたりの貸付限度額は350万円で、固定金利1.95%となっており、教育費全般を手厚くカバーできます。
返済期間は最長で15年、交通遺児家庭や母子家庭などはさらに延長可能です。
申請に際しては、世帯年収の上限(子ども1人世帯で790万円程度)が定められており、それを超えると使えません。
また、申込時には本人確認書類や進学先の合格通知、費用の見積書などが必要です。
審査にかかる期間は約2〜3週間のため、早めに申請するのがおすすめです。
民間の教育ローンに比べて金利が低く、返済も長期にわたるため、家計への影響が少ないことも大きなメリットです。
母子父子福祉資金貸付金制度
母子父子福祉資金貸付金制度は、ひとり親家庭の経済的な自立と子どもの教育・生活支援を目的とした、非常に多岐にわたる支援制度です。
対象は20歳未満の子どもを扶養する母子家庭または父子家庭の親、またはその子を養育する者で、生活の安定や就職・進学を支えるために、10種類以上の貸付メニューが設けられています。
どの制度も、無利子または低利で使え、返済の据置期間も長いため、民間のローンと比べて利用しやすい点が魅力です。
就学支度資金
就学支度資金は、子どもが高校や大学などに進学する際に必要となる初期費用をサポートするための貸付制度です。
進学にかかる負担は授業料だけではなく、入学金や制服代、教科書・教材費、さらには通学用品の購入など多岐にわたります。
こうした一時的な出費に応じられるよう、ひとり親家庭を対象にこの資金が用意されています。
この貸付の対象は、母子または父子家庭の子どもであり、進学が確定していることが条件です。
貸付額は進学先によって異なりますが、一般的に高校入学で10万円程度、大学や専門学校では最大50万円程度までが貸付の目安となっています。
利子は無利子であることが多く、返済開始は卒業後に据え置かれるケースが多いため、子どもが在学中に親が資金の返済に追われる心配は少なくなっています。
申請にあたっては、入学予定校からの合格通知や進学証明書の提出が必要です。
自治体によっては、学資保険や他の教育ローンとの併用に制限がある場合もあるため、事前の確認が大切です。
修学資金
修学資金は、ひとり親家庭の子どもが高等学校、大学、専門学校などで安定して学び続けられるよう、在学中の学費や通学にかかる費用を支援する貸付制度です。
家計の状況によっては、授業料や教材費の支払いが大きな負担となることもあり、この資金はそうした家庭が安心して教育の継続に取り組めるよう設計されています。
貸付対象となるのは、母子または父子家庭の子どもで、正式に学校に在籍していることが条件です。
貸付額は学校の種別によって異なり、高校生では月額18,000円〜30,000円程度、大学や専門学校では月額53,000円〜92,000円程度までが目安となっています(昼夜制や自宅通学か否かによっても変動)。
貸付は在学期間中継続され、卒業後に返済が始まる据置期間が設定されているため、子どもが在学中にすぐに返済義務が生じることはありません。
申請にあたっては、在学証明書や授業料の支払予定額などの書類が必要となり、自治体の福祉窓口を通じて申請を行います。
生活資金
生活資金は、母子家庭または父子家庭が一時的に生活困難な状況にあるとき、その日々の暮らしを維持するために利用できる貸付制度です。
たとえば、失業や離婚直後など収入が不安定な時期や、急な支出で家計が圧迫されたときに、最低限の生活を守るための支援として活用されます。
特に母子家庭では、育児と就労の両立が難しい場合もあり、制度の存在が生活の安定につながります。
この資金の貸付額は、世帯の構成や状況により異なりますが、月額10万円程度までが目安とされています。
貸付期間は原則として1年以内であり、必要であれば延長も可能です。
多くの場合、無利子での貸付となり、据置期間(返済開始までの猶予期間)が設定されているため、すぐに返済を求められることはありません。
貸付を受けた後の生活改善に向けた相談や支援計画が併せて実施されることもあります。
申請は自治体の福祉事務所や自立支援員を通じて行い、生活状況や収入に関する証明書類が必要です。
技能習得資金
技能習得資金は、ひとり親家庭の親が就職に必要な資格や技能を身につけるために、職業訓練や専門学校への通学などにかかる費用を支援する制度です。
自立を目指す上で安定した収入を得ることは、とても重要であり、手に職をつけたいと考える保護者にとって、この資金は力強い味方となります。
特に未経験の分野への就労や再就職を目指す際の選択肢が広がる点が特徴です。
対象は、ひとり親家庭の母または父で、職業能力を向上させる目的で公共職業訓練校や民間の教育機関などに通う場合です。
貸付額は訓練期間や内容により異なりますが、月額68,000円以内(通学制)程度までの生活支援と、教材費や受講料などに対する補助が用意されています。
また、訓練に必要な交通費も一部カバーされることがあります。
無利子での貸付が基本で、返済の据え置き期間も設けられており、訓練期間中は返済の心配がありません。
申請は市区町村の福祉担当窓口を通じて行い、受講予定の講座の案内資料や費用明細、本人の就労意欲を示す計画書などの提出が求められます。
結婚資金
結婚資金は、ひとり親家庭の子どもが結婚する際に必要となる費用を支援するための貸付制度です。
結婚には、引っ越し費用や家具の購入、挙式費用など多くの出費が伴いますが、家庭の経済状況によってはそれを十分に賄えない場合もあります。
そうした背景をふまえ、経済的な理由で結婚を諦めることがないように設けられているのがこの制度です。
対象となるのは、母子または父子家庭の子どもで、婚姻予定があり、結婚を機に自立しようとする場合です。
貸付額の上限は30万円で、婚姻届の提出を見込んだタイミングで使えます。無利子での貸付が基本で、償還期間は5年以内が目安とされています。
結婚にともなう生活基盤の整備を目的としているため、用途が明確である必要があります。
申請は市区町村の母子・父子自立支援窓口で行われ、婚約証明や住民票などの書類の提出が必要です。
審査では本人の将来的な生活設計や経済状況も考慮され、制度の趣旨に合致するかどうかが確認されます。
住宅資金
住宅資金は、ひとり親家庭が自らの住まいを確保し、安定した生活を営むために必要な資金を支援する制度です。
持ち家の取得や住宅の増改築、老朽化に伴う補修など、住環境の整備に関わる大きな支出は、収入の限られた家庭にとって大きな負担となります。
そこで、この貸付制度を活用することで、無理なく住環境を整えることが可能になります。
対象は、母子家庭または父子家庭の保護者で、自己所有の住宅を取得・改修したいと考えている方です。
貸付の上限額は1,500万円(新築)または250万円(改修)と高額で、返済期間は最長で20年です。
利子は無利子もしくは年1.0%で、無理のない返済計画を立てることができます。
住宅ローンの代替として利用できることから、民間金融機関での借入が難しい家庭にとっては、とても効果的な選択肢です。
申請には、住宅の登記簿謄本や改修計画の見積書、本人の収入証明などが必要で、細かな審査が行われます。
審査には時間がかかるため、余裕を持って手続きを開始することが推奨されます。
転宅資金
転宅資金は、ひとり親家庭がやむを得ず住居を移る必要が生じた際に、その引っ越し費用や新たな住居への入居費用などを支援するための貸付制度です。
DVや住環境の悪化、家主の都合による立ち退き、職場や学校への通学環境の改善など、転宅を余儀なくされる理由はさまざまです。
経済的に余裕のない状況では、引っ越し自体が生活再建の障壁となることもあるため、この制度は大きな助けとなります。
対象となるのは、母子家庭または父子家庭の保護者で、転宅の必要性が認められる場合です。
貸付額の上限は26万円で、敷金や礼金、引っ越し業者への費用、家電など生活必需品の購入費用などが含まれます。
多くの場合は無利子での貸付が可能であり、返済期間は最長で6年です。
返済の据置期間も設けられており、転居直後の生活が落ち着いてから返済を始めることができます。
申請には、転居理由の説明書や転居先の賃貸契約書の写し、見積書などの提出が必要です。
就職支度資金
就職支度資金は、ひとり親家庭の子どもや保護者が新たに就職する際に、就職に必要な費用を支援する貸付制度です。
就職が決まっても、スーツや作業着の購入、通勤定期券、必要な道具の準備など、意外と多くの初期費用がかかります。
こうした支出を理由に就職を断念することがないよう、経済的な壁を取り除く目的でこの資金が設けられています。
貸付の対象は、就職先が決定しており、近々就業を開始する予定の母子・父子家庭の保護者またはその子どもです。
貸付上限額は10万円で、無利子で使えます。返済期間は原則として5年以内とされ、すぐに返済を求められるのではなく、生活の安定後に返済を開始できる据置期間も定められています。
民間のローンでは対応できないような少額・短期のニーズに応える点が、この制度の特徴です。
申請は市区町村の福祉窓口を通じて行われ、雇用契約書や就職決定通知、費用の内訳などの書類が必要です。
修業資金
修業資金は、ひとり親家庭の子どもや保護者が、特定の職業に就くために必要な技能や知識を身につける「修業」にかかる費用を支援する制度です。
修業とは、資格取得のための実務研修や職業に必要な実習、長期の専門講座などを含み、就職に直結するスキルを養う機会として、とても重要です。
しかし、その過程で発生する交通費や教材費、道具代などは自己負担になることが多く、経済的に厳しい家庭では躊躇する要因となりがちです。
この資金の貸付対象は、職業に必要な訓練を受ける計画を持ち、実際に通学や受講が決まっている母子・父子家庭の保護者またはその子どもです。
貸付限度額は月額68,000円(通学制の場合)で、期間は最長で2年間程度となっています。
利子は基本的に無利子で、修業期間中は返済が猶予され、修了後に返済が開始される仕組みです。
就業につながる修業であれば、費用の幅広い用途が認められます。
申請は居住地の福祉事務所を通じて行われ、修業先の証明書や費用明細、本人の就労目標などが審査資料となります。

利用限度額が最大800円であり、膨大な資金を調達できます!
融資も最短15分で完了するためすぐに借り入れが可能。
スピーディに多額の資金を調達する際におすすめです。
モビットの詳細・申込みページへ>>
個人事業主が国からお金を借りる方法とは?日本政策金融公庫の融資制度を紹介
日本政策金融公庫が提供する融資制度は、創業間もない個人事業主や小規模事業者が、資金の調達や経営を改善するために利用する公的支援制度です。
担保や保証人がいなくても借りられることも多く、民間金融機関の審査に通りにくい事業者にとって重要な選択肢です。
日本政策金融公庫が提供する融資制度は、個人事業主が創業や経営の安定化に必要な資金を、公的な立場から低金利・柔軟な条件で借りられる仕組みです。
新創業融資制度
新創業融資制度は、これから事業を始めようとする人や開業から間もない個人事業主を対象に、日本政策金融公庫が無担保・無保証で融資を行う制度です。
自己資金が創業時は少なく、金融機関からの借入が難しいケースも多いため、この制度は初期の資金調達手段として大切になります。
起業に伴う設備投資や仕入費、事務所の賃料、広告宣伝費など、幅広い用途に対応しています。
融資限度額は原則として3,000万円まで(うち運転資金は1,500万円以内)で、金利はおおむね年1.5~2.5%程度です。
固定金利で借りられるため、将来の返済計画が立てやすいのも特徴です。
担保や保証人が不要な代わりに、審査では事業計画書や収支予測の内容が重視されます。
一般貸付(普通貸付)
一般貸付(普通貸付)は、日本政策金融公庫が実施する中で最も幅広い事業者を対象とした基本的な融資制度です。
創業後ある程度の運営実績があり、今後の事業拡大や資金繰り改善を目指す個人事業主にとって、使い勝手の良い制度といえます。
運転資金や設備投資、事務所の改修費、人件費など、ほぼすべての事業用途に対応しています。
融資限度額は通常4,800万円までですが、特定の設備資金などに関しては7,200万円まで拡大される場合もあります。
金利は融資内容や経営状況により異なりますが、民間金融機関に比べて低く設定されており、返済期間も最長で20年と長めです。
過去の決算書や納税証明書などから経営状況が審査されるため、ある程度の財務管理が求められます。
災害貸付(特別貸付)
災害貸付(特別貸付)は、自然災害によって事業に甚大な被害を受けた個人事業主や中小企業を対象に、日本政策金融公庫が低利または無利子で資金を貸し付ける制度です。
地震や台風、豪雨、火災などにより営業継続が難しくなった場合、その復旧や再建に必要な費用を速やかに確保できるよう設計されています。
融資限度額は7,200万円までで、用途はとても広く、設備の復旧や事業所の再建、被害に伴う仕入資金、従業員の人件費などさまざまです。
金利は通常の融資に比べて低く、条件によっては据置期間や返済期間の優遇措置が設けられます。
申請にあたっては、被災証明書や罹災証明書のほか、被害内容を示す写真や修繕計画書などの書類が必要になります。
この制度の特徴は、災害直後の混乱した時期に迅速な対応が可能な点です。
マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
マル経融資(小規模事業者経営改善資金)は、商工会または商工会議所の支援を受けている小規模事業者を対象に、日本政策金融公庫が無担保・無保証で融資を行う制度です。
店舗や設備の老朽化、資金繰りの悪化など、経営改善に向けた資金ニーズに柔軟に対応することを目的としています。
対象は、常時使用する従業員が商業・サービス業で5人以下、製造業・建設業などで20人以下の個人事業主です。
融資限度額は2,000万円で、運転資金・設備資金のどちらにも対応しています。
金利は非常に低く、融資時点の基準金利よりも優遇されるケースが多いため、資金負担を軽減したい事業者にとっては魅力的な制度です。
返済期間は運転資金で7年以内、設備資金で10年以内が目安となっています。
申請には、6か月以上継続して商工会や商工会議所の経営指導を受けていることが条件です。
生活衛生改善貸付
生活衛生改善貸付は、飲食業、理容・美容業、旅館業、クリーニング業など、生活衛生関連業種を営む個人事業主を対象にした融資制度です。
これらの業種は、衛生管理や設備の維持が事業継続に直結するため、老朽化した施設の改修や新設備の導入などに資金が必要になる場面が多くあります。
そうした現実に対応するために、この制度が設けられています。
貸付対象となるのは、生活衛生関係営業者で、都道府県の生活衛生営業指導センターを通じて経営指導を受けていることが条件です。
融資限度額は2,000万円までで、用途は設備資金・運転資金の両方に対応しています。
金利は低めに設定されており、返済期間も最長で20年と比較的長期で計画が立てやすい点も特徴です。
申請には、経営指導センターからの推薦書や、資金使途を示す見積書、決算書類などが必要です。

プロミスは最短3分で即日融資可能な消費者金融カードローンです!
上限金利が18.0%であり、他の消費者金融と比較して低めです。
今なら初回利用時から最大30日間の無利息期間が適用されるキャンペーンを実施中です!
プロミスの詳細・申込みページへ>>
即日国からお金を借りることは難しい?なぜ審査に時間がかかるのか
国が提供する貸付制度は、民間のカードローンなどと異なり、申請から資金の振込までに一定の時間がかかることがほとんどです。
「今すぐにでもお金が必要」という状況において、公的制度がすぐに対応できない理由にはいくつかの事情があります。
この章では、なぜ国の貸付制度で即日融資が難しいのか、その背景を3つの視点から解説します。
審査が非常に慎重であるため
国の貸付制度は、税金や公的資金を原資としているため、審査が非常に慎重です。
申請者が本当に支援を必要としているかを見極めるために、収入状況、世帯構成、生活費の内訳、就業状況など多くの情報が確認されます。
制度によっては自治体の福祉担当者との面談が求められ、そこで生活状況や支援の必要性が丁寧に確認されます。
また、必要書類の数も多く、ひとつでも不備があれば差し戻しとなるため、申請者側の準備にも時間がかかります。
さらに、審査には複数の関係部署が関わることが多く、内部確認に日数を要する場合もあります。
即日融資が難しいのは、こうした「確実性と公正さを重視した審査体制」が背景にあるからです。
即日対応可能な制度設計ではないため
多くの公的貸付制度は、制度設計の段階から「即日融資」を目的としていません。
生活や経営の安定を中長期で支援するという理念のもとに構築されており、緊急性よりも継続性・公平性を重視しています。
そのため、申請には収入証明や用途確認書類の提出に加え、支援内容の妥当性を確認する面談や事前相談が必要になることが多いです。
さらに、関係機関とのやり取りや内部審査にも一定の時間がかかります。
制度によっては、審査結果が出るまでに1~2週間、その後の手続きで資金が振り込まれるまでさらに数日を要することも珍しくありません。
即時対応を前提としていない構造上、どれだけ急いでも、民間のカードローンのようなスピード感は期待できない仕組みとなっています。
不正受給や詐欺を防止するため
国の貸付制度では、過去に発生した不正受給や詐欺の事例を踏まえ、チェック体制がとても厳格に整備されています。
税金や公的資金を財源としている以上、本当に困っている人に確実に支援を届けることが求められ、不正を未然に防ぐための対策が重視されています。
そのため、申請者には収入証明書、住民票、本人確認書類の提出が義務付けられており、制度によっては生活状況を確認するための面談や家庭訪問が実施されることもあります。
また、申請内容の裏付けとして、就業先への在籍確認、支出の明細、さらには申請理由を証明するための関連書類(退職証明や医療費領収書など)の提出が必要とされるケースもあります。
こうした厳格な対応により、制度の透明性と公平性は保たれますが、その分、審査には多くの時間と手間がかかることになります。

最大365日と無利息期間の長さが優れている消費者金融です!
原則勤務先への在籍確認も実施しておらず、書類で審査可能。
事前に返済額や総額をシミュレーションすることもできます。
レイクの詳細はこちら>>
国からお金を借りることができなかったときは自治体の助成金制度も活用しよう
国の貸付制度には審査があり、すべての申請が必ず通るわけではありません。
必要性が認められない場合や、書類の不備、要件を満たしていないことが理由で不承認となるケースもあります。
そうしたときには、地方自治体が独自に実施している助成金や給付金制度を検討してみることが大切です。
自治体による支援制度は、地域の特性や住民の実情に応じて設計されており、国の制度と比べて柔軟性があるものも少なくありません。
たとえば、生活困窮者向けの家賃補助、ひとり親家庭への子育て支援金、中小事業者向けの家賃補助や事業継続支援金などが各市区町村で用意されています。
これらは住民税非課税世帯や低所得世帯を対象にしたものが多く、所得基準さえクリアすれば無返済で受け取れるケースもあります。

利用限度額が最大800円であり、膨大な資金を調達できます!
融資も最短15分で完了するためすぐに借り入れが可能。
スピーディに多額の資金を調達する際におすすめです。
モビットの詳細・申込みページへ>>
国からお金を借りることに関するよくある質問
国からお金を借りることについて、多くの人が国や自治体などに寄せている質問と質問への回答を紹介します。
無職でも国からお金を借りられますか?
無職でも国からお金を借りられます。無職の場合に利用するのを推奨するのは、総合支援資金制度です。
総合支援資金制度は生活を立て直すことが目的の制度なので、無職で無収入でも今後就職して生活を立て直そうという意思がある人ならお金を貸してもらえます。
市役所や自治体で即日お金を借りる方法はありますか?
国の公的融資制度は審査に時間がかかるので消費者金融のような即日融資はできませんが、市役所・自治体も同じ事情で即日お金を借りる方法はありません。
お金が早く必要な場合には消費者金融などの利用をおすすめします。
生活福祉資金貸付制度の審査に落ちることはありますか?
生活福祉資金貸付制度の審査は銀行カードローンより通りやすいと言われていますが、審査に落ちることもあります。
審査に落ちる理由は以下の通りです。
- 経済的に余裕があると見なされた
- 他の制度・給付金を利用可能
- 虚偽申請をした
- 債務整理を開始した直後
- 住所が決まっていない
- 自分以外の家族がすでに生活福祉資金貸付制度を利用している
- 今後も収入を得る見込みがなく返済能力がないと見なされた
上記理由に該当する人は、違う方法でお金を借りましょう。

プロミスは最短3分で即日融資可能な消費者金融カードローンです!
上限金利が18.0%であり、他の消費者金融と比較して低めです。
今なら初回利用時から最大30日間の無利息期間が適用されるキャンペーンを実施中です!
プロミスの詳細・申込みページへ>>
まとめ
国からお金を借りる制度は、生活の不安や事業運営の課題に直面した際、確かな支援となる手段です。
特に収入が不安定な個人や、創業間もない事業者にとって、無担保・低金利での融資が受けられる点は大きな安心材料です。
生活福祉資金貸付制度や母子父子福祉資金貸付金制度、日本政策金融公庫による各種融資など、制度の選択肢は多岐にわたり、自身の状況に合った支援策を見つけやすくなっています。
ただし、いずれの制度にも利用条件や審査手続きが存在し、即日の対応は難しいケースがほとんどです。
そのため、早めに情報を集め、必要書類を整えることがスムーズな申請への第一歩となります。
また、万が一国の制度が使えなかった場合でも、各自治体が独自に行う助成金制度を検討することで、生活再建や事業継続への道がひらけます。
重要なのは、「支援があることを知り、適切に活用すること」です。
一人で悩まず、制度を上手に使いながら、安定した未来を築いていきましょう。

最大365日と無利息期間の長さが優れている消費者金融です!
原則勤務先への在籍確認も実施しておらず、書類で審査可能。
事前に返済額や総額をシミュレーションすることもできます。
レイクの詳細はこちら>>
この記事を書いた人
エレビスタ ライター
エレビスタは「もっと"もっとも"を作る」をミッションに掲げ、太陽光発電投資売買サービス「SOLSEL」の運営をはじめとする「エネルギー×Tech」事業や、アドテクノロジー・メディアなどを駆使したwebマーケティング事業を展開しています。
エレビスタは「もっと"もっとも"を作る」をミッションに掲げ、太陽光発電投資売買サービス「SOLSEL」の運営をはじめとする「エネルギー×Tech」事業や、アドテクノロジー・メディアなどを駆使したwebマーケティング事業を展開しています。







