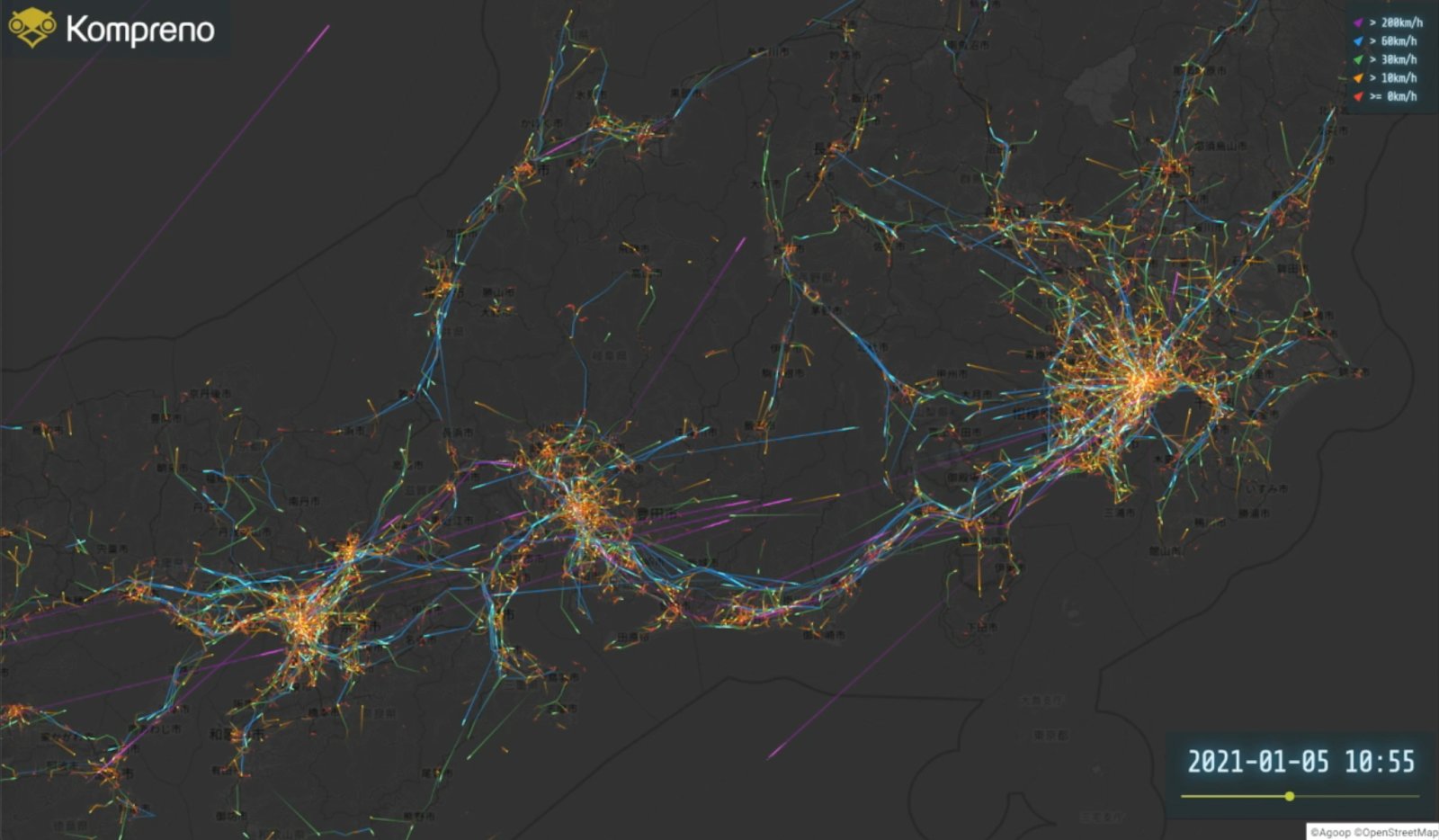中澤 静男
1960年4月1日、大阪市生まれ。公立学校教員・教育委員会指導主事を経て、2011年より現職。
日本の科学技術や経済の発展に寄与することができる人材の育成として「学力向上」が叫ばれる中、これからの時代は競争ではなく共創の時代になるという考えからESD(持続可能な社会の担い手を育てる教育)に注目、以後研究を続ける。現在は、2015年に採択されたSDGs(持続可能な開発目標)の食料問題とエネルギー問題に着目し、農業実践にも取り組んでいる。
目次
introduction
大学で行われるSDGsの取り組みにフォーカスしインタビューする本企画。今回は、SDG大学連携プラットフォーム(SDG-UP)に参加する奈良教育大学の准教授 中澤静男さんへインタビューさせていただきました。
日本が誇る歴史都市である奈良で、早い段階からESDの重要性に着目し研究を続けてきた中澤様。インタビューを通して、奈良教育大学として推進する「歴史文化遺産を通したESD」とはどういったものかを教えていただきました。
将来教員を目指している方、教育の観点から見たSDGsに興味がある方は、この記事を読むことで未来につながるヒントが得られるかもしれません。是非最後まで読んでみてくださいね!
ESDに取り組み始めたきっかけ
–本日はよろしくお願いいたします。奈良教育大学では、大学の3つの柱の一つとして「持続可能な社会づくりに貢献できる教員の養成」を掲げ、ESD(持続可能な開発のための教育)に力を入れていらっしゃいますね。どういったきっかけでESDに着目されたのですか?
中澤さん:
大学がESDに着目するようになったのは、当時社会科教育講座におられた田渕五十生先生が努力されて、2007年に奈良教育大学をユネスコスクールに加盟登録されたのがきっかけだと思います。
そもそもESD(持続可能な開発のための教育)という考え方は、1992年ブラジルのリオデジャネイロで開催された地球サミットで生まれたものです。人々の社会づくりに関する価値観や行動の変革を促すことで、持続可能な社会実現を目指す教育のことを指します。
その後2002年に行われたヨハネスブルグサミットを経て、このESDを世界中に広める流れが生まれました。
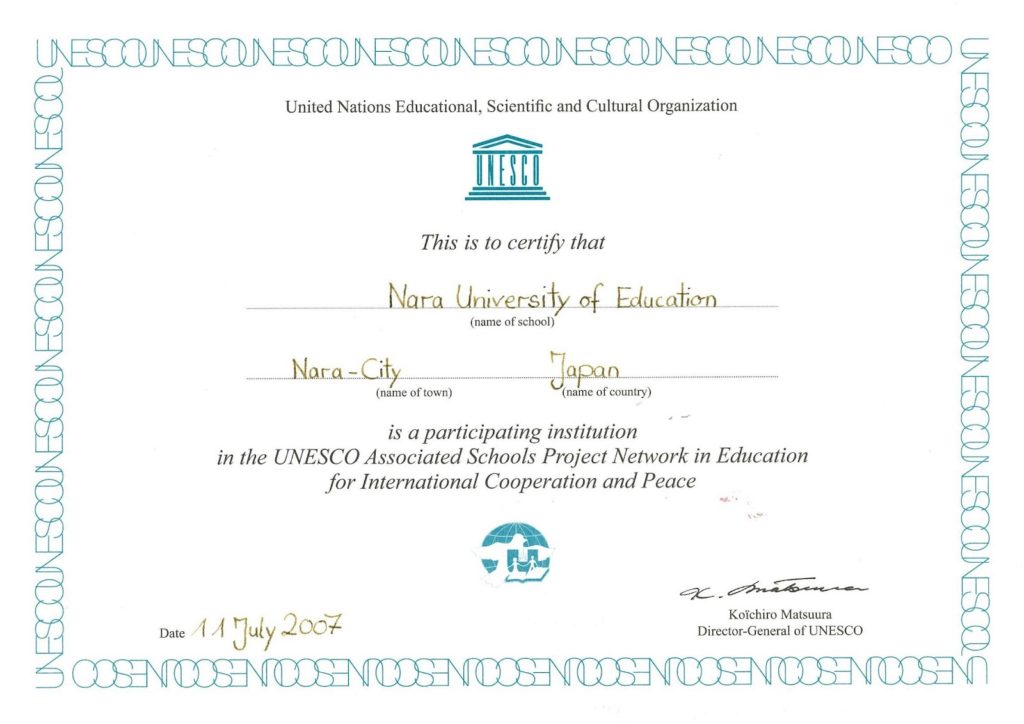
奈良教育大学としては、それまで30年以上にわたり人権教育や環境教育、文化教育に力を入れていました。これをさらに国際的なものへとレベルアップさせるために、2007年に国際平和と人権の福祉の促進を目指すユネスコスクールに加盟したのです。その後の2014年に日本/ユネスコパートナーシップ事業に採択されたことでESDが大きく広がり始めました。
具体的には、まず「奈良ESDコンソーシアム」を立ち上げ、近畿圏を中心にESDの推進を行いました。
2017年には「近畿ESDコンソーシアム」と名称を変え、全国を対象にESDの指導ができる教員の育成やNPO、企業との連携を進めています。
「教育の未来にESDが必要だ」と確信した出来事
–中澤さんは、もともとESDに興味があったのですか?
中澤さん:
いえ、そういうわけではありません。2007年までは大学の教員ではなく、奈良市教育委員会にいたんです。当時、奈良教育大学に在籍されていた田渕五十先生から「大学でユネスコ東アジア地域世界遺産教育国内ワークショップが開かれるから聞きに来たら?」と声をかけてもらったのが、ESDに興味を持ったきっかけでした。
そこで、当時ユネスコスクールの責任者を務めていたニーデルマイヤー博士によるESDについての講演を聞き、雷に打たれたかのような衝撃を受けたんです。それまでESDについて全く知らなかった私は、「これからの教育に必要なのはESDだ!」と確信しました。
–まさに運命の出会いだったのですね!
中澤さん:
そうですね。これをきっかけに、奈良で行われている世界遺産学習をESDの考え方を基盤にした世界遺産学習に作り変えようと決意しました。時期を同じくして、奈良教育大学がESDを行う教員を募集しているのを知りすぐに応募、現在に至るというわけです。
奈良の歴史文化遺産からSDGs達成のヒントを得る
–奈良教育大学におけるSDGsの取り組みの特徴を教えてください。
中澤さん:
一番の特徴は、歴史文化遺産を通したESDを行っている点です。
奈良には、東大寺や興福寺など8つの建築物を総称した「古都奈良の文化財」が世界文化遺産として登録されています。そのうち、平城宮跡以外は1300年もの間、今も受け継がれています。つまり、1300年間にわたって、現役であり続けているということです。これらの文化遺産から持続可能な社会を作っていくためのヒントが得られるのではないかと考えたのです。
このような歴史文化遺産を通したESDを行っているのは、奈良教育大学だけで、全国的に見てもかなり珍しい取り組みだと言えるでしょう。

–歴史文化遺産を通したESDとは、具体的にどういったものなのでしょうか?
中澤さん:
東大寺を例にして説明しますね。
奈良に観光に来られた方のほとんどが、東大寺の大仏様を見て行かれます。「なぜ大仏様を見に行くのですか?」と聞くと、ほとんどの方が「大きいから」「古いから」と答えるんですよね。でも、東大寺の大仏様の本来の価値は全然違います。東大寺の大仏様にどんな想いが込められているのか。ここが、歴史文化遺産を通したESDのポイントととなるのです。
実は、東大寺の大仏様が作られた752年の記録を見ると、奈良時代は天候不順が原因で大きな飢饉が3回もあったことが分かっています。

743年に聖武天皇が出した盧舎那仏造顕の詔(るしゃなぶつぞうけんのみことのり)には、東大寺の大仏様を作る理由として、2つのことが書かれていました。
一つは「乾坤相泰(けんこんあいやすら)かに」。「乾坤」というのは天と地、つまり気候がいつも通り穏やかで地震などがなく平穏であってほしいということを言っています。
これはSDGsの13番「気候変動に具体的対策を」や11番「住み続けられるまちづくりを」に当てはまります。また、飢饉を無くしたいという願いは2番の「飢餓をゼロに」に直結しますよね。
もう一つは「動植ことごとく栄えんことを欲す」です。これは、全ての動植物が栄える世の中にしたいということを意味し、SGDsの14番「海の豊かさを守ろう」、15番「陸の豊かさも守ろう」に該当します。
これ以外にも、天然痘の流行や争いなどをなくし平和な世の中を築きたいとの願いが、東大寺の大仏様に込められているのです。
–奈良時代の人が平和を願って作った大仏様が、時を越えて現代を生きる私たちにどんなメッセージを伝えているのか。しっかりと学び、持続可能な社会を実現するために、活かしていかなければいけませんね。
中澤さん:
そうですね。2009年には、世界遺産を通して自分の住む町をもっと大好きになってほしいという願いを込めて本を作りました。これは、今でも奈良市の小学5年生に全員配布されています。奈良市出身の本学の学生から「先生、世界遺産学習をするなら良い本知ってるよ」と紹介されたことがあるくらい、しっかりと浸透してくれているようで大変嬉しいです。
–素晴らしいですね。色々な形で世界遺産学習の普及に力を入れられているのですね。
中澤さん:
はい。私は、東大寺の大仏様を見られた方に必ず聞くことがあります。それが「奈良時代の人は、様々な問題を解決するために仏教という考え方を基盤に大仏様を造りました。では、SDGsに示された地球的課題を解決するために、あなたはいつから何をしますか?」ということです。
課題の解決を人任せにしてはいけません。持続可能な社会をつくるための価値観を浸透させ行動を促すことが、ESDの本質と言えるのかもしれません。
▲中澤さんが執筆し、奈良市教育委員会が発行している。
ESDを学ぶと子どもが変わる
–ESDを通じて、どのような効果を実感されていますか?
中澤さん:
2つあります。1つは、子どもたちが学習に対して前向きになっていくことです。
奈良教育大学では、教員を目指す学生や現職教員たちを対象に、ESDを行える人材を育成する「ESDティーチャープログラム」を行っています。先生方がESDを実践できれば、目の前の30人の子どもや、その後ろの保護者、さらには地域全体へと広がり持続可能な社会実現に近づくと考えているからです。
このプログラムを始めるにあたり、全国の教員委員会やユネスコスクールを支援する大学のネットワークでヒアリングを実施しました。そこから、教員としての基盤的力量はもちろん、SDGsなどのグローバルな課題への関心、地域自体を教材化するための探求心や指導計画作成能力が必要であることがわかりました。
これらの調査研究をもとに、5つの系統的な研修によるESDティーチャープログラムを構築しました。現在、教員を目指す学生とESDを勉強したい現職教員が一緒になってESDティーチャープログラムに参加してくれています。各自が作成した単元構想案や学習指導案の相互検討会などを行うことで、ESDやSDGsへの理解を深め、互いの実践力を高める場になっています。

実際にプログラムに参加している現職の教員からは、「ESDをやると子どもが変わる」という声を数多くいただいています。ESDを行うことで、子どもたちが学習に対して前向きになっていくことを、教員たちも実感されているようです。
修学旅行を通じたSDGs体験
もう一つ効果を実感しているのが、「奈良の修学旅行を変える」という取り組みです。
これまで修学旅行で奈良に来る子どもたちは「歴史に触れる」ことが主な目的でした。それを「奈良でSDGsを学ぶ」というテーマに変えられるよう、商工会議所や旅館組合、観光業組合と共に活動しています。様々な企業と連携することで、活動に広がりが出てきました。
具体的には、まず奈良教育大学でSDGsについての講義を受けてもらい、その後奈良のフィールドワークに出かけていくという形式です。今までは教科書に載っているものを実際に見るというだけだったものに新たな視点が加わると思います。

–修学旅行という体験を通じてSDGsが学べるというのは、とても面白いですね。
中澤さん:
神社仏閣はもちろん、例えば奈良の鹿からも学べることはあるでしょう。町のいたるところにいる野生の鹿は、餌付けしていなくても人間に近づいてきます。それはやはり、奈良の人と鹿の1300年にもわたる共生の歴史というのがあるのではないかと思うのです。こういったところにも、自然共生社会のヒントが隠されているのではないかと感じています。
奈良でSDGsのことを学んだ子供たちにも、「あなたたちは地元に戻って何をしますか?」と必ず問います。そうすると、地元に帰ってから行動を始めてくれるんですよね。これは非常に学習効果が高いと感じています。奈良へ修学旅行に訪れることが、日本各地のさまざまな地域を変えていく力になって欲しいと期待しています。

持続可能な社会をつくる人材のネットワーク構築を
–SDGsの取り組みを、今後どのように発展させる予定ですか?
中澤さん:
ESDが指導できる教員の養成だけでなく、NPOや企業との連携にも力を入れていきたいと考えています。
来年度、奈良教育大学にESD・SDGsセンターを作る計画があります。そこではこれまでのESDを核とした教員養成や現職教員のESD研修を充実・拡大していきたいと考えています。
既に福岡市や大牟田市、那覇市、山形市などでESDティーチャープログラムを開催しました。そこで学ばれた先生方が中心となって、各地でESDの研究会を立ち上げそれがネットワーク化していけばと思っています。

また、ESDサポータープログラムの構築も進めています。学校教育に、企業、NPO、自治体などが加わることで、より質が高まると考えているからです。
学校教育で大切なのは、「説明納得型」ではなく「発問対話型」の授業です。問いを投げかけることで、子供たちは仲間と相談して苦労しながら答えを導き出します。そのための伝え方や指導の行い方を学べるプログラムをつくっていきたいです。
さらに海外の研究者とのESDに関する共同研究や、海外の大学とのネットワークを築くことで、視野を広げていくことも必要となると考えています。
–ESDサポータープログラムは、誰でも参加できるのでしょうか?
中澤さん:
はい。プログラムが完成次第、来年度あたりから広報もしたいと思います。
奈良でのフィールドワークは実施すると思いますが、できるだけオンライン化しようと思いますので、全国にいるどなたでも参加可能になる予定です。
このプログラムは、主体的対話的な深い学びのできる人材育成に貢献しそうです。
本日はありがとうございました!
インタビュー動画
奈良教育大学 各種リンク
>>奈良教育大学
合わせて読みたいおすすめ記事
この記事を書いた人
スペースシップアース編集部 ライター
スペースシップアース編集部です!
スペースシップアース編集部です!