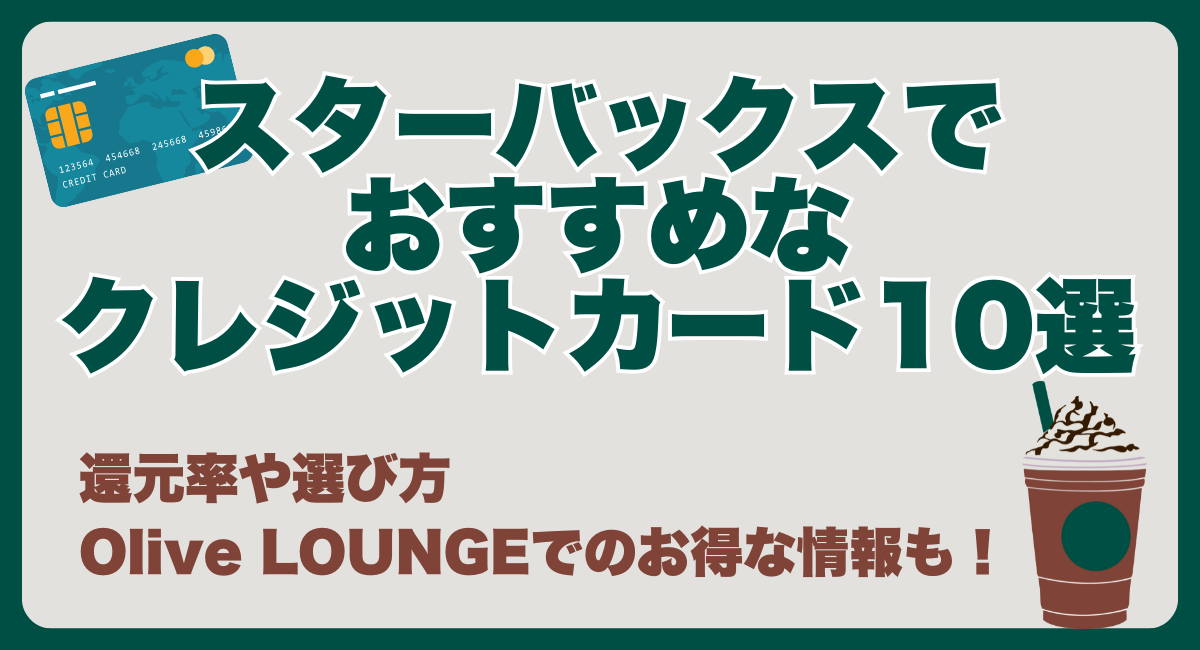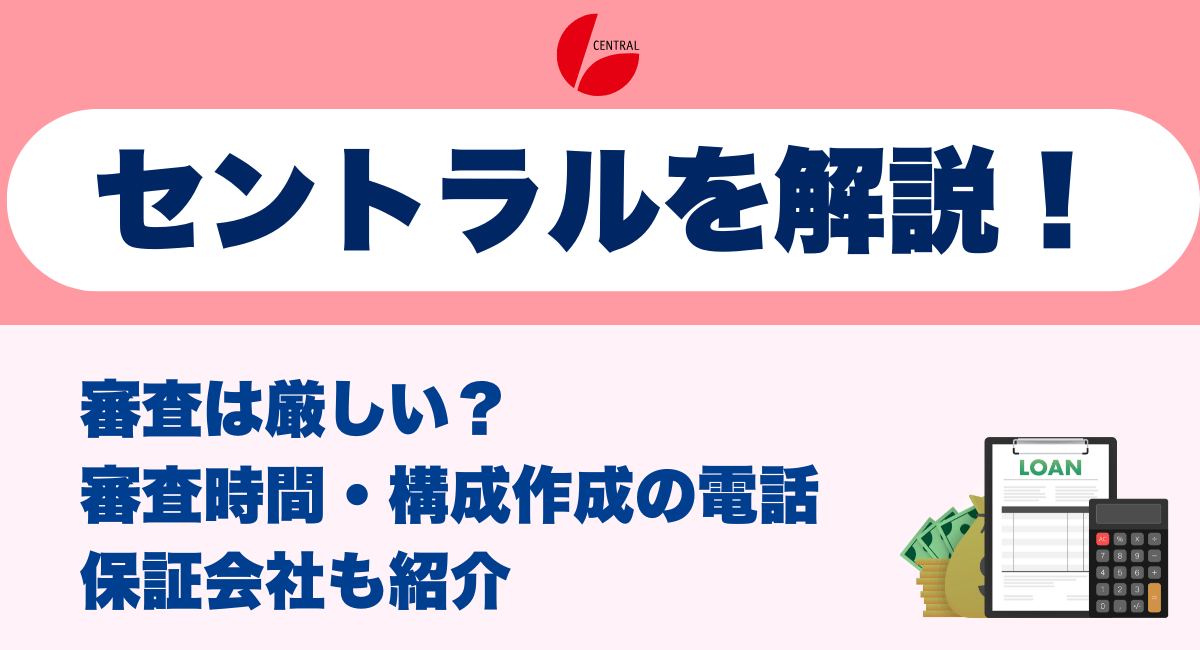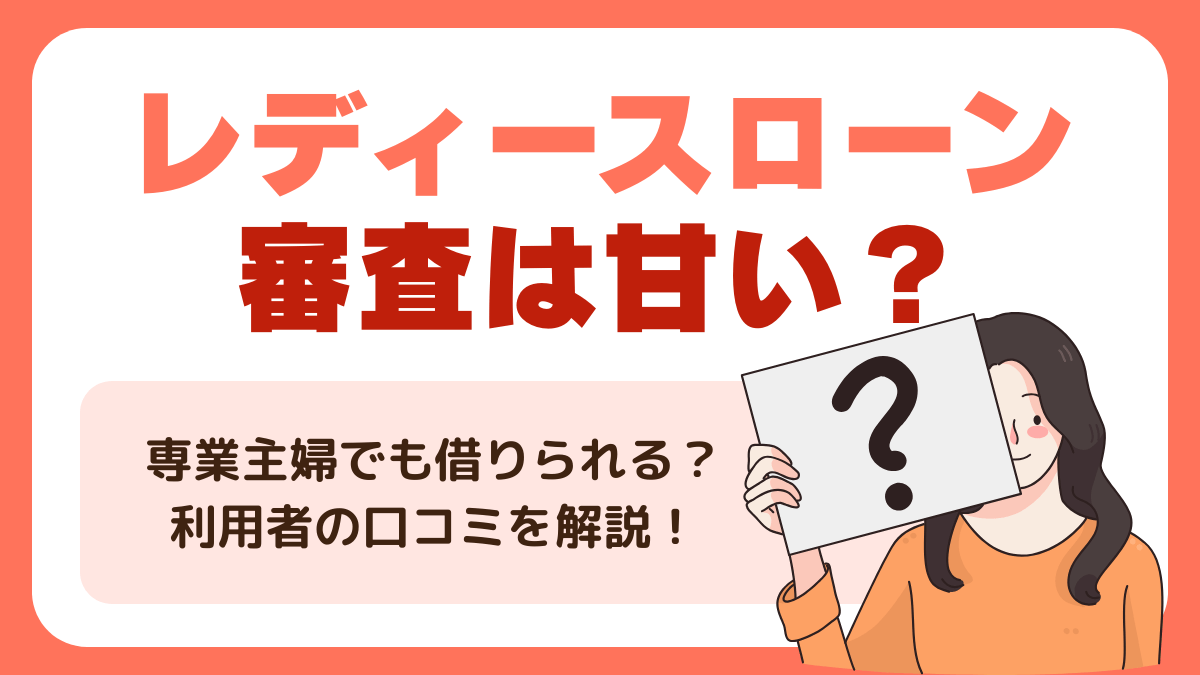株式会社坂ノ途中 横浜美由紀さん 渡邊春菜さん インタビュー
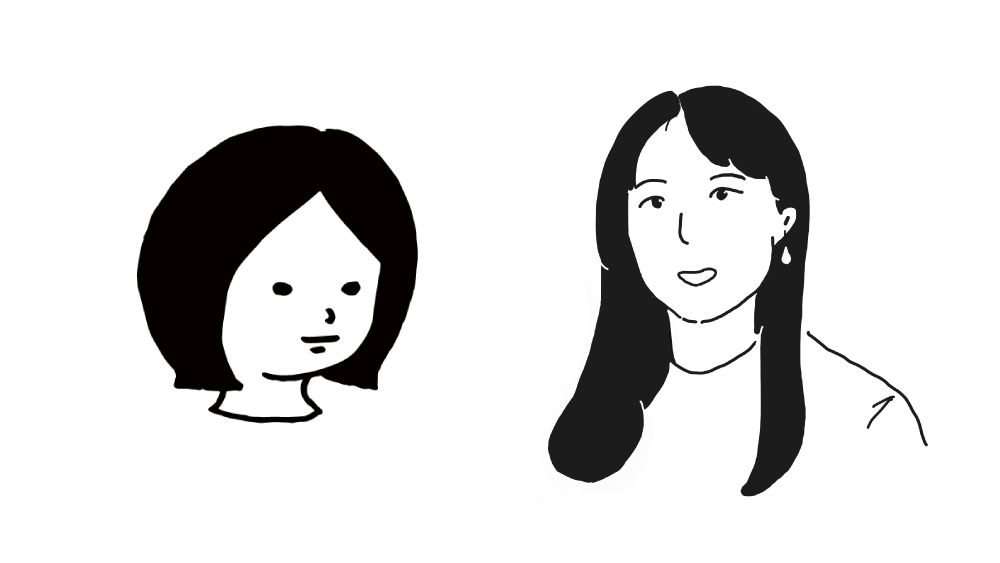
横浜 美由紀
立命館大学国際関係学部卒業。株式会社ロフトワークなどでクリエイティブディレクターを経験したのち、2018年に坂ノ途中に入社。Web/メディア担当を経て、現在は「坂ノ途中の研究室」のメンバーとして、自社が社会環境へ与えるインパクトの調査・測定、情報発信などを行っている。
渡邊 春菜
東京工業大学環境・社会理工学院修了。博士(工学)。専門はランドスケープデザイン、景観工学。大学院在学中の2021 年に坂ノ途中に入社。「坂ノ途中の研究室」のメンバーとして、新規就農者の実態調査や「坂ノ途中の報告書」の作成などに従事している。
目次
introduction
「坂ノ途中」というユニークな社名。そこには、有機栽培に取組む新規就農者が上る険しい坂を伴走したい、という思いが込められています。有機農業への参入と持続があってこそ「環境負荷の小さい農業」は広まりますが、生計が成り立たない現実も少なくありません。同社は、独自のECサイトでの定期宅配、相談対応や集積データの開示などを通じ、新規就農者を支えます。
今回は、同社の横浜美由紀さんと渡邊春菜さんに、有機農業者の現状や、ビジョンを現実化していくための様々な取組みなどを伺いました。
有機農業に挑む新規就農者の苦闘を様々な角度から支援
-まずは、業務の概要をご紹介ください。
渡邊:
「坂ノ途中」は、環境負荷の小さい農業の広がりを目指すソーシャルベンチャーです。創業は2009年で、現在は、提携生産者の野菜をECサイト経由で一般消費者に届ける「定期宅配」をメインの事業としています。オンライン以外では、レストラン、ホテル、小売店などに卸しています。

実店舗としては、京都に小さな八百屋と飲食店を経営しており、この二つが直接お客様と接する機会となっています。
海外事業では、主に東南アジアの森の中で栽培されたコーヒーを輸入し、販売しています。この「海ノ向こうコーヒー」事業では、森林減少の緩和と森林再生、現地の人々の収入向上に貢献することを目指しています。なぜならば、森林伐採や焼畑をして換金作物を育てるよりも、森の中でコーヒーを育てることが、「森林保全」と「収入も雇用も生み出せる状況」に繋がるからです。
-「坂ノ途中」という社名は、どのような背景から生まれたのですか?
横浜さん:
弊社が「何をやっているか」に直結する社名です。提携生産者の殆どが有機農業に取り組む新規就農の方々です。志は強くても、農業は厳しい世界でもあります。新規就農者の3割が5年以内に離農という話も聞きます。だからこそ、新規就農者の方々に寄り添い、経営が成り立ち農業を続けていけるように、その険しい坂を一緒に上っていきたい、という思いが社名の由来です。
-小野邦彦社長が農業分野での起業を決意なさった背景を教えてください。
横浜さん:
学生時代にバックパッカーだった小野は、様々な地で遺跡を見たそうです。眺めるうちに、「遺跡は、言うなれば人間社会が終わったあとの残骸だよなあ。現代社会も危ういのでは?」という思いが湧いてきたそうです。
そんな頃にチベットで、ヤクが草を食べて糞をし、その糞を燃料としてヤクのミルクから作ったバター茶を沸かし、糞燃料の灰を肥しにまた草が育つ、という完璧な循環を目の当たりにしました。全てそこにあるもので完結する、ずっと続けることのできる生き方はとても美しい、と感じたそうです。
環境に負荷をかけず、資源が循環する暮らしを実現するには?と考えた時、重要だと思えたのが農業でした。その結果、学生時代に「環境負荷の小さい農業を広げる」ことをテーマにいつか起業しよう、と決意したとのことです。
新規就農者が抱える収入不安
-掲げられているビジョン・ミッションをお聞かせください。
渡邊さん:
ビジョンは「100年先もつづく、農業を。」です。本来農業は、数千年単位の長い時間軸のなかで営まれてきました。しかし今の都市的、工業的な視点で近代化されてきた農業は、資源が再生されるよりも早い速度で資源を使い、生産するよりもたくさんのエネルギーを投入して成り立っています。このままの農業では、100年すら続かないかもしれません。ならばせめて100年くらいは続けられるような農業にしませんか、という意味を「100年先も続く、農業を。」に込めています。

ミッションは「環境負荷の小さい農業を広める」「多様性を排除しない流通のしくみをつくる」「ブレを楽しむ文化を育てる」の3つを掲げています。ブレを楽しむ文化、というのはちょっと分かりにくいかもしれませんね。弊社は、常々「野菜は生き物」ということを伝えています。生き物だからこそ、季節や育つ地域などによってばらつきが生じます。その「ブレ」を楽しめるような意識を醸成したい、ということです。
-「100年先もつづく、農業を。」の背景である「今の農業はいかにサステナブルでないか」について伺わせてください。
渡邊さん:
環境面で持続性が得られない要因には、農産物の大量生産、大量流通という状況が挙げられます。日本は、戦後、食料を行きわたらせることを中心に考え、大量に生産し、大量に流通させるシステムをつくりました。それが今でも食料生産・流通システムの基盤となっています。
大量に流通させるための生産方式として、化学合成農薬・化学肥料や石油エネルギーなどを投入する、環境負荷の大きい農業が一般的になりました。私たちは、「慣行農業が悪い」と捉えているわけではありません。その地域の風土にもよるでしょう。たとえば砂漠地帯などの食料生産が困難な地域であれば、工場を作って効率的に生産することが必要かもしれません。ただ、一般的には現代農業は環境面でサステナブルとは言えません。
また、有機農業は環境面でサステナブルでも経済面ではサステナブルとは言えません。新規就農者の多くは生産量が少量不安定になりがちで、大量生産・大量流通の仕組みに入りにくいという構造的な問題があります。農業だけで生計を立てるにはハードルが高くなっていて、それが、有機農業が広がるスピードを阻んでいるように思います。

-有機農業を目指す新規就農者の現状を詳しくお聞かせください。
渡邊さん:
日本政府は「2050年までに有機農地の面積を全体の25%にする」という目標を掲げ、有機農業を進めようとしています。しかし、現状では、有機農業に取り組むのは全農業従事者のうちわずか0.5%(※1)です。一方、就農を希望する人々にアンケート(※2)を取ると、9割くらいが有機農業を「やってみたい」「興味がある」と答えているんです。実際に新規就農者で有機農業に取り組む生産者は2割程度と高いです。農業の高齢化も進んでいますし、これからは若い世代の有機農業者を増やすことに取り組むことが、有機農業を広げる現実的なシナリオだと考えています。
しかし、有機農業を想定した新規就農者支援はまだまだ整備されていないのが現状です。
(※1)出典:農林水産省「有機農業をめぐる事情」
(※2)出典:全国農業会議所「2010年度新・農業人 フェアにおけるアンケート結果」
-御社が提携する新規就農者に、何らかの条件を課されていますか?
渡邊さん:
通常、有機農業、有機農産物を扱う流通の会社は、例えば生産者に有機JASなどの認証を要求するケースが多いんです。弊社は、栽培期間中に化学肥料・化学農薬不使用などの独自の取扱基準を設け、いわゆる「認証」は必要としていません。認証を得るには、資金も時間もかかりますから。そこではなく「生産者さんの農業に対する姿勢」にも重きを置くことが、弊社の特徴です。
例えば、品質の向上や美味しい品種を見出す努力、地域社会に融けこみ貢献する意欲、なども重視します。このあたりは、仕入れ担当者が取引の際に生産者さんにしっかりとヒアリングしています。
農業をやる人たちにも様々な観点があります。農的な暮らしをしたい、「坂ノ途中」のような会社に卸したい、どんどん規模を大きくしたい、などの営農スタイルが、弊社とマッチングするかどうかは大事なところです。
「生き物」である野菜の「個性やブレ」を楽しむ意識を醸成
-提携する新規就農者への支援や事業の詳細を、3つのミッションに添ってお聞かせください。まずは「環境負荷の小さい農業を広める」取り組みについて伺います。
横浜さん:
具体的には、新規就農者の方々からの相談を受け、一緒に「いつ、どんな野菜をどれくらい作るか」という作付けの計画を立てます。計画を立てるにあたり、生産者担当チームが相談に乗れる体制を整えています。そして、できた野菜を買い取って販売するところまでを、一貫して行っています。
海外では、「海ノ向こうコーヒー」事業において、森林伐採を防ぐために、森の中で栽培する「アグロフォレストリー」農法によるコーヒー豆を主に東南アジアから輸入し、販売しています。コーヒーは、直射日光が苦手で、木陰でゆっくりと育つことで味がのる作物なんです。その中で現地の農家さんと一緒に、より美味しくなる方法を考えたり、環境負荷を下げるためのワークショップを開いたりしています。当初は東南アジアのみでしたが、現在は30カ国以上から豆を仕入れています。現地の雇用を生み出すという貢献もできていると思います。

-「多様性を排除しない流通のしくみをつくる」ための取り組みをお聞かせください。
横浜さん:
まずは「野菜にはいろいろな個性がある」ことの周知から始まります。例えば、スーパーだと規格が厳しく設定されていて、大根はこのサイズで傷はなし、などとなります。本来野菜は生き物ですから、いろいろな形や大きさがありますし、自然環境の影響を受けていろいろ変化するものなんです。
なぜそんなに厳しい規格が出来上がってしまうかについては、消費者側が生産者側のことを知らず、生産者側も消費者側のことをあまり知らない状況が大きいですね。その間に入るスーパーや卸業者、小売店も疑心暗鬼になり、こういう野菜を売ったらクレームに繋がるのではないか?などの恐れが生まれてしまうと感じます。
多様性を切り捨てない販売の流れ、バリューチェーンの再構築をしたい、というのが弊社のスタンスです。その結果として採用しているのが、ECサイトによる野菜の定期販売です。

渡邊さん:
弊社のお野菜セット定期便の特徴は「消費者が内容を選べない野菜セット」というところにあります。他社さんでは、「好きな野菜」をオーダーするかたちが多いのですが、そうではなく、その時の仕入れ状況や季節などを考慮しながら、担当者がセット内容を決めていきます。
スーパーでは見かけない野菜や、自分からは手に取らない「珍しくて美味しい」「意外に美味しい」野菜もあるんです。今であれば「のらぼう菜」などがそれにあたります。また「菜の花」は、アブラナ科の野菜の花全体を指し、大根の菜花、白菜の菜花などいろいろあるんです。畑で時期を逃してしまった白菜を、菜花として出荷してもらうことで、農家さんの追加収入になったり、消費者には季節を感じるセットを提供できたりと、育てる人も食べる人も互いにうれしい仕組みを整えているんです。多様な取り扱いをすることで、年間400種類くらいの野菜がセットの中に入りますし、「選べない豊かさ」を楽しんでいただければ嬉しいですね。

-「ブレを楽しむ文化を育てる」というミッションについての取り組みにはどのようなものがありますか?
横浜さん:
野菜セットに添えるお便りなどを通じて、野菜の多様性、季節、自然環境による「ブレ」を丁寧に説明することで、そこを分かっていただき、楽しんでもらえるような意識の醸成に努めています。
「おまかせ」を許容しなきゃ、というのではなく、気づいたらいろいろな野菜が食べられるようになった、この季節だからこそこの野菜、と楽しめるようになった、と言っていただけるような工夫により「野菜セットという仕組み」が成り立っていると思っています。
具体的には、〈今の時期の大根に「す」が入るのは、春に芽吹くために植物がエネルギーを使っているから〉と伝えることで「季節の変化」を感じていただいたり、〈長雨のあとのトマトには、甘さが減り水分が増す〉と知っていただくことで、あの地域は雨続きだったのかと思いを馳せていただく、などの発信です。もちろん、我慢して食べてね、というわけではなく、不具合があったら代品をお送りします。〈「す」が入っていそうだから、この箱の大根は全て廃棄しよう〉という、お互いの理解が無いことにより生まれてしまうフードロスを避けたいのです。

生産者を点ではなく面で支え、「皆で生き残る」という理想
-もし、慣行農業をしてきた大規模農家が御社の取り組みに賛同し、有機農業に切り替えての提携を望むとしたら、農業の変革速度はさらに早まると推察されます。今後、そのような方向の選択肢はあるのでしょうか?
渡邊さん:
まさに、そういうことを考えているチームが私たち二人が所属する「坂ノ途中の研究室」です。「坂ノ途中研究室」は、2022年に発足しました。現在は、弊社の事業がどのように社会に貢献しているかの発信、事業改善、新規事業開発、の三本柱で取り組んでいます。
新規事業開発では、もっと流通量を増やす方向性で、これまで取引が少なかった大きな生産者さんとも組み、野菜セットとは別の流通のかたちを作ることを模索中です。野菜セット事業においても、小規模農家さんだけですと、端境期などに仕入れが足りなくなることもあります。少ない割合であれ、大規模農家さんの存在は貴重です。近い将来、さらに大規模農家さんと提携することはありえます。
-そのほかの展望をお聞かせください。
横浜さん:
野菜セットの顧客は増加していますが、それでもまだ、生産者さんの野菜を買い切れてはいません。問題点を分析し、買い切るための事業改善を計画中です。
例えば、弊社では「ダッシュボード」と称するデータの集積を、取引農家さんに開示して役立ててもらっています。毎週集まってくる出荷可能量の情報などからは、現時点でどの野菜がどの農家さんで栽培されているか、などが分かります。それによって、作付け期をずらしたり、あるいは作物を変えたりなどの経営判断が可能となります。現在は弊社との提携農家さんとの間だけでの情報開示のみですが、将来的にはそのダッシュボードを大きく広げていく可能性もあります。
また、基礎的な調査という意味でも、取引先以外の全国の有機農業生産者さんの状況を把握するためにアンケートを実施しています。「坂ノ途中」だけが成長するというのではなく、有機農業を広げていくために、これまでやっていたことプラスアルファを考えています。

そして今後は、自治体さんや企業さんとも連携し、環境負荷の小さい農業の広がりを加速させていきたいと考えています。また、ダッシュボードのようなデータを介すことで、生産者さんが孤軍奮闘するのではなく、皆で協力しながら成長していくことができればと思っています。
-有機農業を持続させることの重要性がよく分かりました。今日はありがとうございました。
株式会社坂ノ途中Online Shop公式サイト:https://www.on-the-slope.com/
この記事を書いた人
壱岐 梢 ライター
ライティング、詩作、翻訳…様々なかたちで言葉と共に仕事をしています。 この世界に入ったきっかけは、宮沢賢治との出会いでした。彼は究極のSDGs 実践者。大好きな言葉の仕事によって、今SDGsに取り組む皆様をご紹介 できることは、大きな喜びです。
ライティング、詩作、翻訳…様々なかたちで言葉と共に仕事をしています。 この世界に入ったきっかけは、宮沢賢治との出会いでした。彼は究極のSDGs 実践者。大好きな言葉の仕事によって、今SDGsに取り組む皆様をご紹介 できることは、大きな喜びです。