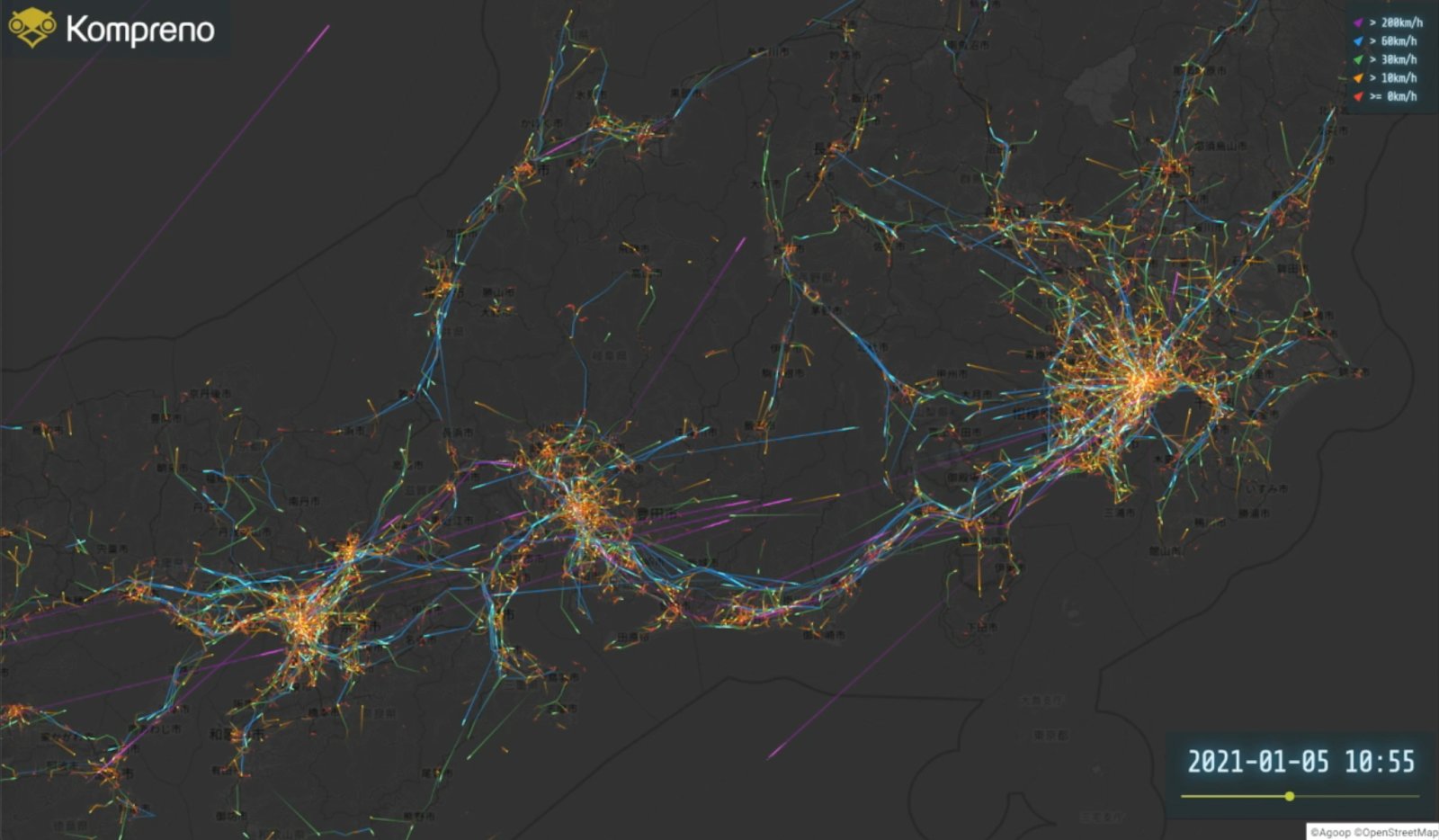NPO法人ユアフィールドつくば 代表理事 伊藤文弥さん インタビュー
伊藤文弥
目次
introduction
障がい者の施設に行ってみたことはありますか?障がいのある人が身近にいない場合は、彼らとどのように接したらいいか、もしかしたらためらうかもしれません。しかし、NPO法人ユアフィールドつくばのような施設が近くにあれば、そんな心配も無くなりそうです。「障がいに限らず生きる上での弱さは誰でも持っている」と話すのは代表理事の伊藤文弥さん。障がいのある方と育んでこられた農業を中心に、その経緯と今後の取り組みについて伺いました。
設立当時の目標は、障がいのある人のために働く場所をつくること。それが次第に変化して・・・
—まずはNPO法人ユアフィールドつくばの概要について教えてください。
伊藤さん:
NPO法人ユアフィールドつくばは、茨城県つくば市で障がい福祉を主に専門に活動している団体です。
具体的には、就労継続支援B型事業所の「ごきげんファーム」やグループホーム「ひだまりベース」、発達障がいのある子ども達のための放課後等デイサービス、訪問看護ステーション、生活介護事業所など、幅広く事業を展開をしています。障がいのある人もない人も、地域のなかで役割を持ち、お互いに助け合いながら成長できる、そんな社会の実現を目指して、様々な分野のプロが事業を運営しています。
特徴的なのは、障がいのある人が農業分野で働く「農福連携」が盛んなことです。障がいのある人たちが100名以上働くごきげんファームでは、年間30品目、100品種以上もの野菜や米などを育てています。
–団体を立ち上げた背景を教えてください。
私が大学4年だった2011年、障がいのある人と働く農場、ごきげんファームを立ち上げたことが始まりです。大学2年の時にインターンシップをさせていただいたご縁で、現つくば市長と一緒に始動しました。
当時は「障がいのある人たちの働く場所が足りていない」、あるいは「農家の担い手がいない」という問題意識がありましたね。ですから障がいのある人たちのための働く場所をつくることを目的にしていました。
しかし、事業を進める中で色々な課題に気づき、目指す姿も変化してきました。ごきげんファームの利用者と接している中で、働くことの他にも彼らが満たされていないことがたくさんあるということに気がついたからです。
例えば、住む場所が不安定だったり、お金があっても自分で上手く使えなかったり、悩みがあっても相談する人がいなかったりなど、働く機会以外のところでも彼らはたくさんの課題を抱えていました。このままのやり方では彼らは幸せにはなれないなと思いました。
そこで「働く機会の提供」の次に目指したのが、「障がいのある人たちが地域でごきげんに暮らすこと」です。ごきげんに働くことから、ごきげんに暮らすことへと変わったんです。これを実現するために、障がいのある人や地域の方たちと信頼関係を築き、誰もが安心できる「共生の場を創る」担い手になることを理念としてやってきました。
そして、この理念が最近さらに変化しています。私たちの事業を通して、安心して働き暮らすことができるようになった障がいのある人たち。そんな彼らの農業によって、今度は地域を良くしていくこと、そして障がいの有無に関わらず、いろんな人たちの居場所になっていきたいと思うようになりました。そのような変化もあり、会社の名前を去年「つくばアグリチャレンジ」から、「ユアフィールドつくば」に変えました。

スムーズな作業のカギは、利用者の「できること」を引き出す方法
—利用者にはどのような障がいの方がおられますか?
伊藤さん:
知的障害、自閉症、ダウン症、発達障害、統合失調症、うつ病、身体障がいなど様々な障がいのある方がおられます。特別支援学校を卒業したばかりの18歳もいれば、65歳を超えている方など、年齢層も多様です。
かつての障がい者福祉制度では、措置制度として自治体が障がい者の住む場所や働く場所を決めていました。そのため、障がいの種類によって入所する施設も異なっていました。しかし、私たちが事業を始めた2011年は、新しい制度に切り替わって数年が経ったタイミングでしたので、障がいのある人自身が利用する施設やサービスを決定できるようになっていました。その結果、様々な方々に利用していただいています。
—利用者の障がいや年齢層が多様ということですが、スタッフとしてサポートをする上でどのような工夫をされていますか?
伊藤さん:
確かに障がい特性に対する理解は必要です。実際に、自閉症の方が働きやすい職場は必ずしも発達障がいの方にとっても働きやすい場所ではありません。ただ、私たちは個別対応というよりは、だれにとっても働きやすい方法を探すことを大切にしてきました。
例えば農場でのじゃがいもの植え付けです。本来、じゃがいもは上の方に芽が集まって出ていますが、家庭菜園の本ではそれを均等になるよう刃を当てて切って植えることが良いとされています。でも、そのやり方では知的障がいのある方は「どこをどう切っていいか分からない」と混乱するんです。「それなら芽のことは気にしなくていいのでとにかく四等分してください」と伝えると、作業が10倍くらい早くなりました。
また土への植え付け時も、じゃがいもの向きは気にしないでいいと伝えるととてもスムーズに作業してくださるんです。彼らは判断するのは苦手でも、作業自体は決して遅くありません。こうした点を意識して作業方法を決めると、どの職員が担当しても上手くいきます。

施設のイベントで来客500人!地域に開かれた施設の秘訣
–ごきげんファームでの取り組みから感じる、農福連携のメリットや問題点について教えてください。
伊藤さん:
農福連携の一番の強みは、地域との関係を築きやすいことです。先に述べたとおり、働く場所の確保と農業の担い手不足の両方を担保することを目的として、私たちは農業を始めました。でも今は別の見方をしています。障がいのある人とない人をつなげる上で、農業はとても有効なんです。
そもそも野菜ほど日常的にすべての人が必要とし、関心を持つものって無いと思います。例えばうちで芋掘り体験を開催すると、かなり幅広い世代の人が訪れてくれます。もともと人間は農作業を喜ぶようにつくられているんじゃないかとさえ思います。野菜を育てること、体を動かすこと、食べられるものが手に入ること。農業は人間が本質的に幸せを感じやすい行為なのかなと。だから農業をきっかけに、地域の人を施設に招きやすいんです。
ただ、収益を上げやすくはないですね。障がいがある人が働きやすい分野でもありません。でもそれ以外のメリットが大きい。それが今でも農福連携を続けている理由です。
–そんなユアフィールドつくばならではの魅力や強みはどのようなものでしょうか。
伊藤さん:
やはり地域に開かれた施設である、ということだと思います。
とにかくたくさんの人に足を運んでもらえる施設にしたくて、先ほどの野菜収穫以外にもイベントを開催しています。養鶏場で卵を採るイベント、障がい者年金についての勉強会、ハーブを使った蚊取り線香を作るワークショップなど、内容は様々です。
また、私たちは毎年夏祭りを開催しています。嬉しいことに今年は地域からの参加者が500人も来てくれたんです。一般的に福祉施設がお祭りをしてもこれほど来客はないと思います。
私は地域と障がい者の関係性はとても大切だと思っていて、地域に溶け込んだ形での支援をするようにしてきました。利用者や保護者を含めて、この考え方を理解し応援してくれる人は多いなと感じています。

社会の分断の解消を目指して、地域全体のために事業をする。
–ここからは話を少し変えて、障がい福祉への理解を広める上で、どのような課題があるのかを伺います。
伊藤さん:
障がいが特別なことだと認識されていることが課題だと思います。かつては山奥に限定されていた障がい者支援施設が、今は街中でも見られるようになりました。それでも施設の中に入ったことがある人ってとても少ないんですよね。
つまり、まだまだ障がいのある人とない人が社会では分断されていて、別の世界を生きているような印象があります。そのため障がいのない人は、地域に障がいのある人がいるのを知らないし、一緒に働くこともありません。
他にも、小さい頃からの教育の在り方にも問題を感じています。今、特別支援教育が必要な子どもの数がものすごい勢いで増えています。私はスクールソーシャルワーカーの経験があるのですが、そのような子どもは小学校から別々に教育を受けていて、国が進めるインクルーシブ教育※と現状は異なると感じています。
※障がいのある人とない人が共に学ぶ仕組み
でもよく考えてみれば、人生の中で自分が障がいの当事者になり得ることって結構多いんですよ。私もうつ病を経験したことがありますが、自分や家族、親戚が人生の中で何かしらの障がいを負う可能性って実はとても高いと思います。むしろ、生きていく上での弱さなんて誰でも抱えていますよね。でもみんな見えないふりをしている。本当は、障がいって誰にとっても身近な問題だと気付いて欲しいんです。だからこのような事業をしています。
振り返ってみると、私も「障がいのある人のために」と思って事業をしていた頃は、自己犠牲を払っているようで辛かったんです。でも今は、私の事業が地域全体にとって必要なことだと思っています。私にとっても私の子どもや妻にとってもこういう事業がつくばにあるということが、大事だと思えるようになりました。そう思えるまで7年位かかりましたね。

–最後に、今後どのような取り組みをしていきたいですか?
伊藤さん:
これからは障がいの有無に関わらず、地域の中の立場が弱い人や困っている人の力になりたいと思います。
その一環で、農場で子どもたちが体験できるイベントや、受刑者が出所前に私たちの農場で行う仕事体験など、新しい取り組みを進めています。でも、福祉ができることはとても多様なので、実践できている分野はまだほんのわずかだと思っています。障がいの有無にかかわらず困っている人たちの力になるために、私たちの事業が世の中の問題とどのように連携することができるかを常に考え、これからも地域に向けて仕事をしていきたいと思います。
–利用者のためだけではなく、自分や地域のためにもこの事業が必要だと、自負を持って取り組まれている伊藤さんのお話しに感銘を受けました。ありがとうございました。
関連リンク
NPO法人ユアフィールドつくば:https://yf-tsukuba.com/
この記事を書いた人
あきもと なおみ ライター
元公務員。苔の魅力のとりこになり、農業(苔培養)で起業。プライベートでは読むことと書くことに幸せを感じる3児の母。ライターの仕事を通した出会いに敬意を示して、大好きな文章を紡ぎます。
元公務員。苔の魅力のとりこになり、農業(苔培養)で起業。プライベートでは読むことと書くことに幸せを感じる3児の母。ライターの仕事を通した出会いに敬意を示して、大好きな文章を紡ぎます。