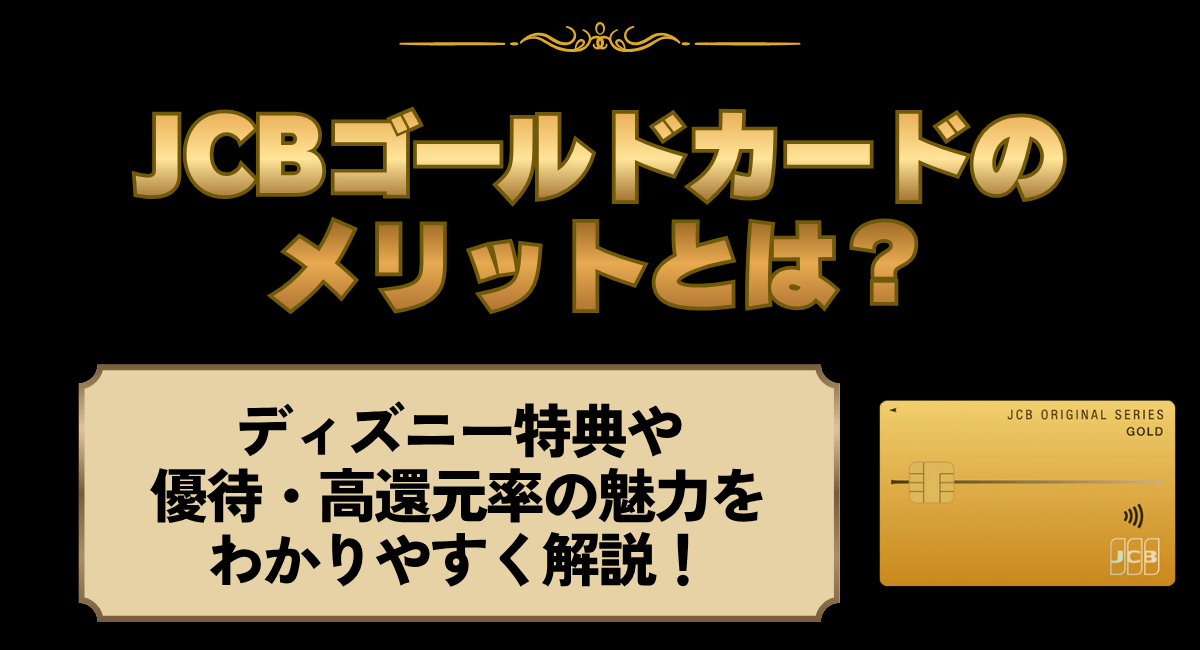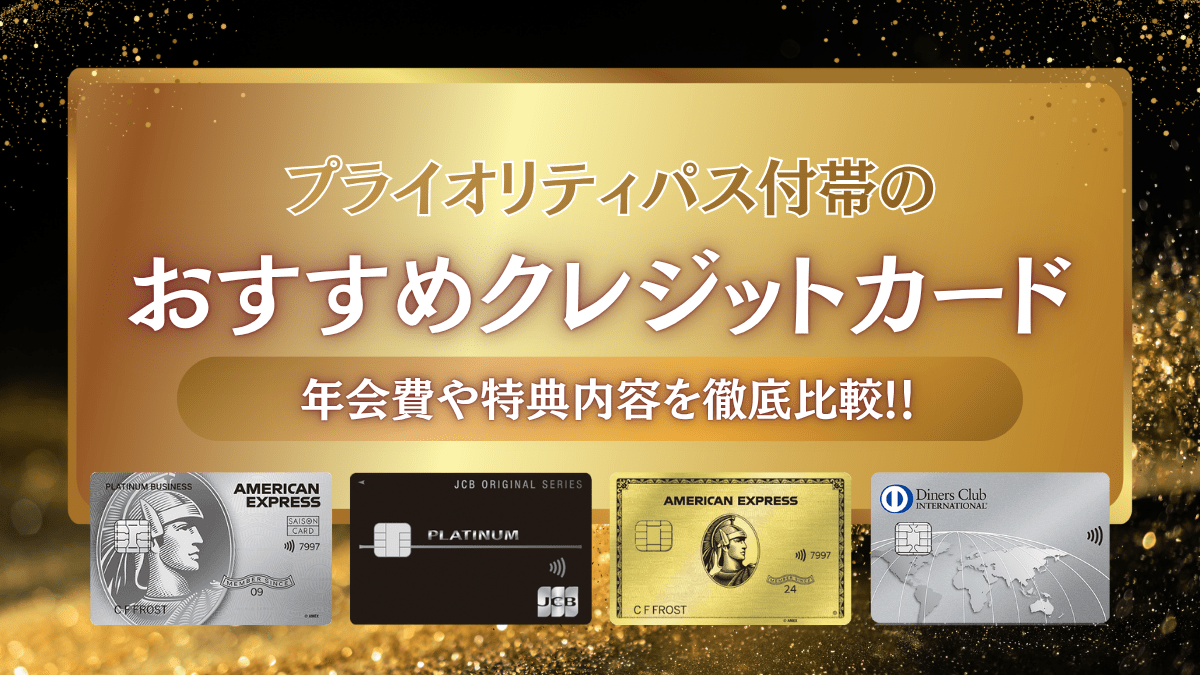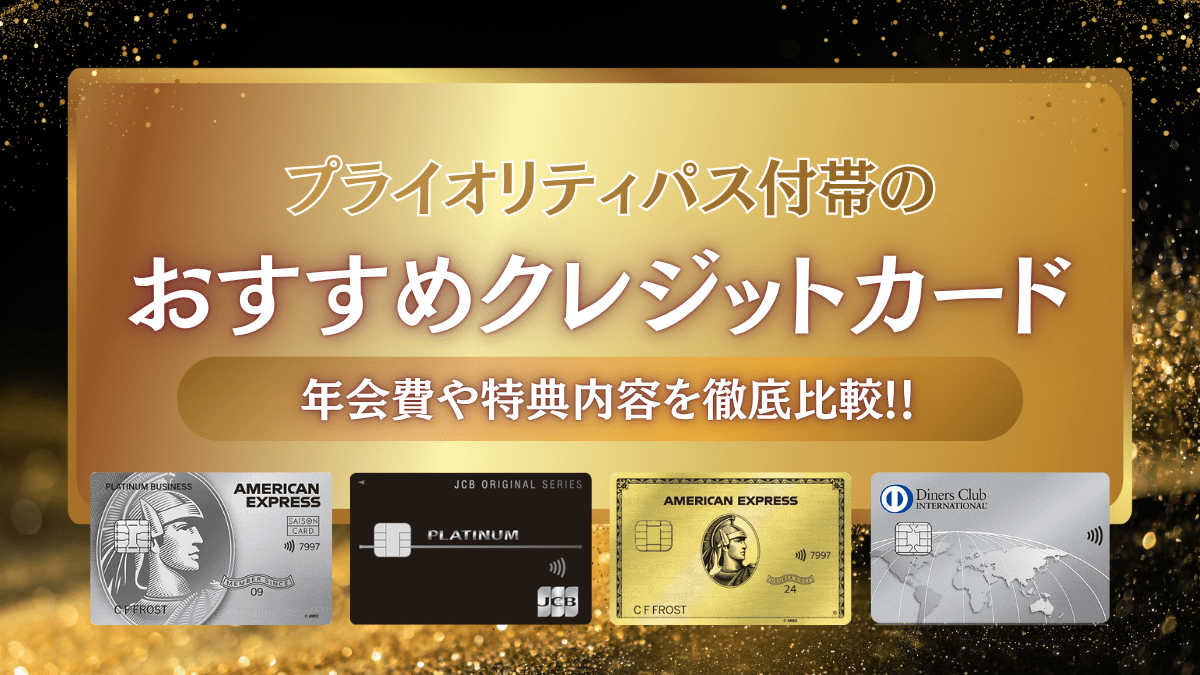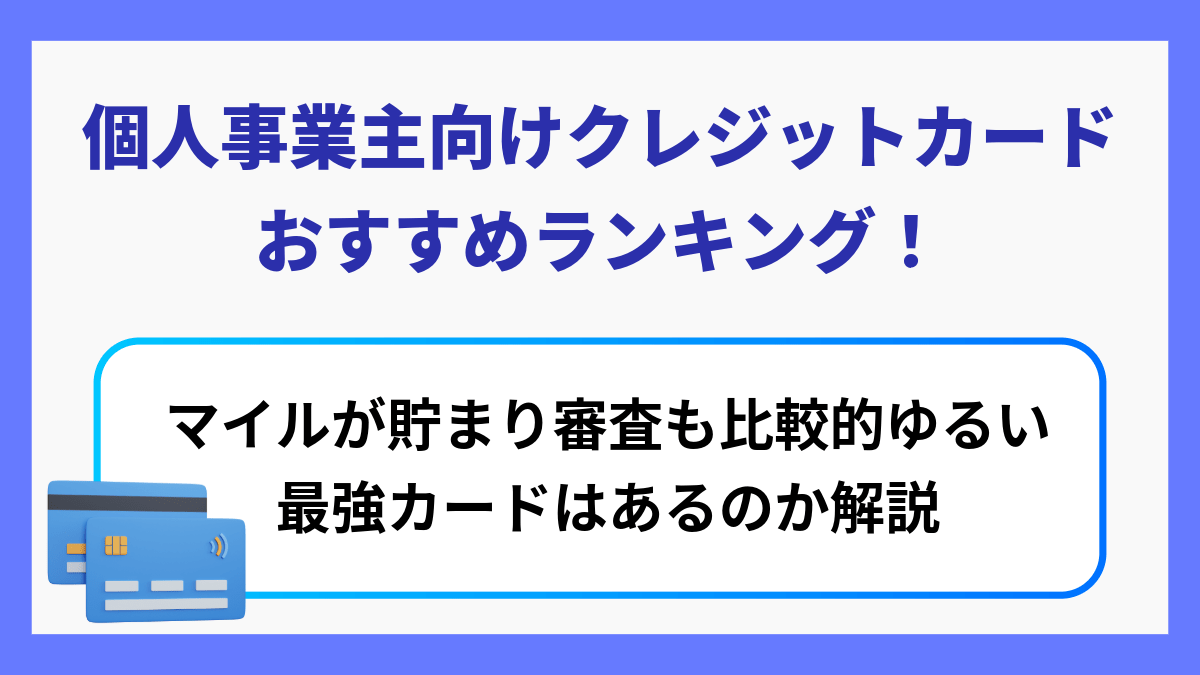明治時代、日本は欧米列強の植民地にならないよう必死に近代化を進めていました。外国の侵略を防ぐため、日本を強くするというのは幕末からの悲願だったといってもよいでしょう。その中心となったのが「富国強兵」と「殖産興業」という二つの政策です。
「富国強兵」は、国を豊かにして軍事力を高める方針で、徴兵制度や西洋式軍隊の導入が行われました。他方「殖産興業」は様々な産業を発展させて経済基盤を強くする試みであり、工場建設や鉄道整備などが積極的に推進されました。
一見、似ているようにも感じられるこの二つの政策には、目的や進め方に大きな違いがあります。しかし実は、互いに補完し合う関係にもありました。
この記事では両者の特徴や相違点、そして現代社会への影響まで、歴史の教科書だけでは分かりにくい側面を含めて紹介します。
目次
富国強兵とは
富国強兵とは、国を豊かにして軍事力を強化し、国力を強めることです*1)。日本では、幕末から明治時代にかけて強まった考え方で、明治政府の国家目標といってもよいでしょう。
明治時代の日本は、生糸や茶、雑貨などの農産物や手工業品を海外に売り、代わりに工業製品を外国から買い入れていました。しかし、このような貿易だけでは、国を守るための軍隊を強化するお金を十分に得ることができませんでした。
そのため、「国を豊かにして軍を強くする」という意味の「富国強兵」という考え方が広まり、日本は経済力と軍事力の両方を同時に発展させる必要があったのです。
富国強兵が必要な理由(歴史的背景)
なぜ、明治政府は富国強兵を目指したのでしょうか。主な目的は2つあります。
- 欧米列強と日本の国力差を縮めたい
- 不平等条約を改正したい
幕末から明治にかけて、欧米列強の軍事力は圧倒的でした。1840年のアヘン戦争や1856年のアロー戦争で、イギリスやフランスは、清国に圧勝しました。この国力差を埋めるには、並々ならぬ努力が必要だったのです。
幕末に結んだ不平等条約の改正も、富国強兵を行った理由の一つです。日米修好通商条約で、日本は治外法権を認め、関税自主権を失っていました。
日本が国際社会で生き残るためには、欧米の強い国々と対等に話し合いができる力が必要でした。19世紀の世界では、他国と交渉するときに軍事的な強さがないと相手にされない時代でした。
そのため、日本政府は「国を豊かにして軍を強くする」という富国強兵の政策を進め、軍事力を高めようとしたのです。この軍事力の強化は、単に戦争のためではなく、国際的な交渉の場で日本の意見を聞いてもらうための手段でもありました。
富国強兵のメリット

明治政府が行った富国強兵により、日本は外国と対等に交渉するための軍事力を手にしました。ここでは、軍事力の強化について解説します。
外国に対抗する軍事力が持てる
政府は、経済力を強めると同時に軍事力の強化を図りました。主な施策は以下の通りです。
- 徴兵令の布告
- 兵器の近代化
- 海軍の拡張
1873年、明治政府は満20歳に達した男子全員に兵役の義務を定めます。「徴兵令」が制定されたことで、日本陸軍は規模を急拡大させることができました。兵器の近代化も行われました。その一つが「村田銃」の採用です。1880年に制式化された国産小銃です。1889年に連発銃に改良され、日清戦争で活躍しました。*4)
陸軍の拡大に加えて、海軍も同時に強化されていきました。その代表は戦艦「三笠」です。三笠は、日露戦争中の日本海海戦において、連合艦隊のトップである東郷平八郎提督が指揮を執った象徴的な艦船です。
三笠はイギリスのヴィッカース社で建造されたもので、日本政府はこの三笠を含む合計6隻の戦艦を購入して、日本海軍に配備したのです。
富国強兵のデメリット・問題点

富国強兵により、日本は軍事力を一気に向上させることができました。しかし、軍事費最優先で国の政治が行われたため、庶民は大きな負担に耐えなければなりませんでした。
庶民の負担が増えた
庶民の負担は大きく分けて以下の2つです。
- 税負担
- 徴兵
政府は軍事力強化の資金を確保するため、地租改正をおこないました。地租改正は、土地と税金の仕組みを根本から変える改革でした。
この制度によって、農民たちは正式に土地の所有者として認められました。しかし、その見返りとして土地の価値の3パーセントを現金で税金として支払う義務が生じました。
3パーセントという数字は少なく思えるかもしれませんが、実際には江戸時代に農民が負担していた税と同程度もしくはそれ以上の重税でした。
このような重税に対して、多くの農民が不満を抱き、日本の様々な地域で地租改正に反対する地租改正反対一揆が全国で起こりました。その結果、地租は3%から2.5%に引き下げられました。
1873年に政府が一般市民に対して兵役義務を課した徴兵令は、人々から激しい抵抗を受けました。反感を買ったのは、徴兵告諭に書かれていた「西人之ヲ称シテ血税ト云フ 其生血ヲ以テ国ニ報スルノ謂ナリ」(西洋人がこれを血税と呼ぶのは、自分の血をもって国に恩返しするという意味だからだ)という言葉でした。
この表現が原因で、徴兵令に反対する農民の抗議行動は「血税一揆」と呼ばれるようになりました。血税一揆の規模は非常に大きく、岡山県では26,000人もの人々が参加し、香川県でも20,000人が立ち上がりました。
このような大規模な抗議活動は日本中の様々な地域で次々と発生し、新政府の政策に対する民衆の不満の大きさを示していました。
殖産興業とは

殖産興業は、明治時代に新政府が取り組んだ国の産業を近代化する政策のことです。「富国強兵」という目標を達成するためには、日本は農業以外にも、新しい工業分野も発展させる必要がありました。
そこで政府は、国内の様々な工業を育て、発展させるための様々な取り組みを行いました。これらの工業を成長させるための政策全体を「殖産興業」と呼んでいます。簡単に言えば、国を豊かで強くするために、新しい産業を育てる取り組みだったのです。
近代産業の育成
明治政府が行った殖産興業政策は、幅広い分野に及んでいます。殖産興業政策を分野別にまとめてみましょう。
| 分野 | 具体的な内容 | 効果・目的 |
| 官営工場の設立 | 富岡製糸場新町紡績所横須賀製鉄所佐渡金山・生野銀山 | 西洋技術の導入模範工場の設立軍需産業の強化 |
| 交通・通信のインフラ整備 | 鉄道建設電信網の整備郵便制度 | 国内物流や移動の効率化情報伝達の迅速化 |
| 技術教育 | 工部省工学寮札幌農学校 | 技術者の育成 |
殖産興業のメリット

明治政府が中心となって実行した殖産興業ですが、どのようなメリットがあったのでしょうか。ここでは、殖産興業の2つのメリットを解説します。
経済成長が加速する:生糸・綿糸産業
明治政府が進めた殖産興業政策は、日本の経済成長を大きく加速させました。特に繊維関連産業である製糸業と紡績業の発展は目覚ましいものがありました。
製糸業(生糸産業)
製糸業(生糸を生産)では、1872年に設立された富岡製糸場が重要な役割を果たしました。この施設は国が設けた模範工場で、フランスから最新技術や機械を導入しました。それまでの手作業中心の生産から近代的な機械化生産へと移行することで、生糸の品質と生産量が向上したのです。高品質な日本の生糸は海外市場で高い評価を受け、重要な外貨獲得源となりました。*6)
紡績業(綿糸産業)
一方、紡績業(綿糸を生産)では、1878年に愛知に国営の紡績所が設立され、イギリスから輸入した機械による近代的な綿糸製造が始まりました。1882年には民間企業の大阪紡績会社が誕生し、その後全国に多くの紡績会社が広がりました。大阪は紡績工場が集中して「東洋のマンチェスター」と呼ばれるほど発展しました。*7)
これらの産業発展により、日本は原材料を輸入して加工品を輸出する貿易構造を確立しました。繊維製品は日本の主要輸出品となり、得られた利益は他の産業への投資に回されて経済全体の成長につながりました。また、工場労働者の増加や関連産業の発達により、社会構造も大きく変化していきました。
交通・通信インフラの整備が進む:鉄道・電信・郵便制度
明治政府が推進した殖産興業政策の大きな成果として、交通網と通信設備の充実が挙げられます。この基盤整備は日本の近代化に不可欠な役割を果たしました。
鉄道
1872年に新橋と横浜を結ぶ鉄道が開通しました。その後、線路は全国へと拡大し、人や物資の移動が格段に速くなりました。それまでは徒歩や馬、船による輸送が主流でしたが、蒸気機関車の登場により輸送力が大幅に向上しました。*7)
通信
通信面では、電信システムの導入が重要な進歩でした。1869年に一般用の電信がスタートしました。電信は、情報伝達の時間を劇的に短縮しました。従来の伝言方法と比べ、即時に連絡が可能となったことで、ビジネスや行政の効率が飛躍的に高まりました。*8)
郵便
郵便制度も整備され、1871年に近代的な郵便サービスが始まりました。全国どこでも均一料金で手紙やはがきが送れるようになり、国民の文書によるコミュニケーションが促進されました。
これらの基盤整備によって、産業の発展が加速し、国内市場の統一が進みました。さらに教育や文化の普及にも貢献し、日本社会全体の近代化を支える重要な土台となりました。
殖産興業のデメリット・問題点

殖産興業は、日本の経済を大きく発展させましたが、すべてがうまくいったわけではありません。
- 官営事業の失敗
- 貧富の差の拡大
ここでは、上記の2つのデメリット・問題点について解説します。
官営事業の失敗
明治政府は殖産興業のモデルケースとして、多数の官営工場を設立しました。官営工場では、”お雇い外国人”を採用し、技術の育成を図りました。この際、政府は多額の資金を投じて工場を設立しましたが、その大半は損失となりました。*11)
そのため、政府は1880年に「工場払下概則」を制定し、軍需産業など一部の部門を除いて民間に払い下げられました。
貧富の差の拡大
明治時代の殖産興業政策は、社会に大きな経済格差をもたらしましたが、この政策によって利益を得たのは主に資本家層でした。彼らは政府や銀行からの支援を受けて新しい工場を次々と建設し、得られた利益を再投資して事業を拡大していきました。また、政府が民間に売却した官営工場を買い取ることで、さらに事業規模を大きくすることができました。
しかし、この経済発展の陰では、多くの労働者が厳しい環境で働いていました。特に繊維工場で働く女性たちは、非常に長い労働時間にもかかわらず、低賃金で働かされていました。
このような労働環境の厳しさは、後の1925年に出版された『女工哀史』という本で詳しく記録されています。この本には当時の女性労働者が経験した苦難が生々しく描かれており、明治の産業化がもたらした社会問題の一面を示しています。*10)
富国強兵と殖産興業の違いをまとめると

| 項目 | 富国強兵 | 殖産興業 |
| 目的 | 軍事力の強化 | 経済成長 |
| 重点分野 | 軍備:陸海軍の整備 | 工業・農業の成長輸出産業の振興 |
| 具体的な施策 | 徴兵令軍艦購入 | 官営工場の設立鉄道建設国立銀行の設立 |
富国強兵と殖産興業は明治時代の重要な政策理念ですが、その目的には違いがありました。富国強兵は「国を豊かにし軍を強くする」という考えで、経済力を高める目的も最終的には軍事力強化のためでした。これに対して殖産興業は「産業を興し発展させる」という経済そのものの成長を中心に据えた政策理念でした。
つまり、富国強兵は軍事的側面に重点を置き、殖産興業は国の産業・経済発展に主眼があったのです。両者は互いに関連しながらも、重視する側面が異なる政策理念だったといえます。
富国強兵・殖産興業とSDGs

富国強兵・殖産興業とSDGsには、どのような関連があるのでしょうか。ここでは、SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」との関わりについて解説します。
SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」との関わり
明治時代の日本において、富国強兵・殖産興業政策は国家の経済力と軍事力を向上させる取り組みでした。この方針により工業化が進み、国の体制は急速に発展しました。
しかしながら、この進展には光と影がありました。社会の中で貧富の格差が拡大し、農民は地租改正により負担が増加しました。工場で働く女性たちは劣悪な環境で低い報酬を受け取るのみでした。一方で、財閥や土地所有者には富が集中していきました。
この状況に対し、民衆は反発し、様々な形で抵抗運動を展開しました。経済的な差異は社会不安を引き起こす要因となったのです。現代のSDGs目標10が目指すものは、過去の教訓を活かし、公平な社会の構築を促進することにあります。歴史が示すように、持続可能な発展には経済的公正さが不可欠なのです。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ
今回は、富国強兵と殖産興業について解説しました。明治時代、日本は欧米列強に追いつくために、この二つの政策を強力に推進しました。富国強兵は軍事力の強化を目指し、徴兵制や軍備の近代化を進めました。
一方で殖産興業は経済発展を目標に、工場建設や鉄道などのインフラ整備に力を注ぎました。富国強兵によって日本は国際的な地位を高めましたが、国民への負担も大きくなりました。殖産興業は経済成長を促しましたが、貧富の格差拡大という社会問題も引き起こしました。
両政策は日本の近代化に大きく貢献しましたが、その光と影は、現代社会における持続可能な発展を考える上でも重要な示唆を与えています。
参考
*1)デジタル大辞泉「富国強兵」
*2)山川 日本史小辞典 改定新版「治外法権」
*3)山川 日本史小辞典 改定新版「関税自主権」
*4)日本大百科全書(ニッポニカ)「村田銃」
*5)デジタル大辞泉「富岡製糸場」
*6)双日歴史館「日本の紡績業の発達~開国以降」
*7)改定新版 世界大百科事典「鉄道」
*8)百科事典マイペディア「電信」
*9)精選版 日本国語大辞典「郵便制度」
*10)デジタル大辞泉「女工哀史」
*11)日本大百科全書(ニッポニカ)「官営工業」
この記事を書いた人
馬場正裕 ライター
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。