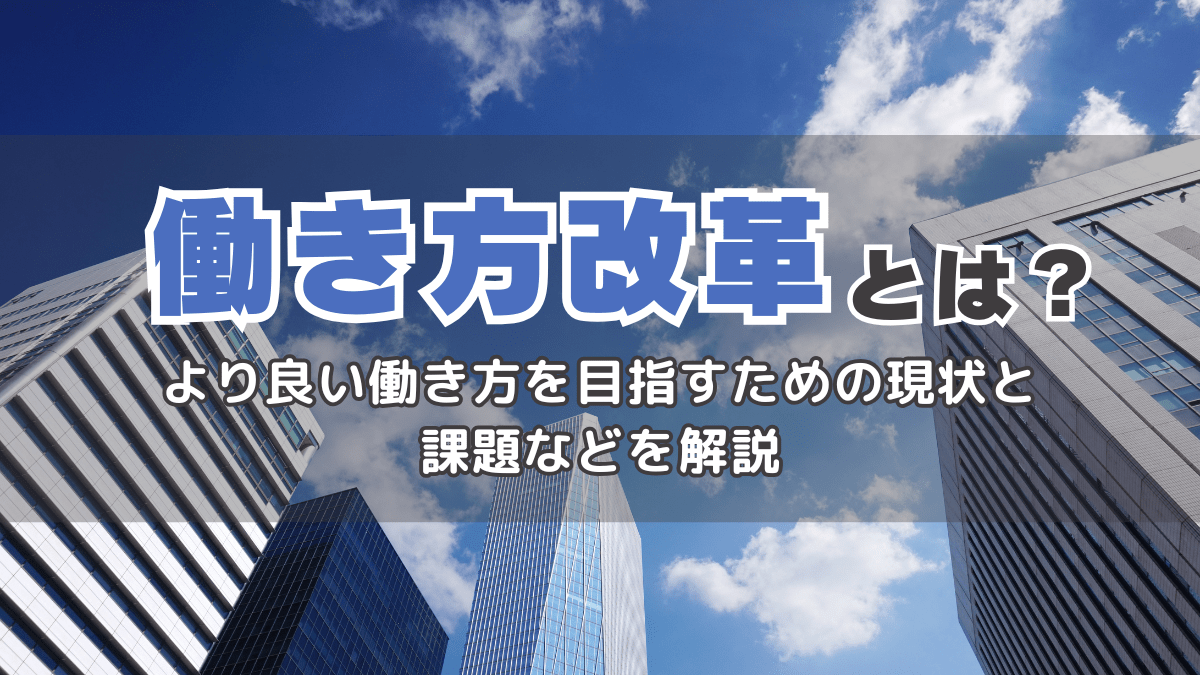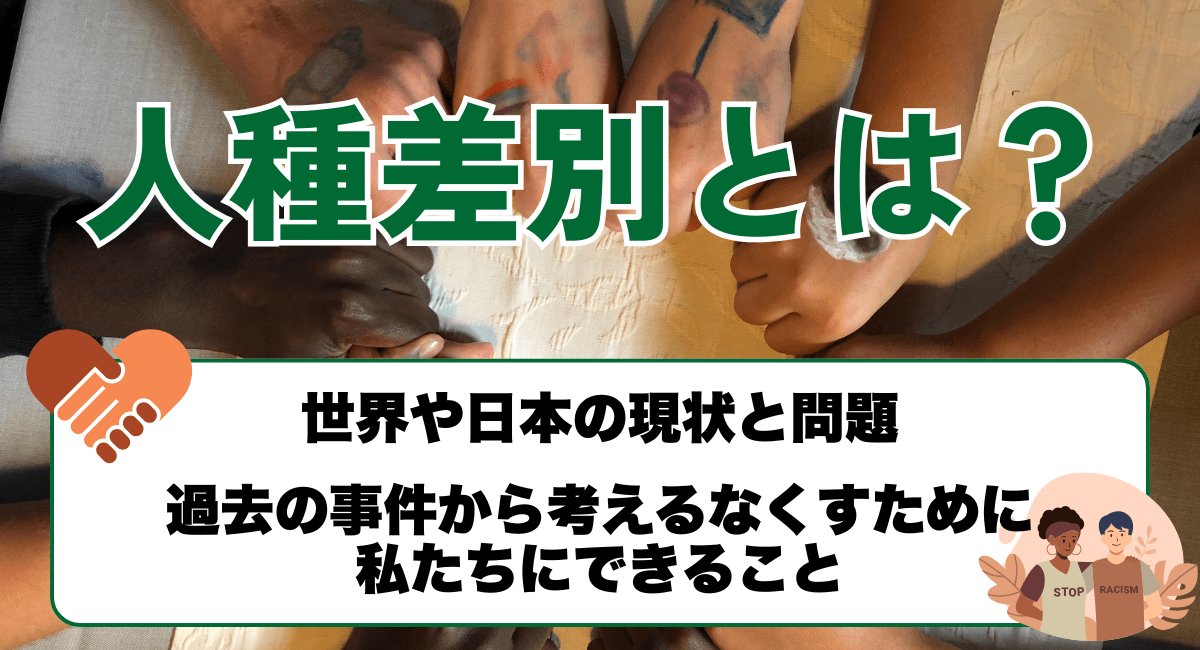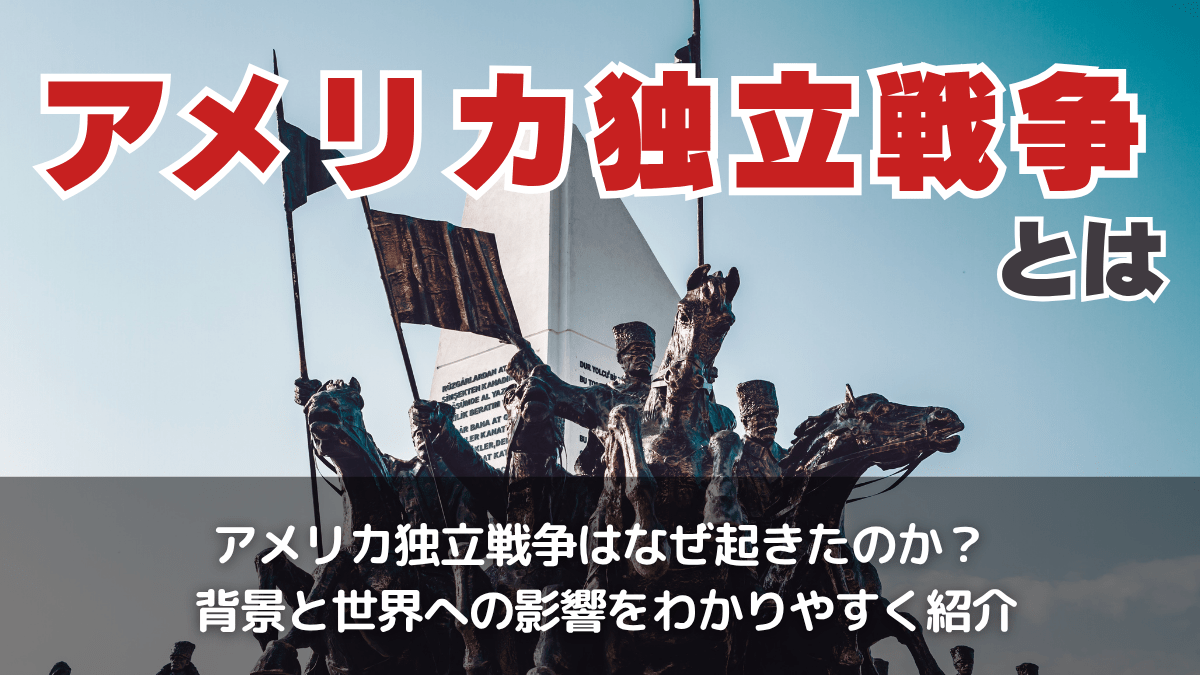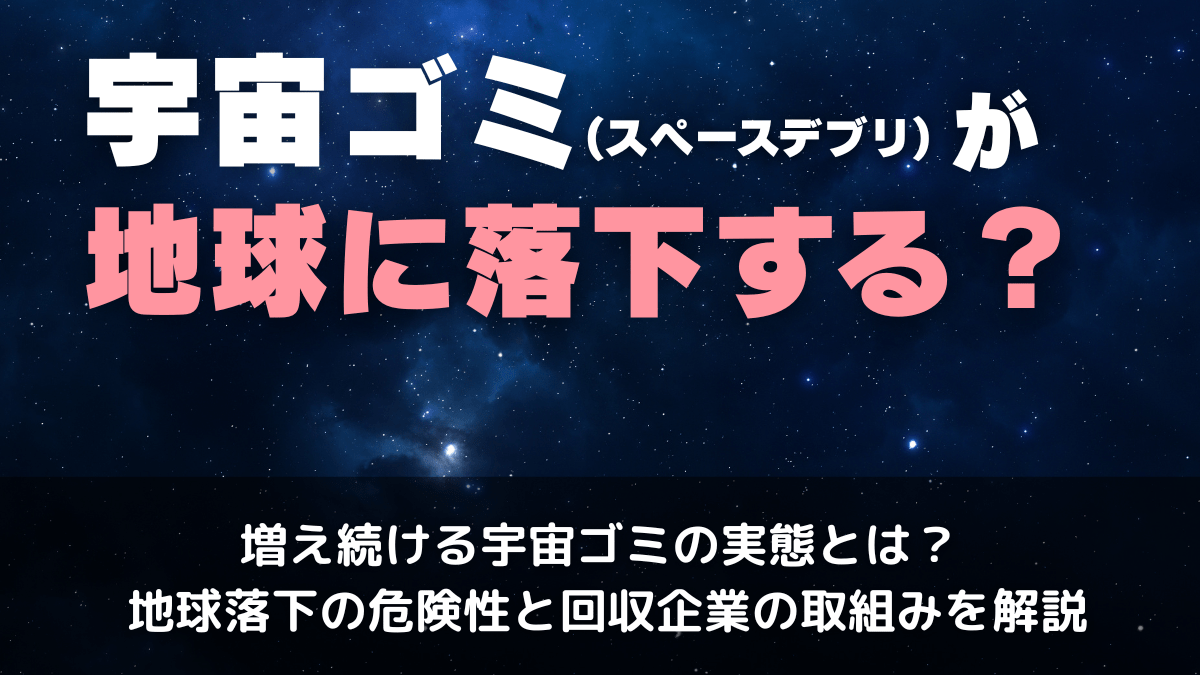最近「インクルーシブ」という言葉をよく耳にします。インクルーシブデザイン、インクルーシブホテル、インクルーシブ教育など、使われている分野はさまざまです。本記事で取り上げる「インクルーシブ公園」もそのうちの1つであり、メディアで取り上げられることも多くなりました。
この記事では、インクルーシブ公園とは何か、なぜ必要なのか、遊具の具体例、注目されている背景、問題点・課題、東京・神奈川・埼玉のインクルーシブ公園の事例、SDGsとの関係を解説します。
目次
インクルーシブ公園とは
インクルーシブには「すべてを包み込む」という意味があり、インクルーシブ公園とは、障がいの有無や年齢、性別、国籍などに関係なく、みんなが楽しく遊べる公園のことです。
なぜ必要?
私たちは地域の人をはじめ、さまざまな人と支え合いながら生活をしています。この中には、公園を利用しにくいと感じている人もいます。例えば、車椅子を使用している人、子どもが周囲に迷惑をかけないか心配する親、体の不自由な高齢者などです。
公園は、憩いや遊びの場として一般に開かれています。多様な人が互いに交流し、地域の人との関係を築いていくことは重要です。その中でインクルーシブ公園は、地域の人との関わりを生み出す役割を担っており、一人でも多くの人が利用できる公園の整備が求められています。
インクルーシブ遊具の具体例
インクルーシブ公園には、インクルーシブ遊具が設置されています。インクルーシブ遊具とは、障がいのあるなしに関係なく使える遊具のことです。5つの具体例を見ていきましょう。
ブランコ
【ハンモック型ブランコ[愛知県安城市:油ヶ淵水辺公園 ぶらリン広場]】
一般的なブランコは、腰掛ける座板と、これを吊り下げるチェーンで作られています。一方、インクルーシブ遊具のブランコは、体を固定できる安全バーが付いているタイプや、寝そべって利用できるハンモック型などがあります。これらは、体を支える力が弱くても乗ることができます。
3歳未満の子どもの遊具
【3歳未満の子どもが遊べる遊具[岐阜県岐阜市:岐阜ファミリーパーク]】
インクルーシブ公園は、年齢にかかわらず遊べる公園であるため、3歳未満の子どもも例外ではありません。寝返り、腹ばいのできる赤ちゃんから、座る、立つ、歩く、走るなどができるようになる3歳ごろまでの遊具もあります。例えば、つかまり立ちや、つたい歩きをサポートする手すりに似た遊具もその1つです。
車椅子を使用したまま遊べる遊具
【車椅子のまま乗れるスロープ付き遊具[神奈川県藤沢市:秋葉台公園]】
車椅子を使用している子どもが使用できる遊具も、インクルーシブ遊具の1つです。例えば、ばねの弾みで上下左右に動くスプリング遊具やシーソーは、車椅子に乗ったまま利用できるように工夫されています。車椅子を使用しない子どもも一緒に乗って遊ぶことができます。
音を鳴らす遊具
【たたくと音が鳴るメロディーパネル[東京都立府中の森公園]】
手でたたく、コマを動かす、バチでたたくなどにより音を鳴らす遊具もあります。手を動かすだけで、音を鳴らせる楽しみを味わうことができます。また、触れる、聴くなどの感覚を刺激できるほか、遊具が複数あれば、他の人たちと一緒に演奏を楽しめます。
健康遊具
【大人向け健康遊具[佐賀県神埼市:日の隈公園キッズパーク]】
大人の健康づくりを目的とした器具が健康遊具です。背伸ばしベンチ、ぶら下がり懸垂、ボートこぎ、腕伸ばしなど、軽いストレッチや運動ができます。インクルーシブ公園に限らず、一般の公園にも設置されるケースが増えてきました。自治体によっては一覧表を公表し、地域の人の健康促進を図っています。
このように、インクルーシブ遊具にはさまざまな種類があります。そして、1つの遊具が、すべての人向けに作られているわけではありません。インクルーシブ遊具が複数設置され、公園全体で多くの人が遊べるほか、さまざまな楽しみ方ができるのがインクルーシブ公園です。
また、インクルーシブ遊具があることだけでなく、公園へのアクセスがしやすく園内を歩き回りやすいこと、大人が子どもを見守りやすい場所があること、休憩場所があること、配慮を促す看板があることなども、大切な要素です。
インクルーシブ公園が注目されている背景
インクルーシブ公園はメディアにも取り上げられるなど、注目されることも増えてきました。この背景には、一体何があるのでしょうか。2つのポイントを取り上げます。
インクルーシブへの関心の高まり
1つ目は、インクルーシブに対する関心が高まっていることが挙げられます。きっかけは2020年、東京都世田谷区にある砧公園に、インクルーシブな遊具公園「みんなのひろば」が誕生したことです。
さらに同年、豊島区に「としまキッズパーク」のほか、インクルーシブを掲げたいくつかの遊び場がオープンしました。インクルーシブという言葉がメディアで紹介されるようになり、人々の関心が集まったと考えられています。
多様な子どもの育ちを等しく保障する考え方
もう1つは、特定の子どもを特別扱いするのではなく、等しくその育ちを保障する考え方が広がっているためです。
令和5年12月22日、子ども政策をまとめた「こども大綱」が策定されました。こども大綱には、「障害のあるこどもは、個々のニーズに応じた丁寧な支援が必要なこどもと捉え、障害の有無で線引しない」「こどもの育ちをひとしく保障する」とあります。子どもを区別することなく育てる環境の整備が、今求められています。
インクルーシブ公園の問題点・課題
注目を集め、今後益々広がるであろうインクルーシブ公園ですが、問題点や課題も見えてきました。
ここでは、利用以外の問題点・課題について、2つの視点から考えてみます。
日本の事例はまだ少ない
インクルーシブ公園は近年、日本において増えてはいますが、設置の進んだアメリカなどに比べて事例はまだ少ないのが現状です。
アメリカでは、障がい者への差別を禁止する「障害を持つアメリカ人法」(ADA)が1990年に成立したのを機に、インクルーシブという考え方が浸透していきました。障がい者が利用できる公園をつくり、差別をなくす取り組みが行われてきたのです。
一方、日本は2006年にバリアフリー法、2016年に差別解消法障害者を施行しました。アメリカに比べて歴史が浅く、取り組みが追いついていないことも、事例が少ない理由の1つと考えられます。
価値が十分に認識されていない
事例が少ないことと併せて、インクルーシブ公園の価値が十分に認識されていないことも課題の1つです。
障害者差別解消法は、障がいの有無によって分け隔てられることなく、個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する目的で制定されました。アメリカが、法律の施行に伴い、差別解消に向かう流れができたのに対して、日本はそうはなりませんでした。
しかし、砧公園の誕生によりインクルーシブという言葉が注目されるようになりました。インクルーシブの意味と公園の価値が今後広く認識されることで、取り組みが進むことが期待されます。
また、公園はそもそも、行政が計画・設計し、管理運営します。一方、インクルーシブ公園は、利用者の意見を聞き、設計のほか完成した後の改善も共に行います。その点では、利用に関する問題点・課題があれば、対応する体制ができていると言えるでしょう。
インクルーシブ公園の事例
次に、インクルーシブ公園の実例を見ていきましょう。東京、埼玉、神奈川の首都圏のインクルーシブ公園を紹介します。
東京
まずは東京のインクルーシブ公園を紹介します。
[世田谷区]砧公園「みんなのひろば」
砧公園内のみんなのひろばは、「障がいのある子もない子も、みんなで一緒に楽しく遊ぼう!」と呼び掛け、みんなが居心地の良いと感じる場所に育てていくことを目指しています。それぞれの人の事情や思いを理解し、地域の人みんなで育んでいく公園づくりを行っています。
リンク:砧公園「みんなのひろば」
[新宿区]新宿中央公園「ちびっ子広場」
新宿中央公園のちびっ子広場は、インクルーシブ遊具のほか、乳幼児専用の遊び場、パネル遊具などを備えています。インクルーシブ遊具の導入は、区立公園では初です。「だれもが楽しく、快適・安全に利用できる」遊び場として、広い休憩スペースも確保しています。
リンク:新宿中央公園「ちびっ子広場」
[品川区]大井坂下公園
大井坂下公園は、区内の小学3・4年生のアイデアを取り入れて整備された公園です。子どもたちは、「だれもが一緒に楽しめるユニバーサルデザインに配慮した公園・遊具」を考えました。その結果、車椅子の人と一緒に頂上まで上ることができる複合遊具など31のアイデアが採用されています。
リンク:大井坂下公園
神奈川
続いて、神奈川のインクルーシブ公園を紹介します。
[横浜市]小柴自然公園
小柴自然公園は、障がいのある人やその支援者団体、専門家、特別支援学校などから意見を聞いて設計された、横浜市で初めてのインクルーシブ遊具広場です。公園内には、車椅子のまま乗れる遊具やロープ付き遊具などを備えています。今後は、利用者にアンケートをとるなどして、利用状況調査を不定期に行う計画です。
リンク:小柴自然公園
[平塚市]平塚市総合公園「みんなの広場」
みんなの広場は、令和4年に市制施行90周年の記念事業として整備されました。障がい者関係団体や保育園・幼稚園などから意見を集め、アイデアを詰め込んだ広場です。障がい児と健常児が一緒に遊び、幼少期から関わりを持ちながら、誰もが自然体で助け支え合う町を目指しています。
リンク:平塚市総合公園「みんなの広場」
埼玉
ここでは、埼玉のインクルーシブ公園を紹介します。
[三郷市]なかよし ひろば
なかよし ひろばは、大学や市内障がい児施設などの有識者の意見を取り入れて整備された広場です。障がいの有無にかかわらず、子どもたちが一緒に遊び「なかよく」なってほしいという思いを込めて、広場名が名付けられました。車椅子や歩行器を使用している人が、介助者と一緒に遊べる遊具などがあります。
リンク:なかよし ひろば
インクルーシブ公園とSDGs
最後に、インクルーシブ公園とSDGsとの関係について確認します。インクルーシブ公園は、SDGsの目標10「人や国の不平等をなくそう」、目標11「住み続けられるまちづくりを」の達成に貢献します。
目標10「人や国の不平等をなくそう」
目標10「人や国の不平等をなくそう」は、年齢、性別、障がい、人種、その他の状況にかかわらず、すべての人に社会に参加する力を与えるとしています。また、差別的な慣行を撤廃し不平等を減らすことを掲げています。
インクルーシブ公園は、障がいの有無や年齢、性別、国籍などに関係なく、すべての人が遊べる公園です。誰かが遊べない、公園に行きにくい、という状況にならないように、配慮する必要があります。インクルーシブ公園を通じて、平等な社会の実現に貢献します。
目標11「住み続けられるまちづくりを」
目標11「住み続けられるまちづくりを」は、女性や子ども、障がい者、高齢者などが、安全で使いやすい緑地や公共スペースを利用できるようにすることなどを目指しています。
安全で使いやすい遊具と周辺環境は、インクルーシブ公園に欠かせません。さまざまな人がインクルーシブ公園に集まることで、住みやすい町づくりが可能です。さらに、地域の人との交流が増えることで、より強いつながりができます。その結果、住み続けたい町になることで、目標を達成できます。
まとめ
インクルーシブ公園は、障がいの有無や年齢、性別、国籍などに関係なく、誰もが楽しく遊べる公園です。日本は、2006年にバリアフリー法、2016年に障害者差別解消法を施行しましたが、インクルーシブ公園が普及するまでには至りませんでした。
ところが2020年の砧公園の開園をきっかけに、インクルーシブ公園が注目されはじめています。この流れを捉えて、日本にも広がることが期待されています。インクルーシブの意味の理解を深めるために、一度足を運んで体感してみてはいかがでしょうか。
<参考文献>
大人も子どもも、障がいがあっても楽しめる。今増えている「インクルーシブ公園」ってなに? | Yahoo! JAPAN SDGs – 豊かな未来のきっかけを届ける
みんなが遊べる、みんなで育てる 都市公園の遊び場づくり参考事例集 令和6(2024)年4月 国土交通省 都市局 公園緑地・景観課
「インクルーシブ公園」を、ムーブメントからスタンダードに|新・公民連携最前線|PPPまちづくり
この記事を書いた人
池田 さくら ライター
ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。
ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。