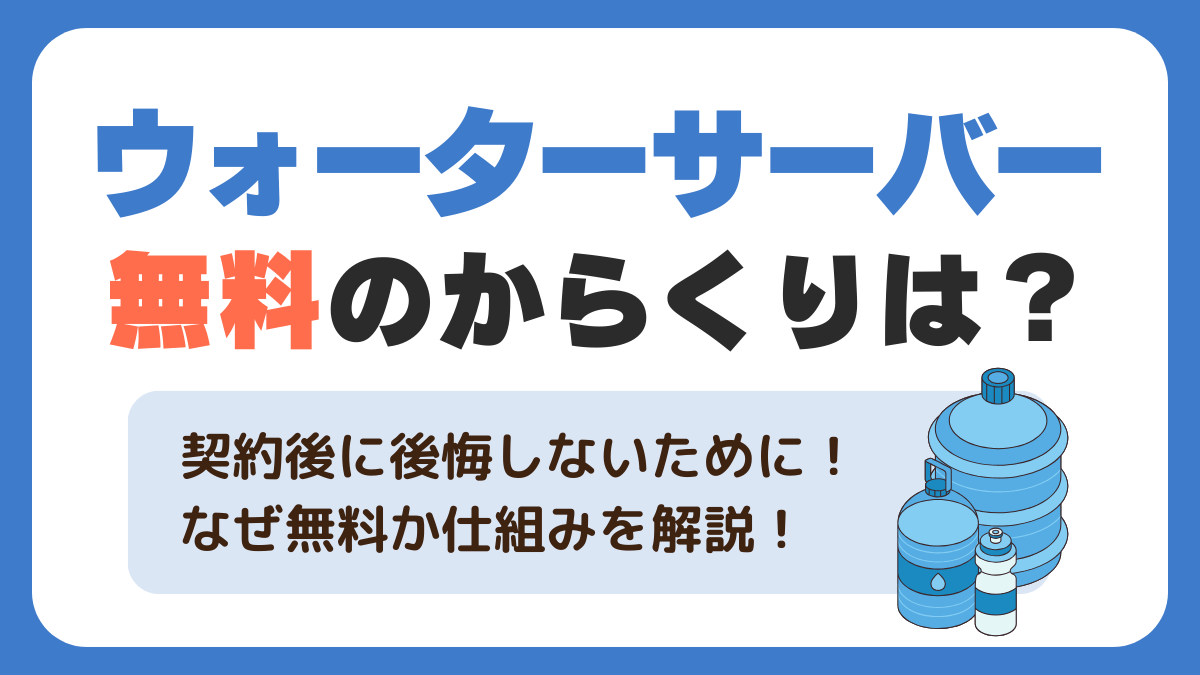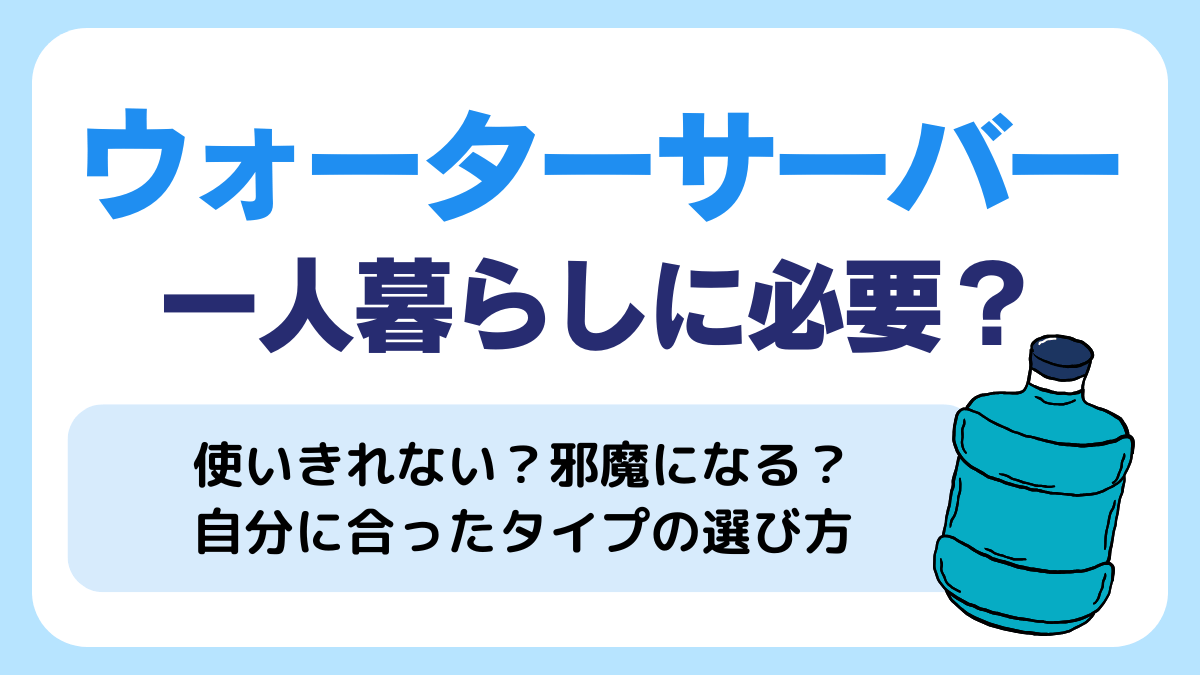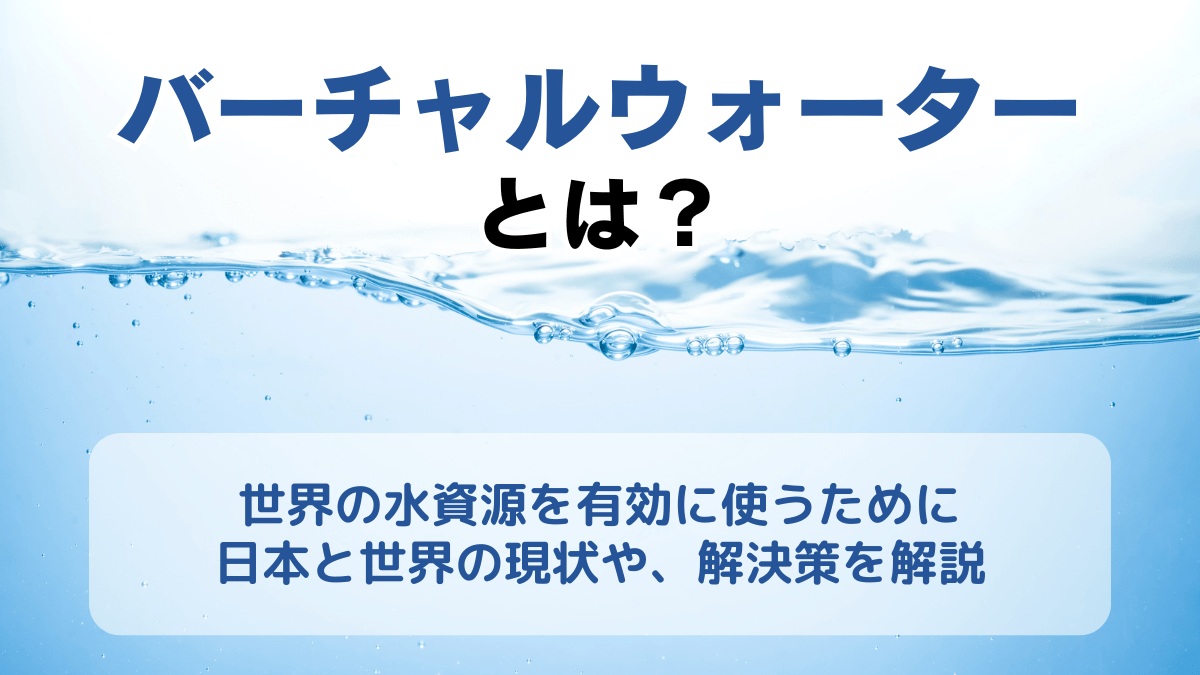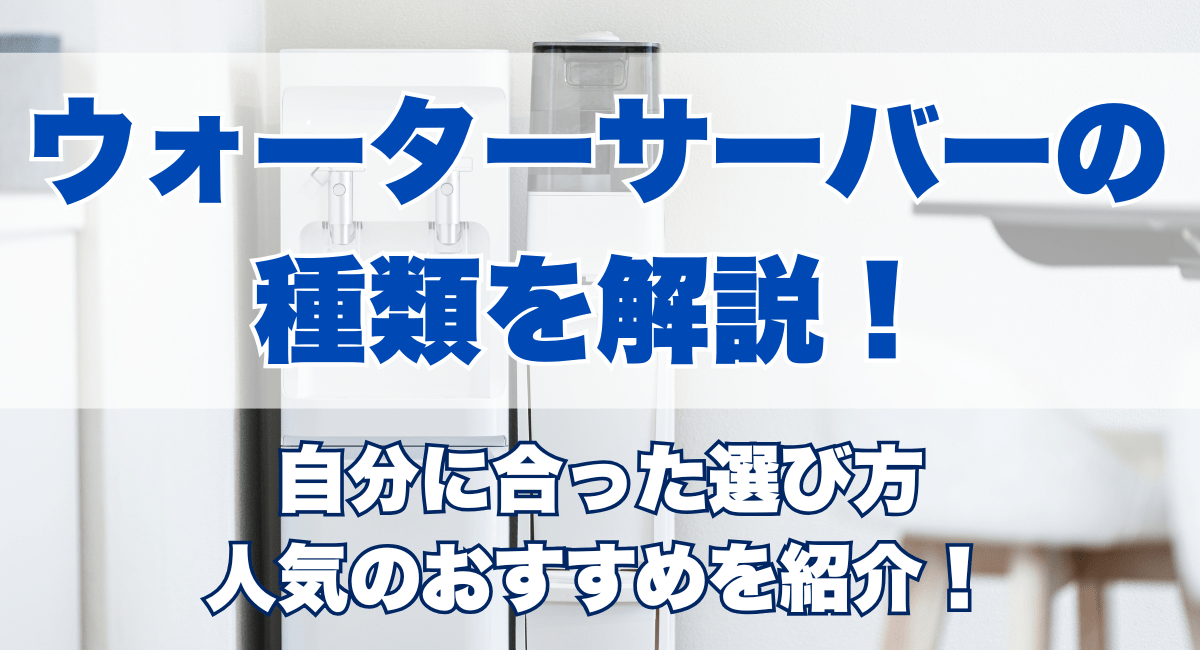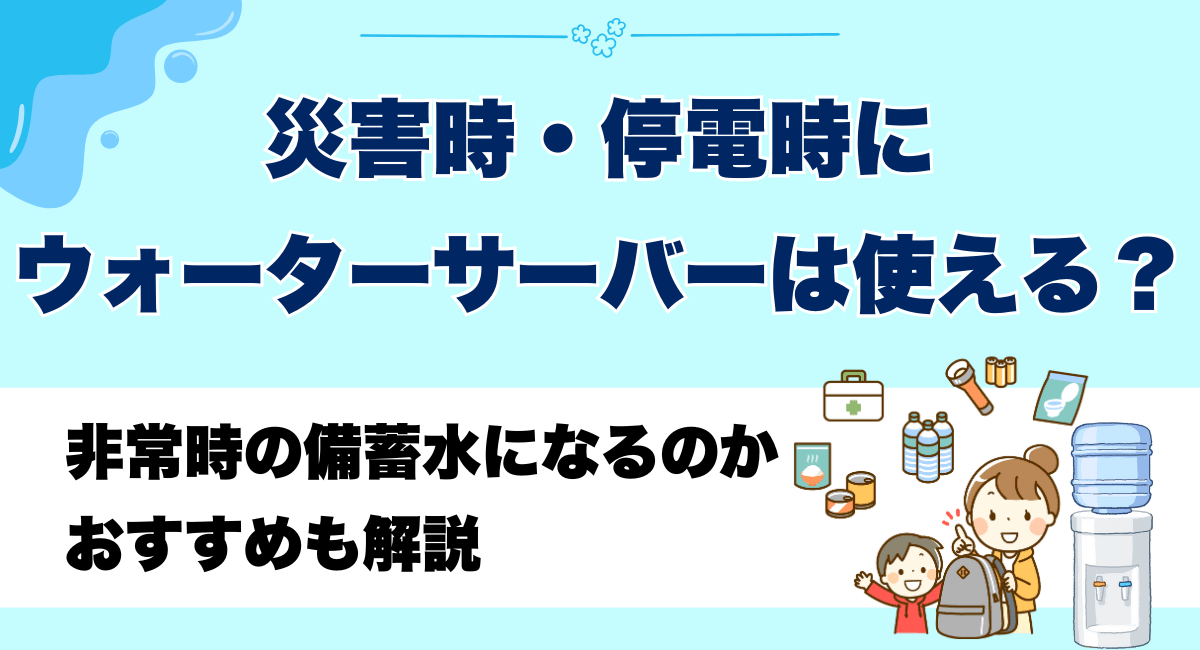文化祭や探求授業でSDGsについて調べようと考えている小学生・中高生の方も多いのではないでしょうか。とはいえ、何をすればいいのかわからない。という方も多いと思います。
そこでこの記事では今すぐ簡単にできるアクションを目標別に並べました。合わせてまとめかたも掲載しているのでぜひ参考にしてみてください。
それでは最初に、SDGsの基本の「き」を簡単に解説してみましょう。
目次
【小学生向け】SDGsとは?わかりやすく解説
SDGsとは「だれひとり取り残さない」という決意のもと、持続可能な未来をつくるために今私たちが何をすべきかをまとめたものです。
環境、貧困、人権、開発、平和など世界はさまざまな問題をかかえています。
子どもたちであれば自分たちが大人になったときのため、大人であれば今日からの未来をもっと生きやすくするため、SDGsはすべての人に必要な達成目標がギュッと詰め込まれています。
17の目標・169のターゲットで構成されている
もう少し踏み込むと、SDGsは17の主要な目標と、それを達成するための169のターゲットで構成されています。
目標とターゲットを詳細に設定することで、各国や地域は自分たちの問題でもあるという意識を持つことができ、「社会」「経済」「環境」の大きな3つの分野で確実に取り組みを進められるような仕組みになっているのです。
そしてSDGsは達成状況を測ることも特徴で、毎年ランキング形式で世界各国の状況がまとめられています。次では日本の達成状況を確認しましょう。
日本のSDGsの達成状況
<日本の達成状況年度別 Sustainable Development Report>
2015年に提唱されてから今年(2023年)で8年が経過しました。
2021年の日本の順位は世界で18位と低い達成状況となっています。
Sustainable Development Report(持続可能な開発報告書)2021によると、特に目標15「陸の豊かさも守ろう」の悪化が見られます。(※1)
また、この報告書からは、ある課題が見えてきます。
今後の課題
SDGs達成のために私たちが持つ課題は、いかに「自分ごと化」に置き換えられるかです。
繰り返しになりますが、SDGsが採択されて今年(2021年)で6年です。
当初と比較して認知度は4倍、項目によっては起きている問題や解決方法も理解していると応える人は増えてきています。
一方で、課題もあります。
寄付をする、オーガニック食材を消費する、再生可能エネルギーへの投資など金銭が伴うアクションに関しては、なかなか踏み出せないと感じる人も多いようです。
- 「活動に参加したいけど自分に何ができるかわからない」
- 「経済的に余裕がなくても世界を変える行動をしたい」
そんな声から生まれたのが国連が提唱した「ナマケモノにでもできるアクション・ガイド」です。
だれひとり取り残さない、というSDGsの決意の中にはすべての人が参加できるように!という意味合いも込められているのです。
まずはチェックしたい!ナマケモノにもできるアクション・ガイド
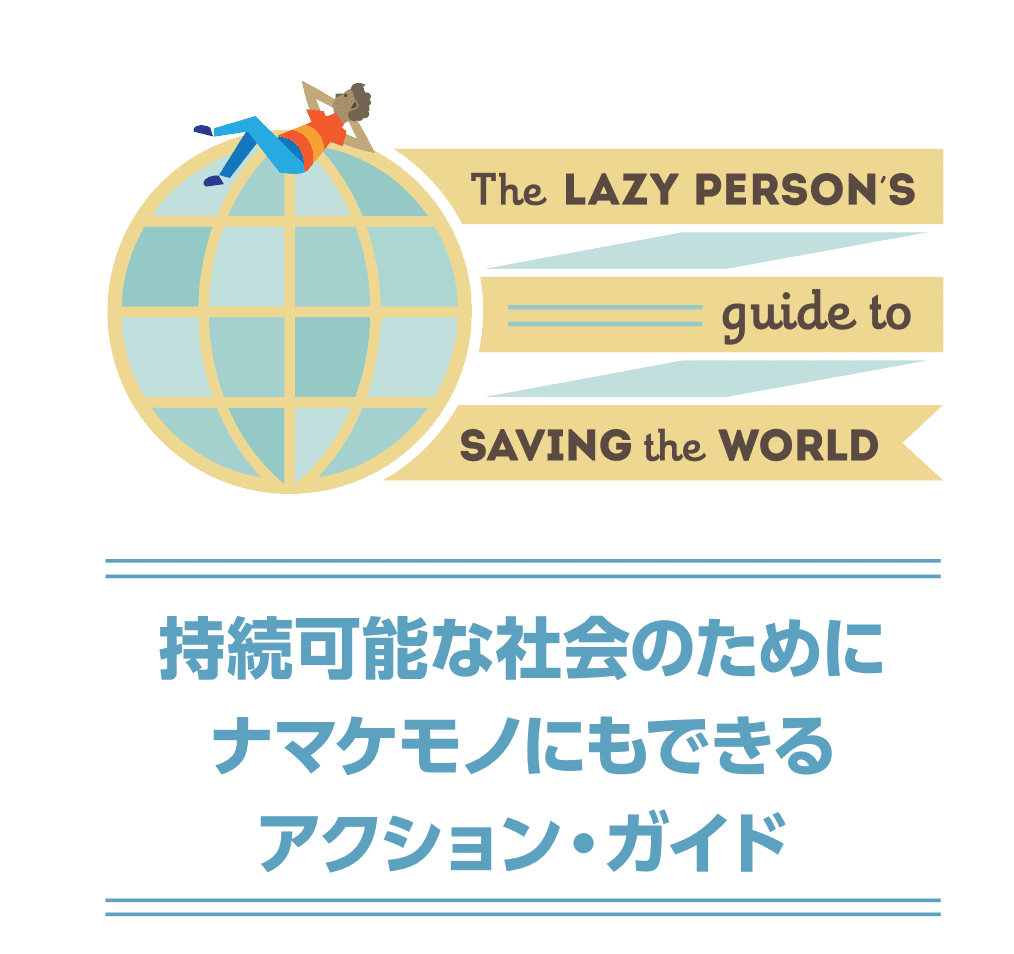
国連ではすべての人がSDGsにかかわれるよう「持続可能な社会のために ナマケモノにもできるアクション・ガイド」を推奨しています。(※2)
レベル1 ソファに寝たままできること
レベル2 家にいてもできること
レベル3 家の外でできること
レベル4 職場でできること
これは私たちはナマケモノだと言っているのではなく、力を抜きながらでも日常からSDGs達成に進んでいけるということを示しています。
では、このナマケモノにでもできるアクション・ガイドをどのように探求授業に活用すれば良いのでしょうか。
探求授業のまとめ方の例
ここでは、レベル2の「できるだけ簡易包装の品物を買おう!」を例に、探求授業のやり方を見ていきましょう。
- 普段使っている商品に使われている包装の重さをチェック
- 次に簡易包装商品を見つけ出す。その包装の重さを量る。
- それぞれの重さを比較して表にまとめる
少ないステップかつ、普段の買い物から親子で一緒に取り組める内容です。簡易包装商品が売っている店や、過剰包装が環境に与える影響をまとめても良いかもしれません。
次からは、もう少し踏み込んで、各目標ごとの研究テーマのヒントを見ていきましょう。
- 〈レベル2〉SDGs1
「子どもの貧困についてまとめてみよう!」 - 〈レベル3〉SDGs2
「地産地消について調査!」 - 〈レベル3〉SDGs2
「自作コンポストでフードロス削減!」 - 〈レベル3〉SDGs3
「運動しながら交流できる「parkrun」に参加!」 - 〈レベル2〉SDGs4
「オルタナティブスクールの魅力を調査!」 - 〈レベル2〉SDGs4
「給食のすごさ!どんな栄養が含まれているの?」 - 〈レベル3〉SDGs5
「おもちゃのジェンダー|男女でどんな違いがある?」 - 〈レベル2〉SDGs6
「どれくらいの水が無駄になっているのか徹底調査!」 - 〈レベル2〉SDGs7
「オフグリッドで電気使用量を調査!」 - 〈レベル3〉SDGs8
「身の回りのエシカルな店をさがぞう!」 - 〈レベル2〉SDGs9
「技術と貧困地域の関係について調査!」 - 〈レベル3〉SDGs10
「身の回りの差別や不平等について一緒に考える」 - 〈レベル3〉SDGs11
「住んでいる街探検!SDGsとの関わりを探す」 - 〈レベル3〉SDGs11
「心地のいい街にするには何が必要?」 - 〈レベル2〉SDGs12
「お金のエネルギーはいったいどれくらいあるの?」 - 〈レベル3〉SDGs13
「グリーンカーテンを作ってみよう!」 - 〈レベル2〉SDGs14
「身の回りのプラスチックは海にどれくらい悪影響なの?」 - 〈レベル2〉SDGs15
「パーム油が使われている商品や製品を調べてみよう!」 - 〈レベル2〉SDGs16
「スマホのリサイクルってどうなっているの?」 - 〈レベル3〉SDGs17
「生産者のことを考えた買い物に挑戦」
SDGs目標1「貧困をなくそう」の探求授業テーマ
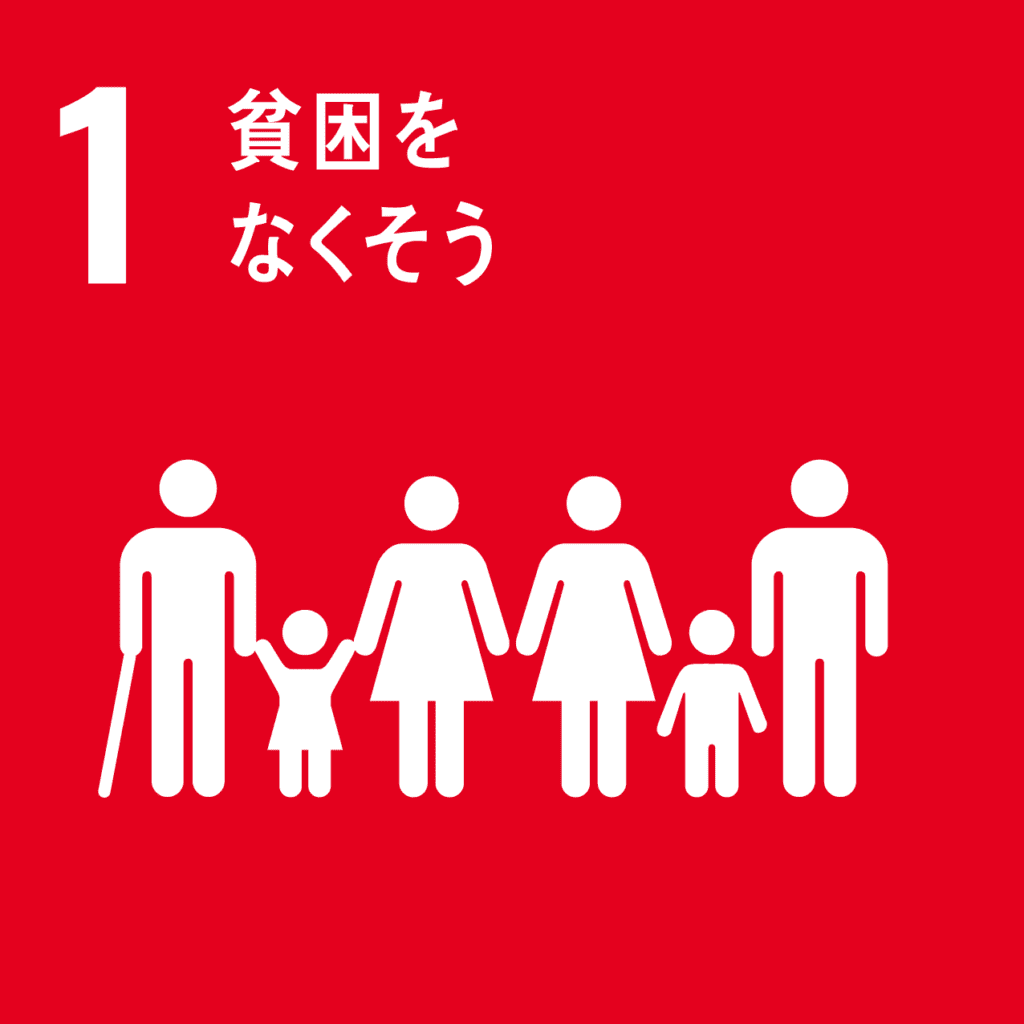
「貧困をなくそう」の概要
全世界で7億8,300万人の人が日本円にして1日210円未満という極度の貧困状態で生活をしています。また日本にも相対的貧困が存在し、子どもの学力や雇用にも影響がでています。
貧困の撲滅は、教育、雇用、気候変動などその他の目標達成にも関わる重要な内容です。
目標1の探求授業テーマ例|子どもの貧困の実態を調べてみよう
貧困というと、遠い国の出来事と感じていまいます。そこで、貧困とは何か、貧困に陥るとどのようなことが起きるのかといったことを調べてみるのもいいでしょう。調べる際におすすめなのがLFAです。
「子どもの貧困に、本質的解決を」をミッションに掲げるLFAは、法・制度を変え、子どものあらゆる「貧」と「困」をなくす社会をつくろうとしている団体です。
LFAでは子どもの貧困の実態を多くの方に知ってもらうきっかけとして、豊富でわかりやすい情報を掲載しています。また、オンラインにて、活動説明会、座談会も開催しています。
探求授業のまとめ方例
- 貧困について調べて、どういった課題があるのかをノートにまとめる
- 自分にできることがないか、グループで話し合ったり、調べたり、考えたりする
- できることを実践してみて、感想をまとめる
SDGs目標2「飢餓をゼロに」の探求授業テーマ

「飢餓をゼロに」の概要
目標2では、飢えをなくし、だれもが栄養のある食糧を手に入れられるように世界規模で農業の仕組みを変えることが求められています。
目標2の探求授業テーマ例②地産地消について調べる
地産地消について調べてみましょう。
探求授業のまとめ方例
- 地産地消の言葉の意味を調べる
- 普段食べているご飯・おかずの材料がどこで作られているのかをチェック
- 家の近くでもその材料が作られていないかを調査
- どれくらい地元の食材に変更できるかを表にまとめる
目標2の探求授業テーマ例②自家製コンポストを作ってみよう!
食品廃棄物を削減するために、コンポストを自宅で作ってみましょう!
飢餓の増加は気候変動による洪水や干ばつも大きな要因とされています。「飢餓をゼロに」の目標達成には気候変動の対応が必要です。
気候変動の要因はさまざまな背景がありますが、中でも私たちの家庭から出る食品廃棄物が処理される過程で温室効果ガスが発生することが報告されています。
埼玉県の調査では、廃棄物処理に伴う温室効果ガスの排出量は県内全体で約95万トン(CO2換算)、焼却施設からはその95%に当たる約90万トンが排出されていると推測されました。
廃棄物を減らすために私たちができることは食品ロス削減に加え、自宅や学校で楽しく挑戦できる「おうちコンポスト」です。
ずぼらだからな・・・と自信のない方でもできる放置するだけで完成するコンポストの作り方をご紹介します。
ずぼらな人でもできちゃう「ほったらかしコンポストの作り方」
・ごはん
・野菜、果物
・卵の殻
・魚、肉類(ただし骨を取り除いて!)
・パン・麺
・落ち葉
・枯草
・土
※作る前の下準備
コンポスト容器がある方は容器を、畑や庭がある場合は穴を掘る
1.水を切っておく
野菜や果物は細かく切っておき、水を切っておく。水分が多いとカビや悪臭の原因となってしまいます。
2.いざコンポストに投入
下準備したコンポスト材料と土を混ぜます。水分が多すぎるとNG。逆に乾燥していると感じたら水道水を霧吹きでさっとかける。混ぜた後は土で覆われるようにします。
4.定期的(週に1度か2度)かき混ぜる
新鮮な酸素を入れて微生物の活動を助けましょう
5.1から4を繰り返し、コンポストが満タンになったら放置
コンポストが満タンになったら1ヶ月放置し熟成させます。その後半月に1度くらいコンポストの中身をかき混ぜると発酵の効率が良くなり質の良い堆肥ができます。
作る過程を写真に撮ってノートにまとめたり、毎日の変化を記録したりすると見栄えが良くなるでしょう。
SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」の探求授業テーマ

「すべての人に健康と福祉を」の概要
目標3では、世界のすべての人々が生涯健康的で幸せな生活をおくれることをめざしています。
感染症にかからないことはもちろん、薬物乱用、アルコール依存をなくすことも求められます。
目標3の探求授業テーマ例|「parkrun」に参加してみよう
運動しながら色々な人と交流してみてはいかがでしょうか。
- 普段どのような運動をしているのか
- 運動をして体調に変化があったか
- 日本の医療制度についてどのように感じているか
などを聞き出せれば、学校ではわからない新鮮な情報を得られるかもしれません。とはいえ、そんな機会や場面がない人も多いと思います。
そこでおすすめしたいのが、すべての人が無料で自分のタイミングで参加できるコミュニティイベント「parkrun(パークラン)」です。
parkrunの特徴は、
- 登録・参加費、ずっと無料
- 世界中(日本では25箇所)で毎週土曜日決まった場所で開催されている
- 開催日時の中で好きなタイミングで参加可能
- 決められた5kmコース内を自由に歩く・ジョギングする・観覧のみでの参加もOK
日本ではすでに25箇所が開催地となっていて、お住まいから近い場所で無料で運動を楽しむことができます。
2020年11月にスタートをした愛知県豊田市白浜公園parkrunイベントディレクターの青木宏和さんは、parkrun開催について次のように話します。(※3)
「parkrunは小さなお子さんからご年配の方まで誰もが自由に参加できる温かい雰囲気のコミュニティイベントです。今後も地域の方にとって交流の場にしていきます。」
詳細を知りたい方、自宅から一番近い開催場所を知りたい方はparkrun 公式サイトをご覧ください。
探求授業のまとめ方例
- 聞いてみたいテーマについて調査する(毎日運動する人はどれくらいいるのか・運動がもたらす効果など)
- 運動しながら様々な年代の人に話しかける
- 聞いた情報をノートにまとめる(年代別に毎日運動をしている人の割合などをまとめるのもいいかもしれません)
SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」の探求授業テーマ

「質の高い教育をみんなに」の概要
生きていくために必要な知識や能力を身につけるために質の高い教育はすべての人に必要なものです。目標4の達成は子どもたちの将来の選択肢が増え、収入が安定し、生きる目的が見つかるなど人生の生きがいにつながります。
SDGs目標4の探求授業テーマ例|新しい教育の形。オルタナティブスクールの魅力にふれる
オルタナティブスクールの魅力に触れ、新しい教育のあり方に触れてみるのも良いでしょう。
多様性を理解するオルタナティブスクールの教育概念が、だれひとり取り残さないSDGsのゴールへと導く可能性があります。
オルタナティブスクールは個人が尊重され主体性を重視した教育が基本です。
探求授業のまとめ方例
- オルタナティブスクールがどのような学校なのかを調べる
- 自分の学校と何が違うのかをまとめる
オヤトコ発信所では日本のオルタナティブスクール一覧を紹介しています。
目標4の探求授業テーマ例②給食について考える
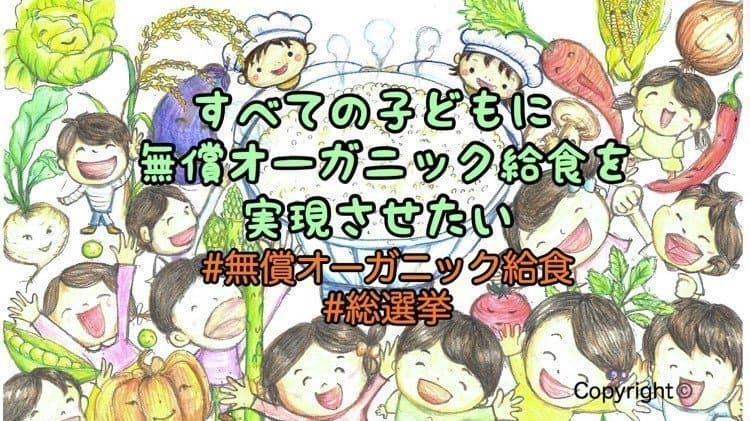
目標2と関連させて、毎日食べている給食について考えてみてはいかがでしょうか。
食と学びはつながっています。この機会にぜひ給食について考えてみましょう。
- どこの食材が使われているのか
- 栄養がどのくらいあって、体にどのような効果をもたらすのか
といったことをまとめるだけでも立派な研究です。
また、オーガニックに興味がある方は、無償オーガニック給食について調べてみるのも良いかもしれません。
世界ではオーガニック栽培や製品販売が急速に進み、日本でも2050年までに有機農業を農地の25%に増やすと発表されました。
そこで子どもたちの学校給食にも質の良いオーガニック食材を!と始まったのが「#無償オーガニック給食」キャンペーンです。
このキャンペーンについて詳しく調べ、オーガニック給食にするにはどのような課題があるのか、どうすれば実現できるのかを自分なりに考えてまとめてみてはいかがでしょうか?
SDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」の探求授業テーマ

「ジェンダー平等を実現しよう」の概要
目標5のゴールは女性と男性が同様に経済的な権利を獲得し積極的に社会に貢献できるジェンダー平等が確立された社会をつくることです。
SDGs目標5の探求授業テーマ例|身近にあるおもちゃのジェンダーを考えてみよう
おもちゃにもジェンダーが存在しています。
子どもたちが生まれて最初に受けるジェンダー不平等は、おもちゃです。
言葉が発達していない小さな幼児は自分の好きなあそびをうまく伝えられません。
男の子用、女の子用と売り場が分かれていますが、それは大人の勝手な判断なのです。
探求授業のまとめ方例
- 男の子用・女の子用と分けられているおもちゃを探す
- そのおもちゃがどうなれば男女共に遊べるものになるのかを考えまとめる
デザインを描いたり、実際にみんなが楽しめるおもちゃを作ったりしてみよう
関連記事:ジェンダーレスとは?世界・日本の現状・企業の取り組みやSDGsとの関連性
関連記事:ゲイとは?ホモやトランスジェンダーとの違い、LGBTとの関係
関連記事:レズビアンをわかりやすく解説!バイとの違い・公言している有名人
SDGs目標6「安全な水とトイレを世界中に」の探求授業テーマ

「安全な水とトイレを世界中に」の概要
世界で起きている水不足は全世界の40%の人に影響を与えています。すべての人が安全な水を確保することで健康維持にかかわり、持続可能な環境づくりにつながります。
SDGs目標6の探求授業テーマ例|水の消費を調べよう!
日々の生活に必要なものがどこからやってきて、どのくらいの資源が使われているかを知ることから始めてみましょう。
そのために有効なのがバーチャルウォーターです。
環境省の調べでは、
- 1kgのとうもろこしを生産するには1,800リットルの水が必要
- 牛肉1kgを生産するには2万リットルの水が必要
とされています。
環境省のバーチャルウォーター自動計算機では昨日食べたもの、今日食べたものにはどれだけの水が消費されたかを知ることができます。
日頃の節水対策で年間18,000円の節約になる!今すぐ始めるべき2つの方法
日々の節水を心がけましょう。
水の無駄遣いをなくすには日常生活のルーティンから変える必要があります。
こまめに節水対策を行えば節約がかない、経済的にも助かるかも。今からできる2つの方法をご紹介します。
顔を洗うとき、歯磨きするとき、食器を洗うときに蛇口を開きっぱなしにしていませんか。
蛇口をこまめに閉めることで年間75,000リットルの節水、金額換算すると年間18,000円の節約になります。
フライパンについた油、お皿についた油をそのまま水で洗おうとしてもすぐには取れず、結果水をたくさん使って洗うことになります。油を流すことは環境にもよくありません。
あらかじめキッチンペーパーで油をできるだけ拭き取っておけば節水にもなりますし大量の洗剤を使わず経済的です。
探求授業のまとめ方例
- 身近にある食べ物や製品にどれくらい水が使われているかを調べる
- 自分にできる節水についてのアクションを考える
- そのアクションがどれだけ水を減らせているのかをまとめる
SDGs目標7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」の探求授業テーマ

「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」の概要
世界の10億人が電気のない生活をしています。目標7のポイントはすべての人が電気を使えるようにすることに加え、地球環境の保全の両立が求められます。
私たちが最初にすべきことは、省エネ対策とエネルギーの無駄遣いをなくすことです。
SDGs目標7の探求授業テーマ例|オフグリッドを通して身近なものの消費電力を調べてみよう!
普段、自分がどのくらい電気を使っているかを調べてみるのはいかがでしょうか。
例えば、スマホを自家発電機で充電してみて、そこからどれだけ電気が使われているかをまとめます。
ちなみに筆者一押しの自家発電機は持ち運び可能なポータブル発電機・スマートタップというもの。車の荷台に収納できるコンパクトサイズなのでアウトドアにも大活躍です。
ここで自宅で自家発電に取り組んでいる方に、その魅力を聞いたところ次の応えが返ってきました。
「コンセントを差せば簡単に得られる電気、大事に使おうと思えるようになったんだ。
スマホ充電をするのに何ワット電気を使っているのかエコが数値化できることで、自分の生活で必要なエネルギーがわかったし、それをするためにはこのエネルギーをどうやって作るかを考えるきっかけとなったね」
当たり前のようにコンセントから供給される電気、届くまでに誰がかかわりどう作られるのか、電気は当たり前ではない、ということを知るには自らが作ってみることも手段のひとつですね。
探求授業のまとめ方例
- 自宅で1日どれくらい電気を消費しているのかを調べる
- スマートタップにスマホをつないで数値を確認する
- 自分にできる節電対策を考えまとめる
関連記事:太陽光発電とSDGsとの関連性|特徴と企業の取り組み、メリット・デメリット
SDGs目標8「働きがいも経済成長も」の探求授業テーマ
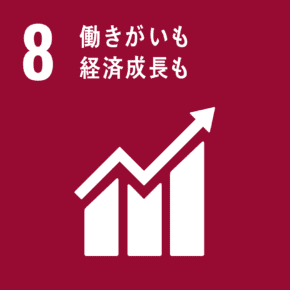
「働きがいも経済成長も」の概要
「働きがいのある人間らしい仕事」は1999年に国際労働機関で提起されました。すべての人が人間らしい仕事につくには、社会の仕組みを学ぶこと、有給休暇をしっかりと取得すること、エシカル企業を応援することがポイントです。
SDGs目標8の探求授業テーマ例|エシカルなお店を調べてみよう!
エシカルなお店に積極的に通って、どのような内容なのかを調べてみましょう。
エシカルを推進する企業や個人店を応援することで、雇用問題や環境問題、社会問題を解決するきっかけになるのです。
たとえばエシカルな個人店ってどんなものがあるの?という疑問に、筆者がおすすめしたいのは「筆談カフェ」です。
筆談カフェとは「おしゃべり禁止」ではなく、音声を使わないコミュニケーションができるカフェです。筆談、ジェスチャー、手話、アイコンタクトを用いて言語ではない会話を楽しむ空間です。
三重県いなべ市に、「桐林館喫茶室」という筆談カフェがあります。
ここは聴覚障害に対するイメージを変えたいという思いから誕生したお店、聞こえないを体験して非言語への理解を深めています。
みなさまもお近くのエシカルなお店を探してみて、社会で起きている不平等を改善していきましょう。
探求授業のまとめ方例
- エシカルに取り組むお店を調べる
- お店に行って、どのような部分がエシカルなのかを体験してくる
- 特徴をまとめる(働き方がエシカル出会った場合、お母さんやお父さんに働くことについて話を聞いて比較してみるのも良いでしょう。)
関連記事:エシカルで環境に優しい「ヴィーガンレザー」のメリット・デメリット、おすすめ商品
SDGs目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」の探求授業テーマ
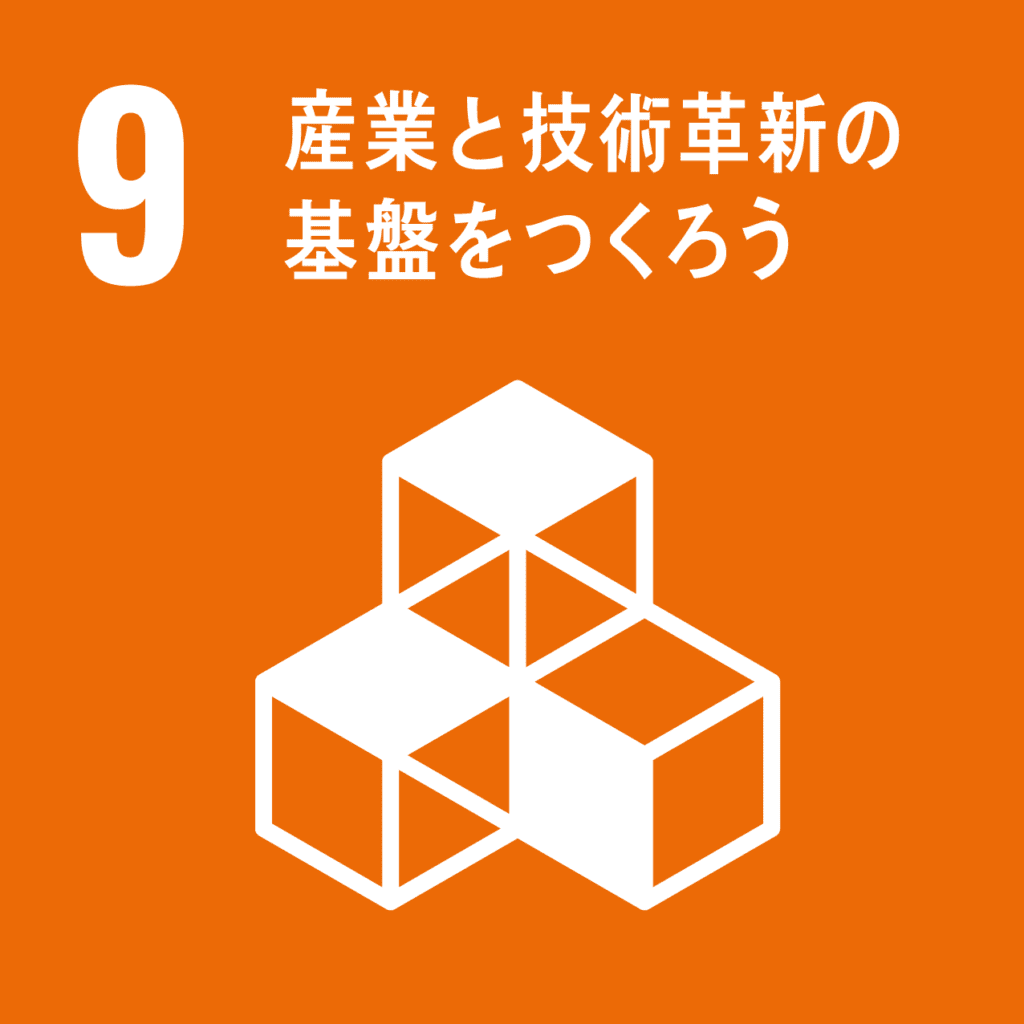
「産業と技術革新の基盤をつくろう」の概要
持続可能な開発には新しい価値を創造するイノベーションが必要です。私たちができることは、日本の技術はどんなものがあるのか、それが世界にどのような影響を与えているのかを知ることから始めてみましょう。
SDGs目標9の探求授業テーマ例|新しい技術が貧困地域にどんな影響を与えているか調べてみよう!
先進国と開発途上国、国境を越えた技術共同開発が、貧困撲滅の解決になることを調べてみましょう。
北海道大学発、AI開発にかかわる調和技研が2019年12月にバングラデシュに「AI SAMURAI JAPAN」という開発拠点を設けました。
調和技研の中村拓哉代表取締役は現地開発に向けてこう話します。
「バングラデシュに開発拠点を設置した理由は、人材の優秀さだ。バングラデシュ発のAIでバングラデシュを豊かにしていきたい」
将来は優秀な人材がバングラデシュと日本の架け橋になってもらい、共に社会問題に取り組んでいきたいということです。(※6)
日本のAI技術が開発途上国にどんな影響を与えているか知ることで、子どもたちであれば技術者への夢が膨らみ、私たちが新技術に対する評価もおのずと高くなるでしょう。
探求授業のまとめ方例
- 貧困地域ではどのような課題があるのかを調べる
- 解決に向けてどのような技術が必要か考える
- 実際にどのような技術が貧困地域に役立っているのかを調べてまとめる
SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」の探求授業テーマ

「人や国の不平等をなくそう」の概要
目標10のゴールのポイントはひとつの国の中で起きている不平等と、国同士のかかわりの中で生じる不平等をなくすことです。
私たちがまずできることは、自分が差別していないか、もしくは差別されていないかを考えることから始まります。
SDGs目標10の探求授業テーマ例|身の回りに差別や不平等がないか周りの人と話してみる
個人の持っている価値観の共有が差別や不平等をなくすきっかけとなります。差別や不平等というのは受けた側が「受けた」と感じた際に発生します。
たとえば、「ワーキングマザー」や「キャリアウーマン」という言葉。
最近ではワーキングマザーを肩書きにしている方もいらっしゃいますし、人によっては嫌う方もいます。
話し手は、母親もしながら働くってすごいね!という尊敬の意を込めているのかもしれませんが、差別表現だと捉える方もいます。
そうした場合、この言葉が相手にとってどう影響を与えるかを話し合うことが、良い関係づくりのきっかけになります。
探求授業のまとめ方例
- 身の回りにどのような不平等があるのかを考えてまとめる
- 実際にどのような不平等があるのかを調べたり、聞いたりする
- 自分にできることを考えて、グループで議論する
- 最後に自分の考えや、周りの反応をまとめる
SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」の探求授業テーマ

「住み続けられるまちづくりを」の概要
目標11のゴールのポイントは、自分が住む地域の運営について知ること、自分がいいと都市のあり方を考えることです。道は安心して歩けるか?危険なところはないか?そうしたことを意識して周囲を見渡してみましょう。
SDGs目標11の探求授業テーマ例①住んでいる地域を探検してみよう!

自分が住んでいる村や町、市の運営に関心を持つと、これまで知らなかったプロジェクトにお目にかかることができたりするものです。
例えば、千葉県木更津市に「KURKKU FIELDS(クルックフィールズ)」は、農業、食、アート、プレイ&ステイ、自然、エネルギーの6つの顔を持つ複合施設、それぞれのカテゴリーでサステナブルな活動を行なっています。
クルックフィールズでは季節ごとに自然の恵みを五感で楽しめるイベントが開催されています。公式サイトのイベント情報で最新イベント情報を確認することができます。
2021年7月1日からは「サマーアドベンチャー2021」(2021年7月1日(木)から9月30日(木)の期間)が開催されており、親子で楽しめるコンテンツが盛りだくさん。
子どのたちの環境教育にぴったりの水辺の生き物観察会や、新鮮な野菜やハーブを使ったピザ作り体験、広大な敷地をめぐるクルックフィールズツアーなど、ワクワクする企画が満載です。
このように、身近な場所でどう楽しむかに意識を向けてみると、新しい発見が見つかるかもしれませんね。
探求授業のまとめ方例
- 身近にあるサステナブルな施設を探す
- 実際に訪れて体験する
- 体験によって自分がどう感じたかをまとめる
- さらには、多くの人にその施設を知ってもらうためにはどうすればいいか、自分なりのPR方法を考えてみる
SDGs目標11の探求授業テーマ例②「どんな条件で心地良いまちなる?」地域のありたい姿を書き出してみよう!
自分がいいと思う都市のあり方、村のありかたを考えてみることから住み続けられるまちづくりはスタートします。
ここで北海道下川町を例にあげてみましょう。
人口約3,300人、地域の9割が森林という下川町は人口減少率が北海道1位、過疎化が進んでいました。
役場職員と町民が知恵を絞り「住みやすい町はなんだろう?」と考えた結果、
- 移住体験(ちょっと暮らし)ができる
- 住宅購入補助制度導入
- 起業補助制度
- 車がなくても生活できる(半径1km圏内で生活できる)
等のまちおこしを行いました。
その活動が評価され、移住してくる人が急増し雇用が増えるなど、住み続けられるまちづくりに貢献したのです。(※7)
探求授業のまとめ方例
- 住んでいる町の特徴をまとめる(自分なりの地図を作ると研究っぽくなります)
- どこが便利で、何が不便に感じるかをリストアップする
- 不便に感じる課題をどうすれば解消できるかを考える
- 機会があれば、役場に行ってその考えを伝えてみて意見をもらう
SDGs目標12「つくる責任つかう責任」の探求授業テーマ
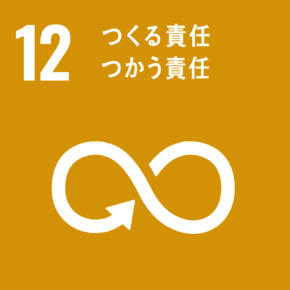
「つくる責任つかう責任」の概要
目標12のゴールのポイントはものの循環を考えることです。たとえば使うものや食べるものがどんな原料からできているか知る、お金の使い方を勉強する、など生活の中に存在するものの生い立ちを学んでみましょう。
SDGs目標12の探求授業テーマ例|お金の良い循環とは?お金の持つエネルギーを考えてみよう
持続可能な未来のためには消費者教育が必要です。そのためには子どもの頃からお金の循環について学ぶことも大切でしょう。
作家でワークライフスタイリストの宮本佳実さんはお金の良い循環についてこう話します。
『お金は自分の幸せを交換できるチケット』ということを前からお伝えしていますが、あなたがお店で何かを買うという行為は、“お金”というチケットを使い、あなたが自分の“幸せ”と交換をするという仕組みです
『お金がどんどん自分のところに巡ってくる考え方とは?』
宮本佳実の「#年収1000万円ガール」になるまで
私たちは毎日、どこかで誰かがつくったものを消費して生活しています。
お金を支払う際も、どこの誰が作ってどんな思いで始めたのかを知って消費をすれば、宮本さんのようなお金の良い循環を生み出すことができます。
探求授業のまとめ方例
- 自分が何にお金を使っているのかをリストアップする
- 支払ったお金がどのように移動するかを調査する
- お金がどのようなルートで移動しているかをまとめる
SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」の探求授業テーマ

「気候変動に具体的な対策を」の概要
目標13のキーワードは二酸化炭素排出量を減らすことです。
私たちができる簡単なアクションは
- リサイクルを意識する
- 余分なエネルギーを使わない
- 自家用車ではなくなるべく公共交通機関を使う
です。
SDGs目標13の探求授業テーマ例|グリーンカーテンを取り入れてみよう

植物の特徴を生かしたグリーンカーテンを取り入れてることは省エネとなり、経済面と環境面に良い影響をもたらします。
横浜市の調査では、グリーンカーテンがある場合、窓は約4℃、室内の床は約6℃下がることがわかりました。
グリーンカーテンを使用することで室内の熱の蓄積を抑えられ、冷房温度を極端に下げる必要がないので省エネになり二酸化炭素排出量を減らせます。
グリーンカーテンに向いている植物は、ゴーヤやヘチマ、あさがお、ひょうたんなどツル科の植物です。育てやすさではゴーヤがおすすめ。実がなれば食材にもなるのでこの夏ぜひ育てて本当に温度に変化があるのかを調べてみましょう。
探求授業のまとめ方例
- グリーンカーテンを設置する場所の温度をあらかじめ測っておく
- グリーンカーテンを設置し、成長記録をつける
- 成長の度合いによって定期的に温度を確認
- 完成したら、どのくらい温度が変化するのかをまとめる
SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」の探求授業テーマ

「海の豊かさを守ろう」の概要
海の豊かさを守るには陸から出るゴミを減らすことがポイントです。私たちが今すぐできることは、使い捨てプラスチックを減らすこと、キッチン周りのものをエコなアイテムに変えることです。
SDGs目標14の探求授業テーマ例|身の回りの製品について見直してみよう!
身の回りの製品が海にどのような影響を与えているのかを調べ、改善策を考えてみましょう。例えば、台所スポンジを植物由来のものに変えることが海洋汚染ストップにつながります。
市販の食器洗いスポンジはほとんどがプラスチック製で、使い続けると徐々にすり減り、細かなマイクロプラスチック粒子として下水から河川、最終的に海へ流れ着き汚染物質となります。
何度も洗って使えるアクリルたわしもエコだと思われがちですが、アクリルもプラスチック仲間で立派な化学繊維。洗うたびに細かい繊維が下水に流れるため一概にエコとは言い切れません。
そこでおすすめしたいのが100%天然由来の「ヘチマたわし」です。
乾燥したヘチマは繊維が非常に細かく昔から靴の中敷や室内用スリッパ、台所スポンジとして使われ、最近では体洗い用のスポンジとしても使われるようになりました。
へちまスポンジを台所スポンジとして活用するメリットは、
- 天然繊維で環境に優しい
- 固めの繊維がフライパン焦げ汚れをごっそり落とす
- 根菜の皮にこびりついた泥を綺麗に掻き落とす
などキッチン周りで発生する日頃の困ったを解決してくれるのです。
市販スポンジの代わりにヘチマたわしを使うことで、キッチンから流れ出るマイクロプラスチックを減らすことができます。
探求授業のまとめ方例
- プラスチックでできている製品を探す
- その製品が海に与えている影響を調べる
- 解決策として何が有効か、どうすれば海にプラスチックが流出しないかを考えまとめる
関連記事:プラスチック問題とは?現状の排出量と環境・海への影響
関連記事:脱プラスチックとは?プラゴミ削減のメリット・デメリット、企業の取り組み
SDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」の探求授業テーマ

「陸の豊かさも守ろう」の概要
2021年の日本の状況で遅れている項目がこの目標15です。私たちがまずできることはペーパーレスを心がけること、パーム油製品は持続可能なものかどうか確認すること、森林の大切さに触れることです。
SDGs目標15の探求授業テーマ例|パーム油が使われている食品や製品を調べてみよう!
パーム油不使用の製品を選ぶ、持続可能なパーム油が使われているかを知ることで森林減少を食い止めることができます。
パーム油はアブラヤシの実から取れるオイルです。年中収穫でき汎用性が高いことから世界中で需要があります。
私たちの身の回りで言えば、ポテトチップスやカップラーメン、揚げ物の原料に使われ、原材料には植物油脂と記載されて登場しています。
このパーム油の出身地はマレーシアやインドネシアの熱帯雨林が多い地域。その地域ではアブラヤシ農園を拡大するために多くの熱帯雨林が伐採されていることが問題となっています。
私たちがパーム油の食品や製品を求めるほど、熱帯雨林は減少してしまうのです。
探求授業のまとめ方例
- パーム油が使われている製品を調べてみる
- パーム油不使用のものがないか調べる
- 持続可能なパーム油製品につけられる認証マークを調べてまとめる
SDGs目標16「平和と公正をすべての人に」の探求授業テーマ

「平和と公正をすべての人に」の概要
現在開発途上国で起きている紛争の原因は先進国の電子機器の普及が関係しているといわれています。すべての国が平和でいられるために、私たちは世界の紛争が起きている原因を知り、私たちが使っている製品が紛争にかかわっていないかを知ることから始まります。
SDGs目標16の探求授業テーマ例|使用しなくなったスマホをリサイクルしてみよう
スマホの再利用を行ったりリサイクルに出したりすることは、世界の平和を取り戻すきっかけとなります。
現代起きている紛争の原因のひとつに、先進国で使う電子機器の需要が影響しています。
武装団は武器調達のために電子機器の原料レアメタルダイアモンドを先進国に売り、アメリカ、イギリス、フランスが紛争当事者に紛争に使用する武器を売っています。
スマホの原料もまたレアメタルで開発途上国の鉱山労働者が採掘し、武力紛争の資金源となっています。
とはいえ、
「手持ちのスマホが紛争悪化に関わっている、だったらスマホを手放そう!」
というのは難しいところですね。
解決方法として有効なのは、スマホの端末リサイクル、もしくは再使用です。
端末を中古購入もしくは再使用すれば端末代がかからずお財布にも優しくなります。
国際環境経済研究所のサイトでスマホのエコな使用方法を説明しているので気になる方は下記リンクをご覧ください。
探求授業のまとめ方例
- なぜスマホが紛争の原因の一つになっているのかを調べる
- スマホをリサイクルするとどのようなメリットがあるか調べる
- リサイクルされたスマホがどのように活用されるのかを調べてまとめる
関連記事:日本のリサイクルの現状と先進国ドイツの取組事例を紹介|生まれ変わって何になる?
関連記事:アップサイクルとは?リサイクルとの違い、メリット・デメリット、企業事例と製品紹介
関連記事:3Rとは?日本企業の取り組み具体例と問題点、私たちにできること
SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」の探求授業テーマ

「パートナーシップで目標を達成しよう」の概要
SDGsは、公的、民間、私たち市民がパートナーシップを組まない限り達成できません。ひとりでできる実施手段と人と協力する協働の活性化が全体をゴールへと導きます。そのためにエシカル(倫理的)に基づいたアクションが求められます。
SDGs目標17の探求授業テーマ例|生産者のことを考えて買い物をしてみよう

フェアトレード製品を意識して購入することが、生産者の人権を守ることになります。
消費大国とよばれる日本を含む先進国ではアジアやアフリカ、中南米など開発途上国で生産された製品がとても安く売られています。
しかし、安く販売される裏側では生産者に賃金が支払われていなかったり、健康に悪い農薬や化学物質が使われていたりと雇用環境に配慮されていません。
生産者に正当な賃金が届くシステムのフェアトレード製品を買うことで、生産者の応援や貧困解決、環境破壊撲滅につながります。
フェアトレード製品の見分け方は上記のフェアトレードマークが製品に付いていることです。
コーヒー、スパイス、チョコレート、ナッツ、フルーツ、野菜のほか、オーガニックコットンなど日用品が見つかります。
探求授業のまとめ方例
- 世界の生産者がどのような環境で働いているのかを調べる
- フェアトレードについて調べる
- 身の回りにあるフェアトレード製品を探してまとめる
まとめ
今回は、目標別に探求授業のテーマとなりそうな内容をご紹介しました。
身近なところにテーマは転がっています。ぜひ何か気になったことがあれば、それが地球や人にどのような影響を与えているのかを考えてみてはいかがでしょうか。
参考文献
(※1)https://www.sdgs-japan.net/single-post/sdsnreport2023
(※2)参考:国連広報センター
(※3)parkrun Japanより
(※4)朝日新聞 「個性として前向きに」 性的少数者が高校生を前に講演より
(※5)参考:西東京市
(※6)ジェトロ 北海道大学発AIスタートアップがバングラデシュに開発拠点を設立
(※7)北海道で暮らそう
この記事を書いた人
スペースシップアース編集部 ライター
スペースシップアース編集部です!
スペースシップアース編集部です!