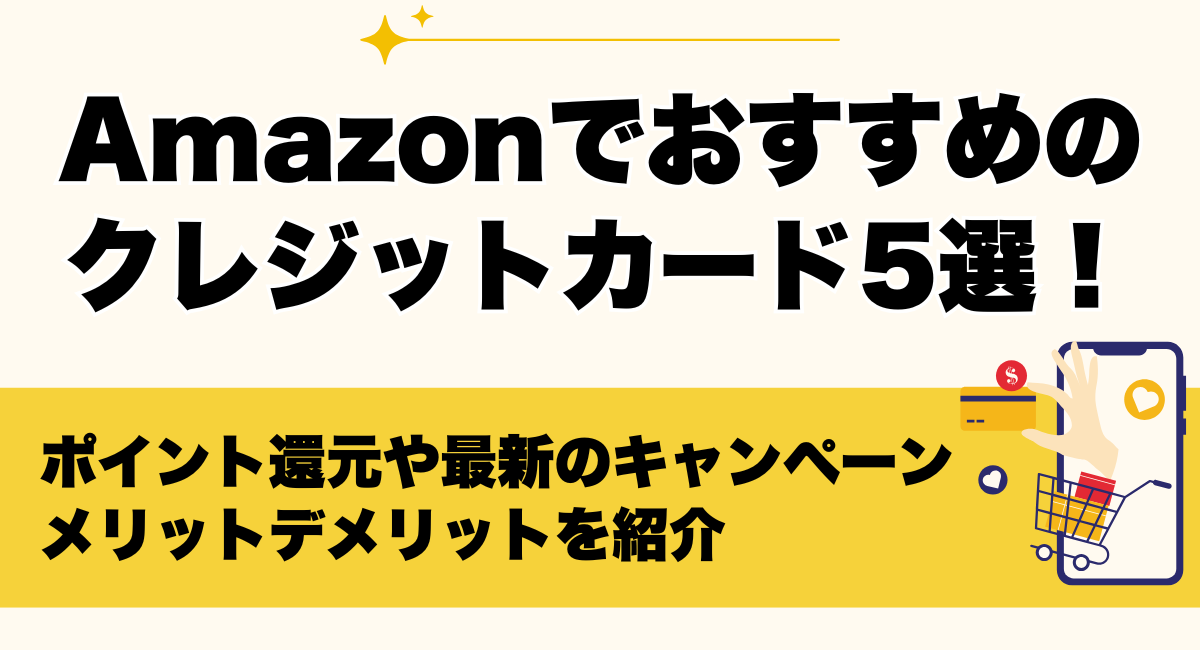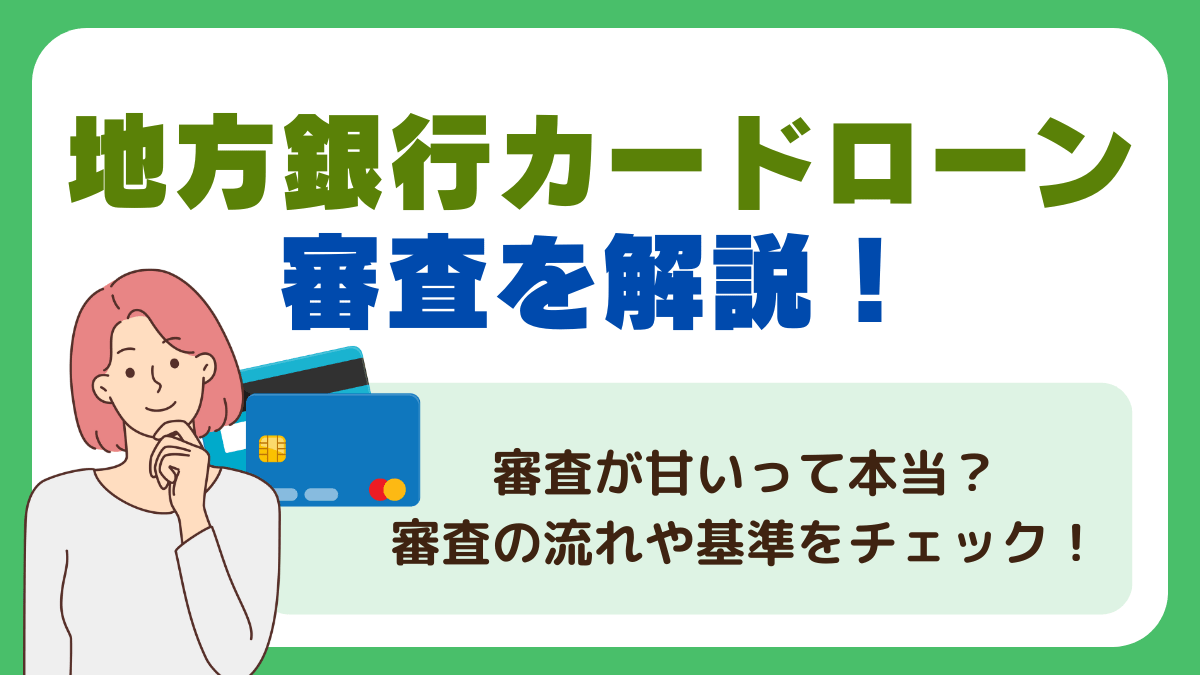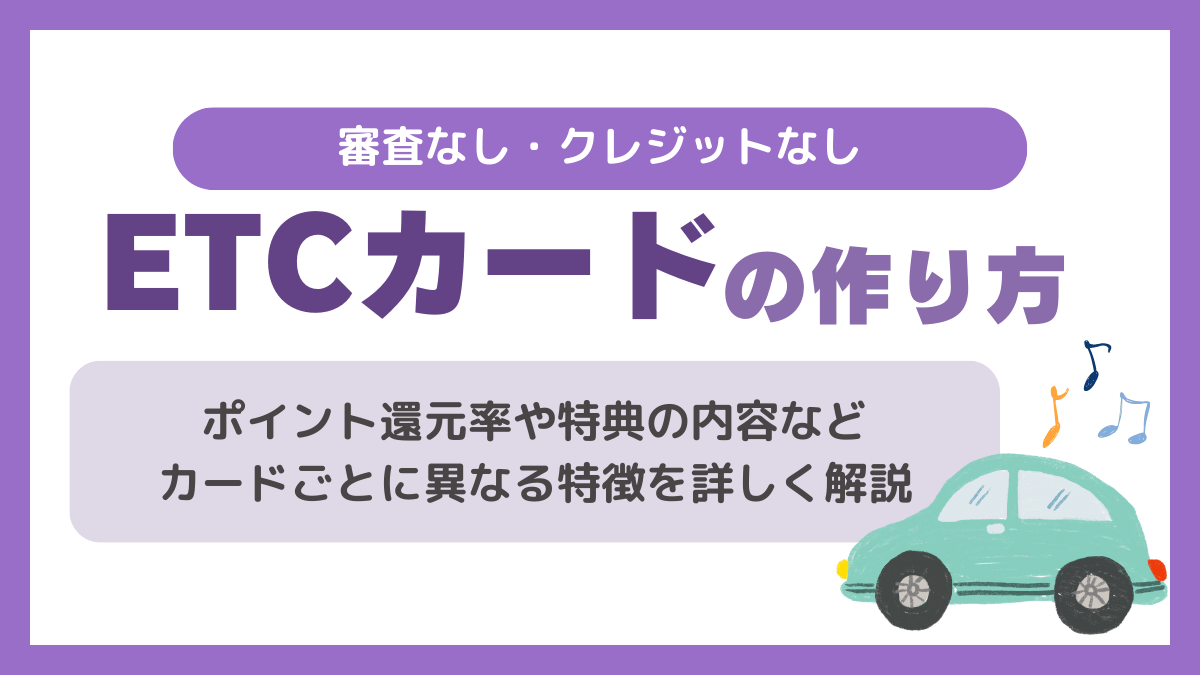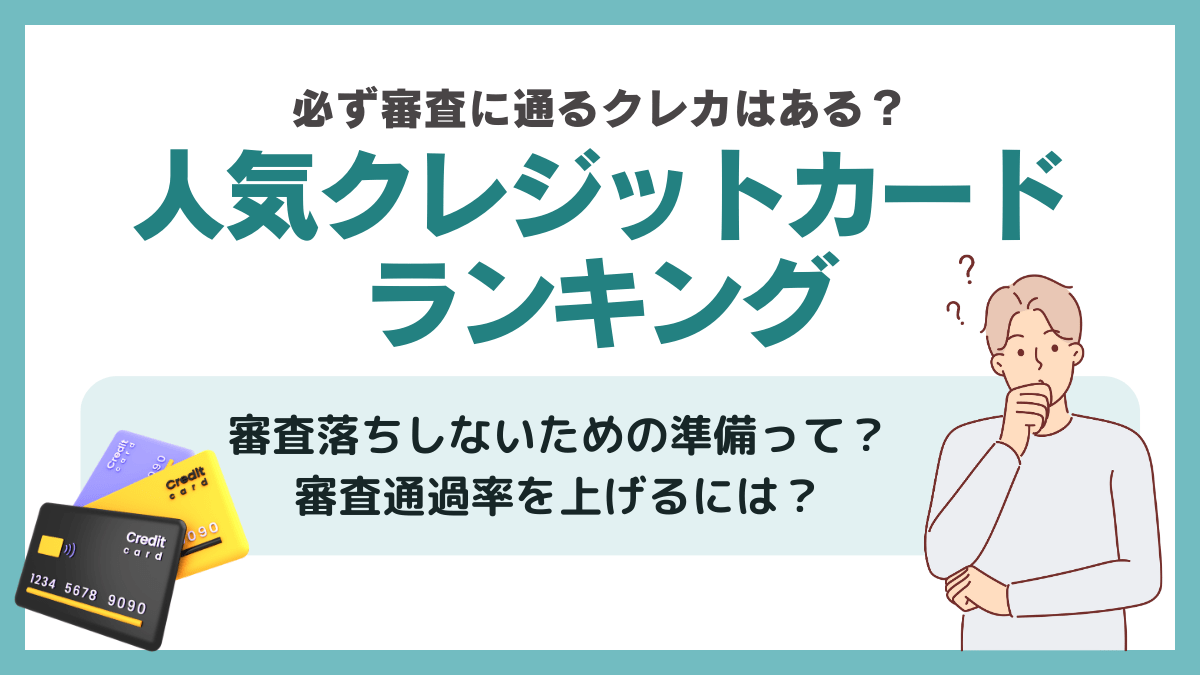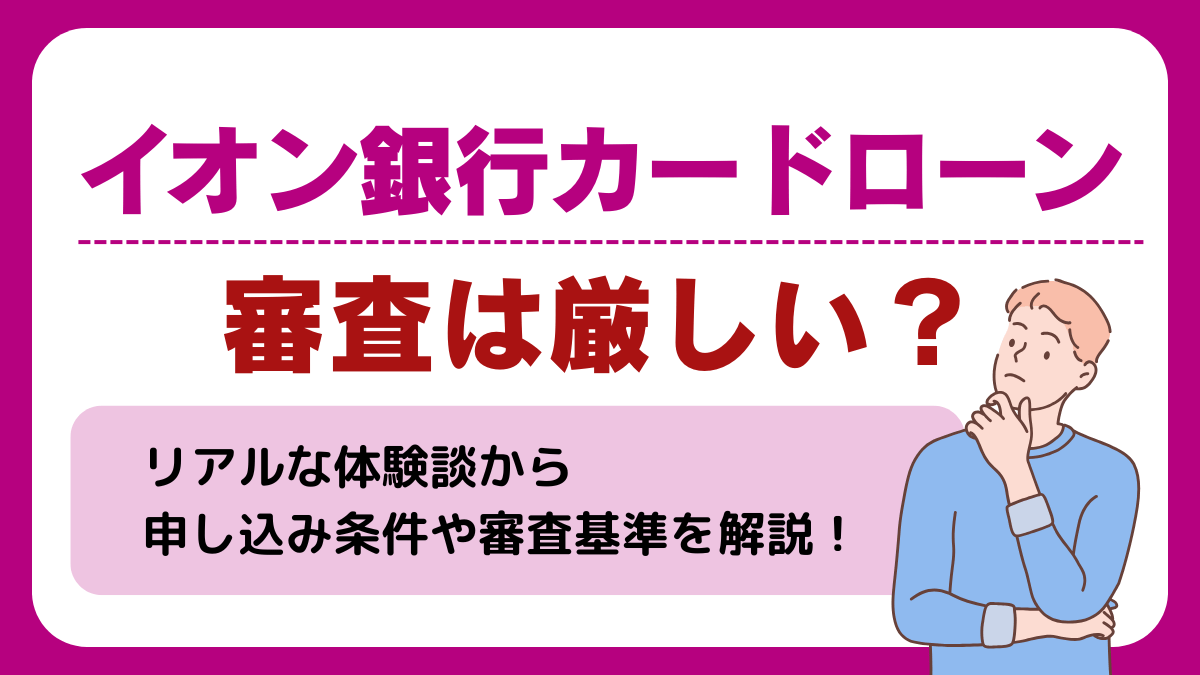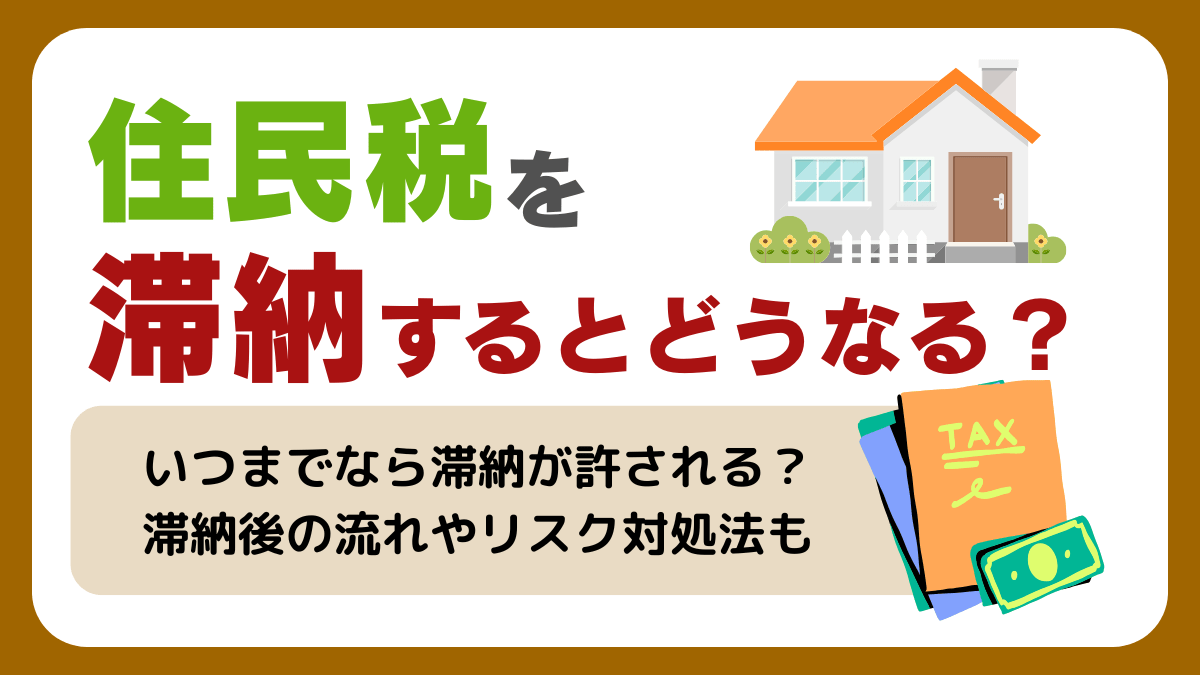私たちの生活にお金は欠かせません。銀行預金はもちろん、証券投資、はたまた近年話題のフィンテックサービスまで、その仕組みは複雑化しています。では、私たちの大切な資産を守る「番人」は誰なのでしょうか?
その答えは、2000年に設立された「金融庁」です。金融庁は、銀行や証券会社などの金融機関がルールを守って健全に業務を行うよう、日々監視しています。近年問題となっているマネーロンダリング対策や、私たちの資産を守るための金融トラブル・詐欺に関する注意喚起なども行っています。
金融庁の仕事は、一見、私たちの日常生活と無関係に思えるかもしれません。しかし実際には、私たちの預金や投資を守るために、そして、安全で便利な金融サービスを安心して利用できるように、金融庁は重要な役割を担っているのです。
今回は、金融庁の仕事内容や財務省との違い、SDGsとの関わりについて解説します。
目次
金融庁とは

金融庁とは、日本の金融行政を一元的に担当する行政機関として2000年に設立されました。大蔵省(現在の財務相)から分離して設立され、英語では「Financial Services Agency(FSA)」と表記されます*1)。
金融庁が設置された目的
金融庁の設置目的は以下の3点です。
- 日本の金融システムの安定性確保
- 預金者や投資家などの保護
- 市場の公正性・透明性の維持
具体的な活動としては、銀行や証券会社、保険会社などの金融機関の監督・検査を実施し、金融機関が適切な業務を行っているか監視しています。
金融監督庁との違い
金融監督庁は1998年6月に設立された総理府の外局です。この機関が設置される以前は、大蔵省が金融に関する行政業務を一手に担っていました。しかし、住専問題への対応をめぐって大蔵省への批判が高まり、金融行政の改革が求められるようになりました。
その結果、大蔵省から証券取引等の監視、金融機関への検査や監督といった機能が分離され、新たに金融監督庁として独立することになったのです。これにより、従来大蔵省が担当していた金融行政の監督業務は、金融監督庁へと移管されることになりました。
一方、金融庁は内閣府の外局として2000年7月に発足した組織です。これまでの金融監督庁に加え、大蔵省金融企画局が統合して金融庁となりました。これにより、金融庁は金融制度の企画・立案から監視まで大きな権限を持つ組織となったのです*3)。
金融庁の仕事内容

金融庁の仕事は、金融制度ルール作り、銀行などの金融機関に対する検査・監督、株取引の監視の3つです。それぞれの仕事内容を見てみましょう。
金融制度のルール作り
金融庁による金融制度のルール作りは、日本の金融システムの安定性と健全性を確保するための重要な取り組みです。具体的には、銀行法、金融商品取引法、保険業法などの法律の制定や改正を通じて、金融機関の業務範囲や行為規制を定めています。
2019年の資金決済法の改正では、暗号資産(仮想通貨)取引に関する規制を整備し、利用者保護の強化を図りました*4)。
金融庁は、金融機関が守るべき法律の制定や、より具体的なルールを作るなどをしています。最近話題のフィンテックなど、新しい技術が登場しても対応できるように、常に最新の状態に対応できるよう、アップデートしています。
金融機関の検査・監督
金融庁は、銀行や証券会社などの金融機関がきちんと法律やルールを守って仕事をしているかを確認するために、「検査」と「監督」という方法を使っています。
検査は、金融庁の検査官が金融機関に直接出かけて行って、書類をチェックしたり、担当者に話を聞いたりして詳しく調査することです。一方、監督は、金融機関から定期的に提出される報告書などを基に、日頃から金融機関の仕事ぶりをチェックすることです*6)。
検査と監督はどちらも金融機関が健全に業務を行うために欠かせないもので、金融庁はこれらを組み合わせることで、金融システム全体の安定を図っています。
証券取引等監視委員会の活動
金融庁の下にある証券取引等監視委員会は、1992年に発生した証券会社の損失補てん事件を契機に、健全な市場の維持を目的として設立されました。主な役割は、株価操縦やインサイダー取引といった不正取引、上場企業による粉飾決算など、市場の公正性を脅かす行為を監視することです*7)。
金融庁の仕事の進め方

金融庁には総務企画局や検査局、監督局などがあり、分担して仕事をしています。ここでは、金融庁の各部署が行っている仕事について、簡単にまとめます。
総合政策局
総合政策局は、日本の金融に関する重要な決定や計画を立てる部署です。銀行やクレジットカード会社など、お金に関わる機関が安全に運営されているかを見守り、問題が起きないようチェックしています。
また、スマホ決済など新しい金融サービスへの対応や、不正なお金の動きを防ぐ対策も行っています。さらに、海外の金融機関とも協力して、世界の金融システムの安定に貢献しています*8)。
企画市場局
企画市場局は、私たちの暮らしに関わる金融の仕組みを作る重要な部署です。銀行や証券会社が守るべきルールを決めたり、一般の人々が安心してお金を貯金や投資に回せる環境を整えたりする仕事をしています。
また、会社がスムーズにお金を集められるように、株式市場などの制度も整備しています。最近では、スマホなどを使った新しい金融サービスにも対応できるよう、様々な人の意見を聞きながら時代に合わせたルール作りを進めています。
監督局
監督局は、銀行や証券会社などの金融機関を常に観察し、問題がないか確認するとともに、必要に応じて改善を求めたり、アドバイスを行ったりしています。同時に、金融機関が法律やルールを守っているかを確認し、預金者や投資家の利益を守りながら、日本の経済が健全に発展するよう支援しています。
証券取引等監視委員会
証券取引等監視委員会は、金融庁の中で、株式市場の不正を監視する専門機関です。株価操作やインサイダー取引といった違法行為を見つけ出し、市場の公平性を守ることで一般の投資家を保護しています。
具体的には、証券会社への立ち入り検査や、怪しい取引の調査を行い、違反を見つけた場合は罰金や業務停止などの処分を金融庁に提案します。
私たちと金融庁の関わり

一見、金融庁の仕事は私たちの日常生活とは無縁に思えるかもしれません。しかし、その業務内容を詳しく見ていくと、実は私たちの生活と密接に関わっていることが分かります。ここでは、金融庁の仕事の中でも、特に私たちの暮らしに深く関わっている側面について、分かりやすく説明します。
消費者金融のルール作り
消費者金融のルールを作るのは、金融庁の重要な仕事の一つです。お金を借りる手段として、消費者金融は身近な存在ですが、過去にはその利用が原因で、多くの人が複数の借金を抱える多重債務が社会問題となりました。
この問題を深刻に受け止めた金融庁は、2010年6月に改正資金業法を施行し、貸金業者に対する新たなルールを定めました。この法改正により、貸金業者はより責任ある貸し付けを行うことが求められるようになり、利用者の借金問題の発生防止が期待されています。
金融トラブルや詐欺への注意喚起
金融庁は、私たちを金融トラブルや詐欺から守るため、さまざまな注意喚起を行っています。主な注意喚起は以下の通りです。
- 金融庁や銀行などを装った詐欺に関する注意喚起
- 詐欺的な投資に関する注意喚起
- 災害などに便乗した詐欺に対する注意喚起
- 預金に関する注意喚起
- 借り入れに関する注意喚起
- 保険に関する注意喚起
- 暗号資産(仮想通貨)に関する注意喚起
出典:金融庁*10)
例えば、SNSやマッチングアプリなどで知り合った人や、実在する著名な人物を装って投資話を持ちかけるという、巧妙な手口の詐欺について紹介しています。
さらに、インターネットバンキングを悪用した預金の不正送金や、身に覚えのないキャッシュレス決済サービスからの不正出金といった、近年増加している金融犯罪の事例もわかりやすく解説しています。
また、お金を借りるときに注意すべき点や、成人年齢が18歳に引き下げられたことで若者が注意すべき金融トラブルについても触れています。これらは、お金に関する知識と危機管理意識を高める上で非常に役立つ内容となっています。
マネーロンダリング対策
犯罪者が不正なお金を隠すために、一見、普通の収入のように見せかける行為を「マネーロンダリング」と言います*11)。金融庁は、銀行や証券会社など、お金を扱う会社に対して、マネーロンダリングを防ぐための対策をしっかりとるように指導しています。
例えば、高額なお金の出し入れや、短期間に何度も取引を繰り返すような場合には、それが本当に本人による正当なものかどうかを確認することが求められます。これは、犯罪者が不正なお金を使えなくするため、そして安全な社会を作るために、とても大切なことです。
NISAの管轄
NISAは、個人投資家の資産形成をサポートするための税制優遇制度で、日本語では「少額投資非課税制度」といいます。金融庁はNISAに関する特設ウェブサイトを解説し、その仕組みや基本的な内容についてわかりやすく解説しています。
【補足】金融庁と財務省の違い

金融庁は、もともと財務相の前身である大蔵省に属していた「金融監督庁」を母体としています。しかし、今は財務省ではなく内閣府に所属する機関となっています。ここでは、金融庁と財務相の違いについて説明します。
財務省とは
財務省は、国のお金に関することを総合的に管理している行政機関です。私たちの生活に密接に関わる税金の制度を考えたり、国の予算をどのように使うかを計画したりする役割を担っています。
また、財務省は税関も管理しており、海外との貿易や出入国の際の検査も行っています。さらに、日本のお金(通貨)を発行する造幣局の運営や、外国とのお金のやり取り(為替)に関する政策も担当しています*12)。
2001年までは大蔵省という名前でしたが、省庁改革により現在の財務省となりました。財務省の下には、税金の徴収や確定申告の受付などを行う国税庁があります。
金融庁と財務相の比較表
金融庁と財務省の違いについて表でまとめてみました。
| 項目 | 金融庁 | 財務相 |
| 設立 | 2000年 | 2001年(旧大蔵省から改組) |
| 位置づけ | 内閣府の外局 | 独立した省 |
| 役割 | 金融システムの安定金融機関の監督 | 国の財政管理 |
| 主な業務 | 金融機関の検査・監督金融制度の企画・立案証券取引の監視金融商品の規制 | 国の予算編成税制の立案国債の管理 |
両者を比較すると、金融庁が金融や証券に特化していることがわかります。財務省の仕事は国の予算管理や税制の立案であることから、両者の役割が異なることがわかるでしょう。
金融庁とSDGs

金融庁は、「サステナブルファイナンス」と密接なかかわりを持っています。ここでは、金融庁がサステナブルファイナンスやSDGs目標17と、どのように関わっているかについて解説します。
SDGs目標17との関わり:サステナブルファイナンスへの取り組み
金融庁は、SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」の実現とサステナブルファイナンスの推進において重要な役割を果たしています。サステナブルファイナンスは、持続可能な社会を実現するための金融的な仕組みのことです。
金融庁の具体的活動は、以下の通りです。
- サステナブルファイナンス有識者会議の設置
- ESG評価機関等の行動規範の策定
- グリーンウォッシュ対策としてのESG投資信託の監督指針の策定
- 脱炭素に関わる取り組み
出典:金融庁*13)
※グリーンウォッシュ
商品やサービスが、あたかも環境に配慮しているかのよう見せかけて消費者をごまかしていること*14)。
このように、金融庁はサステナブルファイナンスの仕組みづくりで大きな役割を果たし、グリーンウオッシュのようなごまかしを防ぐ活動をしているのです。
まとめ
今回は、金融庁について解説しました。金融庁は、日本の金融システムの安定と健全性を維持するために、多岐にわたる役割を担っています。金融機関の検査・監督、金融制度の企画・立案、証券取引の監視などを通じて、預金者や投資家を保護し、公正な市場を維持することに努めています。
近年では、フィンテックやサステナブルファイナンスといった新たな分野への対応も進めており、SDGsにも関与するなど、金融庁の役割はますます重要性を増しています。
金融庁の活動は、私たちの生活や経済活動と密接に関わっており、その役割を理解することは、安全で安定した金融環境を維持するために不可欠です。
参考
*1)日本大百科全書(ニッポニカ)「金融庁」
*2)百科事典マイペディア「住専問題」
*3)百科事典マイペディア「金融監督庁」
*4)金融庁「資金決済法等の改正法の解説」
*5)共同通信ニュース用語解説「フィンテック」
*6)金融庁「子ども向けパンフレット」
*7)共同通信ニュース用語解説「証券取引等監視委員会」
*8)金融庁「金融庁パンフレット」
*9)デジタル大辞泉「多重債務」
*10)金融庁「金融庁からのお願い・注意喚起」
*11)デジタル大辞泉「マネーロンダリング」
*12)金融庁「NISAを知る」
*13)デジタル大辞泉「財務相」
*14)デジタル大辞泉「グリーンウォッシュ」
この記事を書いた人
馬場正裕 ライター
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。