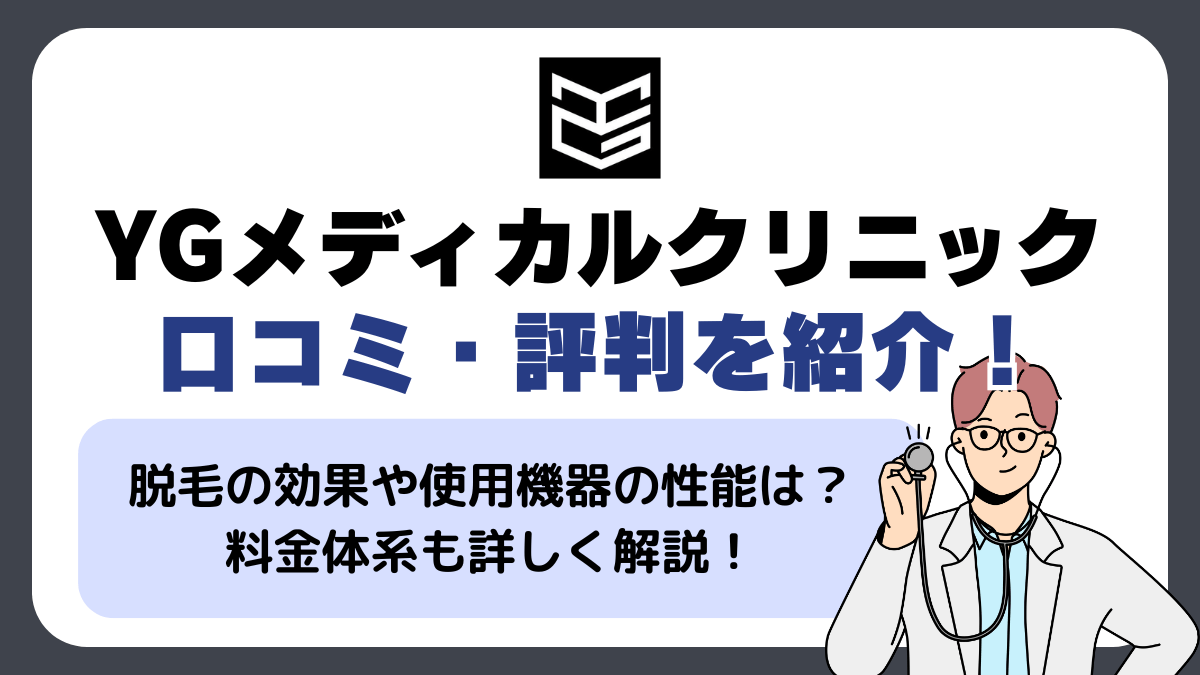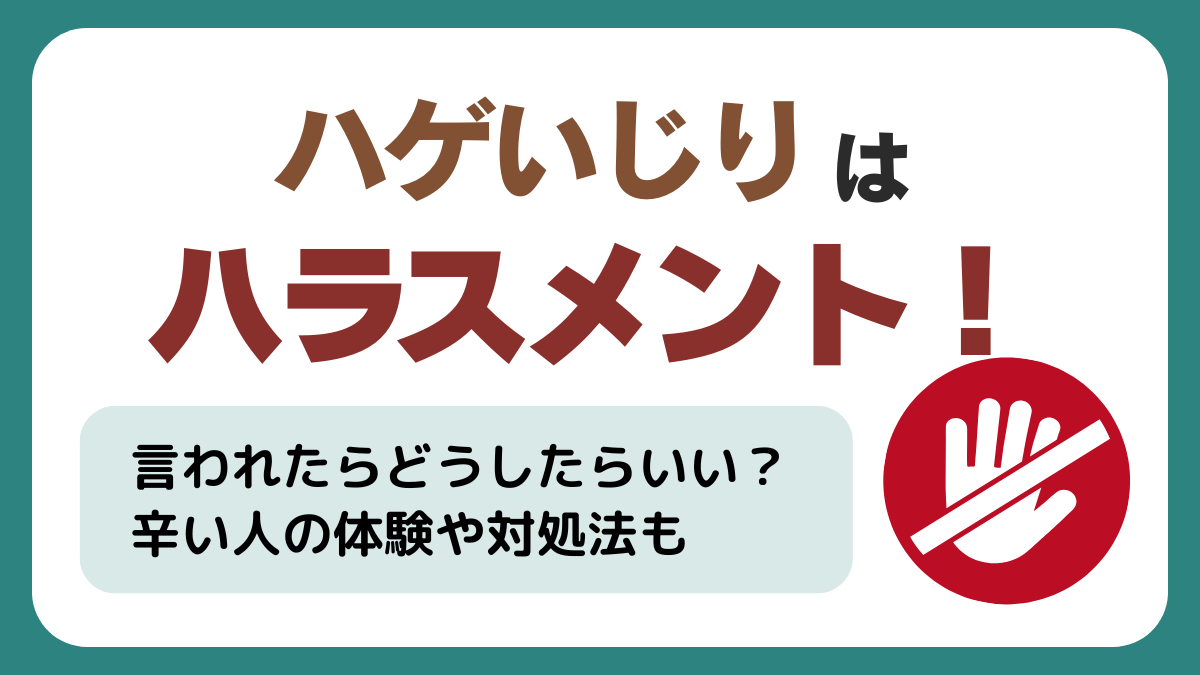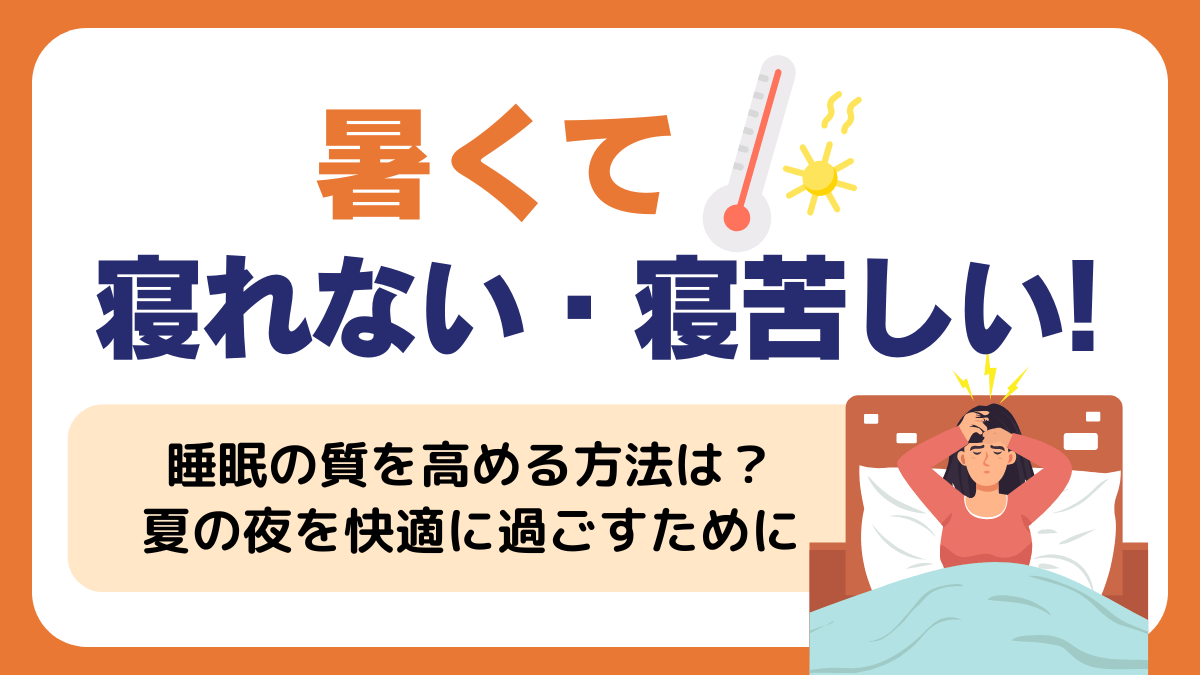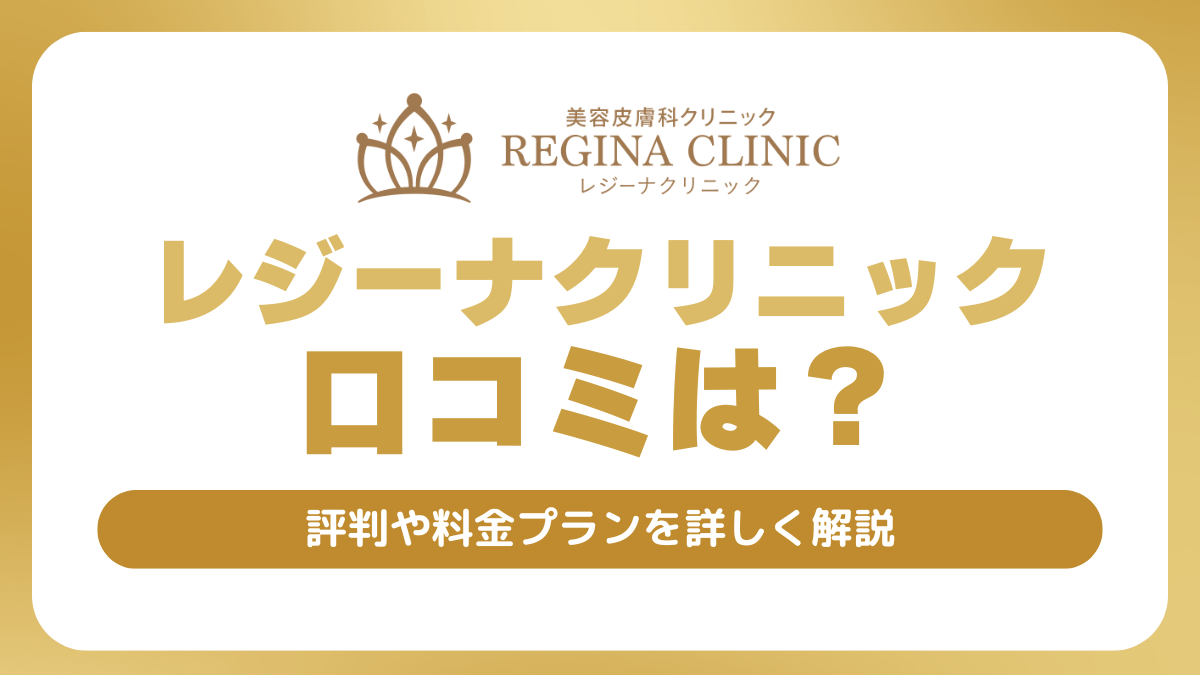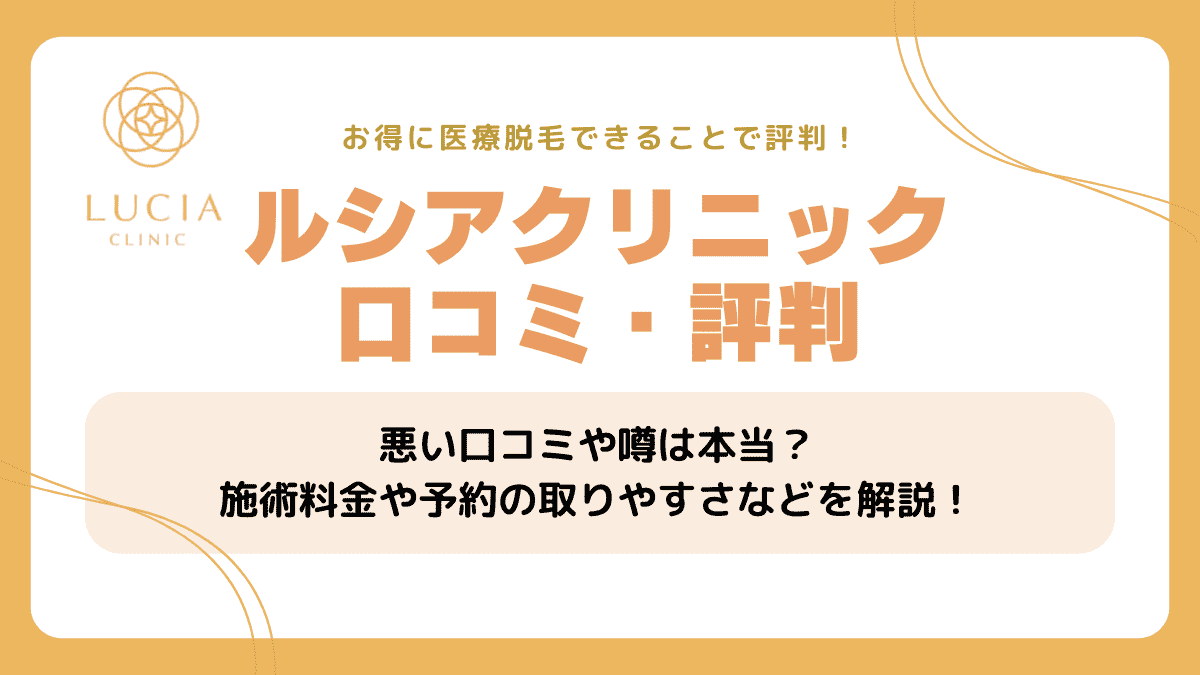優秀な人材の確保、貴重な人材の離職・流出防止、効果的な人材育成や公正な人事評価…。今や日本中の企業で、人事や人材にまつわる悩みは尽きることがありません。その背景には従来までの日本型人事の限界が指摘されており、労使双方にとっても持続可能な働き方が危ぶまれています。
こうした状況を解決する手段として期待されているのがHRテックと呼ばれる技術です。
本記事では、近年注目を集めるHRテックについて、注目される背景や基幹となる技術、取り組み事例などについて紹介していきます。
目次
HRテックとは

HRテックとはHuman Resources(人的資源)とテクノロジーの造語であり、人事に関する業務全般をIT化する技術やサービスのことを言います。
具体的には、従業員や求職者などに関する詳細なデータに基づき、採用活動や人材育成、人事評価から労務管理に至るまで、人事領域の業務全般を効率化、精緻化、高度化するためのIT技術です。
それによって、会社や組織における人事が抱える課題を解決し、個々の人材が持つ能力を最大限に発揮できるようにすることがHRテックの目的です。
HRテック関連の市場規模は現在急激に伸びており、ほんの10年ほど前には100億円にも満たなかったものが、2021年には578億円に達しています。この増加傾向は今後も続くと予想され、2024年には1,700億円、2026年には2,270億円に到達するという予測も出ています。
HRテックはどのような領域で活躍するのか

HRテックは人事関連の業務全般をカバーしており、その範囲は非常に幅広いことがわかります。
具体的な例をあげながら、HRテックが活躍する領域を見ていきましょう。
人材採用・配置
人材採用は、ここ数年でHRテックの導入が急速に進んだ分野です。
それぞれの分野で具体的な業務をあげると
- 求人:採用ホームページや求人サイトの制作、各種検索エンジンやSNSとの連携
- 採用:オンライン面接やAI面接、採用適性検査
- 配置:採用後適性検査、配置提案
などがあります。
近年のHRテックでは、ものの数時間で採用ページが作れる機能が備わるものもあり、大手総合求人サイトや検索エンジンとの連携も容易になっています。
採用面ではコロナ禍の影響もあり、会社説明会や面接のオンライン化はすっかり一般化しました。さらに面接にAIを導入することで、面接官ごとのスキルや性格のばらつきを防ぐことができるほか、応募者の表情や動作の変化を察知するのにも役立ちます。
こうした応募時や面接、適性検査でのデータを元に、入社後の配置部署の提案だけでなく、任意の人や組織との相性を測定することも可能です。
定着と教育
採用した人材をいかに定着させ、教育していくかは、常に人事における最重要課題です。
特に日本の企業では社員エンゲージメント(会社への信頼や仕事へのやる気の度合い)が他の国より低く、人事のミスマッチやモチベーションの低下などを理由にした離職の増加も深刻です。
こうした状況を食い止めるため、HRテックがこの領域で果たす役割も大きくなっています。
具体的には
- パルスサーベイ(社員満足度調査)
- e-ラーニングやオンライン教育
といった手法があります。
社員の意欲や満足度を測るパルスサーベイは、短時間の設問を定期的に行う手法が特徴です。
ここで得られたデータを元に、上司は社員との面談を適切なタイミングで行うことができるようになります。
e-ラーニングやオンライン教育は、既に導入している企業も多いでしょう。さらに現在のHRテックでは、大量の人材育成に役立つコンテンツをサブスク形式でいつでも視聴できるようになっているだけでなく、自社オリジナルコンテンツの追加やスマホ対応も可能になっています。
人事評価

人事評価は企業にとって大きな課題であり関心事であり、この分野でのHRテック導入は特に大きな注目を集めています。
サービスによっては人事評価のワークフローの効率化、多彩な評価方法への対応、自社の既存の手法を併用できるカスタマイズ性の高さなどで、非常に簡単かつ安価な人事評価システムを構築することが可能です。
また、評価データの分析を適切に活用することで、クオリティの高い人事評価面談を行うこともできるようになります。
ただし、人事評価のHRテックの導入は、評価基準を明確にしにくい日本の企業にとってはハードルが高いと感じられるケースも少なくありません。アナログベースに基づいた人事評価制度をどのようにHRテックに落とし込めるかが、導入成功のカギと言えるでしょう。
労務管理
労務管理はHRテックとはあまりなじみがないように思われるかもしれません。
しかし、労務もまた人を対象にする業務であり、さらにこれからは、多様な人材の多様な働き方を適切に管理する必要が生じてきます。その意味で、労務管理の重要性とHRテック導入の必要性はますます高まっています。
労務管理でのHRテックで代表的なものは
- 勤怠管理
- 給与計算
- 人事管理(社内の諸手続き)
です。
出退勤がスマホやPCでどこでもできる勤怠管理システムは、修正や有給休暇の申請もオンラインで可能にします。また、変形労働時間やシフト勤務など多様な勤務形態への対応も容易です。
その勤怠管理システムのデータと従業員情報を使えば、給与や各種控除額、残業代の計算も自動的に行われ、確実で迅速な給与計算ができるようになります。
給与計算のために担当者がタイムカードを回収し、給与ソフトに手入力でといった手間や時間のロス、人的ミスといった事態は、これによって大幅に解消されます。
HRテックが注目されるようになった背景

組織の人事業務においてこうしたHRテックが注目され、必要とされている背景には、以下のような要因があります。
背景①労働力不足を見据えた人事戦略の転換
大きな要因のひとつは、少子高齢化による労働人口の減少によって、深刻な人手不足に悩む企業が増えている現状です。それによって多くの企業では人事戦略を大きく見直す時期に来ています。
現在は宿泊や飲食サービス、運輸・郵便、製造業など多くの分野での人手不足が続いており、この流れは今後も避けられません。それに加えて
- 高い離職率とかさむ採用コスト
- 低い労働生産性
- グローバル化や業界構造の変化
など、人事を取り巻く課題は山積しています。
特に離職率の高さや労働生産性の低さは、人事関連業務が決してうまく機能していないこととも関連づけられるでしょう。その背景には
- 個人の適性・性格と業務とのミスマッチを起こす人員配置
- 従業員の不満や意欲の低下を見極められない
- 人によって能力や意欲、仕事の進め方にばらつきがあり、生産性が上がらない
などの問題があり、どれも人材の活用方法に原因があることがわかります。
こうした課題を解決し、全ての人材を有効に活用しなければ日本の産業に未来はありません。そのため、あらゆる分野でHRテックによる科学的な人事システムの構築が求められています。
背景②人事業務の多様化・複雑化

もうひとつの背景には、社会的環境や雇用環境の変化に伴う、人事業務の多様化や複雑化があります。中でも大きな要因が
- 働き方改革の推進
- 新型コロナウイルスの感染拡大によるテレワークの推進
の2つです。
2019年から政府が打ち出した働き方改革も、労働力の減少による国力低下への危機感が背景にあります。その内容は
- 働き方や雇用形態にとらわれない多様な働き方
- ジョブ型雇用
- 正規と非正規雇用の格差是正
- 女性や高齢者の活用
などの推進が主な目標です。
しかし実際の現場では、データや科学的分析に基づかない、非効率で属人的な人事管理がいまだに色濃く残っており、特に女性の採用や育成の面で大きく遅れをとっています。
ジョブ型雇用の導入が進まない現状もまた、科学的なデータによる業務や人材の分析ができない今の日本型人事業務の特徴と言えるでしょう。
その中で新型コロナウイルスのパンデミックは、こうした仕事の進め方に否応なく変化を迫りました。
時間や勤務場所を制限しないテレワークや在宅勤務は、それまでの労務管理や人事評価システムからの転換を促し、採用活動でのオンライン化も前述の通り一般化しています。こうした変化もまた、HRテックの普及を促す要因となっています。
背景③テクノロジーの発達による業務サポートシステムの進歩
テクノロジーの発達もまたHRテックの普及に拍車をかける要因となっています。
個々の技術については次の章で詳しく説明していきますが、インターネット技術の発展に伴い、大量のビッグデータを収集し解析することが容易になりました。
またクラウド・コンピューティングの発達と、その技術を活用したSaaSなどのサービスなどにより、かつては複雑で高価だったデータ分析を、誰もが手軽に活用できるようになっています。
現在では急速に進歩するAIがあらゆる業務へ導入され、劇的な生産性向上に貢献することが期待されています。こうした技術を取り入れた、使いやすく効率的な人事業務サポートシステムが多数開発されてきたことも、HRテックが注目される背景です。
HRテックと関連するテクノロジーについて

この章では、HRテックを支えるテクノロジーについて説明していきましょう。
①クラウド・コンピューティングとSaaS
クラウド・コンピューティング(クラウド)についてはもはや説明の必要がないでしょう。
これはユーザーが自前のサーバーや業務システムを構築する代わりに、各種サービス事業者がインターネットなどのネットワーク上で提供する機能を利用する仕組みです。
代表的なサービスとしては
- Google(と、そこで提供される多くのサービス)
- Microsoft Azure
- Netflixなどの動画配信サービス
などがあり、インターネット上で展開されているほとんどのサービスがクラウドをベースに提供されていると言っても過言ではありません。
この技術を利用してネット上でソフトウェアとしてのサービスを提供する仕組みがSaaS(Service as a Software)です。
これによって私たちユーザーはPC1台すら必要とせず、いつでもどこでもさまざまなサービスを利用することができます。HRテックについても、人事業務をクラウド上で管理できるシステムが多数開発され、利用者はスマホからでもシステムにアクセスして必要な業務が行えます。
②RPA
RPA(Robotic Process Automation)は、人間がパソコン上で行うような日常的な作業を自動化するというものです。
特徴としては
- 設定されたプロセスを設定された通りに実行し、繰り返し型の定型作業が自動化できる
- プログラミングの素養がなくても直感的に設定でき、負担が少なく自動化できる
- 複数のシステムやアプリケーションと連動しているので煩雑な作業切り替えが不要
などがあり、別システムのデータを参照したデータ入力や照合、エクスポートなどの他、給与計算や勤怠管理など、比較的ルーティン作業の多い業務で大きな効果を発揮します。
③AI(人工知能)

近年飛躍的な進化が進むAI(人工知能)は、機械が人間の知的作業を模倣する技術です。AIの基盤となるのは膨大なビッグデータを活用したディープラーニングという機械学習技術であり、自然言語処理や画像処理に優れた生成AIは私たちの生活にすっかり定着しました。
AI技術はさまざまな産業でも応用されており
- 工場生産ラインをリアルタイムでモニタリングするセンサー
- 画像認識で微細な欠陥を検出する製品の品質管理
- 過去の売上データや市場のトレンドで未来予測や戦略策定を行うデータ分析ツール
などの、多岐にわたる分野で活躍しています。
HRテックでも、飛躍的に進歩したAIの役割は不可欠と言っていいでしょう。その主なものとして
- AIによる、またはAIを取り入れた採用面
- 面接時のデータに基づいた入社後の適切な人員配置を分析
- 社員のモチベーションをリアルタイムで可視化
などの業務で取り入れられています。
HRテックに取り組む企業

日本でも現在多くの企業がHRテックを開発・提供し、その技術を導入することで効果的な人事業務を行なっている企業も増えています。ここではHRテックに取り組む企業の事例を紹介していきたいと思います。
提供側①カオナビ(株式会社カオナビ)
カオナビは、採用後の人材配置、人材育成、評価、モチベーション管理など、幅広い人事業務をカバーするシステムを展開しています。
メイン商品となるカオナビは
- 3,600社の人事ノウハウを蓄積・共有したシステムの活用や改善
- 誰でも使いやすく柔軟なカスタマイズが可能な直感的なUI/UX
- クライアントへの専任サポート体制やユーザーコミュニティの充実
- 外部サービスとの連携や必要な機能の追加が可能で無駄のないシステム構築
などの特徴を備えており、2024年現在、3,600社を超える企業や自治体などで採用されています。
提供側②タレントパレット(株式会社プラスアルファ・コンサルティング)
タレントパレットは、あらゆる人材データの一元化による「科学的人事」を実践することで、人事業務の効率化や人事戦略の意思決定の高度化、人材育成、最適な人材配置、離職防止、採用強化などの実現を進めるシステムです。同社では、かつて社員のモチベーションの低下や変化に気づかずに多くの離職者を出してしまった自社の苦い経験を元に、徹底したマーケティング思考やテキストマイニングなどの分析技術を取り入れています。
タレントパレットの主な機能としては
- 人材データベース:スキル・経歴・評価や役職、年次などあらゆる要素をデータ化。顔写真の併用でプロフィールの確認も容易
- 人材データ分析:部署や評価など自由な分析軸で条件ごとの全体像を直感的に把握可能
- 人的資本ダッシュボード:人的資本の開示にいち早く対応。顧客に合った人的資本ダッシュボードを作れる独自の指標設定ができる
- 労務管理システム:抜け漏れのない自動入力チェック機能や強固なセキュリティ対策
などがあり、データ分析の精緻さに定評があります。タレントパレットはこうしたさまざまな機能が評価され、国内の多くの大手企業で採用されています。
提供側③freee人事労務(freee株式会社)
freee人事労務は、主に中小企業や個人事業主の労務管理業務に特化したHRテックシステムです。
勤怠管理や給与計算、年末調整やWeb社員台帳などの従業員管理、法定三帳簿の自動作成、マイナンバー管理など、労務管理に必要な機能が過不足なく備わっており、クラウドや多様な働き方にも対応しています。freee人事労務の特徴としては
- 導入のしやすさ:初期費用0円、最低月額1,980円〜
- 使いやすさ:個人事業主でも使えるよう設計され、Webマニュアルも完備
- 管理のしやすさ:シンプルな機能や見た目で専任者でなくても使いやすい
などがあります。クラウド給与計算システムとしては40%以上の国内シェアを誇り、導入実績も申し分ありません。
導入側①エイチームウェルネス
エイチームウェルネスは、エイジングケアコスメを中心に、ウェルネスサービスを展開する名古屋の会社です。同社で新卒採用のために導入したHRツールが、ミライセルフ社が提供する適性検査ツール「mitsucari」です。機械学習AIを採用したmitsucariは、72問の質問で14項目の志向性が検査できます。
エイチームウェルネスではこの適性検査結果を参考に採用のミスマッチを減らすだけでなく、社内のメンバー同士でも共有できるようにしています。メンバーがお互いに相手がどんなタイプなのかを知ることによって、社内の組織力強化につなげたい、というのが同社の狙いです。
導入側②ソラスト
ソラストは、医療事務関連サービスの大手企業です。同社で社員の定着率を高めるために導入したのが、AIによるデータ解析ツール「KIBIT」(フロンテオ社)です。
ソラストでは年間5,000人もの入社1年目の社員と複数の面談を行い、コミュニケーションシートに記入してもらった回答をKIBITに読み込ませてデータを数値化し、解析を行いました。ここで離職可能性が高いと判断された社員に対しては、フォロー面談や配置・勤務時間の変更を行うなどの体制改善を行い、離職の防止に効果をあげています。
導入側③近畿大学
5,500人の教職員を抱える近畿大学では、多様な働き方をする教職員の働き方改革を進めるために、AI人事システム「HUE」(ワークスアプリケーションズ)を導入しました。
このシステムの特徴は、文書作成からメール、表計算、ファイル管理など社員が使うあらゆるソフトを統合し、そこで得られる情報を収集、分析することです。
大学では働き方や勤務時間、仕事の繁忙・閑散などが教職員ごとに異なることから、こうしたデータと人事データを併用し、個々の働き方やメンタルヘルスの状態、コミュニケーション状況を捉えることで、働き方改革への活用を目指しています。
HRテック活用に向けた課題

まだHRテックを導入していない企業でも、その必要性を理解し、導入したいと考えている企業は少なくないと思います。ここでは、導入にあたって留意するべきHRテックの課題について見ていきましょう。
課題①個人情報の取得
課題のひとつは従業員の個人情報をどう集め、どう扱うかです。インターネット上の応募者の情報を自動的に取得するようなHRテックのシステムでは
- 本人以外からの個人情報の取得に問題はないか
- AIによる人事評価の情報は「取得」とみなされるのか
- AIによる自動的な人事評価はどこまで許されるのか
といった問題にも留意する必要があります。また、あらゆる個人情報を取得されることによる反発や、AIに自分の評価をされることへの抵抗感も無視できません。
HRテック導入にあたっては、こうした不安や危惧をなくすためにデータ取得や利用の範囲、目的などをしっかり説明できるようにしておく必要があります。
課題②必要な情報(データ)の不足
もうひとつの課題は情報(データ)の不足です。これは、従来の日本企業でジョブ型人事を行なっている所が少なく、分析のモデルとなる客観的な事例や詳細なジョブ定義についてのデータが乏しいということです。これについては、地道なジョブ定義やスキル定義を進めつつ、ISO30414に基づく人的情報開示の活用を行うことも大事になってきます。
課題③デジタルに依存する人事評価
具体的な評価制度を導入していない、または導入歴が浅い中小企業などでは、闇雲にHRテックを導入しても効果が出ないことが少なくありません。
まずはアナログベースでの評価制度構築を念頭に置き
- 社員には何が求められ、何ができればいいのか、どのように判定されるかを見える化する
- 人事評価基準と運用ルールの構築方法を策定する
などの丁寧な評価制度を作るところから始めることが必要です。効率化や簡略化を求めるあまり、安易にデジタルに飛びつき、拙速にHRテックを進めないようにしましょう。
HRテックとSDGs
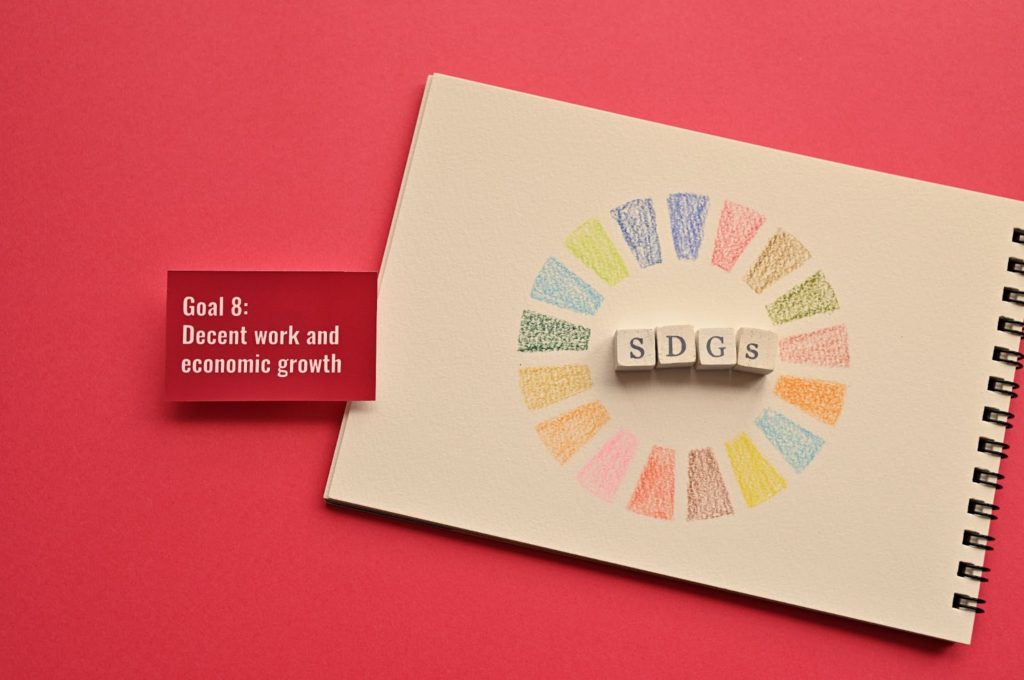
HRテックは、SDGs(持続可能な開発目標)とどのような関係があるのでしょうか。
まず、HRテックが注目された背景を思い返すと、労働力不足対策や働き方の改善があげられます。
そこから導かれる目的は「持続可能な働き方」です。
目標8「働きがいも経済成長も」
この目標では、「持続可能な経済成長とすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがい」が求められています。HRテックによってすべての人が適切で働きがいのある安定した雇用が得られ、自分の能力をフルに活用して高い生産性を上げることができれば、まさに働きがいと経済成長の両立がもたらされるでしょう。
目標3「すべての人に健康と福祉を」
HRテックがもたらすものには、仕事と生活の両立によるウェルビーイングの実現があります。
ウェルビーイングは身体的・精神的に加え、社会的にも良好な状態であることです。
HRテックの活用で、心身ともに無理がなく自分のパフォーマンスを発揮し続けることができれば、SDGsの目標にも掲げられている「Good Health and Well-being」にも繋がっていきます。
>>各目標に関する詳しい記事はこちらから
まとめ

すべての企業と労働者が雇用のミスマッチを解消し、働き手の能力を最大限に活用しようとするHRテックは、日本の労働力が減少し、働き手の確保が困難になりつつある時代には必須の技術といえます。同時に、私たち一人ひとりが真の「持続可能な働き方」を実現するためには、自分に適した働き方で高い生産性を得られ、やりがいのある環境のもとで働くことが不可欠です。
HRテックによって、その実現はより近いものになってくることでしょう。
参考文献・資料
これ1冊でわかる 中小企業のHRテック入門〜わが社でもできる! 導入から運用まで〜:森中謙介・町田耕一著:あさ出版,2022年
「科学的」人事の衝撃 HRテックで実現するマーケティング思考の人事戦略:三室克哉・鈴村賢治・中居隆著:東洋経済新報社,2019年
最新のHRテクノロジーを活用した 人的資本経営時代の持続可能な働き方:民岡良著:すばる社,2024年
HR Techとは?意味・定義 | IT用語集 | docomo business Watch | ドコモビジネス | NTTコミュニケーションズ 法人のお客さま
HRテック(HR Tech)とは?人事がいま知っておくべき知識と導入方法 | HR大学 (hrbrain.jp)
HRテックとは? 注目の理由や代表的なサービス、メリットを解説:朝日新聞SDGs ACTION! (asahi.com)
「HR Tech」とは?[注目ワード解説] (obc.co.jp)
クラウド、AIで人事管理 人事をIT化「HRテック」日経ビジネス:2016年10月31日号
SPECIAL REPORT 強い組織をつくる HRテック最前線 NIKKEI X TREND:2018年11月号
HRテック最前線 採用業務を変え、離職や法律違反を防ぐ NIKKEI COMPUTER 2022年4月2日号
クラウドコンピューティングの仕組みやメリット・デメリットを解説|NTT東日本
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション) 用語解説 | 野村総合研究所(NRI) – Nomura Research Institute
AIの進化と社会への影響: 今知っておくべき10の主要分野 – Reinforz
カオナビ|【シェアNo.1】社員の個性・才能を発掘し、戦略人事を加速化させるタレントマネジメントシステムシステム|株式会社カオナビ
タレントパレット | タレントマネジメントシステム
freee人事労務 – 労務の「人的なミス」をゼロへ
この記事を書いた人
shishido ライター
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。