
SDGs17「パートナーシップで目標を達成しよう」とは国境の垣根を超えて多くの人が協力し、大きな目標の達成を目指すことです。
人々が協力するための道標がSDGs17「パートナーシップで目標を達成しよう」です。
この記事では、SDGs17「パートナーシップで目標を達成しよう」の企業の取り組み事例を紹介していきます!
目次
SDGs17「パートナーシップで目標を達成しよう」とは?簡単に解説!
SDGs17「パートナーシップで目標を達成しよう」の目標は、資金・技術・能力構築・貿易・政策や制度的・パートナーシップ・モニタリングのジャンルに分けられています。
これらは、世界の協力をより強固なものにするための内容となっています。技術や知識などを途上国に伝え、現地の人々の能力を開発することで、世界では、持続可能な開発を実現しようと試みているのです。
目標17を構成する19個のターゲット
資金
| 17.1 | 課税及び徴税能力の向上のため、開発途上国への国際的な支援なども通じて、国内資源の動員を強化する。 |
|---|---|
| 17.2 | 先進国は、開発途上国に対するODAをGNI比0.7%に、後発開発途上国に対するODAをGNI比0.15~0.20%にするという目標を達成するとの多くの国によるコミットメントを含むODAに係るコミットメントを完全に実施する。ODA供与国が、少なくともGNI比0.20%のODAを後発開発途上国に供与するという目標の設定を検討することを奨励する。 |
| 17.3 | 複数の財源から、開発途上国のための追加的資金源を動員する。 |
| 17.4 | 必要に応じた負債による資金調達、債務救済及び債務再編の促進を目的とした協調的な政策により、開発途上国の長期的な債務の持続可能性の実現を支援し、重債務貧困国(HIPC)の対外債務への対応により債務リスクを軽減する。 |
| 17.5 | 後発開発途上国のための投資促進枠組みを導入及び実施する。 |
技術
| 17.6 | 科学技術イノベーション(STI)及びこれらへのアクセスに関する南北協力、南南協力及び地域的・国際的な三角協力を向上させる。また、国連レベルをはじめとする既存のメカニズム間の調整改善や、全世界的な技術促進メカニズムなどを通じて、相互に合意した条件において知識共有を進める。 |
|---|---|
| 17.7 | 開発途上国に対し、譲許的・特恵的条件などの相互に合意した有利な条件の下で、環境に配慮した技術の開発、移転、普及及び拡散を促進する。 |
| 17.8 | 2017年までに、後発開発途上国のための技術バンク及び科学技術イノベーション能力構築メカニズムを完全運用させ、情報通信技術(ICT)をはじめとする実現技術の利用を強化する。 |
能力構築
| 17.9 | すべての持続可能な開発目標を実施するための国家計画を支援するべく、南北協力、南南協力及び三角協力などを通じて、開発途上国における効果的かつ的をしぼった能力構築の実施に対する国際的な支援を強化する。 |
|---|
貿易
| 17.10 | ドーハ・ラウンド(DDA)交渉の結果を含めたWTOの下での普遍的でルールに基づいた、差別的でない、公平な多角的貿易体制を促進する。 |
|---|---|
| 17.11 | 開発途上国による輸出を大幅に増加させ、特に2020年までに世界の輸出に占める後発開発途上国のシェアを倍増させる。 |
| 17.12 | 後発開発途上国からの輸入に対する特恵的な原産地規則が透明で簡略的かつ市場アクセスの円滑化に寄与するものとなるようにすることを含む世界貿易機関(WTO)の決定に矛盾しない形で、すべての後発開発途上国に対し、永続的な無税・無枠の市場アクセスを適時実施する。 |
体制面
政策・制度的整合性
| 17.13 | 政策協調や政策の首尾一貫性などを通じて、世界的なマクロ経済の安定を促進する。 |
|---|---|
| 17.14 | 持続可能な開発のための政策の一貫性を強化する。 |
| 17.15 | 貧困撲滅と持続可能な開発のための政策の確立・実施にあたっては、各国の政策空間及びリーダーシップを尊重する。 |
マルチステークホルダー・パートナーシップ
| 17.16 | すべての国々、特に開発途上国での持続可能な開発目標の達成を支援すべく、知識、専門的知見、技術及び資金源を動員、共有するマルチステークホルダー・パートナーシップによって補完しつつ、持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップを強化する。 |
|---|---|
| 17.17 | さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 |
データ、モニタリング、説明責任
| 17.18 | 2020年までに、後発開発途上国及び小島嶼開発途上国を含む開発途上国に対する能力構築支援を強化し、所得、性別、年齢、人種、民族、居住資格、障害、地理的位置及びその他各国事情に関連する特性別の質が高く、タイムリーかつ信頼性のある非集計型データの入手可能性を向上させる。 |
|---|---|
| 17.19 | 2030年までに、持続可能な開発の進捗状況を測るGDP以外の尺度を開発する既存の取組を更に前進させ、開発途上国における統計に関する能力構築を支援する。 |
SDGs17「パートナーシップで目標を達成しよう」のキーワードは助け合いです。
日本や世界の企業がどのように力を合わせているのか具体的な取り組みをみてみましょう。
SDGs17の達成に向けた日本の企業・団体の取り組み事例
それでは、SDGs17の達成に向けて取り組みを進める日本の企業・団体の事例を紹介します。
岡山ビューホテル

岡山ビューホテルは、滞在期間からチェックアウトまで、きめ細やかなサポートが魅力のホテルです。また、「思いやり(OMOIYARI)」を世界標準語にすることをビジョンに掲げ、岡山県の発展と思いやりのある社会づくりに貢献しています。
パートナーシップを利用した「岡山食活」と「お土産販売」
岡山ビューホテルは、「岡山活性化支援業」を主力事業と考え、SDGsおよび岡山県の魅力向上のために取り組んでいます。
例えば地元生産者と協力し、国内外から訪れるホテル宿泊者にホテル内のレストラン「五感」で、岡山の食材を使ったメニューを提供する「岡山食活」を開催。多くの人に、岡山のおいしい食材を知ってもらうきっかけとりました。
また岡山ビューホテルは公益財団法人YMCAと協力し、「ひだまり~ぬ子ども食堂」をホテル内のレストランにて定期的に開催しています。共働きや単身赴任で1人で食事をすることが多い子ども達に、楽しく食事をする場を提供することが目的です。このホテル主催の子ども食堂は、岡山ビューホテルが初めての試みとなります。
しかし、継続するためには資金が必要です。そこで岡山ビューホテルは子ども食堂の開催費を集めるために、県内の酒蔵と共同でクラウドファンディングを行いました。

また別事業では、岡山ビューホテルのオリジナルのお土産品を販売。
上記のキーホルダーは岡山市の表町商店街の中にある、「就労継続支援A型事業所」の利用者が作りました。このように土産品の開発は、県内の社会福祉法人や就労継続支援施設と協力して行っています。この売り上げの一部も、子ども食堂の運営資金として利用しています。
株式会社マーケットエンタープライス
マーケットエンタープライスは、2015年に日本初のネット型リユース事業を行う企業として上場しました。
その後、メディアプラットフォーム事業やモバイル通信事業も展開しています。「リユース」という言葉が少しずつ浸透してきた現代で、循環型社会への発展に向けて挑戦し続けている企業です。
自治体と連携し行った休眠楽器寄付ふるさと納税
現在、教育機関では楽器不足が問題となっています。この問題を解決するためにマーケットエンタープライスは、使われなくなった楽器「休眠楽器」に注目。国内初となる「休眠楽器」の受け入れを行ったのです。
さらに三重県いなべ市と連携し、「楽器寄付ふるさと納税」の事業を構築。休眠楽器を寄付すると、楽器が不足している教育機関へ寄付される仕組みです。この時マーケットエンタープライスは、楽器の査定を担当しました。
この取り組みは、ふるさと納税制度を利用しているため、寄付した人は楽器の査定額分の税金が控除されます。楽器寄付ふるさと納税事業は、開始2ヶ月で150個の楽器が集まり、教育機関や生徒へ届けられました。現在では、いなべ市を含め約15以上の自治体がこの制度を導入しています。
ふるさとづくり大賞を受賞
マーケットエンタープライスの頑張りもあり、いなべ市は令和2年度のふるさとづくり大賞を受賞しました。ふるさとづくり大賞は、地域の活性化に向けて頑張る団体や個人を表彰し、更なる地域社会の発展を促す目的で開催されています。
受賞理由は下記の通りです。
- ふるさと納税と寄付を組み合わせた新しい方法
- いなべ市の次世代を育む取り組みとして、無理なく導入できる点
いなべ市が事業の受け口となり全国に呼びかけ、リユース事業を行うマーケットエンタープライスが楽器の査定を担当する。互いに協力しなければ、成功することのなかった事業です。
GANON FLORIST
GANON FLORISTは、企業理念に「世界一花を愛せる国を作る」を掲げ、誰もが自然を大切にできる社会づくりを目指しています。2013年に北海道で設立し、現在は世界10ヵ国以上で活動している企業です。
現在は、
- フラワーギフトの製作
- 撮影
- 作品展示
- 装花
- ショープロデュース
- バルセロナやバンコクの大学で花の専門家として指導
など、幅広く手がけています。
地産地消を基盤としたロスフラワー救済プロジェクト
現在、新型コロナウイルスの影響により花の需要が減少しています。そのため生花店では店頭に並ぶ、30~40%の花を廃棄処分しているそうです。また、これ以上の価格低下を防ぐために自ら廃棄処分をする生産者もいます。
生産者にとって一生懸命育てた花を、自らの手で処分することは精神的負担も相当なものでしょう。この現状を改善するために、GANON FLORISTでは「生産者」「生花店」「消費者」と連携し、地産地消を基盤としたロスフラワー救済取り組みを行っています!
クラウドファンディングで約70,000本の花を消費者へ
GANON FLORISTでは、ロスフラワー減少のためにクラウドファンディングを実施。
このクラウドファンディングでは、花の生産者から多くの花を購入するための資金を集めることが目的です。そして、生産者から購入した花を利用して、下記のような取り組みを予定しています。
- フローリストによって全身を花で装飾された人が街中を歩き、道行く人々に「一輪の花」をプレゼント(ロスフラワーの減少につながる)
- 花の市場や生産者の存続のための売り上げを生み出す
- 花の衣装で街を歩き、エンターテインメントで人々に驚きと感動を提供
- 多くの人に花を配ることによって、緊急事態のなかでも北海道に笑顔を増やす
- プロジェクト内容は動画や写真で拡散し、日本中のSNSを花だらけにする
そして、クラウドファンディングの支援者には、
- ドライフラワーのインテリア雑貨
- 生花を使用した撮影
- 定期フラワーアレンジメントのサービス
などのリターンを用意。
集められた資金は、廃棄予定だった約70,000本の花を消費者へ還元することに使われました。この取り組みによってロスフラワーは減少し、多くの生花を消費者へ届けることに成功しています。さらに、生産者と消費者を繋ぐ目的も果たしました。
地球に森を増やす花の定期便
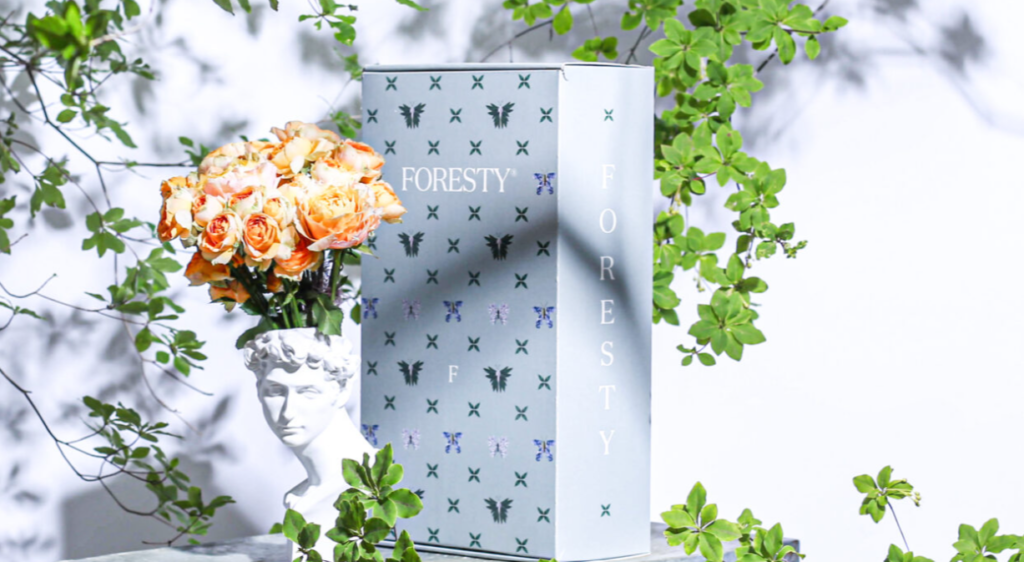
売れ残りが原因で廃棄になる生花を減らすためには、継続的な仕組みが必要です。
そこでGANON FLORISTは、地域で生産された生花を定期的に消費者へ届ける「生花のサブスク」を考案。5種類の中から自分にあったプランを選択すると、フローリストが厳選した北海道産の花が届きます。受け取り方法も、毎月500円の店舗受け取りや定期配送など、ライフスタイルに合った方法を選ぶことが可能です。
そして、このサブスクは、売り上げの一部を植林活動に利用。例えば、毎週3本の花がポスト投函で届くサブスクの場合は、8ヶ月で1本の木を植林できます。
この活動によって、毎月約3,000本のロスフラワーの削減に成功しました。同時に、生花店や生産者の収入の向上にもつながっています。
植林家とパートナーシップを結び、目標15「陸の豊かさも守ろう」などの他の目標にも貢献しました。
>>トップに戻る場合はこちら
SDGs17の達成に向けた世界の企業・団体の取り組み事例
続いては世界に向けた取り組み事例を紹介します。
国連と漁業のパートナーシップ 「海のエコラベル/MSC認証」
MSC(Marine Stewardship Council:海洋管理協議会)とは、1997年に設立された持続可能で適切に管理された漁業の普及に努める国際非営利団体です。
MSCでは、認証制度と水産エコラベルを通じて、限りある水産資源を守る活動を行っています。この活動に企業やNGO、政府が協働することで、国際的に認められ世界へと広がってきているのです。
まさに世界が協力して海を守っているパートナーシップと言えますね。
【関連記事】MSCが推進するMSC認証ラベルとは?商品一覧と日本で普及しない理由
シャボン玉グループ
「健康な体ときれいな水を守る」という企業理念のもと、無添加石けんの製造・販売を行っているシャボン玉グループ。生態系保全活動や学術的な石けんの研究にも取り組み、環境に配慮した石けんを提供しています。また、少量の水量で早く消火でき、環境への負荷も非常に少ない、石けん系泡消火剤の研究・開発も行っています。
JICAと協力して立ち上げたプロジェクトでは、CO2発生量が問題となっているインドネシアの泥炭火災に使用できる泡消火剤の研究・開発を進めてきました。そして2015年にはインドネシアへの提供を実現しています。
JICAとパートナーシップを結び自社の研究開発を活かしているのです。このような企業がたくさん増えてくると良いですね。
株式会社オリエンタル

ものを大事にする日本の中古品は品質がよく、世界でも信頼をされているリユース市場。オリエンタルは活動の場を海外へと広げ、現地の生活向上を支援しています。
具体的には、私たちが大切にとっておいた幼い頃の通学バッグや学習教材などがカンボジアの子供たちへと寄付され、利用されています。
私たちの大切な思い出は、このような形で新たな未来へとつないでくれるものへと変わるのです。
会宝産業株式会社

ブラジルの国立大学CEFET-MG(ミナスジェライス州国立工業技術大学)内に、自動車リサイクル教育センターが設立されています。
会宝産業の国際リサイクル教育センター(IREC)で行った自動車リサイクル研修のメンバーとして来日した、ブラジルの国立大学CEFET-MGの教授は、研修を通してリサイクルの必要性を感じました。そして、多くの人に働きかけ、会宝産業と国際協力機構(JICA)の協力のもと実現しました。
また、マレーシアでも自動車リサイクルシステムの整備を試みています。途上国では、捨てられた車が山積みになっていることも多く、環境改善が不可欠です。この技術が定着することで、解決への糸口になることが期待されています。
自動車産業が進む日本だからこそできる海外への支援ですね。
日本アジアグループ

日本アジアグループは、世界に先駆け、超低落差型の流水式マイクロ水力発電システムを開発。途上国の発展に貢献しています。
このシステムを使った発電機「ストリーム」は、開水路に設置するだけのシンプルな水力発電装置です。大規模な工事が不要で簡単に設置できることは途上国にとっても大きな前リットとなっています。
※発電機「ストリーム」は、国際連合工業開発機関(UNIDO)が実施するプロジェクトで、インド、エチオピア、ケニアの無電化地域などに届けられています。
企業の新しい開発に国際機関が協力して、途上国への支援につながっている例です。
まとめ
ここまでは、日本の中でのパートナーシップや日本から海外へ向けてのパートナーシップなどをご紹介しました。
各企業や団体が自分たちにできることを探し、協力しているのがわかりました。
SDGs17「パートナーシップで目標を達成しよう」を「自分ごと」として捉え、SDGs17に取り組む企業の商品を買ったり、関心を持って広めていくなど自分にできることを積み重ねましょう。
この記事を書いた人
kato ライター










