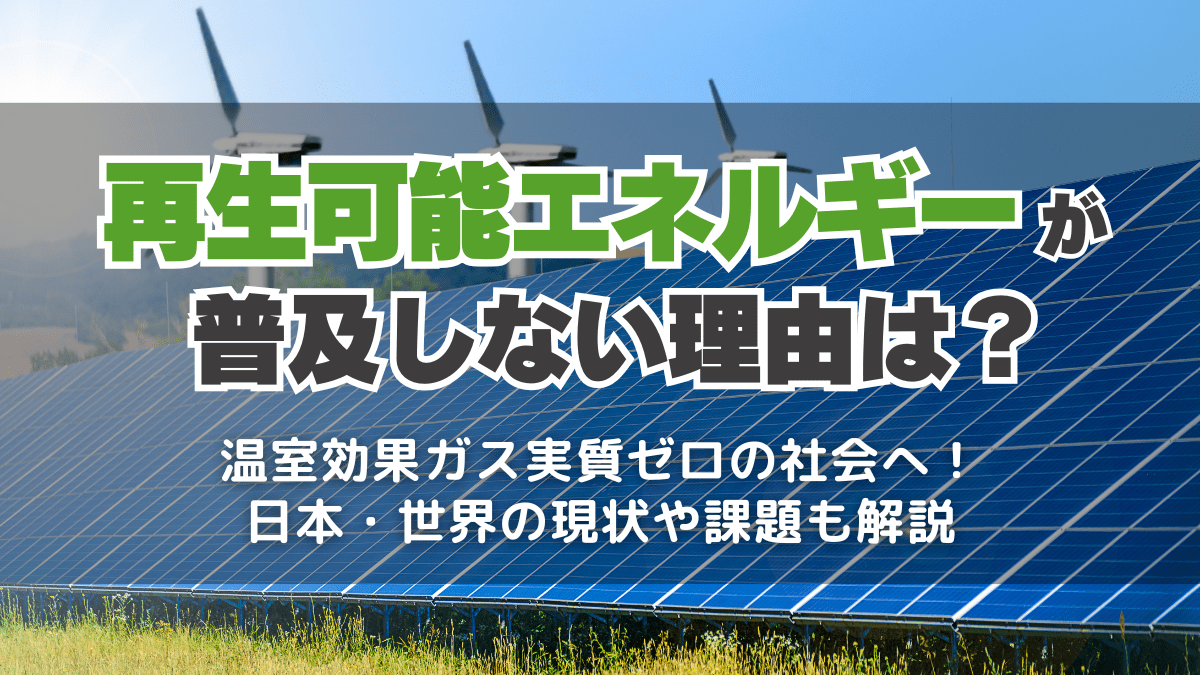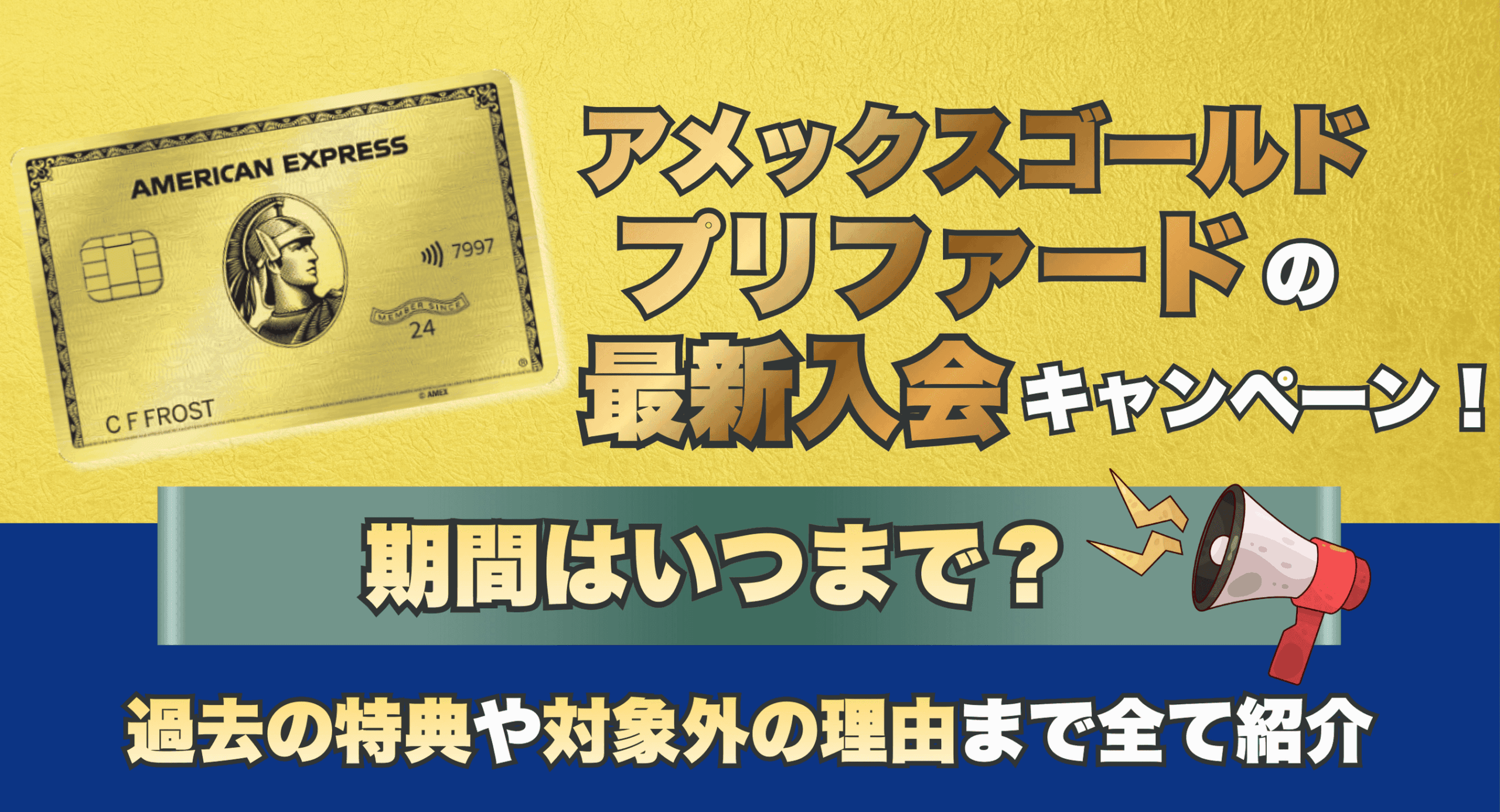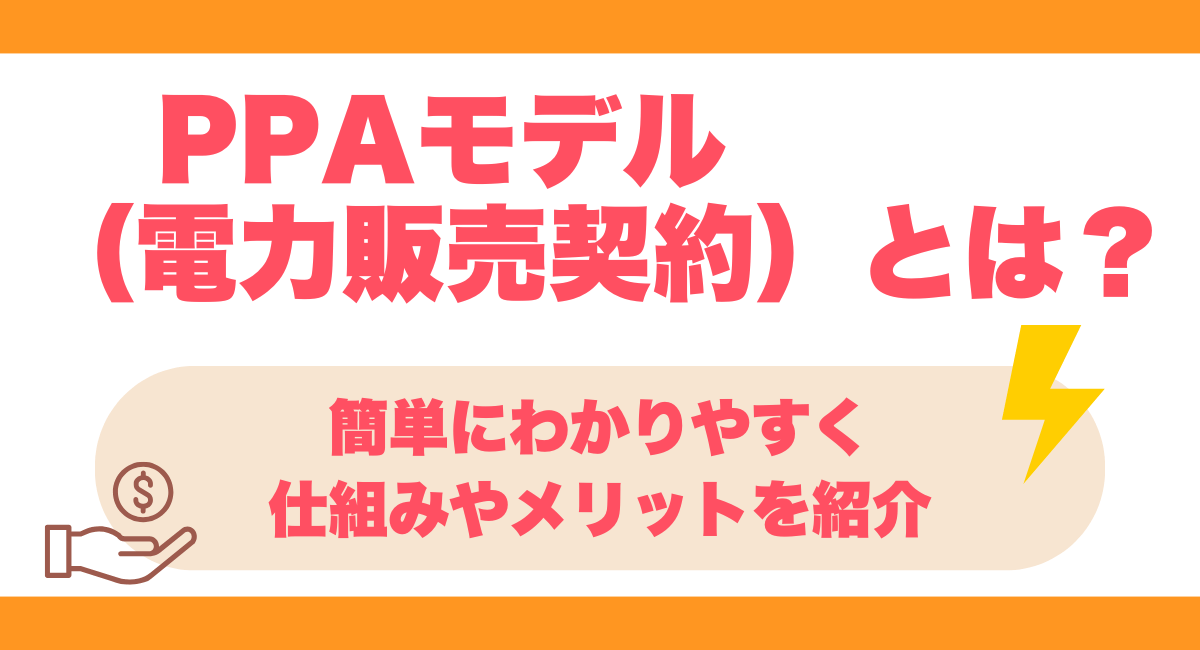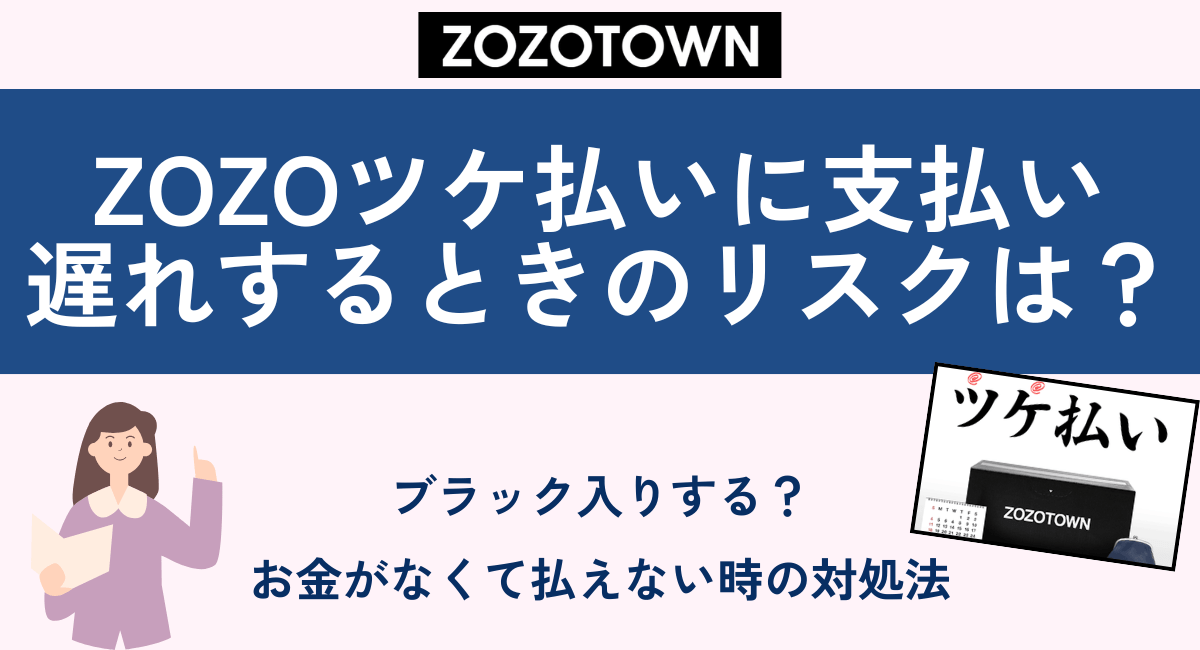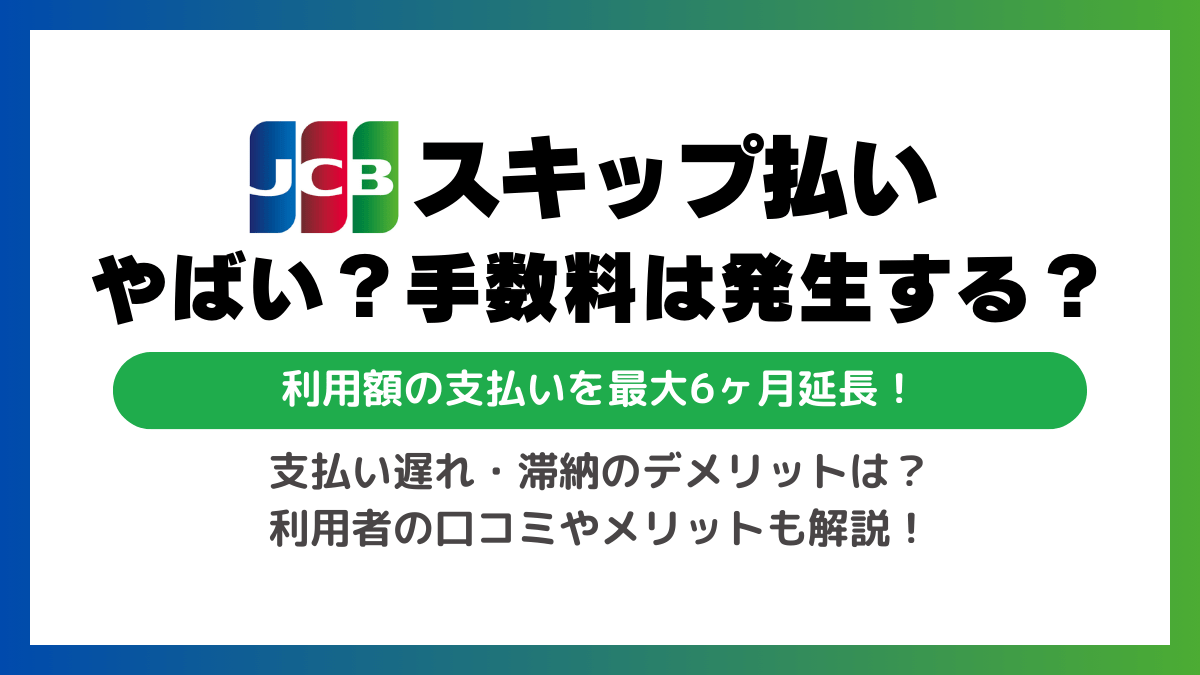東と西をつなぐ広大な交易路ネットワーク「シルクロード」は、約2000年以上にわたり、文明間の架け橋として機能してきました。紀元前2世紀、前漢の張騫が西域への道を切り開いたことから始まり、その後のローマ帝国との交易や唐代の繁栄を経て、ユーラシア大陸を横断する壮大な交流ルートへと発展していきました。
シルクロードの名は、19世紀にドイツの地理学者リヒトホーフェンが命名した「絹の道」に由来しており、中国の絹が最も価値ある交易品だったことを物語っています。
シルクロードは単なる交易路ではなく、異なる文化圏の思想・宗教・技術・知識が行き交う文明の大動脈でした。仏教や製紙法の伝播、ヘレニズム文化の東漸など、多様な文化的影響が日本にまで及んだことは正倉院の宝物が証明しています。
また、モンゴル帝国の時代には空前の繁栄を迎える一方で、ペストの大流行という負の側面も併せ持ちました。16世紀の大航海時代を迎えると海上ルートが発達し、陸のシルクロードは徐々に衰退していきました。
今回は、シルクロードが創られた目的や歴史について解説します。シルクロードに興味がある方は、ぜひ参考にしてください。
目次
シルクロードとは

シルクロードとは、中国から内陸アジアを経由してヨーロッパに至る交易路のことです。具体的には、漢代の都だった長安から敦煌、カシュガルを経由し中央アジアを横断してローマ帝国の東方(シリアや小アジア)に達する道です。*1)
シルクロードの全長は約8,700キロに及ぶ壮大なもので、2014年に洛陽・西安、敦煌、中央アジアのルートが世界遺産に登録されました。*2)
シルクロードの名前の由来は?
シルクロードの名前は、ドイツ語の「Seidenstraßen(ザイデンシュトラーゼン)」に由来します。ザイデンシュトラーゼンとは、「絹の道」を意味する語で、ドイツ人地理学者のリヒトホーフェンによって命名されました。*2)
現在、シルクロードの語は中国や日本などの東アジア世界と、西方の諸地域を結ぶ陸上・海上ルートとして認識されることが多くなっています。*3)
どこからどこまでを指す?
シルクロードは、東西を結ぶ一本の道と思われがちですが、大きく3つの道が利用されてきました。
- 草原ルート
- オアシスルート
- 海上ルート
草原ルートは、天山山脈やアラル海、カスピ海、黒海北方の遊牧地域を横断しています。「草原の道」や「ステップ・ルート」とも呼ばれるこの通路は、紀元前5世紀のヘロドトスの著作『歴史』にも記録が残されており、非常に古くから存在していたことがわかります。*3)
オアシスルートは、中国の古都である洛陽・長安から始まり二つの道筋に分かれる交易路です。一方は天山山脈の南側にある町々を通りカシュガルへ至り、パミール高原を越えて中央アジア方面へ続きます。
もう一方は崑崙山脈の北側の町々を経由してヤルカンドに至り、同じくパミール高原を越えて西アジアやインド方面へと延びています。
この経路は人々が定住する水場のある都市を結ぶ通商路として知られ、「オアシスの道」とも呼ばれています。漢の時代に張騫が西方へ派遣された後、特に活発に利用されるようになりました。狭い意味でのシルクロードとは、まさにこの水場を結ぶ通商路を指すのです。*3)
海上ルートは、南シナ海からインド洋、アラビア海を経てペルシア湾や紅海に至る航路で、古代から活用されていた重要な交易経路です。この航路は「海の道」や「南海路」とも呼ばれ、各地の港町を結ぶ交通網として機能していました。歴史的には秦・漢王朝が成立する以前から既に使われていたと考えられています。*3)
シルクロードが作られた目的

ユーラシア大陸の東端と西端を結ぶシルクロードは、なぜ作られたのでしょうか。その理由は、東西交易の需要にあります。詳しく見てみましょう。
東西交易を行うため
シルクロードを通じて、さまざまな特産品が交易されました。東から西へは絹織物、陶磁器、紙、漆の工芸品、茶などが運ばれました。反対に西から東へは馬、ガラス、毛織物、香料、ワインなどが届けられました。
中国から西方に運ばれた絹は、軽くて高価であったため、主力貿易品となりました。中国産の陶磁器も、西方諸国で愛好されました。他方、中国にとって馬は軍事的にも重要な輸入品です。それ以外にもガラス製品や絨毯、ワインといった西方の珍しい品物が中国に運ばれたのです。
シルクロードの歴史

シルクロードは千年以上の長い歴史を持っています。これから、まずシルクロードの歴史的な流れを時系列に沿って紹介します。その後、特に重要な出来事や特徴について詳しく解説していきます。シルクロードの歴史を理解する上で欠かせないポイントを中心に、わかりやすく伝えますので、どうぞお楽しみください。
【シルクロード略年表】
| 年代 | できごと |
| 紀元前2世紀 | 前漢の張騫が西域に派遣される → シルクロードの整備が始まる |
| 1世紀 | 後漢とローマ帝国の交易 |
| 7世紀 | 唐の時代にシルクロード交易が最盛期を迎える |
| 751年 | タラスの戦いで唐軍がイスラム軍に大敗 → 製紙法が西方に伝わる |
| 14世紀半ば | ペストがシルクロードを通じてユーラシア大陸全体に拡大 |
| 16世紀 | 大航海時代の幕開け → 陸のシルクロードが衰退 |
シルクロードの始まり
中国と西方諸国の貿易は、紀元前403年から前221年の戦国時代にさかのぼります。この時期には、中央アジアのホータン地域から高級な「玉(ぎょく)」が中国に輸入されていました。そして、その見返りとして中国の絹が西方に送られていたと考えられています。*4)
シルクロードが本格的に機能し始めたのは、前漢の武帝の統治期間でした。武帝は積極的に外交政策を推し進め、張騫(ちょうけん)という使者を中央アジアに送りました。この外交活動により、中国は西方の国々と正式な関係を築き、より組織的な貿易を展開することができるようになりました。*4)
仏教の伝来
シルクロードが整備されると、西方から中国に仏教が伝来しました。4世紀から5世紀にかけて、シルクロードのオアシスの一つである亀茲(きじ)出身の僧侶である鳩摩羅什(くまらじゅう)が、長安で多くの仏典を翻訳しました。*5)仏教が中国に伝わったことで、敦煌莫高窟やキジル千仏洞など仏教関連の遺跡が、シルクロード沿いに多数作られました。
7世紀の唐の時代には、三蔵法師として知られる玄奘三蔵がシルクロードを通じて、インドに旅立ちます。彼は、インドで重要な仏典を入手して中国に持ち帰りました。玄奘が持ち帰った仏典や知識は、中国だけではなく日本にも大きな影響を与えたのです。*6)
製紙法の西伝
製紙法とは、紙を作る技術のことです。紙が伝わるまで、ヨーロッパでは羊皮紙が使われていました。羊の皮から作る羊皮紙は、丈夫でしたが非常に高価という欠点がありました。*7)
751年、唐軍とイスラーム軍が戦ったタラス河畔の戦いで、捕虜となった唐の兵士の中に紙をつくる技術を持った者がいたことから、西方世界にも製紙法が伝わったのです。*8)シルクロード上での戦いが、新しい技術を東から西に伝えたことがわかります。
モンゴル帝国によるシルクロード支配
13世紀、チンギスハンが建国したモンゴル帝国は、シルクロード全域を支配する大帝国となりました。東の中国から西の地中海まで、広大な地域が一つの帝国のもとに統一され、シルクロードの交通の安全が保障されたのです。
モンゴル帝国では「駅伝制(ジャムチ)」と呼ばれる制度を整え、一定の距離ごとに宿泊や馬の交換ができる施設を整えました。*9)この時代、東西交流はますます盛んになり、シルクロード沿いの都市は大いに繁栄したのです。
ペストの大流行
東西交流は、プラスの影響だけではなくマイナスの影響ももたらしました。それが、ペストの大流行です。
中国やアジア南部から広がったペストは、シルクロードの交流によってヨーロッパにまで到達し、3,500万人もの死者を出したといいます。*11)
陸のシルクロードの衰退
ユーラシア大陸を東西に貫くシルクロードは、長期にわたってアジアとヨーロッパをつなぐ重要な交易路として発展してきました。しかし、15世紀以後は、徐々に衰退します。
1つ目の衰退の理由は、モンゴル帝国の弱体化です。14世紀になると、最も力を持っていた中国の元が衰退し、他のハン国も衰えていきました。そのため、シルクロードの安全を維持する力を失ってしまったのです。
2つ目の衰退の理由は、大航海時代の到来です。ヨーロッパ諸国が海に活路を見出す大航海時代の始まりにより、陸路を通らずともアジアとヨーロッパの交易が盛んになりました。陸路よりも安全で効率的な海上貿易が主流となり、陸の交易路の重要性が低下したのです。
シルクロードと日本の関係

シルクロードは、海を隔てた日本にとっても重要な意味を持っています。ここでは、正倉院の宝物から、シルクロードと日本の関係を探ります。
正倉院にインドやペルシアからの文物が伝わった
東大寺にある正倉院には、聖武天皇の遺品を中心に、9,000点もの文物が納められています。数々の宝物のうち、シルクロードとの関連がはっきりわかるものとして、「螺鈿紫檀五弦琵琶(らでんしたんのごげんびわ)」があります。
この琵琶は、インド起源と考えられ、螺鈿細工や玳瑁(たいまい)貼りといった特殊な技法で作られています。*12)
ペルシア(現在のイラン)風の水差しである「漆胡瓶(しっこへい)」も有名な文物です。表面に黒漆が塗られた優美な水差しで、銀の薄板で草花や鳥獣の文様が表されています。*13)西アジアと日本のつながりをあらわす貴重な文物です。
コバルトブルーの美しい器である「紺瑠璃坏(こんるりのつき)」も忘れてはならない文物です。紺色のカップ形のガラス坏で、銀製の台座と接着されています。ガラスの部分はペルシアで制作され、足の部分には中国風の龍が彫られています。*14)東西文化が一つの器で融合していることがよくわかります。
シルクロードとSDGs

シルクロードは、東西の文化を結び付ける交易路として繁栄してきました。しかし、その繁栄は争いの理由となってきました。以前に比べると重要性は低下したといっても、シルクロードは重要な交通路であることに変わりありません。
ここでは、シルクロード周辺での戦いのうち、アフガニスタンでの戦争とSDGsの関わりについて解説します。
SDGs目標16「平和と公正をすべての人に」との関わり
シルクロードは、昔から東西を結ぶ大切な交易の道として知られていますが、同時に様々な国や勢力が力を争う場所でもありました。特にシルクロードの重要な地点であるアフガニスタンは、その地理的な位置から長い間、紛争が絶えない地域となっています。
アフガニスタンでは、アメリカとソ連(現在のロシア)の対立や、その後のタリバンの台頭により、何十年も戦争や争いが続いてきました。このような状況の中で、多くの一般市民が平和な暮らしを奪われ、公平な社会から取り残されている現状があります。
SDGs目標16「平和と公正をすべての人に」は、このような戦争や暴力をなくし、すべての人が安心して暮らせる社会を作ることを目指しています。しかし、女性の抑圧などの問題を抱えているタリバン政権の統治が、今後どうなるか未知数です。
シルクロードの歴史と現在の状況は、平和と公正がいかに大切で、同時にいかに達成が難しいかを私たちに教えてくれます。SDGs目標16の達成には、国際社会が協力して紛争地域の平和構築と安定に取り組むことが必要です。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ
今回は、シルクロードについて解説しました。シルクロードは、古代から中世にかけて東アジアと西アジア・ヨーロッパを結んだ交易路網であり、特に中国の絹が主要な交易品であったことからその名がつきました。
紀元前2世紀の張騫の西域派遣をきっかけに整備が進み、7世紀の唐の時代に最盛期を迎えました。シルクロードは、絹や陶磁器、香辛料など様々な物資の交易だけでなく、仏教やイスラム教といった宗教、芸術、技術、知識の交流も促進しました。タラス河畔の戦いでは製紙法が西方に伝わるなど、東西文化の交流に大きな役割を果たしました。
しかし、14世紀にはペストの蔓延経路となり、16世紀の大航海時代以降は海上交易の発達によって衰退しました。それでも、シルクロードが東西文化交流に果たした役割は大きく、現代においても学ぶべき点が多いと言えるでしょう。
参考
*1)山川 世界史小辞典 改定新版「シルクロード」
*2)知恵蔵mini「シルクロード」
*3)改定新版 世界大百科事典「シルクロード」
*4)日本大百科全書「ニッポニカ」
*5)精選版 日本国語大辞典「鳩摩羅什」
*6)改定新版 世界大百科事典「玄奘」
*7)精選版 日本国語大辞典「羊皮紙」
*8)山川 世界史小辞典「タラス河畔の戦い」
*9)改定新版 世界大百科事典「駅伝制」
*10)デジタル大辞泉「ペスト」
*11)改定新版 世界大百科事典「ペスト」
*12)宮内庁 正倉院「螺鈿紫檀五弦琵琶」
*13)宮内庁 正倉院「漆胡瓶」
*14)宮内庁 キッズページ「正倉院の宝物を見てみよう」
この記事を書いた人
馬場正裕 ライター
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。