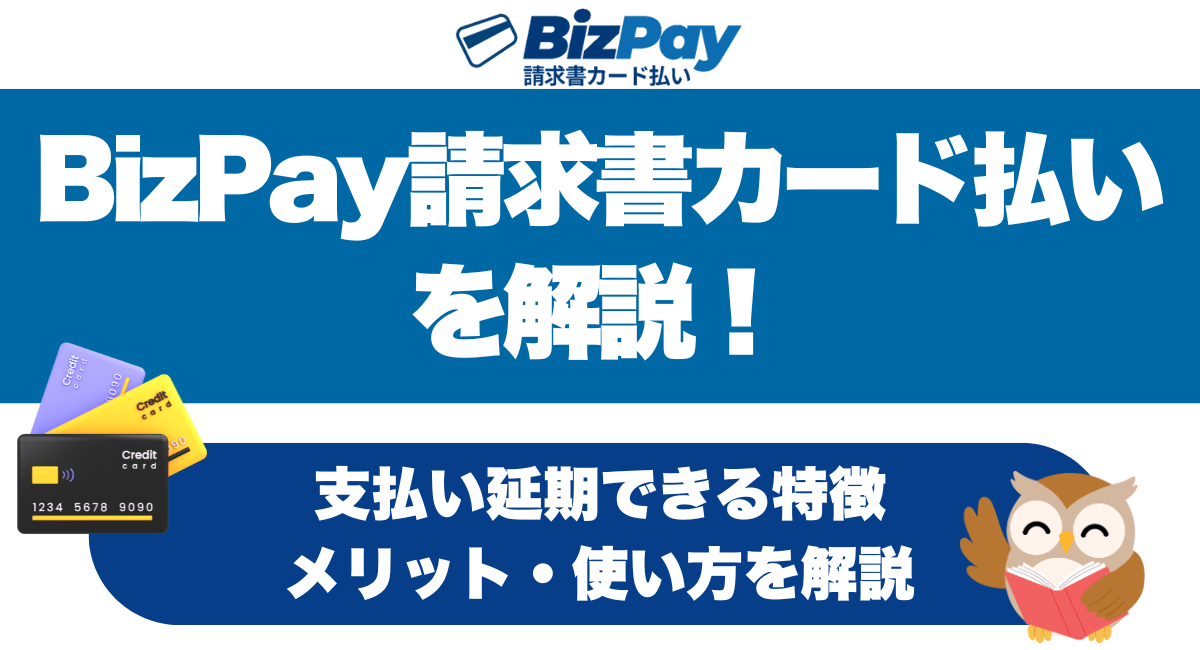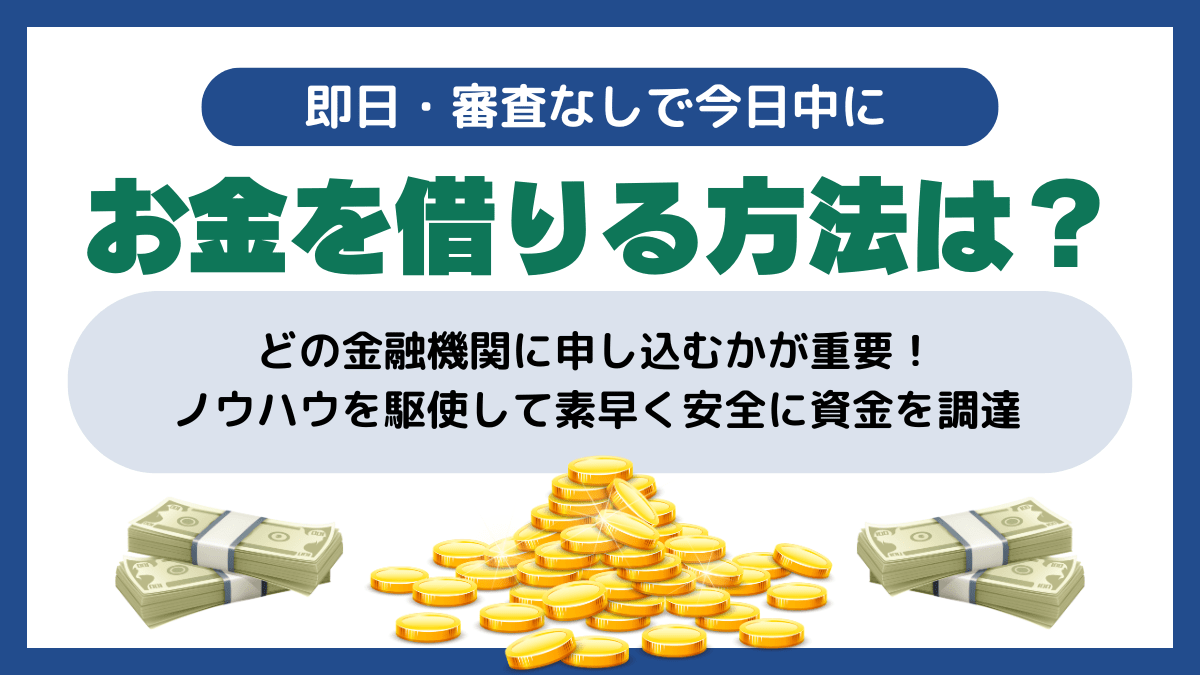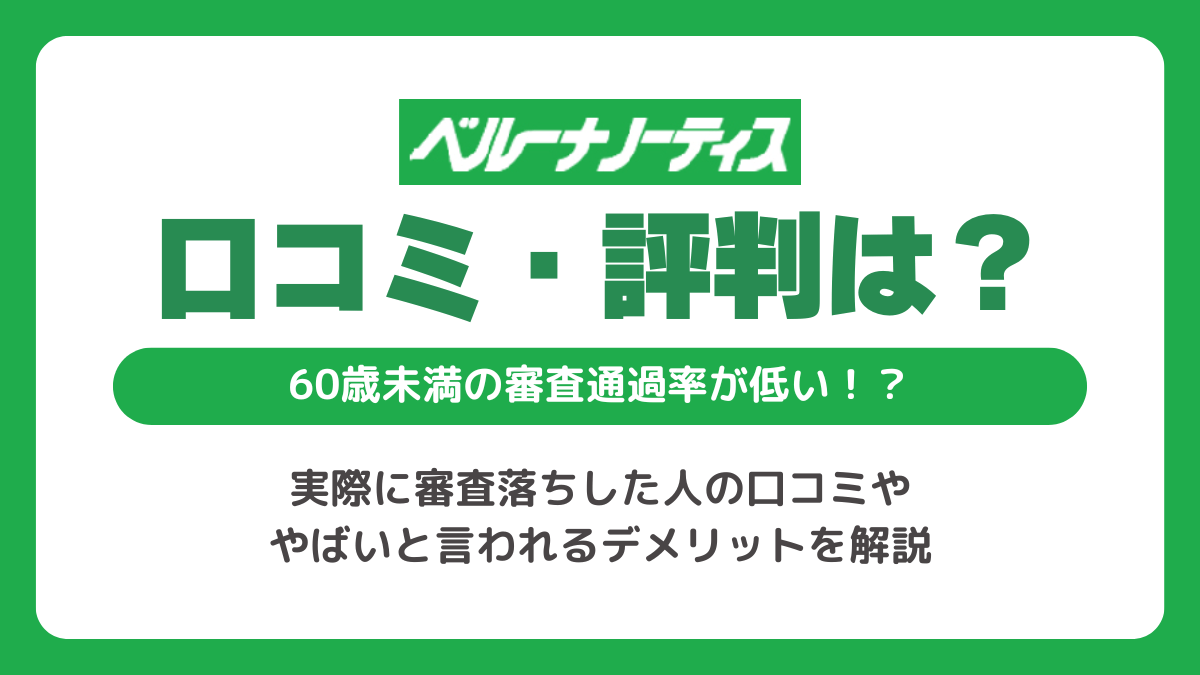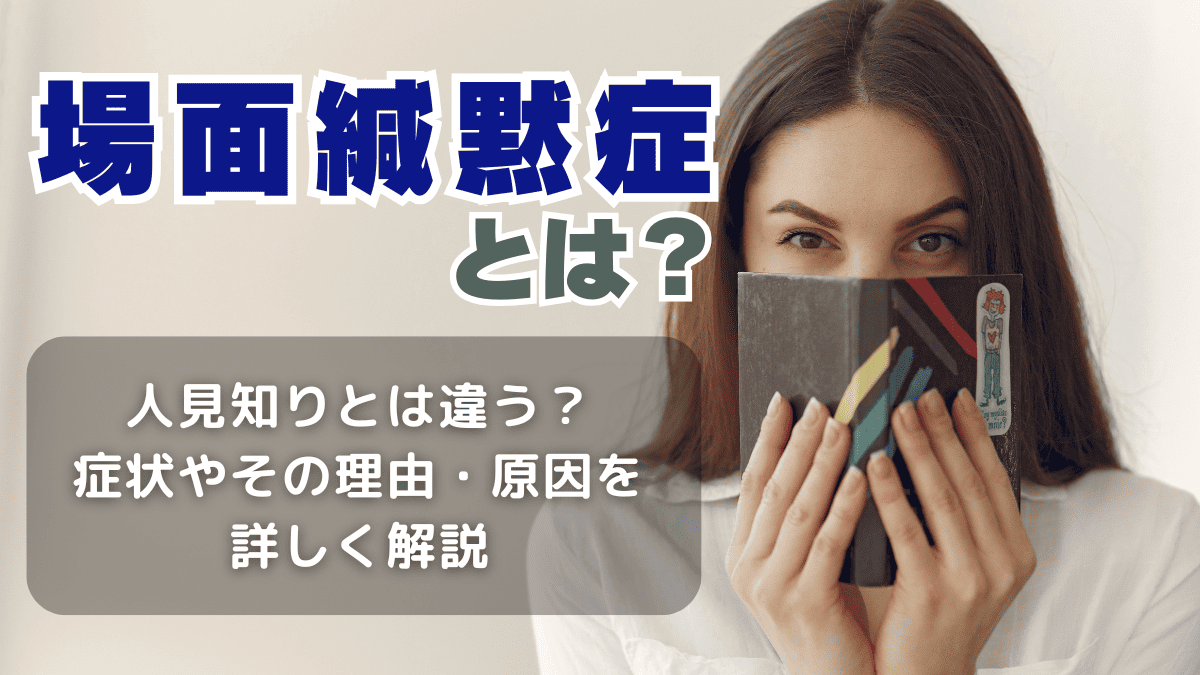認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会 奥寺 憲穂さん インタビュー
目次
introduction
世界では、ワクチンがないためにポリオなどの感染症で命を落とす子どもが、1日に4,000人いると言われます。認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会(以下JCV)は、そんな子どもたちを1人でも多く救うために開発途上国にワクチンを贈る活動を30年以上にわたって続けてきました。
寄付といえば一般的には募金をイメージする方も多いと思いますが、JCVの特徴はさまざまな支援活動への参加方法があることです。特に「ペットボトルキャップ回収」で支援する活動は、年々注目度が上がっています。
今回は事務局長の奥寺さんに、JCV創立の経緯や事業内容、ペットボトルキャップ回収をはじめとしたさまざまな支援活動への参加方法について伺いました。
子どもの命を救うため開発途上国にワクチンを贈る

–まずJCVの団体概要と事業内容について、教えていただけますか?
奥寺さん:
私たちは、「世界の子どもにワクチンを 日本委員会」という東京都の認定を受けている団体で、通称JCVと申します。創設者の細川佳代子が1994年に設立して以来、日本国内の個人や企業、学校、団体など様々な皆様からご寄付をお預かりし、子どもたちへのワクチンと、それを適切に保管するための「コールドチェーン機器」を開発途上国に届けてまいりました。
支援対象のワクチンは、ポリオ、風疹、結核、破傷風といった感染症予防に必要な基礎的なものです。これらの感染症は、日本では耳にする機会が少ないかもしれません。しかし世界では、このような感染症にかかり5歳までに命を落としてしまう子どもが、「1日4,000人」もいると言われています。時間にすると、なんと約20秒に1人の子どもが亡くなっている計算です。私たちはそうした子どもたちの命を1人でも多く救うことを目的に、日々活動を続けています。
–JCVを設立したきっかけをお伺いできますか?
奥寺さん:
先ほど、1日に4,000人の5歳未満の子どもが感染症で亡くなっているとお伝えしましたが、細川がJCVを創設した1990年代初頭には、その数が1日8,000人にも上っていました。細川は、ポリオワクチンなら1人1回分20円、比較的値段の高いMMRワクチン(はしか、おたふく風邪、風疹)でも200円程度というわずかな金額で防げるにもかかわらず、毎日8,000人もの子どもが命を落としていることを知って、大きな衝撃を受けたのです。
ほぼ時を同じくして、1993年11月に京都で開催された「子どもワクチン世界会議」に細川が出席する機会がありました。そこで、「先進国は途上国の子どもの命を守るべきである」という京都宣言が採択された直後、細川は「日本では私が!」と手を挙げ、わずか2か月後の1994年1月にはJCVを立ち上げました。
実は彼女は、1942年の戦時中に生まれ、戦後の荒廃した貧しい日本で育ちました。そのため、先進国から送られてきたミルクやワクチンなどの援助物資を受けたという記憶が残っており、ずっと「日本が発展したら、今度は私たちが支援する側にならなければならない」と思っていたと言います。そのような想いを実現させるためにも、JCVを設立したのです。
–支援をしている開発途上国の状況をお伺いできますか?
奥寺さん:
私たちは現在、開発途上国であるミャンマー、ラオス、ブータン、バヌアツの4カ国の子どもたちにワクチンを届けています。過去には緊急支援として、タジキスタンやパキスタン、シリア、ソマリアやマダガスカルにもワクチンを贈ったことがあります。これらの開発途上国は、地理的な問題、政治的な課題、歴史的背景など、さまざまな要因によって経済発展が思うように進まず、自国だけでは医療や教育といった社会的インフラの維持にも困難が伴います。特に医療面では、独自の力で必要なワクチンや接種環境を準備することが難しいのです。
ワクチンを接種できなければどうなるのでしょうか。新型コロナウイルスが急激に拡大した際、日本でも誰もが右往左往しましたが、例えば「はしか」は新型コロナウイルスの2倍以上の感染力があり、1人が感染すると周囲の10人に感染すると言われています。そして、発症すると10人に1人が亡くなるほど重篤な病気なのです。開発途上国では、特に最も弱い子どもたちに感染が広がりやすく、深刻な影響を受けています。
企業はビジネスと組み合わせて支援ができる

–JCVの支援活動への参加方法は、寄付や募金だけではないのが特徴だと感じました。
奥寺さん:
そうですね。まず個人の場合は、募金箱でご寄付を集めていただく方法が、一番イメージしやすいかもしれません。さらに、「子どもワクチンサポーター」という制度もあり、毎月1,000円や5,000円など任意の金額を口座引き落としやクレジットカードなどで寄付していただくことも可能です。お金での寄付以外には、「使わなくなったもの」や「ペットボトルキャップ」の回収で支援する方法もあります。
そして、JCVの大きな特徴は「支援者の7割以上が法人であること」です。特に企業の占める割合が約60%と非常に高く、これは他の寄付団体と比べても珍しいと思います。企業のJCVの支援方法には、毎年一定額を寄付するスポンサーとなっていただく他に、それぞれの企業の事業やビジネスに連動させた寄付の仕組みも誕生しました。
実際の例でお伝えしますと、「Webの問い合わせやレビュー1件につきワクチン1本を寄付」「ラーメン1杯売れるごとにワクチン1本を寄付」「タクシーが一定距離走るごとにワクチン1本を寄付」などです。JCV側は寄付に関する条件を一切設けていませんので、「ワクチン◯本以上でなければダメ」「最低いくら必要」といった制約はありません。すべて任意で行っていただいているものになります。この仕組みでは、企業のビジネスが成長することで寄付額も増え、それが社会貢献につながるという好循環が生まれています。 ありがたいことに、企業の方々にも「業績が上がることでワクチン寄付が増える」「それが社会貢献になり、社員のモチベーションにもつながる」と感じていただいているようです。

–この「それぞれの企業の事業やビジネスに連動させた寄付の仕組み」は、どのような経緯で誕生したのでしょうか?
奥寺さん:
2024年シーズン限りで引退したプロ野球・福岡ソフトバンクホークスの和田毅投手の功績が、非常に大きいと思います。彼はプロ3年目の2005年から、1球投げるごとにワクチン10本、勝利投手になれば1球20本、リーグやクライマックスシリーズに優勝すれば追加で1万本支援をするのだと、自ら「僕のルール」というものを定めて、実践をしてくださいました。現役を引退された2024年までに和田投手が支援したワクチンは、合計76万を超える本数に到達しています。
そして、和田さんの「僕のルール」活動を多くの人に知ってもらうため、2006年から2008年にかけての2年間、ACジャパンのCMに出演していただきました。このCM効果は絶大で、野球ファンに限らず、日本全国の多くの方々が彼の活動に共感してくださいました。その中で、「ビジネスと連携したルールを作って、子どもワクチン支援をしよう」と考える企業も出てきて、企業の支援活動の裾野が一気に広がったという経緯です。
「使わなくなったもの」をワクチンに!

–支援の方法には、「使わなくなったもので支援」もあるのですね。
奥寺さん:
使わなくなったものを活用した支援は、創設当初からのJCVの伝統でもあります。創設者の細川が講演で「使っていないテレフォンカードを寄付してください」と呼びかけたところ、大量のカードが送られてきたことが、JCVの物品寄付活動の始まりでした。JCVが設立当初からこのような活動を取り入れたのは、日本では「お金を寄付すること」に心理的なハードルを感じる方もいらっしゃるかと思います。そのため私たちは、「お金ではなくても支援できる」という選択肢作りにも力を入れてきました。
現在、SDGsの広がりとともに、この活動はJCVの大きな柱の一つとなっています。特に最近は、企業が物品回収をビジネスに取り入れ、売上の一部を寄付する動きが増えてきました。企業にとっては「ビジネスを通じた社会貢献」をアピールできますし、社員にとってもSDGsやワクチン支援への貢献というモチベーション向上に繋がっているのだと考えられます。
–支援に活用できる「使わなくなったもの」とは、具体的にどのようなものでしょうか?寄付までの流れとあわせて教えてください。
奥寺さん:
書籍やコミック、CD、衣類などリユースとして定番のものから、ブランド品、貴金属、宝石など30品目以上が対象です。提携している買取業者がこれらの物品を買い取り、その売上の一部をJCVに寄付するという流れになります。提携しているいくつかの買取業者は、ホームページや店頭で「買い取られた品物がワクチン何本分に相当するのか」を明記している企業もあります。JCVのHPからは、JCVへ寄付ができる買取サービス企業の一覧や、対象となる物品が確認できます。
その他、書き損じはがきや未使用はがき、未使用切手や使用済みの切手、図書券や商品券などの金券、海外紙幣なども、換金して支援につなげることが可能です。これらは直接私たちの事務局に送付いただければ、ワクチンに換えて途上国の子どもたちへお届けします。
ペットボトルキャップ回収の注目度は上昇中

–「ペットボトルキャップ回収」での支援についても、詳しく教えてください。
奥寺さん:
ペットボトルキャップ回収による支援は、JCVの物品回収寄付の中では最も規模が大きく、今も増加し続けている活動です。実はキャップの回収は、「ペットボトル本体はリサイクルされているのに、キャップは捨てられているのはもったいない」という神奈川県の高校生の声がきっかけとなり、民間でスタートした活動なのだそうです。そして、JCVにも「回収したキャップを社会貢献にも繋げたい」と声掛けいただいたことで、2005年頃からペットボトルキャップ回収を通した寄付が始まりました。参加していただく方法は2種類あります。

1つ目は、集めたペットボトルキャップを回収業者に引き渡していただくと、回収・リサイクル業者がキャップをリサイクル素材に換え、売却した利益がJCVに寄付されるという方法です。

2つ目は、集めたキャップをご自身で回収業者に売却していただき、その金額を直接JCVに寄付いただく方法です。2022年末時点で、41都道府県をカバーする85の事業者、104の拠点でJCVと連携した回収ネットワークが稼働しています。残りの6県もカバーできるよう、さらに拡大を目指しているところです。
—「ペットボトルキャップ回収」は、リサイクルによる脱炭素・資源循環と、子どもたちの命を救うワクチン支援にも繋がる、ダブルの社会貢献活動ができるのですね。
奥寺さん:
キャップの素材はポリエチレンとポリプロピレンというほぼ単一素材のため、非常に再生しやすいのです。しかし、JCVへの寄付分から逆算すると、キャップの回収率はわずか5.8%です。JCV以外の回収ルートを含めても20〜30%程度と推測されますが、詳細なデータは存在しません。日本ではプラスチック回収が進み、清涼飲料のペットボトル本体の回収率は94.4%、リサイクル率は86.9%(2022年時点)に達しているのにもかかわらずです。
そういった問題意識もあり、私たちは全国のプラスチック回収リサイクル事業者とのネットワーク作りに積極的に取り組んできました。その結果、5年前は60社程度だったキャップ回収の提携業者が、今では85社に増加しました。

また、キャップ回収を促すキャンペーンも実施しています。6月の環境月間に合わせて開催している、InstagramやXで、#キャップアクションと付けてペットボトルキャップの写真や動画を投稿するだけで1投稿につきワクチン1人分の寄付に繋がる「キャップアクションキャンペーン」は、昨年新聞記事に取り上げられるなど非常に注目されました。2023年に開始した当初は8,600件程度の投稿でしたが、昨年は1万1,266件に増えました。。
JCVがSNS上で開催するキャンペーンには、もう1つ、「#ハートアクションキャンペーン」があります。こちらは国際チャリティ・デーに合わせて9月~10月に開催しているもので、#ハートアクションと付けてハートの写真や動画を投稿することで、1投稿で1人分のワクチン支援ができるキャンペーンです。ハートのポーズや商品などのほか、ハートの形に並べたペットボトルキャップなども投稿いただいています。昨年は、なんと32,623件もの投稿が集まりました。
SNSのキャンペーンは2020年から開始しましたが、初年度の投稿はわずか500件。二つのキャンペーンを合わせると、5年で100倍近くに膨らんだことになります。参加してくださった皆さんが、共感して周りの方々に声を掛けてくださり、子どもワクチン支援の輪を広げてくださったのです。「#キャップアクション」「#ハートアクション」は、今後も開催予定です。誰もが参加しやすく、支援の輪を広げられる協力方法として、このようなSNSキャンペーンにも力を入れてまいります。
支援の選択肢をさらに増やしたい

–今後の展望をお伺いできますか?
奥寺さん:
私たちの目的は設立当初から変わりません。1人でも多くの子どもの命を感染症から救うため、1本でも多くのワクチンを届けることです。そのためには、JCVの活動を広く知ってもらい、共感の輪を広げることが重要だと考えています。具体的には、ペットボトルキャップ回収などの呼びかけに加えて、QRコードやPayPayを使った少額寄付を可能にすることも検討しています。100円、500円でも、気持ちは同じです。「寄付」という言葉に身構えず、気軽に支援に参加してもらえるよう工夫したいですね。
もう一つ、ミャンマーの現状についても知っていただきたいと思います。ミャンマーは2021年2月の軍事クーデター以降、人権侵害が深刻化し、内戦状態に陥っている地域もあります。そのような状態ですから、当然ながらワクチン接種も滞っています。現在の国軍政権は、日本をはじめ国際的に多くの国から承認されていないこともあって、JCVも現政権への支援を中止。現在は、ユニセフと連携して、国境地帯の少数民族へ直接ワクチンを届ける方式に変更しています。ミャンマー国内のワクチン接種状況は非常に心配ですが、私たちにできることは限られているために、今は状況を注視していくほかありません。
一方で、ラオス、ブータン、バヌアツの3カ国では、順調にワクチン接種が進んでいます。特にブータンは、大半のワクチンで98〜99%という高い接種率を達成しました。また、バヌアツでも、大地震やサイクロンの被害を受けながらも、現地の医師・看護師が海を渡ったり、森を徒歩で移動したりして村まで行き、接種を行う出張ワクチン接種が盛んに行われています。日本では現在、副反応への懸念から接種率が95%を下回っているとも言われていますから、国を挙げて接種を進めているこれらの国々の取り組みは素晴らしいと思います。
JCVは今後も4カ国への支援を継続していくと同時に、将来的にはより多くの国や地域にワクチンを届けられるよう、事業規模を大きくして支援の輪を広げていきたいと考えています。
–貴重なお話をありがとうございました!
関連リンク
世界の子どもにワクチンを 日本委員会:https://www.jcv-jp.org/
この記事を書いた人
朝野めぐみ ライター
会社員をしながら、取材記事を中心に執筆活動をしているライターです。記事を通して、読者の皆様と一緒に「SDGs」について深く学んでいきたいと思います。
会社員をしながら、取材記事を中心に執筆活動をしているライターです。記事を通して、読者の皆様と一緒に「SDGs」について深く学んでいきたいと思います。