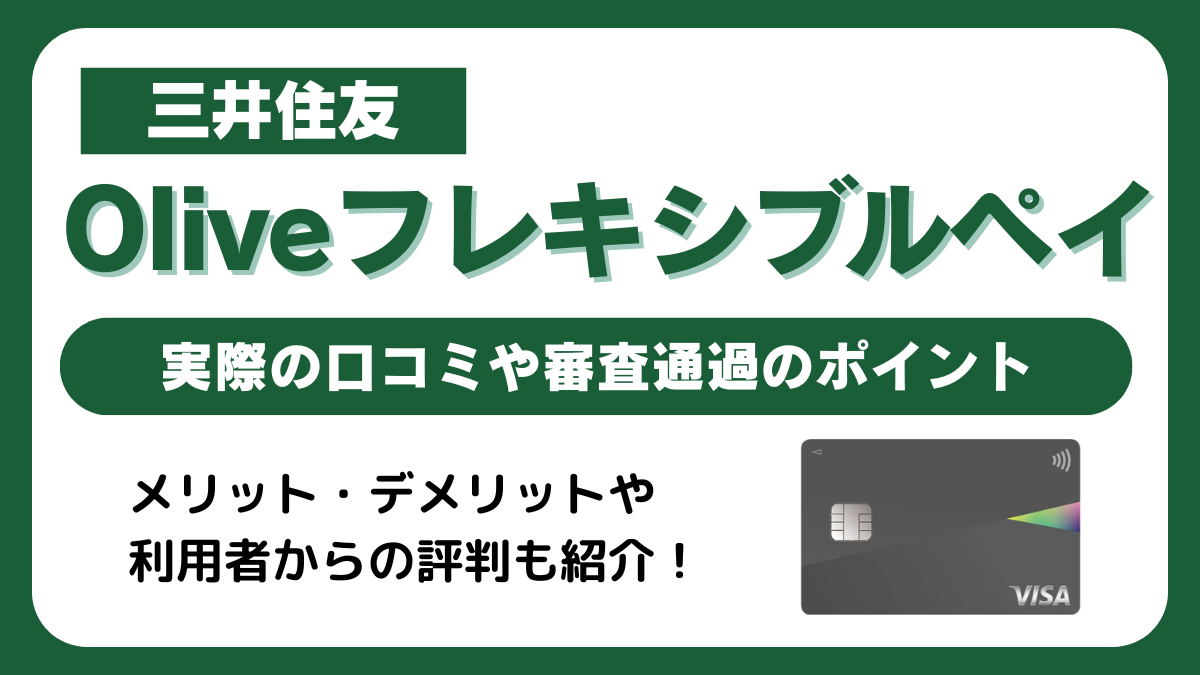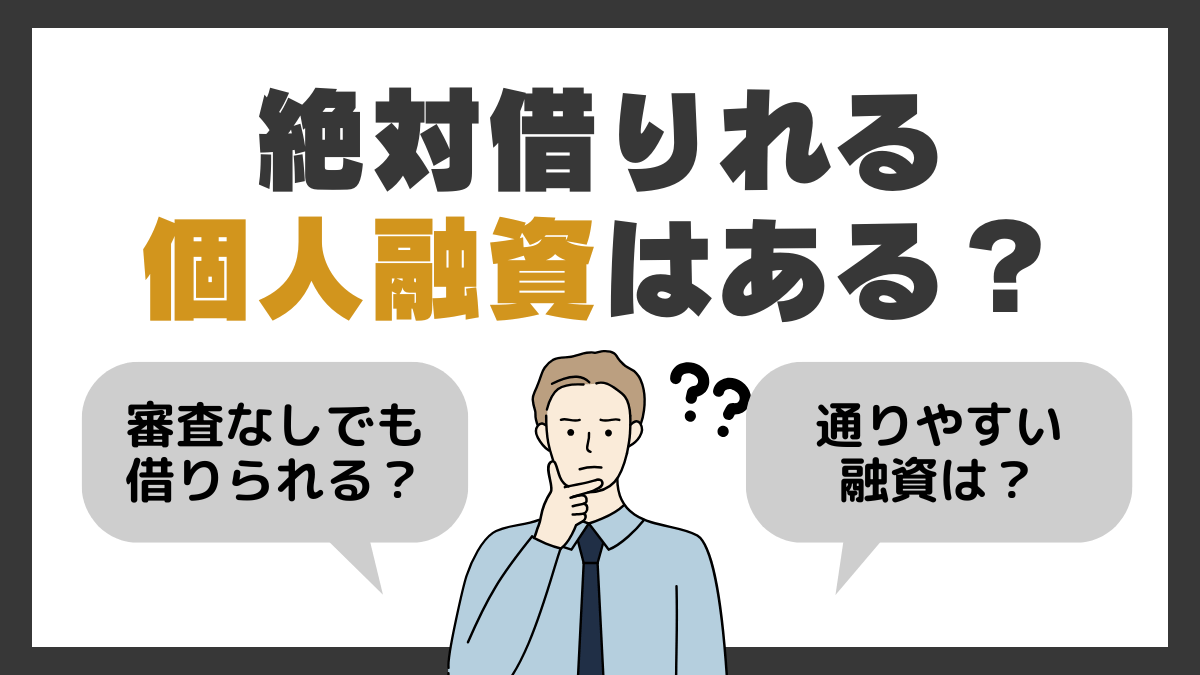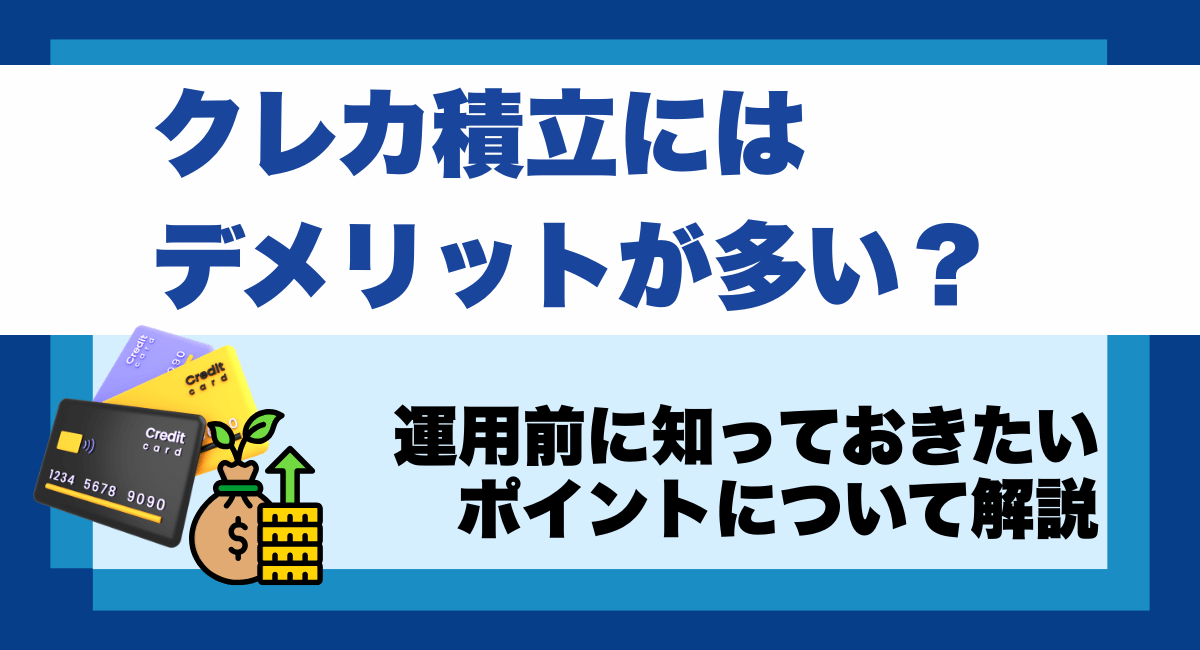金融リテラシー(マネーリテラシー)は、豊かな人生を送るための必須スキルです。お金に関する知識や判断力を高めることで、経済的・心理的な安定と自由を手に入れることができます。
金融リテラシーが高い人と低い人では、どのような特徴や違いがあるのでしょうか?金融リテラシーの重要性と、それを高める方法についてわかりやすく解説します。
より豊かな人生を送るために、あなたのお金との付き合い方を見直してみましょう。
目次
金融リテラシー(マネーリテラシー)とは
金融リテラシー(マネーリテラシー)とは、お金に関する知識や判断力のことです。具体的には、
- 日々の家計管理
- 資産形成
- ローンや保険の仕組み
など、人生を通じてお金と上手く付き合うために必要な知識やスキルを指します。まずは、金融リテラシーを理解するために重要なポイントを確認しておきましょう。
家計管理が基本!
適切な収支管理は金融リテラシーの基礎となります。固定費の見直しや支出項目のチェックなどから収入と支出を把握し、赤字を解消して黒字を確保する習慣を身につけることが重要です。
家計管理によって黒字をキープすることで、計画的な資産形成や緊急時の備えが可能になります。
生活設計とライフプランニング
先を見通しにくい現代だからこそ、長期的な視点で自身の人生設計を行い、それに基づいた資金計画を立てることが求められます。
- 結婚
- 住宅購入
- 子育て
- 老後
など、ライフステージごとに必要な資金を見積もり、計画的に準備することが大切です。
金融商品の理解
効率的な資産形成のためには、
- 預金
- 株式
- 投資信託
- 保険
など、さまざまな金融商品の特徴やリスクを理解することが必要です。各商品のメリット・デメリットを把握し、自分に合った選択ができるよう、金銭感覚を磨くことが求められます。
リスク管理とセーフティネット
また、予期せぬ事態に備えるため、保険や緊急時の資金準備の重要性を理解することも金融リテラシーの一部です。また、詐欺や悪質商法から身を守るための知識も必要不可欠です。
情報リテラシーと批判的思考
金融に関する情報を適切に収集・分析し、信頼できる情報源を見極める能力も重要です。SNSやインターネット上の情報を鵜呑みにせず、冷静に、また理論的に判断する姿勢が求められます。
このような金融リテラシーを身につけることで、より豊かで安定した人生を送ることができます。日々の学習と実践を通じて、お金に関する知識と判断力を磨いていくことが大切です。
次の章では国民の金融教育の在り方の指標としてつくられた「金融リテラシーマップ」について解説していきます。*1)
金融リテラシーマップとは
金融リテラシーマップとは、「最低限身に付けるべき金融リテラシー」の内容を年齢層別に体系的・具体的に示したものです。日本の金融教育を効果的に推進するためのガイドラインとして機能することが期待されています。
金融リテラシーマップは、以下の4つの分野で構成されています。
- 家計管理:収支の適切な管理方法を学び、日々の金銭管理スキルを身につける
- 生活設計:将来のライフプランを明確にし、それに応じた資金確保の必要性を理解
- 金融知識及び金融経済事情の理解:契約の基本、金利などの基礎知識、金融商品の特徴やリスクについて学ぶ
- 外部の知見の適切な活用:金融商品を利用する際に、適切な情報源から助言を得る重要性を理解
各4分野について、簡単に内容を確認していきましょう。
家計管理
| 小学生 | 必要なものと欲しいものを区別する能力を養う簡単な家計の収支計画を立てる習慣を身につける |
| 中学生 | 家計の収入・支出の仕組みを理解する学校活動等を通じて実践的な収支管理を行う |
| 高校生 | 家族の一員として家計全体を意識した支出管理を行う必要に応じてアルバイト等で収支改善を図る |
| 大学生 | 収支管理の必要性を深く理解し、実践する将来の能力向上のための支出を計画的に行う |
| 若手社会人 | 家計の担い手として適切な収支管理を行う趣味や自己啓発のための支出を計画的に組み込む |
| 一般社会人 | 家計簿等を活用し、収支や資産・負債を総合的に管理する必要に応じて収支改善や資産負債のバランス調整を行う |
| 高齢者 | リタイア後の収支計画に基づいた管理を行う年金収入や資産取り崩しを考慮した生活設計を実践する |
家計管理は、日々の収支を適切に把握し、計画的な金銭管理を行うための基本的なスキルを身につける分野です。年齢層に応じて、収支のバランスや優先順位付けの重要性を学びます。
生活設計
| 小学生 | 勤労の重要性と将来への貯蓄の意識を養う計画的なお金の使い方の大切さを理解する |
| 中学生 | 自分の価値観に基づいた生活設計を立てる練習をする将来の自立に向けた基本的な力を養う |
| 高校生 | 進路選択を通じて将来の自分像を具体的に描く大まかな生涯収支の概要を把握する |
| 大学生 | 卒業後の職業を見据えたライフプランを具体化する夢や目標の実現に向けた行動計画を立てる |
| 若手社会人 | 人生の三大資金(教育・住宅・老後)を意識した生活設計を行う計画的な貯蓄・資産運用を開始する |
| 一般社会人 | 職業との両立を図りながらライフプランの実現に取り組む環境変化に応じてライフプランや資金計画を適宜見直す |
| 高齢者 | リタイア後のライフプランを余暇活用や社会貢献も含めて見直す年金受給額を基準とした安定的な生活スタイルを確立する |
生活設計は、将来のライフプランを考え、それに応じた資金計画を立てる能力を養う分野です。各年齢層で、短期的な目標から長期的な人生設計まで、段階的に学習を進めます。
金融・経済知識や適切な金融商品の選択
| 小学生 | 身近な金融トラブルの実態を知る情報を活用して適切な選択をする力を養う |
| 中学生 | 契約の基本概念を理解する悪質商法の見分け方と被害防止策を学ぶ |
| 高校生 | 契約と自己責任の関係を深く理解する消費生活に関する情報収集と活用スキルを身につける |
| 大学生 | 金融商品に関する法令や制度を理解する慎重な契約締結など、適切な対応力を養う |
| 若手社会人 | 金融商品の3つの特性(流動性・安全性・収益性)を理解するリスクとリターンの関係を踏まえた自己責任での商品選択を行う |
| 一般社会人 | 経済動向が金融商品に与える影響を理解する生活設計に基づいた資産形成戦略を実践する |
| 高齢者 | 高齢期における保険の必要性と種類を理解する※リスクに応じた適切な保険商品を選択する※ |
金融・経済知識や適切な金融商品の選択の分野では、金融・経済の基本的な仕組みから、具体的な金融商品の特性やリスクまでを学びます。年齢とともに、より複雑な金融商品や投資の概念を理解していきます。
※高齢者は、公的保険である「後期高齢者医療制度」に加入します。この内容と自己負担額を具体的に把握したうえで、合理的な方法で備えましょう。
外部の知見の適切な活用
| 小学生 | 困ったときの相談方法を身につけるトラブル時の相談窓口を知る |
| 中学生 | トラブル解決の具体的方法を学ぶ相談窓口の利用方法を実践的に理解する |
| 高校生 | 金融商品利用時の相談機関の重要性を認識する適切な情報源からの情報収集方法を学ぶ |
| 大学生 | 金融商品の利用判断に必要な情報内容を理解する適切な相談機関やアドバイザーの選び方を学ぶ |
| 若手社会人 | 金融商品選択時の情報収集と判断力を養う専門家のアドバイスを適切に活用する方法を学ぶ |
| 一般社会人 | 複雑な金融商品の選択やリスク管理に専門家の知見を活用する定期的な金融アドバイスの受診を習慣化する |
| 高齢者 | 成年後見制度の知識を得る高齢者向け金融商品やサポートシステムについての情報を収集し、適切に活用する |
外部の知見の適切な活用は、金融に関する相談や情報収集の方法を学び、適切な外部リソースを活用する能力を養成する分野です。年齢に応じて、相談先の範囲を広げ、より専門的な助言を得る方法を学びます。
金融リテラシーは、年齢やライフステージによって求められるものが異なります。金融リテラシーマップを活用することで、それぞれのライフステージに合った金融知識を認識し、子どもの金融リテラシー教育に役立てたり、自分に足りない知識やスキルを見つけることができます。*2)
金融リテラシー(マネーリテラシー)が高い人の特徴
金融リテラシー(マネーリテラシー)は、経済的な安定と豊かな人生につながる重要な知識です。金融リテラシーが高い人の主な特徴やスキルには以下のようなものが挙げられます。
適切な家計管理ができる
金融リテラシーの高い人は、収支のバランスを把握し、無駄な支出を抑えつつ、計画的な貯蓄を行います。将来の資金需要に備えることができ、経済的な安定性が高まります。
多様な金融商品を理解し、活用できる
預金、株式、投資信託など、さまざまな金融商品の特徴やリスクを理解し、自身の目的に合わせて適切に選択・活用します。これにより、効率的な資産形成が可能となります。
リスク管理能力が高い
予期せぬ出来事に備え、適切な保険加入や緊急時の資金準備をしています。また、投資においても、リスクとリターンのバランスを考慮した判断ができます。
情報収集と分析力が高い
経済ニュースや金融情報を積極的に収集し、批判的に分析する能力を持ちます。投資詐欺などの金融トラブルを回避でき、適切な意思決定が可能となります。
長期的視点での生活設計をしている
ライフステージごとの資金需要を予測し、長期的な視点で資産形成や生活設計を行います。将来の経済的不安を軽減することができ、豊かな人生設計が可能になります。
継続的な学習姿勢がある
金融環境の変化に応じて、常に新しい知識を吸収し、スキルアップを図ります。この姿勢が、変化する経済環境への適応力を高めます。
客観的な視点で判断できる
感情に左右されず、論理的な思考に基づいて行動します。また、情報過多の時代であることを理解し、正しい情報かを判断できる能力を持っています。
お金に関する相談ができる相手がいる
金融リテラシーが高い人は、頼れる相談相手を複数持っていることが多いという特徴もあります。信頼できる専門家を見極め、アドバイスを受けることができます。
金融リテラシーが高い人は、お金に関する知識だけでなく、それを活用する能力、そして将来を見据えた計画性も備えています。つまりお金を、
- 貯める力
- 増やす力
- 稼ぐ力
- 守る力
を、バランスよく持っている、と言えます。これらのスキルや知識を身につけることで、余計なリスクを避け、より豊かな人生を送ることができるでしょう。*3)
金融リテラシー(マネーリテラシー)が低い人の特徴
金融リテラシー(マネーリテラシー)が低い人は、お金に関する知識や判断力が不足しているため、さまざまな金融トラブルに巻き込まれやすく、例えば、
- 「お金が足りない」
- 「なかなかお金が貯まらない」
- 「将来の生活が不安」
など、金銭的に悩みやすい傾向もあります。
金融リテラシー(マネーリテラシー)が低い人の、代表的な特徴を確認しておきましょう。
ずさんな家計管理
収支の把握ができず、衝動買いや無駄遣いが多い傾向があります。これが要因で、貯蓄が進まず、急な出費に対応できない状況に陥りやすくなります。
長期的視点の欠如
ライフプランニングの重要性を理解せず、将来の資金需要を見越した準備ができません。結果として、教育資金や老後資金の不足に直面する可能性が高まります。
リスク管理能力の不足
適切な保険加入や緊急時の資金準備を怠り、予期せぬ事態に対して脆弱な状態に置かれがちです。これにより、突発的な出来事で経済的危機に陥るリスクが高まります。
金融商品への無知
預金以外の金融商品に関する知識が乏しく、リスクとリターンの関係を理解していません。そのため、高リスクの投資に手を出したり、逆に資産運用の機会を逃したりする傾向があります。
情報収集・分析力の不足
経済ニュースや金融情報に関心が薄く、情報を適切に分析する能力が欠如しています。これにより、詐欺や悪質な金融商品に騙されるリスクが高まります。
複利効果の理解不足
長期的な資産形成における複利効果の重要性を理解していません。そのため、早期からの投資や貯蓄の機会を逃し、資産形成が遅れる傾向があります。
自信過剰バイアス
自身の金融知識や判断力を過大評価し、実際の能力とのギャップが大きい傾向があります。これにより、リスクの高い金融行動を取りやすくなります。
もしも心当たりがあれば、それを自覚し、継続的な学習と実践を通じて、金融リテラシーを高めていくことが重要です。次の章では、なぜ金融リテラシーを高める必要があるのかに、もっと焦点を当てていきましょう。*4)
金融リテラシー(マネーリテラシー)を身につける理由
現代社会は、お金を取り巻く環境が複雑化し、金融商品も多様化しています。その中で、お金に関する知識や判断力である金融リテラシーは、単なる知識ではなく、豊かな人生を送るための必須スキルとなりました。
なぜ金融リテラシーを高める必要があるのか、さらに具体的に見ていきましょう。
経済的なトラブルを防ぐ
金融リテラシーが低いと、さまざまな経済的なトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。
- 詐欺被害: 特に高齢者を中心に、金融商品に関する詐欺被害が後を絶ちません。巧妙な手口にだまされ、多額の損失を被るケースも少なくありません。
- 多重債務: クレジットカードの使いすぎや、高金利の消費者金融への借入など、多重債務に陥るリスクも高まります。
- 投資失敗: 十分な知識がないまま投資を行い、大きな損失を出してしまう可能性があります。
金融リテラシーを高めることで、詐欺や不適切な借入、リスクの高い投資などの経済的トラブルを回避し、財産を守ることができます。
より豊かな人生を送るため
金融リテラシーを高めることで、単に経済的なトラブルを防ぐだけでなく、より豊かな人生を送ることができます。
- 資産形成: 適切な資産運用を行うことで、将来の生活を安定させ、夢を実現するための資金を準備することができます。
- ライフプランの設計: 住宅購入、教育費、老後資金など、人生の大きなイベントに備えるための計画を立てることができます。
- 経済的な自立: 金融に関する知識を身につけることで、経済的に自立し、自分の人生を主体的に切り開くことができます。
つまり、金融リテラシーの向上は、長期的な視点での資産管理と人生設計を可能にし、経済的な自由度を高めることで、より充実した人生を実現する力となります。
社会全体の活性化に貢献
個人の金融リテラシー向上は、社会全体の活性化にもつながります。
- 消費の活性化: 金融リテラシーが高い人は、消費に関する判断力も高いため、より賢く消費を行い、経済を活性化させることができます。
- 企業の健全な発展: 投資家としての知識を持つことで、企業の経営状況を理解し、より良い投資判断を行うことができます。
- 社会全体の金融リテラシー向上: 自分自身が金融リテラシーを高めるだけでなく、周囲の人にもその重要性を伝えることで、社会全体の金融リテラシー向上に貢献できます。
このように、個人の金融リテラシー向上は、健全な経済活動の促進と社会全体の金融知識の底上げにつながり、持続可能な経済発展に貢献します。
金融リテラシー検定の創設
近年注目されている金融リテラシー検定は、高校生、大学生、新社会人を主な対象とした金融知識と判断力を測る試験です。IBT(Internet-BasedTesting)方式を採用し、パソコンやスマートフォン、タブレットで受験可能なのが特徴です。
この検定は、2022年4月からの
- 高校教育における金融経済教育の拡充
- 成年年齢引き下げに伴う金融教育の必要性の高まり
などを背景に創設されました。この検定に挑戦することで、金融に関する基礎知識や判断力、リスク管理能力などを測ることができ、自分の弱点を認識し、改善点を見つけることができます。
金融リテラシーは、単に知識を持つだけでなく、それを日常生活に活かすべき力です。年齢や職業に応じて、誰もが身につけるべき重要なスキルです。*5)
金融リテラシー(マネーリテラシー)の高め方
金融リテラシーは、具体的にどのように高めていけば良いのでしょうか?具体的で誰でも実践できる例を紹介します。
まずは基礎知識の習得と現状の把握
第一歩として、家計管理や金融・経済に関する基本的な知識を身につけることが重要です。
- 書籍
- オンライン講座
- セミナー
などを活用し、継続的に学習することをおすすめします。
マネビタ:動画で学ぶお金の知恵
【動画で学ぶお金の知恵「マネビタ」】
金融広報中央委員会が提供する「マネビタ」は、金融リテラシーを高めるための優れた無料オンライン教材です。6分野18タイトルの動画講座で構成され、各動画は約15分で視聴可能です。
- 金融と経済
- ライフプラン
- 借入
- 資産運用
- リスク管理
- トラブル回避
など、幅広いテーマを専門家が分かりやすく解説しています。
また、自身の金融リテラシーの現状を具体的に把握することも重要です。これにより、学習の方向性や重点分野を明確にできます。
実践的なスキルの獲得
知識を実践に移すことで、より深い理解と応用力が身につきます。スマホアプリで家計簿をつけたり、投資シミュレーションを行ったりすることで、実践的なスキルを磨くことができます。
実際にシミュレーションする
【金融庁の高校生向け教材】
金融庁が提供するシミュレーターなどを利用して、具体的にお金をシミュレーションしてみましょう。必要な金額やいつ、何にお金が必要かを考える良い機会になります。
【金融庁が提供するNISAのつみたてシミュレーター】
資格や検定に挑戦!
また、金融リテラシーを高めるための実践的なスキルを獲得する方法として、以下の資格をとることも効果的です。これらの資格は、段階的に挑戦することで、体系的に金融リテラシーを向上させることができます。
①金融リテラシー検定
- 身につくスキル:基本的な金融知識、金融判断力
- 難易度:比較的低い
- 習得時間:1〜2ヶ月程度
試験時間は40分で、50問の問題に答えます。合格基準は100点満点中60点以上です。
②簿記3級
- 身につくスキル:基本的な会計知識、財務諸表の読解力
- 難易度:中程度
- 習得時間:2〜4ヶ月程度
簿記は国家資格ではないものの、小規模企業の企業活動や会計実務に対応する、経理関連書類を適切に処理できるスキルが身につきます。
③FP3級
- 身につくスキル:金融商品知識、ライフプランニング、リスク管理
- 難易度:中程度
- 習得時間:3〜6ヶ月程度
正式には「3級FP技能士」と呼ばれ、国家資格です。金融や生活設計に関する基礎知識が身につき、他の国家資格と比較して比較的難易度が低いという特徴もあります。
最新情報のキャッチアップ
金融環境は常に変化しています。経済ニュースや金融庁などの公的機関からの情報を定期的にチェックし、最新の動向を把握することが大切です。
金融リテラシーの向上は、一朝一夕には実現しません。しかし、継続的な学習と実践を通じて、着実に力をつけていくことができます。あなたの経済的な未来を切り開くために、今日から金融リテラシーを高める取り組みを始めてみましょう。*6)
家族に金融リテラシー(マネーリテラシー)が低い人がいる時の対処法
家族や身近な人が、お金のことで適切な判断ができないことに悩む人は少なくありません。家族間の価値観や生活スタイルの違いから、お金についての考え方や使い方で意見が食い違うこともあるからです。
焦らずに、お互いを尊重しながら、少しずつ理解を深めていくことが大切です。
対処方法
家族の金融リテラシーを高めるために、対処方法の例を挙げます。身近な人との関係や対象の人の年齢・性格などをよく考慮して、無理なくできることから始めてみましょう。
買い物や家計管理など、日常的な場面で金融の基本概念を説明し、実践的な理解を促します。
信頼できるファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談し、家族全体の資産管理や将来設計について助言を受けることも有効です。
家族で投資シミュレーションゲームを楽しんだり、金融に関するドキュメンタリーを視聴したりするなど、楽しみながら学べる機会を作りましょう。
金融リテラシーの向上は一朝一夕には実現しません。焦らず、家族全体で継続的に学び続ける姿勢が重要です。また、お金の話が日常的にできる環境づくりも心がけましょう。
家族の金融リテラシーを高めるためには、焦らず、根気強く、そしてお互いを尊重することが大切です。共通の目標を設定し、具体的に家計管理を共有しながら、少しずつ知識を深めていくことで、家族全体がより豊かな生活を送ることができるようになるでしょう。*7)
日本人の金融リテラシーの現状
【日本の現役世代の多くは、お金に関する悩みを抱えながら生活している】
日本の金融リテラシーは、国際的に見て低い水準であることが多くの調査で明らかになっています。特に、若年層や高齢者層では、金融知識が不足している傾向が見られます。
その背景には、
- 学校教育における金融教育の不足
- 社会全体におけるお金の話しにくさ
などが挙げられます。
金融リテラシーの診断方法
家族の金融リテラシーレベルを客観的に把握するには、以下の方法が効果的です。
- 金融広報中央委員会の「金融リテラシー・クイズ」
- J-FLEC(金融経済教育推進機構)の「お金の知識無料診断」
- 日本FP協会が提供する「便利ツールで家計をチェック」
- 家計の収支状況や将来の資金計画について、具体的に話し合う機会を設ける
これらの方法を通じて、家族全体の金融リテラシーの現状を把握し、改善が必要な分野を特定できます。
【金融広報中央委員会の金融リテラシークイズ】
金融リテラシー(マネーリテラシー)に関するよくある質問
金融リテラシー(マネーリテラシー)に関するよくある質問をご紹介します。
金融リテラシー検定は意味ない?テストの勉強方法は?
金融リテラシー検定は「意味がない」と言われることもありますが、実際には非常に実用的な検定です。
金融リテラシー検定は、日常生活で必要なお金の知識や判断力を体系的に学び、実生活に活かすことを目的としています。検定を通じて金融トラブルや詐欺から自分を守る力が身につき、資産形成やライフプランの実現にも役立ちます。
勉強方法としては、公式テキストを熟読し、出題形式に慣れることが重要です。過去問題や模擬試験を活用し、知識問題だけでなく、文章題や判断力を問う問題にも対応できるようにしましょう。試験は40分間で50問、60点以上で合格となります。
金融リテラシーは何歳から教育したほうがいい?
金融リテラシーの教育は、できるだけ早い段階から始めるのが理想です。
多くの専門家や教育現場では、子どもがお金の存在を認識し始める幼児期から小学校低学年がスタートの目安とされています。親と一緒に買い物をしたり、お小遣いを管理したりする中で、お金の流れや価値を体験的に学ぶことができます。
小学校中学年以降は、実際に一定額のお小遣いを管理させることで、計画的なお金の使い方や貯蓄の大切さを学ばせることが推奨されています。
金融教育は年齢や発達段階に合わせて段階的に進めることが重要で、早い時期から始めることで、将来的な経済的自立やトラブル回避の力を育むことができます。
金融リテラシーが低いとどんなリスクがある?
金融リテラシーが低いと、日常生活でさまざまなリスクに直面する可能性があります。たとえば、詐欺や悪質な金融商品に騙されやすくなったり、クレジットカードの使い過ぎや借金の返済遅延など、家計管理の失敗に陥りやすくなります。
また、保険や投資など将来に備えるための金融商品を正しく選べず、無駄な出費や資産の目減りにつながることも考えられるでしょう。
金融リテラシーは、安心して豊かな人生を送るための基礎的な力と言えます。
金融リテラシー(マネーリテラシー)とSDGs
【投資を通じて社会課題の解決に貢献】

金融リテラシーの向上は、SDGsの目標達成に重要な役割を果たします。適切な金融知識を持つ個人は、自身の経済状況を改善するだけでなく、社会全体の経済的安定にも貢献するからです。
また、金融リテラシーの高い個人は、投資を通じて社会課題の解決に貢献する可能性が高まります。例えば、ESG投資(環境・社会・ガバナンスを考慮した投資)の理解と実践は、持続可能な社会の構築に資金を提供します。
【ESG:環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)】

金融リテラシーが特に関係するSDGs目標を確認していきましょう。
SDGs目標1:貧困をなくそう
金融リテラシーの向上は、貧困撲滅に大きく貢献します。適切な金融管理能力を身につけることで、個人は収入を効果的に管理し、貯蓄や投資を通じて経済的安定を図ることができます。
また、
- マイクロファイナンス(低所得者や零細企業に対して小口の融資や金融サービスを提供する仕組み)
- 金融包摂(すべての個人や企業が適切な金融サービスにアクセスできる状態を目指す取り組み)
などへの理解が進むことで、低所得者層の金融サービスへのアクセスが改善され、貧困からの脱却を支援します。
SDGs目標4:質の高い教育をみんなに
金融教育は質の高い教育の重要な一部です。学校教育や社会人教育を通じて金融リテラシーを向上させることで、生涯にわたる学習の基盤を築くことができます。
デジタル金融サービスの普及と同時に、オンライン学習プラットフォームを活用した金融教育の提供も増加してきました。これによって、より多くの人々が質の高い金融教育を受けられるようになります。
SDGs目標8:働きがいも経済成長も
金融リテラシーの向上は、個人の経済的自立を促進し、労働市場への参加を支援します。適切な金融知識を持つ個人は、キャリア選択や起業の際に、より効果的で適切なリスクをとった決定を下すことができます。
また、金融リテラシーは、持続可能な経済成長に必要となる健全な金融システムの構築にも貢献します。個人投資家の育成は、資本市場の活性化につながり、経済成長を促進します。
SDGs目標12:つくる責任 つかう責任
金融リテラシーは、責任ある消費と生産の促進にも貢献します。金融知識を持つ消費者は、サステナブルな製品やサービスを選択する傾向が高まります。
資本家の間でESG投資への理解が進むことで、企業の持続可能な事業活動を促進し、責任ある生産体制の構築に貢献します。金融機関による環境配慮型金融商品の開発と、消費者によるそれらの選択は、持続可能な消費と生産のサイクルを強化します。
一見あまり関係なさそうに見えるかもしれませんが、金融リテラシーは、SDGsの達成に不可欠な要素です。金融リテラシーを高めることで、私たちはより良い社会の実現に貢献することができます。*8)
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ
金融リテラシー(マネーリテラシー)は、現代において詐欺被害や多重債務などのリスクを回避し、自身の人生設計を主体的に行うために、すべての人に必要です。さらに、ESG投資などを通じて、社会課題の解決にも貢献できます。
「金融リテラシーが低い」と感じた人は、日々の家計管理から始め、徐々に金融知識を深めていきましょう。デジタルマネーや家計簿アプリを利用すれば、簡単に収支記録や全体の把握ができます。
金融リテラシーの向上は、決して難しいものではありません。一歩ずつ着実に進めていけば、必ず成果が表れます。あなたも、より豊かで安定した未来のために、今日から金融リテラシーを高める取り組みを始めてみませんか?
<参考・引用文献>
*1)金融リテラシー(マネーリテラシー)とは
政府広報オンライン『「金融リテラシー」って何? 最低限身に付けておきたいお金の知識と判断力』(2024年10月)
政府広報オンライン『18歳、19歳の皆さん、ご用心!成人になると増える、こんな消費者トラブル ~18歳から大人~』(2023年6月)
JPX『金融リテラシーとは何?意味や身につけるべき最低限の知識を解説』(2023年9月)
MUFG『金融リテラシーって何?20代前半で身に付けておきたいお金の知識と判断力』(2022年3月)
日本銀行『金融リテラシー ~人生を豊かにする「お金」の知恵~』(2020年2月)
NOMURA『金融リテラシーの向上』
金融庁『高校生のための金融リテラシー講座』
金融庁『ライフステージに応じた金融リテラシーについて』(2022年4月)
J-FLEC『(高校生向け)大人になる前に知っておきたいお金の話』(2024年)
国民生活センター『若者の金融リテラシー育成と金融教育』(2022年1月)
日本経済新聞『金融リテラシーと家計資産(1) 資産蓄積を助ける要素』(2024年9月)
*2)金融リテラシーマップとは
厚生労働省『金融リテラシー・マップ』(2014年6月)
J-FLEC『金融リテラシー・マップ「最低限身に付けるべき金融(お金のリテラシー知 識 ・ 判 断 力 )」の項目別・年齢層別スタンダード 』(2023年6月)
日本FP協会『学校における金融リテラシー教育― 今後の課題と提言について』(2015年)
MUFG『相続・承継(財産管理・処分)リテラシー教育について考える』
NOMURA『金融リテラシーの向上』駒村 康平著『みんなの金融 良い人生と善い社会のための金融論』(2022年3月)
金融広報中央委員会『金融リテラシー・マップ』
日本証券業協会『中学校・高等学校における金融経済教育のさらなる拡充に向けた要望書の提出について』(2024年4月)
家森 信善『若者の金融リテラシーと学校における金融経済教育―新しい学習指導要領の円滑な導入に協力を―』(2020年6月)
*3)金融リテラシー(マネーリテラシー)が高い人の特徴
日本銀行『金融リテラシー~人生を豊かにする「お金」の知恵~』(2020年2月)
政府広報オンライン『「金融リテラシー」って何? 最低限身に付けておきたいお金の知識と判断力』(2024年10月)
Money Forward『資産にも大きな開き…金融リテラシーが高い人と低い人の違いとは? 初心者が知識を身につける方法をお金のプロが解説』(2022年11月)
RECRUIT『マネーリテラシーを備えた社会人になろう!』(2024年3月)
MUFG『従業員エンゲージメントと金融リテラシーの関係性について』(2020年11月)
MUFG『金融リテラシー1万人調査の概要 - 男女・年代による金融リテラシーと投資行動の特徴 【若年層編】』(2018年9月)
Yahoo!ニュース『【富裕層の特徴】元証券マンが「お金持ちとそうでない人の特徴一覧」を解説。お金持ちは金融リテラシーが高い?』(2024年8月)
財務省『国民の資産形成と金融リテラシー』(2020年3月)
財務省『金融経済教育の日英比較と日本への示唆―EBPM 的視点から― 』(2024年6月)
日本経済新聞『金融リテラシーと家計資産(3) 物価変動と生活設計』(2024年10月)
全国銀行業協会『わが国家計の資産形成に資する金融制度・税制のあり方』(2018年3月)
総務省『メディア情報リテラシー向上施策の現状と課題等に関する調査結果報告』(2022年6月)
*4)金融リテラシー(マネーリテラシー)が低い人の特徴
日本経済新聞『複利が苦手な日本人 未来を想像できる金融リテラシーを』(2023年8月)
日本経済新聞『金融リテラシー、「自信過剰」こそリスク 人生100年こわくない・資産活用で笑おう(野尻哲史)』(2023年5月)
JPX『Vol.335 連載企画第六回「金融リテラシーと投資行動との間の因果関係②」』
日本経済新聞『本来の金融リテラシーはどこに』(2023年8月)
NOMURA『金融リテラシーとファイナンシャル・ウェルネス』(2022年)
金融広報中央委員会『「金融リテラシー調査2022年」の結果』(2022年7月)
内閣府『平成20年度 年次経済財政報告第5節 リスクマネーの供給と家計・金融機関のリスク対応力』(2008年)
日本取引所グループ『デリバティブ取引と金融リテラシー』(2023年7月)
東証マネ部!『若年層には「金融教育を受けたと自覚しているものの金融リテラシーが低い人」が多い可能性あり!? 日本人の金融行動を測る「金融リテラシー調査」の結果を見る!』(2022年12月)
J-FLEC『(高校生向け)大人になる前に知っておきたいお金の話』(2024年)
信託協会『日本の個人投資家のリスク資産投資』(2020年11月)
金融庁『4 「貯める・増やす」 ~ 資産形成』
法政大学『金融リテラシー、リスク・リテラシーと個人の金融資産形成』(2024年3月)
金融庁『金融リテラシーと家計の消費行動:新型コロナウイルス感染拡大下の実証分析 』(2022年7月)
金融庁『事務局説明資料』(2022年9月)
金融庁『行動経済学の金融経済教育への応用 -行動バイアスからマインドセット・バイアスへ- 』(2016年1月)
日本FP学会『金融リテラシー調査(2022年)からみえる金融教育の課題』(2022年9月)
*5)なぜ金融リテラシー(マネーリテラシー)を高める必要があるのか
国民生活センター『若者の消費者トラブル』(2024年12月)
国民生活センター『そのメール、フィッシング詐欺!』(2024年11月)
政府広報オンライン『暗号資産の「必ずもうかる」に要注意!マッチングアプリやSNSをきっかけとしたトラブルが増加中』(2024年9月)
金融庁『暗号資産に関するトラブルにご注意ください!』(2021年4月)
金融財政事情研究会『金融リテラシー検定』
金融庁『金融経済教育研究会報告書(案)』
日本証券業協会『日本の金融経済教育』
消費者庁『令和2年版消費者白書 2部 第2章 第4節 2.消費者教育の推進』(2020年)
日本経済新聞『本来の金融リテラシーはどこに』(2023年8月)
日本経済新聞『[社説]国民の金融リテラシー向上が欠かせない』(2023年7月)
日本経済新聞『自信生まれる「お金の学び」』
JPX『Vol.335 連載企画第六回「金融リテラシーと投資行動との間の因果関係②」』
東証マネ部!『「大谷翔平選手」に学ぶ見えざる資本 日経記事で学ぶ ~幸福寿命を延ばす投資術2』(2024年10月)
日本経済新聞『金融リテラシーと家計資産(5) 人々の金融リテラシーのレベル』(2024年10月)
日本経済新聞『金融詐欺被害に潜む「自信過剰」』(2024年3月)
JPX『Vol.332 連載企画第三回「日本と諸外国との金融リテラシー水準の比較」』
JPX『金融リテラシーを学ぶ理由とは?求められる3つの背景をわかりやすく解説』(2023年10月)
*6)金融リテラシー(マネーリテラシー)の高め方
金融広報中央委員会『動画で学ぶお金の知恵「マネビタ」』
金融庁『金融経済教育 高校授業副教材 私たちの生活にかかわるお金について勉強してみよう!』
金融庁『つみたてシミュレーター』
日本経済新聞『マネーリテラシー高めて収入増 お金の勉強どこから?』(2023年12月)
日本FP協会『金融リテラシーに関するeラーニング講座「マネビタ~人生を豊かにするお金の知恵~」』
J-FLEC『金融トラブルにあわないためには』
日本経済新聞『マネーリテラシー高めて収入増 お金の勉強どこから?』(2023年12月)
経済産業研究所『金融リテラシー高めるには 中立的立場からの助言重要』(2023年8月)
日本経済研究センター『複利を理解していない日本人』(2015年8月)
MUFG『金融リテラシーって何?20代前半で身に付けておきたいお金の知識と判断力』
厚生労働省『金融リテラシー・マップ 』(2014年6月)
金融広報中央委員会『金融リテラシー浸透の障壁 その改善策とは』
日本経済新聞『金融リテラシー向上で未来つかむ 資産運用で得る幸福』(2023年1月)
日本経済新聞『幸福のためのお金 Life is Beautiful, Life is Money!』(2023年2月)
日本経済新聞『自分に最適化されたマネープランをつかみ取る力』(2023年2月)
JPX『金融リテラシーとは何?意味や身につけるべき最低限の知識を解説』(2023年9月)
金融広報中央委員会『「生活スキル」としての金融リテラシー ~金融教育と消費者教育の連携がますます重要に~』
日本FP協会『金融リテラシーに関するeラーニング講座「マネビタ~人生を豊かにするお金の知恵~」』
金融財政事情研究会『金融リテラシー検定』(2024年)
*7)家族に金融リテラシー(マネーリテラシー)が低い人がいたらどうすればいい?
金融庁『金融経済教育等の推進に向けた調査等支援業務(職域等における金融経済教育を推進するための手法等に関する調査)』(2024年3月)
J-FLEC『お金の知識力無料診断』
日本FP協会『便利ツールで家計をチェック』
神谷 哲司『ファイナンシャル・リテラシー尺度開発の現状と課題』(2016年11月)
日本年金学会『金融リテラシーと独身男女のライフプラン』(2021年12月)
鄭 美沙『若年層のリスク性資産購入経験と金融トラブル経験に関する実証分析』(2021年9月)
野村資本市場研究所『ライフサイクル投資の考え方とその課題』(2018年)
日本経済新聞『金融リテラシーと家計資産(6) 精緻な教育効果の測定が重要』(2024年10月)
日本経済新聞『金融リテラシーと家計資産(8) 「貯蓄から投資へ」の流れ』(2024年10月)
日本経済新聞『あなたの「マネー力」がズバリ分かる5つの質問』(2017年3月)
MUFG『あなたの「金融リテラシー」は?』(2022年1月)
Yahoo!ニュース『「学校で学べない」「どう教えれば」……“お金の教育”どうする? 「金融リテラシー」低い日本ナゼ』(2024年5月)
世界経済フォーラム『女性の金融リテラシーを高め、豊かな人生100年時代を』(2024年4月)
北野 友士, 小山内 幸治, 西尾 圭一郎『学校・家庭・社会が金融リテラシーに与える影響の検証』(2022年)
大学ジャーナル『金融リテラシーと経済学的思考を身に付けよう』(2024年12月)
NOMURA『家庭における金融教育の意義とは何か?』
NOMURA『家計管理にも資産運用にも必須! 金融リテラシー調査に見る 80年代生まれ世代の特徴は?』(2017年9月)
伊藤 宏一『高齢者の金融ケイパビリティ問題と相談・支援体制』
日本経済新聞『投資詐欺、実体験に学ぶ手口 なりすましや恋愛感情悪用』(2024年8月)
日本FP協会『【金融経済教育の浸透に課題】約9割の教員が金融経済教育の必要性を実感するも生徒への浸透率は1
強』(2024年7月)
*8)金融リテラシー(マネーリテラシー)とSDGs
金融庁『高校生のための金融リテラシー講座』(2022年3月)
金融庁『金融行政とSDGs』(2018年12月)
大和総研『SDGs と金融経済教育 』(2019年8月)
日本経済新聞『資料①SDGs 17の目標』(2021年)
野村資本市場研究所『SDGsと金融経済教育の推進』(2020年9月)
この記事を書いた人
松本 淳和 ライター
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。