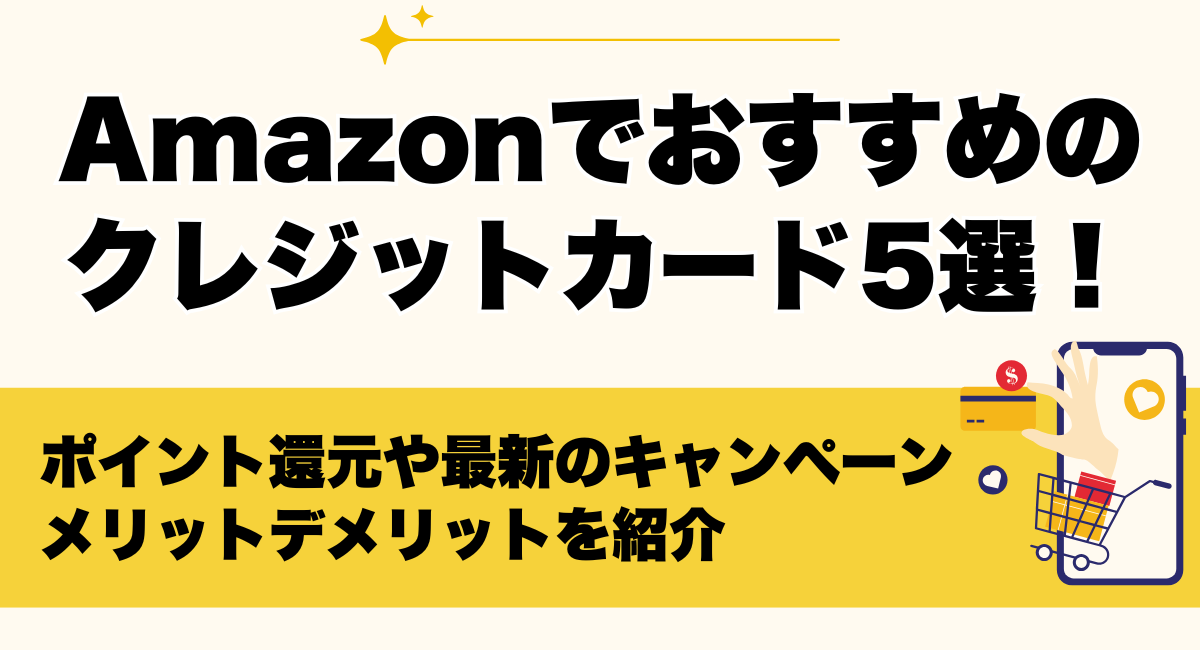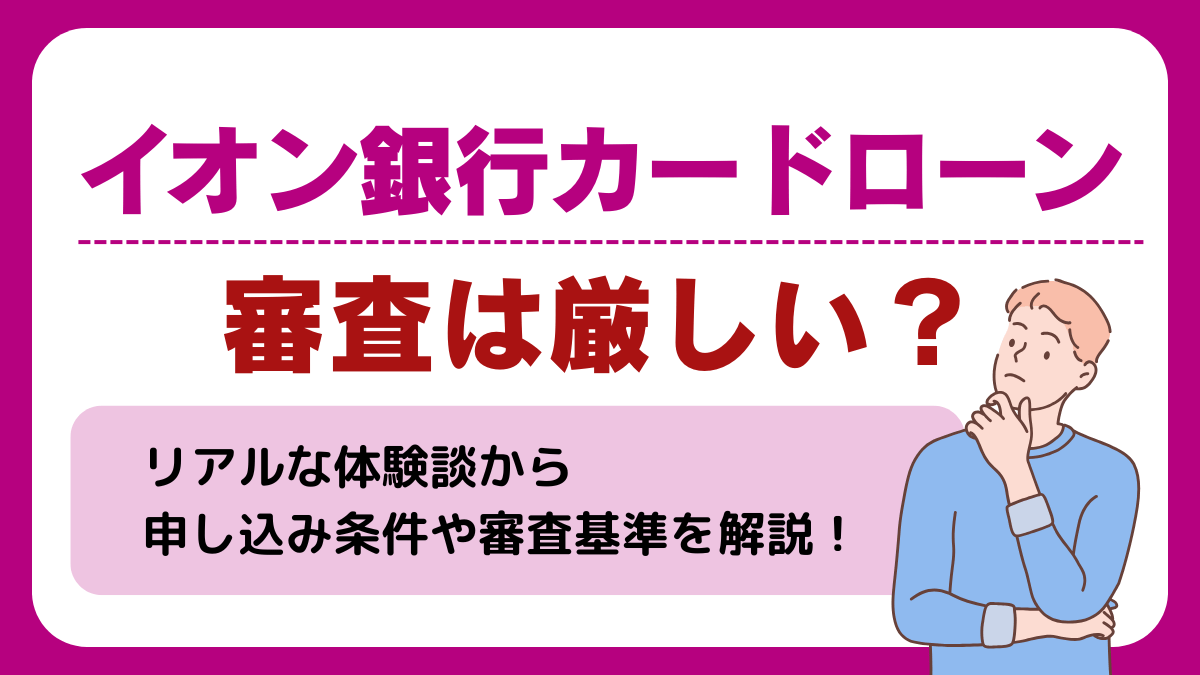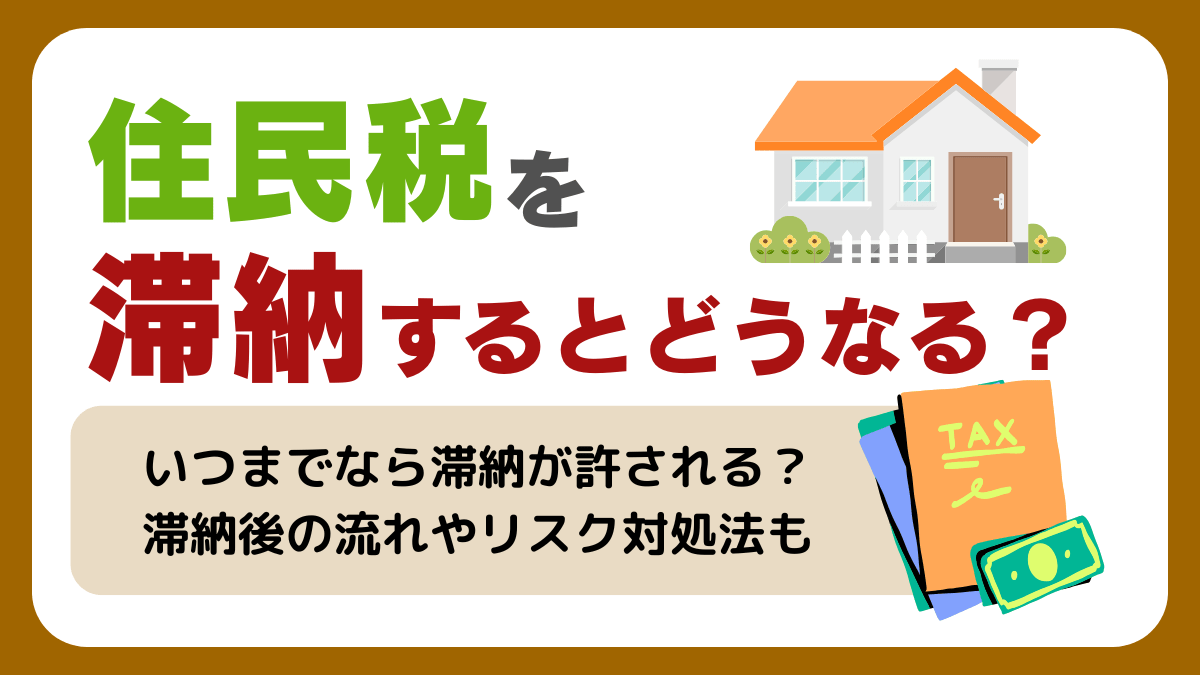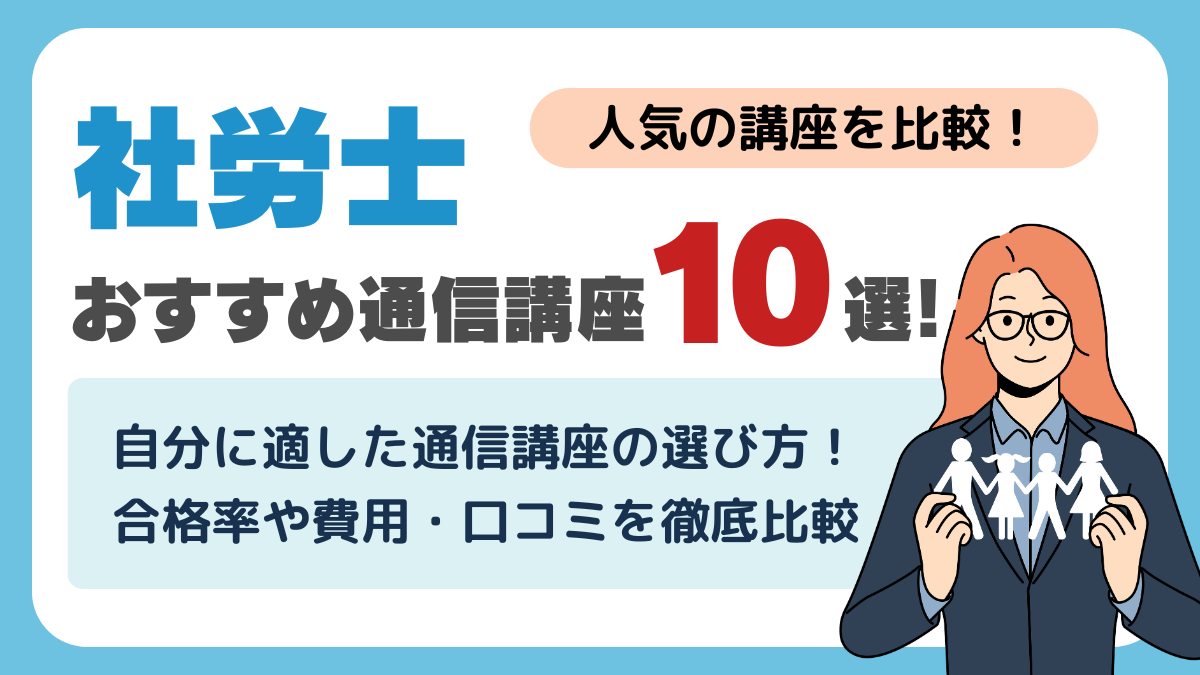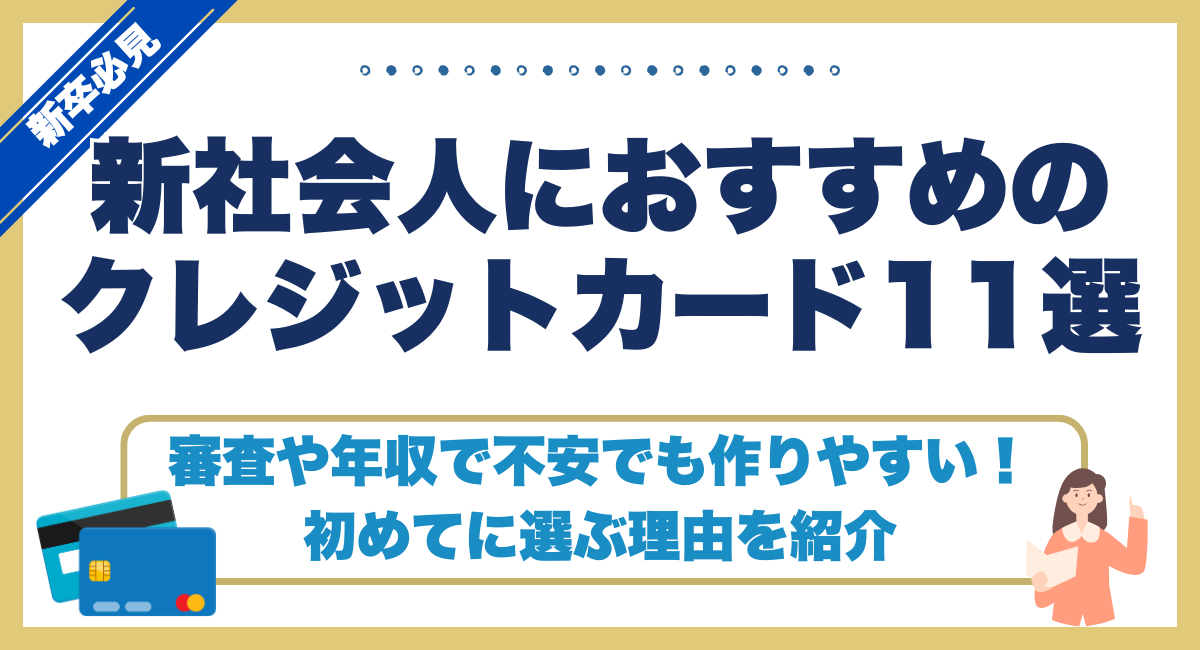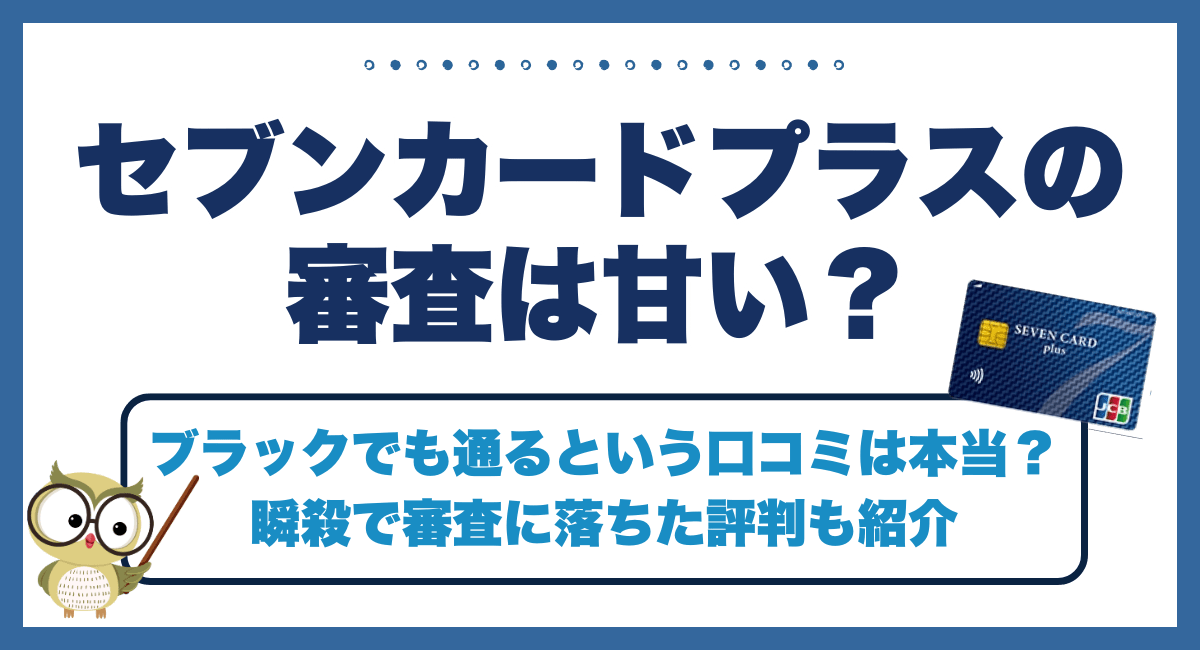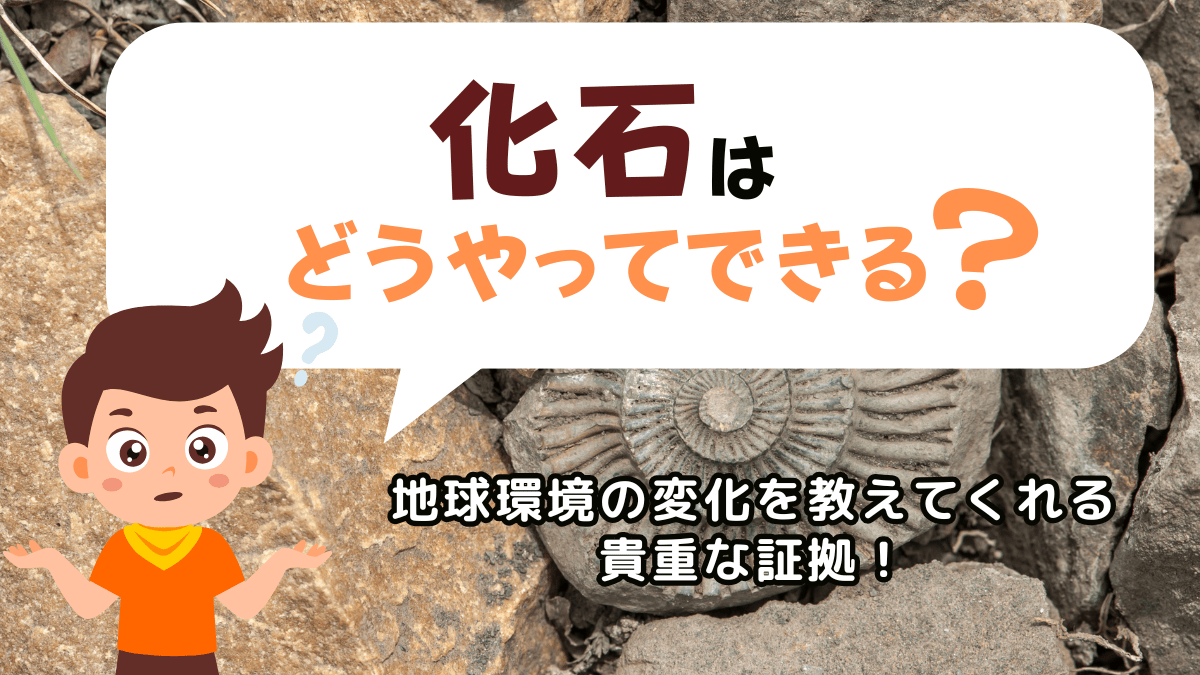
太古の昔、地球に生きた恐竜や生き物たち。彼らの姿は時を超え化石として現代に伝えられています。では、あなたは化石のでき方を知っていますか?
化石は地球環境の変化を教えてくれる貴重な証拠です。各地で発見される、アンモナイトや恐竜、植物やプランクトンなど、さまざまな化石から、私たちは多くの情報を知ることができます。
「化石とは何か」から、化石の種類、でき方、発掘方法など、化石研究の基本をわかりやすく解説します。
目次
化石とは

太古の痕跡を今に伝える化石は、地球の歴史を紐解く鍵として、私たちに多くの情報をもたらしてくれます。化石は、古生物学という学問分野で研究されており、35億年にわたる生命の記録を私たちに残してくれています。
それでは、化石について、もっと詳しく見ていきましょう!
化石の定義
化石とは、過去の生物の遺骸や活動の痕跡が、地層や岩石の中に保存されたものを指します。化石として残っている物の代表的な例として、
- 生物の骨や殻
- 葉の跡
- 足跡
などが挙げられます。これらの化石は、地球の歴史や過去の環境を知る上で重要な手がかりとなります。
示準化石と示相化石
化石には、示準化石と示相化石という2つの重要な分類があります。
示準化石
示準化石は、地層の年代を特定するのに役立つ化石です。短い期間に広い地域に分布し、その後絶滅した生物の化石が示準化石として使われます。
例えば、
- 三葉虫:カンブリア紀(約5億2100万年前)〜ペルム紀(約2億5200万年前)
- アンモナイト:デボン紀(約4億1900万年前)〜白亜紀(約6600万年前)
- フズリナ:石炭紀(約3億5890万年前)〜ペルム紀(約2億5200万年前)
- イノセラムス:ジュラ紀(約2億100万年前)〜白亜紀(約6600万年前)
- 貨幣石(カヘイ石):始新世(約5600万年前)〜中新世(約500万年前)
などが有名です。
【地層の時代と代表的な示準化石】
示相化石
示相化石は、過去の環境を推定するのに役立つ化石です。特定の環境に生息していた生物の化石が示相化石となります。
例えば、
- サンゴ:暖かく浅い海
- シジミ:湖や河口
- アサリ・カキ・ハマグリ:浅い海
- ブナの葉:温帯のやや寒冷な地域
- マンモス:寒冷な気候
などが代表的です。
化石からわかること
化石は過去の生物や環境について多くの情報を提供してくれます。主に以下のようなことがわかります。
- 生物の進化の過程
- 過去の気候や環境の変化
- 大陸の移動や地殻変動の歴史
- 絶滅イベントとその原因
恐竜の化石であれば、
- 体の構造
- 生態
- 生息していた年代
- 絶滅の原因
などを推測する重要な手がかりとなります。
化石研究の最前線
現代の化石研究では、最新の技術を駆使して以前より詳細な分析が行われています。CTスキャンやX線などの技術を用いて、化石の内部構造を調べることができるようになりました。
また、DNA分析技術の進歩により、比較的新しい化石からDNAを抽出し、遺伝子レベルでの研究も可能になっています。これらの研究は、生物の進化や環境変動の理解を深めるだけでなく、現代の生態系保全や気候変動対策にも役立つ重要な知見をもたらしています。
化石は、地球の過去を解き明かす鍵であり、私たちの未来を考える上でも重要な役割を果たしています。次の章では、化石の種類について見ていきましょう。*1)
化石の種類
【スピノサウルスの復元骨格】
化石は、太古の生命や環境の痕跡を今に伝える貴重な証拠です。その形態や保存状態によって、さまざまな種類に分類されます。
化石には、大きく分けて3つの種類があります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
体化石

体化石は、生物の体の一部または全体が化石化したものです。骨、歯、貝殻などが代表的な例です。
アンモナイトや三葉虫の化石は、体化石の中でも特に有名です。体化石は、古生物の形態や構造を直接観察できるため、進化の研究に重要な役割を果たしています。
生痕化石
【福井県勝山市の恐竜化石発掘現場で発見された足跡化石面】
生痕化石は、生物の活動の痕跡が化石として残ったものです。例えば、
- 足跡
- 巣穴
- 這い跡
- 糞
などが挙げられます。生痕化石は、古生物の行動や生態を推測する上で貴重な情報源です。
恐竜の足跡化石からは歩き方や群れの行動など、糞からは何を食べていたかなどを推測することができます。
化学化石
化学化石は、生物由来の有機物が化石化したものです。
- 石油:主に海洋プランクトン
- 天然ガス:主に海洋プランクトン
- 石炭:主に陸上の植物、特に大型のシダ植物
などが代表的な例です。これらは、古代の生物が堆積物中で分解されずに残り、長い年月をかけて変化したものです。ただし、化石燃料の形成は現在も続いており、比較的新しい時代(第三紀※など)に形成されたものもあります。
これまでに発見された化石の種類
これまでに発見された化石の種類は実に多様で、25万種以上にも及びます。最近の発見では、2025年1月に中国で新属新種の竜脚形類が発見され、リシュロン・ワンギ(Lishulong wangi)と名付けられました。
また、2025年2月にはアメリカで北半球最古の恐竜化石が発見され、アーヴェイタム・バーンドゥーイヴェチェ(Ahvaytum bahndooiveche)と命名されています。日本でも2025年1月に福井県で原始的なスッポンの仲間、アドクス科プロアドクス属の化石が発見され、日本初の記録となりました。
【福井県で発見されたプロアドクス属の化石】
【甲羅(左:背甲/右:腹甲)の発見部位(着色部分)】
このように、化石の新発見は、私たちの古代生物に対する理解を常に更新し、太古の地球の姿をより鮮明に描き出します。
これまでに発見された数多くの化石は、それぞれ異なる情報を私たちに提供してくれます。*2)
化石のでき方
【珪化木(木の化石)】
化石ができる過程は、生物の死から始まり、数百万年から数億年という長い時間をかけて完成します。化石ができるまでには、何が必要なのでしょうか?
化石形成の条件
化石になるためには、特定の条件が必要です。化石ができる主な条件には以下の3つがあります。
①迅速な埋没:生物の遺骸が速やかに堆積物に覆われること
生物が死んだ後、すぐに土や泥に覆われることがとても重要です。これにより、遺骸が散らばったり、他の動物に食べられたりすることを防ぎます。
つまり、「速やかな埋没」が、化石の形成に欠かせない第一歩となります。
②酸素の遮断:腐敗を防ぐため、酸素との接触を断つこと
遺骸が酸素に触れると、バクテリアによる分解が進みやすくなります。酸素を遮断することで、腐敗の進行を遅らせることができます。
このような「酸素の遮断」は、水中や泥の中など、酸素が少ない環境で起こりやすく、化石の保存状態を良好に保つ重要な要因です。
③適切な環境:温度や圧力、化学的条件が適していること
化石が形成されるには、
- 低温であること
- 適度な圧力がかかること
- 周囲の化学成分が骨や殻を溶かさないこと
など「適切な環境条件」が必要です。これらの条件が揃うことで、長い時間をかけて遺骸が鉱物に置き換わり、化石として保存されます。
化石形成のプロセス
化石形成は以下の段階を経て進行します。
- 生物の死亡と埋没
- 軟組織の分解
- 硬組織の保存または置換
- 地層の形成と圧密
このプロセスは通常、数百万年以上の時間を要します。例えば、恐竜の骨が化石化するには、少なくとも1000万年以上かかると考えられています。
特殊な化石形成
時には、驚くほど保存状態の良い化石が発見されることがあります。2017年に発見されたボレアロペルタ※は、白亜紀前期の地層から発掘された非常に保存状態の良い装甲恐竜の化石です。
【白亜紀前期の地層から発見された非常に保存状態の良いボレアロペルタ】
この化石は、皮膚や鱗、さらには体色の痕跡まで残っており、古生物学者に貴重な情報を提供しています。また、琥珀に閉じ込められた昆虫や小動物の化石も、驚くほど詳細な情報を保持しています。
樹脂に閉じ込められた生物は、酸素から遮断され、ほぼ完全な状態で保存されることがあるのです。
化石燃料の形成
化石は、古代の生物が変化してできたものですが、その中には私たちの生活に欠かせないエネルギー源となるものもあります。それが、化石燃料です。
化石燃料の起源
石油や石炭などの化石燃料は、古代の植物やプランクトンなどの遺骸が、地中で長い年月と圧力をかけられて変化したものです。これらの有機物は、地中で熱分解され、液体や気体の炭化水素へと変化します。
化石燃料のでき方
化石燃料は以下のような過程を経て生成されます。
- 植物プランクトンや動物プランクトンの死骸が海の底に沈む
- バクテリアによって分解され、ヘドロ状になる
- その上に土砂が堆積
- 長い年月をかけて石油や天然ガスに変化する
化石燃料と環境問題
化石燃料は、私たちの生活に不可欠なエネルギー源ですが、燃焼時に二酸化炭素を排出し、地球温暖化の原因となることが問題視されています。そのため、近年では再生可能エネルギー※への転換が世界中で進められています。
化石は、偶然と奇跡が重なり合って生まれた、太古の記憶を閉じ込めたタイムカプセルです。化石のでき方を理解することは、過去の生態系や環境を解明する上でとても大切です。
また、化石燃料の形成過程を知ることは、現代のエネルギー問題を考える上でも重要な視点を提供してくれます。*3)
化石の発掘方法

化石の発掘は、太古の生命の痕跡を現代に蘇らせる魅力的な作業です。しかし、それには適切な知識と技術、そして忍耐力が必要です。発掘の手順、必要な道具、そして注意点について確認していきましょう。
【発掘の準備】
まずは化石発掘を始める前に、適切な装備を整えることが重要です。また、発掘場所は慎重に選定しましょう。
地質図や過去の発掘記録を参考に、化石が見つかる可能性の高い場所を特定します。また、必要な許可を取得することも忘れずに行いましょう。
必要な道具
発掘には以下の道具が必要です。
- ハンマーとタガネ:岩石を割るための基本的な道具
- ブラシ:化石の周りの土や岩を取り除くため
- ルーペ:小さな化石や細部を観察するため
- 保護具:ゴーグル、手袋、ヘルメットなど
- 記録用具:ノート、カメラ、GPS機器
発掘の手順
【野外恐竜博物館での化石発掘体験の様子】

化石の発掘は、慎重さと専門知識を要する作業です。ここでは、化石発掘の基本的な手順を詳しく見ていきましょう。
①地層の表面を注意深く観察し、化石の兆候を探す
まず、地層の表面をじっくりと観察します。化石の一部が地表に露出していることもあります。
色の変化や特徴的な形状に注目し、化石の存在を示す手がかりを探します。時には、ルーペを使って細かな部分まで確認することも大切です。
②化石の周りを慎重に掘り進める
化石の兆候を見つけたら、その周りを慎重に掘り進めます。ハンマーやタガネを使いますが、化石を傷つけないよう細心の注意を払います。
少しずつ岩を削り、化石の輪郭が見えてきたら、さらに慎重に作業を進めます。
③化石を含む岩塊全体を取り出す
化石の全体像が見えてきたら、周囲の岩ごと取り出します。化石だけを取り出そうとすると、壊れてしまう可能性があるためです。
④発見場所、日時、地層の状態などを詳細に記録する
発見した場所のGPS座標、日時、地層の状態、周囲の環境などを、可能な限り詳しく記録します。スケッチや写真撮影も行いましょう。
これらの情報は、後の研究で非常に重要になります。化石の価値は、こうした詳細な記録とセットであることを忘れないでください。
⑤化石の運搬
発掘した化石は慎重に運搬する必要があります。化石を新聞紙で包み、クッション材で保護します。大型の化石の場合、石膏で覆って保護することもあります。
⑥クリーニング
発掘現場から持ち帰った化石は、専門的な技術を用いてクリーニングします。この過程では、化石を傷つけないよう細心の注意を払いながら、周囲の岩石や土を取り除きます。
化石の発掘は、適切な知識と技術、そして忍耐が必要な作業です。しかし、何百万年も前の生命の痕跡を自らの手で掘り出す経験は、比類のない興奮と発見の喜びをもたらしてくれます。*4)
化石とSDGs

化石研究は、地球の過去の気候変動や生態系の変化を明らかにし、現代の地球が抱える課題への理解を深める上で重要な情報を提供します。また、化石燃料に依存しない持続可能なエネルギー源の開発や、生物多様性の保全にも役立つ研究です。
つまり、一見あまり関係のあるように見えない化石研究は、SDGsの目標達成に向けた重要な役割を担っているのです。化石研究が特に貢献できるSDGs目標について見ていきましょう。
SDGs目標4:質の高い教育をみんなに
化石は、地球の歴史や生命の進化を学ぶ上で非常に効果的な教材です。博物館での化石展示や教育プログラムは、子どもから大人まで幅広い層に科学教育を提供し、環境意識を高めることができます。
また、化石発掘体験などのアクティビティは、実践的な科学教育の機会を提供し、SDGs目標4の達成に貢献します。
SDGs目標7:エネルギーをみんなに そしてクリーンに
化石燃料は、現代社会のエネルギー源として欠かせない存在ですが、地球温暖化の主な原因の一つでもあります。化石の研究は、過去の地球の気候変動を解明し、温暖化の影響を予測する上で重要な情報を提供します。
また、化石燃料に代わる新たなエネルギー源、例えば地熱エネルギーやバイオ燃料などの開発にも貢献します。具体的には、
- 過去の地層から有機物の分解過程を解析し、バイオ燃料の生成効率を高める研究
- 地熱活動の活発な地域の地質構造を調査し、地熱発電の可能性を探る研究
などが進められています。
SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を
化石記録は過去の気候変動の証拠を提供します。例えば、氷河期の化石や温暖期の化石を研究することで、気候変動のメカニズムや生態系への影響を理解することができます。
このような知識は、現在の気候変動対策の立案や予測モデルの改善に活用され、SDGs目標13の達成に向けた具体的な行動につながります。
SDGs目標14:海の豊かさを守ろう
海洋生物の化石研究は、海洋生態系の長期的な変化を理解する上で重要です。過去の海洋環境の変化と生物の適応や絶滅の過程を研究することで、現在の海洋保護政策の立案に貢献できます。
また、化石燃料の使用削減を促すことで、海洋酸性化の防止にも間接的に貢献し、SDGs目標14の達成を支援します。
SDGs目標15:陸の豊かさも守ろう
陸上生物の化石研究は、陸域生態系の進化と変遷を明らかにします。このような知識は、現在の生物多様性保全策の立案に活用されます。
また、化石記録から過去の大量絶滅イベントを研究することで、現在の生物多様性の危機に対する警鐘を鳴らし、保全活動の重要性を訴えることができます。これらの活動は、SDGs目標15の達成に向けた具体的な貢献となります。
まとめ
【最古の人類である可能性が提唱されるサヘラントロプスの化石】
化石は、太古の地球からのメッセージであり、その研究は地球の過去、現在、そして未来を繋ぐ重要な役割を担います。化石の研究は、
- 気候変動を理解する
- 生き物の多様性を守る
- 資源を大切に使う
など、現代の私たちにとって大切なことに役立っています。
例えば、深海に眠る希少なレアアース泥の生成過程に、微生物の化石が関与している可能性が指摘されています。これは、持続可能な資源開発と環境保全の両立に向けた新たな道を開くかもしれません。
また、2025年度から福井県立大学に日本初の「恐竜学部」ができます。化石研究の新たな扉を開き、未来の古生物学者や地球科学者を育成する画期的な機会となるでしょう。
ぜひ、あなたも博物館に行ったり、化石発掘体験に参加したりして、化石についての知識を深めてください。化石について学ぶことで、地球の歴史を知り、未来のことを考えることができます。
化石はまだまだ研究の余地がある、魅力にあふれた研究分野です。同時に化石研究は、地球の過去を解き明かすだけでなく、現代の環境問題解決への鍵も握っています。
気候変動や生物多様性の危機に直面する今、化石から学ぶ知識は私たちの未来を守る重要な手がかりとなります。化石について学ぶことを通じて、地球の歴史のロマンを感じながら、持続可能な未来を創造する鍵を見つけることができるのです。
恐竜学部のように、新しい学びの場も生まれています。あなたの探究心と情熱が、将来この分野に革新をもたらし、地球科学の新たな境地を切り開くかもしれません。*5)
<参考・引用文献>
*1)化石とは
福井県立恐竜博物館『地層の時代はどうしてわかるの?』
地質調査総合センター『化石』
地質調査総合センター『化石からわかること ①』
原子力発電環境整備機構『地層と化石~地層の年代を調べてみよう~』
福井県立恐竜博物館『化石ってなに?冷凍マンモスは化石なの?』
福井県立恐竜博物館『化石はどうやってできるの?』
福井県立恐竜博物館『恐竜の足跡からなにがわかるの?』
愛媛県総合科学博物館『生痕化石 -化石になった生きものの生活のあと-』
島根半島・宍道湖中海ジオパーク『示準化石と示相化石』
四国西予ジオバーク『5 化石の意味と化石からのメッセージ』
茨城県自然博物館『化石研究所へようこそ! -古生物学のすすめ-』
笠岡市立カブトガニ博物館『生きている化石(展示物)』(2011年3月)
京都大学『はじめての古生物形態学』
東京大学総合研究博物館『化石の付加価値』
大阪県立博物館『化石とは何か』
九州大学『地球惑星博物学研究室』
九州大学『小さな化石から過去の地球環境変動を探る』
九州大学総合研究博物館『前田 晴良 MAEDA, Haruyoshi』
北海道大学総合研究博物館『古生物学』
前田 晴良『アンモノイド化石を起点としたタフォノミーの挑戦』(2018年2月)
松隈 明彦『九州大学の化石研究と標本』
NATIONAL GEOGRAPHIC『第5回 恐竜を研究する意味』
日本経済新聞『数億年前から同じ姿の「生きた化石」5選、絶滅危惧種も』(2024年4月)
*2)化石の種類
WIKIMEDIA COMMONS『Spinosaurus skeleton』
福井県立恐竜博物館『日本初のプロアドクス属カメ化石について』
福井県立恐竜博物館『恐竜の分けかたは?』
福井県立恐竜博物館『これまでに何種類の恐竜が発見されているの?』
福井県立恐竜博物館『恐竜の卵の化石は、どの種類の恐竜のものかわかるの?』
福井県立恐竜博物館『化石の色に違いがあるのはなぜ?』
兵庫県立人と自然の博物館『4 種類のアンモナイトを見分けよう』
富山市科学博物館『恐竜足跡化石の見つけかた』
徳島県立博物館『宍喰町竹ケ島周辺の地層と生痕化石【野外博物館】』(1995年6月)
地質調査総合センター『「生痕化石―大地に刻まれた生命の痕跡」開催報告』(2024年1月)
兵庫県教育委員会『1.岩石、鉱物の見分け方と化石の取り扱い』
HONDA『デビューの倍率はアイドル以上!?奇跡きせきの存在そんざい「化石」に会いに行こう』
佐川地質館『珍しい化石』
島根半島・宍道湖中海ジオパーク『新生代の化石』
中国地質調査業協会『地層と化石』
九州大学『九州大学百年の宝物』(2011年2月)
九州大学総合研究博物館『九州大学の化石標本』
九州大学総合研究博物館『津屋崎や百道浜でも見られる!芦屋層群の生痕化石』
千葉大学『生痕化石から探る古生物の行動生態とその進化』(2018年4月)
東條文治,安井 謙介『示準化石教材に使用するゴニアタイト化石の分類群について』(2017年)
成田 敦史『葉化石から推定する古気候―基本原理と教育への応用―』(2018年6月)
*3)化石のでき方
WOKIMEDIA COMMONS『PetrifiedWood』
WIKIMEDIA COMMONS『Nodosaur』
Australian Museum『How do fossils form?』(2016年11月)
福井県立博物館『化石はどうやってできるの?』
福井県立恐竜博物館『福井県の恐竜発掘 化石ができるまで』
福井県立恐竜博物館『骨が化石化するにはどのくらいの時間がかかるの?』
大阪自然史博物館『化石のでき方』
富山市科学博物館『足跡化石のできかた』
九州大学総合研究博物館『高くなりすぎたヒマラヤ』
環境科学技術研究所『化石(2) 分子化石』(2005年1月)
土屋 建『化石になりたい よくわかる化石のつくりかた (生物ミステリーPRO)』(2018年7月)
NATIONAL GEOGRAPHIC『なぜ琥珀から極上の化石が発見されるのか?』(2023年4月)
NATIONAL GEOGRAPHIC『椎の化石を南半球で初めて発見、なぜすごい?』(2019年6月)
日本経済新聞『恐竜時代最後の貴重な光景を伝える、驚きの化石群を発見』(2023年11月)
日本地質学会『アメリカ合衆国ユタ・コロラド州境界、ダイノソー・ナショナル・モニュメントとユインタ山』
地層科学研究所『しんかしないしんかい魚、シーラカンスの話―深部の環境特性と、地層処分を考える―』(2013年9月)
製品評価技術基盤機構『石油のなりたち』
*4)化石の発掘方法
WIKIMEDIA COMMONS『化石発掘体験』
American Museum of Natural History『Techniques』
American Museum of Natural History『Techniques in the Field』
Arizona Museum of Natural History『Field Methods』
Australian Museum『How are fossils found and excavated?』(2016年7月)
CARNEGIE MUSEUM OF NATURAL HISTORY『In the Field: Following the Work of a Paleontologist』
Field Museum『Fossil Hunting 101』(2016年10月)
福井県立恐竜博物館『第一次恐竜化石発掘調査』
福井県立恐竜博物館『発掘作業・クリーニング』
九州大学『地球の歴史を調べるための新たな化石研究法』(2024年6月)
沼田町化石館『化石採集に使う道具と方法』
兵庫県立人と自然の博物館『岩石・鉱物・化石の採集と標本の作り方』
NATIONAL GEOGRAPHIC『第2回 恐竜化石の「掘り出し方」』
NATIONAL GEOGRAPHIC『第3回 急斜面から2トンの化石を運び出すには』
*5)まとめ
筑波大学『~恐竜研究は止まらない!~』
福井県立大学『恐竜学部 国内初の恐竜学部、誕生。』
この記事を書いた人
松本 淳和 ライター
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。