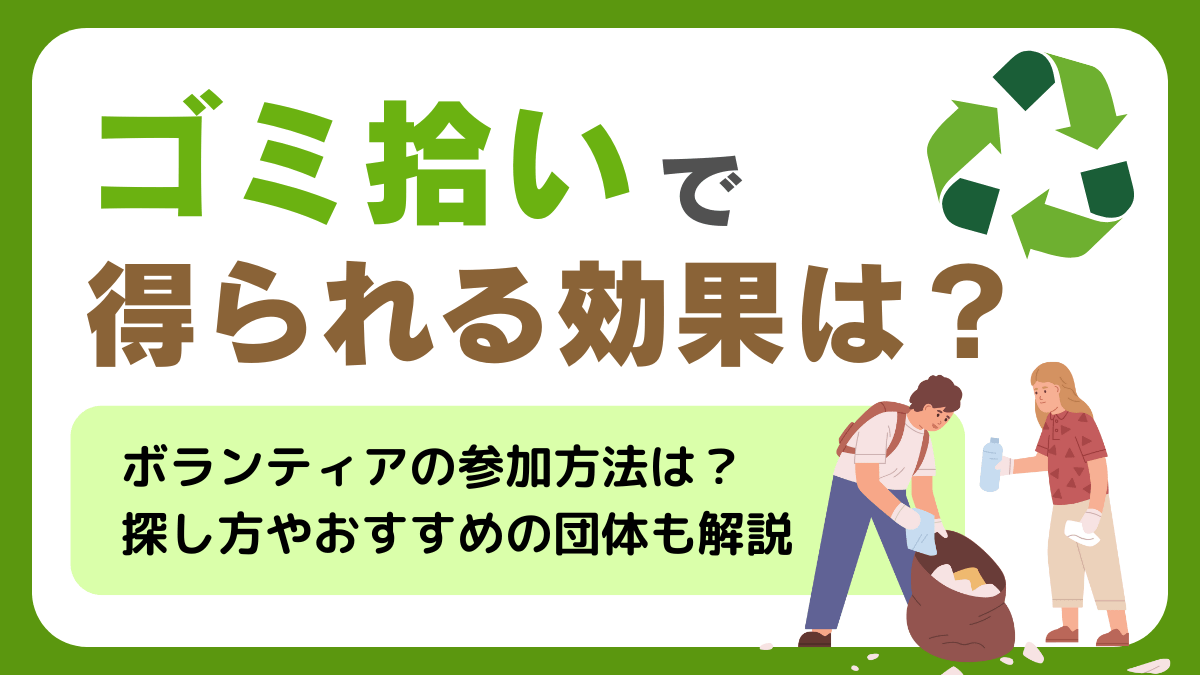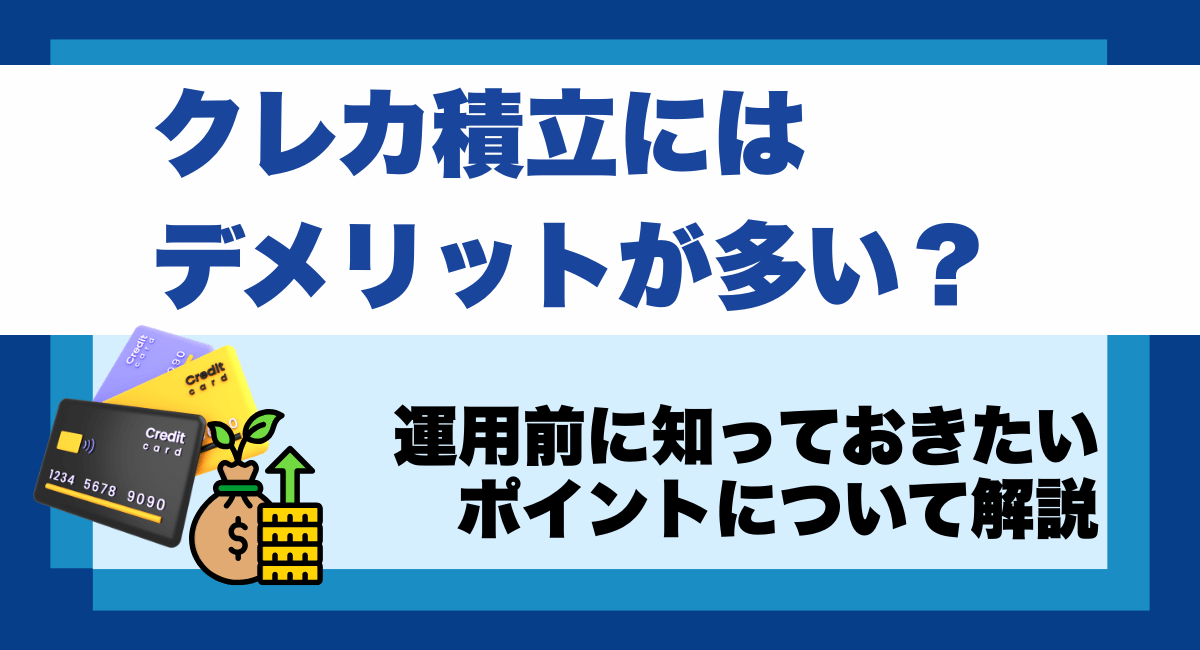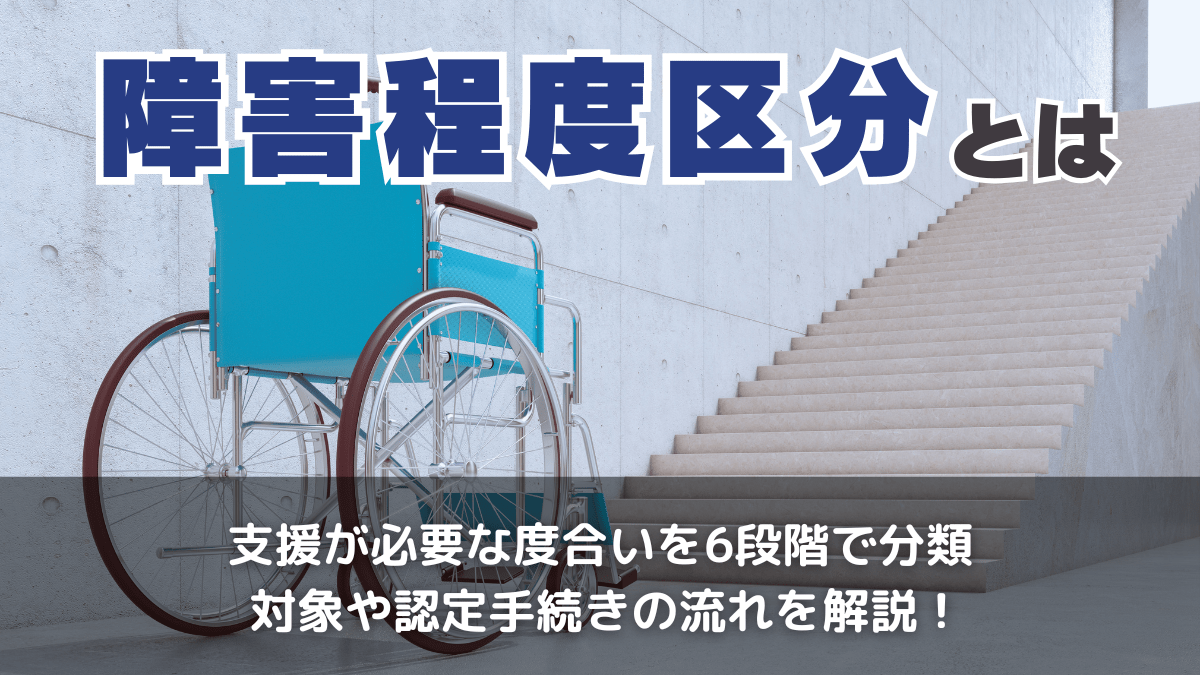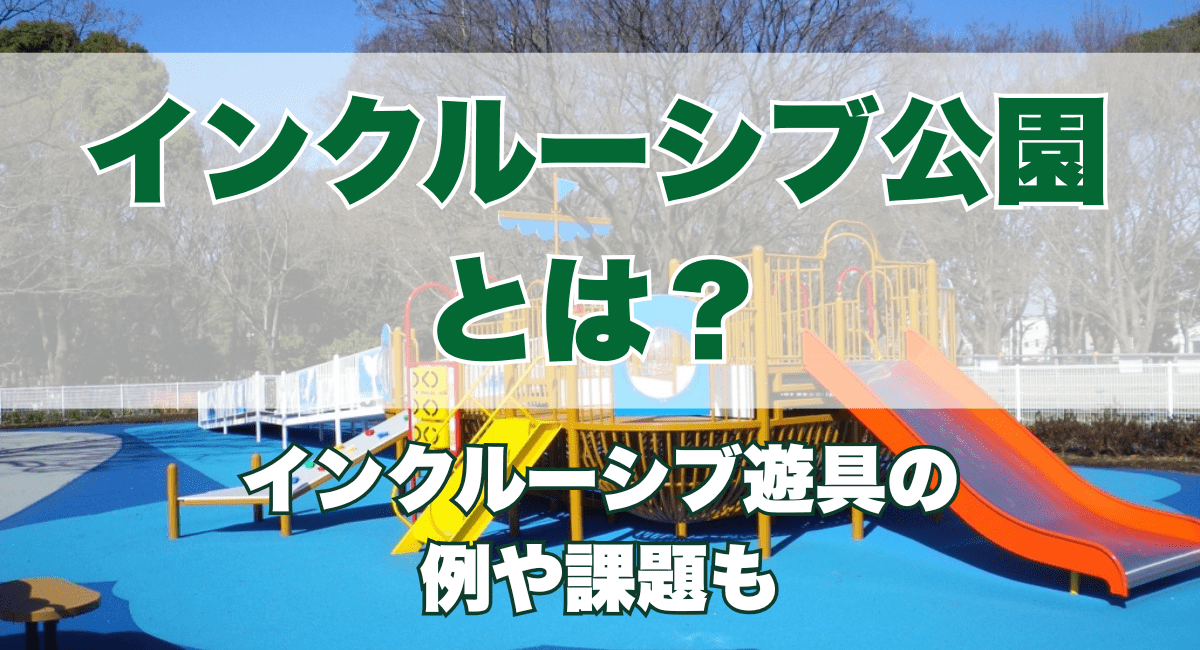日本の少子化対策待ったなしの現在、妊娠・出産・育児を安心して迎えられる環境づくりが求められています。特に経済的不安や育児の孤立など、さまざまな問題を抱える家庭への支援は不可欠であり、そのために現在進められているのが「妊娠期からの切れ目のない支援」です。はたしてこれが現状の支援の不足や制度の課題を克服するものになるのか。本記事では、その必要性と課題について考え、より充実した支援のあり方を探ります。
目次
切れ目のない支援とは
妊娠期からの切れ目のない支援とは、妊娠・出産から子育てまでの広い範囲で切れ目が起こらないような包括的な子育て支援を行うことです。
特に貧困や孤立、障害など、困難を抱えている母子のいる家庭では、出産や育児に関する支援制度をうまく利用できないことが少なくありません。そうした個々の複雑な事情に対応するためには、より柔軟で包括的な支援が必要となります。
そのため、従来の枠組みではうまく機能せずに生じていた切れ目をなくすために設けられる枠組みが、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援と呼ばれるものです。
具体的な「切れ目」とは?

では、従来の子育て支援で生じていた「切れ目」とは、具体的にどのようなことを言うのでしょうか。
組織のつながりのなさによる支援の切れ目
切れ目を生じさせる原因のひとつは、子育て支援に関わる諸機関同士での連携が取れていないことです。例えば同じ自治体でも、市町村の保健センターと保健所、児童相談所と保育所・幼稚園、NPO支援団体など、支援を行う機関はたくさんあります。しかし、それらはお互いがどんな支援をどこまで行っているかの情報共有が十分でないため、個別の対応になってしまうことが少なくありません。
年齢による切れ目
もうひとつの切れ目は、子どもの成長に伴う支援機関の変化などによって、必要な支援が止まってしまうことです。
例えば何らかの困難を抱えた子どもの支援について
- 母子保健〜保育・幼児教育、学校教育への移行時に支援情報の引き継ぎが不十分
- 家族が他の自治体に転出する時に転入先の支援機関への情報伝達が不十分である
などによって、孤立や虐待のリスクを見落としてしまうなどがあげられます。
特に、就学前の5歳はこうした切れ目が生じやすいとされています。
支援関係の切れ目
その他の切れ目としては、支援を求める当事者と関係機関との関係がスムーズにいかないという問題があります。
現在は、どの家庭でも子育てが困難な状況に陥る可能性を秘めています。にもかかわらず、支援者との信頼関係の構築ができないために、何かしらの問題を抱えていたり育児に悩む母親ほど周りに頼れない、または頼りたがらないことが少なくありません。
また、地域における支援の担い手不足や、関係機関同士の連携不足によって、一見重大な問題やリスクがないと判断された家庭には、潜在的に必要とされている支援が行き届かないといったことも起こり得ます。
子ども家庭センターの設置
こうした切れ目の発生を防ぎ、包括的できめ細やかな、切れ目のない子育て支援を行うために全国の市区町村に新たに設置されたのが子ども家庭センターです。
同センターは、従来児童福祉を担っていた「子ども家庭総合支援拠点」と、母子保健を担っていた「子育て世代包括支援センター」が2024年4月に統合された機関です。
令和6年の時点で、子ども家庭センターは876自治体で1,015か所が設置されていますが、これはまだ全国の50.3%に過ぎません。国は市町村に子ども家庭センターの設置を義務付けており、さらに全国展開を進めています。
切れ目のない支援が必要とされる背景

現在の子ども福祉において切れ目のない支援が必要になっている背景には、いくつかの理由がありますが、
孤立化する子育て家庭の増加
切れ目のない支援が必要となっている背景には、子育て家庭が孤立化しつつあるという現状があげられます。これには日本の家族構成の変化が大きく影響しており、
- 核家族が増え、子どもを見てくれる祖父母がいない
- 特に都市部において隣近所や地域のコミュニティとの付き合いがない
などによって周囲とのつながりが弱くなり、「地域で子どもを見守る」といった働きかけも少なくなっていきます。そしてこうした状況は妊娠、出産や子育てについての妊産婦の不安や負担を増やし、特に問題を抱える家庭はより孤立化しやすくなっていきます。このため、地域レベルでの切れ目のない支援の重要性が高まっています。
困難を抱える母子の増加

また近年は、子育て家庭が抱える問題がより多様化、深刻化しており、その数も増加傾向にあります。いくつかの例をあげると
- 若年層の望まない妊娠
- 虐待・DV(家庭内暴力)の増加
- ひとり親家庭、特に母子家庭の増加と経済的困窮
- 障害児、特に発達障害を抱える子どもの増加
- ヤングケアラーの増加
- 移民、外国にルーツを持つ家庭
など、各家庭が抱える問題はさまざまです。そして、こうした問題は必ずしも複雑な背景を抱えた家庭だけではなく、一見問題のなさそうな家庭でも不登校や発達障害などの問題に直面することは珍しくなくなっています。
従来の支援体制の限界
こうした多岐にわたる問題を支援するためには、従来のように個々の事案に別々の機関が担当する支援体制ではカバーしきれません。
前項であげたさまざまな問題は母子保健・児童福祉、学校、児童相談所、さらには障害者支援施設など複数に分かれており、各家庭によって複数の支援拠点にまたがることもあれば、年齢・学齢によっても担当機関が変わります。
そのため前述したような切れ目が生じ、必要とする家庭への支援が滞ることになります。
この切れ目をなくすことが、今回の切れ目のない支援の本丸です。
切れ目のない支援の具体的な内容

子ども家庭センターでは、今回の組織再編によってより包括的で、切れ目のない支援を行うことを目指しています。その主な内容は以下のような取り組みがあります。
母子保健機能の業務
子ども家庭センターでは、母子保健機能を強化して妊娠期から特に3歳までの切れ目のない支援をマネジメントします。
具体的には、次の1~4の業務を通じて、妊産婦と乳幼児、その家族の現状を継続的に把握して必要なサービスや支援を提供するため、関係機関との連携や連絡・調整を行い、その後の経過をフォローして評価を行います。
- 妊産婦や乳幼児の状況の継続的な把握と記録・管理:保健師などによる面談や家庭訪問、関係機関からの情報
- 妊娠・出産・育児に関する相談への対応と情報提供・助言・支援・保健指導
- 妊産婦や乳幼児等の課題やニーズに対応するためのサポートプラン策定
- 保健医療または福祉関係機関との十分な連絡調整:連絡調整支援の継続性と整合性確保
児童福祉機能の業務
子ども家庭センターでは、それまで児童相談所が担ってきた家庭相談を市町村の責務とするため、児童相談所などとの連携のもと子育て支援事業を実施することになりました。
その具体的な業務には、以下のようなものがあります。
- 子ども家庭支援全般業務
- 虐待予防・早期発見に視点を置いた支援
- 要支援児童などへの支援
- 特定妊婦(出産前後に特に支援を必要とする妊婦)の把握と支援
- 家庭支援事業の利用勧奨と措置
- ヤングケアラー支援
関係機関との連携
子ども家庭センターによる切れ目のない支援業務のためには、地域において母子保健機能・児童福祉機能を限定的に捉えることなく、民間を含む多様な関係機関との日常的な連携が必要です。
主なものだけでも
- 都道府県・市町村
- 医療機関・保健センター・保健所
- 児童相談所
- 保育所、幼稚園、小中高等学校、教育委員会
- 家庭支援事業やこども食堂など民間を含む子育て支援関係事業
- 児童養護施設
- 里親・ファミリーホーム
- 障害者支援機関
- NPO・ボランティア
など、連携が求められる機関は多岐に渡ります。
子ども家庭センターは、これらの関係機関や担当者と顔の見える関係性や信頼関係を築き、支援を必要とする子どもや、家庭を協力して支援できる体制づくりを行うとしています。
障害のある子どもと家族への支援
子ども家庭センターでは障害児(発達支援が必要な子どもも含む)やその家庭への支援にあたっては、児童発達支援センターや障害児相談支援事業所、障害福祉部局などと連携してサポートプランの作成などを行うことになります。
具体的には、
- 障害のある子どもと家族への相談
- 相談支援専門員による障害児支援利用計画案を作成
- 障害児通所/入所支援および障害福祉サービス支援につなげる
- すでにサポートプラン対象児の場合は障害児相談支援事業所と積極的に情報共有を行う
などといった支援事業をサポートしていくことになります。
切れ目のない支援のメリット

子ども家庭センターによる切れ目のない支援が本格的に始まることで、妊産婦や子育て支援に対するさまざまなメリットが期待されています。
親・家庭の負担軽減
切れ目のない支援で最も期待されるメリットは、ワンストップで総合的な相談や支援を提供することで、利用者が別々に相談する負担を軽減できるようになることです。
地域のさまざまな機関が連携することで、利用者の困りごとの内容や子どもの年齢・学齢などにかかわらず、継続的な支援を一元的に提供することで、安心して子育てができる環境を整えていくことができます。
疾病や虐待、障害の早期発見につながる
切れ目のない支援体制が確立されることで、妊産婦や子どもの身体的・精神的状態を多方面から、早期に把握・介入することができます。各機関同士で効果的に情報を共有し、適切な相談や健康診断を行うことで、子どもの疾病や障害だけでなく、母親の産後うつや新生児への虐待の有無などの早期発見に結びつけやすくなります。
子どものレジリエンスを支える
包括的で連続的な切れ目のない支援は、子どものレジリエンス(個人や環境の逆境にもかかわらず良好に適応すること)能力を支える上でも有益な役割をはたします。
成長過程のどのような局面でも家庭や地域の関わりにおいて安全な環境や模範となる人、支えてくれる人が複数いることは、さまざまなリスクを防ぐ要因となり、生活や自身の変化に対する継続的・肯定的な適応能力を育む助けになります。
そのためには、切れ目のない支援により公的・私的なつながりを含めた関係性や社会資源を、地域生活の拠点にしっかりと根付かせることが必要です。
切れ目のない支援のデメリット・課題

一方、切れ目のない支援を運用する上では、本当の意味で利用できるものにするためには、従来からの課題や運用で生じるデメリットを克服していかなければなりません。
情報提供の問題
切れ目のない支援の課題のひとつは、利用者への効果的な情報発信です。
実際の現場では支援が必要な子育て家庭にさまざまな支援が実施され、支援者が連携するネットワークも多数あります。にもかかわらず、
- 3か月訪問で保健推進員が教えてくれるまで『拠点』のことを知らなった
- 最初はどこにベビー用品が売っているかわからなかった
- ファミリー・サポートセンターの登録方法を調べるのが面倒
など、利用者への伝わり方が不十分で必要な情報が届かずになかなか利用されない、育児の負担軽減につながっていないという報告事例も少なくありません。
子育て家庭と早期につながるには、SNSなどを利用した情報発信や、一元化した支援者の情報を届けるなど、やり方に工夫が必要といった意見も上がっています。
信頼関係の構築

切れ目のない支援で必要なことは、個と個の関係に基づき、利用者の立場で信頼関係を構築することです。特に複雑な事情を抱えている親の家庭ほど、自分から支援を求めてこない事例は少なくありません。
一例をあげると、他人に相談できない事情で妊娠をした女性は自治体へ届け出がしづらく、勇気を振り絞って行政や医療機関へ相談しても、そこで相談や受診が遅いと咎められることもあります。これにより、支援を受けることを拒んでしまうことにつながってしまいます。
支援側としては、対象者の事情や背景を十分に理解し、相手の落ち度を責めたり問題を指摘したりするのではなく、利用者を中心に考える視点を持てるかどうかが課題となります。
支援データの共有
切れ目のない支援を実現するには関係機関同士の密な連携が不可欠です。
しかし、各支援機関が保有する支援データを管轄をまたいで共有することで、個人情報などの運用上の問題が生じてしまうというデメリットが発生します。具体的には
- どのデータをどこまで共有するか
- 指定管理者やNPOなど外部団体とどこまで情報を共有するか
- セキュリティ対策はどうするか
- 維持・運用費用の捻出
などの課題が出てくるため、これらに対応できるような体制を構築する必要があります。
世界における切れ目のない支援の事例
この章では、先進的な海外の切れ目のない子育て支援の事例を紹介していきます。
これらの事例では、子育て支援の政策、組織、プログラムなどの面で、子どもとその家族を社会と効果的に結びつけ、包括的な支援体制を築くことに成功しており、その点で世界的に見本となるべき事例であると言えるでしょう。
事例①ネウボラ(フィンランド)
ネウボラ(Neuvola)はフィンランド語で「アドバイスを受け取る場所」を意味し、妊娠期から就学前までの子どもとその家族に切れ目のない支援を提供する公的施設です。
1922年に設立され、民間の活動によって支えられたネウボラは、現在は社会保険庁の管轄で設置が義務化され、地方自治体が運営する保健センターの一つとなっています。
ネウボラは出産まで妊婦と胎児の健診などを行う出産(マタニティ)ネウボラと、就学年齢の6歳まで子どもと家族に子育て支援を行う子どもネウボラが軸になっており、
- 地域の保健師(ネウボラナース)との対話やつながりを重視した継続的な信頼関係
- 医療的な診断だけでなく、家族関係全体を含む発達保障や経済面、暴力、虐待リスクなどの問題も把握する総合健診や両親学級の開催
- 医療機関や専門家、学校、地域の支援と密に連携した切れ目のない支援
などの取り組みが特徴です。
フィンランド全体では約850ヶ所のネウボラが設置されており、病気予防や心身の健康促進のために、出産する親と子どものほぼ100%が利用しています。
事例②ファミリー・ハブ(イギリス)
ファミリー・ハブは、0〜19歳の子どもと家族が直面する問題を解決し、より良い関係性を構築するために切れ目のない支援を行う事業です。
これは社会的・経済的格差の深刻化や移民の増加などの問題が子どもたちの健康や福祉に影響を与えないよう、包括的な子育てを支援するために2003年に作られた「シュア・スタート(Sure Start)」事業を基盤としており、
- 健康と発達=子どもセンターが地域において家族を支える「ワンストップ」の拠点であり、乳幼児期の早期介入による子どもの発達支援の重要性を再確認
- 雇用支援と保育=地域内で雇用主やジョブセンターと連携し職業訓練や就職サービスを提供するとともに子育ての状況を充実させる
- 関係支援=カウンセリングやペアレンティング支援などによって、子どもたちが安心できる居場所としての安定的な家庭や家族関係の構築
- 複雑な必要性を抱えた家族の支援=子どもたちの生命が危険にさらされないように、DVや虐待など深刻な問題がある家族への介入的な支援
の4点を目標に自治体、公共団体やボランティア、民間諸団体などと緊密に連携して事業を行っています。現在ファミリー・ハブは独立した非営利組織のもとで運営され、多様な専門性を持つ常駐スタッフによる
- 出産や健康に関する相談や乳児の食事に関するアドバイス
- 周産期のメンタルヘルスサポート提供
- 家庭学習のサポート
- 両親学級の受講やDVに対する支援
など多岐にわたるサービスを提供しており、必要とするすべての子どもや家族に対して切れ目なく、簡単に支援が行き渡るようにすることを目指しています。
事例③ノーバディーズ・パーフェクト(カナダ)
ノーバディズ・パーフェクト(NP)は、1980年初頭に当時のカナダ保健福祉省と大西洋4州の保健部局によって始まった子育て支援事業です。
NPは、若年/ひとり親/孤立している親/所得が低い/十分な学校教育を受けていない、などの理由で子育て支援プログラムや情報をほとんど利用できない、0歳から5歳までの子どもを持つ親たちを対象にしています。
このプログラムでは、必要に応じてテキストを参照しながら、参加者がそれぞれの悩みや関心事を10人前後のグループ学習で継続的に話し合うことで
- 地域での子育て支援の探し方
- 愛情と甘やかすこととの違い
- 無理なく子どもにいうことをきかせるには
- よくある問題行動にどう対処するか
- 子どもの学びをどう促すか
- 子どもがよくかかる病気とけがや事故の防ぎ方
などを学び、子育てのスキル育成や他の親とサポートし合える関係を構築することなどを目的としています。
NPが特徴的なのは「価値観の尊重」と「体験を通して学ぶ」の2つを基本的な考え方の軸にしながら、「正しい」子育て方法を学ぶのではなく、子育てに悩む親に自分の長所を気づかせ、前向きな育児方法を見出す手助けを最も重視していることです。
切れ目のない支援とSDGs

妊娠期からの切れ目のない支援の充実は、SDGs(持続可能な開発目標)における重要な目標達成に貢献します。この分野で関係の深いものとしては以下の達成目標があげられます。
目標1「貧困をなくそう」
近年の子育て家庭で深刻化しているのは、生活困窮家庭の増加です。子育てに問題を抱える家庭に適切な社会保護制度や対策が施されることで、貧困や困窮の解消が期待されます。
目標3「すべての人に健康と福祉を」
困難に直面している家庭では、子どもだけでなくその親も病気や障害のリスクを抱えているケースが数多く存在します。経済的不安を感じることのない、安全な保健サービスの提供はすべての人に保証されるべきものです。
目標4「質の高い教育をみんなに」
切れ目のない支援では、学校や教育委員会との連携も求められます。子どもの生育に不安を抱えることなく、質の高い発達支援や就学前教育を充実させることは、その後の良好な教育環境にもつながります。
目標5「ジェンダー平等を実現しよう」
切れ目のない支援が必要になる過程で困難に直面するのは、多くの場合女性です。
女性だけが不当に負担を負わされないためにも、包括的な公共サービスや社会保障の提供、ジェンダー平等に基づいた世帯・家族内における責任の分担が必要と言えるでしょう。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ

妊娠期からの切れ目のない支援は、現在も組織の再編による整備が進められており、その背景にある多様で複雑な事情を抱えた家庭の存在は、もはや特別なことではありません。
今後は明らかになった課題を踏まえ、どの家庭に対しても当事者に寄り添ったよりきめ細かい支援を行うことが求められます。すべての子どもが安心して成長できる社会を目指すためには、本当の意味で切れ目のない、適切な支援が行き届く体制が必要となります。
参考文献・資料
子ども家庭福祉における地域包括的・継続的支援の可能性 : 社会福祉のニーズと実践からの示唆 / 柏女霊峰編著 ; 藤井康弘[ほか]著. — 福村出版, 2020.
こども家庭センターガイドライン|こども家庭庁
「こども家庭センターガイドライン」について
こども家庭センターとは?2024年に設置された背景と期待される役割、働く職員について解説 | なるほど!ジョブメドレー
こども家庭センターの設置状況等について
2.(3)妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援について-厚生労働省
母子保健の動向と施策 ~地域における妊娠期からの切れ目ない支援~ 子ども家庭局母子保健課
田川文,岡本玲子,小出恵子,田中美帆 母子保健において保健師が対応している「切れ目」とは ―質的記述的研究― 日本公衆衛生看護学会誌 JJPHN Vol.12 No.3 (2023)
子育て世代包括支援センターと切れ目のない支援とは 佐藤拓代 小児保健研究 第77巻第4号,2018 (319~321)
第31期沼尾ゼミ⑧ 千葉県市川市 滝口陽子 1 妊娠期から切れ目のない子育て支援体制を考える ~地域と子育て家庭をつなぐために~
ネウボラとフィンランドの切れ目のない家族支援 (フィンランド大使館 広報部 2017年6月10日)
遠藤和佳子 世界各国の事例からみる子育て支援の 基本的な考え方・理念 ──ヨーロッパ、北アメリカ、オセアニアの地域を中心に─ 関西福祉科学大学紀要第28号(2024)
この記事を書いた人
shishido ライター
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。