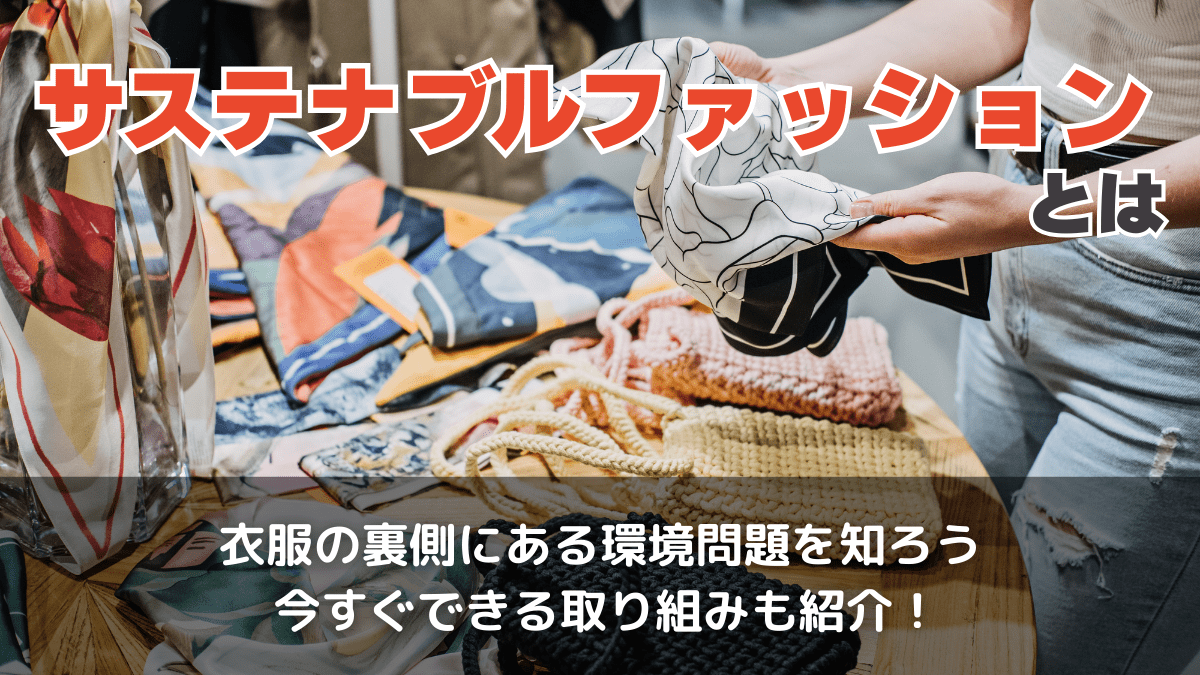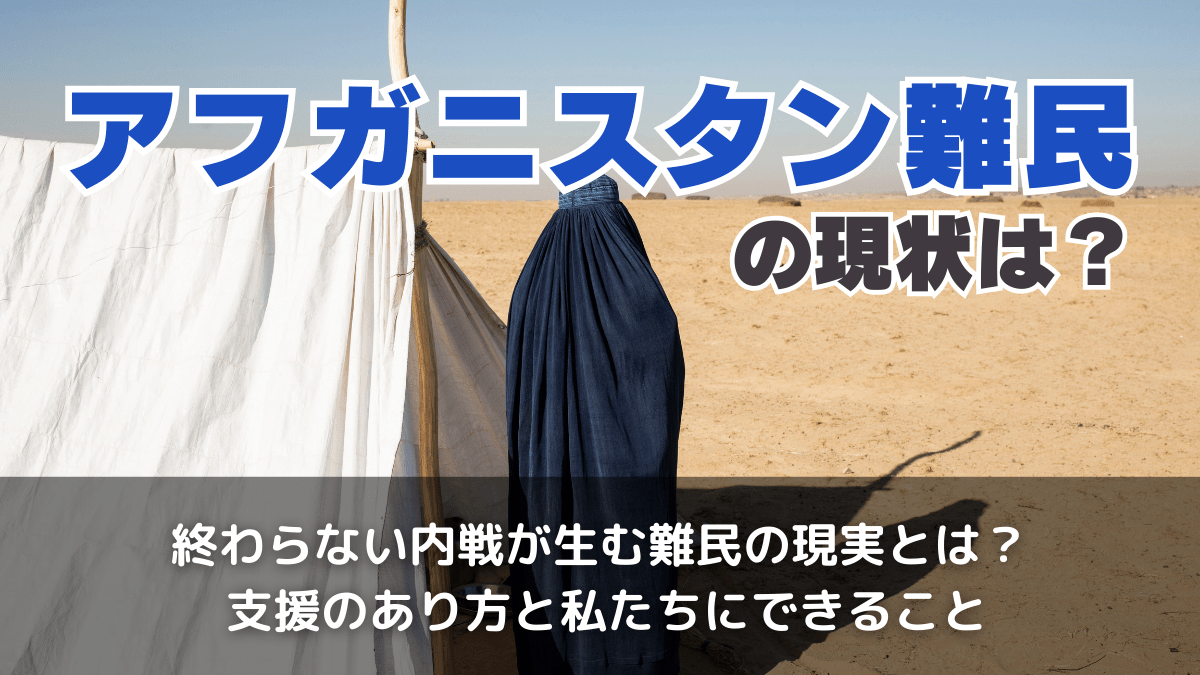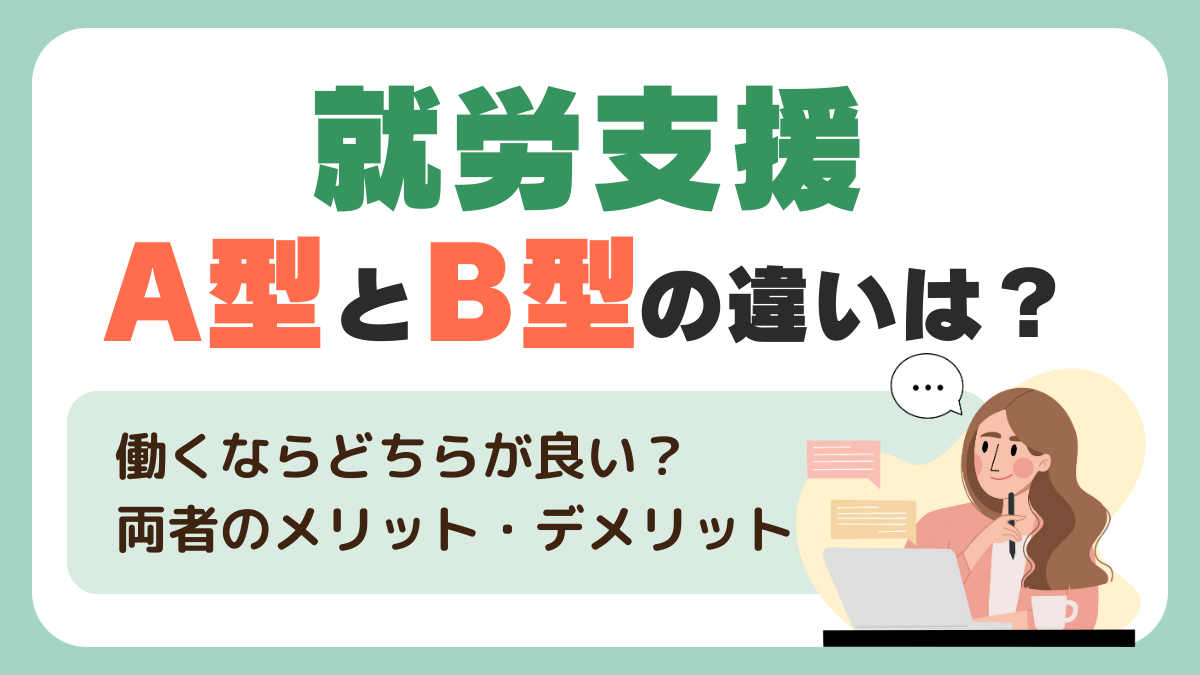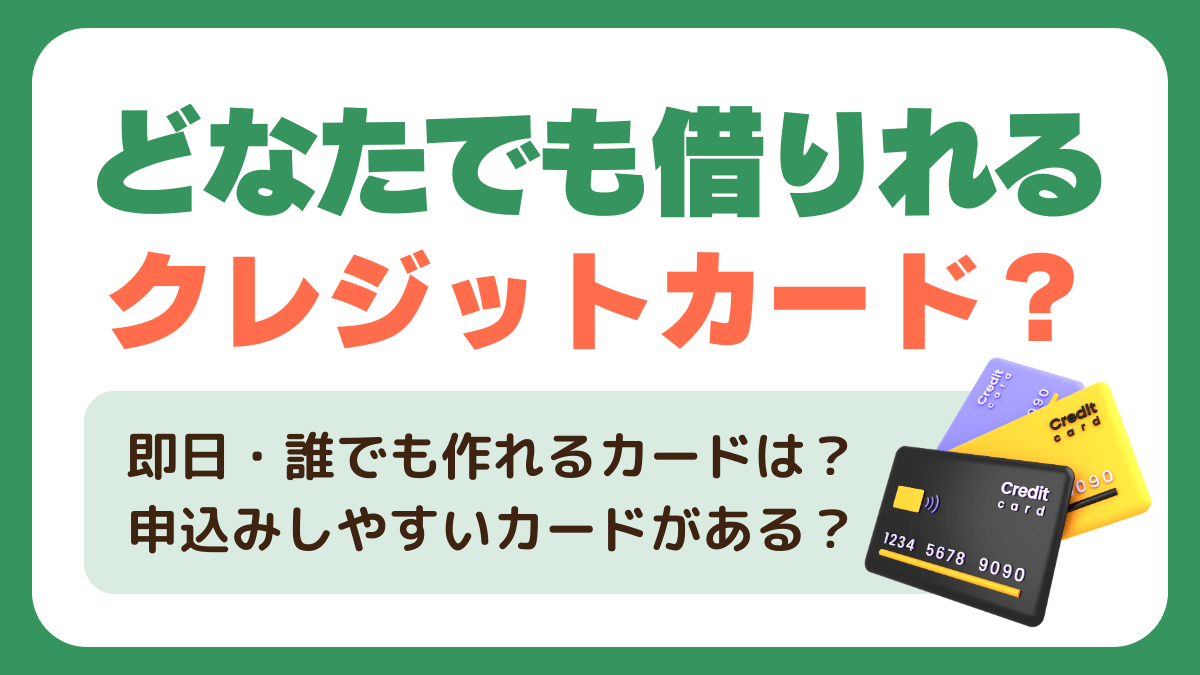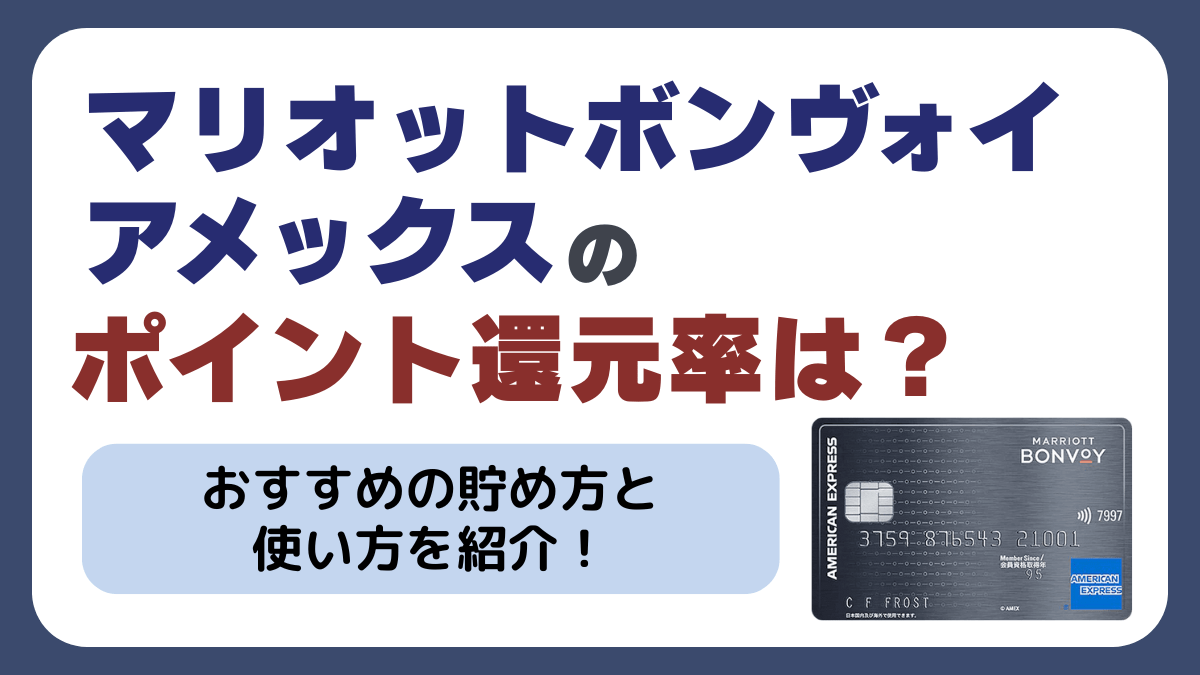コロナ禍で落ち込んだ経済を復活させるべく、世界ではさまざまな取り組みが模索されています。
中でも「グリーンリカバリー」は、かつての経済活動へ戻すのではなく、より環境に配慮した形で経済を立て直す、パリ協定やSDGsの達成にもつながる取り組みとして注目を浴びています。
そこで今回は、まだ日本であまりなじみのないグリーンリカバリーについて、世界での現状や取り組み例、個人単位でできる行動のヒントをお伝えします!
目次
グリーンリカバリーとは|意味を解説
グリーンリカバリー(Green Recovery)とは、英語で「緑の復興」を意味する、経済を中心とした復興のための政策を指します。
グリーンリカバリーは環境を重視した経済政策
グリーンリカバリー最大のポイントは、経済活動の中に環境を重要な軸として捉えること。
例えば、再生可能エネルギーの整備はもちろん、商品製造の段階で従来よりも温室効果ガス排出量を大幅に減らす取り組みといった、環境を意識する経済政策がグリーンリカバリーと言えます。
単純に「経済活動のため」ではなく、周囲の自然や地球全体の環境に配慮した政策が求められているのです。
では、なぜグリーンリカバリーが注目されているのか、次で具体的に説明します。
グリーンリカバリーが注目されている理由
なぜ今グリーンリカバリーなのか?世界で注目を浴びている理由について紹介します。
理由①コロナ禍で落ち込んだ経済の立て直し
2020年2月、世界中で新型コロナウイルスによるパンデミックが発生し、ほとんどの国・地域がロックダウンや行動規制に見舞われ、経済の停滞が起こりました。
その影響で、日本をはじめほとんどの国や地域で経済面の打撃を受けています。
下の図は、NHKがまとめた「コロナ禍での実質GDP成長率の推移(2019年9月~2021年9月)」です。
パンデミックが発生した2020年2月以降、大きな波があることが分かります。
内閣府の分析によると、GDPの落ち込みがあった時期の最大要因は「個人消費」と「輸入」でした。
グローバル化した社会では、人や物の動きが止まれば自然と消費も落ち着きます。
そこでグリーンリカバリーは、従来の輸出入に頼った事業や物の消費だけではなく、その国や地域の資源・特徴を活かした新たな分野への投資が求められるのです。
理由②新たな雇用を生み出すきっかけになる
コロナ禍では、経済の停滞に加えて、さまざまな理由で解雇・離職した人が急増しました。さらには、次の仕事探しに苦労する人も未だ多くいます。
この課題に対しグリーンリカバリーでは、新たな事業・研究へ投資することで、コロナ禍で仕事を失った人や働き方を再考している人にとって、よいチャンスとなります。
つまり、新たな雇用創出の場としても期待ができるのです。
理由③気候変動に立ち向かうための投資
グリーンリカバリーは、近年で最も喫緊の課題として取り上げられる「気候変動」に立ち向かうための事業・分野へ、積極的な投資を行います。
気候変動は、私たちの普段の暮らしはもちろん、経済活動の中で大量に排出する二酸化炭素が原因で、加速している地球温暖化が関係していると言われています。
2021年、8年ぶりに報告されたIPCC(気候変動に関する政府間パネル)のレポートでは「温暖化の原因が人間の活動であることは疑いの余地がない」と断定しました。
現在のペースで経済活動を続ければ、地球温暖化はますます激化し、異常気象や生態系の崩壊は加速していくでしょう。
そこで、化石資源を用いず二酸化炭素を放出しない再生可能エネルギーへの転換や、プラスチックではなく土に還りやすい素材を用いた商品の開発などを行う企業へ投資することで、気候変動を食い止める狙いがあります。
理由④多様な生物の保全や自然環境の改善
グリーンリカバリーは、今ある自然環境と生態系を守り、さらに除染や植林のような自然環境の改善に向けた活動を積極的に支援する傾向にあります。
気候変動の緩和のためには、温室効果ガスの排出量を減らすだけでなく、二酸化炭素を吸収する能力を持つ樹木や微生物の力が必要です。
森林が持つ、地盤を固めるパワーや水の浄化作用は、異常気象による自然災害を起こしにくくし、万が一被害を受けても回復しやすい強靭さを発揮できるため、グリーンリカバリーによる自然環境の保全活動への投資は今後ますます重要になっていくでしょう。
また森林には、野生生物の半数以上が生息していますが、うち1万4千種が絶滅の危機に瀕しており、彼らの住処を守ることも求められています。
野生動物の住まいが失われれば、生態系が崩壊して新たな異常気象を生むだけでなく、新型コロナウイルスのような感染症の発生リスクも高まるため、私たち人間にも大きな影響があるのです。
自然や生物を守り、地球の未来を明るくするためには、グリーンリカバリーの推進が重要なキーポイントです。
理由⑤パリ協定の達成にも貢献する内容

グリーンリカバリーは、地球温暖化対策の国際協定「パリ協定」の達成に貢献することがポイントです。
パリ協定とは、世界全体で温暖化対策を進めていくための条約です。
2015年12月にフランス・パリで開催されたCOP21(国連気候変動枠組条約第21回締約国会議)で締結され、200もの国と地域が参加しています。
パリ協定の目的は「地球の温度上昇を、産業革命前と比較して2度以内、できれば1.5度以内に抑えること」です。
IPCCを筆頭とする科学的な知見をもとに、目標達成のためには2050年までに脱炭素社会を実現する必要がある点にも言及しています。
先述したように、グリーンリカバリーでは気候変動に立ち向かうべく、脱炭素に関連した事業や温暖化による異常気象・自然災害に強いインフラ整備といった分野にも投資を行います。
そのため、パリ協定にも関連した内容であり、目標の達成に貢献できるのです。
理由⑥SDGsへの関心の高まり

経済活動の立て直しや新規雇用の創出、環境の保全につながる事業・研究の推進といった側面を持つグリーンリカバリーは、SDGsと大きなかかわりを持っています。
近年、特に日本でもSDGsへの関心が高まっており、それに伴いグリーンリカバリーへの注目度も高まっているのです。
では、SDGsとグリーンリカバリーとの関連性について、もう少し詳しく見ていきましょう。
SDGsとは
SDGs(Sutainable Development Goals)とは「持続可能な開発目標」の略です。
2015年の国連会議で採択され、環境と経済・社会の3つを軸にした17個の目標と、169のターゲットが設定されました。
国や地域・個人の立場を超えて協力し合い、2030年までに達成することを目指しています。
グリーンリカバリーは経済と環境のバランスを両立しながら、持続可能な社会を目指していく政策がメインで、特にSDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」と関連しています。
グリーンリカバリーとSDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」の関連

SDGs13では、現代において人類最大の課題である気候変動とその影響に対し、具体的な解決・対策を求め、持続可能な社会を築くための目標です。
国の政策として気候変動対策を盛り込み、気温上昇の緩和や異常気象が引き起こす自然災害への適応を目指しています。
先ほど「グリーンリカバリーは、パリ協定の目標達成に貢献する」と述べましたが、SDGsとパリ協定は繋がっています。特に気候変動の観点では、グリーンリカバリーを通して気候変動の緩和に向けた取り組みを進めることで、SGDsの達成に大きく貢献できる可能性があるのです。
このようにグリーンリカバリーは、環境・経済・社会の面から注目を集めていることが分かりました。
次では、グリーンリカバリーが抱える課題について見ていきましょう。
グリーンリカバリーの課題・問題点
メリットが多いように思えるグリーンリカバリーですが、デメリットもいくつか見受けられます。
ここでは「安定したエネルギーの供給」と「気候変動対策への効果」の2点に絞ってお伝えします。
課題・問題点①安定したエネルギー供給には時間がかかる
グリーンリカバリーでは、脱炭素化を目指して、化石燃料である石炭・石油を避ける傾向にあります。ただし、ここがネックとなって天然ガスを巡った国間での競争が起こっている現状もあるのです。
結果として、日本をはじめEUでは特に電気代・暖房代の高騰が問題となっており、コロナ禍で収入が減少した貧困層を中心に、多くの市民に大きなダメージを与えています。
例えば筆者がかつて住んでいたリトアニアでは、2022年から天然ガスで供給する電気・ガス代が、前年に比べて27~36%上昇する見込みです。これは欧州でもまだグリーンエネルギー供給量が少ないことが原因で、安定までには時間がかかることが分かります。
また天然ガス自体、発電の際は燃やして二酸化炭素を発生するため、そもそもグリーンなのか?という議論もあります。
よりクリーンで快適な再生可能エネルギー供給のためには、エネルギー源についての議論を進めると同時に、グリーンリカバリーによる積極的な投資と迅速な対応が求められているのです。
課題・問題点②グリーンリカバリーの割合はまだ低い
グリーンリカバリーは気候変動へ立ち向かい、人々の暮らしを守るためにも大切な投資です。
しかし、新型コロナウイルスによるパンデミックが発生してから、経済の立て直しに使われる投資額のうち、グリーンリカバリーの割合がまだまだ低い点は課題といえます。
以下は、OECDによる「経済立て直しに費やされる金額(2021年)」を、環境へのインパクトごとに示したグラフです。
(単位:10億USドル。緑:環境に配慮している、濃グレー:環境破壊に繋がる、オレンジ:環境破壊につながる恐れがある、薄グレー:全体の投資額)
全体の投資額30.2兆ドルのうち、緑の部分は6.7兆ドルほどでした。
つまり、経済を立て直すために使われる金額のうち、グリーンリカバリーに関する投資額は全体のたった21%に過ぎず、残りの79%は、環境に悪い影響を及ぼす可能性を示しています。
ただし、グリーンリカバリーへの投資額が増えているのも事実です。特に2021年4月以降では、グリーンリカバリーに対する投資金額は以前の2倍にもなりました。
今後、よりスピーディーにグリーンリカバリーの投資割合を増やしていかなければ、結局のところ気候変動の緩和に繋がらないのでは、という懸念があります。
世界と日本のグリーンリカバリーに対する現状
次に、世界と日本では、実際にどのようなグリーンリカバリーの現状があるのかを見ていきましょう。
【世界】ヨーロッパの現状は?
ヨーロッパは世界の中でもいち早くグリーンリカバリーを掲げ、積極的な行動を起こしています。
その一策として、2021年12月には長期の経済復興プロジェクト「NextGrenationEU」を発表しました。
予算額は80兆ユーロを超え、以下の分野を対象としています。
- クリーンな再生可能エネルギー
- 持続可能な交通機関と駅の整備
- デジタルスキルを持つ人材の育成
- 気候変動への対応(全体予算の30%を使用)
なお、一部のEU連盟国のグリーンリカバリーに対する予算の割合については、Green Recovery Trackerがまとめた以下のグラフを見てみましょう。
(緑:グリーンリカバリーに相当するもの、グレー:特に気候変動の対策にならないもの、赤:環境への影響が懸念されるもの)
どの国も、グリーンリカバリーへの金額はまだ少ないものの、努力している様子がうかがえます。
また金額の大きさではなく、グリーンリカバリー投資の割合でいうと、フランスやスペインは30%以下とあまり高くなく、ドイツは38%ほど。最も進んでいるのはフィンランドの42%です。
教育にも力を入れている!
またEUでは、将来を担う子どもたちへの教育に力を入れ、環境に配慮した行動の実践を促しています。
OECDがまとめた下のグラフは、OECD14ヶ国の学校での「環境に配慮した項目を教育する割合(2016年)」です。
(縦軸:左から 異なるゴミの収集、ゴミを減らす取り組み、環境に優しい商品の購入、エネルギーを無駄にしない取り組み)
国によって多少のばらつきはあるものの、EUの中でも先進的な取り組みが注目されるフィンランドやスウェーデン・ノルウェーといった北欧諸国での教育率の高さが目立ちます。
幼いうちから地球の現状について学習し、個人の取り組みが気候変動への大きなインパクトにつながるという認識を持つことで、グリーンリカバリーへの理解の高まりが期待されます。
このように、グリーンリカバリーによる投資を通じて、経済活動から教育まで、あらゆる分野への投資が、気候変動を少しでも緩和するために大切と言えます。
【日本】グリーンリカバリーへの議論は消極的
日本の政府レベルでは、残念ながらまだグリーンリカバリーについての活発な議論が行われていません。
しかし一部の企業では、すでにESG投資をはじめ、環境に配慮した事業への投資が常識となりつつあります。
※ESG投資:環境・社会・ガバナンスに考慮した投資のこと。気候変動や人権侵害に関与する事業はリスクがあるとし、持続可能性を重視した分野への投資に積極的な姿勢を示す投資家が増えている。
また2021年4月には、日本政府が温室効果ガス削減目標(NDC)を、従来の26%から46%へ引き上げました。しかしこの数字は科学的根拠に乏しく、Climate Action Trackerの報告によると、本来ならば60%以上を目指さなければ、パリ協定の目標である「2050年までに脱炭素(カーボンニュートラル)社会の実現を目指す」ことを達成するのは難しいと推測されています。
2020年には、環境省主導でサイト「Sustainable and Resilient Recovery from COVID-19(持続可能性と強靭性を備えたコロナウイルス感染症からの復興)」が立ち上がりました。オンラインでの議論やデータを通して、日本をはじめ80の国と地域のグリーンリカバリーに関連する、再生可能エネルギーへの転換や設備投資といったプランを発信しています。
ただし英語のみのサイトという意味では、あくまでも国外への情報提供にとどまっており、日本国内でグリーンリカバリーを推進する姿勢に関しては、まだ消極的です。これからの展開に期待したいところです。
世界の政府・企業のグリーンリカバリーの導入事例
ここまで、グリーンリカバリーの基本知識や現状についてお伝えしてきました。
次に、実際にどのような形でグリーンリカバリーを導入しているのか、世界の事例をいくつか見ていきましょう。
【北欧諸国】国を超えた取り組み!グリーンリカバリープラン
かねてより福祉の充実度が高く、世界幸福度ランキングの上位に常連国として名を連ねているのが、フィンランドとノルウェー・デンマーク・スウェーデン・アイスランドの北欧5か国です。
こうした北欧諸国では、パンデミック以前から気候変動対策となる再生可能エネルギーへの転換や、二酸化炭素の排出量を減らす取り組みを積極的に行ってきました。
今回ご紹介するのは、各国政府によって成り立つNordic Counsil of Ministersによる、グリーンリカバリープランです。
2020年9月に、環境問題の解決に関連したビジネスへの投資予算として、2億5千万デンマーククローネ(約43億円)を発表。再生可能エネルギーやカーボンニュートラルを掲げる企業だけでなく、デジタル技術による気候変動対策も含まれています。
新規事業だけでなく、気候変動による災害対策も同時に進行し、災害に強い国づくりと新規の雇用創出を見込む計画です。
当プランは2021~2024年までの機関を想定し、北欧諸国は2030年までに世界で最も持続可能で統括された地域となることを目指しています。
商品販売だけでなくサスティナブルな取組に積極的なIKEAや、クリーンエネルギーによるリチウム電池生産を行なうNorthvolt(ノースボルト)のように、すでにユニコーン企業を多く輩出する北欧諸国。今後の進展に期待が高まります。
【ドイツ】検索エンジンEcosia発!クリーンな事業を支援するファンド設立
ドイツ生まれの検索エンジン「Ecosia(エコシア)」は、ユーザーが検索するごとに世界中の植林活動に貢献できるツールです。
公式ページでは、実際にどれくらいの樹が植えられたのかをチェックでき、1度検索するごとに最大1キロの二酸化炭素を削減できます。私たちユーザーにとっても、検索エンジンの選び方ひとつで環境活動に貢献できるのはうれしいですね。
そのEcosiaが新たにはじめたのは、投資会社「World Fund」の設立です。2040年までに20億トンもの二酸化炭素削減を掲げるEcosiaは、年間で最低10億トンの二酸化炭素排出量を抑え、持続可能な事業を目指すスタートアップ企業への投資を行なうことを発表しました。
ファンドの規模は350億ユーロ(約457億円)にのぼり、すでに投資が行われている企業もあります。
そのひとつが、ドイツのスタートアップ企業「Recup(リカップ)」です。提携先の飲食店・施設でテイクアウト品をオーダーすると、紙容器の代わりにポリプロピレン製のカップや容器が提供されます。
使い終わった容器をパートナー連携店舗へ返すと、デポジットとして1ユーロが返ってくる仕組みです。
何度も洗って使えるうえ、紙コップの原料となる木材や輸送に必要なエネルギーの節約になる点がメリットです。ドイツではすでにほぼ全土で展開しており、今後は国外での展開が望まれます。
私たち個人にもできるグリーンリカバリーの取り組み
グリーンリカバリーは、国や企業といった大きな組織に限らず、個人でも実践できる取り組みがたくさんあります。
今回は、ぜひすぐにでも実践してほしい、3つのヒントを取り上げてみました。
おうちの電気を見直そう!パワーシフト
最も効果が大きく実践しやすい個人の取り組みとして「パワーシフト」があります。
パワーシフトとは、家庭や会社で使用するエネルギー源を、石油・石炭のような化石燃料から再生可能エネルギーを扱う電気業者へシフトすることです。
2016年より、電力小売り全面自由化によって、日本では各家庭・企業で使用する電気事業者を選べるようになりました。
そのため、一戸建てはもちろん、ほとんどのアパートや建物でも部屋ごとに、好きな電気業者を選んで契約できるのです。
エネルギー分野における二酸化炭素の排出量は、世界でも大きな割合を占めています。さらにデジタル化が進み、個人・企業にかかわらず電気の消費量は増加傾向にあります。
ここで、OECDがまとめた以下の図「エネルギー関連の二酸化炭素の排出量の変化」をご覧ください。
戦後を皮切りにエネルギー消費量が増え、2000年代からはグラフが急上昇しています。それに伴い、化石燃料の採掘や輸送・発電の段階で膨大な量の二酸化炭素を排出しているのです。
一方の太陽光や風力といった再生可能エネルギーの場合、発電段階で二酸化炭素を排出する心配がありません。また原子力発電のように、有害な化学物質の生成や処理などの問題もなく、クリーンで安全なエネルギー供給が可能になります。
パワーシフトのやり方は、とても簡単です。契約したい電気事業社のインターネットにアクセスし、ネットで見積・契約が可能なところも増えています。契約の切り替えは電力会社が行ってくれるので、現在使用している会社へ連絡する必要はありません。
さらに、場合によっては従来の電気料金よりも安くなることがあるため、まずは気軽に見積もりを取ってみてはいかがでしょうか。
再生可能エネルギーへパワーシフトする家庭が増えれば、化石燃料エネルギーに関連する二酸化炭素をぐっと抑えられ、グリーンリカバリーによる事業活性化の貢献にもつながります。
しろくま電力(パワー)
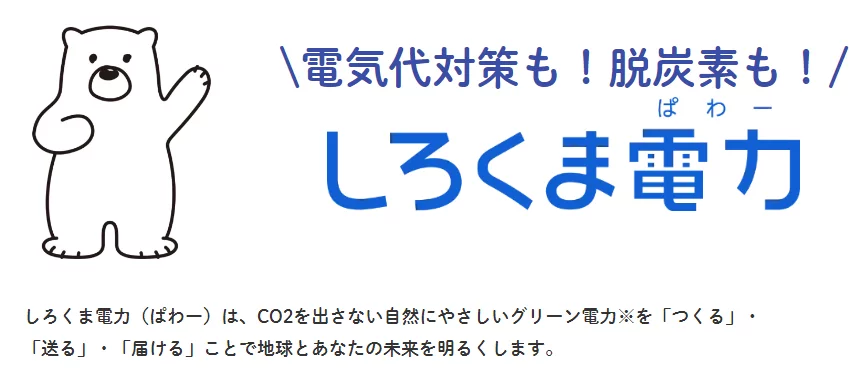
| 運営会社 | afterFIT |
| 供給エリア | 北海道・東北・東京・北陸・中部・関西・中国・四国・九州 |
| 電源 | トラッキング付非化石証書 |
| 解約金 | 0円 |
しろくま電力は、自然に優しい「グリーン電力」を供給している新電力です。トラッキング付の、どこで発電された電気かが分かる非化石証書を使用することによって、実質的にCO2排出量ゼロの再生可能エネルギー由来の電気を供給しています。
「しろくまプラン」は、基本料金・電力量料金ともに地域の大手電力会社よりも安く設定されており、乗換で電気料金が安くなると期待できます。300kWh以上の電力量料金が安くなるため、電気を多く使う家庭に特におすすめです。
ただし、燃料費高騰時には「電源調達調整費単価」「料金高騰準備金」という独自の費用が加算されますので、注意してください。
スマ電

| 運営会社 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ |
| 供給エリア | 東北・東京・北陸・中部・関西・中国・四国・九州 |
| 電源 | 再生可能エネルギー指定非化石証書 グループで所有する太陽光発電所の余剰電力活用 |
| 解約金 | 0円 |
スマ電は2016年の電力自由化開始当初から電力供給を行っている新電力です。150,000世帯の契約実績があり、スマ電ヘルプページやLINEでのサポートサービスも充実しています。
スマ電の家庭向け料金プラン「CO2ゼロホームプラン+」は、再生可能エネルギー指定非化石証書を利用して、実質的に二酸化炭素排出量がゼロになる料金プランです。
その特徴は、なんといっても基本料金が0円になること!契約容量が大きい家庭ほど、乗換でお得です。さらに、グループで所有する300ヵ所以上の太陽光発電所を活用して、昼間の電力量料金が安く設定されています。
お年寄りや小さなお子さんがいたり、在宅勤務をしたりして、昼間に電気を多く使うという家庭なら、よりメリットが大きくなるでしょう。
化石燃料の投資へ加担しないために「ダイベストメント」を行う
個人でできるグリーンリカバリーへの貢献に関して、もうひとつ大きな行動は「ダイベストメント」です。
ダイベストメント(Divestment)とは、英語で「撤退・引き上げ」を意味する言葉です。
以下は、非営利団体Bank of Climate Changeによるレポート「化石燃料に投資する金融機関ランキング」です。
(単位:10億ドル)
世界の金融機関がどれだけ化石燃料に関連する事業へ投資しているかが伺えます。上位には、日本の金融機関が名を連ねていることもわかります。
私たち消費者は、こうした情報を知らずに金融機関を契約するケースがほとんどかもしれません。しかし預けたお金は、環境に悪影響を与える化石燃料の採掘などの資金として使われていることもあるのです。
そこでダイベストメントでは、化石燃料に関連する事業へ投資していない銀行へ乗換えることをおすすめしています。
乗換え先に迷った場合は、350 Japanが掲載している「クールバンクリスト」を参考にしてみて下さい。
筆者も先日ダイベストメントを行ないましたが、キャッシュカードや契約印・本人確認証を持っていれば簡単に解約できました。
また、銀行以外にも企業や負債のダイベストメントもあります。株の売買や投資をしている人は、購入する前に「この企業はどんな活動をしているのか」をチェックしてみましょう。
普段の買い物にも気を配る
グリーンリカバリーは経済政策の一環ではありますが、消費者に積極的な買い物による消費を求めているわけではありません。
むしろ、今までの買い物・消費のあり方を再考し、より環境に配慮したお金の使い方、つまり買い物という形の投資活動が求められます。
例えば、食品。栽培の段階で農薬・化学肥料を大量に使用した場合、農地周辺に住む生態系への影響が出てしまいます。化学成分が水や土壌に流れると、その地域で暮らす人々の健康被害も考えられるのです。
また、自分が住んでいる地域から出来るだけ近い場所で作られた商品を選べば、輸送にかかる膨大なエネルギーを節約できます。
他にも、衣服やコスメ・日用品まであらゆるアイテムに、同じような考え方を当てはめてみましょう。すると自然に、グリーンリカバリーに適した事業へ貢献できるでしょう。
自分たちが支払ったお金が、どこでどのように使われているのかを意識することは大切です。環境や労働者・生態系へ配慮したアイテムを積極的に選んで、生産者を買い支えるのは、消費者である私たちの役割です。
まとめ
今回はグリーンリカバリーについて、パリ協定・SGDsとの関係性や、実際の導入事例について紹介しました。
先行例として挙げた欧州からは、単なる経済復興政策ではなく、2050年までの脱炭素社会に向けた取り組みとして、また気候変動の緩和に向けたチャンスとして、前向きにとらえる姿勢がうかがえました。
日本も今後、できるだけ早い段階でグリーンリカバリーの推進が求められます。
パリ条約やSDGsの達成に向けて、持続可能な社会の実現のためにも、環境に配慮した企業を、投資という形で積極的に応援しましょう。
<参考リスト>
Recovery plan for Europe | European Commission
The 2021-2027 EU budget – What’s new? | European Commission
Green Recovery Tracker Home Page
Think green : Education and climate change | Trends Shaping Education Spotlights | OECD iLibrary
ESG投資について|財務省
1.5°C-consistent benchmarks Japan|NDC-JapaneseTranslation
Platform for REDESIGN 2020
Nordic Region to invest DKK 250 million in green digitalised business sector | Nordic cooperation
COVID green recovery|Which European nations are showing promise?
The Nordic prime ministers | Nordic cooperation
How green are governments’ COVID-19 recovery plans? | World Economic Forum
Northvolt – the future of energy | Northvolt
Spotifyも輩出 「北欧のシリコンバレー」スウェーデン注目のスタートアップ | AMP[アンプ] – ビジネスインスピレーションメディア
環境テックでユニコーン1000社誕生も。グーグルの競合は450億円規模のファンド設立で投資加速(AMP[アンプ])
Ecosia|the search engine that plants trees
World Fund
RECUP – das deutschlandweite Pfandsystem für Coffee-to-go
パワーシフトとは?(2020/11/30より)|power-shift.org
Banking on Climate Change 2020|Banking on Climate Chaos
売却しましょう||letsdivest.jp
この記事を書いた人
のり ライター
東京生まれ&育ちのリトアニア在住ライター。森と畑に出会い「自然と人とが寄り添う暮らし方」を探求するように。現地で暮らし学んだ北欧の文化と植物、日本で体験したマクロビ&パーマカルチャーを糧に、食・暮らし関連を中心に執筆中。普段はほぼベジ。
東京生まれ&育ちのリトアニア在住ライター。森と畑に出会い「自然と人とが寄り添う暮らし方」を探求するように。現地で暮らし学んだ北欧の文化と植物、日本で体験したマクロビ&パーマカルチャーを糧に、食・暮らし関連を中心に執筆中。普段はほぼベジ。