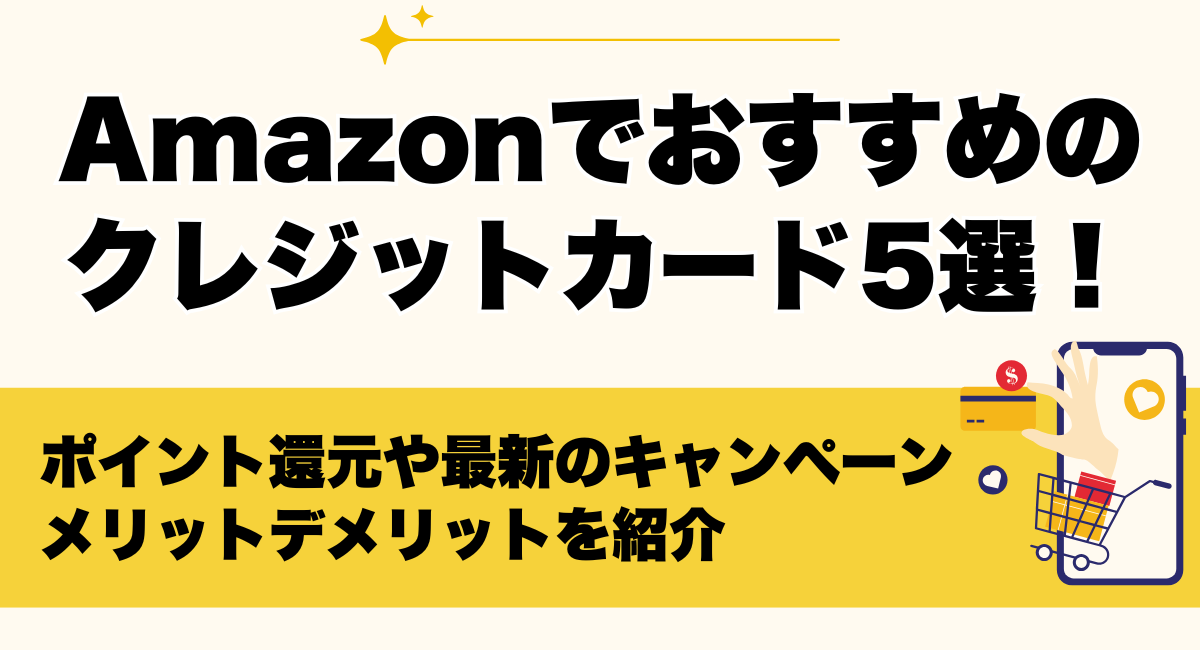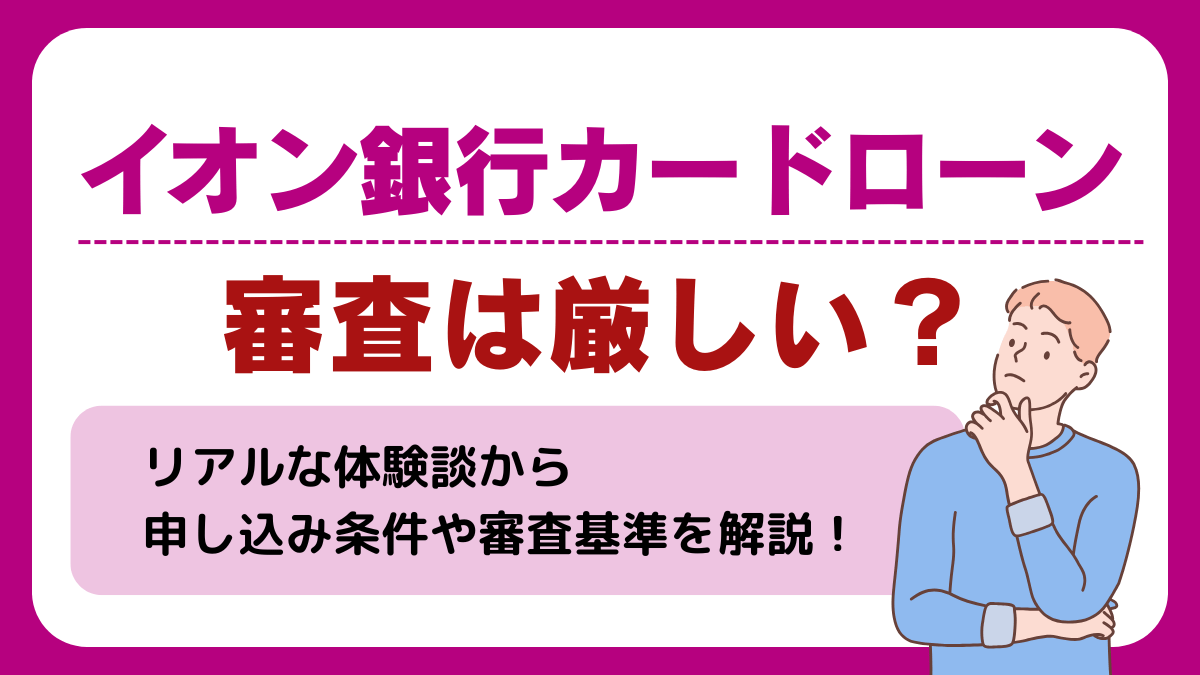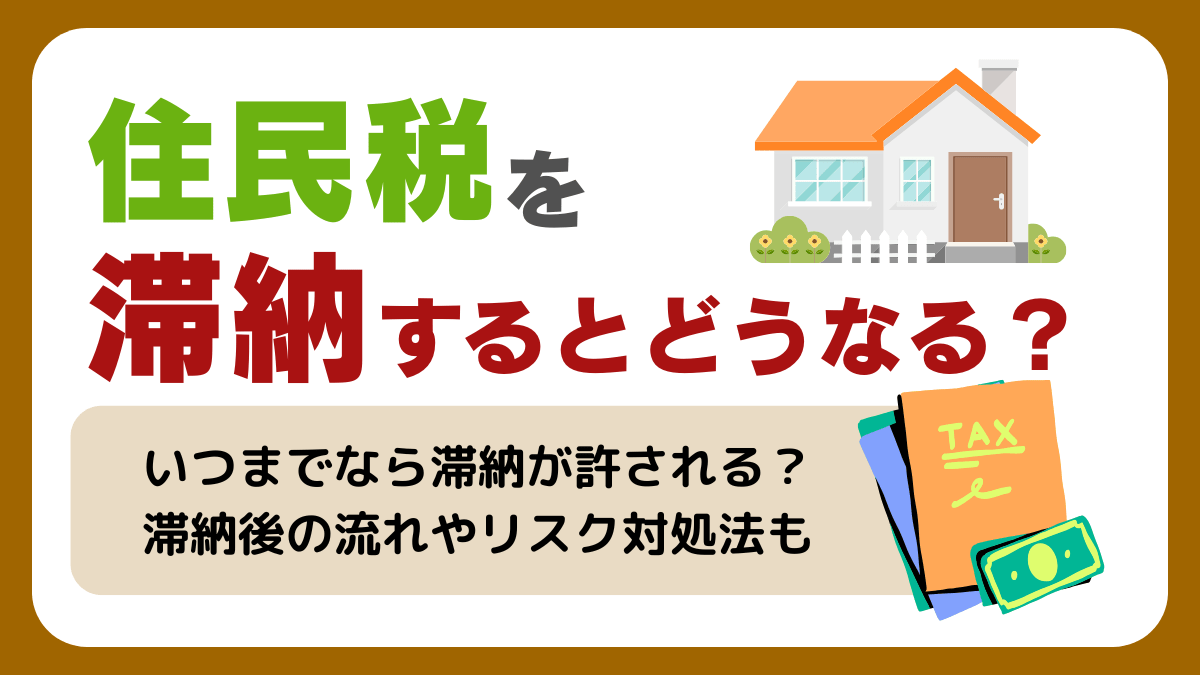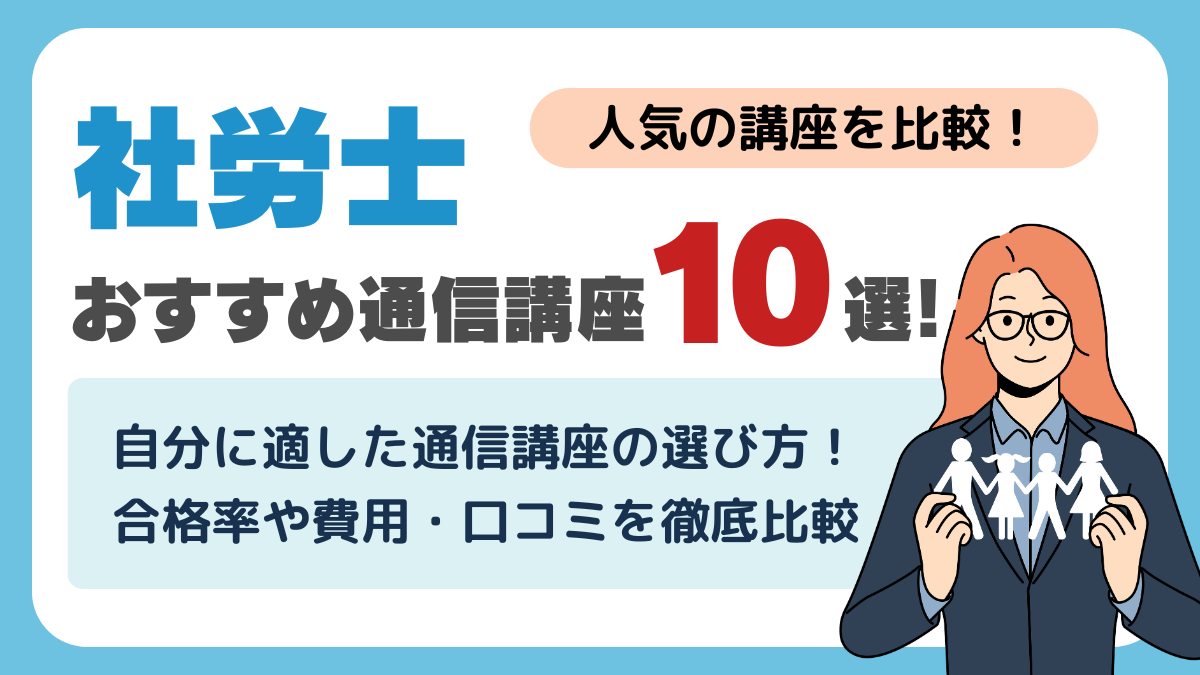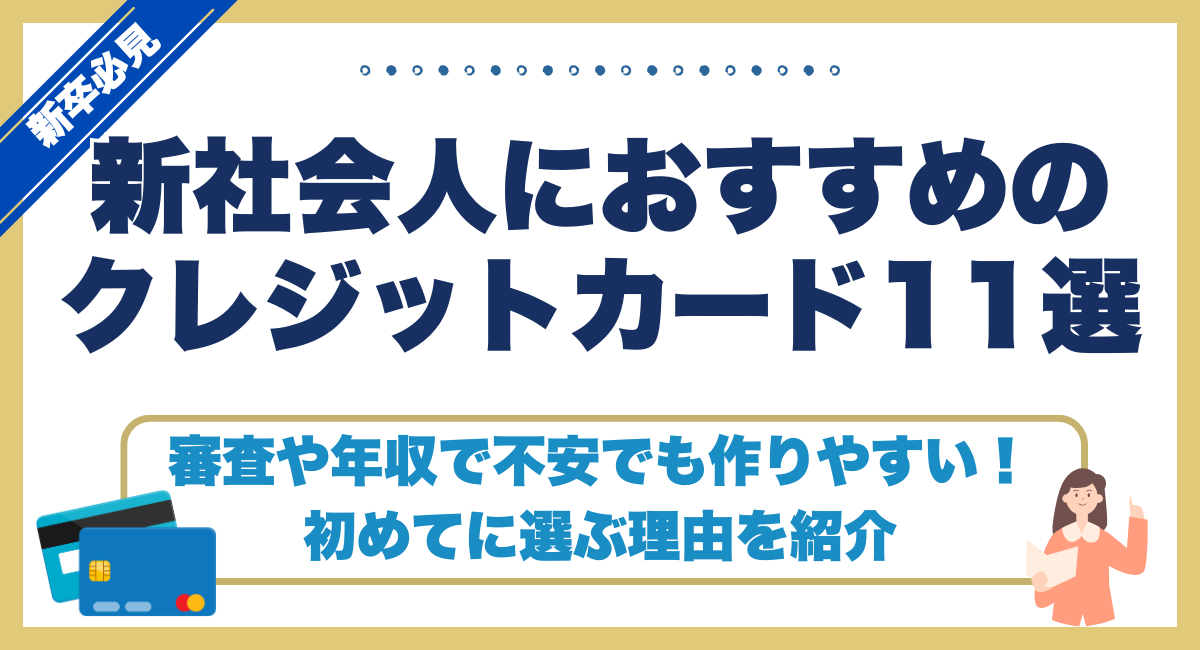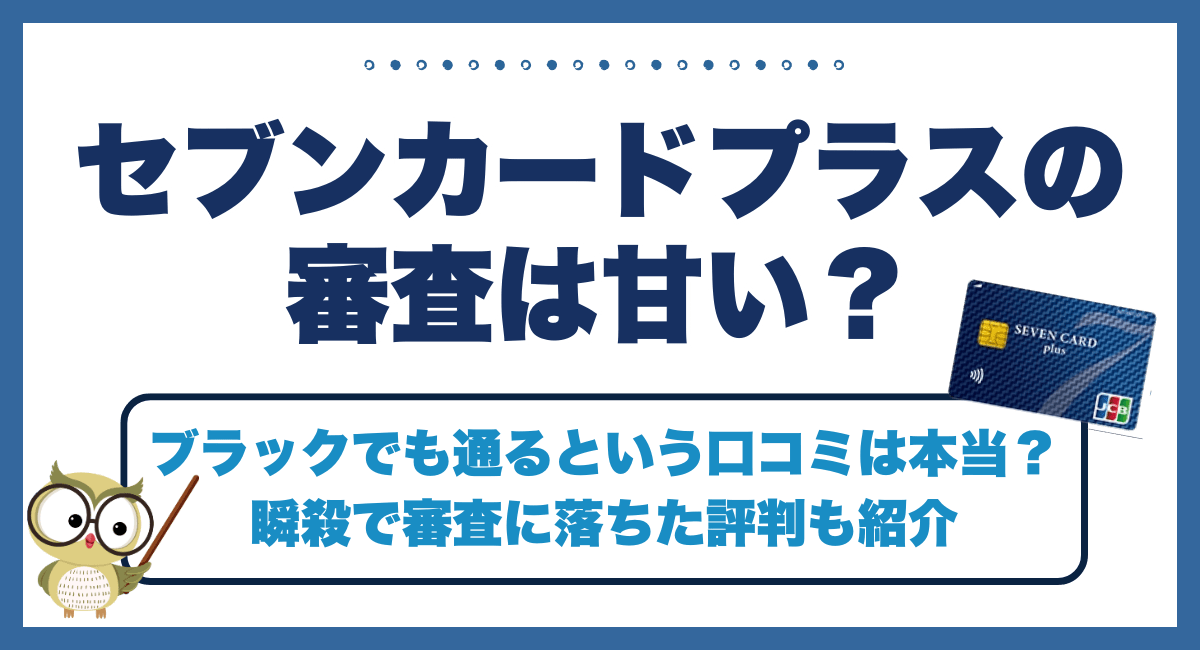1979年、イランで起きた歴史的な革命は、中東地域の政治体制を大きく変えただけでなく、世界のエネルギー情勢にも大きな影響を与えました。
「なぜ革命が起きたのか?」
「革命後のイランはどう変わったのか?」
こうした疑問に答えるには、イラン革命が起こる前の政治体制や欧米との関わりについて理解しなければなりません。また、2022年に世界中の注目を集めたイランの女性たちによる抗議デモの背景にも、イラン革命が深く関わっています。
この記事では、パフレヴィー朝の独裁体制から、イスラム法に基づく新たな政治体制への転換、そして現代に至るまでの変遷を、女性の人権問題も含めてわかりやすく解説します。現代史を理解するために必要なイラン革命の知識を整理していきますので、ぜひ参考にしてください。
目次
イラン革命とは

イラン革命とは、これまでイランを支配していたパフレヴィー朝が打倒され、イラン・イスラム共和国が成立した革命です*1)。
1978年1月、聖地コムで神学生のデモが弾圧されたことをきっかけに、反国王勢力が大きくまとまりました。亡命中のホメイニがその中心となり、大規模なデモが各地で頻発しました。
状況が悪化する中、国王パフレヴィー2世は国外へ脱出しました。その後、ホメイニが帰国し、1979年2月11日に革命政府が実権を握り、イランは新たな時代を迎えました。この革命によって、イランは政治体制や社会構造が大きく変化したのです。
目的
イラン革命は、親米的なパフレヴィー王朝を倒し、イスラム教シーア派の教義に基づく政治体制を樹立することを目的としました。
パフレヴィー2世の世俗化政策や欧米依存への不満が高まる中、ホメイニが指導するイスラム主義運動が支持を集めました。革命でアメリカやイギリスなど外国勢力の影響力を排除し、イスラムの価値観に基づく独立国家を目指したのです。
イラン革命が起きた背景

イラン革命が起きた背景にはどのようなことがあったのでしょうか。ここでは、革命が起きた原因と革命の流れについて解説します。
革命が起きた原因
革命が起きた原因は、パフレヴィー朝の独裁体制やパフレヴィー2世が実施した「白色革命」に対する強い不満、経済政策失敗に対する不満などがありました。それぞれの内容について詳しく見てみましょう。
パフレヴィー朝の独裁体制
革命が起きた原因を知るには、革命前のイランの状況を理解しなければなりません。イランでは、1925年以降、パフレヴィー朝の支配が続いていました。パフレヴィー朝は、強力な軍事力による独裁政治を行い、国内では急速な近代化を行いました*4)。
「白色革命」への強い不満
パフレヴィー2世は1961年に議会を停止させた後、イランの近代化と西欧化を目指す改革を始めました。この改革は「白色革命」と呼ばれ、社会のあらゆる面で大きな変化をもたらしました。
具体的には、農地を再分配し、森林を国の所有とし、国営工場を民間に売却して労働者に利益を分配しました。また、労使の権利や義務を定め、女性に選挙権を与え、さらに国民の読み書き能力を向上させるための取り組みも行いました。
これらの改革は一定の成果を上げましたが、皇帝が強引に改革を進めたことで、国民やイスラム教の宗教指導者の間に不満が募っていったのも事実でした*5)。
経済政策失敗に対する不満
1973年の石油危機をきっかけに、政府は経済成長を促進しようと様々な政策を打ち出しましたが、その試みはうまくいきませんでした。むしろ、物価が急激に上がるインフレ、農業の生産性の低下、都市部での貧困層の増加、そして一部の人々だけが富を独占するような社会の不均衡といった、様々な問題を引き起こしてしまいました。
革命の流れ
1978年、イランの聖地ゴムで起きた反政府デモを政府が弾圧したことをきっかけに、全国で反体制運動が広がりました。抗議活動は、パフレヴィー2世の西洋化政策や独裁的な統治に対する不満から発展したものです。抗議活動が拡大する中、イラン国内では海外亡命中のイスラム教シーア派の指導者ホメイニの影響力が強まっていきました。
革命の動きが激しさを増す中、1979年1月、パフレヴィー2世は国外へ亡命しました。同年2月、14年間の亡命生活を終えたホメイニがフランスからイランに帰国し、熱狂的な支持者たちに迎えられました。
帰国後まもなく、暫定政府が樹立され、4月1日にはイラン・イスラム共和国の成立を宣言し、政教一致の新体制が確立されました。これにより、イランは王政からイスラム法に基づく政治体制へと大きく転換することになりました。革命は、中東地域における政治情勢にも大きな影響を与えました。
イラン革命が与えた影響

イラン革命は、国内だけでなく、周辺国やイランと石油を取引していた多くの国々との関係にも大きな変化をもたらしました。ここでは、石油資源の国有化とイランとアメリカの関係悪化、イラン=イラク戦争について解説します。
石油資源の国有化
イラン革命前、石油資源は国際石油資本、特にイギリスのアングロ・イラニアン石油会社(AIOC)が支配していました。AIOCはイランの油田開発を独占し、利益を吸い上げていました。1953年に一時国有化が試みられましたが、パフレヴィー2世の独裁下で国際石油資本の支配が復活しました*7)。
イラン革命後、イランは国内の石油資源を国有化しました。これは、革命によって国外の石油会社が撤退したためです。
その後、イランは資源を守ることを重視し、原油の生産量を大きく減らしました。他のOPEC加盟国もこれに賛同したため、世界的に石油の供給量が減少し、石油価格が急激に上昇しました。これが第二次石油危機と呼ばれる現象です。
イランとアメリカの関係悪化
イランとアメリカの関係は、1979年のイラン革命を境に大きく変化しました。革命前のパフレヴィー朝時代、両国は友好的な関係を築いており、イランはアメリカの重要な同盟国でした。しかし、イスラム革命後、新しい指導者ホメイニが反米路線を打ち出し、両国関係は急速に冷え込みました。
特に決定的だったのは、1979年に発生したアメリカ大使館人質事件です。反米感情に燃えるイランの若者たちがテヘランのアメリカ大使館を襲撃し、大使館員を444日間にわたって人質に取りました。アメリカは救出作戦を試みましたが失敗し、最終的に両国は国交を断絶することになりました*10)。
その後も核開発問題や経済制裁を巡って対立が続き、現在に至るまで両国の関係修復は実現していません。
イラン=イラク戦争が始まる
イラン革命によって誕生した新政権の影響力拡大を警戒したイラクのフセイン政権は、1980年にイランへの軍事侵攻を開始しました。イラクは、アメリカをはじめとする西側諸国や湾岸アラブ諸国の支援を受け、短期決戦での勝利を目指しましたが、イランは人海戦術で抵抗し、戦争は長期化しました。
1982年にはイランが反撃に転じてイラクへ侵攻し、両国の消耗戦となりました。1987年に国連安保理決議598号が採択され、イランがこれを受諾したことで、1988年8月に停戦が実現し、8年におよぶ戦争が終結しました*11)。
イラン革命からその後における女性の人権について

イラン革命後のイラン人女性の人権は、国際的なジェンダーギャップ指数で最下位に近い順位に位置づけられるほど、厳しい状況にあります。
マフサ・アミニさんの死と抗議デモ
2022年のマフサ・アミニさんの死亡事件は、その現状を浮き彫りにし、イラン全土で大規模な抗議デモを引き起こしました。この事件は、ヘジャブの着用を強制する風紀警察によって逮捕されたアミニさんの急死がきっかけであり、女性たちの自由な服装や自己決定権への強い不満が爆発したものでした*12)。
抗議デモがもたらした変化と挫折
デモの最中、一時的にヘジャブ着用の強制が緩み、女性たちは自由な服装で外出できるという経験をしました。この経験は、自身の権利の欠如を自覚させ、「自分の権利を主張してもよい」という意識を芽生えさせる転換点となりました。
しかし、政府は抗議活動を暴動とみなし、逮捕や死刑を含む徹底的な弾圧を行った結果、デモは沈静化し、ヘジャブの着用が再び強制されるという状況に戻ってしまいました。
さらに、女子校での有毒物質攻撃事件は、デモで活躍した女性たちへの報復ではないかという疑念を生み、女性たちの安全に対する懸念を一層深めました*12)。
イラン人女性の願い
イランの女性たちが求めているのは、単にヘジャブの着用をやめることではなく、自身の人生を自ら決定する自由です。しかし、その願いは現状では叶えられていません。イラン革命から40年以上が経過した今もなお、女性の基本的人権は十分に保障されているとは言えないのです。
イラン革命と日本の関わりは?

イランは日本から約7,500km離れた場所にある遠い国です。一見何も関係がないように思うかもしれませんが、石油資源に乏しい日本にとって、産油国であるイランは重要な国です。ここでは、イラン革命によって起きた第二次石油危機について解説します。
第二次石油危機による経済混乱が起きた
1978年から1982年にかけて発生した第二次石油危機において、日本は第一次石油危機での経験を活かし、比較的冷静に対応することができました。
この危機は、イラン革命やイラン・イラク戦争の影響により、OPECが原油価格を大幅に引き上げたことで引き起こされました。原油価格は約3年間で2.7倍まで高騰し、日本経済にも大きな影響を及ぼしましたが、政府と企業は省エネルギー対策や代替エネルギーの開発を進め、国民も冷静な消費行動を維持しました。
第一次石油危機での経験から、買い占めや売り惜しみなどのパニック行動を抑制することができ、物価上昇や経済成長率の低下は避けられなかったものの、社会的混乱を最小限に抑えることができたのです*13)。
イラン革命とSDGs

イラン革命は、王政を打倒してイスラム共和国ができたという点で世界の歴史上大きな出来事です。この出来事をSDGsの観点から見ると、どのようなことが見えてくるのでしょうか。ここでは、イラン革命とSDGs目標5との関連について解説します。
SDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」との関わり
イラン革命とSDGs目標5は、女性の権利とジェンダー平等という観点で深い関連性があります。1979年のイラン革命後、イスラム法に基づく政策により、女性の権利は大きく制限されました。特にヘジャブの着用義務化や、教育・就労機会の制限など、それまで進んでいた女性の社会進出や男女平等の動きが後退することとなりました。
これは、SDGs目標5が掲げる「ジェンダー平等の実現」という理念とは相反する状況を生み出しました。2022年のマフサ・アミニ氏の死をきっかけに起きた抗議行動は、イランの女性たちが長年直面してきた権利制限への異議申し立てとして注目を集めました。
このような状況は、SDGs目標5の達成に向けた課題を浮き彫りにしています。特に女性の基本的人権の保護、政治参加の機会確保、そして差別的な法制度の撤廃という点で、イランの現状はSDGsの目指す方向性との大きな隔たりがあることを示しています。
まとめ
今回はイラン革命を取り上げました。この記事では、イラン革命が単なる政権交代ではなく、社会構造、国際関係、さらには女性の権利にまで大きな影響を与えた変革であったことを解説しました。
イラン革命によって、イランは石油資源を国有化し、アメリカとの関係が悪化、さらにはイラン・イラク戦争へとつながるなど、中東情勢を大きく変動させるきっかけとなりました。
特に、イラン革命後の女性の人権状況については、国際的なジェンダーギャップ指数で低い位置づけとなっており、マフサ・アミニさんの死をきっかけとした抗議デモが起きたことからも、その深刻さが伺えます。
イラン革命は、現代のイラン社会や国際社会を理解する上で不可欠な出来事であるといえるでしょう。
参考
*1)山川 世界史小辞典 改定新版「イラン革命」
*2)旺文社世界時事典 三訂版「ホメイニ」
*3)山川 世界史小辞典 改定新版「シーア派」
*4)ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「パフラビー朝」
*5)山川 世界史小辞典 改定新版「白色革命」
*6)百科事典マイペディア「イラン革命」
*7)ENEOS「石油産業の歴史 第1章第3節 中東石油資源の発見と共同支配」
*8)山川 世界史小辞典 改定新版「国際石油資本」
*9)山川 世界史小辞典 改定新版「中央条約機構」
*10)NHK「1からわかる!アメリカ vs. イラン(1)なぜ対立するの?」
*11)山川 世界史小辞典 改定新版「イランイラク戦争」
*12)NHK「「自分のことは自分で決めさせて」 女性が生きづらさ感じる理由は」
この記事を書いた人
馬場正裕 ライター
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。