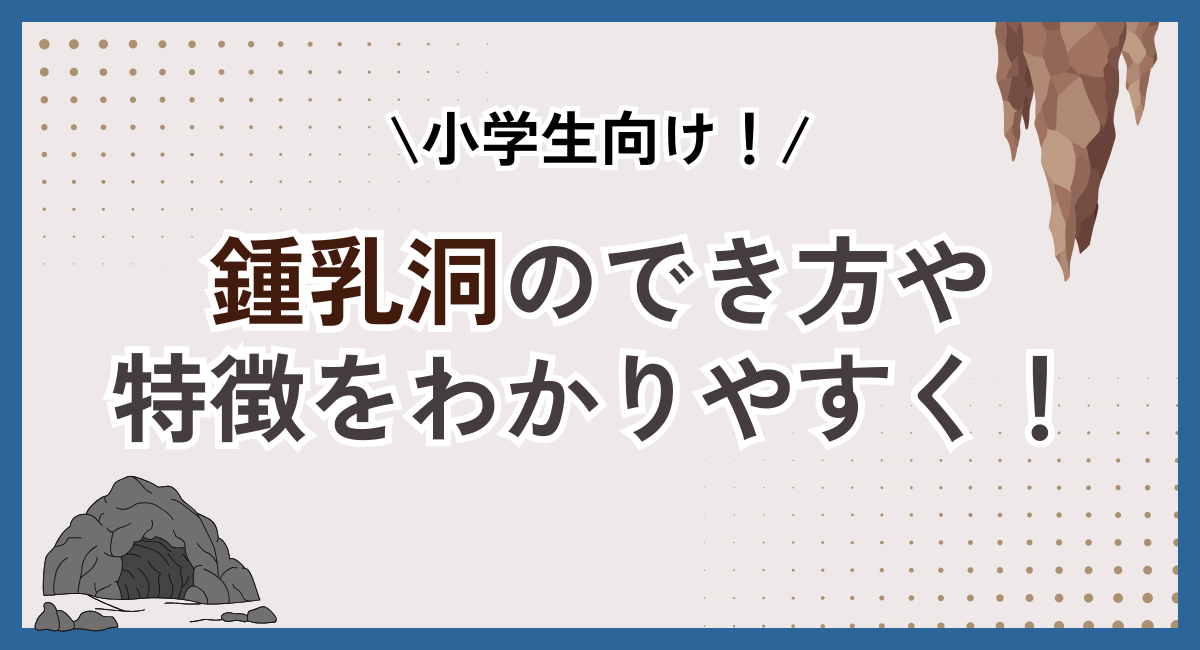
地底に広がる幻想的な世界、鍾乳洞。長い年月をかけ、自然がつくり出した芸術は、私たちを魅了してやみません。
鍾乳洞のでき方、特徴、そしてそこに息づく不思議な生き物。鍾乳洞は、まさに地球の歴史を今に伝える貴重なタイムカプセルのようなものです。
そして、人類の歴史、生物多様性、気候変動、SDGs目標への貢献など、鍾乳洞には、地球と共に生きるためのヒントが秘められています。鍾乳洞の神秘的な世界へ、探検に出かけましょう!
目次
鍾乳洞とは?
【カステッラーナ・グロッテの鍾乳洞(イタリア)】
鍾乳洞とは、石灰岩の地層に雨水が長い時間をかけて浸透し、石灰岩が溶けてできた空洞のことです。内部には、鍾乳石や石筍(せきじゅん)※といった独特の形をした岩石が見られ、幻想的な景観を作り出しています。
鍾乳洞は、長い年月をかけて自然が作り出した芸術品とも言え、多くの人々を魅了してきました。
【沖永良部島白蛇洞の鍾乳管※】
【石筍の生成のモデル】
鍾乳洞の世界には、私たちの想像を超える不思議がたくさん隠されています。それでは、鍾乳洞について詳しく見ていきましょう。
鍾乳洞の学術的定義
鍾乳洞は、地質学的には「石灰洞」の一種として分類されます。石灰岩に形成された洞窟で、特に鍾乳石の発達した洞窟を鍾乳洞と呼びます。
鍾乳洞と他の洞窟の違いは、そのでき方(形成過程)にあります。鍾乳洞は、主に水の化学的作用によって形成されるのに対し、鍾乳洞ではない洞窟は風化や浸食、火山活動など、他の様々な要因で形成されます。
世界の鍾乳洞
【ベトナム ソンドン洞窟】
世界には数多くの鍾乳洞が存在しますが、その中でも特に有名なものがあります。例えば、世界最大の鍾乳洞として知られるのがベトナムのソンドン洞窟です。
この洞窟は2009年に発見され、2016年に3つの国際機関から世界最大の洞窟として認定されました。その規模は圧巻で、内部に40階建てのビルが入るほどの広さがあります。
日本も比較的鍾乳洞の多い国と言えます。特に、石灰岩地帯が広がる西日本や南西諸島に多く分布しています。
鍾乳洞と人類の歴史
【岡山県 備中鐘乳穴(真庭市)】
鍾乳洞は古くから人類と深い関わりを持ってきました。原始時代から、洞窟は人類の住居や避難所として利用された痕跡が確認されています。
例えば、沖縄のガンガラーの谷では、約2万3千年前の釣り針が発見されており、人類がかなり古くから洞窟を利用していたことがわかっています。
また、鍾乳洞は古くから信仰の対象にもなってきました。日本では、岡山県にある備中鐘乳穴が平安時代の文献にも記載されており、古くから人々に知られていたことがわかります。
現代では、鍾乳洞は重要な観光資源となっています。しかし、その美しさと神秘性を守るためには、訪れる際に注意すべきことがあります。ゴミを捨てない、鍾乳石に触れないなど、自然を大切にする心が必要です。
鍾乳洞は地球の長い歴史を物語る貴重な自然遺産です。その形成過程や人類との関わりを知ることで、私たちは地球の神秘と自然の大切さを学ぶことができます。*1)
鍾乳洞の特徴
【北海道上川郡の当麻鍾乳洞】

鍾乳洞は、地球の長い歴史が刻まれた神秘的な空間です。その特徴は地質学的な側面だけでなく、生物学、考古学、さらには人類の歴史とも深く関わっています。
地質学的特徴
鍾乳洞は、カルスト地形に見られる代表的な地形の一つです。
鍾乳洞の形成には数十万年から数百万年もの時間がかかり、地球の歴史を物語る貴重な自然遺産となっています。
カルスト地形
【カルスト地形と鍾乳洞】
カルスト地形とは、石灰岩などの水に溶解しやすい岩石で構成された地形のことです。この地形は、雨水や地下水による侵食(主に溶食)によって形成されます。
カルスト地形は、主に炭酸カルシウムを含む岩石が二酸化炭素を含んだ水と反応して溶け出すことで進行します。
生態系の特徴
【キクガシラコウモリ】
光が届かず、温度と湿度が安定した環境は、特殊な生物の進化を促しました。このため、鍾乳洞内には、独特の生態系が存在します。
代表的な洞穴生物としては、コウモリ類(キクガシラコウモリやユビナガコウモリなど)が挙げられます。
また、洞窟の環境に適応した小さな生き物も多く存在し、中には目が退化し、触覚や嗅覚が発達した種も見られます。
例えば、洞窟にのみ生息しているメクラチビゴミムシは地下生活に強く適応した昆虫で、以下のような特徴を持っています。
- 複眼の退化: 地下の暗い環境に適応し、目が退化
- 感覚毛の発達: 目の代わりに、触角や体表の感覚毛が長く伸びて発達
- 体色の変化: 色素を失い、赤褐色(飴色)に変化
- 皮膚の変化: 甲虫なのに皮膚が薄く軟らい
- 後翅の退化: 飛ぶ必要がないため、翅が退化
- 筋肉の退化: 翅を動かすための筋肉も退化
上翅の融合: 左右の翅が融合して一つのお椀状になり、腹部の上にかぶさっている
これらの特徴により、メクラチビゴミムシは低温で多湿な地下浅層の狭い空隙を効率的に移動し、生活することができます。
【アシナガメクラチビゴミムシ(日本を代表する超洞窟種)】
海外の鍾乳洞に住む変わった生き物の代表例として、ホライモリが挙げられます。ホライモリは、眼は退化し、体は真っ白で、外エラを持つなど、洞窟環境に高度に適応した特徴をもっています。
水中の振動や化学物質を感知する能力に優れ、獲物を捕らえたり、外敵を避けたりすることができます。寿命は100年を超えることもあり、非常に長寿な生物です。
【体をくねらせて蛇のように泳ぐホライモリ(スロベニア、イタリア、アルバニア)】
環境保全の重要性
鍾乳洞の生態系は、長い年月をかけて形成された繊細なバランスの上に成り立っています。そのため、人間の活動によって簡単に乱されてしまう危険性があります。
例えば、観光客のために設置された照明が、光に敏感な洞窟生物たちの生活リズムを狂わせてしまう可能性が問題になっています。このような影響を防ぐには、鍾乳洞を保護しながらも、人々が自然の素晴らしさを体験できるよう、慎重にバランスを取る必要があります。
鍾乳洞は、地球の歴史、生命の進化、そして人類の文化を物語る貴重な自然遺産です。その特徴を理解し、保護していくことは、私たちの重要な役目と言えるでしょう。*2)
日本の代表的な鍾乳洞
日本には数多くの鍾乳洞が存在し、その中でも特に有名なものが「日本三大鍾乳洞」として知られています。これらの日本を代表する鍾乳洞について見ていきましょう。
龍泉洞(岩手県)
【岩手県 龍泉洞の第三地底湖】
龍泉洞は、岩手県岩泉町に位置する鍾乳洞です。総延長は5km以上と推定され、そのうち約700mが一般公開されています。
龍泉洞の最大の特徴は、透明度の高い地底湖です。特に第三地底湖は「ドラゴンブルー」と呼ばれる神秘的な青色で知られ、多くの観光客を魅了しています。また、龍泉洞は5種類のコウモリが生息する貴重な生態系を有しており、国の天然記念物に指定されています。
秋芳洞(山口県)
【山口県秋芳洞の「百枚皿」】
秋芳洞は、山口県美祢市にある日本最大級の鍾乳洞です。総延長は約10.7kmに及び、そのうち約1kmが観光コースとして公開されています。
秋芳洞の見どころは「百枚皿」と呼ばれる鍾乳石の形成です。これは、石灰岩が溶解と再結晶を繰り返してできた棚田のような形状で、世界的にも珍しい景観として知られています。
秋芳洞は特別天然記念物に指定されており、3億5000万年前からの地球の歴史を物語る貴重な自然遺産です。
龍河洞(高知県)
【高知県龍河洞の洞内にある「神の壺」】
龍河洞は、高知県香美市にある鍾乳洞で、総延長は約4kmです。龍河洞の最大の特徴は「神の壺」と呼ばれる奇跡的な造形です。
これは、弥生時代の土器が鍾乳石に巻き込まれて一体化したもので、約2000年の時を経て形成されました。龍河洞は国の天然記念物および史跡に指定されており、地質学的価値だけでなく、考古学的にも重要な遺跡となっています。
鍾乳洞の地域分布
日本の鍾乳洞は、石灰岩地帯に多く分布しています。特に西日本や南西諸島に多く見られ、東日本では比較的少ないのが特徴です。
これは、日本の地質構造と関係しており、石灰岩の分布が地域によって異なるためです。鍾乳洞は、地球の長い歴史を物語る貴重な自然遺産であり、地質学、生物学、考古学など、さまざまな研究の対象となっています。*3)
鍾乳洞のでき方
【岐阜県郡上市の大滝鍾乳洞】
鍾乳洞の形成過程は、地質学的な時間スケールで進行する壮大な自然の営みです。鍾乳洞のでき方を理解することで、私たちは地球の歴史と環境変動の痕跡を読み解くことができます。
鍾乳洞のできる条件
鍾乳洞が形成されるためには、主に以下の条件が必要です。
- 石灰岩の存在
鍾乳洞の主な構成要素である石灰岩は、サンゴや貝などの海洋生物の遺骸が長い年月をかけて堆積してできた岩石です。 - 地殻変動
海底で形成された石灰岩層が、地殻変動によって地上に隆起する必要があります。 - 水と二酸化炭素
雨水や地下水に溶け込んだ二酸化炭素が、石灰岩を溶かす重要な役割を果たします。
鍾乳洞のできる過程
鍾乳洞の形成は、以下のような段階を経て進行します。
- 溶解段階
雨水が大気中の二酸化炭素を取り込み、弱い炭酸になります。この弱酸性の水が石灰岩を少しずつ溶かしていきます。 - 空洞形成段階
溶解が進むにつれて、石灰岩の割れ目や断層に沿って空洞が形成されます。これらの空洞が徐々に拡大し、連結していきます。 - 鍾乳石形成段階
空洞内で水滴が蒸発する際に、溶けていた炭酸カルシウムが析出し、鍾乳石や石筍などの洞窟生成物が形成されます。
【鍾乳洞のできる仕組み】
鍾乳洞ができるまでにかかる時間
鍾乳洞の形成には、非常に長い時間がかかります。人が入れるサイズの鍾乳洞ができるまでには、数万年から数十万年の時間が必要だと考えられています。
例えば、1cmの鍾乳石が形成されるのに100年以上かかることもあり、数メートルの鍾乳石は数万年から数十万年もの歳月をかけて成長してきたことになります。
【1滴1滴で形を作る鍾乳石】
鍾乳洞の研究からわかること
鍾乳洞の研究は、地球の過去の環境や気候変動を理解する上で重要な役割を果たしています。
- 過去の気候
鍾乳石の成長パターンや化学組成を分析することで、過去の気候変動を高精度で推測することができます。 - 地震や津波の記録
鍾乳石の成長の乱れから、過去に発生した大規模地震や津波の痕跡を読み取ることができます。 - 地質学的プロセス
鍾乳洞の形成過程を研究することで、地球の表面で起こる化学的・物理的プロセスについての理解が深まります。
鍾乳洞は、地球の長い歴史を物語る貴重な自然の記録装置です。その形成過程を理解することで、私たちは地球環境の変遷や未来の気候変動予測に重要な手がかりを得ることができるのです。*4)
鍾乳洞とSDGs

鍾乳洞は、特別な生物相が広がる生物多様性の宝庫です。また、鍾乳洞の研究は過去の気候変動を解明し、未来の環境変化予測に重要な役割を果たしています。
これらの特性からも、鍾乳洞はSDGsの目標達成に様々な面で重要な存在であることがわかります。鍾乳洞と関係の深いSDGs目標を確認してみましょう。
SDGs目標6:安全な水とトイレをみんなに
鍾乳洞は、地下水脈と密接に関連しており、水源涵養や水質浄化に重要な役割を果たしています。鍾乳洞の保全は、地下水の持続可能な利用を促進し、水資源の保全に貢献します。
例えば、山口県の秋吉台では、鍾乳洞を流れる地下水が周辺地域の貴重な水源となっており、地域住民の生活を支えています。また、沖縄県の鍾乳洞では、地下水が自然のフィルターを通ることで浄化され、良質な水が湧き出しています。
SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を
鍾乳洞内の鍾乳石は、過去の気候変動の記録を保持しています。鍾乳洞の研究により、長期的な気候変動パターンを理解し、将来の気候変動予測や対策立案に貢献しています。
現代の技術では、鍾乳石の成長速度や成分分析から、過去の気温や降水量の変化を推定することができます。また、鍾乳石に含まれる微量元素の分析から、過去の海洋環境の変化を復元することも可能です。
SDGs目標15:陸の豊かさも守ろう
鍾乳洞は独特の生態系を有し、多くの固有種や絶滅危惧種の生息地となっています。世界中の洞窟には5万種から10万種もの生物が生息していると推定されており、その保護は生物多様性の維持にとても重要です。鍾乳洞の保護と持続可能な管理は、これらの特殊な生態系を守り、陸上生態系の保全に貢献しています。
SDGs目標17:パートナーシップで目標を達成しよう
鍾乳洞の保護と研究は、国際的な協力と連携を必要とします。例えば、「国際洞窟・カルスト年2021」※のような取り組みは、世界中の研究者、保護団体、地域コミュニティを結びつけ、鍾乳洞の重要性に対する理解を深め、保護活動を促進しています。
このような国際的なパートナーシップは、SDGsの目標達成に向けた協力体制の強化に貢献しています。
このように、鍾乳洞の保護と研究は、SDGsの複数の目標達成に貢献する重要な取り組みです。鍾乳洞を守り、学び、活用する取り組みに参加することで、私たち一人ひとりがSDGsの実現に貢献できるのです。*5)
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ
【個体数が激減しているユビナガコウモリ(絶滅危惧II類)】
鍾乳洞は、地球の歴史を今に伝える貴重なタイムカプセルであり、生物多様性の宝庫でもあります。しかし、近年の気候変動の影響による大雨や、開発による環境破壊など、鍾乳洞の保全には多くの課題が残されています。
最近の出来事として、2023年に沖縄県南大東島の水中で大規模な鍾乳洞が発見され、調査が進められています。この発見は、未知の生態系や地質学的知見をもたらす可能性があり、鍾乳洞研究の新たな展開が期待されます。
鍾乳洞を保全し、未来にも残していくために、私たち一人ひとりが鍾乳洞の重要性を理解し、関心を持つことが大切です。鍾乳洞を訪れる際には、そこの環境への配慮を忘れずに、自然の神秘と美しさを体感してください。
鍾乳洞は、私たちに地球の歴史と生命の不思議を教えてくれる貴重な存在です。その保護と研究を通じて、私たちは持続可能な未来への道筋を見出すことができるでしょう。
鍾乳洞について理解を深め、この素晴らしい自然遺産を次世代に引き継いでいきましょう!*6)
<参考・引用文献>
*1)鍾乳洞とは?
WIKIMEDIA COMMONS『Grotte Castellana (5)』
Vietjet Air『世界一の壮大な洞窟、ソンドン観光』
岡山県観光連盟『まさに穴場スポット!神秘的な世界を探検できる岡山の鍾乳洞3選』
Science Portal『観察法のイロハのイ 自然がつくった神秘の空間鍾乳洞』(2019年1月)
竜ヶ岩洞『鍾乳洞の形成 鍾乳洞とは?』
竜ヶ岩洞『洞窟の種類 洞窟とは?』
竜ヶ岩洞『人類と洞窟 洞窟の利用』
龍泉洞『龍泉洞からのお願い』
三陸ジオパーク『地底に広がる鍾乳洞「古代の海の贈り物」』
南アフリカ観光局『古代の祖先の足跡を歩く「人類のゆりかご」』
Valley of Gangala『太古との邂逅』
Valley of Gangala『ガンガラー秘話』
鳴門市観光サイト『備中鐘乳穴』
NATIONAL GEOGRAPHIC『特集:世界最大の洞窟を踏破した!』(2011年1月)
NATIONAL GEOGRAPHIC『【解説】世界最古の洞窟壁画、なぜ衝撃的なのか?』(2018年2月)
VET JO『ソンドン洞窟が3機関から世界最大に認定、世界初』(2016年9月)
CNN『2千年前に隠された銀貨や宝飾品、鍾乳洞で発見 イスラエル』(2015年3月)
日本経済新聞『スロベニアの壮大な地中探検 川が流れる洞窟の絶景』(2018年10月)
*2)鍾乳洞の特徴
当麻町『当麻鍾乳洞』
WIKIMEDIA COMMONS『Peillot P3260031mod』
小松 貴『日本の地下空隙に生息する陸生節足動物の多様性』(2018年)
WIKIMEDIA COMMONS『P anguinus1』
稲積水中洞窟『稲積水中鍾乳洞とは』
国土交通省『中山風穴』
HONDA『原始時代にタイムトリップ!?「鍾乳洞しょうにゅうどう」を探検たんけんしよう』
あぶくま洞『第5章 滝根町の洞穴はどうやってできたの?』
あぶくま洞『第7章 あぶくま洞・入水鍾乳洞に生物っているの?』
竜ヶ岩洞『鍾乳石の名前と種類』
竜ヶ岩洞『洞穴生物の分類』
岐阜県博物館『飛騨大鍾乳洞』
岐阜県博物館『縄文洞』
京都府『京都府レッドデータブック2015 キクガシラコウモリ』
滝観洞『自然の造形美「滝観洞」』
日本自然保護協会『名護市辺野古崎沖合の長島における 鍾乳洞の詳細が明らかになる』(2021年8月)
千葉県教育委員会『白浜の鍾乳洞』
NATIONAL GEOGRAPHIC『いつか訪れたい「竜のすみか」伝説をもつ洞窟、スロベニア』(2022年12月中日新聞『国内唯一飼育のホライモリに注目 碧南海浜水族館で2日から辰年企画展』(2023年12月)
柿添 翔太郎『地下環境に生息する昆虫類の遺伝資源収集と多様性解明-沖縄本島から発見された新属新種オキナワアシナガメクラチビゴミムシ- ―地下性昆虫保全研究グループ―』(2024年)
和紙のふるさと 小川町『Ⅴ 古寺鍾乳洞の動物相調査』
中村 光一朗『千葉県における洞穴性コウモリ類の生息洞穴の分布と保全のための評価の試み』
菊池正志『岩手県岩泉町の氷渡洞におけるケイブシステムと二次生成物』(2010年)
福井市自然史博物館『福井県における洞穴性コウモリ類の分布に関する知見』(2005年)
*3)日本の代表的な鍾乳洞
龍泉洞『龍泉洞の見どころ』
龍泉洞『古の龍泉洞』
WIKIMEDIA COMMONS『Akiyoshi02』
WIKIMEDIA COMMONS『Kami Kochi Ryugado Inside 6』
国土交通省『3.地質を反映した地形』
環境省『その他湿地 七ツ釜鍾乳洞の地下水系』
環境省『事例 No.57 山口県美祢市秋吉台』
秋吉台国定公園『秋吉台の山麓にある東洋屈指の大鍾乳洞―特別天然記念物 秋芳洞―』
秋吉台国定公園『カルスト台地に息づく3億5000万年前からの地球の記憶』
美祢市『秋芳洞(あきよしどう)』(2020年10月)
龍泉洞『龍泉洞について』
香美市『龍河洞』
文化庁『国指定文化財等 龍河洞』
四国電力『鍾乳石が織りなす神秘的な空間「龍河洞」』
三陸ジオパーク『45.龍泉洞・新洞』
*4)鍾乳洞のでき方
大滝鍾乳洞・郡上観光グループ『時の雫が刻んだ大自然の造形美 大滝鍾乳洞』(2024年9月)
日本化学工業協会『02 未完の芸術ー鍾乳洞』(2005年5月)
稲積水中洞窟『稲積水中鍾乳洞とは』
あぶくま洞『鍾乳洞はどうしてできるの?』
あぶくま洞『第3章 滝根町周辺の地質って?』
中国地質調査業協会『風化作用』
竜ヶ岩洞『鍾乳洞の形成 鍾乳洞とは?』
和紙のふるさと 小川町『古寺鍾乳洞調査報告書-地質・動物・植物-』(2023年)
稲積水中鍾乳洞『稲積水中鍾乳洞とは』
大沢 信二『鍾乳洞の気象と鍾乳石の成長』(2009年12月)
木村 颯『石灰洞におけるアラゴナイト鍾乳石の生成要因』(2022年3月)
上伊那教育委員会『戸台の石灰岩層と秋葉鍾乳洞について』
吉村 和久『カルストにおける化学的過程と鍾乳石に保存される古環境』
日本自然保護協会『長島の洞窟の現地調査および天然記念物指定を求める要望書を提出しました』(2018年8月)
植村 立『鍾乳石から気候変動を読み解く』(2016年)
琉球大学『最終氷期の沖縄はどのくらい寒かったのか? 〜貝化石と鍾乳石による新しい地質考古学的手法からの復元〜』(2021年11月)
吉村 和久『鍾乳洞に記録された大規模地震と津波』(2019年4月)
*5)鍾乳洞とSDGs
藤井 秀道『環境に関する情報開示と保全取組が経済パフォーマンスを向上させることを解明』(2024年12月)
農林水産省『景観-主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観』
国土交通省『健全な地下水の保全・利用に向けて』(2007年3月)
沖縄県『第3章 現状と課題』
IUCN『46,300種以上の生物に絶滅の危惧がある。全評価種の28%以上に相当する。』
*6)まとめ
WIKIMEDIA COMMONS『ユビナガコウモリ』
環境省『事例 No.57 山口県美祢市秋吉台』
農林水産省『堰事業における環境影響評価に係る主務省令の解説』(2018年3月)
林野庁『保護林制度等の現状と課題』(2014年6月)
国際協力機構『自然環境保護における地域住民参加の条件と課題 中国自然保護区の事例から』(2004年6月)
日本自然保護協会『メディアも報じなかったある「数字」(IUCNレッドリスト2020解説-3)』(2020年7月)
この記事を書いた人
松本 淳和 ライター
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。























