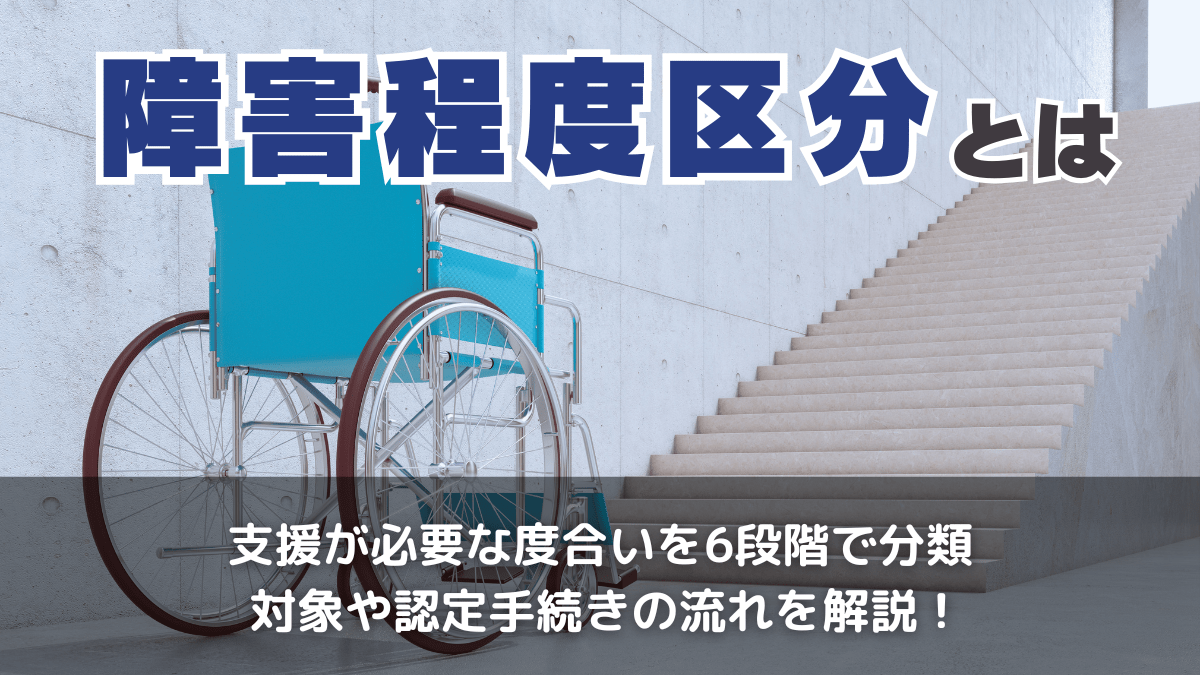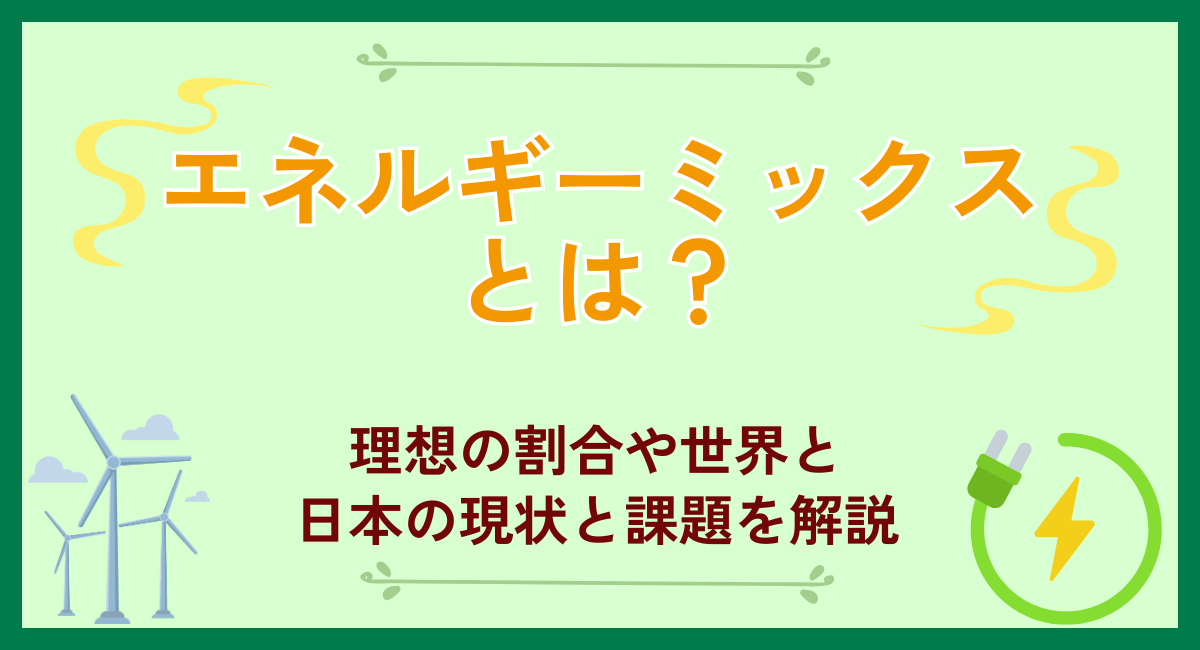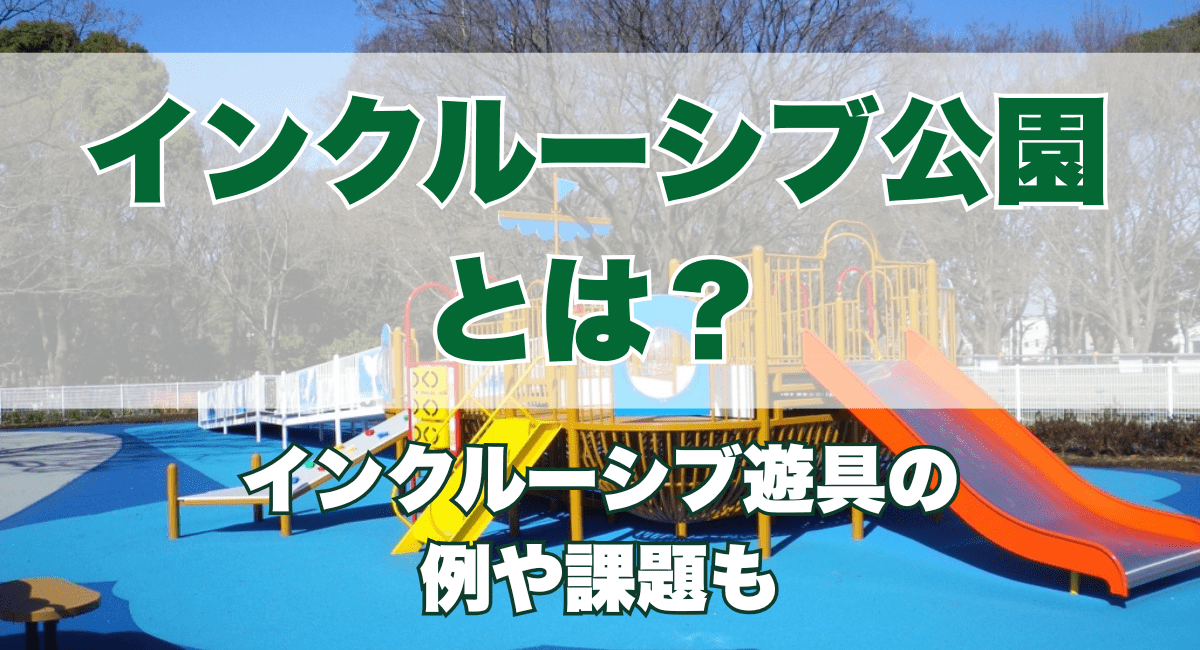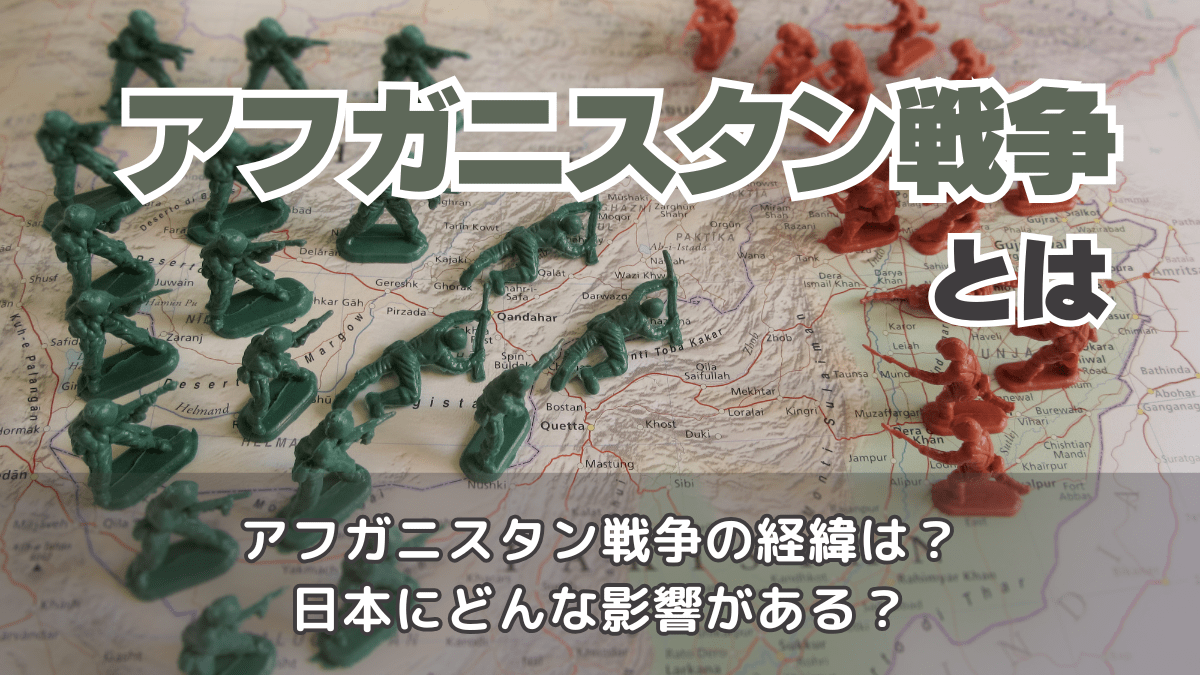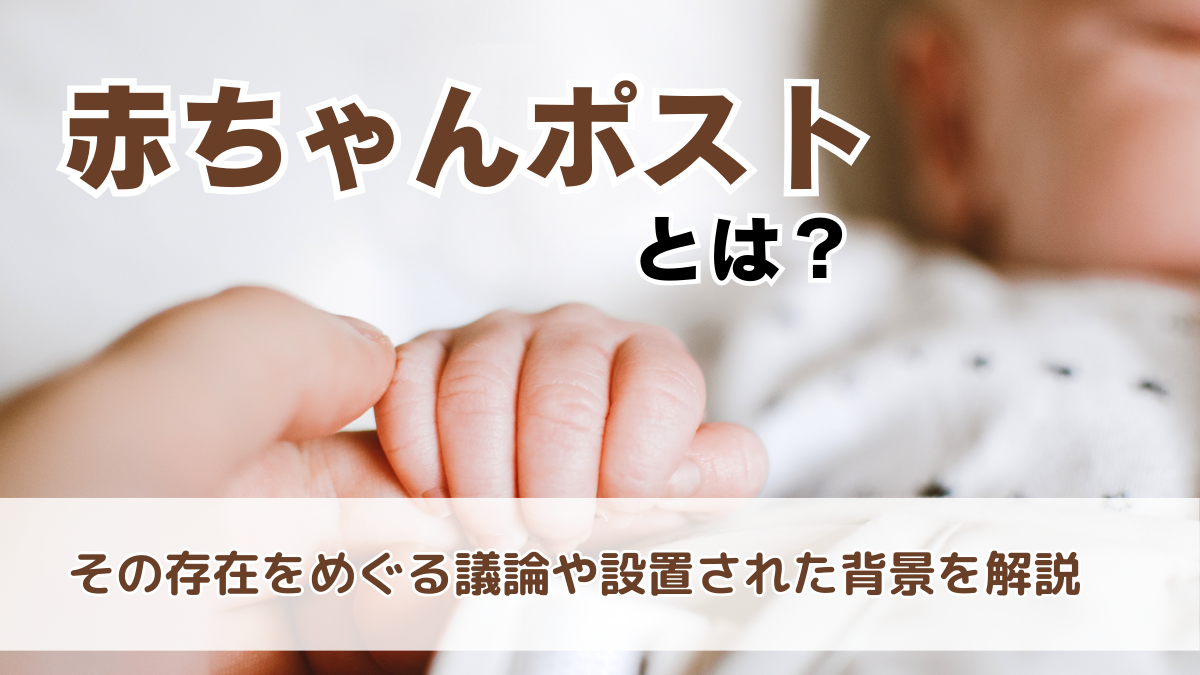
妊娠・出産や子育てに悩む女性の数は年々増加の一途を辿り、残念なことに児童遺棄や虐待の悲劇も後を絶ちません。
こうした問題が深刻化し始めた頃から、頼る人がいない母親とその子どもを救うために設けられたのが赤ちゃんポストです。しかし、その設立には当初から賛否両論があり、今もなお議論は続いています。赤ちゃんポストとはどのようなもので、その意義とは何なのか。改めて考える必要があります。
目次
赤ちゃんポストとは
赤ちゃんポストとは、親がどうしても自分で子どもを育てられない場合に、匿名で赤ちゃんを預けられる場所のことです。国内では、熊本市の医療法人聖粒会慈恵病院が2007年に設置した「こうのとりのゆりかご」ただ一ヶ所のみとなっています。
こうのとりのゆりかごには、2024年までの17年間で合計170人の赤ちゃんが預けられており、その存在をめぐって議論を巻き起こしながらも、出産や子育てに困難を抱えた女性たちの子どもを受け入れ続けてきました。
なお、赤ちゃんポストという名称は正式なものではありません。
当時の慈恵病院理事長・蓮田太二氏(故人)は、子どもは「もの」ではなく、託す場所として「ポスト」という名前は適切ではないとして「こうのとりのゆりかご」と命名しました。
その上で、本記事では一般に浸透している名称としてあえて「赤ちゃんポスト」を使用します。
赤ちゃんポストの仕組み
国内唯一の赤ちゃんポストである「こうのとりのゆりかご」は、慈恵病院一階の産科・小児科病棟南側の一角に設置されています。
ポストの構造
ポストは、外壁に備え付けられた高さ50センチ、幅58センチの扉の中にあり、扉の横には
「赤ちゃんをあずけようとしているお母さんへ 秘密は守ります 赤ちゃんの幸せのために扉を開ける前にチャイムを鳴らしてご相談ください」
という看板とインターホンがあります。ポストに入れる前になんとか思いとどまり、相談してほしいという思いからです。また令和3年3月からは、子どもの出自情報を少しでも残してもらうため、扉の前にメッセージカードの記載台が設置されました。
ポストの扉は二重になっています。外側の扉を開けると一通の手紙が置かれており、この手紙を手に取らなければ内側の扉は開きません。そしてこの手紙にもまた、相談や連絡を勧める旨が書かれています。
手紙を取り、内扉の引き戸を開けると、保温機能や酸素吸入機を備えた専用の保育器があり、そこに赤ちゃんを預け入れる仕組みになっています。預け入れて扉を閉めると自動でロックされ、外から扉を開けることはできません。
扉は開くと同時に産婦人科のナースステーションに通知されるようになっており、すぐさま看護師が駆けつけ、赤ちゃんの状態を確認して医師に連絡する体制がとられています。
この時点で預け入れた者との接触ができれば、できるだけ相談につないでいます。
預けられた後はどうなる?
赤ちゃんポストは、病院が子どもを引き取ってくれる施設と誤解されがちですが、あくまでも緊急避難の場です。
産婦人科病棟で赤ちゃんが保護されると熊本市と児童相談所、警察へ連絡し、健康面の安全が確認されるまでの間、引き続き病院で保護されます。その後は、
- 身元が分かる手がかりなどをもとに熊本市の児童相談所が調査
- 身元が判明すれば出生地の児童相談所を通して乳児院や児童養護施設などに入る
- どうしても身元が判明しなければ熊本市長が名前をつけ単独の戸籍が作られる。その後熊本市の乳児院や児童養護施設へ入所
となり、いずれの場合も児童養護施設での養育や里親への委託、特別養子縁組などの社会的養護につなげていくことになります。
赤ちゃんポストが設置された背景

赤ちゃんポスト「こうのとりのゆりかご」が作られるに至ったのは、2000年代初期から乳児の置き去りや殺害、遺棄が相次ぎ、社会問題になり始めたという背景があります。
こうした問題を重くみた慈恵病院・蓮田太二理事長は2004年に、ドイツの赤ちゃんポスト「ベビークラッペ」を視察。「遺棄されて亡くなる子どもの命を救いたい」という思いを新たにした蓮田氏は日本版ベビークラッペの創設を決意し、2006年に設置のための施設変更を熊本市に申請しました。
国を巻き込んだ論争に
申請を受理した熊本市は「ゆりかご」の設置が現行の法令に違反しないかを慎重に検討するため、国や県と協議を始めました。
市が特に判断に苦慮したのは、親が新生児をポストに預けることが
- 児童虐待防止法の児童虐待
- 母子保健法の妊娠の届け出義務
- 民法の親族の扶養義務
- 刑法の保護責任者遺棄罪
- 児童の権利に関する条約
などに違反しないかという法的整合性でした。
熊本市は戸籍法や遺棄罪、児童福祉法など関連法規すべてを関係部局と議論した上で、社会的影響の大きさを考慮して単独での判断を避け、国(厚生労働省・法務省)の見解や書面による回答を求めます。
両省とも「安全が確保されれば法的な問題はない」という見解を示しながらも、当時の安倍首相や一部の閣僚が否定的な発言をしたことで、文書での正式な回答はありませんでした。
それでも法的な問題をクリアしたと判断した市は、2007年4月に慈恵病院に変更を許可します。こうして翌5月に「こうのとりのゆりかご」の運用が開始されたのです。
なぜ赤ちゃんポストに子どもを預けるのか

開設当初「年に一人あるかないか」という病院の想定に反し、こうのとりのゆりかごにはこれまで平均0.93件、つまり月にほぼ一人のペースで子どもが預け入れられてきました。
そしてそのほとんどが母親であり、赤ちゃんポストに子どもを預けにきた女性たちにも、さまざまな背景があります。
理由①予期せぬ妊娠・望まぬ妊娠
赤ちゃんポストに子どもを預け入れる大きな理由のひとつは、予期せぬ妊娠や望まない妊娠です。そして妊娠の背景を見ても
- 中高生など若い世代の妊娠
- 不倫関係による妊娠
- 性暴力や売春などによる妊娠
などといった問題を抱えていることがほとんどです。
彼女たちの多くは、こうした理由で妊娠の事実を知られたくないがために、誰にも相談できないまま一人で子どもを産み落とし、思い悩んだ結果赤ちゃんポストへ子どもを預け入れる道を選んでしまいます。
理由②パートナー・家族の反対
また本人ではなく、相手の男性や女性の親・祖父母などが産み育てることに反対し、赤ちゃんポストを使うよう勧めたという事例もありました。本人は子どもを育てる意思があるにもかかわらず、
- (男性が)養いたくない/子どもに関心がない
- (親・祖父母が)世間体を気にする
- 戸籍が汚れる
などの理由で養育を認めてもらえないという、信じがたいケースも報告されています。その中には、経済的に安定した人や教育職にある家庭も少なくありません。
理由③生活の困窮

他の理由として大きいのが、経済的理由などによる生活困窮です。
日本における相対的貧困率は2021年に15.4%ですが、ひとり親家庭では実に44.5%にも上ります。生活意識調査でも母子家庭の82.7%が「生活が苦しい」と答えており、未婚のまま妊娠・出産した女性や妊娠の時点で生活が困窮している女性が安心して子どもを産み育てることは困難なことがわかります。実際に赤ちゃんポストを利用した女性の中には
- 既に子どもが複数いるのに妊娠してしまい、これ以上養えない
- 次に出産してしまうと生活保護を取り消されると思った
- 学生で妊娠・出産してしまい学業と育児が両立できない
などといった声がありました。
生活困窮は赤ちゃんポストに預け入れた理由の中でも突出して高い割合を占めており、直近の数年はこの割合がひときわ高くなっています。
理由④育児不安・負担感
令和に入ってから急増した預け入れの理由に、育児への不安と負担感があります。
直近の調査報告では産後の強い育児不安、いわゆる産後うつなどで衝動的に赤ちゃんポストに入れたケースが複数見られました。
理由⑤子どもの障害
親が子どもに障害があることを受け入れられずに、赤ちゃんポストを利用した事例も見られました。赤ちゃんポストに預けられた170人の子どものうち17人に、ダウン症や先天性の心疾患、脳性麻痺、形成異常など何らかの障害があったこともわかっています。
追いつめられる女性と身勝手な男たち
これらの事例のほとんどに共通しているのが社会的孤立です。
そこには家族に妊娠を知られたくない、身近な者や行政サービスにも相談できない、あるいは公的支援を知らないなど、多くの女性が追いつめられている現実があります。
そして多くの事例でもうひとつ共通しているのが身勝手な男性たちの存在です。
彼らはパートナーの妊娠にも出産にも総じて無関心で、中には中絶を強要する者すらいます。こうした身勝手な男性が責任を放棄し、女性にすべての負担を押しつけていることが、赤ちゃんポストを含む児童福祉の問題を深刻化させる一因であることは間違いありません。
赤ちゃんポストのメリット

赤ちゃんポストは設置以来多くの想定外の事例に遭遇しながらも、そのいくつかのメリットによって、困難を抱える親や子どものために一定の役割を果たしてきました。
メリット①新生児の命を救う
赤ちゃんポストのメリットとしてあげられるのが、遺棄されて亡くなる可能性のある子どもに医療的ケアを施せることです。
特に妊娠を誰にも話せず、孤立出産をした女性の中には、妊産婦健診や母子手帳交付などを受けていない者も多く、自分で出産して産後の処置を行う例も少なくありません。その結果乳児は、へその緒の化膿や多血症、低体温などの生命の危険に晒されやすくなります。
慈恵病院では常に医療スタッフが常駐し、ポストに預け入れられた直後から迅速なケアが行えることで、こうした危険を防いできました。
メリット②社会的養護との連携の意義
慈恵病院は、こうのとりのゆりかご設置の当初から市と児童相談所、警察との緊密な連携を取ることで、速やかな支援体制を確立しているのが特徴です。
その後の対応についても、子どもにとって何が最善かを考慮してそれぞれの事情に応じた養育先の選定などにつながっている、と評価されています。
また慈恵病院には全国から妊娠に関する相談が多数寄せられており、こうした相談内容や預け入れた理由への分析や対策が、公的機関による支援・相談体制の充実を促している側面も無視できません。
メリット③匿名で受け入れることへの親の安心感
赤ちゃんポストのメリットとして慈恵病院が主張するメリットとしては、匿名で預けられることへの親の安心感があります。
ここまで見てきたように、孤立し追いつめられた妊婦や母親は、実名を名乗ることで不利益になるさまざまな経済的・社会的問題を抱えています。
病院側が匿名での受け入れを保証することは、母親の預け入れへの心理的ハードルを下げ、社会からの緊急避難先としてさまざまな社会的支援に結びつける入口にもなり得ます。
赤ちゃんポストのデメリット・課題

一方で上記のメリットは、そのままデメリットへとつながる危険性もはらんでいます。
「子どもの命を守る」という観点で設置された赤ちゃんポストですが、預けられた後に生じる問題を考えると、全面的に肯定はされていないのも事実です。
デメリット①母子の身体的安全
赤ちゃんポストへの懸念のひとつが、出産から預け入れまでの間に母子が身体的に危険な状態に陥ることです。
孤立出産によって子どもが低体温や感染症など生命の危険に晒されることについては前述しましたが、一方では
- 遠方から熊本への長時間移動が新生児への処置を遅らせ、治療を要する状態を生じさせたまたは悪化させた可能性がある
- 障害やアレルギーなど養育に必要な情報が不足する
- 預け入れ後に実母との接触ができない場合や診察を拒否される場合に、産後の心身の安全性が確保できない、福祉的なケアにつなげられない
などの問題も指摘されています。熊本市もこうした現状を憂慮し、結果的に生命の危険が回避されて養育につなぐ意義は認めながらも「設備上の安全性のみをもって、こどもの生命・身体の安全性が確保されていると評価することは難しい」と評価しています。
デメリット②出自を知る権利との兼ね合い
匿名に重きを置く慈恵病院の運用方針は、預ける側のメリットである反面、子どもの自分の出自を知る権利にとってはデメリットとなります。
国連の「子どもの権利条約」でも、自分の実の親を知る権利は保障されており、ポストに預けられた子どもはいずれ自分の本当の親を知りたくなる時がやってきます。
熊本市の専門部会では、この「出自を知る権利」に照らして匿名性の問題を指摘する一方、慈恵病院側は匿名性を堅持する姿勢を崩していません。
こうした問題に対処するため、慈恵病院では2017年に内密出産制度を導入しました。
これは妊婦の身元情報を病院の一部の者にしか明かさずに出産するもので、匿名で子どもを預けたい親と、いずれ出自を知りたい子どもの権利を両立できるとされています。
デメリット③安易な預け入れを助長する懸念
当初から指摘されていたデメリットは、安易な預け入れを助長する点です。
預け入れた親の中には子育てに困難を抱える人が多数いる一方で、世間体や職業を優先し、罪悪感なく手放す人も少なくありません。
実際、赤ちゃんポストの社会的認知が広がるにつれ、2回利用するケースや障害のある子の預け入れが増加したこともあり、最終手段ではなく選択肢の一つとして扱われる懸念があります。
その他の赤ちゃんポストをめぐる動き

近年では、慈恵病院以外でも赤ちゃんポスト設立に向けた動きが目立っています。
こうのとりのゆりかごに賛同した関西のNPO法人は、2017年に神戸市の助産院で赤ちゃんポスト設置を計画しましたが、常駐医師の確保が困難なため断念しています。
また、2022年には北海道当別町に民間団体による「ベビー・ボックス」が開設されていますが、北海道は運営を公的には認めていません。いずれの例も、運用の困難さや行政との連携の不備が壁となっています。
2023年9月には、東京都墨田区にある社会福祉法人賛育会が、2024年度から妊娠相談や内密出産、赤ちゃんポストの設置を開始するとしており、今後の動向が注目されます。
赤ちゃんポストに託された子どもの現在

日本初の赤ちゃんポストであるこうのとりのゆりかごが始まってから、今年で18年目を迎えます。この間に預け入れられた子どもたちのその後はどうなっているのでしょうか。
熊本市の「こうのとりのゆりかご専門部会」の報告書によれば、170名のうち身元が判明しているのは135人(79.4%)となっており、令和5年の時点では
- 児童養護施設での養育…身元判明:25人/身元不明:6人
- 里親のもとでの養育…身元判明:9人/身元不明:5人
- 実の家庭に引き取られた…32人
- 特別養子縁組が成立…身元判明:63人/身元不明:24人
という状況になっていることがわかっています。
預けられた男性の話
そんな中、かつて赤ちゃんポストに預けられた男性が、18歳になった時に実名で自らの生い立ちを公表したことが話題になりました。
男性の名前は宮津航一さん。こうのとりのゆりかごの運用初日に預けられた最初の子どもで、その時点で既に3歳だったことも関係者に衝撃を与えました。
ほどなく現在の養親のもとに預けられた宮津さんは、新しい家族の愛情に包まれながら育ちます。しかし本人は、預けられた時のことをおぼろげながら記憶しており、賛否両論ある「こうのとりのゆりかご」について当事者として発信する意義から、いずれ公表したいという気持ちを持っていました。
現在、子ども食堂の活動を行う宮津さんは、赤ちゃんポストという名称について再考すべきことや公的な育児支援・サポートを充実させた上で、最終手段としてのこうのとりのゆりかごの役割を評価しています。
赤ちゃんポストとSDGs

SDGs(持続可能な開発目標)の観点からも、赤ちゃんポストが果たす役割は少なくありません。中でも関連が深いのが
の2つの目標です。そしてこれらの目標を達成するには
- 妊産婦と乳児に対する安全で包括的な福祉体制の整備(目標3)
- 女性に対するあらゆる差別や有害な慣行の撤廃(目標5)
- すべての人々、特に男性に対する包括的性教育の実施(目標5)
といった取り組みが不可欠となってきます。
まとめ

赤ちゃんポストの存在は、私たちの暮らす社会がいかに子どもを産み育てることが難しくなっているかという事実を浮き彫りにしました。それは決して当事者である母子だけの問題ではなく、父親であるべき男性、そして社会全体が等しく考えるべき課題でもあります。
慈恵病院の蓮田元理事長は生前、赤ちゃんポストの設置にあたって「こんなものは本来使われるべきではない。これが使われなくなることが理想」と語っていました。一日も早く、その日が来ることを願うばかりです。
参考文献・資料
赤ちゃんポストの真実:森本 修代/小学館,2020年
なぜ、わが子を棄てるのか-「赤ちゃんポスト」10年の真実:日本放送協会/NHK出版2018年
「こうのとりのゆりかご」第6期検証報告について|熊本市要保護児童対策地域協議会 こうのとりのゆりかご専門部会
医療法人聖粒会慈恵病院 こうのとりのゆりかご
第32回北海道自治研集会 第Ⅱ-①分科会 子育て支援と児童虐待「こうのとりのゆりかご(赤ちゃんポスト)」をめぐる状況と行政サービスに与えた影響 熊本県本部/衛生医療評議会・事務局長 伊津野浩
「乳児遺棄を助長する」と大逆風…それでも元熊本市長が「日本初の赤ちゃんポスト」にGOサインを出した理由|PRESIDENT Online
子どもの9人に1人が貧困に陥る日本親子に必要な支援のあり方は | RENGO ONLINE
3歳で「ゆりかご」に預けられた男性(19)が、生い立ちを公表した理由「好奇の目に晒されないよう、ずっと家族の秘密にしていた」 | 文春オンライン
「“赤ちゃんポスト”出身だとは言いたくない」3歳で「ゆりかご」に預けられた男性(19)が語る、里子たちの現状 | 文春オンライン
この記事を書いた人
shishido ライター
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。