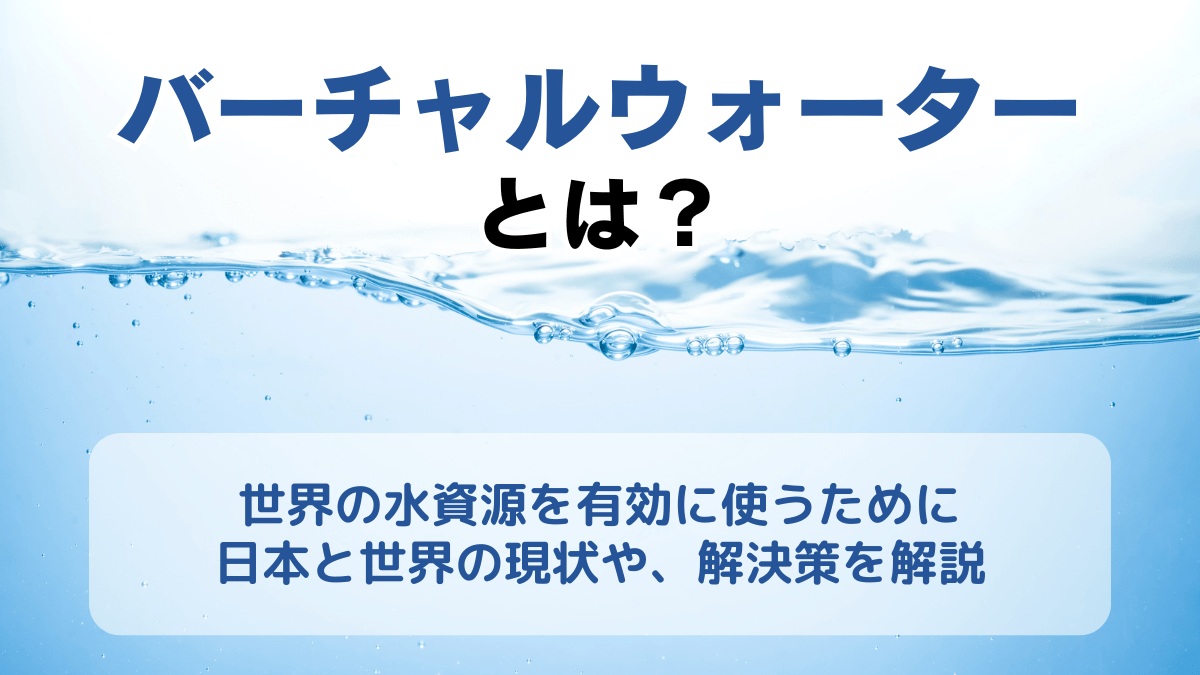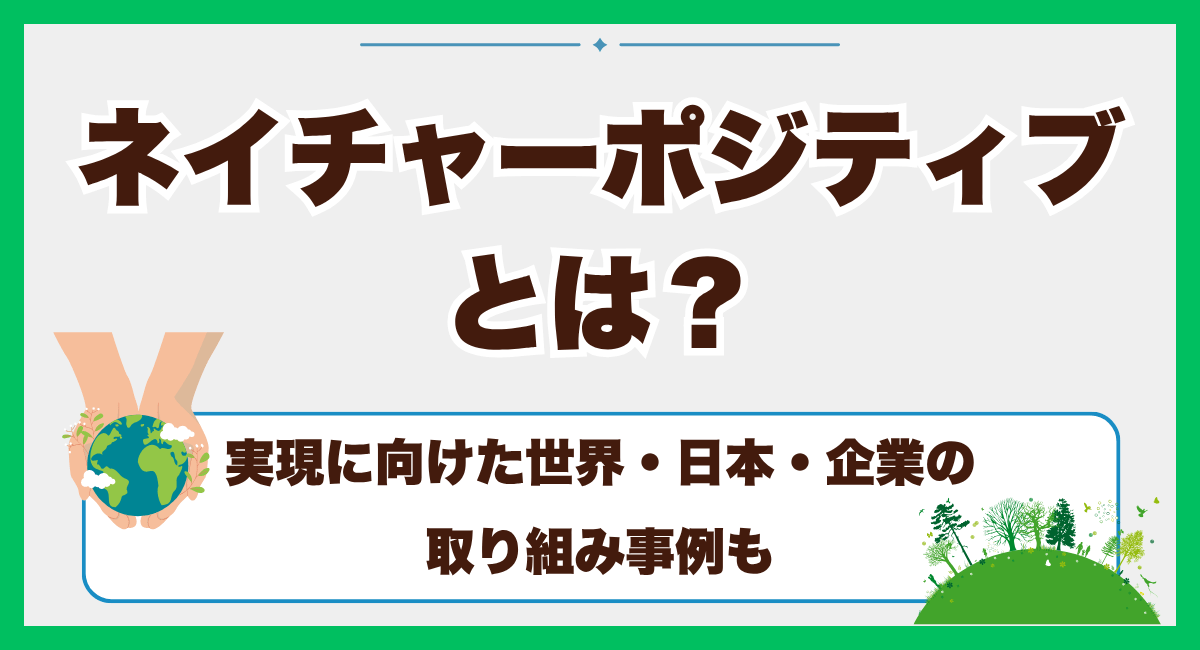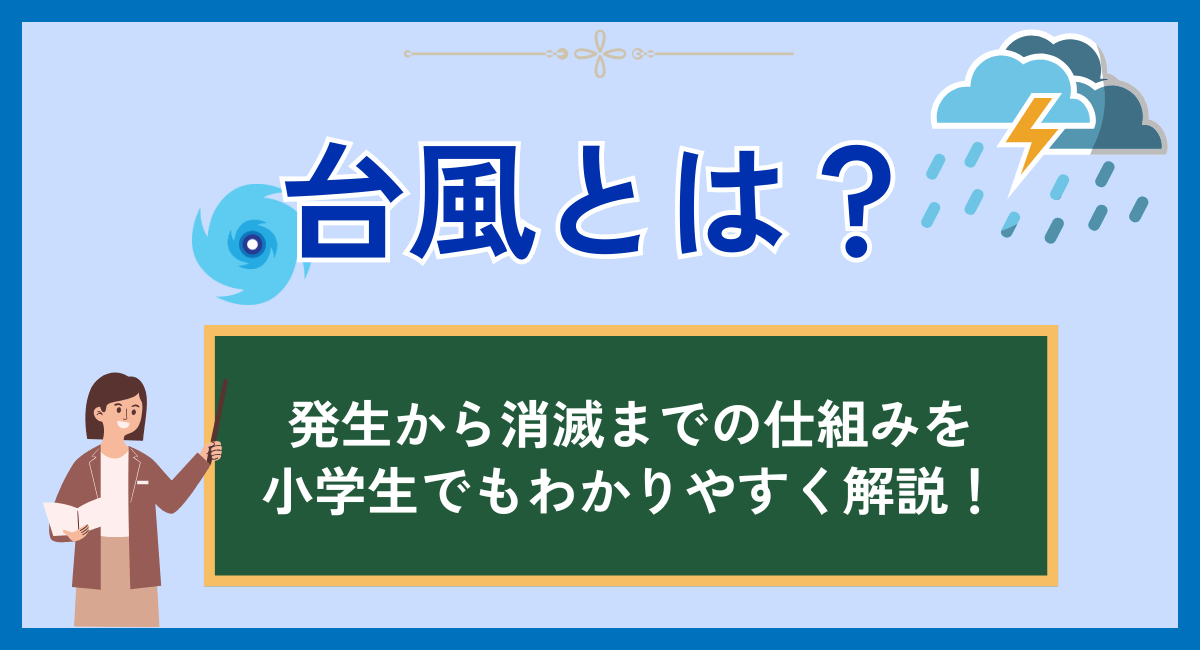
台風は日本や世界の各地に、強風や豪雨をもたらし、時に甚大な被害を引き起こします。台風とは、どのような気象現象なのでしょうか?
地球温暖化との関係も指摘される中、その発生から消滅までの仕組みを理解することは、安全な生活を送る上でも重要です。台風の発生メカニズムから、過去の災害事例、そして未来への備えまで、多角的な視点から小学生にもわかりやすく解説します。台風を知り、地球と共生するための知識を身につけましょう。
目次
台風とは

台風とは、北西太平洋または南シナ海で発生する熱帯低気圧のうち、低気圧域内の最大風速が約17m/s以上に達したものを指します。これは気象庁によって定められており、台風の学術的な定義として広く認知されています。
台風について理解するために、いくつかの重要なポイントを見ていきましょう。
台風の学術的な定義
台風は、次の2つの条件を満たす熱帯低気圧として定義されます。
- 発生場所:赤道より北側で東経180度より西側の北西太平洋、または南シナ海
- 最大風速:低気圧域内の10分間の最大風速が約17m/s以上
これらの条件を満たす熱帯低気圧は「台風」と呼ばれます。台風は主に赤道付近の熱帯地域で発生し、海面からの水蒸気をエネルギー源として勢力を増していきます。
ハリケーン、サイクロンとの違い
台風、ハリケーン、サイクロンは、本質的には同じ気象現象です。これらはすべて熱帯低気圧が発達したものですが、発生する場所によって呼び名が異なります。
- 台風:北西太平洋または南シナ海
- ハリケーン:北東大西洋、北大西洋、メキシコ湾、カリブ海
- サイクロン:北インド洋(アラビア海、ベンガル湾)
また、最大風速の定義にも若干の違いがあります。ハリケーンは約33m/s以上、サイクロンは台風と同じく約17m/s以上とされています。
【世界各地の発達した温かい低気圧の呼び方】

台風の大きさと強さ
台風の勢力は、その大きさと強さによって表現されます。
【台風経路図(実況と5日先までの予報)】
大きさ
大きさは、強風域(風速15m/s以上)の広さによって決定されます。上の経路図では黄色い円で表されています。
- 大型:強風域の半径が500km以上800km未満
- 超大型:強風域の半径が800km以上
【大きさの階級分け】
強さ
強さは、最大風速によって段階に分類されます。
- 強い:33m/s以上44m/s未満
- 非常に強い:44m/s以上54m/s未満
- 猛烈な:54m/s以上
これらの分類は、台風情報で「大型で強い台風」「超大型で非常に強い台風」などと表現されます。
【台風の強さ】
単位と階級分け
台風の中心気圧を表す単位には「ヘクトパスカル(hPa)」が使用されます。この数値が低いほど強い低気圧となり、強風になる可能性が高くなります。
1951年以降、日本へ上陸直前の台風で最も低い中心気圧は925hPaでした。
台風は複雑な気象現象ですが、これらの基本的な知識を理解することで、台風情報をより正確に解釈し、適切な防災対策を取ることができます。次の章では、台風の発生から消滅までの仕組みについて詳しく見ていきます。*1}
台風の仕組み

台風は、その発生から消滅までに驚くべき変化を遂げる自然現象です。台風がどのように生まれ、成長し、そして消えていくのか、その仕組みを確認してみましょう。
①発生
【台風の発生する仕組み】
台風の誕生は、熱帯の海上で始まります。水温が27度以上の海域で、大気の状態が不安定になると、積乱雲が発生します。
これらの積乱雲が集まり、組織化されると熱帯低気圧となります。
【風の強さ (予報用語) 平均風速 (m/s) おおよそ の時速】
熱帯低気圧の中心付近の最大風速が17m/s以上に達すると、正式に台風として認識されます。台風の発生は年中続いています。
しかし、台風の進路は季節によって変わります。
【月別の台風発生・接近・上陸数の平均値】
台風の発生には、海面からの水蒸気の供給が不可欠です。暖かい海面から蒸発した水蒸気が上昇気流となり、凝結する際に放出される潜熱が台風のエネルギー源となります。このプロセスが継続することで、台風は勢力を増していきます。
②移動
【台風の月別の主な経路】
台風の移動は、大気の流れに大きく影響されます。一般的に、台風は西よりに進み、その後、北に向きを変えて日本付近に接近します。この動きには、地球の自転による影響(コリオリの力※)が関係しています。
春先には、台風の発生緯度が低く、フィリピンなど西側の進路を通ることが多くなります。一方、夏になると、より高緯度で発生する台風が増え、太平洋高気圧の周りをなぞるような進路で日本付近へと北上してくる傾向があります。
台風の発生数は8月が最も多く記録されます。しかし、8月に発生した台風は経路が不安定な事が多く、日本に接近する台風が増えるのは通常、9月以降です。
※コリオリの力
コリオリの力とは、地球のような回転する場所で、動くものが曲がって見える現象。地球の自転によって、地上を移動する物体は、実際にはまっすぐ進んでいるにもかかわらず、曲がって進んでいるように見える。北半球では右に、南半球では左に曲がって見える。台風の渦巻きや、長距離を飛ぶ飛行機・ミサイルの軌道計算に影響する。フランスの科学者、コリオリが発見した。
【コリオリの力が無い場合・働いた場合】
台風の回転方向もコリオリの力の影響を受ける
コリオリの力により、北半球では台風は反時計回りに回転します。この回転は台風の構造を維持し、さらなる発達を促します。
台風の中心付近では、強い上昇気流が発生し、周囲から空気が吸い込まれます。この上昇気流が「台風の目」を形成します。
【台風の目】

③消滅
台風の寿命は平均で5.2日程度です。消滅の過程は主に以下のように進みます。
- 台風が陸地への上陸:水蒸気の供給が絶たれ、摩擦により勢力が弱まる
- 寒冷な海域への移動:暖かい海面からのエネルギー供給が減少
- 中緯度帯での温帯低気圧化:前線を伴う温帯低気圧に変化
台風が温帯低気圧に変化すると、中心付近の風や雨は弱まりますが、より広い範囲で強風や大雨が発生する可能性があります。場合によっては再発達して勢力が強まることもあるため、台風から温帯低気圧に変わっても油断せず、警戒を続ける必要があります。
予測・情報の重要性
【暴風域に入る確率の分布図の例(5日先まで)】
【台風経路図の見かた(観測点の色)】
台風が日本に接近・上陸する際、その進路や強度の予測が非常に重要になります。気象庁は、台風に番号を付けて管理し、その動向を常に監視しています。
また、アジア太平洋地域の国々が協力して、台風にアジア名を付けることで、防災意識の向上を図っています。例えば、2024年の最大の台風は第10号で、アジア名は「サンサン」でした。
台風に関する最新の研究
最新の研究では、台風の観測技術が飛躍的に向上しています。例えば、名古屋大学の研究グループは、航空機から投下する気象測器(ドロップゾンデ)を開発し、台風の目の中の詳細なデータを取得することに成功しました。これにより、台風の構造や強度変化のメカニズムがより深く理解されつつあります。
【台風の目に上空から気象測器(ドロップゾンデ)を投下する研究】
台風の仕組みを理解することは、防災・減災の観点から非常に重要です。気象学の進歩により、台風の予測精度は年々向上していますが、気候変動の影響で台風の性質も変化している可能性があります。今後も継続的な研究と観測が必要とされています。*2)
台風の影響
【平成16年台風第18号の高波による被害(北海道神恵内村)】

台風は、その強大な力で私たちの生活に多大な影響を及ぼします。強風と豪雨、高潮と高波など、台風がもたらす現象は時に甚大な被害をもたらすこともあります。
台風の影響を正しく理解し、適切な対策を講じることが重要です。
【台風が引き起こす災害】

強風と豪雨
台風の最もよくわかる特徴は、強い風と激しい雨です。台風の中心に近いほど風は強くなり、特に進行方向に向かって右側(危険半円)で最も強い風が吹きます。
台風の目の周りを積乱雲が壁のように取り巻いており、そこでは猛烈な暴風雨となります。台風の外側200〜600 kmには帯状の降雨帯があり、長時間にわたって激しい雨をもたらします。
【台風の危険半円(北半球の場合)】
この強風と豪雨は、建物や樹木に被害を与えるだけでなく、
- 飛散物による怪我
- 大量の廃棄物
- 土砂災害
- 洪水・浸水
- 停電・断水
- 交通の遮断
など二次被害も引き起こします。
高潮と高波
台風接近時には、気圧低下による海面の吸い上げ効果と強風による海水の吹き寄せ効果により、高潮が発生します。日本では特に
- 東京湾
- 伊勢湾
- 大阪湾
- 瀬戸内海
- 有明海
など、遠浅で南に開いた湾では高潮の影響が大きくなります。
【吸い上げ効果】
【吹き寄せ効果】
【高潮の発生】
高潮に加えて高波が重なると、海岸堤防を越えて海水が陸地に流れ込み、大規模な浸水被害をもたらす可能性があります。過去50年間に潮位偏差が1m以上となった高潮も記録されており、沿岸部では特に注意が必要です。
生活への影響と対策
台風の接近時には、交通機関の乱れや停電、断水などが発生する可能性があります。台風の影響が強くなる前に、食料や飲料水、懐中電灯などの備えを整えておくことが重要です。
また、ハザードマップで自分の住む地域のリスクを確認し、
- 警報・注意報
- 土砂災害警戒情報
- キキクル(大雨・洪水警報の危険度分布)※
などの最新情報に注意を払う必要があります。
【台風による一般の生活への影響】
近年の研究では、地球温暖化の影響により台風の勢力が増す傾向にあることが指摘されています。このため、これまでの対策に加えて、政府や地方自治体などでは、気候変動を考慮した新たな防災・減災対策の検討も進められています。*3)
代表的な台風の被害例
【2013年の台風ハイエンによるフィリピン・タクロバン市郊外の被害の様子】
台風は古来より人々の生活に大きな影響を与え、歴史に刻まれてきました。文学作品から歴史的事件、近代の観測記録まで、台風の様子や被害は様々な形で記録されています。
これらの記録から、台風の歴史と人類の関わりを深く理解することができます。また、近年の台風は発生数が減る傾向が見られる一方で、強度が増し、日本列島の太平洋側への接近が増えています。
歴史的な記録の中の台風
【海没する元軍(葛飾為斎・画)】
日本の古典文学野中にも台風の描写が見られます。平安時代の作品である清少納言の『枕草子』や紫式部の『源氏物語』では、「野分」という言葉で台風が表現されています。
これらの作品では、台風がもたらす風景の変化や人々の心情が繊細に描かれており、当時の人々の台風に対する認識を垣間見ることができます。
また、歴史上最も有名な台風の記録の一つは、1281年の弘安の役(元寇)で元軍を襲った「神風」と言えるでしょう。この台風により元軍の船団が壊滅的な被害を受けたとされ、日本の歴史を大きく変えた出来事として知られています。
近代以降の大きな台風
【伊勢湾台風による名古屋市の被害状況】
近代に入ると、台風の観測や記録がより詳細になります。
- 1945年の枕崎台風
- 1959年の伊勢湾台風
- 1934年の室戸台風
は「昭和の三大台風」と呼ばれ、非常に大きな被害をもたらしました。特に伊勢湾台風は、死者・行方不明者が5,000人を超える大災害となり、その後の防災対策に大きな影響を与えました。
【室戸台風の天気図(1934年9月21日)】
世界に目を向けると、1970年11月にバングラデシュを襲ったボーラ台風(ボーラ・サイクロン)は、30万人以上の犠牲者を出す大惨事となりました。この災害は、気象観測技術の重要性と防災対策の必要性を世界に強く認識させるきっかけとなりました。
近年の大きな台風
【サイクロン・ナルギス】
21世紀に入っても、台風による大規模な被害は続いています。2008年5月にミャンマーを襲ったナルギス台風(サイクロン・ナルギス)は、13万人以上の犠牲者を出し、気候変動が台風に与える影響について議論を呼びました。
2013年にフィリピンを襲った台風ハイエン(フィリピン名:ヨランダ)は、観測史上最大級の勢力を持つ台風として記録されました。この台風は、高潮による甚大な被害をもたらし、気候変動による台風の強大化への懸念をさらに高めました。
日本においても、2019年の台風19号(令和元年東日本台風)は、広範囲に記録的な大雨をもたらし、各地で河川の氾濫や土砂災害が発生しました。この台風は、都市部における水害対策の重要性を再認識させる契機となりました。
【令和元年東に半台風による被害の様子】
このような台風による被害の歴史を振り返ることで、私たちは自然の力の大きさを再認識し、より効果的な防災対策の必要性を学ぶことができます。同時に、気象観測技術の進歩や気候変動研究の重要性もよくわかります。
台風の歴史は、人類と自然との関わりを考える上で、貴重な教訓を与えてくれるのです。*4)
台風とSDGs

台風とSDGs(持続可能な開発目標)は、一見すると関連性が薄いように思えるかもしれません。しかし、台風研究や対策は、気候変動への適応、災害に強い社会づくり、そして環境保全など、多くのSDGs目標達成に貢献しています。
また、台風に関する取り組みは、
- 気象学的研究
- 防災・減災対策
- 復旧・復興支援
- 環境保全
- 生態系保護
まで広い範囲にわたります。これらの活動は、SDGsが掲げる「誰一人取り残さない」という理念に沿うもので、特に気候変動対策や持続可能な都市づくりなどの目標達成に大きく貢献しています。
特に関係の深いSDGs目標を見ていきましょう。
SDGs目標11:住み続けられるまちづくりを
台風対策は、災害に強いまちづくりに直接的に貢献します。例えば、高潮対策としての堤防整備や、豪雨に備えた排水システムの改善は、都市インフラの強化につながります。
また、ハザードマップの整備や避難計画の策定は、災害に強いコミュニティづくりを促進します。
SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を
台風の研究は気候変動の影響を理解し、適応策を考える上で重要な役割を果たしています。例えば、台風の強度や頻度の変化を分析することで、将来の気候変動シナリオの精度向上に貢献しています。
さらに、台風に強い建築技術の開発や、早期警報システムの改善は、気候変動への適応力を高める具体的な対策となっています。
SDGs目標15:陸の豊かさも守ろう
台風は、森林破壊や土砂災害を引き起こし、生態系に深刻な影響を与えることがあります。森林の保全や持続可能な土地利用は、台風による被害を軽減するだけでなく、生物多様性を守る上でも重要です。
このような台風とSDGsの関係性を理解し、統合的なアプローチを取ることで、より効果的な災害対策と持続可能な社会の実現が可能になるのです。*5)
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ

台風は、その強大な力と複雑な仕組みで、私たちの生活に多大な影響を与える自然現象です。最近では、AI技術を活用した気象予測モデルの急速な進歩が挙げられます。
これにより、台風の進路や強度の予測精度が飛躍的に向上し、より効果的な防災対策が可能となっています。しかし一方で、気候変動の影響により、台風の強大化や頻発化が懸念されており、今後さらなる対策が必要とされています。
台風に関する知識を深めることは、単に自然現象を理解するだけでなく、防災意識の向上や持続可能な社会の実現にもつながります。私たち一人ひとりでも、ハザードマップの確認や家族で避難計画を決めておくなど、具体的な防災対策をしておくことが重要です。
また、環境保護活動や気候変動対策への参加も、間接的に台風被害の軽減につながる可能性があります。
あなたは、自分の住む地域の台風リスクをどれだけ把握していますか?
台風は脅威である一方、地球の気候システムの重要な一部でもあります。私たち一人ひとりが台風への理解を深め、適切な対策を講じることで、より安全で持続可能な社会の実現に貢献できるのです。
自然と共生しながら、よりよい未来を築くために、今日からできることを始めましょう!*6)
<参考・引用文献>
*1)台風とは
気象庁『台風を知る』
気象庁『台風情報の種類と表現方法』
気象庁『台風の大きさと強さ』
国立情報学研究所『デジタル台風:台風の強さと大きさ – 気圧と風速の単位』
気象庁『気圧配置 台風に関する用語』
気象庁『台風とは』
気象庁『台風の大きさと強さ』
気象庁『台風予報の精度検証結果』
気象庁『~台風の季節~』
国立情報学研究所『デジタル台風:台風の一生 – 台風(熱帯低気圧)の定義と長寿台風・温帯低気圧との関係』
国立情報学研究所『デジタル台風:台風(タイフーン)・ハリケーン・サイクロン』
*2)台風の仕組み
日本ジオパーク『台風について』
気象庁『風の強さ (予報用語) 平均風速 (m/s) おおよそ の時速』
気象庁『台風の発生、接近、上陸、経路』
気象庁『台風を知る』
気象庁『台風情報の種類と表現方法』
気象庁『台風の一生』
気象庁『台風の番号とアジア名の付け方』
気象庁『過去の台風の番号と名前の対応表』
国立情報学研究所『デジタル台風:台風経路図(台風進路図)』
国立情報学研究所『デジタル台風:台風観測とドボラック法』
国立情報学研究所『デジタル台風:台風の上陸・接近・通過の定義』
国立情報学研究所『デジタル台風:前線と台風』
国土交通省『台風に関する豆知識について』
名古屋大学『気象50のなぜ+10 45.コリオリの力(ちから)とは?』
九州大学『台風を発達・維持させる新たな巨視的メカニズム』(2019年7月)
九州大学『台風の遠隔降水の謎を紐解く新たなメカニズムを提唱~水蒸気コンベアベルトがもたらす梅雨期の豪雨~』(2023年6月)
金田 幸恵,和田 章義『非常に強い台風に見られる二つの発達プロセス』(2015年12月)
科学技術振興機構『A-1.「制御可能性」を導く新しい気象データの構築・解析と制御手法設計』
三重大学『台風衰弱の新プロセス~圏界面変動の影響~』(2015年)
坪木 和久『:航空機観測によるスーパー台風の力学的・熱力学的構造と強化プロセスの解明』(2023年3月)
島畑 あゆみ,三野 弘文『コリオリの力の台風への影響を正しく理解するための試行』(2023年3月)
日本気象学会『コリオリ力の「ユリイカ」』(2013年2月)
大阪市立科学館『台風のはなし』(2022年11月)
日本気象学会『洪水災害に対する気候変動の影響と適応』(2022年7月)
nikkei4946『台風発生の仕組みや防災対策を知る』(2016年9月)
防災化研『“台風の眼”に測器投下、取得データの高精度を実証 ~世界各国の数値予報で活用、台風観測が大きく前進~』(2024年10月)
*3)台風の影響
気象庁『高波による災害』
国土技術研究センター『国土を知る / 意外と知らない日本の国土』
環境省『勢力を増す台風~我々はどのようなリスクに直面しているのか~』(2023年)
気象庁『台風に伴う風の特性』
気象庁『台風に伴う雨の特性』
気象庁『大雨の影響』
気象庁『台風に伴う高潮』
気象庁『高潮と台風の進路』
気象庁『台風に伴う高波』
気象庁『海岸の高潮と高波の重なり合い』
気象庁『台風への備え』
気象庁『令和6年台風第10号による大雨、暴風及び突風 令和6年(2024年)8月27日~9月1日 (速報)』
国土地理院『ハザードマップポータルサイト 身のまわりの災害リスクを調べる』
国立情報学研究所『デジタル台風:地球温暖化と熱帯低気圧(台風・ハリケーン) 1. 地球温暖化と熱帯低気圧』
国立情報学研究所『デジタル台風:2024年台風10号(サンサン|SHANSHAN)』
環境省『気候変動による災害激甚化に関する影響評価結果について~地球温暖化が進行した将来の台風の姿~』(2023年7月)
環境省『できることから始める「気候変動 × 防災」実践マニュアル- 地域における気候変動リスクを踏まえた防災・減災対策のために -』
経済産業省『台風15号に伴う停電復旧プロセス等に係る検証について』(2019年10月)
政府広報オンライン『大雨や台風の気象情報に注意して 早めに防災対策・避難行動をとりましょう』(2025年2月)
名古屋大学『海の生物は台風によって影響されるの?』
琉球大学『気象災害について 台風による被害』
日本経済新聞『温暖化が進めば台風の勢力増す 環境省試算』(2023年10月)
日本経済新聞『[社説]常識超えた台風10号を教訓に』(2024年9月)
BBC『台風10号が九州を北上、避難や警戒の呼び掛け続く』(2024年8月)
*4)代表的な台風の被害例
WIKIMEDIA COMMONS『Aerial view of Tacloban after Typhoon Haiyan』
気象庁『台風による災害の例』
気象庁『伊勢湾台風から学んだ東京湾の高潮防災』(2019年9月)
気象庁『令和元年東日本台風(台風第19号)による大雨、暴風等』(2019年10月)
国立情報学研究所『デジタル台風:過去の台風災害・被害』
国立情報学研究所『デジタル台風:ベンガル湾のサイクロン:Cyclone NARGIS(ナルギス) (2008) – ミャンマーで大規模災害』
JAXA『ミャンマーに大きな被害をもたらしたサイクロン「Nargis」(2008年5月2日)』
JAXA『地球が見える 2008年 JAXAにおける洪水災害観測 −ミャンマーを襲ったサイクロン「ナルギス」−』(2008年5月)
総務省『1 災害廃棄物の発生状況と課題等』
国土交通省『台風 30 号(フィリピン)の被害概要について』
在フィリピン日本大使館『台風30号被害に対する緊急無償資金協力の実施』(2013年11月)
Wikipedia『台風』
荒木裕子『伊勢湾台風の広域避難とその解消プロセス』
古文・漢文の世界『枕草子「野分のまたの日こそ」現代語訳・解説|清少納言の独自の視点に注目しよう』(2025年2月)
青空文庫『源氏物語 野分 紫式部 與謝野晶子訳』
NATIONAL GEOGRAPHIC『元寇の神風、本当に吹いた?』(2014年11月)
日本気象学会『文永の役に嵐は吹いたのか』(2009年11月)
法務省『バングラデシュ』(2012年9月)
国連大学『気候変動による移住者の話:ダッカのスラムより』(2017年2月)
内閣府『過去の災害に学ぶ 20 1959年9月26日 伊勢湾台風 その1』
内閣府『第1章 伊勢湾台風災害の概説』
内閣府『令和2年版 防災白書|特集 第1章 第1節 1-3 令和元年東日本台風による災害』
山口 正隆『昭和の3大台風時の瀬戸内海,伊勢湾,東京湾における波高分布の再現』(2011年)
東北大学『フィリピンの台風災害調査でわかったこと』
*5)台風とSDGs
国土交通省『コラム・事例 地球温暖化と大雨、台風の関係』
国土交通省『国土交通白書 2022 1 気候変動に伴う災害の激甚化・頻発化』(2022年)
環境省『令和6年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 第1章 第六次環境基本計画が目指すもの』(2024年6月)
環境省『令和4年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 第1章 1.5℃に向けて』(2022年6月)
*6)まとめ
気象庁『備えていますか?東日本台風の再来』
気象庁『台風情報の現状と課題』
日本気象協会『2025年の夏も全国的に猛暑 観測史上1位タイの高温となった2024年との違いは?』(2025年2月)
日経XTECH『AI気象モデルが急速に高精度化、世界の天気予報がPC1台かつ1分で』(2024年9月)
この記事を書いた人
松本 淳和 ライター
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。