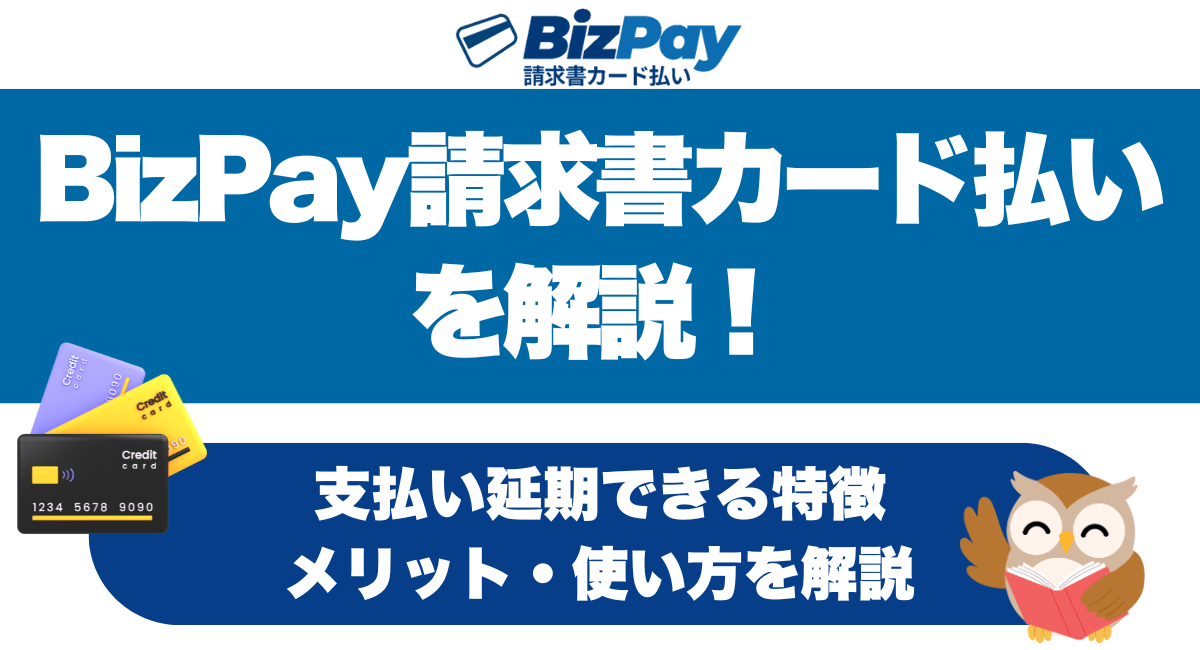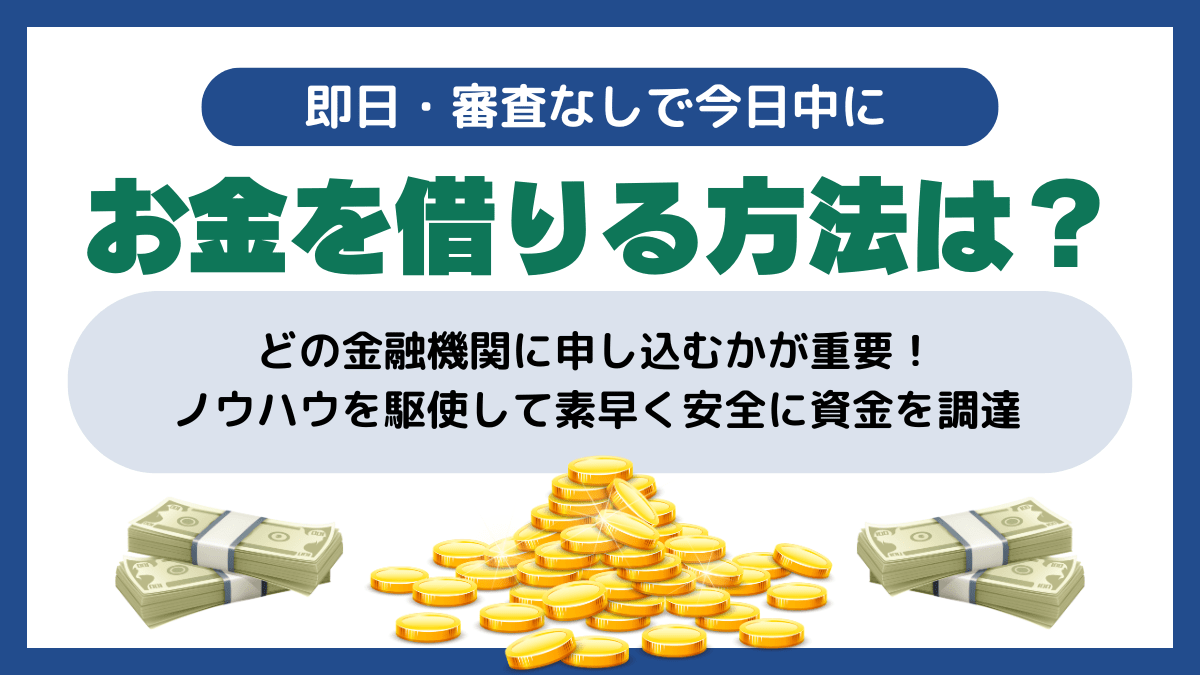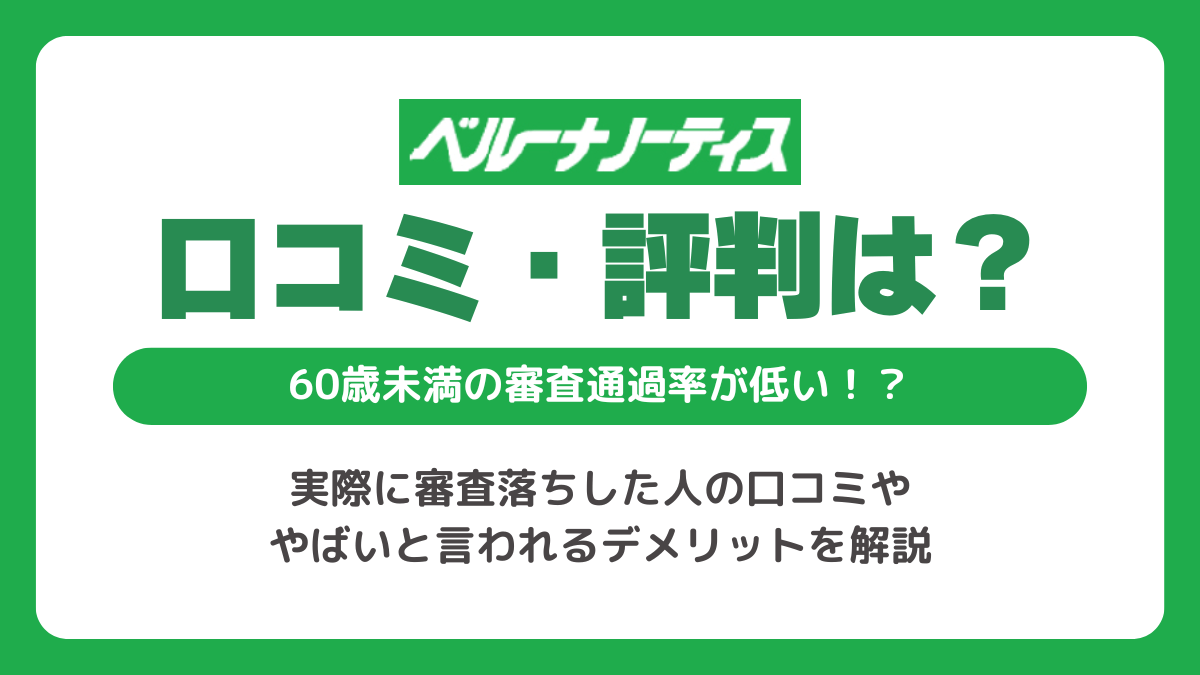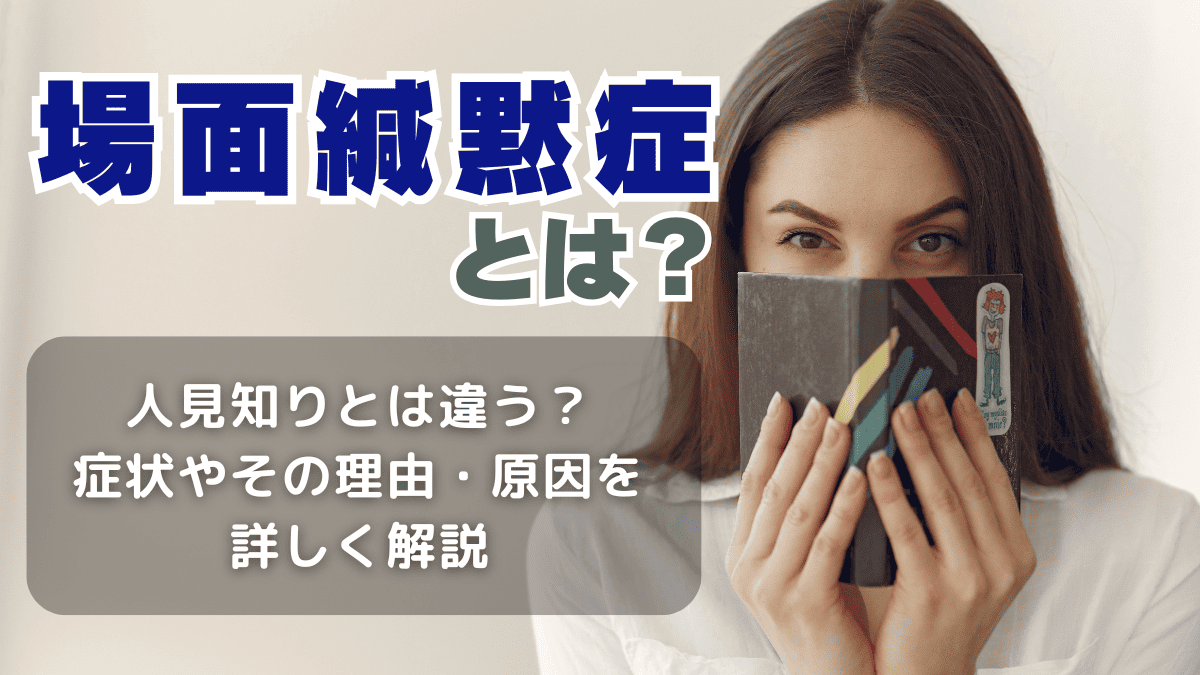「法の支配」の源流であるローマ法は、現代のグローバル社会にも大きな影響を与え続けています。実用性と柔軟性を兼ね備えたローマ法は、時代を超えて普遍的な価値を持ち、日本の民法にも深く根付いています。
古代ローマの概要やそこから生まれた法の歴史、それが日本に与えた影響などをわかりやすく解説します。
目次
ローマ法とは
【元老院でカティリナを攻撃するキケロ チェーザレ・マッカリ画(1888年)】
ローマ法とは、古代ローマ社会において適用された法規範の全体を指します。それは、共和政期から帝政期を経て、東ローマ帝国(ビザンツ帝国)にまで継承され、約千年以上にわたって発展し続けた、非常に広範かつ複雑な法体系です。
古代ローマで生まれ、発展した法体系であるローマ法は、単に過去の遺産というだけでなく、現代の多くの国の法制度に深く根を下ろす、非常に重要な存在です。
ローマ法の構成要素
ローマ法は、単一の法典として成立したわけではなく、時代の変遷とともに多様な要素が積み重なって形成されました。まずは主な構成要素を理解し、ローマ法の全体像を把握しておきましょう。
慣習法(ius non scriptum)
ローマ社会の初期において、人々の間で長年にわたり受け継がれてきた慣習は、重要な法源としての役割を果たしました。成文化された法律が存在しない時代においては、社会秩序を維持するための基本的な規範となっていたのです。
例えば、古代ローマ初期においては、「祖先の慣習(mos maiorum)」と呼ばれるものがあり、
- 家長(パテルファミリアス)が絶対的な権威を持ち、家族構成員に対する広範な支配権を持つ
- 債務を返済しない者は一定期間拘束され、返済がなければ奴隷として売却される
- 被告が法廷への出廷を拒否した場合、原告は証人を立ててその者を強制的に連行できた
などが慣習とされていました。
十二表法(Lex Duodecim Tabularum)
共和政初期の紀元前5世紀に制定された十二表法は、ローマ最初の成文法であり、貴族と平民の間の法的平等を求める平民の要求に応える形で成立しました。内容は、
- 訴訟手続
- 家族法
- 財産法
- 刑法
など多岐にわたり、後のローマ法発展の基礎となりました。十二表法は、それまで貴族が独占していた法の知識を公開し、法の下の平等の原則を示す画期的な出来事でした。
法務官告示(edictum praetoris)
法務官とは、訴訟の審理を担当する官職であり、任期が1年であるため、就任ごとに告示(edictum)を発して、その年の裁判の原則や手続を示します。特に、外国人との間の訴訟を担当する外国人法務官の告示は、ローマ市民法(ius civile)とは異なる、普遍的な法の原理を含む万民法(ius gentium)の発展に大きく貢献しました。
民会法・元老院決議(lex et senatus consultum)
共和政期には、市民の集会である民会で可決された民会法(lex)も重要な法の源でした。帝政期に入ると、民会の権限は縮小し、皇帝の諮問機関である元老院の決議(senatus consultum)が事実上の法律としての効力を持つようになりました。
皇帝法(constitutio principis)
帝政期になると、皇帝の勅令、告示、回答などが皇帝法(constitutio principis)として重要な法源となりました。特に、後期のローマ帝国においては、皇帝法がローマ法の主要な部分を占めるようになります。
法学者法(responsa prudentium)
ローマでは、著名な法学者が示した学説や法律の解釈も、重要な根拠として扱われていました。特に、アウグストゥス帝の時代に公認された法学者の意見は、裁判官を拘束する力を持つようになり、ローマ法の発展に大きな影響を与えました。
ローマ法大全(Corpus Iuris Civilis)
東ローマ帝国のユスティニアヌス帝の命により編纂されたローマ法大全は、ローマ法の集大成であり、後のヨーロッパ法学に決定的な影響を与えました。ローマ法大全は、
- 法典(Codex Iustinianus): 皇帝の勅令を集成したもの
- 学説彙纂(Digesta seu Pandectae): 著名な法学者の学説を集めたもの
- 法律提要(Institutiones): 法学初学者のための教科書
- 新法(Novellae Constitutiones): 法典編纂後にユスティニアヌス帝が制定した新法
の4部から構成され、長年にわたるローマ法の発展の成果を体系的にまとめたものです。
これらの多様な構成要素が、相互に影響を与え合いながら、千年以上にわたるローマ法の歴史を形作ってきたのです。次の章では、これらの要素を踏まえつつ、ローマ法が持つ独自の特徴について見ていきましょう。*1)
ローマ法の特徴

ローマ法が2000年以上の時を経て、今なお法学の基礎として参照され続けているのは、その独自の特徴と普遍性によるものです。ローマ法の特徴を理解するため、いくつかの重要な観点から見ていきましょう。
実用主義と柔軟性
ローマ法の最大の特徴は、その実用主義的なアプローチにあります。ローマ人は法を理論的体系ではなく、具体的な紛争解決のための道具として発展させました。
法務官(プラエトル)という役職者は、既存の法が不十分な場合、新たな救済方法を創造する権限を持ち、社会の変化に法を適応させていきました。この「法務官法」の発展により、ローマ法は硬直することなく柔軟に進化を続けることができたのです。
専門法学の発達
ローマ法では、法の専門家である法学者(ユリスコンスルティ)の存在が特徴的でした。彼らは法律相談に応じ、法的見解を示す「回答」(レスポンサ)を通じて法の発展に貢献しました。
特に古典期(紀元1世紀〜紀元3世紀)には、
- パピニアヌス:セプティミウス・セウェルス帝に重用され、倫理性と公平性を重視したローマ法古典期の代表的法学者
- ウルピアヌス:パピニアヌスの弟子で、公法と私法の区別や主権概念を整理し、「ローマ法大全」に多く引用された法学者
- パウルス:古典期ローマ法学の中心人物で、緻密な法理論と実務的分析に優れ、多数の著作が「ローマ法大全」に収録された法学者
などの著名な法学者が現れ、法解釈の精緻化と体系化に尽力しました。彼らの著作は後に「学説彙纂」※に収録され、ローマ法の精髄として後世に伝えられています。
公法と私法の区分
ローマ法は、
- 公法(ユス・プブリクム)
- 私法(ユス・プリワトゥム)
を明確に区別した最初の法体系でした。ウルピアヌスの有名な定義によれば、「公法とは国家の構成に関する法であり、私法とは個人の利益に関する法である」とされています。
この区分は現代の法体系にも受け継がれ、国家と個人の関係を整理する上での基本的な枠組みとなっています。
これらの特徴が複雑に絡み合い、ローマ法は、単なる古代の法体系を超え、普遍的な法的思考の原型として、後世の法制度に多大な影響を与えることになったのです。続く章では、このような特徴を持つローマ法が、どのように歴史の中で発展してきたのかを辿りましょう。*2)
ローマ法の歴史

ローマ法は紀元前5世紀の十二表法に始まり、6世紀の「ローマ法大全」で頂点を迎えるまで、1000年以上かけて発展を続けました。多民族統治と社会変革の要請に応えながら進化したその歴史は、現代法の基盤形成プロセスそのものといえます。
ここでは、ローマ法が古代から現代へと継承されるまでの3つの転換点を掘り下げます。
十二表法と法の公開革命
紀元前449年、平民の要求により成立した十二表法は、慣習法の成文化によって「法の支配」の基盤を築きました。従来、貴族神官が独占していた法解釈を文字で固定化し、
- 第1表:訴訟手続
- 第2表:訴訟手続
- 第3表:債務奴隷制の規制
- 第4表:親族法(家父長権など)
- 第5表:相続法・遺言
- 第6表:土地所有と占有
- 第7表:隣人関係
- 第8表:不法行為(窃盗、傷害など)、同害報復の原則
- 第9表:公法(反逆罪、死刑など)
- 第10表:埋葬・葬儀の規制
- 第11表:解釈・補足(第1表~第10表の解釈や修正)
- 第12表:解釈・補足(第1表~第10表の解釈や修正)
を明文化しました。特に「法の前の平等」原則は、前445年のカヌレイウス法で貴族と平民の通婚を認めるなど、身分制度の緩和を促しました。
法学者ガイウス※が指摘したように、この成文化は「市民の権利を可視化する革命」でした。ただし、この頃のローマの土地の相続は、昔ながらの保守的な方法(銅と秤を使った儀式など)が残り、柔軟に変えていく必要がありました。
帝政期の法整備と普遍性の獲得
カラカラ帝のアントニヌス勅令(212年)で帝国内全自由民に市民権が与えられると、ローマ法は「万民法」として普遍性を強化します。異民族間取引で発展した諾成契約や共同海損制度が帝国標準となり、法学者ウルピアヌスは「自然理性」※に基づく衡平の概念を確立しました。
特に注目すべきは法学者解答権制度です。ハドリアヌス帝(2世紀)が五大法学者に与えた公式解釈権※は、パピニアヌスやパウルスの学説を権威ある法源とし、判例法体系の原型となりました。
しかし3世紀の軍人皇帝時代には立法が乱発され、法体系の混乱がユスティニアヌス法典編纂の遠因となっています。
ローマ法大全と中世ヨーロッパへの継承
6世紀、東ローマ皇帝ユスティニアヌス1世がトリボニアヌスらに命じて編纂した「ローマ法大全」は、矛盾する学説を整理し「永遠不変の法」として体系化しました。この中の「学説彙纂」に収録されたパピニアヌスの「法は善と衡平の術」という定義は、現代の法哲学にも通じる普遍性を獲得しています。
中世ボローニャ大学でイルネリウスが再発見したこの法典は、注釈学派※によって教会法と融合しました。15世紀のドイツ継承※では「ローマ法は書かれた理性」とされ、ナポレオン法典(1804年)やドイツ民法典(1900年)の直接的なモデルとなりました。日本を含む大陸法諸国の法体系は、この流れを汲んでいます。
ローマ法の歴史は、社会の多様性に対応する法制度の進化そのものです。次は、この普遍的な法思想が日本にどのように根付いたかを探っていきましょう。*3)
ローマ法が日本に与えた影響
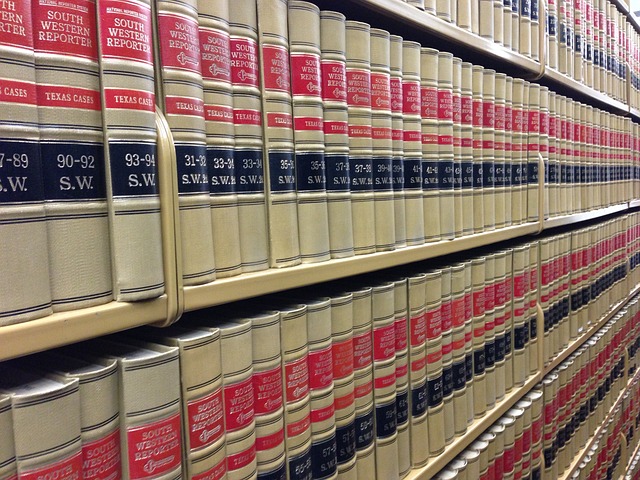
ヨーロッパの法体系を経由してローマ法が日本の近代法に色濃く影響を与えた事実は、
- 現代の民法
- 法学用語
- 土地制度
- 権利観念
にまで及んでいます。明治維新以降、日本がどのようにローマ法を受容し、独自の法文化と融合させてきたのか、重要な3つのポイントを確認しましょう。
①明治民法とローマ法の間接的継受
明治時代、日本は近代化のために西欧の法体系を積極的に導入しました。特にドイツ民法やフランス民法が参照されましたが、これらはともにローマ法を母体としています。
フランスからは法学者ボアソナードが招かれ、旧民法の起草に携わり、その後ドイツ民法典(BGB)を基礎とした現行民法が制定されました。このため、日本の民法は、
ローマ法→ドイツ法・フランス法→日本法
という間接的なルートでローマ法の影響を受けたといえます。
たとえば「契約自由の原則」や「所有権絶対の原則」など、ローマ法由来の基本理念が日本民法の根幹に据えられています。
②所有権・契約・手続き概念への影響
ローマ法の「所有権」という概念は、私的所有権の排他性や独占性を強調し、明治期の日本の土地制度や民法に大きな影響を与えました。
- 「一地一主」の原則
- 土地の排他的支配
という考え方は、ローマ法的所有権観念をフランス法やドイツ法を通じて受容したものです。
また、契約法や民事訴訟手続きにもローマ法の用語や原則が多く残っています。例えば、
- 「契約締結上の過失(culpa in contrahendo)」
- 「合意は守られるべし(pacta sunt servanda)」
といった表現は、現代日本の法学教育や実務でも用いられています。
③日本社会における権利意識とローマ法
ローマ法は個人の権利意識を強調する法体系ですが、日本社会では「権利主張よりも和解を重視する」文化が根強く残っています。これは、古代中国の律令制度の影響や、法律を「統治の道具」とみなす伝統が背景にあるためです。
そのため、日本の法律は法制度としてはローマ法的な要素を受け入れつつも、社会の運用や意識の面では独自の発展を遂げてきたと言えます。
ローマ法は、現在の日本の民法や土地制度、契約・訴訟手続きの原則に広く影響を及ぼしつつ、日本独自の社会文化と融合し、独特の法意識や運用を形成しています。次の章では、ローマ法とSDGsとの関係を考察していきましょう。*4)
ローマ法とSDGs

ローマ法が築いた
- 「法の普遍性」
- 「公平性」
- 「社会的包摂」
の理念は、SDGsが掲げる「誰一人取り残さない」持続可能な社会の実現と深く重なります。ローマ法は多民族社会の中で合理的かつ公平なルールを発展させ、社会の安定や市民の権利保護を追求してきました。SDGsもまた、経済・社会・環境のバランスを重視し、包摂的な成長と公正な制度の確立を目指しています。
SDGsが目指す社会の実現に、ローマ法の知見がどのように貢献できるのか、具体的な目標ごとに見ていきましょう。
SDGs目標10:人や国の不平等をなくそう
ローマ法は、異なる民族や階層に対しても一定の法的平等を保障する仕組みを発展させました。現代では、移民やマイノリティの権利保障や、差別解消のための法制度設計にローマ法の「万民法」や「衡平」の理念が生かされています。
各国が法の下の平等を徹底し、社会的・経済的な格差を是正するための法整備を推進する際、ローマ法の合理的かつ普遍的な原則が参考となります。
SDGs目標16:平和と公正をすべての人に
ローマ法は「法の支配」や「公正な裁判手続き」の基礎を築きました。現代の司法制度や人権保障、紛争解決の枠組みは、ローマ法の法理を継承しています。
特に、誰もが公正な手続きにアクセスできる社会の実現は、SDGs目標16の中核です。
- 透明性
- 説明責任
- 法の下の平等
といった原則を社会全体に根付かせるために、ローマ法の理念が今なお重要な役割を果たしています。
SDGs目標17:パートナーシップで目標を達成しよう
ローマ法における「万民法」の発展は、異なる文化や慣習を持つ地域間の調和をはかるための知恵でした。この異文化間の法的調和という考え方は、グローバルな課題に対する国際協力の枠組み構築にも示唆を与えます。
ローマ帝国が広大な領域を統治する上で培った「多様性の中の一体性」という発想は、現代の国際協力においても重要な視点です。法の調和を通じた持続可能な国際社会の構築において、ローマ法の歴史的経験から学ぶべき点は少なくないでしょう。
ローマ法の精神は、SDGsの目標達成に向けて、法の基盤づくりや社会正義の実現、包摂的な制度設計を支える力となっています。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ

ローマ法は、古代ローマで生まれ発展した法体系でありながら、2000年以上の時を超えて現代社会の法制度に多大な影響を与え続けています。
- 市民法
- 万民法
- 法務官法
などの柔軟かつ実用的な法体系は、普遍的な正義の概念を追求する中で生まれ、現代法の基礎となりました。
近年では、イタリアのローマ大学を中心に「デジタル・ローマ法学」という新たな研究分野が発展し、古代の法典をAIで分析することで現代の法的課題への応用を探る試みが進んでいます。このような研究は、古代の知恵と現代技術の融合により、複雑化するグローバル社会の法的課題解決に新たな視点をもたらす可能性を秘めています。
ローマ法の普遍性と柔軟性は、異なる文化や社会背景を持つ地域にも共通する法的基盤を提供してきました。日本を含む多くの国々がローマ法の原則を直接・間接に継承したことは、法が単なる地域的慣習ではなく、人類共通の知恵であることを示しています。
法の歴史を学ぶことは、単に過去を知るだけでなく、現代の法制度をより深く理解し、未来の法のあり方を考える上で不可欠です。あなた自身の日常生活の中で、契約を結んだり所有権を主張したりする場面で、どのようにローマ法の知恵が息づいているか考えてみてはいかがでしょうか?
法の仕組みや歴史を知ることは、より公正で持続可能な社会を共に創造するための第一歩となるはずです。
<参考・引用文献>
*1)ローマ法とは
WIKIMEDIA COMMONS『Cicero Denounces Catiline in the Roman Senate by Cesare Maccari – 3』
Wikipedia『ローマ法』
世界史の窓『ローマ法』
世界史の窓『ローマ法大全』
世界史の窓『十二表法』
世界史の窓『万民法』
SWI swissinfo『ヨーロッパの法制度に影響を与え続けるローマ法』
Giovanni Finazzi『Istituzioni di diritto romano』(2022年9月)
*2)ローマ法の特徴
京都大学『ROMAHOPEDIA(ローマ法便覧) 第五部 古代ローマの法技術』
日本大学『ローマ法と法学教育』
日本大学『ローマ法における不法行為責任の概念』
塚原 義央『古代ローマにおける自然法思想の研究―ius naturaleとius gentiumとの関係について―』(2017年5月)
Manuale di diritto privato romano『PREMESSA METODOLOGICA E CRONOLOGICA』
Archeologia Viva『L’eredità del diritto romano Archeologia e diritto』(1998年10月)
三成 美保『【法制史】ローマ法継受とその影響』(2015年2月)
板持 研吾『ローマ法雑誌創刊号』(2020年)
松尾 弘『所有権譲渡の「意思主義」と「第三者」の善意・悪意(一)』(1993年7月)
小野 秀誠『契約の自由と当事者の地位─契約と基本権─』(2008年3月)
*3)ローマ法の歴史
笹倉 秀夫『ヨーロッパにおける法の継受の観点からー滝沢報告へのコメント』(2014年10月)
三成 美保『【法制史】ローマ法の成立と発展』
三成 美保『ユースティーニアーヌス法典』(2014年3月)
世界史の窓『ローマ共和政』
世界史の窓『ローマ帝国』
Università di Ferrara『ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO I PERIODI E LE FONTI』
ANTONIO GUARINO『STORIA DEL DIRITTO ROMANO』(1998年)
李 鈞『清末民国期におけるローマ法研究』(2015年7月)
早稲田大学『人間生活の法化』(2014年5月)
*4)ローマ法が日本に与えた影響
夢ナビ『日本の法律、そのルーツは古代文明ローマにあった』
夢ナビ『現代の民事裁判は2000年前のローマ法に原型ができていた?』
藤原 稲治郎『ローマ法を継受したわが国の弁理士像』(2007年)
滝沢 正『比較法学からみた日本法のアイデンティティ」(2014年10月)
福島 正夫『法の継受と社会=経済の近代化(一)』(2014年5月)
高橋 宏司『コモン・ロー国への日本法紹介:その方法論』
衆議院『「立憲主義、憲法改正の限界、違憲立法審査の在り方」に関する資料』(2018年11月)
この記事を書いた人
松本 淳和 ライター
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。