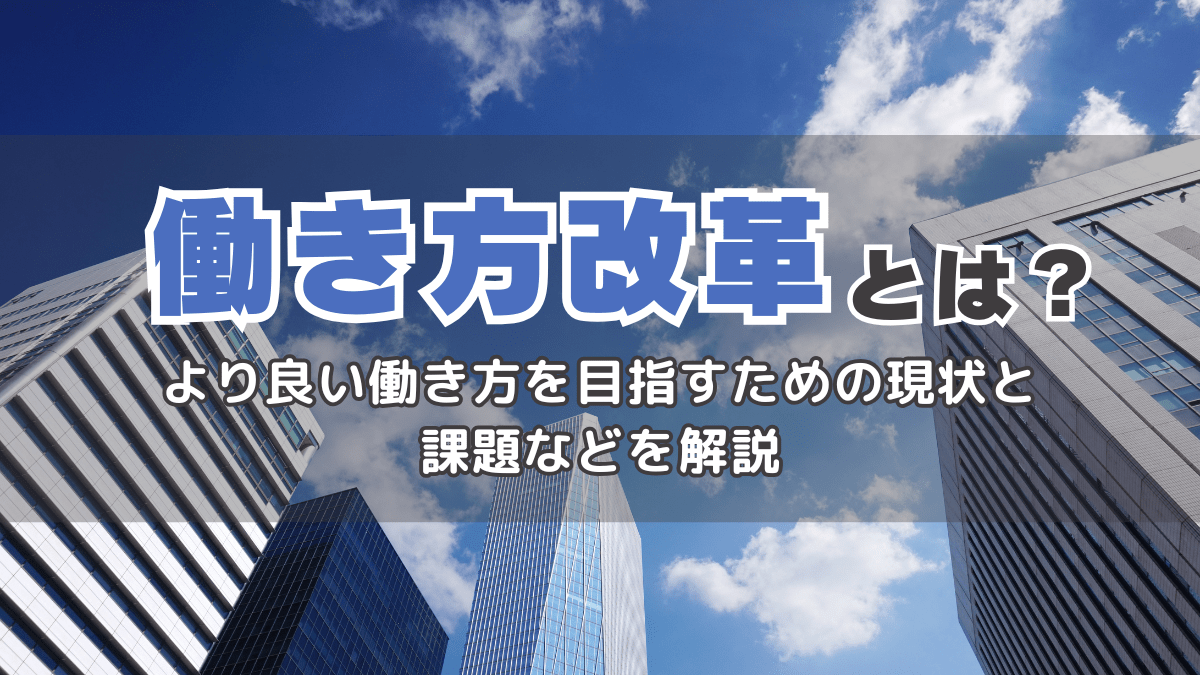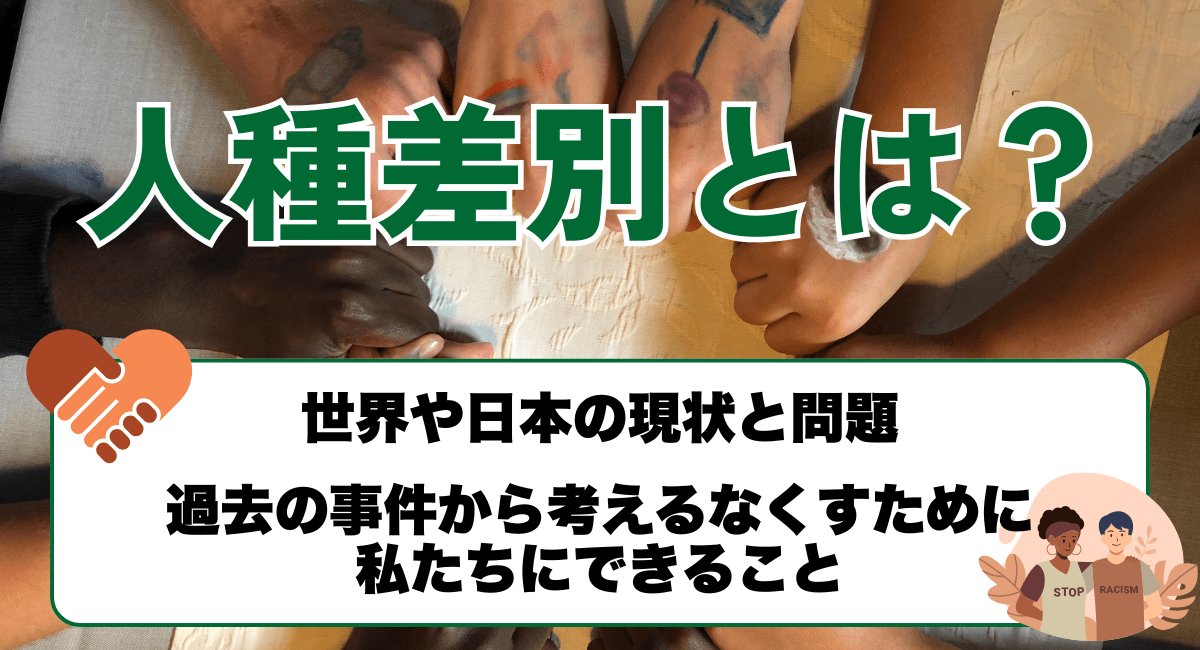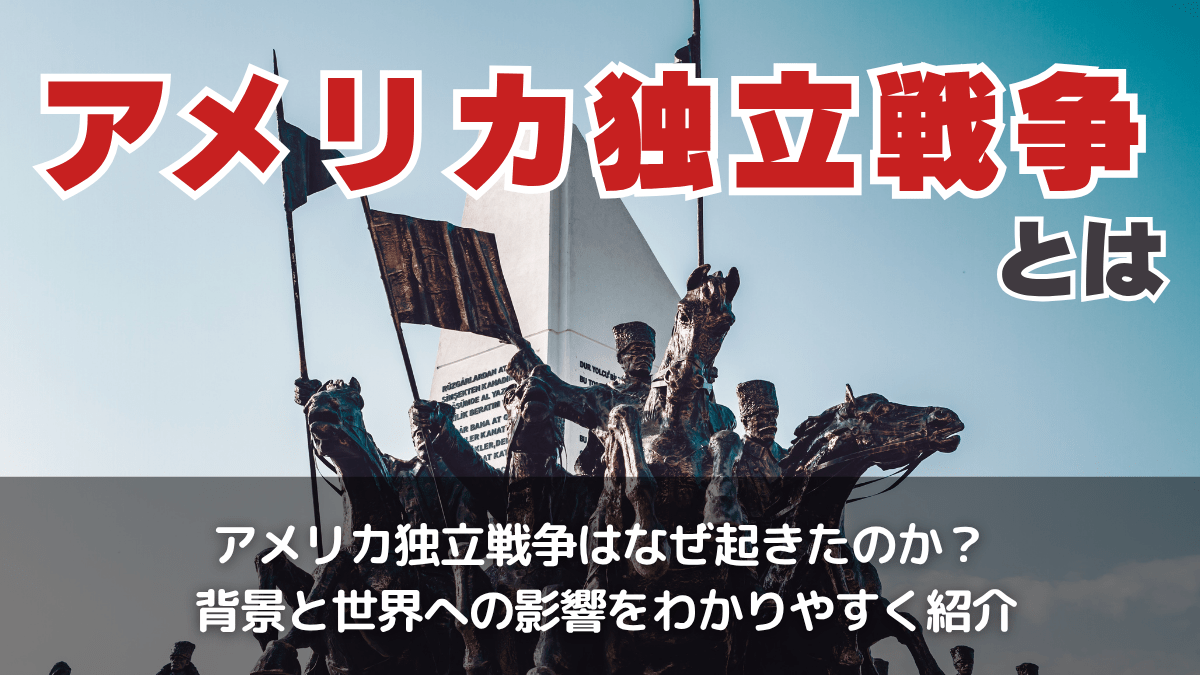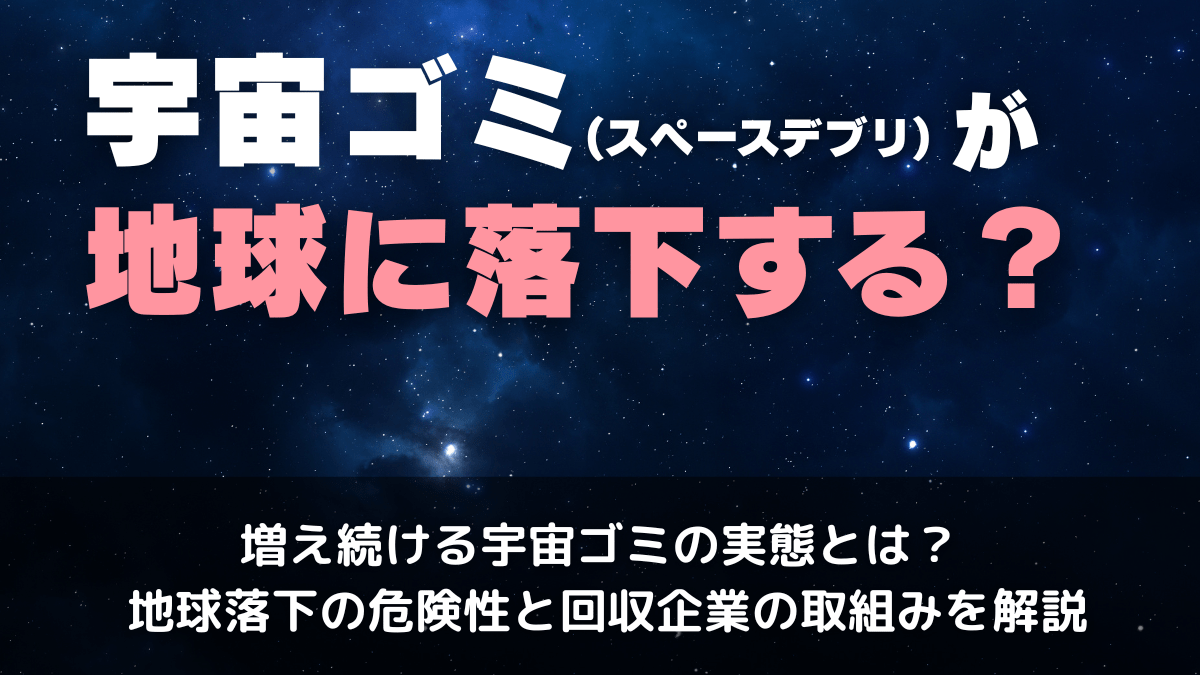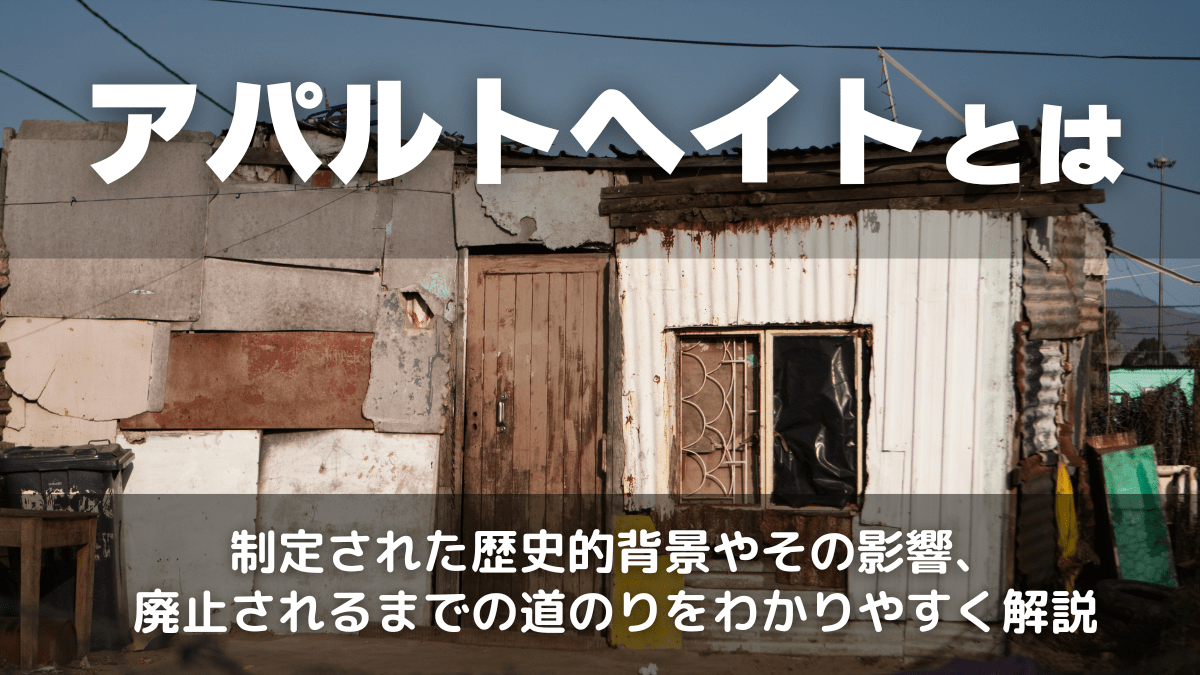
もし、あなたが生まれた瞬間に、住む場所や仕事、恋愛対象まで決められているとしたら、そうした人生に耐えられるでしょうか。
今から30年以上前の南アフリカでは、白人と非白人はあらゆる面で分離されていたのです。この制度をアパルトヘイトといいます。
アパルトヘイトが行われていた南アフリカでは、白人と非白人を完全に分離し、教育、居住、結婚、就職など、あらゆる面で差別が見られました。なぜ、このような差別的な制度が生まれたのでしょうか。
そこには、南アフリカが抱える独特の事情があります。
この記事では、アパルトヘイトが制定された歴史的背景から、その影響、そして廃止されるまでの道のりをわかりやすく紐解きます。ぜひ参考にしてください。
目次
アパルトヘイトとは?簡単に解説
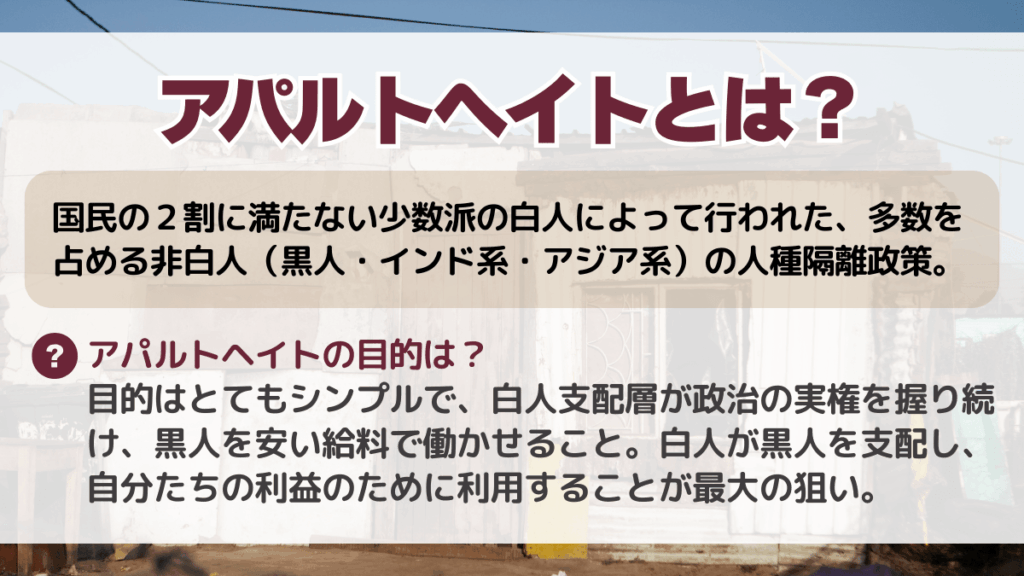
アパルトヘイトとは、国民の2割に満たない少数派の白人によって行われた、多数を占める非白人(黒人・インド系・アジア系)の人種隔離政策のことです*1)。人種隔離政策自体は、1910年の南アフリカ連邦発足から始まっていましたが、本格的に整備されたのは1948年以降です。
その後、1991年に廃止するまで43年間にわたって、アパルトヘイトが継続しました。
アパルトヘイトの語源
アパルトヘイトという言葉は、オランダ系白人(ブール人)が話すアフリカーンス語で「分離」や「隔離」を表す言葉*2)です。この政策は、南アフリカに住むオランダ系やイギリス系の白人たちが、黒人など非白人の人々を社会から切り離して支配するために行われました。
1910年に南アフリカ連邦が成立しましたが、これはイギリスによる支配を経て実現したものでした。しかし、連邦が成立した後も、白人による非白人への差別的な隔離政策は変わることなく続けられました。
アパルトヘイトの目的
アパルトヘイトの目的は、とてもシンプルです。白人支配層が政治の実権を握り続け、黒人を安い給料で働かせることでした。白人たちは黒人を自分たちと対等に扱うつもりはなく、ただ働き手として都合よく使うことを考えていました*。
要するに、白人が黒人を支配し、自分たちの利益のために利用することが、アパルトヘイトの最大の狙いだったのです。
アパルトヘイトはどこの国で起きた?
アパルトヘイトは南アフリカ共和国で実施されました。南アフリカ共和国はアフリカ最南端に位置しており、面積は日本の約3倍である約122万平方キロメートルです。
首都はプレトリアであり、1488年にポルトガル人航海者バルトロメオ・ディアスが希望峰に到達したことで有名です。
南アフリカの白人政府が非白人に対して人種差別・隔離政策を行いました。住む場所や公共施設を白人のように利用できず、不遇を受けていたのが現状です。
アパルトヘイトは、国際社会から非難され1990年代に廃止されています。1994年にはネルマン・マンデラが大統領に選ばれ、多民族社会を実現しました。
アパルトヘイトが制定された背景
南アフリカでは、20世紀後半まで人種隔離政策アパルトヘイトが続きました。その誕生には、南アフリカという国の複雑な歴史が深く関わっています。
ここでは、南アフリカ連邦の成立からアパルトヘイトの成立、そして南アフリカ共和国によるその強化に至るまでの歴史を紐解き、制度が生まれた背景に迫ります。
南アフリカ連邦の成立
アフリカ最南端に位置する南アフリカ連邦は、1910年、イギリス連邦内の自治領として成立しました。
これは、それ以前の南アフリカ戦争でイギリスと激しく争った、トランスバール共和国とオレンジ自由国という二つのブール人共和国が、イギリスの植民地であったケープ植民地、ナタール共和国と合併した結果です*5)。
南アフリカ連邦は人口構成では、オランダ系の子孫であるブーア人(アフリカーナー)とイギリス人などの白人が少数派でしたが、彼らは人口の80%以上を占める非白人に対して、極端な差別・隔離政策を実施しました*5)。
アパルトヘイトの成立
白人による非白人の差別・隔離政策は、南アフリカ連邦が成立した1910年から行われていました。当時、南アフリカでは、さまざまな法制度によって人種隔離が行われていました。アパルトヘイトを支えた主な法律は、以下の通りです。
【アパルトヘイトを支えた法制度】
| 人口登録法 | すべての南アフリカ人を、白人・黒人・カラード(混血)のように人種で登録することを定めた法律*4) |
| 土地法 | 国土の87%の土地を白人が所有すると定めた法律*4) |
| 雑婚禁止法 | 南アフリカに住む白人と黒人の婚姻を禁じた法律 |
| 隔離施設留保法 | 人種別の施設の分離を合法化した法律 |
これらの法律により、白人と非白人は完全に分離されていたのです。
南アフリカ共和国によるアパルトヘイトの継続
南アフリカは当時、イギリス連邦という、イギリスとその旧植民地などからなる国家連合に属していました。しかし、アパルトヘイト政策を続ける南アフリカに対し、連邦の盟主であるイギリスは強く反対し、両国の関係は悪化していきました。
そしてついに1961年、南アフリカはイギリス連邦から脱退し、新たに「南アフリカ共和国」として独立する道を選びました。これは、国際的な孤立を深める結果となりましたが、南アフリカ政府はアパルトヘイト政策を維持し続けました*7)。
アパルトヘイトで行われたことの具体例
アパルトヘイトは、生活の隅々まで及んでいました。たとえば、南アフリカの人口の大半を占める黒人は、国土のわずか13パーセントの不毛な土地に強制的に居住させられていました。
黒人は狭い地域に押し込められ、経済的に白人に依存せざるを得なくなります。
日常生活では、人種による分離が徹底されており、結婚や恋愛関係において人種間の交際は違法とされました。
加えて、人種別の学校制度が設けられ、黒人は質の低い教育しか受けられませんでした。公共の場では、バスや公園、病院などあらゆる施設で人種による区分けがなされ、「白人専用」のエリアには非白人は立ち入ることができませんでした。
職場でも差別は顕著で、黒人は低賃金で危険な仕事に従事させられ、昇進の機会も制限されていました。このような差別的な制度は、法律や慣習によって体系的に維持され、非白人の権利は著しく制限されていたのです*8)。
アパルトヘイト廃止はなぜ?いつ?背景にあった問題
アパルトヘイトは白人優位のために作られた仕組みで、法律によって守られていました。しかし、国連による働きかけや南アフリカの国際的孤立、反アパルトヘイトの動きなどにより南アフリカ政府は徐々に追い詰められます。
1991年にはアパルトヘイトの関連法が全て撤去され、廃止されています。
ここではアパルトヘイトが廃止された背景について解説するため、ご覧ください。
アパルトヘイトの問題点
アパルトヘイトの主な問題点は、以下の通りです。
- 黒人の選挙権を奪い、白人支配を強化した
- 黒人と白人の格差が広がった
1つ目の問題点は、黒人に選挙権がなかったことです*9)。そのため、社会の中で大きな割合を占めていた黒人たちは、自分たちの意見を政治に反映させることができませんでした。
その結果、白人たちが決定した政策に従わざるを得ない状況に置かれていたのです。
2つ目の問題点は、黒人と白人の格差が大きく広がったことです。黒人は、白人よりも劣悪な環境で生活し、労働面でも苦しい立場に置かれていました。先述したように、教育においても、白人と同等のものは与えられませんでした。そのため、経済・社会面でも白人との差は歴然としていたのです。
国連による働きかけ
アパルトヘイトを厳しく批判したのが国連です。国連は、1950年代から南アフリカ政府に対し、アパルトヘイトが国連憲章や世界人権宣言と相容れないものであると非難しました。
たとえば、国連総会は1962年に「国連反アパルトヘイト特別委員会」を設置したり、1971年に南アフリカとのスポーツ交流イベントボイコットを呼びかけたりといった活動を行いました。こうした活動は、アパルトヘイトが廃絶されるまで続きました*10)。
反アパルトヘイトの動き
1960年代以降、反アパルトヘイト運動が活発化します。主な事件は以下の通りです。
【反アパルトヘイトの動き】
| 年代 | 事件名 | 内容 |
|---|---|---|
| 1960年 | シャープビル事件 | 人種差別に抗議したアフリカ人の集会で白人警官が発砲した |
| 1976年 | ソウェト蜂起 | ソウェトで起きた反アパルトヘイト闘争 |
| 1977年 | スティーブ・ビコ惨殺事件 | 運動の指導者である大学生のスティーヴ=ビコが拷問を受けて惨殺された |
シャープビル事件は、ヨハネスブルグ近郊のシャープビルで、白人警官が集会に参加した人々に無差別発砲を行った事件です。
アパルトヘイト政策の一環として、黒人が白人居住区に入る際に身分証明書の携行を義務付けた「パス法」に対し、多数の人が抗議行動を行いました。これに対し、白人警官らが発砲したため、69名が命を落とし、186名が負傷する惨事となりました*11)。
ソウェト蜂起は、ヨハネスブルグのアフリカ人居住区であったソウェトで起きた学生の抗議デモに対し、武装警察が発砲した事件です。死者500人以上、負傷者2,000人以上を出した事件でした。
事件の余波は他の黒人居住区にも広がり、翌年まで騒乱が継続しました*12)。
スティーブ=ビコは、黒人の学生運動の指導者です。彼は、「黒人意識運動」を率い、黒人の伝統や文化の価値を見直し、誇りと自信を取り戻し、政治への関心を高めることで、黒人の解放を目指しました。
しかし、その活動はアパルトヘイトを維持したい政権の脅威となり、1977年、警察に拘束されたビコは、激しい拷問の末、命を落としました。彼の死後、南アフリカ政府に対する国際的な非難が強まり、南アフリカと国交を断絶する国も現れます。
ネルソン・マンデラの登場
ネルソン・マンデラは、アパルトヘイトに対して闘った象徴的な人物です。1952年には有色人種として初めて弁護士となり、アフリカ民族会議で中心的な役割を果たしながら、白人政権による人種隔離政策に対して粘り強く抵抗を続けました。
その活動により1962年に逮捕され、終身刑という重い判決を受けることになります。その後、28年もの長きにわたって投獄される苦難の時期を経て、1990年についに釈放されました。
釈放後は、白人政権と話し合い、アパルトヘイト撤廃に向けて活動します*13)。
アパルトヘイトの撤廃
1970年代後半、黒人による反アパルトヘイト運動が激化しました。国連や諸外国による圧力が増す中、白人政権はアパルトヘイト撤廃に動き出します。
【アパルトヘイト撤廃の動き】
| 1983年 | カラード(混血)とインド系住民に選挙権を与える |
| 1985年 | 雑婚禁止法、背徳法、パス法を撤廃 |
| 1986年 | 黒人との権力分担を声明 |
| 1989年 | デクラーク大統領の就任 |
| 1990年 | マンデラ釈放 |
| 1991年 | 人口登録法、土地法、集団地域法の廃止 →アパルトヘイトの終焉 |
| 1993年 | デクラーク大統領とマンデラ氏がノーベル平和賞を受賞 |
| 1994年 | 南アフリカ史上初の全人種参加による選挙を実施 →マンデラ政権の成立 |
マンデラ大統領の就任により、長年続いた白人による人種隔離政策に基づく統治が終わり、黒人が主体となる新しい南アフリカが誕生しました。この歴史的な転換を象徴するように、1994年には国旗も一新され、現在使用されているデザインとなりました。
アパルトヘイトに関してよくある疑問
アパルトヘイトの撤廃は、人類の歴史上大きな出来事となりました。ここでは、アパルトヘイトに関するよくある質問を2つ取り上げます。
アパルトヘイトが対象になった国は?
アパルトヘイトは南アフリカ共和国で起きたものです。アパルトヘイト政策は1948年から1994年までの間、南アフリカ政府によって実施され、白人と非白人の人種を分離。非白人に対するさまざまな差別と抑圧が行われました。
この制度は1990年代初頭に廃止され、1994年の民主的な選挙でネルソン・マンデラが大統領に選出されることで終焉を迎えました。
アパルトヘイトは日本人に関係ある?
アパルトヘイトが行われている間、非白人は差別されていました。
しかし、日本人を含むビジネス関係者は「名誉白人」として特別待遇を受けていました。これにより彼らは白人が住む場所を選んだり、白人専用の施設を利用したりすることができましたが、永住権などの法的権利は認められていませんでした*14)。
日本はアパルトヘイトに反対しており、いくつかの規制を設けていましたが、同時に貴重な鉱産資源を持つ南アフリカとの経済関係も軽視できませんでした。欧米諸国が制裁として南アフリカとの貿易を縮小する中、日本は貿易を続けました。
そして、1987年には南アフリカの最大の貿易相手国となってしまいます*15)。
このため国際社会から強い批判を受けることになります。これを受けて日本政府は国内企業に対し慎重な対応を求め、翌年には南アフリカとの貿易を縮小することとなりました*16)。
アパルトヘイトが廃止された後、日本政府は南アフリカに対して積極的な支援を行います。その一環として、マンデラ氏を日本に招待しています*17)。
アパルトヘイトを廃止した人は誰?
アパルトヘイトを廃止した人物は、フレデリック・デクラークです。1990年に黒人のネルマン・マンデラを釈放し、1991年には国会でアパルトヘイトの廃止を宣言しています。
1994年には、ネルマン・マンデラが黒人初の大統領に就任し、さまざまな人種が共存できる国を目指しました。ネルマン・マンデラ政権下の副大統領は、フレデリック・デクラークです。
アパルトヘイトは英語で何という?
アパルトヘイトは英語で「apartheid」と表します。アパルトヘイトは、アスカヌーン語でも「分離・隔離」を意味しています。
アパルトヘイトとSDGs
アパルトヘイトは、白人による支配を維持するため、黒人をはじめとする非白人の権利を法的に制限し差別する仕組みでした。これは、SDGsの理念に大きく反することです。ここでは、SDGs目標10との関わりについて解説します。
SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」とアパルトヘイトには深い関連があります。アパルトヘイトは、南アフリカで1948年から1994年まで続いた人種隔離政策であり、人種による差別と不平等を制度化した象徴的な事例です。
この政策は、白人優位主義に基づき、有色人種の基本的人権を著しく制限し、教育、居住、雇用などあらゆる面で差別を強いました。
このような不平等な社会システムは、SDGsの「誰一人取り残さない」という理念と真っ向から対立します。
アパルトヘイトの経験は、人種や民族による差別がいかに社会の持続可能な発展を阻害するかを示す重要な教訓となっています。
SDGs目標10は、このような過去の過ちを繰り返さないよう、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教などに関係なく、すべての人々の機会均等を確保し、成果の不平等を是正することを目指しています。
まとめ
アパルトヘイトは、南アフリカにおける人種隔離政策として43年間続きました。白人支配者層が非白人を差別・隔離し、政治的・経済的な支配を維持するために実施されました。人種によって居住地域や施設が分けられ、教育や雇用の機会も制限されました。
しかし、国連や国際社会からの批判、反アパルトヘイト運動の高まりにより、政策は徐々に緩和され、最終的に1991年に廃止されました。ネルソン・マンデラの大統領就任により、新しい民主的な南アフリカが誕生しました。
アパルトヘイトは、SDGsの目標10にある「人や国の不平等をなくそう」との関連で多くの教訓を残しています。
参考
*1)知恵蔵「アパルトヘイト」
*2)旺文社「アパルトヘイト」
*3)日本大百科全書「アパルトヘイト」
*4)外務省「第4章 各地域の情勢と日本との関係 第7節 アフリカ」
*5)旺文社世界史事典 三訂版「南アフリカ連邦」
*6)デジタル大辞泉「南ア戦争」
*7)山川 世界史小辞典 改定新版「南アフリカ連邦」
*8)日本大百科全書(ニッポニカ)「アパルトヘイト」
*9)国際連合「アパルトヘイトとの戦い」
*10)国際連合広報センター「アパルトヘイト」
*11)改定新版 世界大百科事典「シャープビル事件」
*12)ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「ソウェト蜂起」
*13)旺文社世界史事典 三訂版「マンデラ」
*14)改定新版 世界大百科事典「南アフリカ」
*15)アフリカ日本協議会「反アパルトヘイト運動の経験を振り返る」
*16)外務省「第3章 各地域情勢及びわが国との関係 第8節 アフリカ」
*17)外務省「第4章 各地域の情勢と日本との関係 第7節 アフリカ」
この記事を書いた人
馬場正裕 ライター
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。