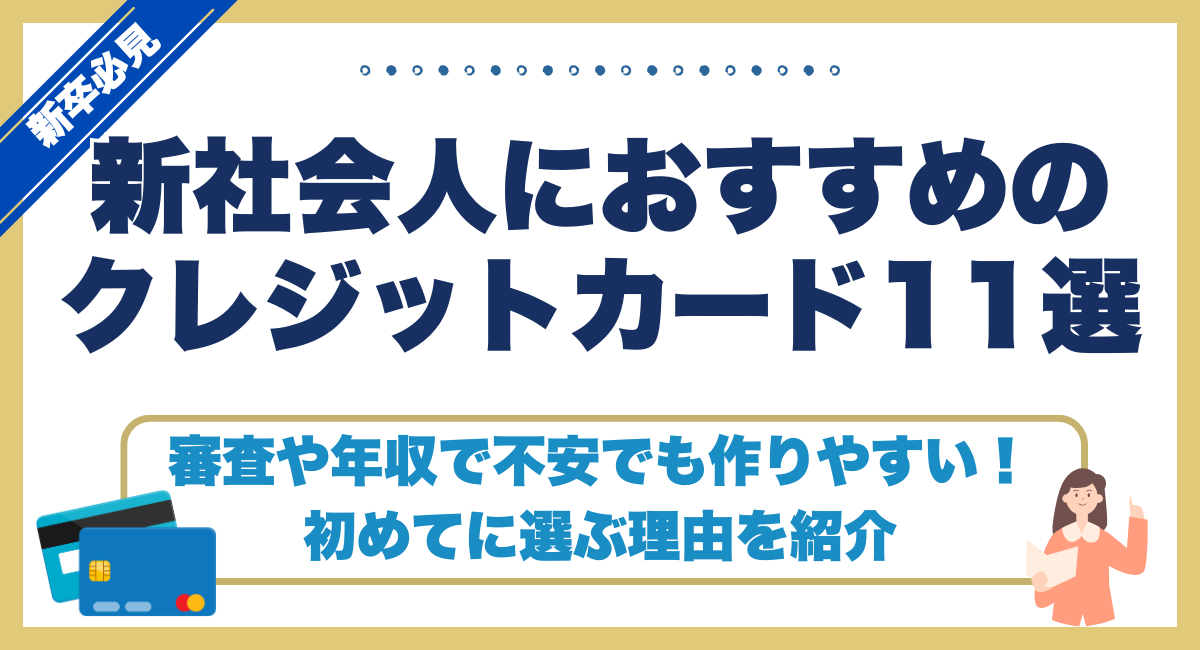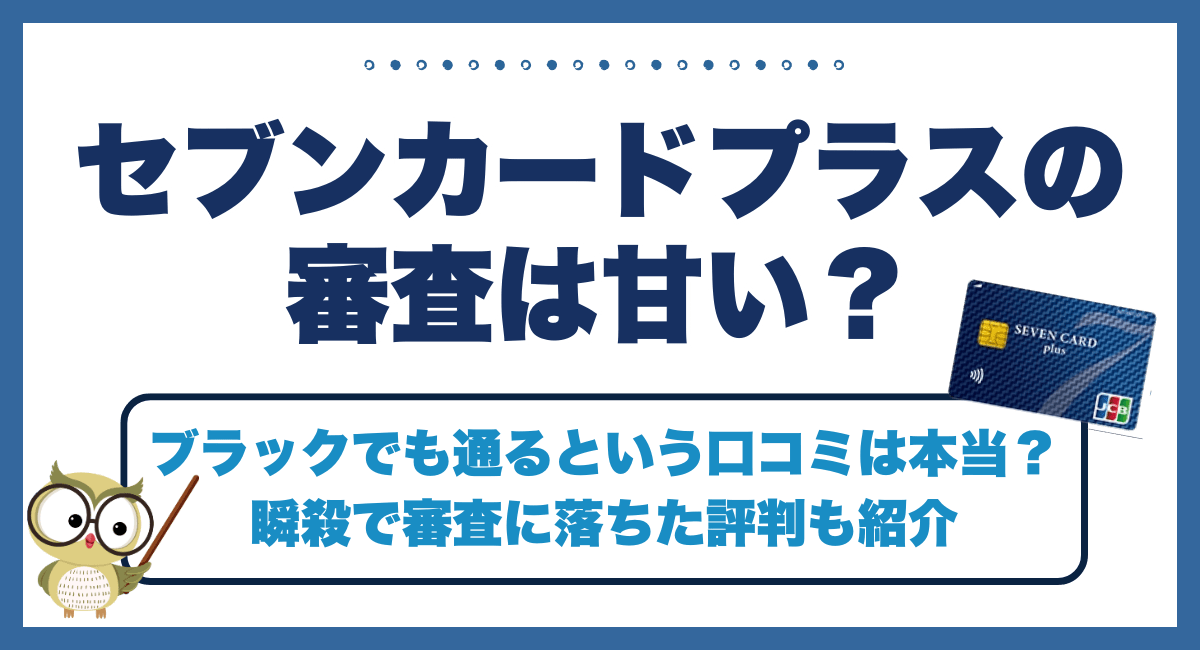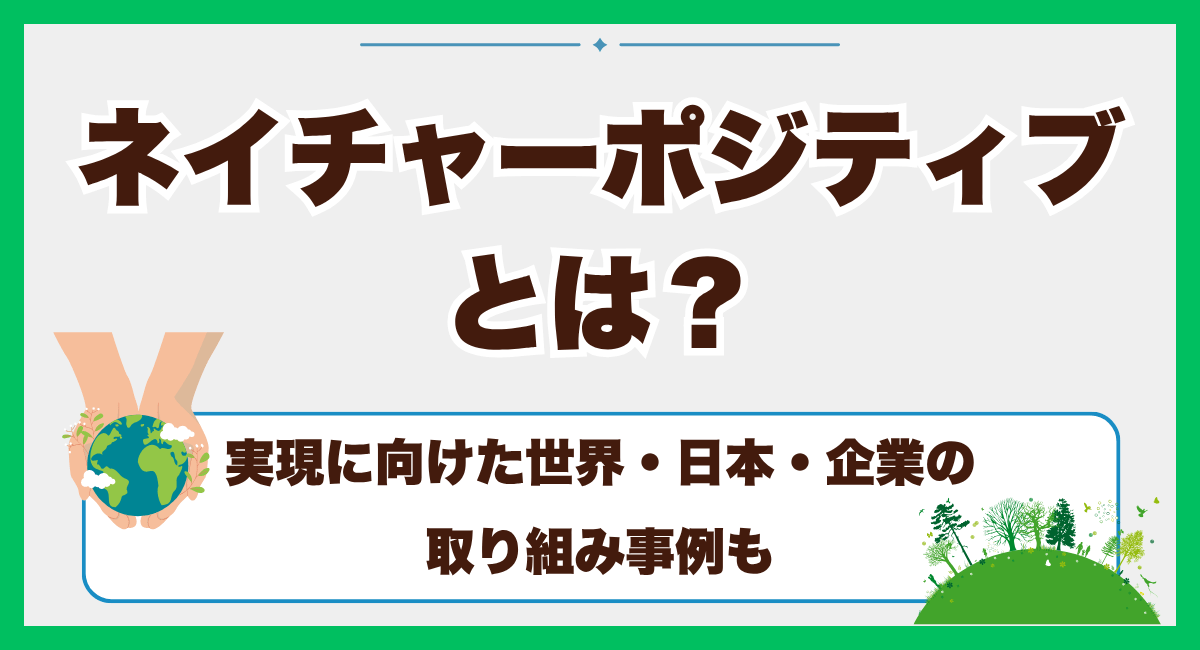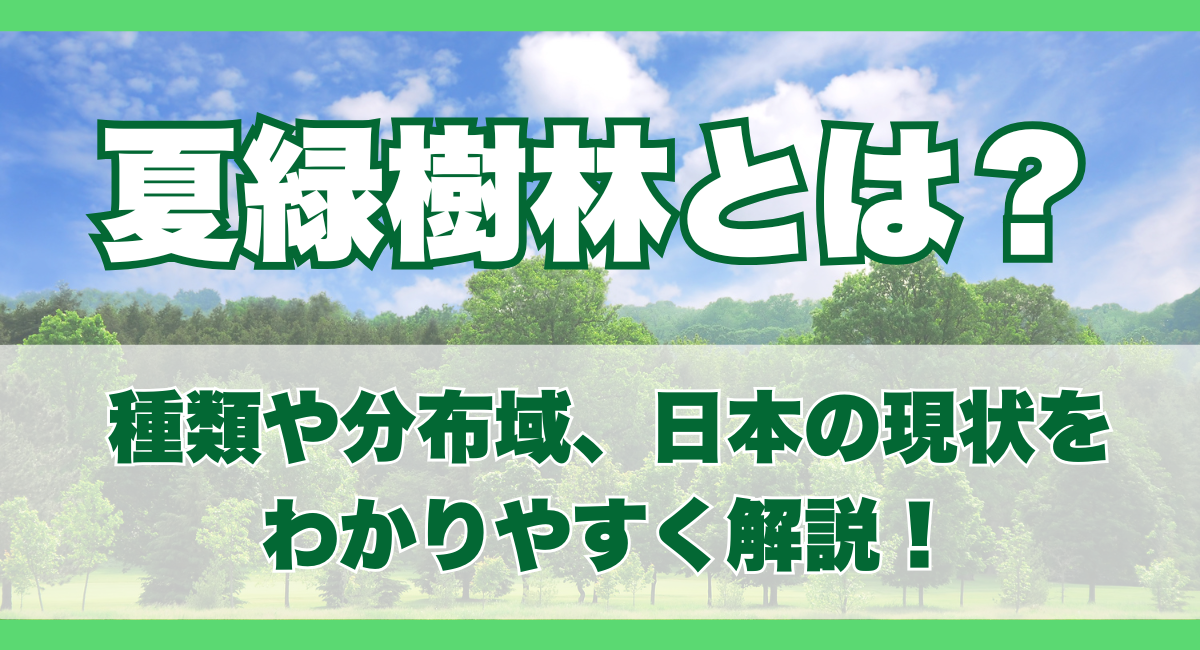恐竜が絶滅した原因は、長年の謎でした。最新の研究が、隕石衝突説を裏付ける新たな証拠を示す一方で、絶滅前の恐竜の状況にも注目が集まっています。
もし恐竜が絶滅しなかったら、地球はどうなっていたのでしょうか。地球の様子は?人間との共存は?恐竜絶滅の真相と、その影響を探ることで、現代の環境問題にも新たな視点が得られます。恐竜の歴史から最新の研究結果まで、科学的な知見に基づいた情報をわかりやすく解説します。
目次
恐竜の歴史

恐竜は、地球上に約2億3000万年前に出現し、約6600万年前に絶滅するまで、長きにわたり地球の生態系の頂点に君臨した生物群です。その姿や生態、そして突然の絶滅は、多くの人々を魅了し続けています。
恐竜の定義と特徴
そもそも恐竜とは、中生代に繁栄した陸生脊椎動物※の一群を指します。これらは爬虫類に属しますが、現代の爬虫類とは異なる特徴を持っています。
最も顕著な違いは、恐竜が直立した姿勢で歩行することです。これは、恐竜の脚が体の真下に位置しているためで、この特徴により効率的な移動が可能でした。
【爬虫類・恐竜と哺乳類・絶滅したワニに近縁な動物の後ろ足のつき方】
左:トカゲやワニなど一般的な現生の爬虫類。中央:恐竜、哺乳類。右:ラウイスクス類(絶滅したワニに近縁な動物)
よく恐竜と混同される生物
【白亜紀に生息したプテラノドンの化石】
現在の学術的な恐竜の定義は、「鳥とトリケラトプスの直近の共通祖先と、そのすべての子孫」とされており、同時期に生息していた海生爬虫類や飛行爬虫類は、正確には恐竜に含まれません。
代表的な例として、以下のような生き物が挙げられます。
プテラノドン: 翼竜の一種で、恐竜ではない。白亜紀後期に生息した大型の飛行爬虫類
フタバスズキリュウ: 首長竜の一種で、白亜紀後期の海に生息していた海生爬虫類
モササウルス: 海生爬虫類の一種で、白亜紀後期の海に生息していた
魚竜: イルカに似た姿を持つ海生爬虫類の一種で、三畳紀から白亜紀にかけて生息していた
ディメトロドン:哺乳類に近い祖先を持ち、背中に大きな帆のある単弓類で、恐竜よりも古い時代に生息していた
これらの生物は、恐竜と同じ中生代に生息していたため、恐竜と混同されることがありますが、系統的には異なる分類群に属しています。
恐竜の時代

恐竜の歴史は、三畳紀後期(約2億3000万年前)に始まります。この時期、最初の恐竜が出現しました。その後、ジュラ紀(約2億100万年前〜1億4500万年前)を経て、白亜紀(約1億4500万年前〜6600万年前)に至るまで、恐竜は地球上で繁栄を続けました。
順を追って詳しく見ていきましょう。
三畳紀:恐竜の誕生
【三畳紀の恐竜:プラテオサウルスの全身骨格教本】
先述したように、三畳紀後期、最初の恐竜が登場しました。この時期の地球は、超大陸パンゲア※が形成されており、気候は全般的に温暖でした。
初期の恐竜は比較的小型で、他の爬虫類と生態系を共有していました。
【パンゲア大陸の分裂】
【後期三畳紀の恐竜:エオラプトル(体長約1m)】
三畳紀の代表的な恐竜として、以下の例が挙げられます。
- エオラプトル: 最古の恐竜の一つで、原始的な特徴を持ちながら高速で走る
- コエロフィシス: 軽量で俊敏な小型肉食恐竜で、三畳紀後期に繁栄
- プラテオサウルス: 初期の竜脚形類で、長い首と尾を持つ大型の植物食恐竜
- ヘレラサウルス: 初期の獣脚類で、二足歩行の肉食恐竜として知られている
これらの恐竜は三畳紀に出現し、その後の恐竜の進化と多様化の基礎を築きました。
ジュラ紀:恐竜の多様化

ジュラ紀に入ると、恐竜は急速に多様化し、大型化していきました。この時期、最初の鳥類も出現しました。
ジュラ紀後期には、巨大な竜脚類や獰猛な肉食恐竜が出現し、恐竜が生態系の頂点に立つようになりました。
【カーネギー自然史博物館のステゴサウルス・ウンガルトゥスとされる複合骨格標本】
ジュラ紀の代表的な恐竜として、以下のような例が挙げられます。
- アロサウルス: ジュラ紀後期の最大級の肉食恐竜で、群れで狩りをした可能性がある
- アーケオプテリクス: 最古の鳥類とされ、羽毛と翼を持ち、恐竜の特徴も残す
- ステゴサウルス: 背中の特徴的な板と尾のスパイクを持つ大型の植物食恐竜
- ディプロドクス: 長い首と尾を持つ巨大な竜脚類で、全長約26メートルに達する植物食恐竜
白亜紀:恐竜の全盛期

白亜紀は、恐竜の全盛期でした。この時期、恐竜は最大の多様性を誇り、様々な環境に適応していきました。
私たちがよく知る恐竜の多くは、この時期に生息していました。白亜紀の代表的な恐竜として、以下の例が挙げられます。
- ティラノサウルス・レックス: 白亜紀後期の最大級の肉食恐竜
- トリケラトプス: 特徴的な3本の角と首飾り状のフリルを持つ大型の植物食恐竜
- ヴェロキラプトル: 小型で俊敏な肉食恐竜で、知能が高く、群れで行動したと考えられている
- アンキロサウルス: 全身を覆う骨板と尾端の骨こぶを持つ装甲性の植物食恐竜
K-Pg境界と恐竜の絶滅
約6600万年前、突如として恐竜の時代は終わりを迎えます。この時期は、白亜紀と古第三紀(古第三紀はかつて古第三紀と呼ばれていました)の境界にあたり、K-Pg境界と呼ばれています。
この境界で、鳥類を除く全ての恐竜が絶滅しました。
【恐竜が生きていた時代の名前】
恐竜の子孫
しかし、恐竜は完全に絶滅したわけではありません。現代の鳥類は、羽毛の生えた獣脚類(羽毛恐竜)から進化したとされています。
近年の羽毛恐竜の発見により、獣脚類から鳥への進化過程もだんだんと明らかになってきました。よく知られている始祖鳥(アーケオプテリクス)は、ジュラ紀後期に生息した初期の鳥類で、恐竜と鳥類の両方の特徴を持っていました。
つまり、現代の鳥類は恐竜の直接の子孫であり、約1万種の恐竜の子孫が現在も世界中に生息していることになります。
【ジュラ紀に生息した始祖鳥(アーケオプテリクス)の化石】
恐竜研究の歴史
恐竜の研究は、19世紀初頭から始まりました。1824年、イギリスの地質学者ウィリアム・バックランドがメガロサウルスの化石を発見し、これが最初の恐竜の学術的な記載となりました。
その後、多くの研究者によって新種の恐竜が次々と発見され、恐竜学は急速に発展していきます。日本でも、1934年に北海道帝国大学の長尾巧教授が、当時日本領だったサハリンで日本人初の恐竜化石を発見しました。
現在では、福井県が「恐竜王国」として知られ、日本の恐竜研究をリードしています。
日本での恐竜の化石の発見:フクイラプトル
【フクイラプトル復元骨格】
フクイラプトルは、2000年に日本初の新種恐竜として命名された獣脚類※で、最新の研究によりアロサウルス類の進化型であるメガラプトル類に分類されています。体長4.2メートル、体重175〜300キロと推定されますが、発見された化石は未成熟個体のため、成体はさらに大型化したと考えられています。
その他にも、
- パラリテリジノサウルス:2022年に北海道の蝦夷層群オソウシナイ層から発見された獣脚類
- ティラノミムス:2023年に福井県の手取層群から発見された獣脚類で、デイノケイルス科に属す
- ヒプノヴェナトル:2024年に兵庫県の篠山層群から発見された獣脚類トロオドン科の新属新種
- ササヤマグノームス:2024年に兵庫県の篠山層群から発見された初期角竜類の新属新種で、推定全長約80cm
などが、日本固有の恐竜とされています。日本の恐竜研究は近年急速に進展しており、今後もさらなる新種の発見が期待されます。
恐竜の研究は、常に新しい発見によって覆されてきました。例えば、かつては恐竜を冷血動物と考えていましたが、現在では少なくとも一部の恐竜は温血動物だったと考えられています。
また、最近の研究では、多くの恐竜が羽毛を持っていたことが明らかになっています。
恐竜の歴史は、地球の歴史そのものです。彼らの進化と絶滅は、地球環境の大きな変化を反映しています。恐竜の研究は、過去の地球を理解するための重要な鍵となっているのです。*1)
恐竜が絶滅した原因

恐竜の絶滅は、地球の歴史上最も劇的な出来事の一つです。長年の研究により、その主な原因が約6600万年前の巨大隕石の衝突であることが明らかになっています。
この時期の地層は「K-Pg境界」と呼ばれています。K-Pg境界を含む岩石層には、イリジウムやプラチナのスパイクが見られ、これは隕石衝突の証拠※と考えられています。
アメリカワイオミング州で採取された岩石のK-Pg境界には、上下の白亜紀・新生代第三紀の層に比べて1000倍のイリジウムを含んでいることがわかっています。
【K-Pg境界を含む岩石】
恐竜絶滅の原因について、最新の研究成果を交えて見ていきましょう。
隕石衝突による大災害
メキシコのユカタン半島沖に幅約10キロの小惑星チクシュルーブが衝突したことで、地球環境は激変しました。隕石の衝突は、以下のような、想像を絶する規模の大災害を引き起こしたのです。
- 衝突の瞬間、巨大な熱放射が発生し、周辺地域は一瞬にして焼き尽くされた
- 少なくともマグニチュード10.1の超巨大地震が発生し、地球全体を揺るがした
- 地形によっては最大305メートルの巨大な津波が発生し、沿岸部を壊滅させた
- 衝突点周辺では、地殻から噴出物が流れ出し、焼けた大地を熱い砂と灰で覆い尽くした
- 衝突点に近い場所では、地面は厚さ数百〜千メートルを超える岩屑の下に埋まった
【K-Pg境界での巨大隕石落下直後の大規模酸性雨と銀・銅に富む粒子の生成の仕組み】
衝突後の環境変化

衝突の約45分後、一陣の風が時速965キロという驚異的な速度で一帯を吹き抜け、岩屑を撒き散らし、立っているものをすべてなぎ倒しました。このとき、105デシベルという、人間の耳には耐えられないほどの爆発音が鳴り響きました。
空は暗さを増し、衝突によって巻き上げられた岩屑が流星のように地球に降り注ぎました。ガラス質の小球であるマイクロテクタイトが赤熱した状態で降り注ぎ、まさに「この世の終わり」のような光景が広がりました。
岩屑は低高度から大気圏に再突入し、ゆっくりとした速度で、赤外線を放射しながら落ちてきました。これらは、赤っぽく光っていたと考えられています。
長期的な環境への影響
最終的に恐竜を含む地球上の生命の大半を消し去ったのは、より長期的な環境への影響でした。赤い光が消えた後、地球をめぐる灰と岩屑が日の光を遮り、最初の数時間は真っ暗闇に近い状態だったと考えられています。
その後数週間、数カ月、あるいは数年の間は、夕暮れ時か、どんよりとした曇りの日のような状態が続きました。植物の光合成が劇的に減少し、食物連鎖の崩壊が始まりました。
煤や灰が大気中から洗い流されるまでには何カ月という時がかかり、酸性の泥のような雨が地球に降り注ぎました。
さらに、大規模な火事は大量の毒素を生み出し、地球の生態系を保護するオゾン層を一時的に破壊しました。小惑星の衝突直後、地球は核の冬※に続き、激しい温暖化を経験しました。この急激な気候変動は、多くの生物種にとって致命的でした。
恐竜の絶滅は、このような複合的な要因によって引き起こされました。最新の研究により、近年ではこのときの衝突の影響がより詳細にわかってきています。
私たちは過去の大絶滅イベントから、今後より多くを学べるでしょう。*2)
恐竜が絶滅したと言われる隕石に関する最新研究
【チクシュルーブ隕石の落ちたユカタン半島衛星写真】
恐竜絶滅の謎を解く鍵として、最大の原因となったチクシュルーブ隕石の研究が飛躍的に進展しています。最新の科学技術を駆使した分析により、隕石の起源や衝突の詳細が明らかになりつつあります。
同時に、日本でも新たな恐竜の発見が相次ぎ、恐竜研究に新たな光を当てています。これらの最新の研究成果について、確認していきましょう。
チクシュルーブ隕石の起源が判明
2024年8月、チクシュルーブ隕石の正体が明らかになりました。研究チームは、隕石の残骸からルテニウムという希少元素の化学組成を分析し、その結果、チクシュルーブ隕石が木星より外側の「外太陽系」で形成された炭素質コンドライト隕石だったことが判明しました。
この発見により、問題の隕石が彗星などの、その他の天体ではなかったことが確認されました。これは、白亜紀を終わらせたのが小惑星の衝突であったという説を強く裏付けるものです。
隕石衝突の新たな証拠
2021年2月、東京大学を中心とする研究チームは、問題のクレーター内部から、小惑星由来の元素を高濃度で含む地層を発見しました。この地層には、イリジウムを含む衝突ダストが含まれており、全球に降り注いだ証拠となっています。
この発見も、隕石衝突説がこれまでで最も有力な仮説であることを裏付けるものです。研究チームは、クレーター内部の地層を詳細に分析することで、衝突直後の環境変動のメカニズムを解明しようとしています。
日本の恐竜研究最前線:ササヤマグノームスの発見
【2024年に新属新種として正式に記載されたササヤマグノームス】
2024年9月、日本の恐竜研究に新たな発見がありました。兵庫県丹波篠山市の篠山層群大山下層(約1億1000万年前)から発見された植物食恐竜(角竜類)の化石が、新属新種「ササヤマグノームス・サエグサイ」として正式に記載されたのです。
【ササヤマグノームスの化石(全部で17点の化石が発掘された】
ササヤマグノームスは、「篠山の地下に隠された財宝を守る小人」という意味を持ち、その名前は発見地と化石の小ささ(推定体長は約80cm)に由来しています。この発見は、日本の恐竜相の多様性を示すとともに、アジアと北米の恐竜の関係性を解明する重要な手がかりとなる可能性があります。
チクシュルーブ隕石の起源解明や、日本での新種恐竜の発見など、最新の研究成果は私たちに太古の地球の姿をより鮮明に描き出してくれています。しかし、恐竜絶滅の研究は、新たな発見が従来の物語を覆し、さらに新しい物語が浮かび上がってくるのが常です。
今後も、新たな技術や方法による研究が進み、恐竜絶滅の謎がさらに解明されていくことでしょう。*3)
もしも恐竜が絶滅していなかったら

恐竜が絶滅せずに現代まで生き延びていたら、地球はどのような姿になっていたでしょうか。この想像力をかき立てる仮説は、科学者たちの間でも興味深い議論を呼んでいます。
恐竜の運命を変えた可能性のある要因や、彼らが生き残った世界の姿について、最新の研究成果を交えながら探ってみましょう。
隕石衝突回避シナリオ
隕石さえ衝突しなかったら、恐竜は絶滅していなかったかもしれません。この仮説は多くの科学者によって支持されています。
2019年の研究によると、6600万年前の大量絶滅のときまで、恐竜が衰退する兆しは全くなかったとされています。
しかし、この見解には注意が必要です。白亜紀最後(マーストリヒト期)については、詳しい状況がわかるほど化石が見つかっていないため、化石記録の偏りを考慮する必要があります。
知的進化の可能性
恐竜が絶滅を免れていた場合、彼らはどのように進化していたでしょうか。カナダの古生物学者デイル・ラッセル教授は、肉食恐竜が進化して知性を持つ「恐竜人間(ディノサウロイド)」になる可能性を提唱しました。
この仮説は科学的根拠に乏しいものの、恐竜ファンの想像力を刺激する魅力的なアイデアです。実際には、恐竜の進化の方向性を正確に予測することは困難です。
生態系への影響
恐竜が生き残っていた場合、現代の生態系は大きく異なっていたでしょう。最先端の生態学やデータサイエンスを駆使した地球システムのモデルによると、哺乳類の進化や植物の多様性に大きな影響があったと考えられ、現在とは違った生物相が形成されていた可能性が高いと言えます。
例えば、ブドウのような果実の進化が遅れていたかもしれません。この推測は、かつて大型恐竜の存在が植物の種子散布戦略に影響を与えていたことに基づいています。
人類との共存シナリオ
恐竜と人類が共存する世界を想像するのは、恐竜ファンにとって魅力的なテーマです。しかし、科学的には非常に低い可能性しかありません。
もしも、恐竜が生物の中で支配的な存在であり続けていた場合、人類のような高度な知性を持つ哺乳類が進化する機会はなかったかもしれません。
一方で、鳥類は恐竜の子孫であるという事実もあります。この観点からすれば、私たちは既に「恐竜」と共存しているとも言えるでしょう。
恐竜が絶滅しなかった世界を想像することは、生命の進化の複雑さと偶然性を理解する上で重要です。同時に、現在の生態系の貴重さと、私たちが直面している環境問題の重要性を再認識させてくれます。*4)
恐竜絶滅とSDGs

恐竜の絶滅研究とSDGs(持続可能な開発目標)は、一見無関係に思えますが、地球環境の保護と生物多様性の維持という共通点があります。恐竜絶滅の研究は、現代の環境問題や生態系の脆弱性を理解する上で重要な洞察を提供し、SDGsの目標達成に貢献しています。
特に恐竜絶滅研究の知見が活用されているSDGs目標を見ていきましょう。
SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を
チクシュルーブ隕石衝突後の急激な気候変動は、現代の気候変動問題と類似点があります。例えば、北海道大学の研究「移りゆく環境が野生動物に与えるインパクトを考える」(2025年2月)では、恐竜絶滅時の環境変化と現代の気候変動を比較し、野生動物への影響を予測しています。
この研究は気候変動対策の重要性を強調し、具体的な保護策の立案に貢献しています。
SDGs目標14:海の豊かさを守ろう
恐竜絶滅時の海洋生態系の変化は、現代の海洋保護活動に重要な示唆を与えています。国立科学博物館の真鍋真氏の研究では、恐竜絶滅時の海洋生態系の変化を分析し、現代の海洋保護活動に活用できる知見を提供しています。
SDGs目標15:陸の豊かさも守ろう
恐竜絶滅後の生態系回復過程は、現代の生物多様性保護活動に応用可能です。北海道大学総合博物館の小林快次教授の研究では、この回復過程を分析し、絶滅危惧種の保護や生態系の回復プログラムの設計に活用されています。
恐竜絶滅の研究は、過去の大規模な環境変化と生態系の反応を理解する上で重要な役割を果たしています。これらの知見は、SDGsの目標達成に向けた具体的な行動計画の立案や、効果的な環境保護政策の策定に大きく貢献しています。*5)
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ

約6600万年前のチクシュルーブ隕石の衝突が主な原因とされる恐竜絶滅は、急激な環境変化が生態系に与える影響を示す貴重な例となっています。この分野の研究は、気候変動対策や生物多様性の保護など、SDGsの目標達成にも大きく貢献しています。
過去の大規模な環境変化と生態系の反応を理解することで、現在直面している環境問題に対し、より適切に対処できる可能性があります。今後は、恐竜絶滅研究と現代の環境科学をさらに統合し、より包括的な地球システムの理解を目指す必要があります。
私たちが恐竜絶滅について学ぶことは、地球の歴史と生命の脆弱性を理解し、環境保護の重要性を認識する良い機会となります。あなた自身は、日常生活でどのように環境保護に貢献できるでしょうか?また、恐竜絶滅から学んだ教訓を、どのように次世代に伝えていくことができるでしょうか?
現代に生きる私たちは、誰もが地球の歴史から学び、持続可能な未来のために行動を起こすことができます。恐竜たちが残してくれた貴重な教訓を心に刻み、より良い地球の未来を創造していきましょう。*6)
<参考・引用文献>
*1)恐竜の歴史
WIKIMEDIA COMMONS『Sprawling and erect hip joints – horiz』
WIKIMEDIA COMMONS『Eoraptor resto. 01』
WIKIMEDIA COMMONS『Plateosaurus Skelett 2』
WIKIMEDIA COMMONS『Pangea animation 03』
WIKIMEDIA COMMONS『Stegosaurus ungulatus』
WIKIMEDIA COMMONS『Pteranodon cat』
WIKIMEDIA COMMONS『Archaeopteryx lithographica (Berlin specimen)』
WIKIMEDIA COMMONS『Fukuiraptor Odaiba 2』
福井県立恐竜博物館『恐竜が生きていた時代の名前は?』
Wikipedia『恐竜』
国立科学博物館『日本の恐竜発見史 ①』(2007年12月)
国立科学博物館『日本の恐竜発見史 ②』(2007年12月)
国立科学博物館『日本産恐竜・発見ラッシュ!』(2007年12月)
東京大学『恐竜の走行能力の進化の解明 ~白亜紀は恐竜高速化の時代だった~』(2025年1月)
東京大学総合研究博物館『恐竜の歩き方の特殊性と進化の関係』
神戸大学『大量絶滅と恐竜の多様化を誘発した三畳紀の「雨の時代」』(2020年12月)
福井県立博物館『世界で最初に恐竜の化石が発見されたのはいつ?』
福井県立博物館『恐竜が地球にいたのはいつごろ?』
福井県立博物館『三畳紀、ジュラ紀、白亜紀といった地質時代の名前の由来は?』
福井県立博物館『恐竜ってどんな生き物なの?』
福井県立恐竜博物館『フクイラプトル・キタダニエンシス』
福井県立恐竜博物館『鳥が恐竜ってホント?』
高波 鐵夫『6600 万年前の K/Pg(白亜紀/古第三紀)境界-北海道浦幌町の山奥で触れる-』
福井県公式観光サイト『福井は恐竜王国!? その理由と福井で恐竜を楽しむ方法とは』(2023年8月)
九州観光機構『太古の記憶を辿る、恐竜と化石の島【御所浦島】』(2024年11月)
HONDA『どこまでわかってきている?「恐竜きょうりゅう」の最新のふしぎとナゾ』
HOKKAIDO DEGITAL MUSEUM『白亜紀から新生代へ、恐竜・化石をめぐるタイムトラベル』
東洋経済ONLINE『恐竜はヒトの800倍超の1億6000万年栄えた』(2018年12月)
日本経済新聞『ほぼ腕のない新種の肉食恐竜、南米パタゴニアで化石発見』(2024年6月)
日本経済新聞『2度の大量絶滅乗り越え 恐竜1.5億年、繁栄の秘密』(2020年10月)
NIKKEIリスキリング『最古の「現生鳥類」発見 恐竜の絶滅前、起源にも波紋』(2020年4月)
NIKKEIリスキリング『海岸で大量の恐竜の足跡 謎多いジュラ紀中期にヒント』(2018年4月)
NATIONAL GEOGRAPHIC『1.6億年前の恐竜の足跡、空白の時代知るヒント』(2018年4月)
*2)恐竜が絶滅した原因
WIKIMEDIA COMMONS『K-T-boundary』
量子科学技術研究開発機構『隕石衝突後の環境激変の証拠を発見〜白亜紀最末期の生物大量絶滅は大規模酸性雨により引き起こされた?〜』(2020年2月)
University of BRISTOL『Dinosaurs were thriving before asteroid strike that wiped them out』(2019年3月)
University of California, Berkeley『66 million-year-old deathbed linked to dinosaur-killing meteor』(2019年3月)
BBC『Dinosaur-killing asteroid strike gave rise to Amazon rainforest』(2021年4月)
ScienceNews『The dinosaur-killing asteroid impact radically altered Earth’s tropical forests』(2021年4月)
NATIONAL GEOGRAPHIC『小惑星衝突「恐竜絶滅の日」に何が起きたのか 1000km先でも即死、時速965kmの風が大木をなぎ倒し、巨大地震も発生』(2016年6月)
NATIONAL GEOGRAPHIC『恐竜絶滅、小惑星の落ちた場所が悪かったせい?小惑星の衝突で大量絶滅が起こるのは地球表面の13%、東北大ほか研究』(2017年11月)
NATIONAL GEOGRAPHIC『恐竜絶滅、なぜ鳥だけが生き延びた?』(2018年5月)
NATIONAL GEOGRAPHIC『隕石衝突まで恐竜は減っていなかった、新研究』(2019年3月)
NATIONAL GEOGRAPHIC『恐竜の滅亡に第2の小惑星衝突が関与していたか、痕跡を発見 西アフリカで新たな痕跡、同時期に複数の衝突があった可能性』(2022年8月)
NATIONAL GEOGRAPHIC『恐竜絶滅は春に始まった、小惑星衝突の季節をついに特定、研究 衝突直後に死んだ魚の化石を分析、秋だった南半球のほうが生物に有利?』(2022年2月)
NATIONAL GEOGRAPHIC『小惑星衝突「恐竜絶滅の日」に新事実、1600km先のガスが155℃に』(2022年3月)
NATIONAL GEOGRAPHIC『研究室に行ってみた。国立科学博物館 恐竜 真鍋真 第6回 恐竜が絶滅した「瞬間」の化石が見つかった!』
日本経済新聞『恐竜を絶滅させた巨大隕石の正体判明、レアタイプだった』(2024年9月)
日本経済新聞『恐竜のがん、世界初確認 CTや顕微鏡使い化石解析』(2020年8月)
NIKKEIリスキリング『克明に分かった恐竜最後の日 小惑星衝突の一部始終』(2019年9月)
Sience Portal China『中国による恐竜の卵の研究、絶滅の新たなメカニズムを提示』(2022年9月)
*3)恐竜が絶滅したと言われる隕石に関する最新研究
WIKIMEDIA COMMONS『Nodosaur』
WIKIMEDIA COMMONS『Sasayamagnomus UDL』
兵庫県立人と自然の博物館『兵庫県・篠山盆地から新属新種の角竜類を発見
「ササヤマグノームス・サエグサイ」』
東北大学『白亜紀中期の海洋生物の大量絶滅は7回の巨大火山噴火とアジア大陸東部の湿潤化が原因』(2024年3月)
Yahoo!ニュース『【三田市】新属新種の恐竜「ヒプノヴェナトル」「ササヤマグノームス」の化石がひとはくにて展示中』(2024年9月)
東京大学『恐竜を絶滅させた小惑星の痕跡を衝突クレーター内に発見 -全球に降り注いだイリジウムを含む衝突ダスト-』(2021年2月)
東京大学『太陽系の外から降り注ぐ微粒子に生命の痕跡を探す』(2023年3月)
九州大学『生物絶滅規模の天体衝突の痕跡から環境変動メカニズムを解読する』(2024年3月)
福井県立恐竜博物館『恐竜絶滅の原因として、最も有力と考えられている仮説とは?』
NATIONAL GEOGRAPHIC『14年間隠されていた「決闘する恐竜」化石、ついに表舞台へ』(2020年11月)
NATIONAL GEOGRAPHIC『隕石衝突後の世界を生きた恐竜たち』
NATIONAL GEOGRAPHIC『「恐竜絶滅」の隕石の正体判明、レアタイプだった、火山説も除外 6600万年前の大量絶滅の原因、木星より外でできた「C型小惑星」』(2024年8月)
NATIONAL GEOGRAPHIC『恐竜の巨大化と絶滅から学べること 「巨大恐竜展 2024」監修者が解説』
今井 拓哉『恐竜時代の福井 約 1 億 2000 万年前の 動植物 相と環境』(2022年11月)
nature『琥珀に恐竜時代の鳥類の翼』(2025年)
Newsweek『巨大隕石の衝突が「生命を進化」させた? 地球史初期の新事実』(2024年11月)
CNN『32億年前の地球衝突で海を沸騰させた巨大隕石、「肥料爆弾」と呼ばれる理由とは』(2025年2月)
日本経済新聞『東工大・東大・東邦大など、約6,600万年前の巨大クレーター内から小惑星由来の元素を高濃度で含む地層を発見』(2021年2月)
現代ビジネス『じつは「ティラノサウルス」が「異様に」多かった…! 地層を調べてわかった「恐竜大絶滅の少し前」の意外な様子』(2023年3月)
Yahoo!ニュース『完全な姿とどめたミイラ化恐竜化石を発見 ── カナダ・アルバータ州』(2017年5月)
*4)もしも恐竜が絶滅していなかったら
日本経済新聞『鳥になった恐竜、空飛ぶ進化のカギ 羽毛や翼を「転用」』(2024年10月)
BBC『What if dinosaurs hadn’t died out?』(2017年9月)
BBC『Would dinosaurs still be here if an asteroid hadn’t hit Earth?』(2020年11月)
Newsweek『「知性を持っていた?」もし恐竜が絶滅していなかったらどうなっていたのか』(2022年11月)
Museum of Science『What if the Dinosaurs Hadn’t Gone Extinct?』(2020年11月)
POPULAR SCIENCE『If dinosaurs hadn’t gone extinct, we may not have delicious grapes』(2024年1月)
FUTURO PROSSIMO『Dinosaurs, what the world would be like if they hadn’t gone extinct』(2022年11月)
NATIONAL GEOGRAPHIC『Would dinosaurs have died without an asteroid strike? Here’s the science.』(2019年3月)
リクルートワークス研究所『恐竜は、絶滅していない』(2019年6月)
*5)恐竜絶滅とSDGs
NATIONAL GEOGRAPHIC『過去の「大量絶滅」と現在の空恐ろしい類似点 全生物種の75%超が絶滅した過去5回を解説、人類は6度目を起こすのか?』(2019年9月)
NATIONAL GEOGRAPHIC『研究室に行ってみた。国立科学博物館 恐竜 真鍋真 第3回 恐竜絶滅の謎を解く鍵と、その意味とは』
財務省『恐竜が人間に送るメッセージ 北海道大学総合博物館教授 小林 快次』
国立環境研究所『大量絶滅イベントにおける一次生産量停止が生態系に与える影響の解明(令和 5年度)Impacts of reduction of primary production on ecosystems in mass extinction events』(2023年)
北海道大学『移りゆく環境が野生動物に与えるインパクトを考える』(2025年2月)
*6)まとめ
United Nations Development Programme『気候変動から人類を救う!「絶滅を選ぶな」と訴えた恐竜フランキー、初来日!』(2024年4月)
Nomura+『恐竜が現代の私たちに教えてくれること』(2023年12月)
国立環境研究所『環境研究・技術開発戦略(答申)の背景にある自然共生社会』(2016年)
この記事を書いた人
松本 淳和 ライター
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。