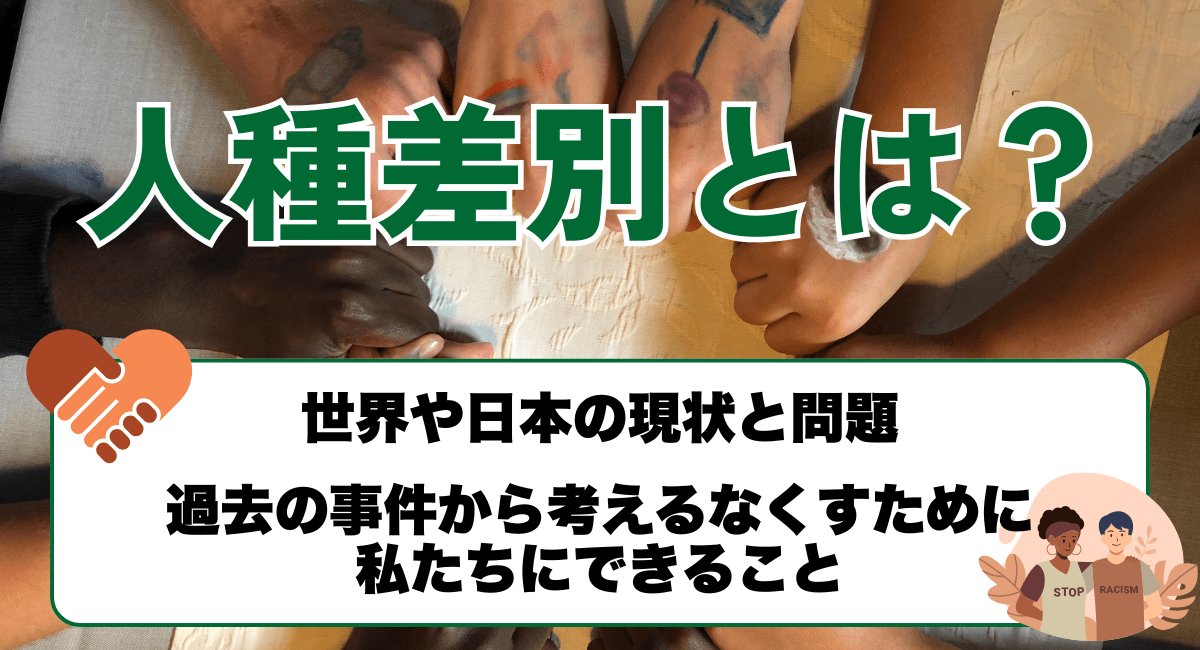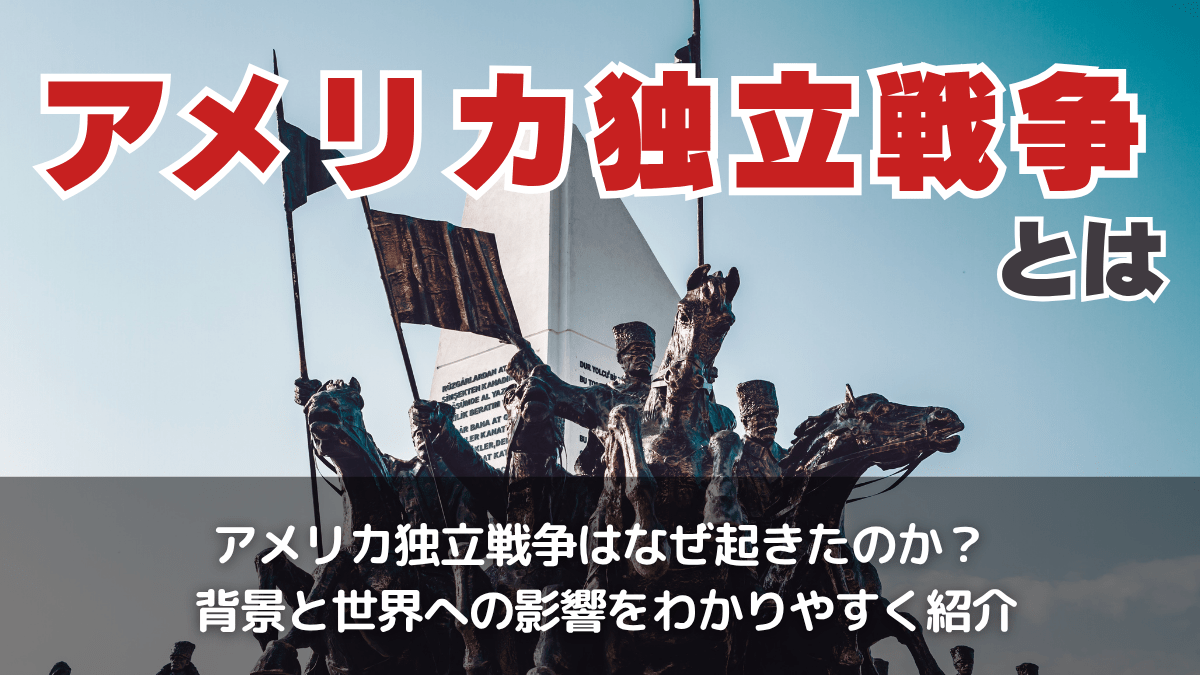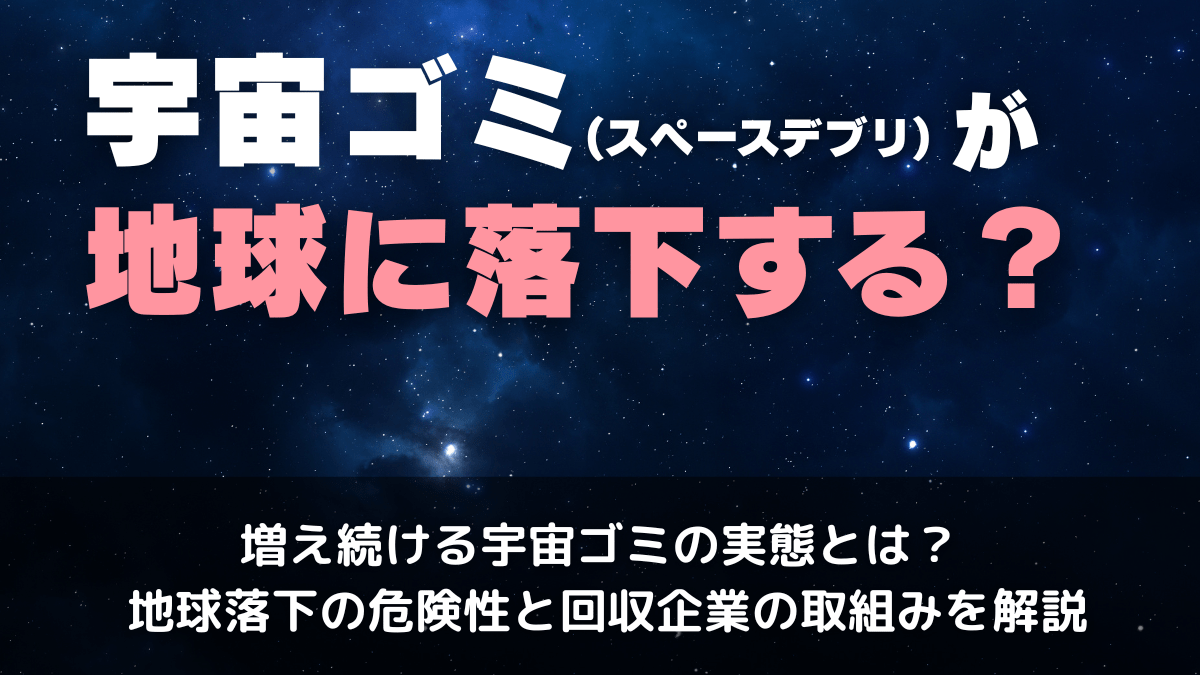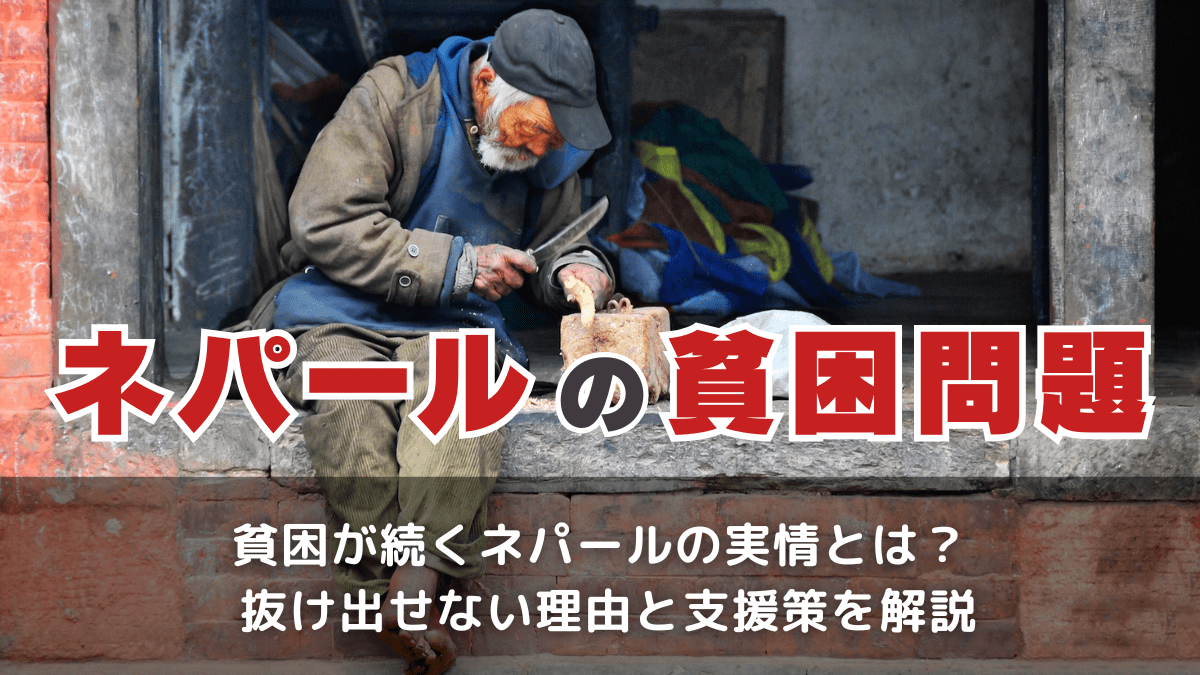「障害」という言葉から、あなたはどんなイメージを思い浮かべるでしょうか? 病気、怪我、そして、それらが引き起こす日常生活の困難…。もしも、あなたが、あるいはあなたの大切な人が、ある日突然、これまで通りの生活を送ることが難しくなったとしたら? 「障害」は決して、他人事ではありません。
日本では、約9.3%の人々が何らかの障害を抱えており、その数は1,000万人を超えています。では、障害のある方が、住み慣れた地域で、安心して自分らしく暮らし続けるためには、どんな支援が必要なのでしょうか?
その支援内容を決定するのが「障害支援区分」です。これは、単に「障害の重さ」を測るのではなく、「その人が必要とする支援の度合い」を明らかにすることで、一人ひとりに最適なサポートを届けるための、重要な指標です。
今回は、障害支援区分の内容や対象者、調査項目、認定の手続きなどについて解説します。
目次
障害支援区分とは

障害支援区分とは、「障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの」と定義されています*1)。必要とされる支援の度合いによって以下のように区分されています。
- 非該当
- 区分1
- 区分2
- 区分3
- 区分4
- 区分5
- 区分6
*1)
最も支援度合いが低いのは区分1で、区分6が最も支援の度合いが高いとされています。障害支援区分という全国共通の基準(度合い)を目安とし、支給の過程をより透明化・明確化して、公正・中立・客観的なものにすることを目指したのです。
障害程度区分との違い
障害者への支援制度において、以前は「障害程度区分」が使われていましたが、2014年4月からは「障害支援区分」へと移行しました。これは、障害のある方が必要とする支援をより適切に判断し、公平で行き届いたサービスを提供することを目的とした変更です。
【障害程度区分と障害支援区分の違い】
| 障害程度区分 | 障害者等に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするため当該障害者等の心身の状態を総合的に示すもの |
| 障害支援区分 | 障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの |
出典:厚生労働省*1)
障害程度区分で重視されたのは、「障害の程度(重さ)」を示すことでした。一方、障害支援区分では「標準的な支援の度合い」が重視されています*1)。
従来の障害程度区分では、主に身体障害の程度に着目した評価が行われていたため、知的障害や精神障害の特性が十分に反映されない場合がありました。そこで、新たな制度である障害支援区分では、認定調査項目や基準を見直すことで、知的障害や精神障害のある方の状況をより的確に把握できるように改善されました。
両制度とも区分1から区分6までの6段階で評価を行い、数字が大きいほど必要な支援が多いことを示すという基本的な枠組みは維持されています。また、二次判定においても知的・精神障害者の特性への配慮が強化され、より専門的な立場から個々の状況を丁寧に判断する体制が整えられました。
障害支援区分の役割
障害者へのサービス提供を公平・公正にするために、障害支援区分が設けられました。認定調査や医師の意見書に基づき、客観的な基準によって区分を決定することで、担当者の主観に左右されにくく、より透明性の高いサービス提供を目指しています。この区分により、必要なサービスを適切に提供することが期待されます。
障害福祉の対象者について

障害福祉サービスの対象者は、障害者総合支援法によって決められています。
障害者総合支援法第4条では、障害福祉サービスを受けられる「障害者」を以下のように定義しています。
- 身体障害者(18歳以上)
- 知的障害者(18歳以上)
- 精神障害者(18歳以上)
- 発達障害者(18歳以上)
- 治療法が確立していない疾病その他の特殊な疾病の人(18歳以上)
- 障害児(18歳未満)
*3)
それぞれの内容について詳しく見てみましょう。
身体障害者
身体障害者とは、身体の機能に永続する障害のある人のことで、身体障害者福祉法の第4条で以下のように定められています。
- 視覚障害
- 聴覚または平衡機能の障害
- 音声や言語機能、咀嚼機能の障害
- 肢体不自由
- 政令で定める障害
*4)
これらの障害があると認められると、「身体障害者手帳」が交付されます。
知的障害者
知的障害者も障害福祉サービスの対象となります。厚生労働省は知的障害を
「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」
出典:厚生労働省*5)
と定義しています。
知的障害の判定基準として用いられているのがIQ(知能指数)と日常生活能力です。
【知的障害の程度の基準】

上記の基準は、あくまでも知的障害者の判定基準であり、知的障害者福祉法には知的障害の定義が無いことに注意が必要です。知的障害を有する人が障害福祉サービスを受ける際は、各市町村の窓口に相談し、障害支援区分に該当するかどうか確認しなければなりません。
精神障害者
障害者のうち、精神障害を有している人のことを精神障害者といいます。代表的な精神障害は以下の通りです。
- 統合失調症
- 気分障害
- てんかん
- 依存症
- 高次脳機能障害
*6)
統合失調症の代表的な症状は幻覚や妄想で、自分の悪口やうわさ、指図する声が聞こえる幻聴が知られています。気分障害の顕著な例は、双極性障害(躁うつ病)で気持ちが激しく上下する症状が見られます*6)。
何らかの原因で発作が起きるてんかんや何かに過度の依存をしてしまい、自分の力で止められない依存症、脳にダメージが残ることでさまざまな障害が発生する高次脳機能障害なども精神障害に区分されます*6)。
精神障害者には、症状に応じて「精神障害者保健福祉手帳」が交付されますが、同手帳を持っていなくても障害福祉サービスを受けられます。
発達障害者
発達障害とは、脳機能の発達が関係する障害です*7)。発達障害者支援法の第2条では、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義しています。
出典:e-GOV*8)
代表的な発達障害は、以下の3つです。
【主な発達障害】
| 自閉スペクトラム症 | コミュニケーション障害やパターン化した行動興味・関心の偏りやこだわりアスペルガー症候群も含む*9) |
| 注意欠陥多動性障害(ADHD) | 集中できないじっとしていられない衝動的に行動する |
| 学習障害(LD) | 読む・書く・計算するなどが極端に苦手 |
【発達障害の特性】

上の図を見てわかるように、発達障害は複数の障害が重なることもあれば、障害の程度や年齢、生活環境によっても違いが見られます。障害福祉サービスを受けるには、各市町村の窓口に相談し、障害支援区分に該当するかどうか確認する必要があります。
その他:難病患者と障害児
特定の障害には該当しないものの、治療法が定まっていなかったり、特殊な病気であったりする人(難病患者)は、障害福祉サービスを受けられます。現在、指定難病の数は341です。診断基準など詳しいことは、厚生労働省の「指定難病の概要、診断基準等、臨床調査個人票(告示番号1~341)※令和6年4月1日より適用」でご確認ください。
また、18歳未満で身体障害や知的障害、精神障害、発達障害、難病などを有している場合も障害福祉サービスの対象となります。
障害支援区分の詳細

障害支援区分は、障害のある方が福祉サービスを利用する際の必要度を示す基準です。障害の程度や日常生活での支援の必要性に応じて、1から6までの6段階で判定されます。
たとえば、非該当の場合、受けられるサービスは「同行援護」と「共同生活援助」ですが、区分6の場合は、すべてのサービスが受けられます。
ただし、生活介護や施設入所支援のように年齢を考慮するケースや、療養介護のように区分ごとに規定があるサービスもあります。後ほど詳しく解説します。
障害支援区分の調査項目
障害支援区分の認定調査は、80項目に及びます。
【障害支援区分の認定調査項目】

80項目は5つのカテゴリーに分けられています。
- 移動や動作等に関連する項目(12項目)
- 身の回りの世話や日常生活関連する項目(16項目)
- 意思疎通等に関連する項目(6項目)
- 行動障害に関連する項目(34項目)
- 特別な医療に関する項目(12項目)
これらの項目について、いくつかの段階に認定していきます。さらに、見守りなどの支援も評価対象に加えます。
また、認定調査と並行して医師意見書も取得します。医師意見書とは、障害者の主治医などが、利用申請者の疾病や身体の障害状況、精神の状況などを医学的知見からまとめる書面のことです。認定調査と医師意見書に基づいて、一次判定が行われる仕組みです。
障害支援区分の認定を受けるメリット
障害支援認定を受けるメリットは、適切なサポートが受けられるようになることです。詳しく見ていきましょう。
自立支援給付が受けられる
自立支援給付とは、障害者総合支援法や児童福祉法に基づいて行われる障害者支援のサービスのことです。原則として、国が費用の2分の1を負担します。
【障害者総合支援法の給付・事業の全体像】

主な自立支援給付は以下の通りです。
| 事業名 | 事業内容 |
| 介護給付 | ホームヘルプサービス(居宅介護)や施設入所支援など日常生活をサポートするサービス |
| 訓練等給付 | 障害者が地域で生活するため、適正に応じて受けられる訓練などのサービス機能訓練、生活訓練、就労に関する訓練など |
| 自立支援医療 | 心身の障害を除去・軽減するための医療について、自己負担額を軽減する公費負担医療制度 |
| 相談支援 | 地域移行支援:障害者支援施設や精神科病院、保護施設、矯正施設などを退所して施設を利用する人が対象地域定着支援:単身で単身で生活する障害者などが対象。常時連絡体制を確保して緊急時に必要な支援を行う |
| 補装具 | 障害の状態によって、義肢や車いすなどの補装具の購入や修理のための費用を支給 |
*11)
障害支援区分と給付の関係
自立支援給付の内容は、障害支援区分と密接にかかわっています。
【障害支援区分と給付の関係】

訓練等給付や相談支援については、区分に関わらず利用できるのに対し、介護給付は障害支援区分の段階に応じて支給されるサービスの内容が異なります。
【各サービスと障害支援区分の対応】

たとえば、行動援護であれば障害支援区分が3以上という規定のほかに、認定調査項目の中の「行動関連項目」の合計点数が10点以上という条件が付きます。
障害支援区分の認定手続き
障害支援区分の認定は、どのような手続きで進められるのでしょうか。ここでは、障害支援区分認定の流れや一次判定・二次判定の内容について解説します。
障害支援区分認定の流れ
障害支援区分の認定の流れは、以下の通りです。
【障害支援認定の運用の流れ】

各市町村に障害支援認定の申請が出た場合、市町村は認定調査を実施し医師意見書を取得します。それらの結果に基づき、市町村は判定ソフトを使って一次判定を行います。その後、一次判定の結果を精査・確定するために二次判定が行われます。二次判定終了後に、市町村の障害支援区分が確定し、申請者に通知されるのです。
一次判定
障害支援区分の一次判定は、システムを用いた自動的な処理によって実施されます。具体的には、認定調査で得られた80項目の調査結果と、医師が作成した意見書から選択された項目をコンピューターの判定ソフトウェアに入力することで判定が行われます*9)。
一次判定では、申請者の心身等の状態から必要とされる支援の度合いが数量化されます。これを、過去の認定データと照合して最も確率が高い区分を割り出します*9)。
ここで判明するのは必要なサービスの数量であり、障害の種別や症状をあらわすものではない点に注意が必要です。
二次判定
二次判定は、市町村審査会で行われる判定のことです。
二次判定で行われる内容は、以下の通りです。
- 一次判定の精査や確定
- 認定調査の特記事項や医師意見書の特記事項の勘案
市町村審査会は、一次判定の内容に明らかな矛盾や不整合がある場合は、再調査の実施を決定できます。市町村審査会は、審査判定の最終判断をゆだねられているため、非常に重要な役割を果たしています。
市町村は、市町村審査会での審査結果を踏まえ、申請者に障害支援区分を通知し、自立支援給付を行います。
障害程度区分とSDGs
障害支援区分は、SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」と密接にかかわっています。ここでは、SDGs目標10と障害程度区分のかかわりについてまとめます。
SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」との関わり
SDGs目標10のターゲット10.2では、「2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、すべての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する」として、障害を持っている人々も取り残さず社会を発展させることを目指しています*12)。
2022年段階の障害者の総数は1,164万6千人であり、総人口の約9.3%に相当します。内訳は、身体障害者が423万人、知的障害者が126万8千人、精神障害者が614万8千人となっています*13)。
これほど多くの方々が、日常生活を送る上で様々な困難に直面する障害を抱えています。障害を持った人が社会の一員として充実した日々を送るためには、行政による制度的な支援や、社会全体での理解と協力が欠かせないです。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ
今回は障害支援区分についてまとめました。障害支援区分制度は、障害者への福祉サービス提供を公平かつ適切に行うための重要な仕組みです。認定は詳細な調査項目と医師意見書に基づいて行われ、一次判定と二次判定という二段階のプロセスを経て決定されます。
この制度により、身体障害だけでなく知的障害や精神障害の特性も適切に評価され、必要な支援を受けられるようになりました。SDGsの目標達成にも貢献し、障害者の社会参加と自立を支える基盤となっています。
参考
*1)厚生労働省「障害者総合支援法における「障害支援区分」への見直し」
*2)知恵蔵「障害者総合支援法」
*3)e-GOV法令検索「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律 第四条」
*4)e-GOV法令検索「身体障害者福祉法 第四条」
*5)厚生労働省「知的障害児(者)基本調査:調査の結果」
*6)厚生労働省「精神障害(精神疾患)の特性(代表例)」
*7)政府広報オンライン「発達障害って、なんだろう?」
*8)e-GOV法令検索「発達障害者支援法」
*9)厚生労働省「障害支援区分に係る研修資料≪共通編≫第5版」
*10)厚生労働省「障害者総合支援法における「障害支援区分」への見直し」
*11)厚生労働省「自立支援給付の種類」
*12)スペースシップアース「SDGs10「人や国の不平等をなくそう」の問題や解決策を徹底解説」
*13)厚生労働省「障害者の数」
この記事を書いた人
馬場正裕 ライター
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。