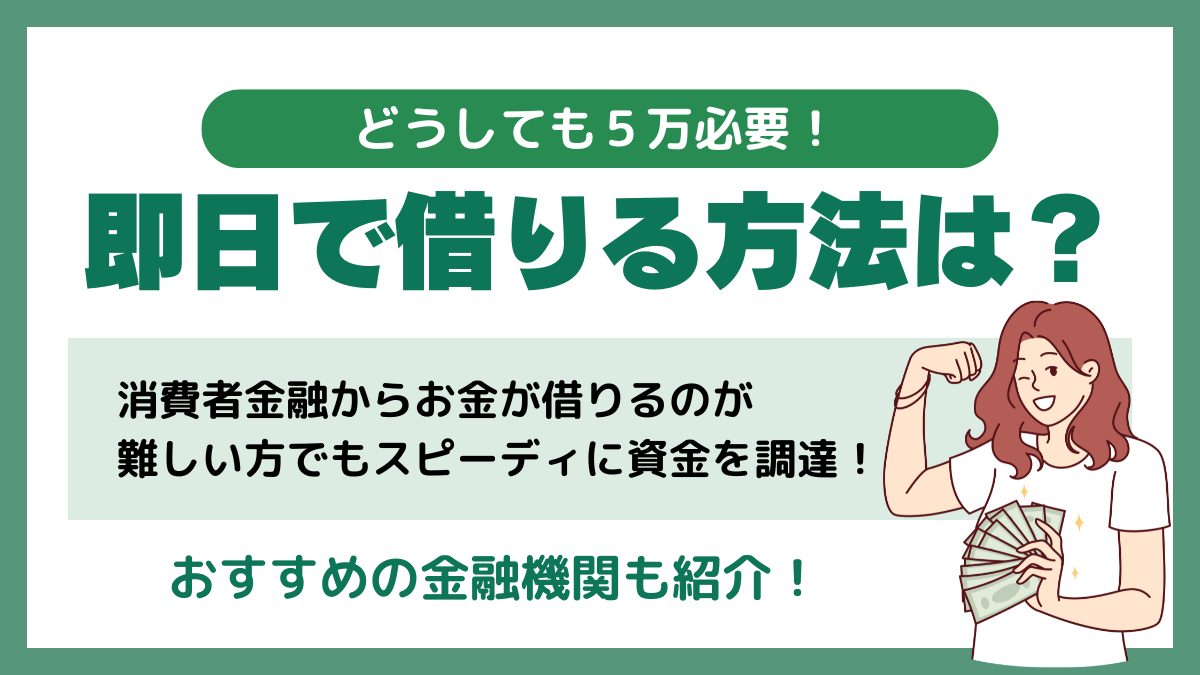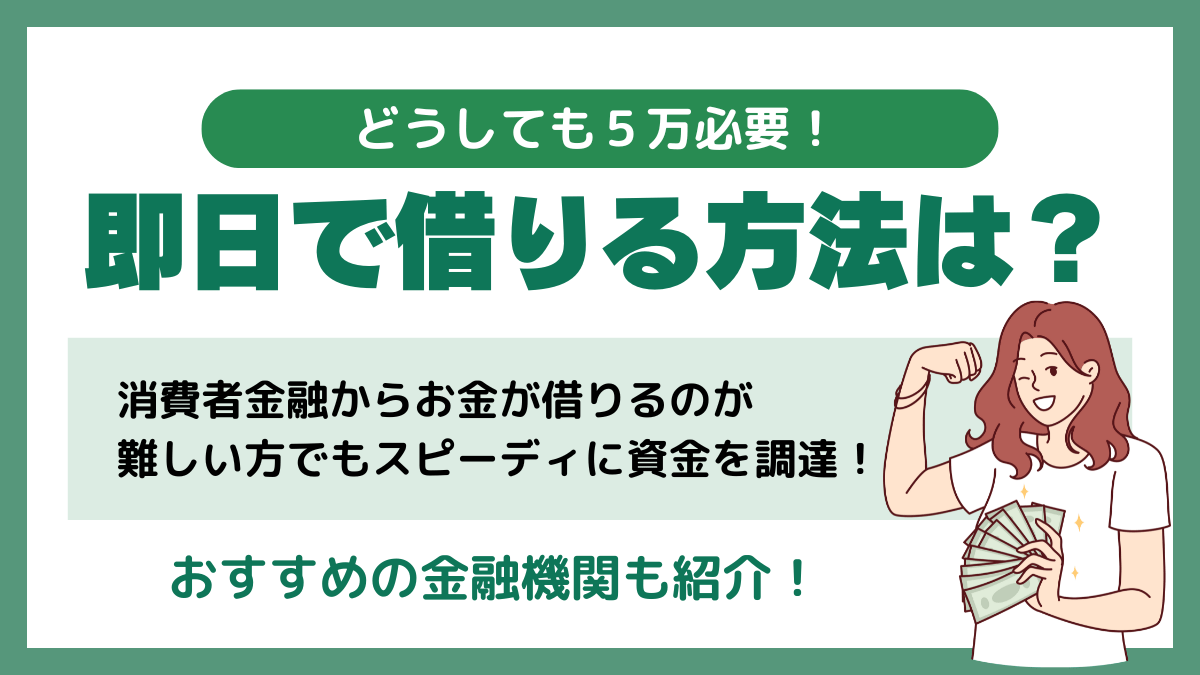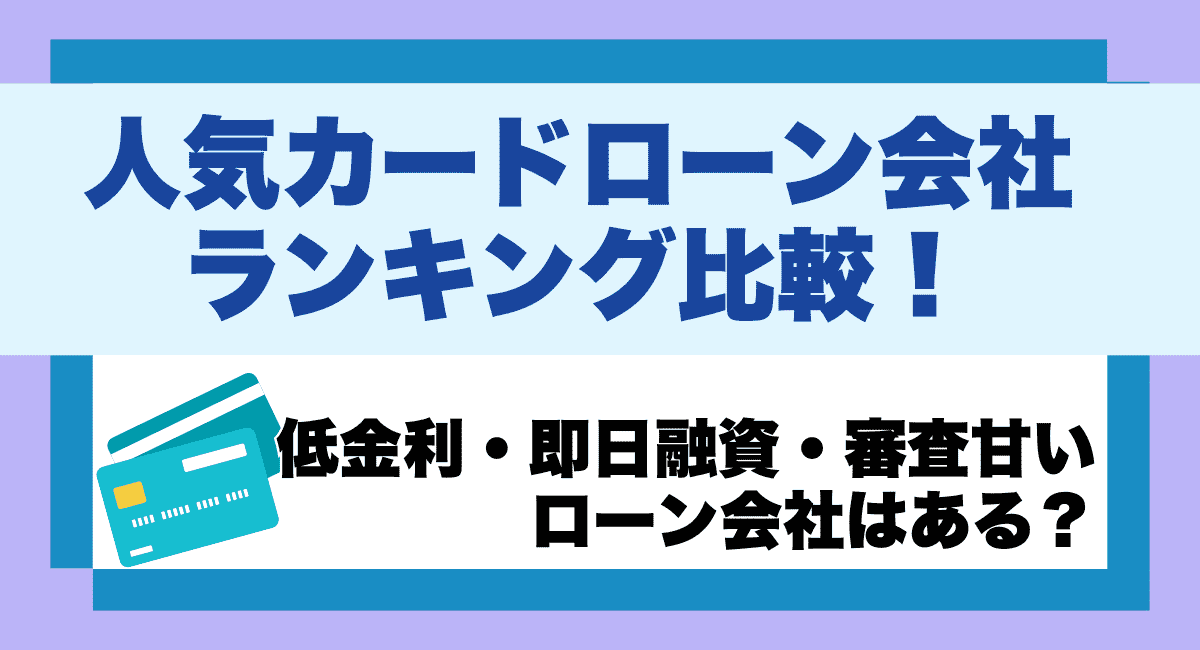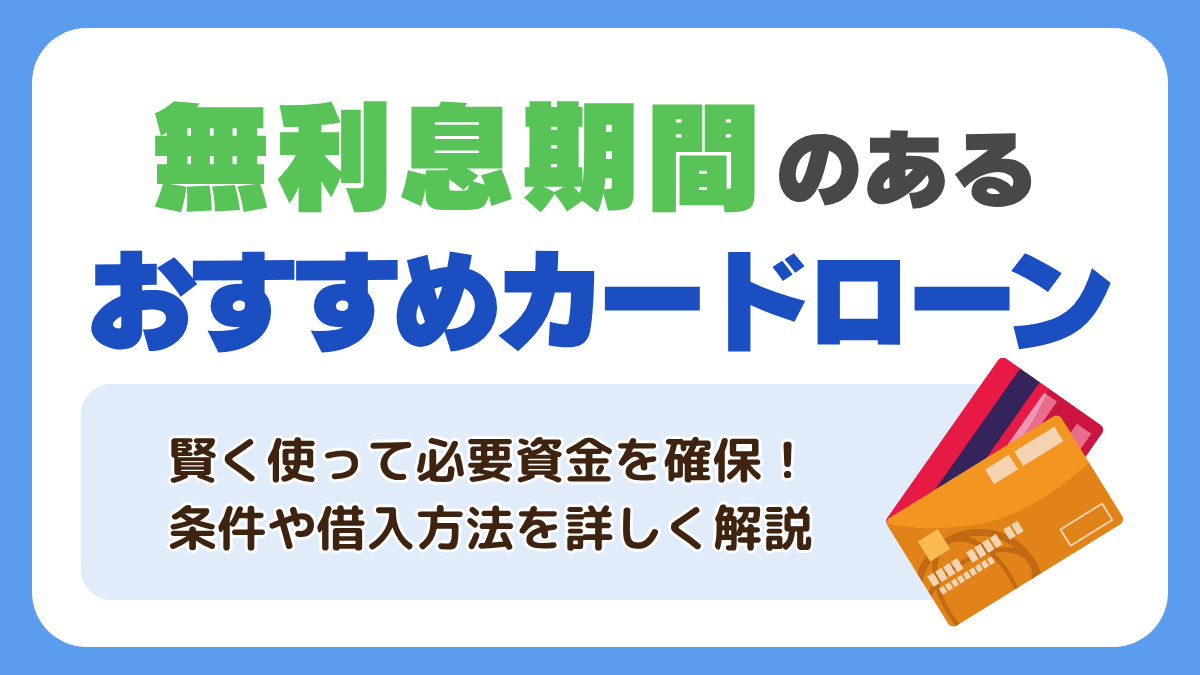モスクワにある赤の広場は、かつてソビエト連邦(ソ連)の中心地として数々の歴史的瞬間を見守ってきました。1917年の十月革命から始まったソビエト連邦は、スターリンの強権的な工業化と大粛清、そして第二次世界大戦での苦難を経験します。
その後、冷戦という新たな国際秩序の中で超大国としての地位を確立するものの、アフガニスタン侵攻による疲弊やペレストロイカの失敗により、1991年に崩壊の道を辿りました。
日本との関係では、中立条約や共同宣言などの外交的変遷もありました。壮大な実験と言われた社会主義国家としての理想と現実のギャップは、現代の社会にも繋がる教訓を私たちに残しています。
本記事では、ソビエト連邦についてわかりやすく解説します。
目次
ソビエト連邦とは

ソビエト連邦とは、1923年から1991年まで存在した社会主義国家です。ユーラシア大陸の広大な地域を支配し、15の共和国からなる多民族国家でした。政治は共産党が一党支配し、経済は国が計画的に管理していました。
冷戦時代には、アメリカと対立して世界の二大勢力の一つとなり、宇宙開発や科学技術で多くの成果を上げました。しかし、経済の行き詰まりなどから最終的に解体し、ロシアなど複数の独立国家が誕生しました。*1)
構成国
ソビエト連邦の構成国は、以下の15カ国です。
- ロシア連邦
- ウクライナ
- 白ロシア
- ウズベク
- カザフ
- グルジア
- アゼルバイジャン
- モルダビア
- リトアニア
- キルギス
- ラトビア
- タジク
- アルメニア
- トルクメン
- エストニア
ユーラシア大陸の東の端から、ヨーロッパの東部に至る広大な地域が、ソビエト連邦としてまとまっていました。
【1917年〜1922年】ソビエト連邦が成立するまで

ソビエト連邦が誕生する前、この地域はロシア帝国としてロマノフ家の皇帝が統治していました。ロマノフ家は約300年間続いた王朝でしたが、その支配が終わることでソビエト連邦が生まれました。
ここでは、ロシア帝国からソビエト連邦への移行において重要な出来事である十月革命について解説します。
十月革命
十月革命は1917年、第一次世界大戦の終わり頃にロシアで起きた革命です。実際には11月に発生しましたが、当時のロシア暦では10月だったため、この名前で呼ばれています。レーニン率いる集団(ボリシェヴィキ)が、臨時政府を倒して権力を握りました。
革命の背景には、戦争による苦しみや貧困があります。十月革命の前に起きた二月革命で、皇帝ニコライ2世は権力を失っていました。しかし、二月革命でできた臨時政府は、人々が望んだ戦争終結をしませんでした。レーニンはこうした民衆の願いに応える形で立ち上がり、首都ペトログラード(現在のサンクトペテルブルク)を制圧したのです。*2)
政権を取ったレーニンらは、戦争をすぐに終わらせる方針や土地を国の所有にするなどの改革を次々と実行しました。
これに対し、レーニンが率いるボリシェビキに反対する勢力は、外国からの援助を得ながら抵抗し続けました。この対立による戦いは「干渉戦争」と呼ばれています。干渉戦争は1922年まで続きましたが、最終的にはレーニン側が勝利を収めました。その結果として、1922年12月30日に「ソビエト社会主義共和国連邦」が正式に樹立されたのです。*3)
【1922年〜1953年】スターリン時代

1922年にレーニンが病気になると、スターリンとトロツキーの間で後継争いが始まりました。争いに勝ったスターリンは、政敵を次々と排除していきましたが、ドイツ軍の侵攻によって苦しい状況になります。
しかし、最終的にドイツとの戦争に勝利したスターリンは、自身を中心とした独裁政治体制を確立しました。スターリン体制の歴史的な流れについて、ここでは整理していきます。
スターリンとトロツキーの権力闘争
1922年、ソ連を創設したロシア革命の指導者レーニンが脳出血で倒れました。その後、レーニンの後を継ぐ立場を求めて、スターリンとトロツキーの間で激しい争いが始まりました。
実は、レーニンは亡くなる前の遺言でスターリンを権力の座から排除するよう指示していたのですが、これは実行されませんでした。結果として、スターリンが権力争いに勝ち、ソ連の新たな指導者となりました。
大粛清
大粛清とは、1930年代にソ連でスターリンによって行われた大規模な弾圧のことです。スターリンに反対する人々を「人民の敵」というレッテルを貼って、次々と逮捕や処刑を行いました。最初は反対派を狙っていましたが、やがてスターリンの側近たちも標的になり、政府の高官や軍の幹部も多数処刑されました。
例えば、ソ連軍のトップリーダーだったトハチェフスキーも犠牲になりました。この大粛清では約157万人が逮捕され、そのうち68万人が命を奪われたと言われています。スターリンが自分の権力を守るために恐怖政治を行ったのです。*6)
独ソ戦とスターリン体制の確立
第二次世界大戦が本格化する前、ドイツとソ連は互いに攻撃しないという約束(独ソ不可侵条約)を交わしていました。しかし、1941年6月、ヒトラー率いるナチス政権はこの条約を破り、突如ソ連領土へ軍隊を送りました。不意を突かれたソ連は初め大混乱に陥り、ドイツ軍は首都モスクワまであと少しという場所まで進軍しました。
苦境に立たされたソ連側は、モスクワや重要な都市レニングラードを何としても守り抜き、態勢を立て直します。1942年8月、南部の工業都市スターリングラードでの激しい市街戦でソ連軍が勝利すると、戦いの流れが変わりました。最終的にソ連はドイツに勝利しましたが、死者は軍人・民間人を合わせ約2,700万人に及びました。*7)
第二次世界大戦に勝利したスターリンは、独裁体制を強化しました。この体制を「スターリン体制」といいます。スターリン体制は、彼が1953年に亡くなるまで続きました。
【1953年〜1985年】フルシチョフの登場とその後
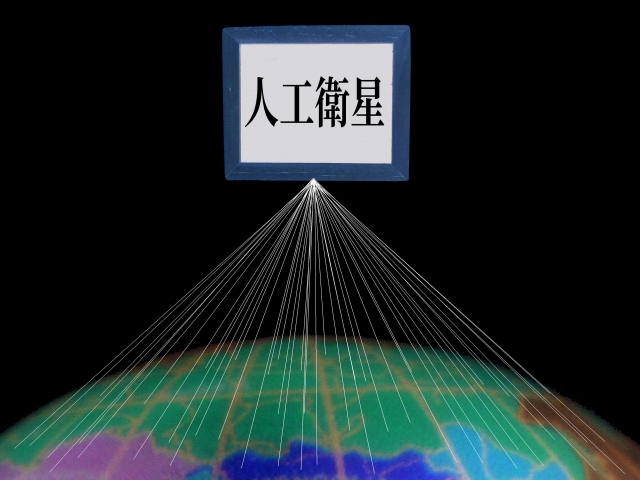
スターリンの死後、ソ連はマレンコフ首相やフルシチョフ共産党第一書記らによる集団指導体制に移行しました。その後、実権を握ったのはフルシチョフです。ここでは、フルシチョフのスターリン批判と、フルシチョフ以後のソ連の政治について解説します。
スターリン批判
スターリン批判は、1956年2月、ソ連共産党の重要な会議で行われた出来事です。フルシチョフ第一書記が、亡くなった前指導者スターリンの問題点を厳しく指摘しました。
発表の中でフルシチョフは、スターリンが自分を神のように崇めさせ、多くの市民の権利を奪い、疑い深い性格から無実の人々を大勢処刑したことを明らかにしました。また、独ソ戦でも警告を無視するなど、国に大きな損害を与えた判断ミスがあったと説明しました。
発表は公式には公開されませんでしたが、アメリカによって世界中に広められ、大きな衝撃を与えました。スターリン批判をきっかけに、ポーランドやハンガリーでは抗議活動が起こり、中国はソ連との関係が悪化したのです。*9)
その後、1958年から首相を兼任したフルシチョフは、訪米してアイゼンハワー大統領と会談するなど、米ソ共存路線を推進しましたが、1964年に失脚してしまいます。
長期にわたる停滞の時代
1964年にフルシチョフが失脚した後、ブレジネフがソ連の指導者となりました。彼の政権期は約18年間続き、「安定と停滞の時代」と呼ばれています。
ブレジネフ時代は、政治的には大きな混乱がなく安定していましたが、経済発展の面では問題が多く見られました。アメリカを中心とする西側諸国との軍備競争に多くの資金を使い、一般国民の生活向上には十分な予算が回りませんでした。
国内では共産党の権力が強まり、政府批判をする人々は取り締まられました。自由な意見表明ができない社会の雰囲気が広がり、多くの知識人や芸術家が国外に逃れました。
また、官僚による硬直した管理体制により、新しい考えや改革が進まず、国全体が古い体制のまま時間だけが過ぎていくという状況でした。この時期の問題が後にゴルバチョフの改革につながることになります。
ソビエト連邦の崩壊理由
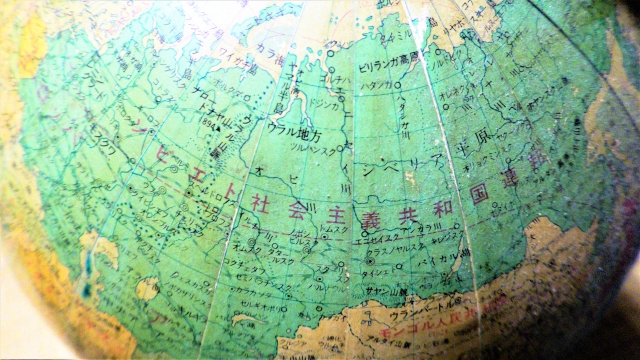
ブレジネフ政権以後、ソ連は長期にわたって停滞した状態でした。しかし、アフガニスタンからの撤退やペレストロイカの失敗により、ソ連は急速に崩壊していきます。
アフガニスタン侵攻で疲弊
1979年、当時の超大国ソ連はアフガニスタンに軍隊を送り込みました。この行動は友好的な政府を守るためでしたが、結果的に大きな代償を払うことになります。
現地では強い抵抗運動が発生し、アメリカをはじめとする西側諸国がこれら反対派に資金や武器を提供しました。長引く戦闘により、ソ連軍は予想以上の被害を受け、多くの兵士が命を落としました。
また、この軍事行動は国家予算に大きな負担をかけました。軍事費が膨らむ一方で、国内の生活必需品は不足し、市民の不満が高まっていきました。
さらに国際社会からの批判も強まり、ソ連の世界的な評判は大きく損なわれました。西側との緊張関係も深刻化し、冷戦がさらに激化する原因となったのです。
1989年にソ連軍が撤退する頃には、この侵攻は明らかな失敗と認識されました。そして、政治的混乱や経済困難とあいまって、わずか数年後のソ連崩壊につながる要因の一つとなりました。*9)
ペレストロイカの失敗
1985年、山積する諸問題の解決を託されたのがゴルバチョフです。ゴルバチョフはペレストロイカでソ連を立て直そうとしました。
ペレストロイカとは、1980年代後半にソビエト連邦(旧ソ連)で行われた大規模な改革のことです。1985年に当時52歳だったミハイル・ゴルバチョフが指導者になり、国の仕組みを変えようと始めた取り組みです。
ゴルバチョフは、情報公開を意味する「グラスノスチ」という方針を掲げ、国内の問題点を明らかにしながら社会の立て直しを図りました。また、海外との関係も改善しようとしました。
しかし、経済の立て直しは思うように進まず、政治面での変革が先に進みました。1989年には自由な選挙が実現し、翌年にはゴルバチョフが大統領になりました。
民主的な改革が進むにつれて、共産党の力が弱まり、経済は混乱し、各地域が独立を求める動きが強まりました。ゴルバチョフは様々な対策を試みましたが、1991年に保守派による政権奪取の試みが起こり、これによって改革の試みは終わりを迎えました。*11)
ソビエト連邦と日本の関係

日本とソ連の関係は、大きく変化をし続けてきました。ここでは、戦前と戦後に分けて日ソ関係を整理します。
戦前の日ソ関係
戦前の日本とソ連の間柄は、複雑かつ緊張に満ちたものでした。明治時代の日露戦争後、両国の状況はいったん落ち着きましたが、1917年のロシア革命を機に再び対立が深まります。その後、日本は革命反対派を助けるためシベリアへ軍隊を送り込みました。この状態は1925年の日ソ基本条約締結まで続きます。
1930年代に入ると、満州(現在の中国東北部)をめぐる利害衝突が激化し、1939年にはノモンハンという場所で大規模な軍事衝突が発生し、大日本帝国は大きな打撃を受けました。
1941年には両国間で日ソ中立条約が結ばれ、一時的に関係改善が見られましたが、第二次世界大戦末期の1945年8月、ソ連はこの約束を破り、旧満州地域や千島列島などへ侵攻しました。この行動が現在まで続く領土問題の原点となっています。*12)
戦後の日ソ関係
第二次世界大戦後、日本とソ連の関係は複雑な道をたどりました。戦争終結直前にソ連が日ソ中立条約を破棄して参戦し、多くの日本人が北方地域で捕らえられて労働を強いられました(強制労働)。この問題は両国の信頼関係に大きな傷を残しています。
冷戦時代、日本はアメリカ側に立ち、ソ連との距離が広がりました。1951年のサンフランシスコ平和条約にソ連は署名せず、1956年に国交は回復(日ソ共同宣言)したものの、北方領土問題は解決しませんでした。
経済面では限られた交流があったものの、政治的な緊張関係が続きました。1970年代に一時的に関係改善の兆しがありましたが、アフガニスタンへの軍事介入によって再び悪化しています。
ゴルバチョフ政権のペレストロイカによって1980年代後半には対話が進みましたが、ソ連崩壊後もロシアとの間で、領土問題は未解決のまま今日に至っています。*12)
ソビエト連邦とSDGs
ソビエト連邦が歴史に登場したころ、SDGsという考えは存在しませんでした。SDGsが登場するのはソ連崩壊後の2015年だからです。しかし、ソ連が掲げた社会主義とSDGsには共通する部分も見られます。ここでは、ソビエト連邦とSDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」との関わりについて解説します。
SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」
ソ連の社会主義とSDGsは、不公平な状況の解消を重視する点で共通しています。社会主義はロシア革命後、皇帝や貴族などの特権層の権力を排除し、平等な共同体を目指しました。現代のSDGsも世界の経済的・政治的な不均衡を改善しようとする取り組みです。
しかし、両者には重要な違いがあります。ソ連では国家と党による管理が強化され、個人の権利が制約されていました。対照的に、SDGsは各国の多様な制度を認めながら国際的な協力を通じて目標達成を図ります。
また、SDGsは環境保全や教育機会の拡大など、幅広い課題に取り組む包括的な枠組みである点も異なります。民主主義や個人の尊厳を大切にしながら、誰も取り残さない発展を追求するアプローチは、過去の社会主義とは異なる道筋を示しています。
まとめ
今回は、ソビエト連邦(ソ連)についてまとめました。ソビエト連邦は1923年から1991年まで存在した社会主義国家です。1917年の十月革命をきっかけに誕生し、レーニンの指導の下で国家の基礎が作られました。
その後、スターリンが実権を握り、急速な工業化を進める一方で大粛清という恐怖政治を行いました。第二次世界大戦ではドイツとの激しい戦いの末に勝利し、冷戦時代にはアメリカと対立する超大国となりました。
しかし、経済の行き詰まりやアフガニスタン侵攻の失敗、そしてゴルバチョフのペレストロイカ政策が思うように進まなかったことで、1991年に崩壊しました。
日本とは北方領土問題を抱えながらも、共同宣言などで関係改善を図りました。社会主義国家としての理想と現実のギャップは、現代社会にも重要な教訓を残しています。
参考
*1)精選版 日本国語大辞典「ソビエト社会主義共和国連邦」
*2)百科事典 マイペディア「十月革命」
*3)日本大百科全書(ニッポニカ)「干渉戦争」
*4)山川 世界史小辞典 改定新版「スターリン」
*5)山川 世界史小辞典 改定新版「トロツキー」
*6)山川 世界史小辞典 改定新版「大粛清」
*7)共同通信ニュース用語解説「独ソ戦」
*8)ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「スターリン批判」
*9)共同通信ニュース用語解説「ソ連のアフガン侵攻」
*10)デジタル大辞泉「ゴルバチョフ」
*11)山川 世界史小辞典 改定新版「ペレストロイカ」
*12)日本大百科全書(ニッポニカ)「日ロ関係」
この記事を書いた人
馬場正裕 ライター
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。