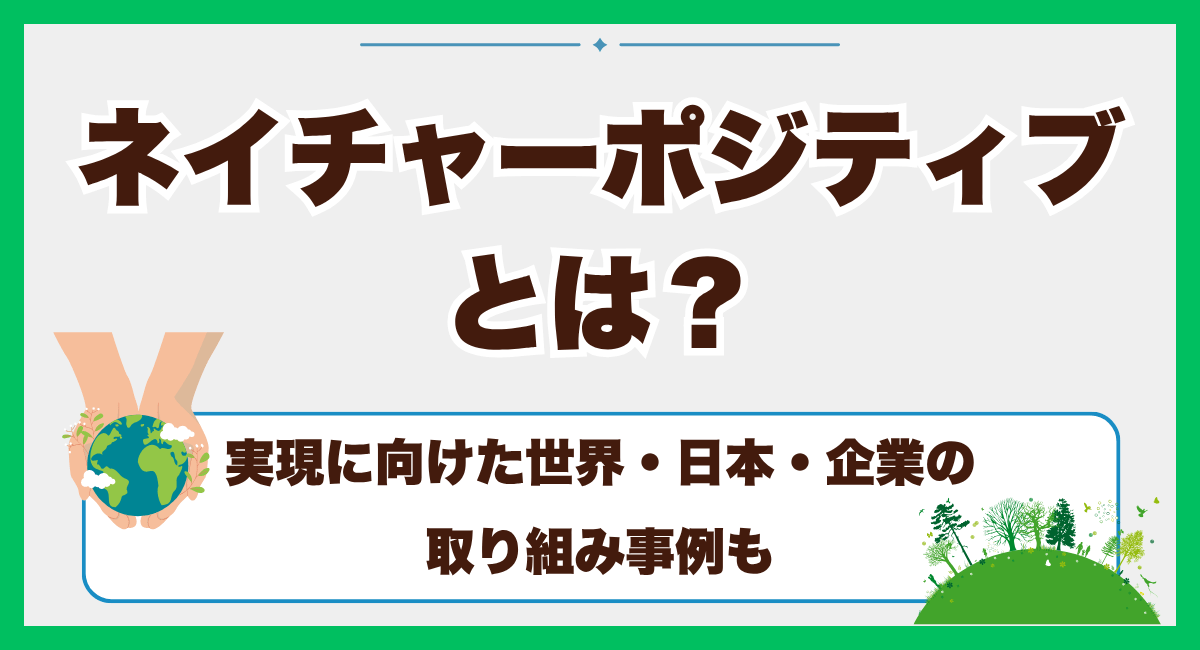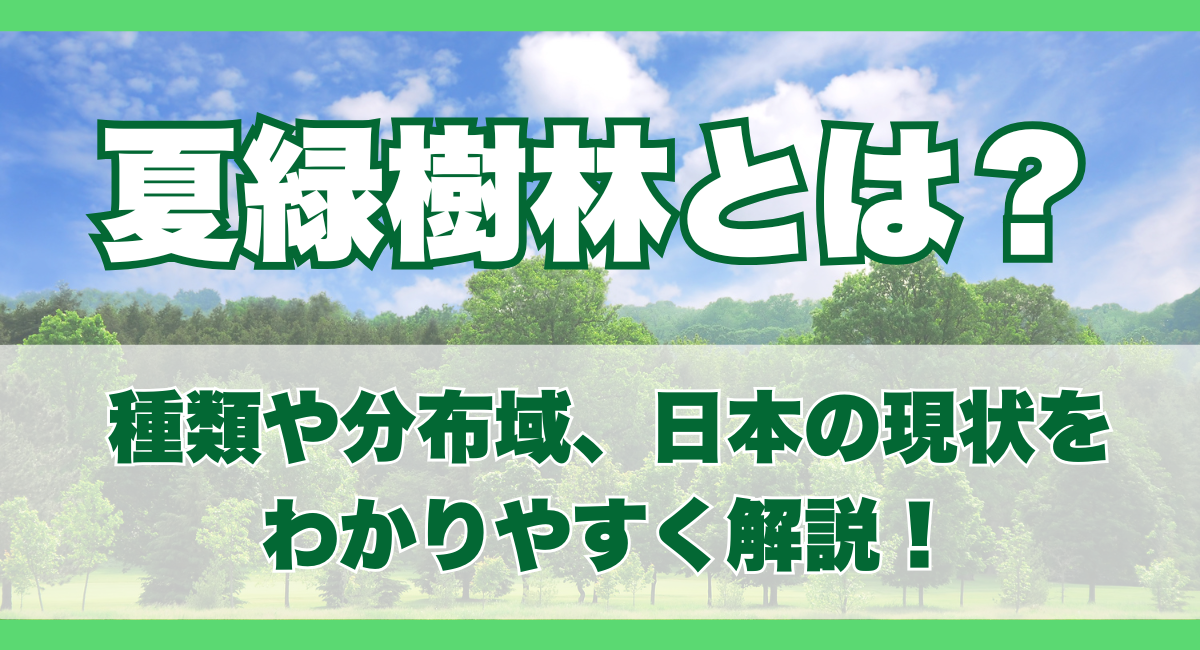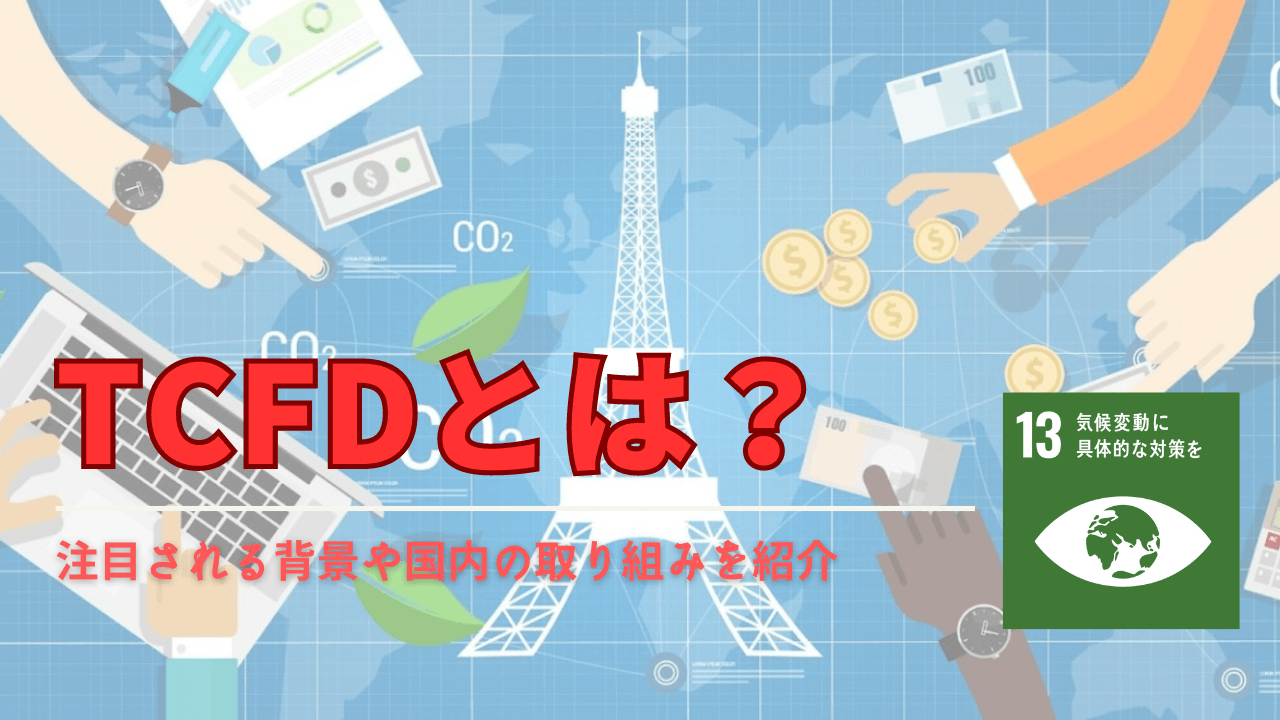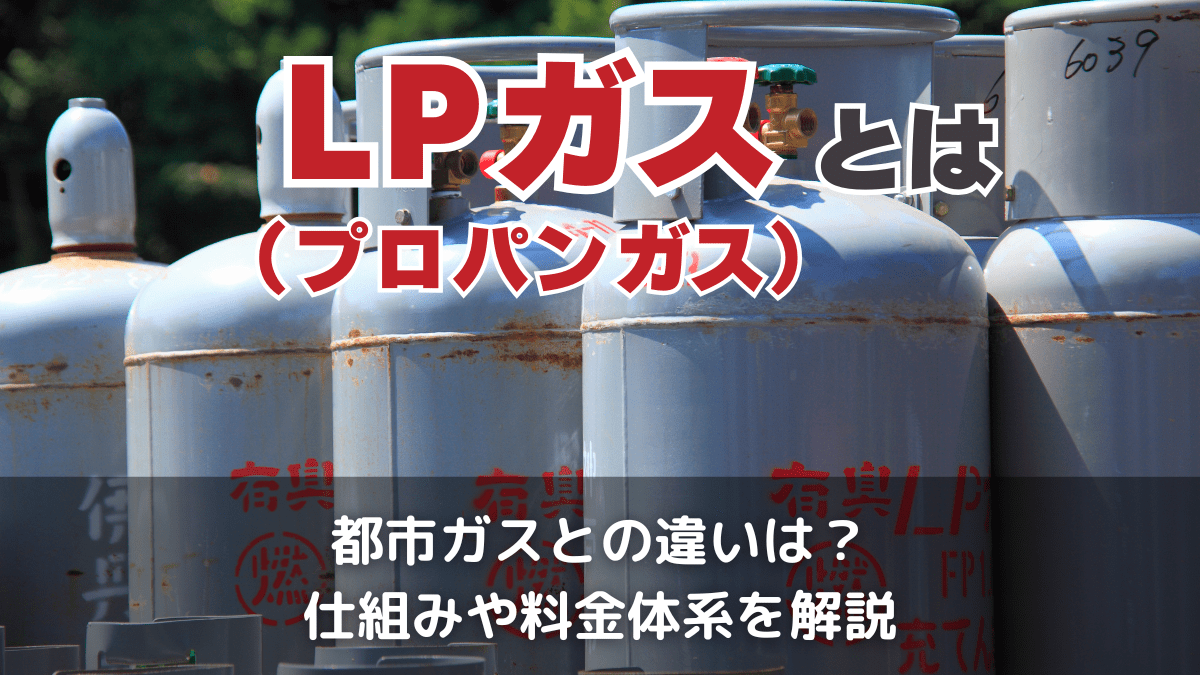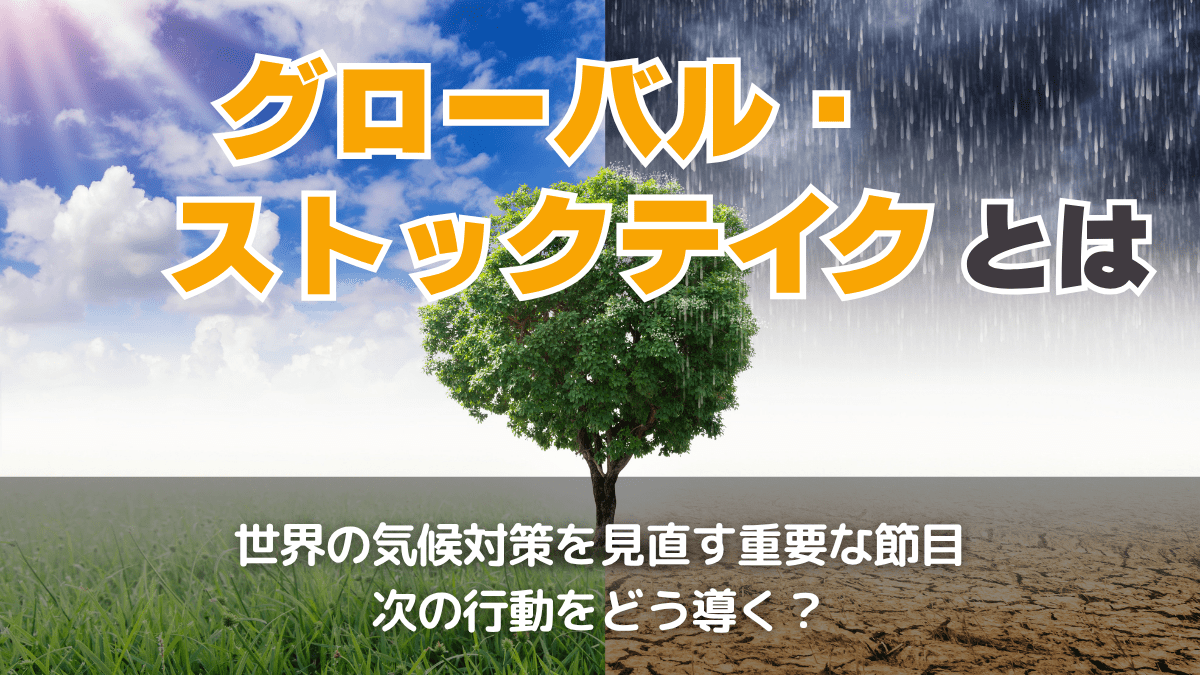スウェーデンやデンマークの北欧諸国は、世界の中で最も自転車道の整備が進んでいる国のひとつです。
スウェーデンでは1970年代に入ってから、歩道と自転車道の整備がはじめられました。そして現在スウェーデン環境保護庁は、2025年をめどに自転車をはじめとするバスや電車などの公共交通機関、つまり自家用車以外の移動手段の割合を25%増やすことを国家目標としています。
それは気候変動の被害を可能な限り食い止めるためのアプローチであり、脱炭素社会への挑戦でもあります。一般的なスウェーデン人は環境への関心が高く、また、健康意識も高い傾向にあります。積極的に自転車に乗ることは、そのどちらもを叶える理想的な選択なのです。
スウェーデン政府が国をあげて各都市部に建設中の自転車道、そしてスーパー自転車道といわれる専用道路建設についてご紹介していきます。
目次
自転車の増える理由、自転車を増やす理由

2020年のパンデミックの年に、スウェーデンでは自転車人口が急激に増加しました。当時を振り返ってみると、バスなど公共交通機関を積極的に使う市民の数は、ほぼありませんでした。いつもバスの中は、空っぽだったのです。
実に、公共交通機関の利用は42%も落ち込みました。それに伴い急激に増えたのが自転車人口です。もともとサイクリングロードの発達しているスウェーデンでは、10〜15km圏内は通勤や通学に自転車を使う人も少なくありません。
ほかにも、さまざまな原因や政策などがあり、自転車人口の増える理由となっています。
①持続可能な交通手段である
環境問題が大きく取り沙汰される昨今、持続可能な交通手段は、気候危機に対抗する上で外すことのできない、絶対に重要な部分です。
②気候危機に対処できる
自転車を積極的に利用することは、ガソリンを使って走る自動車にくらべて、二酸化炭素の排出量を格段に減らせます。
③地形が自転車利用に適している
土地が広大なスウェーデンですが、おもに都市部や南部には平坦な土地が多いのが特徴です。これは、デンマークにもいえることですが、土地自体が平らな場所が多いため、体力的に自転車利用が苦にならないのは大きなメリットです。
④サイクリングロードが発達している
街中の至るところに張り巡らされるように、発達している都市部のサイクリングロード。主要道路を除いて信号も少なく、走りやすいのが特徴です。バスを待つ時間や、信号に引っかかる時間などを考えると時間の短縮にもなり、ストレスが軽減します。
自転車を使いたくなる理由、自転車人口を増やす対策

政府の発表によると、自転車人口増加の可能性がもっとも高いのが、都市部です。つまり、より自転車で走りやすい町づくりや、インフラを整えるのはとても重要だと考えられます。より多くの人に自転車を使ってもらうことが、環境を考える上でも理想的なのです。
車が使いにくい社会
移動手段を考えた場合に、自家用車はとても便利です。多くの荷物を運んだり、家族の人数が多い場合にも必要ですね。
スウェーデンだけでなく欧州全体の傾向ですが、車の所持や利用を減少させるために、さまざまな対策が取られていることがわかります。
たとえば、スウェーデンの隣国・デンマークでは車の税金が高く、180%です。
都市部に暮らす場合、駐車場代金も頭を悩ます問題です。戸建てやアパートの場合、敷地内や契約駐車場が使えますが、圧倒的に数が足りません。そのため、路駐を余儀なくされます。路駐の場合、住民とそうでない人で駐車代金が異なります。
コペンハーゲン市内では、以前は土日の路駐は基本的には無料でしたが、現在は法が変更になっています。そのなかで、EV車だけは恩恵があり、駐車はいつでも無料です。EVに買い替えた人が「駐車場代がかからないのが一番よいところ」というのも頷けます。
また、ディーゼル車はほかのガソリンと比べてガソリン代が非常に割高です。ディーゼル車の場合、旧市街など場所によっては立ち入りのできない区域さえあります。
(※市内の駐車ルールや金額は場所によって異なります。また、スウェーデン人がデンマークで駐車違反をした場合にも、国をまたいで請求書が届きますので、注意が必要です。)
そのほかにも、万一事故が起こった場合、歩道や自転車道での接触事故は車側の過失になります。信号のない歩道の多いスウェーデンですが、横断歩道や環状交差点(ラウンドアバウト)の侵入時に車は停車(または徐行)が原則。これは、教習所でも厳しく習います。
ガソリンスタンドの出入り口や駐車場から車道に出るとき、車道の手前に自転車道がある場合が多いので、このようなデザインの道路ではとくに注意が必要です。人や自転車と接触した場合には、100%車側の過失となります。
自転車を利用しやすいインフラ整備

出典:Spaceship Earth
ここ数年の間に増え続けている自転車人口。政府や自治体ごとの政策もあり、新たに自転車道が作られたり、今まで専用レーンのなかった道路にも、自転車レーンが設置されたりしています。
通勤や通学のために、人と自転車だけの専用高架橋が誕生したエリアもあります。また、新しく設置された自転車専用レーンが、従来の自動車道よりも広くなっているエリアすらもあるのです。
メンタルデザイン的には、自転車レーンが増えると、それを日常的に目にする機会の多い人々が、自転車利用を不便と感じづらくなってくるという考え方もあります。
また、実際に自転車を利用してみると、車道と完全に分離された自転車レーンは交通量の面からも移動がしやすいことがわかります。信号も少ないので、自動車よりも早く目的地へ到着できます。
健康管理やメンタルヘルスに与える影響

スウェーデン人はもともと、健康意識の高い国民であることも無視できません。積極的に野菜や果物を摂取し、体を動かすのが大好きです。
自治体で「15km圏内は自転車通勤を奨励」と謳っている町もあります。能動的に体を動かすことが健康管理に役立ち、リフレッシュできることは周知の事実です。
運動で得られる健康的なマインドは、1日自転車に乗ったからといってすぐに実感できるものではありません。けれども、毎日運動を続けることで、自然とストレスがたまりにくくなったり、体が丈夫になったりするのを実感できる人は多いでしょう。
自転車助成金の存在
たとえば雇用主が自転車を購入し、期間限定(この場合、雇用期間中)で従業員に対し、レンタルやローン・リースという形で自転車を提供します。福利厚生の一環として提供でき、自転車助成金(Cykelförmån)の対象として扱われます。
免税対象は自転車本体(施錠のためのロック・ライト・冬用タイヤなど周辺機器を含む)のみですが、ペタル式の自転車でも、電動式の自転車でも種類に関係なく適用されます。
実際、スウェーデンの多くの雇用主が従業員に対して自転車をリースしています。なかには、入社すると自転車を1台与えてくれる企業もあるほどです。ただし、従業員が正味給与から自転車代金を天引きされる場合には、助成額は減額されます。
公共交通手段を利用しやすい工夫
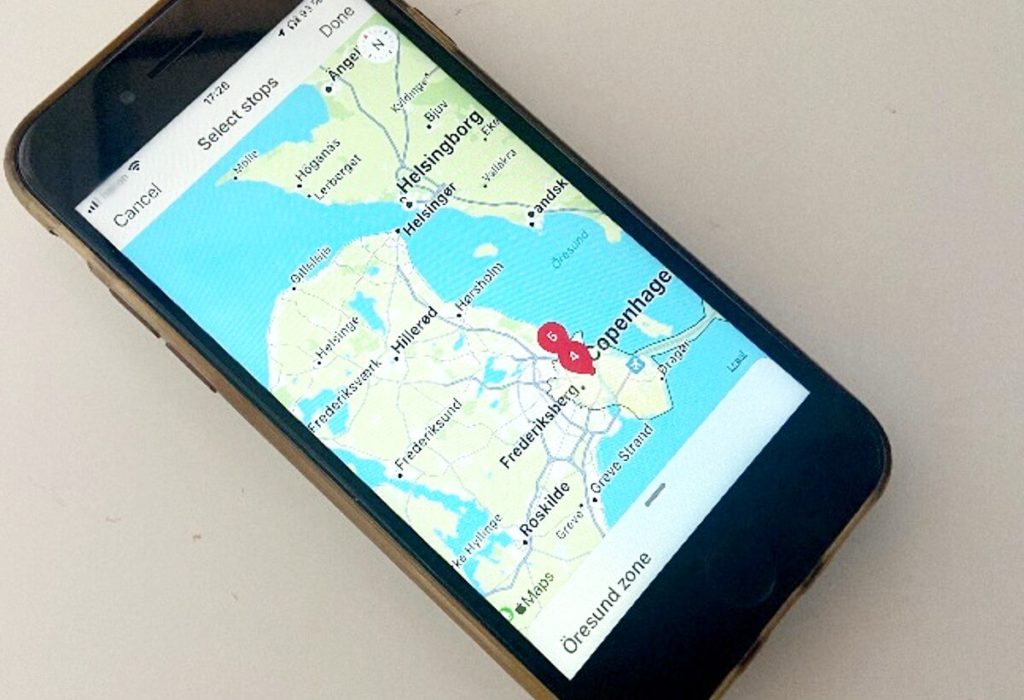
自転車を利用する以外にも、実は公共交通手段が手軽で使いやすい工夫もされています。現在では都市部の多くで、市バスはバイオマスエネルギーで走っているため、環境に優しい移動手段のひとつと考えられています。
①携帯アプリの発達
バスや電車などの公共交通機関は、チケットを事前にアプリで購入できます。時刻表も随時更新されていて、遅れがある場合にも簡単にほかのルートを検索できます。もちろん、駅の券売機でも購入可能です。
アプリを利用すると、2人目からの代金が20%オフになるなどサービスもあります。交通費を大幅に節約できるので、家族や友人同士の利用が増えます。
②5km以上離れている場合通学にバスカードが支給される
学生限定のサービスにはなりますが、自宅から学校までの距離が5km以上離れている場合には、通学のためのバスカードが支給されます。
③デンマークとスウェーデン両国間で同じ切符が利用できる
隣国デンマークへ行く場合など、国をまたぐ旅程の場合にも、同じ切符の利用が可能です。北欧諸国は全部通貨が異なりますが、自分の国の通貨で購入できるのが利点ですね。往復の切符を買えば、指定ゾーン内では24時間公共交通機関が乗り放題なので、移動の際も便利です。
自転車専用高速レーン(スーパーサイクルロード)の整備

出典:Spaceship Earth
新興の密集都市部では、自転車での移動手段は、今後ますます重要な役割を担うことになり得ます。環境に優しく、都市と都市・都心と地方を密接につなぎ、更に周辺の街を結ぶ通勤ルートの確保は、人々の最大の関心ごとともいえます。
いまスウェーデンの都市部では、その構想を叶えるための「スーパーサイクルロード」の建設が進んでいます。
スーパーサイクルロードとは?

出典:Spaceship Earth
都市が地方自治体やスウェーデン運輸省と協力して、今までの自転車道を通勤や通学に適した自転車道へアップグレードする動きです。実際に近年では車道の範囲が狭められ、代わりに自転車道が広くなった道路を見つけられます。
具体的な構想は、ルート全体に一貫性があるのが特徴です。まず安全性を重視し、好アクセスであり、道路を設置しやすい場所につくるだけではなく、主要道路を確実に結ぶ役割も必要です。
スーパーサイクルロードは自転車が走るのに十分なスペースがあり、対向車の追い越しなどによって妨げられたり、安全を脅かされたりすることがありません。
スーパーサイクルロード建設の背景

市の交通およびモビリティ計画によると、自転車による移動の割合は、遅くとも2030年までに少なくとも30%に増加する必要があるといわれています。2023年現在の数値は26%で、わずかに及びません。
今後も引き続き予想される継続的な人口増加と相まって、サイクリング人口の増加により、とくに都市部の自転車道はますます混雑することが予想されます。
スーパーサイクルロードの開発の目的は、サイクルネットワークのより高い基準を通じて、多くの人々が快適に利用できるようにすることです。多くの人々が移動手段に自転車を選択するための条件や、自転車を利用したいと思えるだけの魅力的なまちづくりは必須です。
スコーネ地方最初のスーパーサイクルロードは、C11と名付けられたルートで、マルメ市と近郊のロンマを結ぶルートです。2024年には全体のルートが完成する予定となっています。
スーパーサイクルロードの利点

出典:Spaceship Earth
都市部では市内の移動には自転車を使う割合が高くても、都市部と郊外の街の移動には自動車や交通機関を利用する割合が増えるのは、どこの国でも同じでしょう。
自治体の目標は、自転車人口をさらに増やして、車を選ぶ人を減らすことです。そのために、自転車道は街を移動するすべての人にとって、より安全である必要性があります。
すべての人というのは、サイクリストだけではなく自動車愛用者や、歩行者全てということです。スーパーサイクルロードの建設のために、道幅の狭くなった車道はたしかにあります。しかし、車道とサイクリングロード、そして歩道とは明確に分離する必要があります。
スーパーサイクルロードは一方通行の場合2.5m、2車線の場合は3.5mほどの広さが取られています。広い自転車レーンがあることで、多くのサイクリストが利用できます。それだけでなく、状況に関係なく自分のペースで運転するためにも、広いスペースの確保は理にかなっています。
たとえば、自転車道と自動車道が分離されることにより、対自動車接触事故が減る可能性があります。サイクリストが歩道をわたらないということは、歩行者がより安全であり、安心して日常生活を送れるということです。
しかし一方で、自転車専用道路ができることで、通常よりも大幅にスピードを出すサイクリストが出てくる可能性も挙げられます。実際にスウェーデンやデンマークでは、自転車の事故発生件数は多く、身近で何度も耳にしたことがあります。
現在スウェーデンのヘルメット着用義務は15歳までですが、大人のヘルメットやホーヴディング(Hövding)着用率は日本よりも高いと感じます。実際に事故にあった方で、ドクターから「ヘルメットがなかったら死んでいたよ」といわれた人もいます。
自転車専用道路の拡大にともなって、ヘルメットの義務化や交通ルールの整備など、新たな問題点も出てくるかもしれません。
スウェーデンの自治体は今後、自転車専用道路に対して、さらに強力な投資を行う予定です。
まとめ

多くの国民が自転車を利用したいと思う前段階として、当然ですがそれなりの問題点もあります。
たとえば、南スコーネ地方に暮らす住民が通勤や通学手段に自転車を選択した場合、約半数が30分以内に仕事場や学校に到着できます。それにも関わらず、実際に自転車を選択する住人は10%〜40%ほどと都市によって大きく差が出ています。
南スウェーデンの多くの地域は平らで、自転車での移動には向いています。しかし、冬場には風がとても強くなるという特徴もあります。また、冬になると寒さのため、自転車人口も減少します。スウェーデン全土で考えると、必ずしも自転車が一番の移動手段とはいえません。
しかしながら個人的な感想では、自転車を利用するようになって、実際には移動に関してのストレスは大幅に減ったといえます。
スウェーデンはバスのルートが発達してはいますが、毎日頻繁に遅れるのも普通です。急いでいるときや夜遅くなってしまったとき、冬場の寒さの中で、いつ来るかわからないバスを待つ時間は本当に苦痛です。自転車での移動は、それらの多くの問題を解決してくれます。
スウェーデンの都市部では、今後さらに人口増加が加速すると考えられています。スーパーサイクルロードの建設で、以前と比べて明らかに自転車移動が楽になった実感があります。
スウェーデンに暮らす人が、必ずしも環境のことだけを考えて生きているわけではありません。スウェーデン人のすべてが、環境問題のために自転車利用にシフトチェンジするようになるとは思いません。
しかし自転車道の発達により、少なくとも「バスより自転車のほうが楽」という考えに変わる可能性は否定できません。無理のない範囲の自分のための選択が、結果的に環境にも優しく、健康のためにもなるのだったら、ある意味ベストだといえるのではないでしょうか。
この記事を書いた人
スペースシップアース編集部 ライター
スペースシップアース編集部です!
スペースシップアース編集部です!