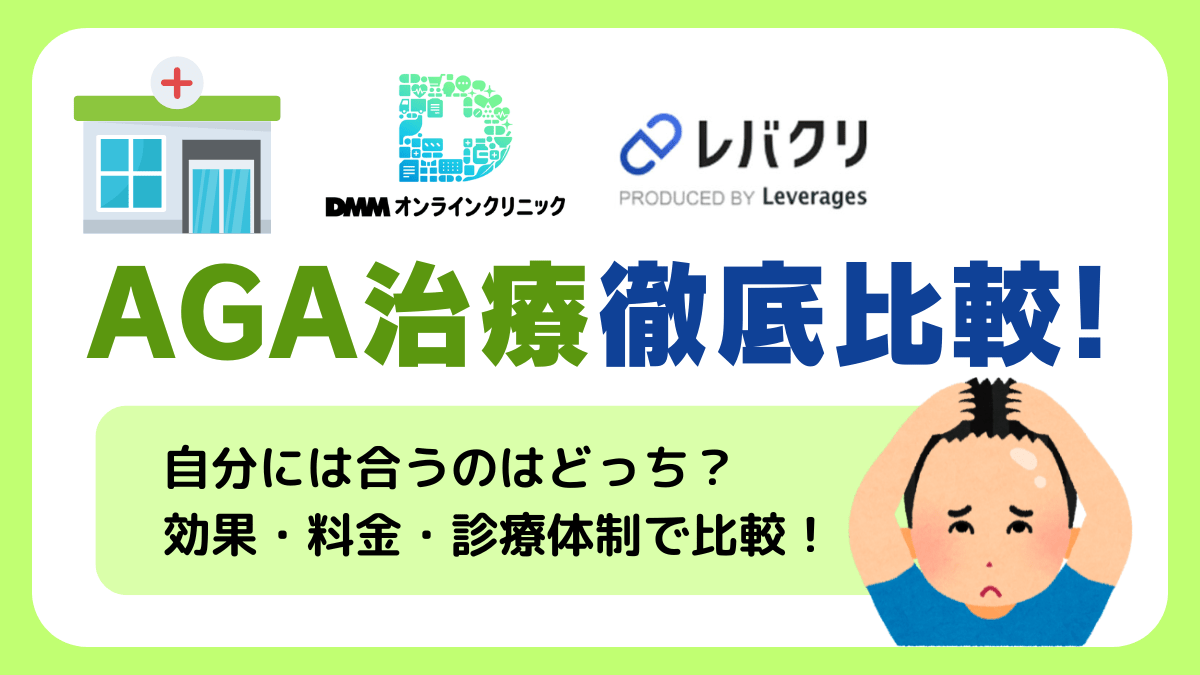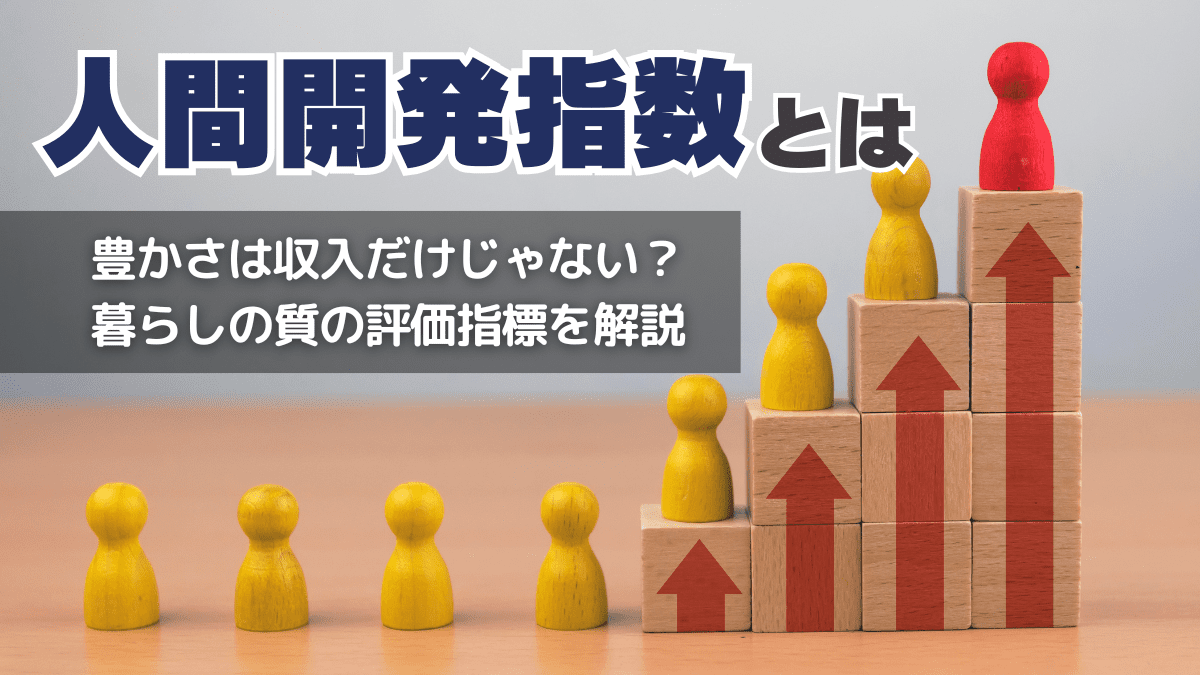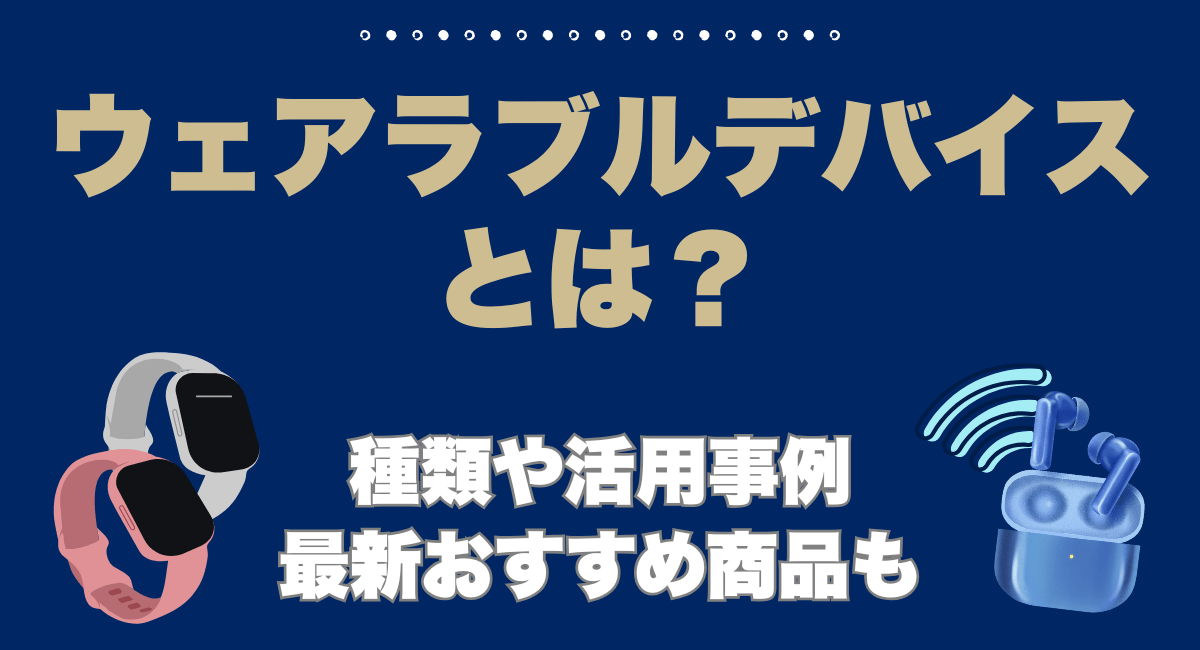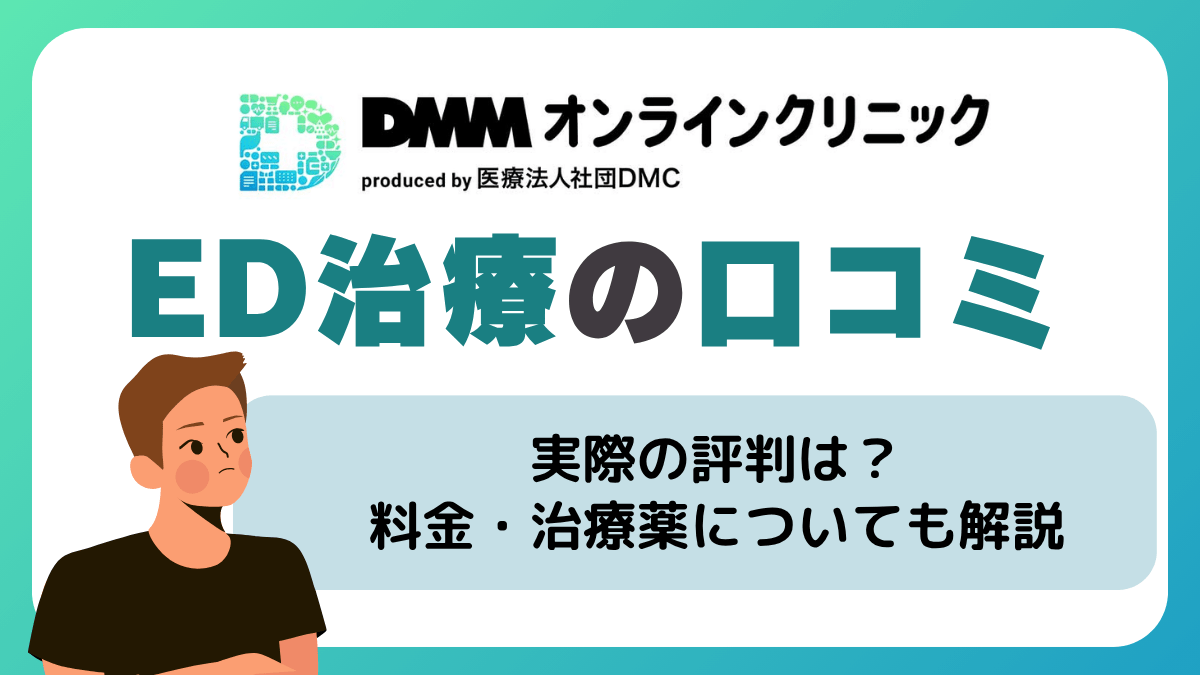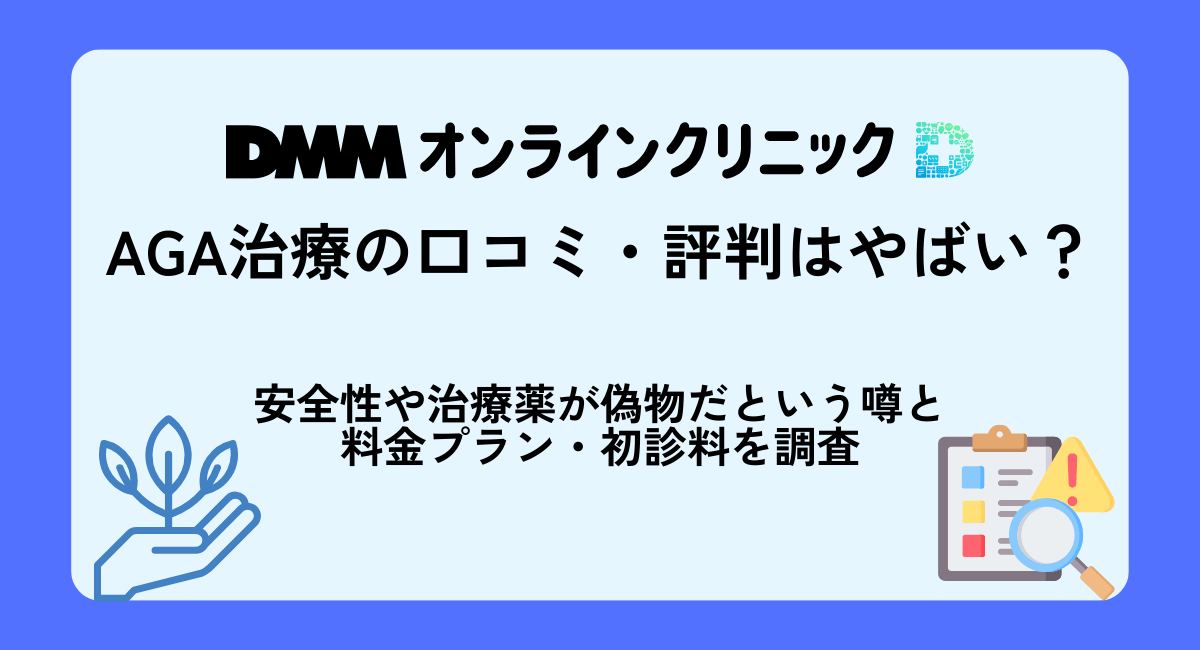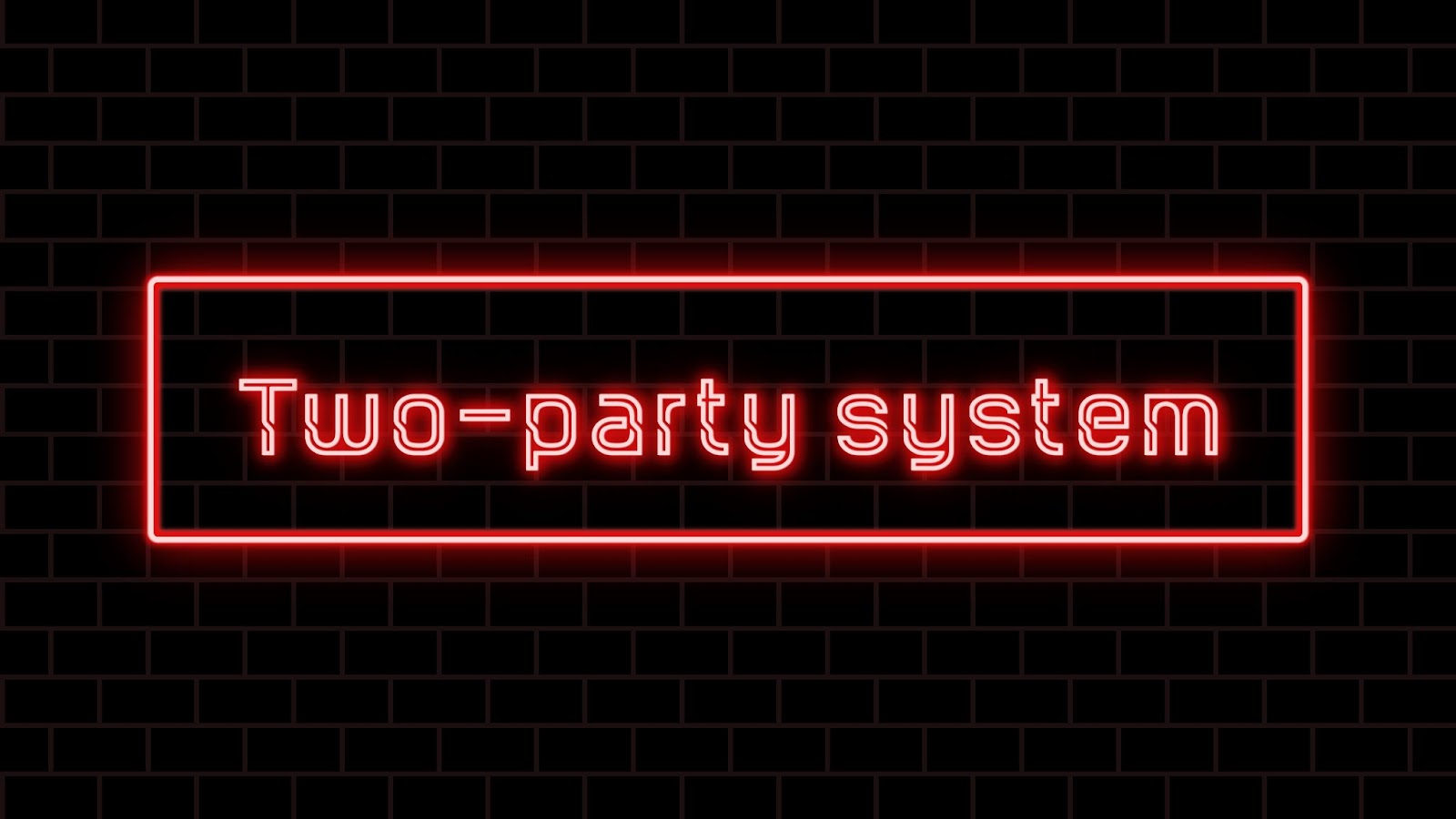
2024年11月のアメリカ大統領選挙でトランプ氏の再選が決まりました。トランプ氏と共和党はそれまでとは大きく異なる政策を打ち出すと見られ、内外の政策や人々の生活に大きな影響が及ぶことは必至です。こうした大きな変化の背景には、二大政党制という政治体制が関連してきます。
二大政党制とはどのような制度で、どんなメリットやデメリットがあるのか。果たして民主主義にとって二大政党制は望ましいのか。詳しく見ていきましょう。
目次
二大政党制とは
二大政党制とは、民主主義国家の議会で通常2つの大政党が互いに争い、この2つの主要政党が議席のほとんどを占めている体制を言います。
二大政党制を定義する明確な基準はありませんが、大まかには二大政党の勢力が拮抗し、一方が他方を圧倒していない状況を指すことが多いようです。他の政党も存在しますが、基本的に第3党以下は極めて少数派で、政権運営にほとんど影響力を持てないようになっています。
二大政党制になる理由
二大政党制の形成には、その国の選挙制度が関係してきます。
一般的に、比例代表制という制度をとっている国では多党制になりやすく、反対に小選挙区制を採用している国では二大政党制になる傾向が強くなります。
- 比例代表制…各政党の得票率(獲得票数を有効得票総数で割った値)に応じて議席数が決まる制度
- 小選挙区制…一つの選挙区で一人だけが当選する制度
なぜ小選挙区制は二大政党制になるの?
小選挙区制のような、比例性が低い制度が二大政党制に近づく理由は以下の通りです。
小選挙区制では候補者が何人出ても、当選は基本1人だけです。そのためマイナーな政党に近い意見を持つ有権者は最初から勝ち目がないと思い、1番手、2番手の政党のうち、自分の意見にどちらかというと近いと感じる党に投票する傾向が強くなります。結果的に大政党に票が集まり、これが国政選挙で行われると、二大政党制に近づいていきます。
二大政党制の歴史

二大政党制は、議会制民主主義が成立した過程から、あるいは人間が社会的集団を形成し始めた頃からその基盤が作られてきたといっても過言ではありません。
始まりは王権vs議会の権力闘争
議会制民主主義の祖であるイギリスでは、名誉革命後に新しく迎え入れる国王の政治権力をどの程度受け入れるかで議会が二つに分かれました。その結果
- 国王が権力を担うことに寛容なトーリー(王党派)
- 議会が国政の中心になるべきと主張するホイッグ(議会派)
に二分されます。やがてそれぞれは保守党と自由党という二大政党に転じていくことになります。
財産による対立構図

19世紀に入ると、新興する資本家勢力と貴族階級の間での対立が政党間の対立へと発展します。
特にイギリスでは、貴族として財産を所有する保守党と、自ら事業を興して財を成す自由党が対立する構図が形成されました。
やがて各国で国民国家が形成され、選挙権の拡大などで国民の政治参加が進みます。その過程で大衆政党が誕生していくにつれ、普通選挙が定着した1920年ごろには、経済的な利益配分が主な争点になっていきました。この頃から各国の主要政党は、資本家政党と労働者政党に二分されていくようになります。
宗教対立がもたらした党派対立
大陸ヨーロッパの一部で政党間の対立をもたらしたのは、キリスト教内部におけるカトリックとプロテスタントという宗派対立です。
19世紀半ば以降プロテスタントが多数化するようになると、社会の世俗化や自由主義化が強まり、それに対抗して伝統的な社会を守るカトリック政党がドイツやベルギーなどで見られるようになります。
当時の人々にとってこうした宗教対立は、現在の私たちには想像ができないほど生活文化や社会経済にも密接に結びついており、その影響は大きなものでした。
自由主義vs社会民主主義
第二次世界大戦後になると、経済成長の成果をいかに分配するかという方法の違いによって、自由主義政党と社会民主主義政党が、政権交代を伴う競争を繰り広げるようになります。
イギリスでは20世紀に入り、労働党が自由党を追い落として二大政党の一角の座を奪い、今日に至っています。
例外の国アメリカ
こうした国々とは異なり独自に発展してきたのが、アメリカの二大政党制です。
建国当初のアメリカは13の植民地の集合体に過ぎず、それぞれの関係も良好とは言えませんでした。19世紀になると連邦政府の強大化に反対するリパブリカンズと、連邦政府の役割を重視するフェデラリスツに分かれます。
やがて東海岸諸州と西部諸州との間で、人口密度の違いによる政治的格差が生じます。これが新たな対立の火種となり、西部州の支持派は民主党を結成して政権を奪取するに至りました。やがて奴隷制に反対する一派により、新たな党が結成されます。これが現在の共和党です。
二大政党制を導入している国

現在、世界で二大政党制になっている国は、イギリス、アメリカ、オーストラリアなどであり、伝統的に小選挙区制を採用しているイギリスの影響が強いことがわかります。
ただし二大政党制と多党制との間には明確な定義づけがないこと、小選挙区制を採用している国は二大政党制になりやすいことから、その他でも二大政党制に近い状態になっている国があります。
イギリス
上記の歴史からわかるように、イギリスは長く二大政党制をとり続けてきました。小選挙区制で選ばれて議会で最大数を取った党の党首が首相となり、基本的には保守党と労働党が二大政党として交代で政権を担ってきました。両党の力は拮抗しており、常に政権交代の可能性があるため、選挙には緊張感があります。
| 名称 | 政策の特徴 | 主な支持層 |
| 保守党 | 自由競争と伝統を重視/小さい政府志向 | 貴族・富裕層 |
| 労働党 | 公共サービスや福祉の充実を重視/大きな政府志向 | 労働者・中産階級 |
2024年11月時点での政権党は労働党(スターマー首相)で、14年ぶりの政権奪還です。ただし現在の労働党は比較的中道的な立場とされています。
またイギリスでは、イングランド以外の3地方にも独立した議会があり、北アイルランドではイギリスからの独立を目指すシン=フェイン党と、連合維持派のユニオニスト連合に分かれています。
アメリカ
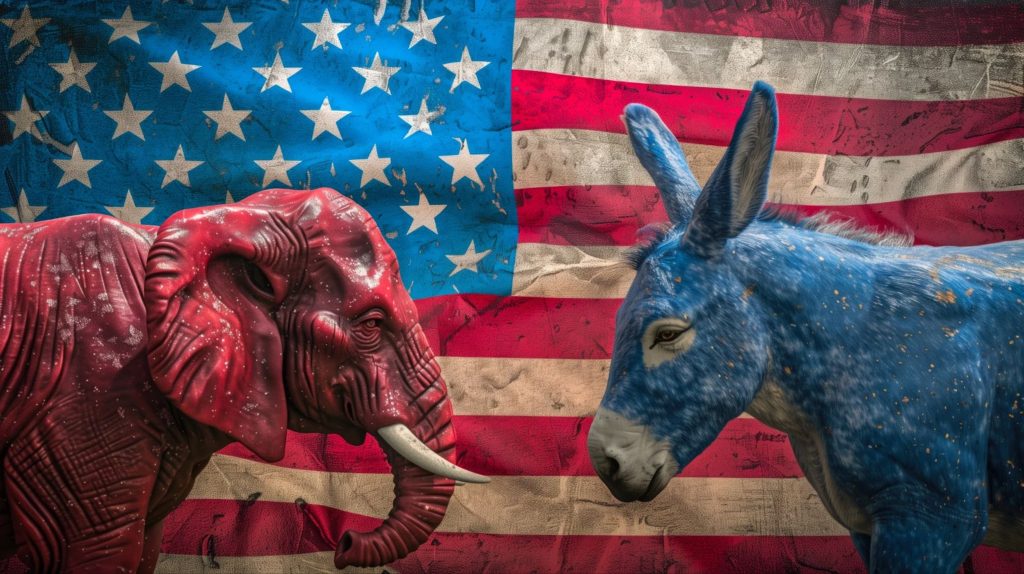
アメリカの二大政党制は、その成り立ちや特殊な制度などで他の国とは異なる性格を持ちます。アメリカは政党の構造がゆるやかで、党の主義主張ではなく、政治家個人や支持者たちの主張や要求を重視する点がヨーロッパの政党とは大きく異なります。
最も特徴的なのは、直接投票に見えて間接投票ともいうべき複雑な大統領選挙の仕組みです。選挙の流れを見ても
- 予備選挙や党員集会で代議員(各州の支持者)を獲得
- 全国大会で各党の候補者を決定
- 国民による大統領選挙
- 選挙人団による投票・上下院決定
こうした選挙プロセス自体が二大政党ありきで作られているため、共和党と民主党以外の党が政権に食い込むことは極めて困難になっています。
| 名称 | 政策の特徴 | 主な支持層 |
| 共和党 | 個人主義・自由競争・市場経済重視/小さな政府志向/銃所持やキリスト教福音派の価値観重視/LGBTQ+や移民に排他的 | 保守的富裕層や白人労働者層 |
| 民主党 | 国の市場介入を認め、福祉や社会保障を重視する大きな政府志向/LGBTQ+や移民に寛容 | 東海岸や西海岸のリベラル層、高学歴者、人種・性的マイノリティ |
アメリカでは近年経済状況の変化や移民の増加により、両党の違いは社会に軋轢を生み出すことになりました。2024年の大統領選挙ではその対立と分断が極めて深刻であることが明らかになり、今後の先行きを不安視する声は高まっています。
オーストラリア
英連邦に属するオーストラリアでは、自由党及び国民党からなる保守連合と、リベラルな労働党が二大政党を形成し、政権交代を繰り返しています。
現在の政権党は労働党で、2022年5月の連邦議会総選挙で勝利し、8年8か月ぶりに政権交代を果たしています。首相は同党党首のアルバニージー氏が務めています。
連邦議会や州議会の選挙では、候補者に順位を付ける優先順位付け投票が特徴です。これによって無所属や小政党の政策を反映しやすくさせ、二大政党の権力の独占防止を図っています。
カナダ
カナダは、現在与党であるトルドー首相の自由党と保守党の2強体制です。ただどちらも中道寄りで極端な政策はとりません。また地域政党・ケベック党が第3党として議会での発言権を有しています。
二大政党制のメリット

議会政治における二大政党制のメリットには、以下のような点があげられます。
メリット①政権交代が行いやすい
二大政党制のメリットのひとつが政権交代が行いやすくなるということです。
二大政党制では、有権者が政権を選ぶ選択肢は実質的に二つしかありません。そのため政権与党への大きな不満や重大な失政が生じた場合は、次の選挙で政権が入れ替わる可能性が高くなります。このような政権交代が容易な体制は、より強い危機感と緊張感をもって政権運営に取り組むモチベーションともなります。
メリット②政権が強くなり安定する
二大政党制は与党に委任する構造ができやすい分、大政党の力が強力になります。そのため安定した政権基盤と強いリーダーシップのもとで法案や政策の実現がしやすくなります。また、強い力を持った与党が野党との対立軸を明確にできる分、理想とする政策を首尾一貫して断行できる点も二大政党制のメリットと言えるでしょう。
メリット③有権者が選びやすい
有権者側のメリットは、選挙の際の選択がしやすくなることです。多党制になるとさまざまな主張を掲げる政党が乱立し、有権者がそれぞれの党の違いや公約を比較して、投票先を選ぶのは容易ではありません。その点二大政党制ならば、細かい違いは分からなくても、自分の考えに近い党を二者択一で選ぶことができます。
二大政党制のデメリット

上記で述べたような二大政党制のメリットは、逆にデメリットにもつながります。特に経済が落ち込み社会が不安定化する状況では、以下のようなデメリットが顕在化しやすくなると言われています。
デメリット①少数派の意見が反映されにくい選択肢の少なさ
二大政党制では、有権者は実質二者択一の選択肢しかありません。これにより
- 二大政党のいずれも支持しない少数派の意思が反映されにくい
- どちらも支持しない人も他に政権の選択肢がないため、消極的に選んでいる
- 無投票者や死票が増える
といった事態につながるため、民意の集約や反映が必ずしも正しくなされていないという問題点が指摘されています。また、ある勢力が支配的になると、自らの優位になる選択肢や争点しか提示しなくなるため、より選択肢が狭まるという「動員のバイアス」が強化される点も問題の一つです。
デメリット②社会の不安定さを招く
近年の二大政党制では、双方の党の差異は少なくなる傾向にあります。ただし、対立する二党の政策が全く違う場合ひとたび政権交代が起こると、大幅な政策変更を余儀なくされ、政治的混乱が起こります。
その典型的な例が今回のアメリカ大統領選挙です。トランプ次期政権による極端な政策転換により、化石燃料産業への支援や保守的宗教教育、LGBTQ+を否定する法案、自国第一主義政策などが強力に進められるという不安から、国の分裂をも危惧する声が上がっています。
デメリット③党利党略に走り対立が先鋭化する
もう一つのデメリットは二大政党の対立がエスカレートしがちになることです。
選択肢が二つしかない二大政党制は、対立する党を叩けば自党の支持を得られるため、相手のスキャンダル探しや中傷、バッシングなどが激化し、政策論争が疎かになりがちです。
近年のアメリカ大統領選挙などはまさにこの状態に陥っているといっても過言ではありません。
日本は現在二大政党制をとっている?

日本では長く自民党の長期政権が続いていると言われていますが、二大政党制をとることはなかったのでしょうか。
大正〜昭和は二大政党制だった
明治以降議会制民主主義を取り入れた日本では、1900(明治33)年に伊藤博文が創立した政友会が、長く野党を圧倒した時代がありました。
1916(大正5)年に野党合同で創設した憲政会は、加藤高明の下で政権を奪取。以降は政友会と政権交代を繰り返す二大政党制であり、戦後も自民党と社会党が55年体制と呼ばれる二大政党制に近い体制をとっていました。
二大政党制への試みと挫折
その後自民党の一党支配が長く続いた状況から、政権交代がしやすい二大政党制の確立を目指して選挙制度が改革されます。1994年にそれまでの中選挙区制から、小選挙区比例代表並立制に変更されたことも追い風になり、少数政党を集約させた民主党が2009年に政権を奪取しました。
しかしその後の政権運営の拙さなどで国民の支持を失い、2012年に再び自民党に政権を奪回されて今日に至ります。
2024年の衆議院選挙では自民党が過半数を割り込み、立憲民主党が肉迫する結果になりました。
しかし、第3党となった国民民主党の動向や、二大政党制そのものへの疑問などもあり、現在の日本で二大政党制となるかどうかは不透明です。
二大政党制とSDGs

二大政党制、特に保守とリベラルが対立する状況では、SDGs(持続可能な開発目標)の達成度合いが大きく左右されます。二大政党制は強いリーダーシップで政策を推進するため、短期間で達成を目指すSDGsにとって追い風となりますが、SDGsを軽視する政権の場合大きな障壁となります。
企業や富裕層の利益を重視する保守政権の下では、目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」が推進されやすくなります。
その反面、福祉や格差是正、気候変動対策や生物多様性保全、LGBTQ+の権利尊重などに関わる
- 目標1「貧困をなくそう」
- 目標3「すべての人に健康と福祉を」
- 目標5「ジェンダー平等を実現しよう」
- 目標10「人や国の不平等をなくそう」
- 目標13「気候変動に具体的な対策を」
などの目標と関連する政策を重視しているのはリベラル政党です。
二大政党のどちらが政権を握るかによって、SDGsを推進するか停滞させるかが変わると言っていいでしょう。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ
主要な大国のいくつかで採用されている二大政党制は、シンプルかつ強力、それでいて流動性に富む制度とされてきました。しかし、複雑化し混迷を極める現在の政治情勢では、その負の側面が強くなっている傾向も見られるようになっています。
それぞれの国は社会状況や背景、国民性などの違いがあるため、二大政党制と多党制のどちらが優れているかを断定することはできません。私たち有権者にできることは、自分たちにとって望ましい社会とは何かを考え、議論し、それに相応しい政治体制が実現されるような政治行動をとることではないでしょうか。
参考文献・参考資料
民主主義にとって政党とは何か-対立軸なき時代を考える(セミナー・知を究める 3):待鳥 聡史/ミネルヴァ書房,2018年
教養としての世界の政党-日本の今、これからが見えてくる:山中 俊之/かんき出版,2024年
二大政党制の批判的考察 : ラスキ、ミリバンドを中心にして 小松, 敏弘, 2014.03.29. — (東海大学経営学部紀要. 1号, 2013)
にだいせいとうせい【2大政党制】 | に | 辞典 | 学研キッズネット
Voters_4号 特集 二大政党制を考える
民主主義の発展と連立政治 – 二大政党制とデモクラシー 生活経済政策,2010,5 No.160
小選挙区制のしくみ – あすなろ学習室
比例代表制のしくみ – あすなろ学習室
アメリカではなぜ第三党が台頭しないのか 2021-10-13 待鳥聡史(京都大学教授)日本国際問題研究所
【イギリス政権交代】スターマー英首相、新内閣を発足 財務相に初の女性 – BBCニュース
投票が「国民の義務」のオーストラリア 複雑な「順位付け」方式 その意義とは?:朝日新聞GLOBE+
オーストラリア基礎データ – Ministry of Foreign Affairs of Japan
日本に二大政党制は無理 座談会|政治・経済|中央公論.jp
昭和史から問う「二大政党制は終わったのか」 いまこそ甦らせたい戦前、普通選挙時代の夢と教訓 | 歴史になる一歩手前 | 東洋経済オンライン
昭和史から問う「二大政党制は終わったのか」 いまこそ甦らせたい戦前、普通選挙時代の夢と教訓 | 歴史になる一歩手前 | 東洋経済オンライン
この記事を書いた人
shishido ライター
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。