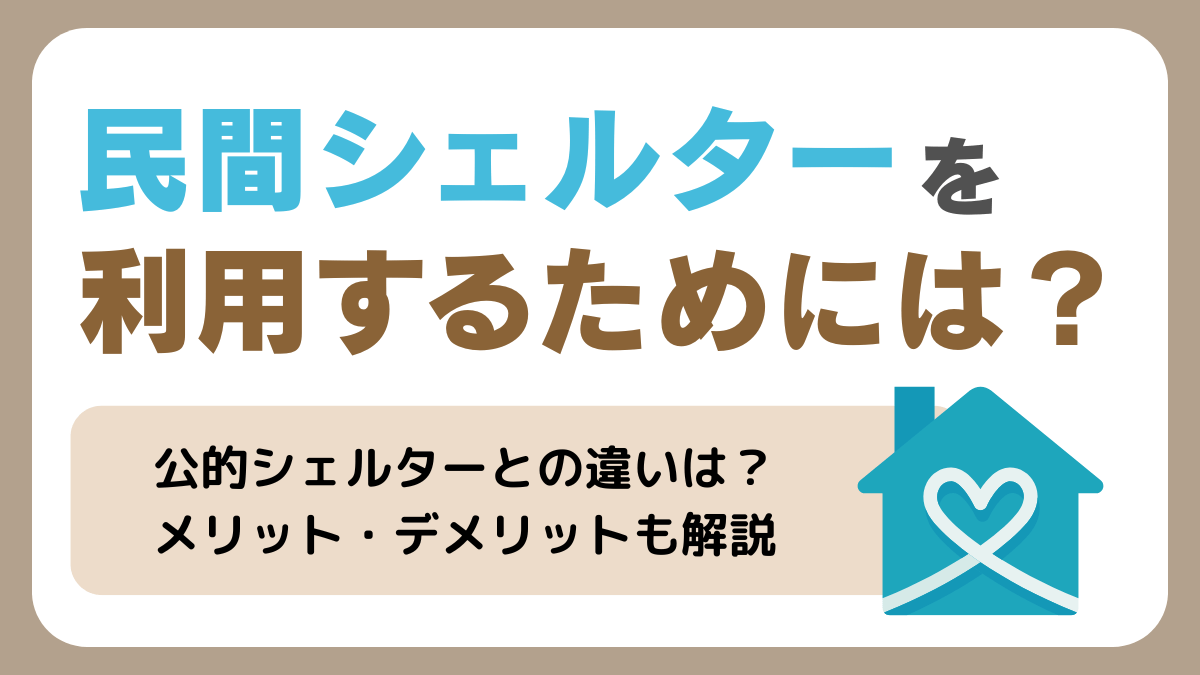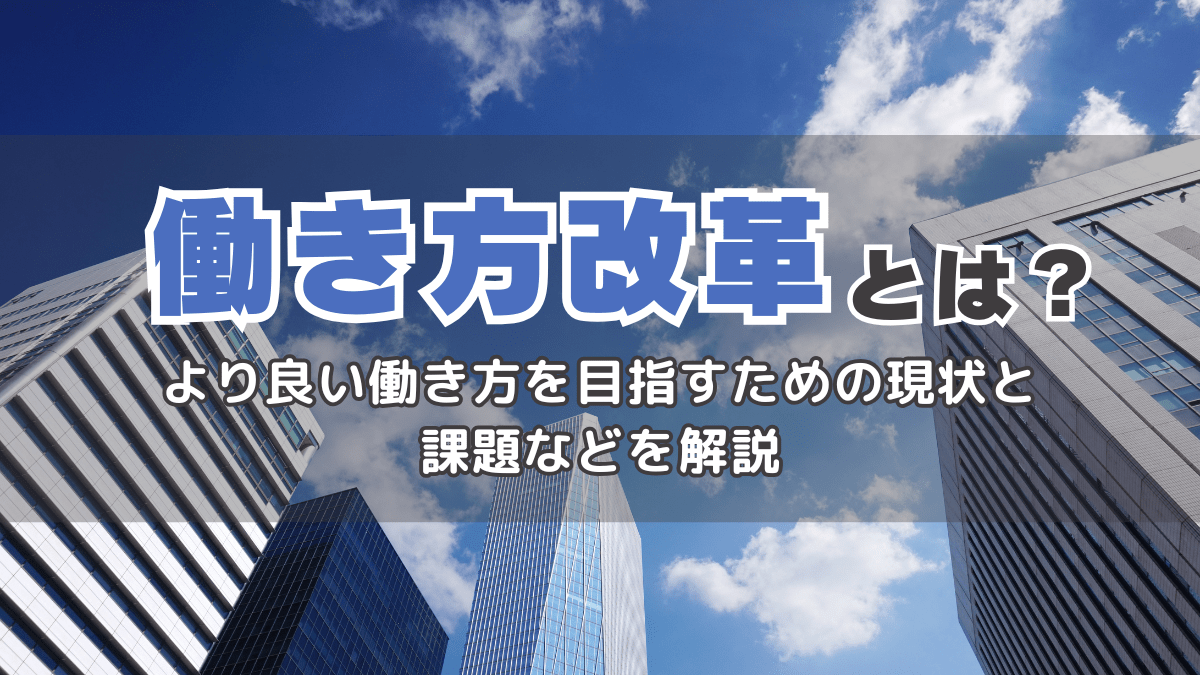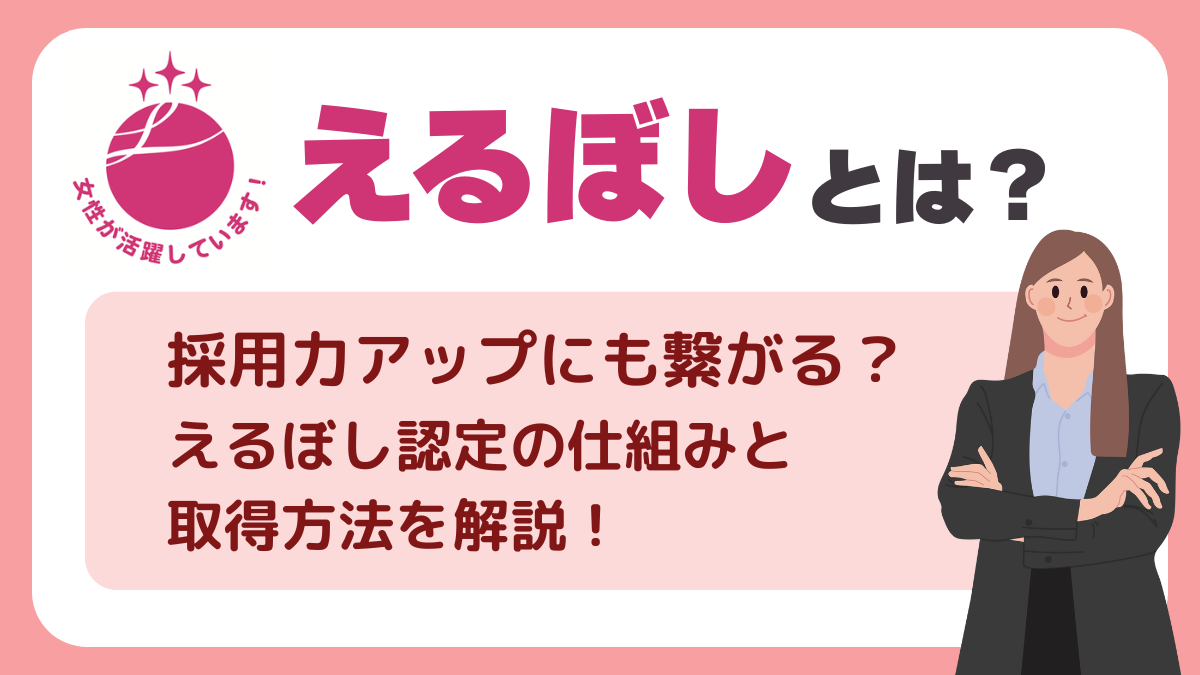大塚 小百合
1980年、徳島県阿波市生まれ。
社会福祉法人蓬莱会 常務理事
特別養護老人ホームケアプラザさがみはら 施設長
相模原市高齢者福祉施設協議会 副会長
相模原市在宅医療・介護連携推進会議 副会長
資格:社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員
<略歴>
関西学院大学文学部卒業
関西学院大学大学院 社会学研究科 社会福祉学専攻 博士前期課程修了 社会学修士
関西学院大学専門職大学院 経営戦略研究科修了 経営管理学修士(MBA)
大学卒業後、市役所福祉職、社会福祉協議会、急性期病院のMSW、当法人新規事業準備室長としての勤務を経て現職に至る。YouTube「ゆるっと!!かいご」のレギュラーとして特養にまつわる家族向け動画を発信中。
目次
Introduction
相模原市のSDGsパートナー企業の一つ、ケアプラザさがみはらは、特別養護老人ホームです。多くの取り組みを行う中、組織として何を大切にしているのか、取り組みが本格化するまでの道のりやスタッフへの想い、これからケアプラザさがみはらが地域に対してどのように在りたいのかなどを伺いました。
SDGsへの取り組みは10種以上。自身の経験から特に女性活躍・子育て支援に注力
-まずは、ケアプラザさがみはらについて教えてください。
大塚さん:
ケアプラザさがみはらは特別養護老人ホームで、主に介護が必要なお年寄りの方の中でも中〜重度(要介護3〜5)の介護度の方が入居しています。
ショートステイも含めて全部で140床の施設になります。
「社会福祉法人蓬莱会」が運営しており、法人としては43年目、他にも複数の施設を運営しています。
-早速ですが、ケアプラザさがみはらではSDGsへの取り組みをされていると伺いました。
具体的にはどんな取り組みがあるのでしょうか。
大塚さん:
17の目標のうち、9つの目標に対する取り組みを、10種以上行っています。例えば環境面での配慮としては、入居者の残食を少なくするための嗜好調査やメニュー作成、施設共用部へのLED照明の導入などです。また教育の観点からは、資格取得支援制度やWEB研修、介護動画マニュアルの無料公開をしています。
-まだまだたくさんの取り組みがあるようですね。特に力を入れている取り組みとしてはどのようなものがありますか。
大塚さん:
職員の働きがいにつながる取り組みとして、子育て中の女性・障がい者・高齢者・外国人の積極雇用や女性管理職の積極登用、職員用託児室の設置などが挙げられます。また、同一労働同一賃金も実現しました。
さらに地域医療に関わるものとして、高齢者の不要な救急搬送を減らすためのACP(アドバンス・ケア・プランニング)に注力しています。
-女性の活躍や、子育て支援には特に力を入れていらっしゃるのですね。
大塚さん:
はい。女性活躍や子育て支援への取り組みは市からも評価していただいています。最近、相模原市の「仕事と家庭両立支援推進企業表彰」で受賞しました。

-どのようなきっかけがあって、SDGsに取り組むことになったのでしょうか。
大塚さん:
今力を入れている女性活躍や子育て支援に対しては、自分が結婚や出産を経験して、現在もワーキングマザーとして働いていることがきっかけです。
こちらの施設には託児所が併設されているのですが、自分も出産直後は子供を預けながら働きました。
-ご自身でも利用されたんですね。
大塚さん:
私の母親も子育てをしながら働くワーキングマザーでした。その姿を見ていたので、ケアプラザさがみはらの立ち上げ当初から、当施設にも働く女性を支える仕組みを作りたいという強い希望がありました。
-託児所はその取り組みのうちの一つですね。
大塚さん:
そうですね。
とても女性が多い業界で、当施設の職員も7割が女性です。ですから、人材確保の観点でも、女性が働きやすい環境作りが必要になっています。
自分の経験や周りのお母さん職員の声を聴きながら、子育て支援の仕組みや勤務形態の仕組みを積み上げていきました。
働く人から選ばれる施設に。職場環境の整備への長い道のり
-その他の取り組みとして、「同一労働同一賃金の実現」という項目もありましたが、詳しく教えてください。
大塚さん:
パート職員も多いのですが、彼らにとっても働きやすい環境作りをしています。正社員同様に賞与や資格手当、扶養手当などの各種手当、退職金システムを作ったりしました。年度ごとの昇給もあります。やりがいをもって働いてもらいたいと考えています。
-大変だったことも多いのではないでしょうか。
大塚さん:
キャリアパスシステムと新たな給与規定を連動させる仕組み作りに時間がかかりました。足掛け3年はかかっています。
-お金のことは、行動力や皆さんの想いですぐに実現できるわけではないのですね。
大塚さん:
そうですね。社労士とも相談したり、相当な時間を費やしています。
当施設では扶養手当は子供1人あたり1万円お支払いしているのですが、他にはない高額な設定だけに、資金繰りのことなどを考えて制度として実現するまでに相当苦労しました。
-そこまでしても、支援をしていきたいという想いがあったのですね。
大塚さん:
そうです。
今は、働く側が働く企業を選ぶ時代です。当施設が他の施設とどう違うか・何が売りなのかを、働きたいと思っている方々に分かりやすく伝える必要がありました。
なので、子育て支援の明確なかたちの一つとして、1万円の扶養手当というのは外せなかったですね。
入居者、ご家族、地域、それぞれに寄り添うためのACP
-他に、今力を入れているものとしてはどのような取り組みがあるのでしょうか。
大塚さん:
※ACP(アドバンス・ケア・プランニング)に関する取り組みを行っています。
大塚さん:
終末期に望まない救急搬送を減らすため、入居開始時から本人や家族と話し合い、「本人が望まない治療をしない」・「老衰として穏やかに逝く」といった意思決定が早い段階でできるよう、支援しています。
-入居者の方の最期を一緒にお迎えする取り組みなのですね。
大塚さん:
そうです。なので、ACPを行うには、職員が入居開始時から時間をかけてご本人やご家族に関わり、対話し、皆さんの想いを汲み取りながら支えていく必要があります。
-職員の方の理解を得るのは大変だったのではないでしょうか。
大塚さん:
施設の立ち上げ当時、職員は相模原で地元で新規に採用の方々、管理者の私とは完全に初めましてという状況でした。
看取りを行いたいという想いは私にはありましたが、実際に現場で看る職員からは「死を看取るのは怖い」「どうしたらいいか気持ちがついていかない」という反応があり、3年ぐらい、うまく進められない時期がありました。
-ACPを行えるようになったのにはどういった変化があったのでしょうか。
大塚さん:
職員に対しては、死を迎えるというのは重大なことなので、無理強いは絶対にせず、本人たちの意思を尊重しました。
3年かけて、じっくり私の想いを伝えていく中で、職員から「やってみたい」という声を挙げてもらえるようになり、「まずは一人この方をお看取りしてみましょう」と少しずつ取り組んでいきました。
-今では皆さん納得して取り組んでらっしゃるのですね。
大塚さん:
職員と管理者が二人三脚で行う必要がありますし、入居者さんとご家族にもよく知ってもらう必要がある取り組みです。
ご家族向けの看取り説明会も行っていて、職員も積極的にご家族へ話してくれています。
積極的なACPの仕組みづくりは3年がかりでしたが、お看取りをする施設としては全国平均に対して約2倍の割合でお看取りを選択していただける施設になりました。
-じっくり取り組んでらっしゃった結果ですね。
大塚さん:
そうですね。ご家族やご本人とお互い話をしやすい仕組みづくりも必要なのですが、それも職員と二人三脚で行ってきました。
ご本人、家族の意思決定があれば終末期に不必要な救急搬送をしなくていいので、地域の医療資源を守る意味でも貢献できていると思います。
入居者、職員それぞれへの想いを取り組みに反映
-最後に、今後の展望を聞かせてください。
大塚さん:
女性活躍、ジェンダー平等の観点ですと、子育てが始まることで女性が諦めなければいけないキャリアがどうしても出てきていることを実感します。管理職のうち6割は女性ですが、子育て世代真っ只中という方はまだほとんどいないのが現状ですし、自分自身、子育てをしながら管理者を務める中で、両立への壁は大きいと感じます。
-ステップアップしたくても、できない方もいらっしゃるのですね。
大塚さん:
環境さえ許せばキャリアを継続して積み上げていける、管理職としての適性があると思えるような女性が諦めている姿を見ています。
なので、今後はそこで諦めないで続けていけるような支援や仕組み作りを強化していきたいですね。
-ACPについてはどうでしょうか。
大塚さん:
全体的な仕組みづくりが整ってきたので今後は質を高めていきたいですね。
特別養護老人ホームは「終の棲家」といわれています。なので、その方のQODを大事にしたいです。
-QOL(クオリティー・オブ・ライフ)に対して、QOD(クオリティー・オブ・デス)ですね。
大塚さん:
はい。どのような死を迎えるかは、ご本人だけではなく家族や関わった方すべてに影響があります。どう死ぬかを考えれば、どう生きるかを考えることにつながりQOLの底上げになるのかなと。
”心残りゼロケア”、つまり本人もご家族も職員も「やりきった」「生き切った」と思えるような最期を迎えてもらえるような取り組みを今後も行っていきたいです。
-人の一生を考えるきっかけにもなるお話を伺えました。
本日は貴重なお話をありがとうございました。
この記事を書いた人
スペースシップアース編集部 ライター
スペースシップアース編集部です!
スペースシップアース編集部です!