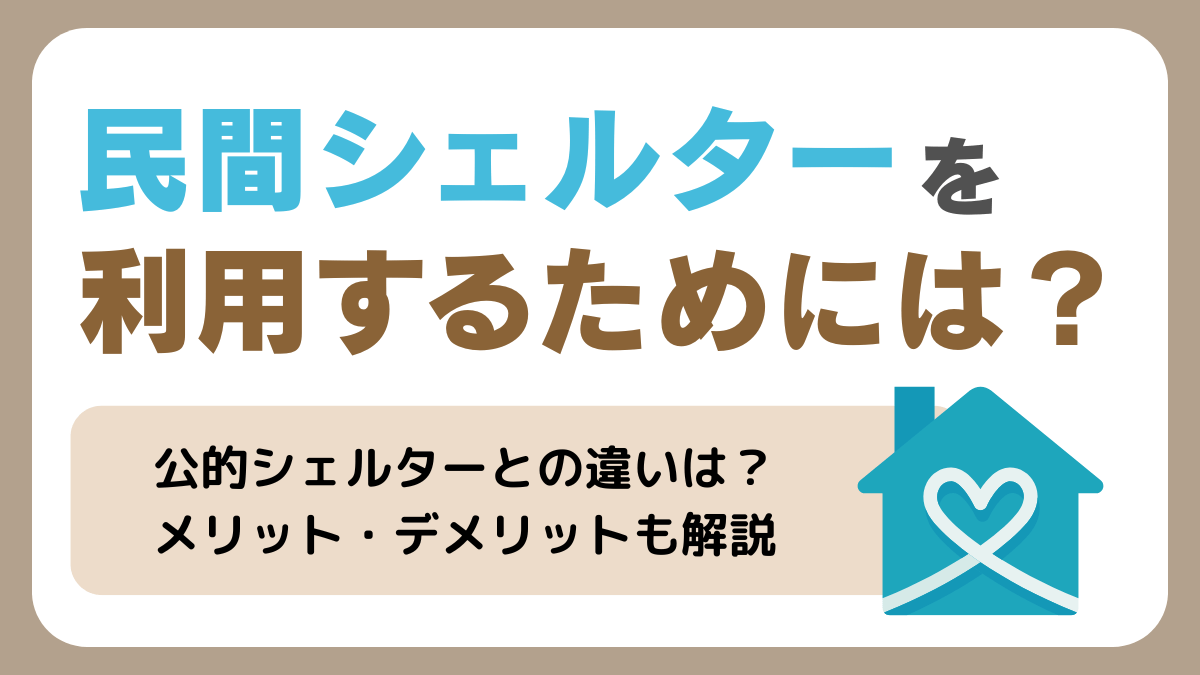
「シェルター」は避難所という意味があり、さまざまな用途で使われている言葉です。ここでは、一般的にDVシェルターと呼ばれているものでも、特に民間シェルターについて解説していきます。
民間シェルターの役割や公的シェルターとの違い、メリット・デメリット、そして実際に利用したいとなった場合の利用方法や、入居中にやるべきことなどをまとめています。
今すぐに利用する予定がなくても、万が一に備えて知っておくべき情報をお伝えしますので、不安要素のある方やそうでない方も、ぜひご一読ください。
目次
民間シェルターとは
民間シェルターとは、「民間団体によって運営されている暴力を受けた被害者が緊急一時的に避難できる施設」とされています。(出典:民間シェルター | 内閣府男女共同参画局)
もともと「シェルター」は避難所という意味があり、核爆弾から避けるための「核シェルター」や、地震などの自然災害から身を守る「防災シェルター」、犬猫などの動物保護のためのシェルターもあります。雨風を避ける場所として、バス停やタクシー乗り場にある屋根や覆いもシェルターと呼ばれることがあります。
その中でも「主にDV(家庭内暴力)の被害にあっている人が一時的に避難できる場所」がこの記事で取り上げる民間シェルター(DVシェルター)です。
公的・民間どちらのシェルターも、DVを行う配偶者などが連れ戻そうと追いかけてくることを防ぎ、安全を確保する必要があるため、所在地は公開していません。外部と連絡を取ると情報が漏れる恐れがあるため、公的シェルターではスマホやインターネットの利用も制限されています。
ここからはさらに踏み込んで、民間シェルターの特徴や公的シェルターとの違いについて解説していきます。
民間シェルターの活動内容・役割
民間シェルターは、公的シェルターと同じようにDV等の被害があり家に帰れない人たちの駆け込み寺として機能しています。そして、多くの民間シェルターは公的支援ではカバーされない人たちの受け皿となっています。具体的には、
- 公的シェルターの基準※を満たさずに入れない
- 公的シェルターが老朽化や財政難で使用できない
といった場合、その穴を埋めているのが民間シェルターです。一時保護にとどまらず、相談や自立へのサポートも行っています。
※NPO法人全国女性シェルターネットの調査によると、障がいや疾病のある方・外国籍の方・男性・ペット連れの方も、行政では一時保護されないことがあると示されています。
また、気軽に参加できるお話会やカフェを定期的に開催している団体もあります。こうした取り組みは女性がシェルターに駆け込む事態になることを未然に防ぎ、DV問題を早期解決に導いていきます。
公的シェルターとの違い
もう少し踏み込んで、公的シェルターとの違いを見ていきましょう。
行政が運営する公的シェルターは、各都道府県に設置されています。公的シェルターを利用したい場合、自治体によって名称は異なりますが、配偶者暴力相談支援センターや女性相談、警察などに相談することで一時保護施設(公的シェルター)に繋いでもらえます。相談の状況によっては、委託している民間シェルターを紹介されることもあるでしょう。
民間シェルターと公的シェルターの違いをまとめました。
| 公的シェルター | 民間シェルターの例 | |
|---|---|---|
| 費用 | 無料 | 1泊1,000~1,500円程度子ども1人500円程度 |
| 入居できる期間 | 原則2週間 | 2週間程度~応相談 |
| 部屋 | 相部屋 | 個室シェアハウス |
| 食事 | 給食 | 各自で用意 |
| 生活リズム | 起床、食事、就寝時間が決まっている | 自由 |
管理のしやすさから大部屋で生活リズムが決められているなど、全国一律で同じサービスを提供する公的シェルターに対して、民間シェルターは各自の負担となりますが時間は自由、個室を用意している施設が多い傾向にあります。
このように、利用者の安心を確保することを目指して民間シェルターは発展してきました。次に民間シェルターがどのようにして誕生し、発展してきたのか、歴史をふりかえってみましょう。
歴史・変遷
1956年(昭和31年)に交付された「売春防止法」により、今で言う公的シェルターが整備されました。当初は、戦後混乱期の中で売春を行う女性を保護し更生するための施設でした。
その後、1985年(昭和60年)に日本で初めての民間シェルター「ミカエラ寮」が、横浜のキリスト教団体により設立。
1990年代後半になると、世界的にDVや虐待が注目を集めるようになりました。日本でもシェルター運動が活発になり、各地で小規模シェルターを運営する人が増えていきました。
1998年(平成10年)、個々の民間シェルターの情報交換を目的として「女性への暴力駆け込みシェルターネットワーキング」が誕生し、全国規模のシンポジウムを開催。この団体は現在「NPO法人全国女性シェルターネット」と改名し、60団体ほどが加盟する民間シェルター最大のネットワークとなっています。
シェルターネットの働きかけもあり、2001年(平成13年)「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」が交付・施行されました。日本ではこの頃からDVが人々に広く認知されるようになり、各都道府県ごとに「配偶者暴力相談支援センター」の配置が決定。公的シェルターの門戸がDV被害者にも解放され、民間シェルターは一時保護の委託先・連携先として位置づけられることとなりました。
シェルターの種類
シェルターには、DV被害者向けやホームレス支援、動物保護など目的ごとにさまざまな種類があります。ここでは主なシェルターの特徴や役割について解説します。
福祉シェルター
福祉シェルターは、経済的困窮や住まいを失った人、高齢者、障害者など、支援を必要とする人々を一時的に保護・支援する施設です。ホームレスの方が対象になることもあり、食事や寝床の提供だけでなく、生活相談や自立支援、就労支援なども行います。
自治体やNPO法人が運営しており、行政との連携も密です。緊急避難場所としてだけでなく、生活再建に向けた第一歩を支える場所として機能しています。
女性シェルター
女性シェルターは、暴力や人間関係のトラブル、性的搾取などから女性を守ることを目的にした保護施設です。特に配偶者や恋人からの暴力(DV)被害に遭っている女性の避難場所として利用されることが多く、子ども連れの入居も可能です。
心のケアや生活支援、法律相談などが提供され、安心して生活を立て直す環境が整えられています。利用には自治体や支援団体への相談が必要な場合があります。
DVシェルター
DVシェルターは、配偶者やパートナーからの暴力(ドメスティック・バイオレンス)に苦しむ人々が身を寄せられる保護施設です。緊急時には匿名で受け入れが行われ、居場所が特定されないよう配慮された施設で、安全確保が最優先されます。
心理的・法律的支援、転居や仕事探しのサポートもあり、自立に向けた支援が一体となっています。女性・母子だけでなく、男性向けの施設も一部存在します。
母子シェルター
母子シェルターは、DVや虐待、経済的困窮などにより住まいを失った母親と子どもを対象にした保護施設です。安心して生活できる環境を提供し、教育・医療・就労など子育てに関わるさまざまな支援が行われます。
専門スタッフによる育児相談や心のケアもあり、子どもの発育環境にも配慮された体制が整っています。行政・NPOなどが運営しており、相談を通じて入居できる仕組みです。
犬など動物のシェルター
動物のシェルターは、飼い主のいない犬や猫、保護された動物たちを一時的に預かり、譲渡先が見つかるまで保護する施設です。殺処分ゼロを目指して活動している団体も多く、健康管理やしつけ、社会化トレーニングなどを通して、安心して迎え入れられるよう準備を行います。
ボランティアや寄付で運営されていることも多く、支援の受け皿として地域社会に根ざした取り組みが進められています。
民間シェルターの一覧
| 種類 | 名称 | 運営主体 | 対象 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 女性シェルター | しんぐるまざあず・ふぉーらむ | NPO法人 | シングルマザー、女性 | 支援住宅・就労支援・DV相談など多方面で支援 |
| 母子シェルター | かにた婦人の村 | 宗教法人 | DV被害女性と子ども | 長期滞在可能。心のケアを重視 |
| DVシェルター | ウィメンズネット・こうべ | NPO法人 | DV被害女性 | 匿名避難・24時間相談・カウンセリング対応 |
| 福祉シェルター | 自立支援センターふるさとの会 | 一般社団法人 | ホームレス、高齢者など | 自立支援プログラムあり、生活保護申請も支援 |
| 動物シェルター | アニマルレフュージ関西(ARK) | 非営利団体 | 犬・猫などの保護動物 | 譲渡活動、トレーニング、災害時一時保護も対応 |
民間シェルターはそれぞれの目的や支援対象に特化して運営されており、行政にはない柔軟な支援や継続的なケアを提供できる点が特徴です。特に女性・母子・DV被害者向けのシェルターでは、心身の回復や自立に向けた伴走型支援が行われており、困難な状況にある人々にとって重要な安全網となっています。
民間シェルターを利用するためには
民間シェルターを利用できる条件は基本的に公的シェルターと同じです。とはいえ、民間シェルターでは臨機応変に対応してもらえる場所が多くあります。基準に満たないからと諦めずに探してみましょう。ここからは、民間シェルターの利用方法を紹介します。
利用条件
公的シェルターでは、DVの被害を受けているなど命の危険があることが最優先となります。
一方民間シェルターでは、相談内容によって柔軟に対応しています。場所によっては、全く利用条件を設けず、困った人すべてを対象にしている施設もあります。もちろん定員はありますが、一度相談してみてはいかがでしょうか。
証拠を準備する
利用するにあたって、DVなど困っていることが客観的に見てもらえるように、以下のような証拠を集めておくといいでしょう。相談員の方も理解しやすく、適切な支援を素早く受けられます。
- 医師による診断書や受診歴
- 受けた傷や壊れた物の写真
- 警察や公的機関への相談記録
- 相手の発言の録音
- 相手とのメッセージのやり取りの記録
- いつ何をされたかの具体的な記録(日記)
利用期間
公的シェルターの利用期間は原則2週間ですが、民間シェルターの場合は1ヶ月程度〜、もしくは個人の状況に応じて決める場所が多くなっています。就職や次の住居が決まっていない状態で退去にならないような対応がなされています。
シェルターを利用する際の注意点
シェルターを利用する際は、安全に避難し安心して生活を再建するためにも、事前に知っておきたい注意点があります。どんな準備や確認が必要なのか見ていきましょう。
子供と一緒に利用できるシェルターもある
子どもと一緒に利用できますが、男の子の場合は小学生低学年までと決められている場合もあります。これは、男性に恐怖を感じる利用者も多いためです。とはいえ、男性利用者を受け入れている施設であれば、中学生以上の男子でも一緒に入居できる場合があるので、確認してみましょう。
また、現状ではペットと共に入居することを認めていない民間シェルターがほとんどですが、最近は一緒に入れる施設も増えているので、こちらも事前に確認しておきましょう。
シェルターに持っていった方が良いアイテム
シェルターに避難する場合は、自宅に戻らないまま各種手続きを行うことになるので、できれば以下のものを持っていきましょう。
- 現金
- 預金通帳(自分名義、子ども名義)
- 印鑑
- キャッシュカード
- 健康保険証
- 母子手帳
- 年金手帳
- 身分証明書
- 最低限の衣類(おむつなど)
- 常備薬など生活に必要なもの
- DVの証拠となるもの
これらは身元確認や各種手続き、生活再建に欠かせない重要なアイテムです。避難時にすべてを持ち出せなくても、最低限「現金・身分証・通帳」は優先的に確保しておくと、入所後の支援がスムーズに受けられます。
何か不安があれば事前に相談窓口へ連絡

これらの準備を整えるのと同時進行で、行政の「配偶者暴力相談支援センター」や、女性相談、最寄りの警察に連絡しましょう。その際に希望すれば、連携している民間シェルターを紹介してくれます。
また、各民間シェルターのホームページに記載の電話番号、メール、LINEなどへ直接連絡してもいいでしょう。場所によっては行政を通じた利用のみとしている施設もありますので注意してください。
シェルター入所にあたってかかる費用
費用は、1泊あたり1,000円〜2,000円程度です。子どもはひとりにつき1泊500円程度です。公的シェルターが無料なのに対し、民間シェルターはお金がかかってしまうので躊躇してしまうかもしれませんが、場所によって一定の無料期間を設けていたり、利用料の相談に乗ってくれたりする所もあります。食事も、フードバンクの提供を受けられる場合があります。
シェルター入居後の生活
公的シェルターの場合、携帯・インターネットなどを使った外部との連絡や外出の制限があります。これらはシェルターの安全を守るためです。一方の民間シェルターは自由な施設もあれば、公的シェルターと同じように制限される場合もあります。
基本的に生活リズムは自由となりますが、まずは自身の精神を回復し、その後に支援員との面談や手続き関係、就職活動、住居探しなどを行います。
民間シェルター入居後にすべきこと
民間シェルター入居後は、支援員に手伝ってもらいながら、やるべきことがたくさんあります。詳しく見ていきましょう。
手続き関係
DV被害にあった場合、以下のような手続きをする必要があります。
- 「保護命令」の申立て
加害者から保護してもらうための手続き。裁判所に申し立てる。
- 住民票の発行禁止手続き
住民票を移動する場合、加害者が住民票や戸籍の写しを請求しても受理されないようにする。
- 健康診断
- 離婚調停の手続き
- 就労へのサポート
- 保育園や学校の転園・転校の手続き
- 生活保護の手続き
このうち、「保護命令」には以下の3点が含まれます。
- 接近禁止命令
6か月間、被害者のつきまといや付近の徘徊を禁止する。
- 退去命令
2か月間、被害者とともに生活していた住居から退去し、付近の徘徊を禁止する。
- 子に対する接近の禁止命令
被害者が未成年の子と同居している場合、上記の接近禁止命令が効力を有している間、子の住居、学校等、子の身辺につきまといや徘徊することを禁止する。
保護命令に違反した場合には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が課せられるため、加害者にとっては大きな抑止力になります。
退去後の生活費・住居の確保
退去後に自立するための仕事と住居を探す必要があります。すぐ仕事に就けない場合は生活保護も受けられるので、支援員と相談しましょう。
民間シェルターのメリット
大まかな流れを把握したところで、次は民間シェルターのメリットを見ていきましょう。
素早く柔軟なサポート
行政では、基準を満たしていないとシェルターを利用できないケースがあります。また、受付時間が決まっていたり、処理に時間がかかったりすることも課題として挙げられています。
対して民間シェルターでは、
- 緊急であれば24時間対応
- 基準に満たないとしても「困った!」という状況が伝われば臨機応変に支援が可能
- 利用料金や期間も個々の状況に応じて対応
というように、素早く柔軟なサポートを実施しているケースが見受けられるのがメリットです。
気持ちに寄り添う
公的シェルターを利用するまでに、同じ説明を違う場所で何回もしなくてはならなかったり、基準を満たすかどうか厳しく聞かれたりする場合もあるようです。ひどいDVの様子を相談場所で、次は警察署で、さらにはシェルターでも説明しなければならないとなると、何度も辛い出来事を思い出すことになり、二次被害が発生する可能性もあります。
民間シェルターは、もともと「DV被害者を支援したい!」という有志が運営している施設であり、より気持ちに寄り添った支援が期待できます。人員も転勤することがないので専門性のあるスタッフが多いのが特徴です。
民間シェルターのデメリット
いいこと尽くしのようですが、民間シェルターにもデメリットがあります。
支援内容の基準がない
民間シェルターは、運営主体が自治体ではなくNPOや民間団体であるため、それぞれが独自の方針や支援内容を設定しています。その結果、提供されるサービスや滞在期間、費用負担の有無などが施設によって大きく異なり、全国で統一された基準が存在しません。
例えば、ある施設では生活再建のためのカウンセリングや就労支援を行っていても、別の施設では一時的な避難のみしか対応していない場合もあります。このように支援のばらつきが大きいことから、利用者がどの施設を選ぶべきか判断しづらく、支援の公平性や情報のわかりやすさに課題が残っています。
定員が少ない
民間シェルターの多くは、限られた資金や人員で運営されており、受け入れ可能な人数がごく少数にとどまるケースがほとんどです。特に、スタッフが常駐できる環境を整える必要があるため、大規模な施設として運営することは難しく、定員が「数組」または「数名」に限定されることが多く見られます。
そのため、緊急避難を必要とする人が同時期に重なると、すぐに満室となり、受け入れを断らざるを得ない状況も発生します。結果として、保護を求める人がすぐに入居できず、別の地域や公的施設を探す負担が生じる点がデメリットといえます。
公的シェルターのメリット
公的シェルターは、国や自治体が運営する施設であり、一定の基準に基づいた支援を受けられるのが特徴です。以下ではその主なメリットを解説します。
安全性と信頼性が高い
公的シェルターは国や自治体が運営しているため、利用者の安全とプライバシーが確保されている点が大きな特徴です。暴力や虐待からの緊急避難先として、一定の基準に基づいた管理体制が整っており、セキュリティ面でも安心感があります。
また、スタッフも専門的な知識や経験を持つ人が多く、利用者の状況に応じた対応が可能です。信頼性の高い保護体制により、被害者が安心して次のステップへ進める環境が提供されます。
生活支援が受けられる
公的シェルターでは、単に住居を提供するだけでなく、日々の生活に必要な支援も充実しています。例えば、食事や衣類の支給、医療機関との連携、心理的サポート、福祉サービスの紹介、就労支援など、生活再建に必要なあらゆる支援が受けられます。
特にDVや虐待を受けた人にとっては、安心して休養しながら、再出発に向けて準備できる場所です。専門職の支援員による相談対応も行われています。
費用負担が少ない
公的シェルターの大きなメリットのひとつは、経済的な負担が非常に少ない点です。多くの施設では一時保護の名目で無償での利用が可能となっており、利用者の経済状況に応じた柔軟な対応が取られています。
シェルターを利用する時点では所持金がほとんどない、働ける状況にないという人も多いため、費用面での配慮があることは安心につながります。経済的ハードルが低いため、支援が必要な人が躊躇なく避難・保護を求めやすくなっています。
公的シェルターのデメリット
公的シェルターは安全性や支援体制が整っている一方で、制限や課題も存在します。利用を検討する際は、以下のようなデメリットも理解しておくことが大切です。
プライバシーの確保が難しい
公的シェルターでは限られたスペースを複数の利用者と共有することが多く、個室が用意されているケースは一部に限られます。相部屋での生活や共用スペースでの交流が避けられないため、プライバシーが確保しにくく、精神的な負担を感じる方も少なくありません。
特にDV被害など心身ともに疲弊している状態で利用する場合、他人との接触にストレスを感じることも多く、安心して休息する環境が整っていないと感じる方もいます。
滞在期間に制限がある
公的シェルターは基本的に一時避難を目的としているため、長期間の滞在は認められていないことが一般的です。滞在できる期間は数日から数週間程度に限られ、原則として次の住まいが決まるまでの「つなぎ」としての利用になります。
そのため、住居探しや就労支援の段階に進む前に退所を求められるケースもあり、十分な準備が整わないまま生活を再開しなければならないリスクがあります。
施設数や受け入れ枠が限られている
公的シェルターは行政が運営しているものの、全国的に見るとその数は多くなく、地域によっては施設が1か所しかないこともあります。また、定員も限られており、急な利用希望に対応できないこともあります。
特に母子や障害を持つ方、外国籍の方、ペット同伴希望者などは対応できる施設がさらに少なく、受け入れを断られるケースもあります。そのため、入所を希望する場合は早めの相談と情報収集が重要です。
民間シェルターの現状
以上のようなデメリットを踏まえ、民間シェルターの現状を見てみましょう。
民間シェルターは増加傾向にある
民間シェルターは、2020年(令和2年)現在、124の施設があります。古い資料となりますが、以下の表からは少しづつ増えていることが分かります。
これと比例するように、DV相談の件数も増えています。以下は配偶者暴力相談支援センターへの相談件数を表したグラフです。
2020年に「DV相談プラス」という24時間対応の相談窓口ができてから、高い水準で相談数が推移しています。
これは、コロナ禍などの不安定な社会情勢によりDV被害が増加していることも考えられますが、「DV相談プラス」という相談しやすいツールができたことで、隠れていた被害が表面化している可能性もあるでしょう。
シェルターネットが設立された1990年代、行政のある調査では60代以上の女性の多くがDVに関する項目に無回答だったそうです。被害はあっても表に出してはいけないという風潮が見て取れます。(DVシェルターが目指す新たなステップ|全国女性シェルターネット 北仲千里さん×ジャーナリスト 浜田敬子さん【聞き手】)
現在ではDVが広く知られるようになり、支援に関する整備が整えられたことで、被害に合っている女性たちが声をあげるようになってきています。
人手不足・資金不足
しかし、民間シェルターを取り巻く現状として、人手不足と資金不足に関する課題があります。
民間シェルターは、NPO法人など営利目的でない団体や個人が運営を行っています。利用料だけでは経営が成り立たないので、行政からの委託費と、個人や法人などからの寄付を主な財源としています。委託費は少なく、寄付は確実にあるものではないので、多くが資金不足に陥っています。
そのため、スタッフもボランティアスタッフの割合が多くなっています。以下のグラフはスタッフの勤務形態を表しており、全体で30%以上のスタッフがボランティアで働いています。
「その他」には、社会福祉法人が運営する母子生活支援施設などが入ります。
スタッフの高齢化も問題とされており、同じ報告書のデータでは、全体の35%ほどを60代のスタッフが占めています。
民間シェルターは運営できる?
補足として、民間シェルターは個人や企業でも運営できるのかについても紹介します。
運営団体
多くの民間シェルターは、NPO法人、社会福祉法人、財団法人、宗教法人が運営を行なっていますが、法人格を持たない場所も増えています。運営団体について取り決めはありませんので、シェルターとなる建物があれば、始めることができるでしょう。
しかし、補助金を受けるにあたって法人がない場合は実績、体制が問われることもあります。運営する場合には信頼を得られるような体制を整えましょう。
補助金について
民間シェルターに対する行政からの財政支援については、都道府県と契約して支援を受ける一時保護委託制度があります。相談センターなどからの紹介で入居者を受け入れることで支援を受けられます。
また、以下のように個別に補助金を設けている自治体もあります。
- 千葉県:令和5年度千葉県民間シェルター等活動支援補助金
令和5年度に行われた。対象事業に1,000万円を上限とした補助を行う。
- 岐阜県:民間シェルター確保等事業費補助金
継続的に行われている。令和3年度は県内の民間シェルター2団体に計1,508万円支給された。
クラウドファンディングで資金を集めている団体もあります。リターンには代表者の講演や、SNSグループへの招待などが用意されているようです。
他にも企業による支援金もあります。不動産を扱うLIFULL HOME’Sでは、ACTION FOR ALLという取り組みを展開しています。そのうち「えらんでエール」では、物件の問合せをすると支援が選べて、LIFULL HOME’Sから各団体に寄付金が送られる仕組みになっています。2022年には、DV被害者や虐待被害者、難民、ホームレスの支援を行う10団体(うち4団体が民間DVシェルター運営)への支援を行いました。支援を受けた民間シェルターでは、改修費用や家電の購入に充てられています。
民間シェルターに関するよくある質問
民間シェルターは公的施設と異なり、運営主体やサービス内容が多様です。ここでは、利用を検討する際によく寄せられる質問をまとめ、わかりやすく解説します。
いま受けられる具体的支援は?
避難直後は「安全確保→衣食住→手続き」の順で支援を受けられます。到着直後に身の安全を確認し、個室または相部屋へ案内されます。
食事・生活必需品の提供、心身のチェック、緊急連絡の代行が続きます。翌営業日以降は保護命令や住民票閲覧制限の申立て、子の学校手続き、就労・生活保護の相談へ進みます。必要に応じ弁護士・医療・心理の専門家につなぎます。
DVシェルターに関するネットの噂は本当?
多くは誤解です。連絡制限や外出制限は身元特定と追跡を防ぐ安全措置として運用されています。スタッフはDV対応の研修を受け、夜間も緊急対応が可能です。
衛生や騒音は施設差があるため、匿名相談でルールと環境を事前確認すると不安が減ります。不安点は「何が、いつまで、なぜ必要か」を必ず質問してください。
民間と公的シェルターはどちらを選ぶべき?
緊急度・同伴条件・費用・滞在期間で選びます。命の危険が切迫しているなら、公的が迅速かつ原則無償で安全確保に長けます。
子どもやペット同伴、就労継続、柔軟な滞在延長を重視するなら、民間が適する場合があります。迷うときは相談窓口に同時連絡し、空き状況と条件を比較して最短で安全に入れる方を選択してください。
子どもやペットも一緒に入れるシェルターはある?
すべてのシェルターで子どもやペットの同伴が許可されているわけではありませんが、母子専用シェルターやペット同伴可能なシェルターも存在します。母子シェルターでは、子どもの安全と生活環境にも配慮された支援が提供され、学習支援や育児支援なども充実しています。
一方でペット同伴可のシェルターは限られており、主に民間団体が運営しています。動物が家族の一員として扱われる重要性が広まりつつあり、対応施設も徐々に増加しています。利用を検討する際には、事前に施設へ確認し、必要書類や予防接種の有無などをチェックしておくことが大切です。
民間シェルターとSDGsの関係
最後に、民間シェルターとSDGsの関係について確認しましょう。
目標5「ジェンダー平等を実現しよう」と関係
民間シェルターやDV問題は、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」と関連があります。目標5は「すべての女性と女の子に対するあらゆる差別をなくす」ことを目指しており、民間シェルターの利用者のほとんどが女性であることを鑑みると、ジェンダーによる不平等が見られます。一概には言えませんが、配偶者の女性を「自分の物」としてとらえ、気に入らないと暴力をふるう男性が一定数いるのは確かです。
民間シェルターの整備により、多くの女性をはじめとする被害者が救われ、DV問題の解決に繋がれば、ジェンダー平等にも近づいていくでしょう。
まとめ
本記事では民間シェルターについてまとめました。
民間シェルターには公的支援ではカバーできない部分を補う役割があります。公的シェルターと違い柔軟性があり、気持ちに寄り添った支援ができるメリットがありますが、個々団体による差が大きいこと、資金不足、人手不足などの課題もあります。
また、利用するための手順や、入居後に行うべき手続きもまとめました。
民間シェルターの運営についても、個人でも運営でき、資金獲得のための補助金が各種用意されています。
ジェンダーの平等に反する行為であるDVを減らすためにも、被害の早期発見や支援が重要です。また、民間シェルターを利用するか悩んでいる方は、一度専門機関に相談してみてください。
<参考資料>
民間シェルター | 内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同参画局:「DV等の被害者のための民間シェルター等に対する支援の在り方に関する検討会」報告書
内閣府男女共同参画局:DV等の被害者のための民間シェルター等に関するアンケート調査
内閣府男女共同参画局:民間シェルターのメリット・デメリット
LIFULL HOME’S:命の駆け込み寺「民間シェルター」。さまざまな役割と施設をめぐる課題
LIFULL HOME’S:ACTION FOR ALL
NPO法人全国女性シェルターネット
シェルターネット:日本の DV 対策の現状 ここがおかしい。
東京ウィメンズプラザ
NPO法人おかやまUFE
千葉県市川市のシェルター | Le Phare【ルファール】 | ダイバーシティ工房
生活困窮者支援NPO法人サマリア
5.ジェンダー平等を実現しよう | SDGsクラブ
DVシェルターが目指す新たなステップ|全国女性シェルターネット 北仲千里さん×ジャーナリスト 浜田敬子さん【聞き手】
この記事を書いた人
スペースシップアース編集部 ライター
スペースシップアース編集部です!
スペースシップアース編集部です!











