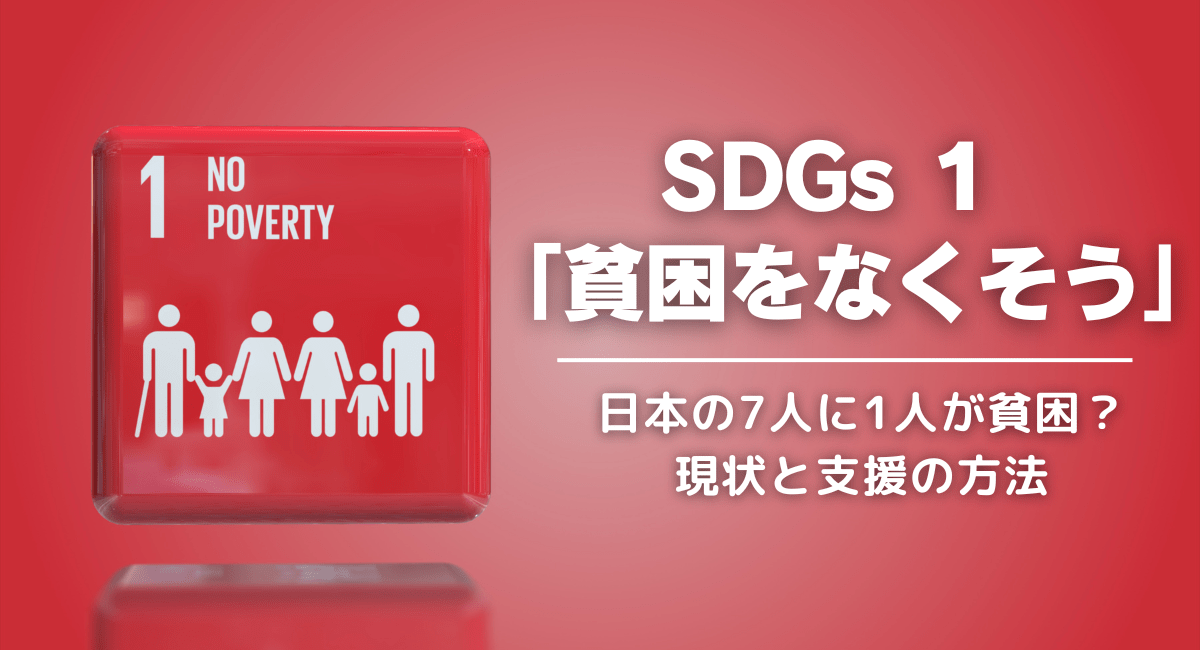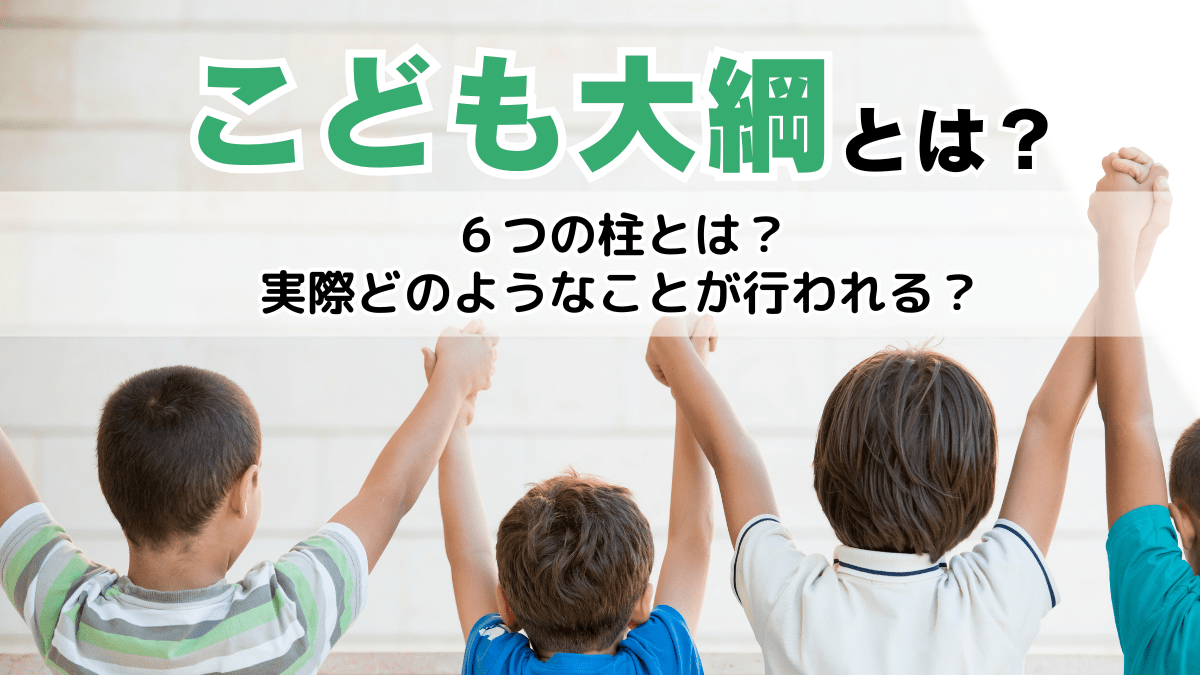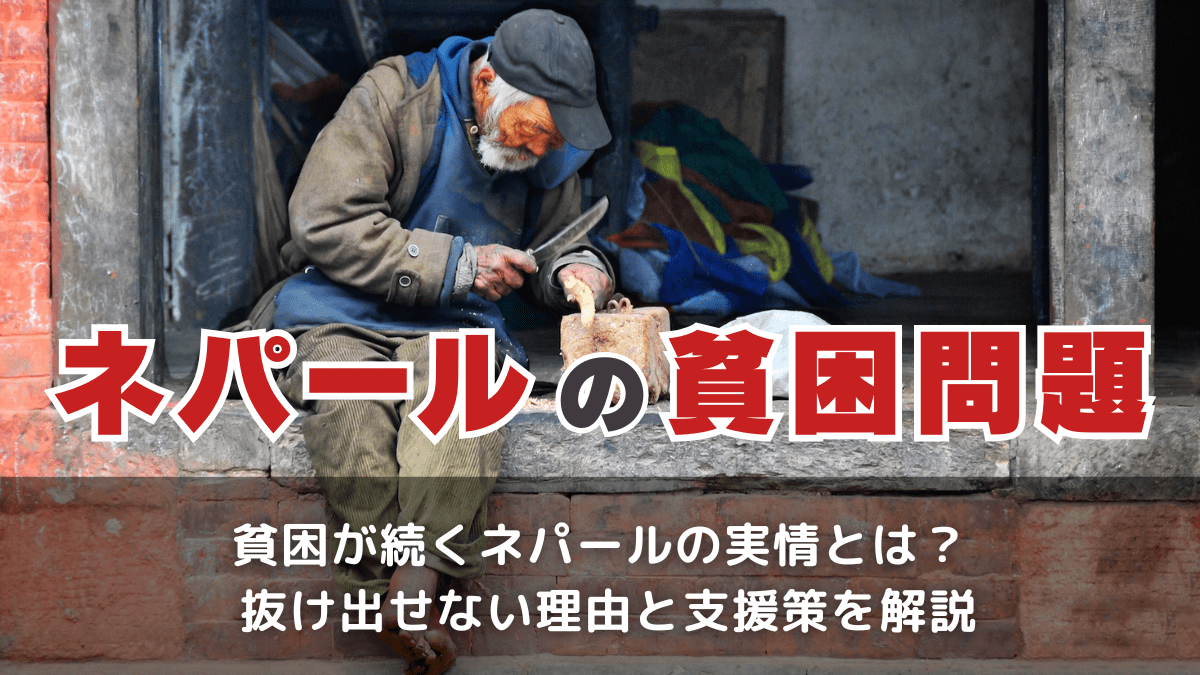
世界最高峰の山であるエベレストや、世界遺産が多く残ることから観光地としても人気のネパール。
そのネパールでは、貧困が大きな問題となっています。
本記事では、ネパールの貧困の現状や原因、解決に向けた取り組みについて紹介していきます。
目次
ネパールについて
まずはネパールについてどのような国なのか確認しましょう。
ネパールの基本情報
基礎データ
| 首都 | カトマンズ |
| 人口 | 3003万4,989人(2021年) |
| 面積 | 14.7万平方キロメートル(北海道の約1.8倍) |
| 言語 | ネパール語 |
| 民族 | パルバテ・ヒンドゥー、マガル、タルー、タマン、ネワール等 |
| 宗教 | ヒンドゥー教徒(81.3%)、仏教徒(9.0%)、イスラム教徒(4.4%)他 |
| 主要産業 | 農林業、貿易・卸売業、交通・通信業 |
| 1人あたりGDP | 142,411ルピー(約1,208ドル)(2021年度) |
多民族国家
ネパール(正式名称は「ネパール連邦民主共和国」)は、中国チベット自治区とインドに接する内陸国です。
ネパールは様々な民族が暮らしている多民族国家です。公用語はネパール語ですが各民族の言葉や、都市部では英語も使われています。宗教はヒンドゥー教を主流としつつ、仏教徒やイスラム教徒も暮らしています。
国土
国土は北側にヒマラヤ山脈があり、約8割が丘陵・山岳地帯と豊かな自然が特徴的です。世界最高峰エベレストの登山口となっており、日本からも多くの登山家が訪れています。
インドとの国境近くには、ブッダの生誕地と言われているルンビニがあります。ルンビニは世界遺産に登録されており、観光客、巡礼者も多く訪れている場所です。
食事
食事に目を移すと、ネパールでは「ダルバート」を主に食しています。豆(ダル)のスープ、ご飯(バート)、スパイスで味付けされたおかず(タルカリ)、漬物のセットで、日本で言う定食のようなものです。
他には、鶏肉やジャガイモ、スパイスなどが入った蒸し餃子の「モモ」もよく食べられています。
ネパール宗教について
ネパール宗教について解説します。
ネパールの宗教はヒンドゥー教?宗教の割合
ネパールの宗教割合
| 宗教 | 割合 |
|---|---|
| ヒンドゥー教 | 81.3% |
| 仏教 | 9.0% |
| イスラム教 | 4.4% |
| キラント教 | 3.1% |
| キリスト教 | 1.4% |
| その他 | 0.8% |
ネパールは多民族・多宗教国家として知られていますが、ヒンドゥー教が最も広く信仰されている宗教です。国民の約8割以上がヒンドゥー教徒であり、これは隣国インドと共通する特徴です。
ヒンドゥー教はネパール社会の伝統や日常生活、価値観に深く根付いています。
ヒンドゥー教以外にも、仏教、イスラム教、キラント教、キリスト教、アニミズム(自然崇拝)など、さまざまな宗教が共存しています。
特に仏教は、ネパールがブッダ生誕の地ルンビニを有することからも、歴史的・文化的に重要な位置を占めています。イスラム教やキラント教も一定の信者数を持ち、宗教的な多様性がネパールの特徴となっています。
ネパール宗教は肉を食べられない?
ネパールでは、国民の約8割がヒンドゥー教を信仰しており、ヒンドゥー教徒にとって牛は神聖な存在です。そのため、牛肉や牛由来の食品を食べることは宗教的なタブーとされています。
牛肉だけでなく、牛の脂やゼラチンなども避ける傾向があり、厳格なヒンドゥー教徒の中には肉全般や魚、卵、五葷(ニンニクや玉ねぎなど)も口にしない人もいます。
一方で、水牛やヤギ、鶏肉は食べられることが多く、レストランでも「バフ(バッファロー)」と呼ばれる水牛の肉料理が一般的です。また、イスラム教徒は豚肉を避け、牛肉を食べる場合もあります。
ネパールは多宗教社会のため、食文化やタブーには個人差や地域差も大きいですが、牛肉を避けることはネパール社会で広く共有されている重要なマナーです。
ネパール宗教のタブー
ネパールでは宗教的なタブーが日常生活に深く根付いています。特にヒンドゥー教徒が多いため、牛肉を食べることは厳しく禁じられており、牛を傷つける行為自体が重大なタブーとされています。
また、食事や物の受け渡しの際に左手を使うことは不浄とされ、失礼な行為と見なされます。他人の頭に触れることも避けるべき行動です。さらに、他人が口をつけた食べ物や飲み物を共有することも穢れとされ、嫌がられる傾向があります。
寺院や聖地では静かに振る舞い、宗教的なシンボルや像を不用意に触らないことも重要です。公の場で宗教や政治について議論することや、カースト制度に関する話題に踏み込むこともタブーとされています。
これらの宗教的・文化的なタブーを理解し、尊重することが、ネパール社会で良好な関係を築くための大切なマナーです。
ネパール人が日本に来る理由
ネパール人が日本に来る主な理由は、高い賃金水準と安定した労働環境にあります。ネパールの平均月収は日本と比べて大幅に低く、国内で十分な収入を得ることが難しいため、多くの人が家族を支えるために海外での就労を選びます。
特に日本は、最低賃金や福利厚生が整っており、治安も良いことから安心して働ける国として人気があります。また、特別なスキルや日本語力がなくても働ける職種が多いことも魅力の一つです。
日本とネパールの経済格差は大きく、同じ労働でも日本で働くことで数倍の収入を得ることができ、仕送りを通じて家族の生活を向上させることができます。
さらに、日本はネパールに対して経済的な支援も行っており、両国の友好関係や日本社会への親しみやすさも、ネパール人が日本を選ぶ理由となっています。
ネパールの歴史
ネパールの貧困問題を考える上で、国の歴史は重要なポイントです。
近代以前
ネパールは旧石器時代から人が住んでいたことが確認されています。ネパールの語源は諸説ありますが、「ネ(ne)」という人物が最初に「統治(pal)」 したので、「ネパール(Nepal)」となったという説があります。
1769年、カトマンズを支配したシャハ王朝が、現在とほぼ同じネパール地域を支配し、以後ネパール王国が約240年続いていきます。
イギリスの支配下に
1814〜16年には、インドの植民地化を進めていたイギリスとの間でグルカ戦争(ネパール=イギリス戦争)が起こりました。その戦いに負けたネパールは、イギリスの保護国となります。グルカ兵と呼ばれるネパール兵士をイギリスに提供し、インド支配の戦力として重要な役割を担いました。
第二次世界大戦後
第二次世界大戦後の1951年、国王による立憲君主制が始まりました。次第に国王による独裁体制が強まっていき、60年には議会が解散され、政党も禁止されました。
これに対抗して国民の間では民主化運動が高まり、1990年に国王は民主化を盛り込んだ新憲法を承認しました。その翌年には選挙が行われ、ネパール会議派が第一党となりました。
1995年、ネパール共産党毛沢東主義派(毛派)が結成され、王政打倒・人民共和制を掲げて武装闘争を開始。これによりネパールは内戦状態となります。
2001年に宮廷内で王族殺害事件が起こったことにより毛派が優勢となり、2008年国王は退位、ネパールは連邦制の民主共和国となりました。しかしその後も毛派と国軍との対立、毛派とネパール会議派との対立など、混乱が続いています。
ネパールの貧困の現状
ここからは、現在のネパールの貧困状況を見ていきましょう。
GDPから見るネパールの貧困状況
先述したように、ネパールは国土の約8割を丘陵・山岳で占めているため、第一次産業が中心となっており、経済的に苦しい立場に置かれている国です。
国の経済力の指標の一つである1人あたりのGDPは約1,208ドル(2021年度 )*1)と、日本の約46,768ドル(2022年度)*2)と比べると38分の1です。経済的に厳しいネパールは後発発展途上国に位置付けられています。
貧困率から見るネパールの状況
| 年度 | 貧困率 |
|---|---|
| 1995/96年度 | 41.8% |
| 2003/04年度 | 30.8% |
| 2010/11年度 | 25.2% |
| 2019年 | 21.6% |
貧困率は世界銀行が定めた基準で、1日1.9ドルを国際貧困ラインとし、そのライン以下で暮らす人々の人口に対する割合を示したものです。
経済的に厳しいとはいえ、ネパールの貧困率は下のように年々下がっており、改善してきていることが分かります。
ネパールで貧困が改善した背景には国家計画委員会による貧困対策があります。国家計画委員会はネパールの発展に関する計画を作成する機関で、5年ごとに作成・実行されています。*4)
第8次5カ年国家計画(1992~1997)以降は、貧困の削減と平等な社会の実現を目指す動きが加速し、それに従って貧困率も大きく低下しました。*4)具体的な施策としては、農業振興やエネルギー開発、地方のインフラ整備などを進める過程で貧困率の削減を目指す施策を実行しています。*5)
しかし、ネパール国内の貧困格差の縮小は道半ばです。
少し古いデータですが、2010/11年度の調査では、以下の図のように山岳部の貧困率は42.3%、丘陵地帯の都市部は8.7%と差が開いています。
ネパールの貧困世帯の生活
では、ネパールの貧困世帯は実際にどのような生活をしているのでしょうか。
生活の様子
ネパールは、国全体として電力や道路などのインフラ整備が遅れており、学校や病院へのアクセスが困難な地域が多く存在しています。
特に山岳地域では、山の斜面に集落が点在しており、飲料水を確保することさえ困難な状態です。水を汲むために、標高差のある産地を往復しなければならず、1日の労働の大部分をそれに費やしている村もあります。
他にも、
- 住居が簡素であるため、災害に対して脆弱
- 仕事は農業などの季節労働に依存
- 女性や若者の雇用機会が不足している
などの課題を抱えています。
食事
ネパールの食生活は、朝食・軽いおやつ・夕食というほぼ2食が基本となっています。
都市部や貧困以外の世帯では、2食に加えて、
- 朝起きてすぐの甘いおやつ
- 合間に飲む甘いチャイ
- 塩や砂糖、油をたっぷり使ったおかず
を口にする傾向にあると言います。
しかし、1日1.9ドル以下の所得しかない貧困層にとって、このような食事をとるのはとても難しいことです。
加えて、物価高騰が貧困層の生活を直撃しています。2022年に世界的に広がったインフレの波にネパールも巻き込まれました。特に2022年3月以降は、毎月7%を超える高インフレとなり、主食の小麦粉などを輸入に頼るネパールでは生活に苦しむ人が増えたと考えられます。*6)
ネパールが貧困から抜け出せない原因・理由
では、なぜネパールの農村部では、このような貧困から抜け出せないのでしょうか。原因を考えていきましょう。
教育格差
ネパールでは教育の格差があります。その理由のひとつとして、先述した地理的な要因が挙げられます。山岳地域では学校までの距離が長かったり、道が整備されていなかったりと、学校に通いにくい状況となっているのです。
もうひとつの理由に、地方と都市部の設備・教員の格差があります。都市部では設備の整った学校で、英語を使った質の高い教育が行なわれている一方で、地方では教員不足はもちろん、自然災害で損壊した校舎がいつまでも修復されないまま外で学習している場合もあります。
3つ目の理由が、男女の教育格差です。ネパールには児童婚の慣習があり、女子は15歳までに10%(2015年)、18歳までには41%(2015年)が結婚させられ、教育の機会が奪われています。
教育以外にも、児童婚は発育が不十分な状態での妊娠・出産による心身への大きな負担も問題となっています。
カースト
カースト制度も貧困を生み出す理由のひとつとなっています。カースト制度は、ヒンドゥー教の文化や信仰に根ざした社会的な階層制度です。ネパールでは以下のようなカーストに分けられているとされます。
- バフン(ブラーマン)(僧侶・学者)
- チェトリ(王族・戦士)
- チベット・ビルマ語系の民族(平民)
- パニ・ナチャルネ(労働者・下層階級)
さらに、「ダリッド」や「ハリジャン」と呼ばれる指定カーストが存在します。これらは一般的にカースト制度の外にあり、死や地に結びつく職業に従事していることが多いため、社会的な排除や差別を受けています。他にも、宗教や民族独自のカーストも存在します。
カーストの中でも、特に生活水準が低いのが指定カーストに属する人々です。ネパールと同じくヒンドゥー教が多数を占めるインドの事例を見てみましょう。
インドでは指定カーストの割合が全人口の16.9%を占めます。インド全体の貧困率が21.9%であるのに対し、指定カーストの貧困率は29%と高めに推移しています。*7)これは、類似した文化的背景を有するネパールにもあてはまります。
カマイヤ
カマイヤはネパールの一部地域で見られる労働制度で、ネパール語で「奴隷労働者」を意味します。この制度は、貧困や債務を負う人々が、土地所有者や大地主のもとで奴隷労働を強制されます。
主に農作業や家事労働に従事し、土地所有者から賃金を得ることはほとんどありません。彼らの労働条件は過酷であり、劣悪な労働環境や不適切な住居条件で働かされることが一般的です。
2000年代以降、カマイヤは人権侵害であるとの認識が広がり、ネパール政府や国際機関、市民社会団体などの取り組みによりカマイヤ制度の撤廃が進められています。
2002年には、ネパール政府によって「カマイヤ解放プログラム」が実施され、カマイヤの解放と再定住、土地の割り当て、教育や職業訓練の提供などの支援が行われました。
その後、2013年にはカマイヤ解放法が制定され、カマイヤ制度の完全な廃止を目指す法的な枠組みが整えられました。
これらの取り組みによりカマイヤの解放が進んでいますが、まだ課題や困難が残っている地域も多くあるのが現状です。
自然災害
大雨や地震などの自然災害も貧困を招く原因です。
例えば2015年には、カトマンズの北西約80kmを震源とするマグニチュード7.8の地震が起こり、建物の倒壊や土砂災害、死者約9,000人という甚大な被害をもたらしました。この2015年の大地震はネパール経済に壊滅的打撃を与えました。
1996年から2006年まで10年にわたって内戦が続いたネパールは疲弊した状態でした。そのあとで起きた大地震は、改善傾向にあった貧困を悪化させてしまいます。
地震の後で行われた調査によれば、調査した場所のほぼすべての家屋が全壊・半壊するといった深刻なダメージを受けています。政府の支援だけでは足りず、かなりの金額を自分たちが持ち出しています。*15)
また、地震による被害は貧困層にもかなりの経済的打撃を与えたと予想できます。実際、貧困層が多い低位カーストの人々は消費支出が減少しています。
地震前からの貧困が原因かもしれませんが、地震が貧困の悪化に拍車をかけたことは否めません。*15)
ネパールの貧困を撲滅するための各国の取り組み
このような貧困問題を抱えるネパールは、国際的にどのような支援を得ているのでしょうか。2014〜2015年にかけてのデータを例に、国際支援の取り組みをみてみましょう。
国際支援の概況
2015年にネパールに国際支援を行った国家や機関は合計38です。支援総額は11.3億ドルに達し、そのうち90%がODA(政府開発援助)です。*8)
次に、支援した国・組織の支援割合をみると、
- 1位 世界銀行 18.43%
- 2位 イギリス 16.47%
- 3位 ADB(アジア開発銀行) 14.49%
でした。*8)
世界銀行とADBという国際機関の割合が全体の3割以上を占めています。イギリスの支援割合が高いのは、インドを植民地支配していたころからネパールとつながりがあったからです。
国際支援の使い道
【2014年の国際支援金の用途】
| 保健セクター | 17.41% |
| 地方開発 | 12.23% |
| 教育 | 11.13% |
| 道路建設 | 8.48% |
| エネルギー | 7.69% |
| 飲料水 | 6.95% |
| 農業 | 4.96% |
ネパールに寄せられた国際支援は以下のように使用されました。
これを見ると、貧困撲滅に必要な保健や教育、飲料水、食料、社会インフラなどに資金が回されたことがわかります。
世界銀行の取り組み
2019年、世界銀行は自然災害に弱いというネパールの特性を考慮し、国内のインフラ構築を進めるための支援会議を開催しました。参加したのはネパール政府や日本の専門家などです。地震災害に対するノウハウを持つ日本の協力を得て、災害に強い強靭なインフラを構築するのが狙いとなっています。*11)
また世界銀行は、ネパールの水力発電の開発も支援しようとしています。そのうちの一つが「アルン渓流上流域水力発電プロジェクト」です。しかし、水力発電に適した地形は、自然災害の影響を受けやすい場所でもあるため、防災に関するノウハウを持つ日本が支援に参加しています。*12)
ネパールの貧困を撲滅するための日本の取り組み
世界銀行などの国際機関を通じた支援のほかに、日本単独でもネパールを支援しています。
日本政府による対ネパール事業展開計画
日本政府による支援の主な内容は以下のとおりです。
- 運輸交通インフラ整備の支援
- 電力エネルギー分野の支援
- 農業・農村開発の支援
- 教育プログラムの支援
- 保健セクター強化の支援
- 都市環境改善の支援
- 震災復興・防災の支援
*13)
具体的には、首都カトマンズの交通環境改善や水力発電所の建設支援、灌漑プロジェクトへの協力、農業教育の強化、教育アドバイザーの派遣、新型コロナウイルス対策支援、カトマンズ盆地の水道サービス向上のためのアドバイス、文化遺産の修復に関する支援など多岐にわたります。*13)
また、WFP(世界食糧計画)と連携し、母子保健や栄養改善への支援として3.64億円、ヌコワット郡の学校食糧計画に3.52億円を拠出するなど、継続的なネパール支援を行っています。*14)
ネパールの貧困を撲滅するための企業や団体の取り組み
続いては、企業によるネパールへの支援を紹介します。
ネパリバザーロ

ネパリ・バザーロは、ネパールの子どもたちの育成と女性の自立支援を目的として1991年に日本で活動を開始したフェアトレード会社です。ネパールの伝統的な技術や特産品を活かした商品を販売し、就業機会の拡大や仕事作りの支援を行なっています。
手織り布を使った服や手編みのセーター、手摘みの紅茶やコーヒー、カレースパイス、手作りの洋銀カトラリーなどを販売しています。
ネパールの貧困を撲滅するために私たちができること
ネパールの貧困解決に向けて、私たちができることはあるのでしょうか。
事実を知り、支援すること
私たちにできることは、まずは正しい情報を知ることです。過度に悲観や楽観視せず、どんな状況なのかを把握しておくことが大切です。
そして、国際機関やNGOに寄付をしたり、フェアトレード製品を購入してみたりしてもいいでしょう。
具体的な支援先としては、児童労働削減に尽力しているNFOシャプラニールやUnicefの活動に協力している日本ユニセフ協会、ネパールの防災活動などを支援している日本赤十字などがあります。
他にも多数のNGP・NPOがネパールの貧困問題を解決しようと活動しているので、ぜひ調べてみてはいかがでしょうか。
ネパールの貧困問題や宗教に関するよくある質問
ネパールの貧困問題や宗教に関するよくある質問を紹介します。
ネパールの貧困率はどのくらい?
ネパールの貧困率は近年改善傾向にありますが、依然として国民の約20%が貧困ライン以下で生活しています。
地方や山岳地帯では都市部よりも貧困率が高く、教育や医療、インフラへのアクセスが限られていることが課題です。
政府や国際機関による支援も進められていますが、経済格差や雇用機会の不足が根強い問題となっています。
貧困解決に向けてネパールで行われている取り組みは?
ネパール政府や国際機関は、教育の普及や職業訓練、マイクロファイナンスの導入、インフラ整備など多角的な支援を行っています。
また、日本を含む海外からの経済支援や技術協力も進んでおり、農業の近代化や女性の社会進出支援なども貧困削減に貢献しています。
ネパールで宗教的なタブーはありますか?
ネパールでは牛肉を食べることがヒンドゥー教徒にとって大きなタブーです。また、左手で物を渡すことや他人の頭に触れることも避けられています。
寺院での振る舞いや食事のマナーなど、宗教的なルールが日常生活に根付いているため、訪問時には注意が必要です。
ネパールの宗教は仏教徒もいる?
ネパールには仏教徒もいます。ネパールの宗教構成を見ると、ヒンドゥー教徒が約81%と最も多いですが、仏教徒も約9%を占めており、イスラム教徒や他の宗教とともに多様な信仰が共存しています。
仏教は、シャカ族出身のブッダ(釈迦)が現在のネパール・ルンビニで生まれたことから、歴史的にも深い関わりがあります。特にタマン族やシェルパ族、グルン族、ネワール族などの一部民族は仏教を主な信仰としています。
ヒンドゥー教と仏教の習慣や祭りが重なり合うことも多く、寺院や祭礼を共同で行う地域も存在します。ネパールはこのように多宗教社会であり、仏教徒も確かに存在しています。
ネパールの貧困問題とSDGsの関係
最後に、ネパールの貧困問題とSDGsの関係性を確認しておきましょう。
様々な目標と関連
ネパールの貧困問題の解決は、様々な目標と関連しています。例えば目標1「貧困をなくそう」では「2030年までに、世界中で極度に貧しい暮らしをしている人をなくす」ことを定めています。ここでの「極度に貧しい暮らし」とは貧困ライン以下の生活のことです。
他にも、貧困の原因となっている様々な格差をなくすことは目標10の「人や国の不平等をなくそう」に、教育が貧困解決になることから、目標4「質の高い教育をみんなに」とも関連しています。
まとめ
ネパールの貧困問題についてまとめました。ネパールの貧困率は下がってきているものの、依然として高い水準にあります。貧困から抜け出せない原因には教育や身分的な格差が存在し、法や制度の改正だけでは改善できない状況が伺えます。
貧困の解決に向けて、数多くの国際機関や国、企業や団体が取り組んでいます。私たちもできることを少しずつ取り組んでいきましょう。
参考資料
ネパール基礎データ|外務省
第3 章 ネパールの概況と開発動向|外務省
日本のODAプロジェクトネパール無償資金協力|外務省
ネパール王国|財務省
worldvision:ネパールの貧困原因は教育格差?ネパールの貧しい子どもを支援する方法
ネパール | 世界の子どもたち | 日本ユニセフ協会
JICA:貧困プロファイル ネパール
JICA:ネパール | 各国における取り組み
ユニセフ・ネパール事務所 穂積智夫代表による報告 「ユニセフの早婚/児童婚への取り組み」
ネパリ・バザーロ
*1)外務省「ネパール基礎データ|外務省」
*2)OECD「GDP and spending – Gross domestic product (GDP) – OECD Data」
*3)外務省「後発開発途上国(LDC:Least Developed Country)」
*4)創価大学大学院紀要「南アジア諸国との比較におけるネパールの貧困と人間開発の現状」
*5)千葉大学「ネパールおける国家計画の変遷 Ⅰ はじめに」
*6)CEIC「ネパール | 消費者物価指数(CPI)変化率 | 1964 – 2023 | 経済指標 | CEIC」
*7)JICA「インド JICA 国別分析ペーパー JICA Country Analysis Paper 独立行政法人 国際協力機構 2018 年 3 月」
*8)千葉大学「ネパールにおける海外支援に関する国家計画の対応」
*9)世界銀行「世界銀行」
*10)財務省「アジア開発銀行(ADB) 」
*11)世界銀行「ネパールで強靭なインフラ構築を促進」
*12)世界銀行「ネパールにおけるダムの安全性確保:アルン渓谷の防災行動計画策定に向けてのロードマップに関するオンライン協議」
*13)外務省「対ネパール事業展開計画」
*14)外務省「日本のODAプロジェクトネパール無償資金協力 案件概要」
*15)関西学院大学「ネパール大地震後の貧困と復興1)」
この記事を書いた人
馬場正裕 ライター
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。