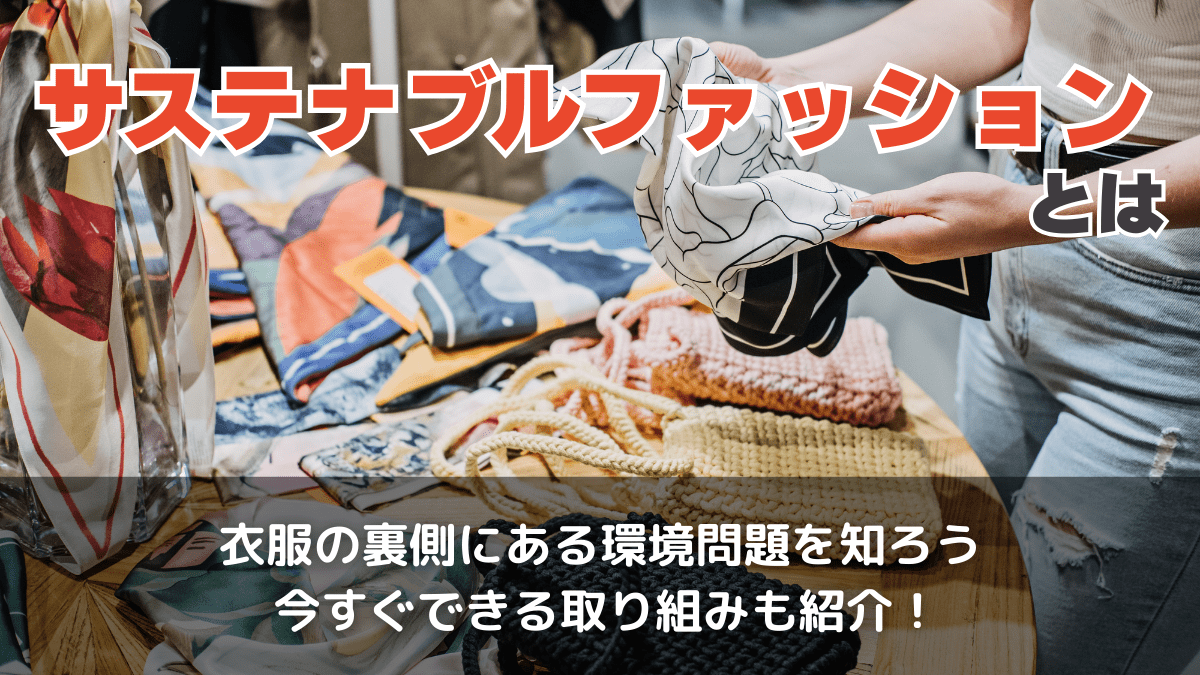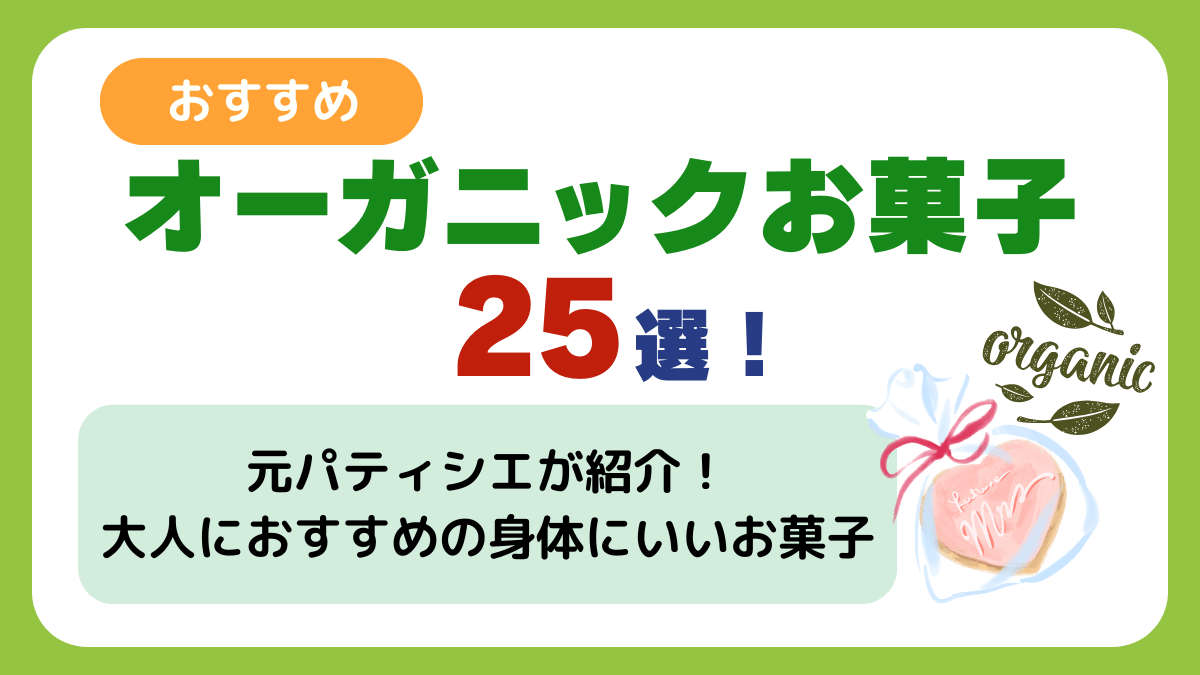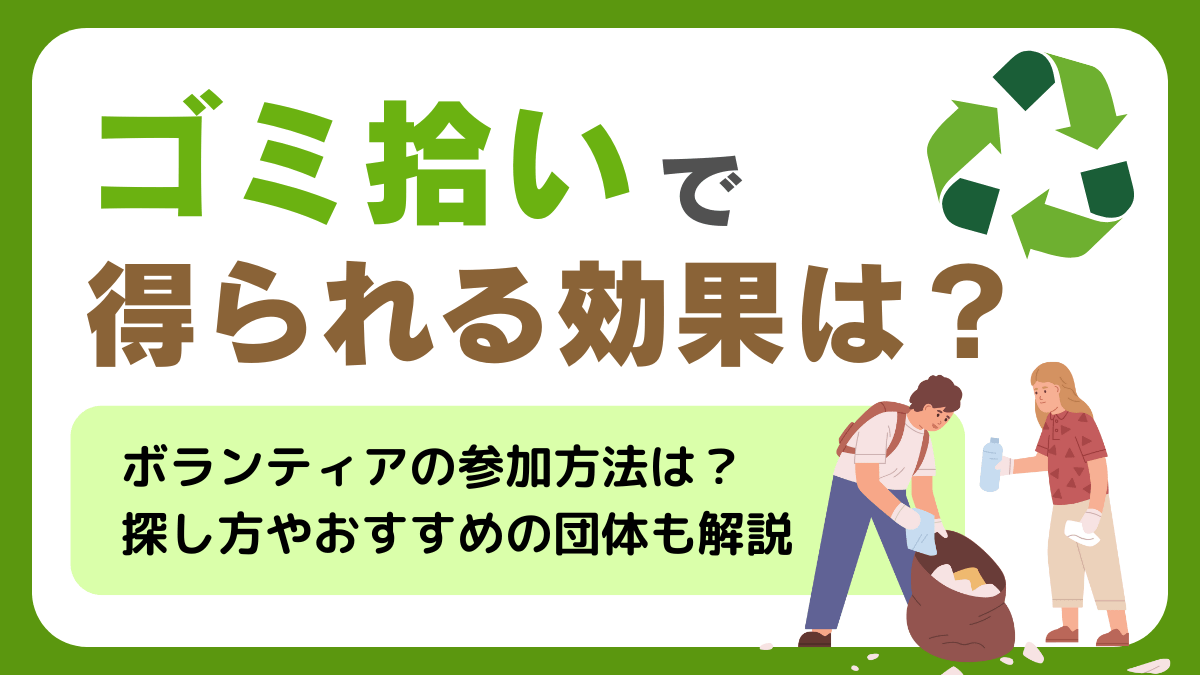近年、気象や自然災害による価格高騰や食品ロス量の削減の観点から、再生栽培(リボーンベジタブル)が注目されています。再生栽培とは、具体的にどのような栽培方法なのでしょうか。
まずは、再生栽培とは何かを知りましょう。
目次
再生栽培とは

再生栽培とは、調理の際に余った野菜やくだものの種やヘタを、水に浸したり土に埋めたりして再生させる栽培方法のことです。野菜やくだものの、再生能力の高さを生かした栽培方法と言われています。基本的に、実ではなく葉や茎の部分を育てるところも特徴です。
食材として再び活用できることは勿論ですが、成長する過程も見れるため「観察する楽しさ」も味わえます。そのため、食育の一環として子どもと一緒に育てる人もいるようです。
リボーンベジタブル・リボベジとも
再生栽培は、野菜やくだものの「再生(Reborn)」する力を活かした栽培方法であることから、「リボーンベジタブル(Reborn vegetable)」や「リボベジ」とも呼ばれています。
再生栽培のメリット

続いては、再生栽培を行うメリットを見ていきましょう。
お財布に優しい
再生栽培は、調理する際に出た野菜やくだものの種やヘタを活用します。また、豆苗やネギなど数回収穫できる品種を選べば、収穫できる間は野菜を購入する頻度も減るため節約になります。野菜やくだものは、季節や自然災害の影響を受けて値段が変動しやすい食材の1つです。自宅で再生栽培を行うことによって、急な価格高騰にも対応しやすくなるでしょう。
また、「料理に少し使いたいだけだから、こんなに沢山はいらないな」という場合も、再生栽培であれば必要な量だけ収穫できます。例えば、料理の飾りや調味料として使われるものの、量はそこまで必要のないハーブ類。まとめて販売されているうえに、値段が少しお高めなことも多く、購入を躊躇してしまうこともあるのではないでしょうか。
再生栽培であれば、その問題も解決できます。さらに、ハーブ類は生命力が強いものが多いため、初心者にもおすすめです。
品種によっては簡単に生育できる
再生栽培を行う野菜やくだものは、基本的に水に浸けたり土に埋めたりするだけで育つ品種が多いことも魅力です。水を使う場合は入れ替えを毎日しなければいけませんが、肥料も基本的に不要なため簡単に生育できます。野菜やくだものを育てることに慣れていない人や、忙しい人も気軽に始められるでしょう。
家の広さに関係なく気軽にできる
育てる品種によって多少異なりますが、再生栽培に必要なものは、
- 植える野菜やくだものの種やヘタ
- 水(または用土)
- ヘタや種を入れる容器
の3つだけなので、少ないスペースで育てられるところもメリットのひとつです。
食品ロス問題の解決に貢献
近年、耳にする機会が増えた食品ロスは家庭でも発生しており、削減が求められています。家庭内食品ロスの主な原因としては、
- 食べ残し
- 賞味期限切れによる直接廃棄
- 調理の際に皮やヘタ、種などの不可食部分を過剰除去や廃棄する
が挙げられます。
再生栽培は、本来であれば下処理の際に捨てられてしまうヘタや種を活用するため、③の食品ロスを削減できます。
再生栽培のデメリット・注意点

メリットの多い再生栽培ですがデメリットもあるため、しっかりと理解し挑戦しましょう。
水替えが毎日必要なため人によっては面倒と感じる
水に浸して再生栽培を行う場合は、カビや雑菌が繁殖しやすいため、毎日水の入れ替えを行わなければいけません。特に夏場は、気温が高く再生栽培用の容器内の水温も上がります。腐ったりカビや藻が生えたりする危険性が高いことから、1日2回の水替えが推奨されています。
再生栽培は、人が食べる目的で行うことが多く、衛生面には細心の注意を払う必要があります。しかし、それでも「面倒だ」と感じる人には難しいかもしれません。
衛生面には注意が必要
衛生面に気をつけていても、専門的な設備や環境で栽培しているわけではないため、できれば生食を避け、炒めたり湯通ししたりするなどの加熱調理がおすすめです。
再生栽培に向かない品種もある
野菜やくだものの中には、再生栽培に向かない種類もあります。
主に、根や葉がないものは再生できないと言われており、例えば、
- きゅうり
- さやえんどう
- オクラ
などが挙げられます。
その他にも、ブロッコリースプラウトやカイワレ大根などのスプラウト類もできません。理由としては、再生するために必要な新芽を出す箇所(成長点)が双葉の近くにありますが、収穫の時に摘み取ってしまうためです。
その一方で、同じスプラウト類である豆苗は、成長点が豆付近(根本)にあります。そのため、茎〜葉の部分をカットしても再生できます。「挑戦したけれど再生できなかった」とならないように、栽培方法に適しているかも確認しましょう。
再生栽培の始め方・準備するもの

ここからは、再生栽培を始めるにあたってのポイントについて詳しく見ていきます。
容器はペットボトルやトレーでも大丈夫
再生栽培は、ペットボトルやプラスチックトレーを使い育てることも可能です。飲み終わったペットボトルや、くだものが入っていたトレーをきれいに洗い使いましょう。プラスチックごみの削減にもつながります。また、ペットボトルやトレーであれば、誤って容器を落としたとしても割れて怪我をする心配もありません。
土は必要?
土は、育てる野菜やくだものの種類によっては必要です。
- コマツナ
- ほうれん草
- トマト
- 唐辛子
- パプリカ
- ゴーヤ
- バジル
などを、育てる場合は準備しましょう。
なかには、水耕と土の両方で栽培可能な種類もあります。例えば、豆苗の再収穫が目的であれば、水耕栽培で問題ありません。しかし、育ててエンドウマメにするのが目的であれば、土が必要です。
土は、様々な種類の土を混ぜ合わせて作ることもできますが、最近は「培養土」と呼ばれる土も販売されています。初心者や忙しくて土を作る暇のない人は、育てる品種に合った培養土を活用しましょう。
再生栽培は野菜の状態も重要
再生栽培は、もととなる野菜の状態も重要です。野菜を購入する際は、下記のポイントに気をつけると良いでしょう。
| 根を使うもの | ヘタを使うもの | 種を使うもの |
|---|---|---|
| ・野菜の根が切られていない ・葉が瑞々しく鮮度が高い | ・茎や葉が残っている ・ヘタが乾燥していない鮮度の高い | ・実が完熟している ・なかには、種がない又は育ちにくい品種も存在するため、よく確認する |
実の中に種があるものは採種と下処理が必要
トマトやパプリカ、アボカドなど、実の中に種があるものは、下記のように種を取り出し下処理を行います。
- 野菜を半分に切り、スプーンを使い種の部分を傷つけないように取り出す
- トマトのようにゲル状のものに包まれていたり、ぬめりがあったりする場合はザルに入れて洗い流す
おすすめの再生栽培できる野菜と育て方

ここからは、実際に再生栽培されることの多い野菜やくだものを紹介します。
レタス
まずは、サラダやスープなど幅広い料理に使えるレタスです。いくつか種類がありますが、今回はリーフレタスの再生栽培について紹介します。
【必要なもの】
- 根元が残っている状態のリーフレタス
- 容器(マグカップやグラス、半分にカットしたペットボトルなど)
- 水
【手順】
- リーフレタスの根元から6センチほどの部分をカットする
- 容器にレタスの根本が5ミリほど浸かる量の水を入れる(※水は毎日入れ替える)
- 5日~1週間ほどで新芽が伸びてくる(※個体によって異なります)
- 数枚の葉が5センチ程度伸びたら収穫
上手に育てるポイント・注意点
- 生育温度は15~20℃が好ましい。おすすめの栽培開始は10月~5月(水耕栽培で)
- カットした切り口の葉が茶色くなってきた場合はハサミで取り除く
- 屋内の日当たりの良い場所で育てる
- 水の入れ替えを忘れないようにする
大根(葉)
多様な料理に使える大根は、葉の部分を再生させます。大根の葉は、根の部分より栄養が豊富で、ビタミンやミネラルなどを多く含んでいます。
【必要なもの】
- 大根が入る器(水に浸すため、深皿たタッパーなど)
- 葉(茎)がついている大根
- 水
【手順】
- 大根のヘタの部分を2センチほどカットする
- カットした大根を水に浸ける(※水は毎日入れ替える)
- 新芽が葉(茎)の中央から生えてくる
- 葉が食べられそうな大きさに成長したら収穫
上手に育てるポイント・注意点
- 生育温度は15~20℃。ほぼ通年育てられる
- 2月に栽培を始めると春に菜の花が咲く(食べられる)
- 屋内の日当たりの良い場所で育てる
- 外側の葉が変色してきたら取り除く
パイナップル
料理や缶詰、ジュースなどに使われるパイナップルは、葉の部分を使い再生栽培を行います。しかし、株が再生し実をつけることもありますが、3年以上かかり難易度も高いため、初心者には難しいでしょう。
【必要なもの】
- パイナップル(葉付き)
- 紙ポッドまたは植木鉢
- 受け皿
- 培養土
【手順】
- 実に付いている葉(クラウン)を雑巾絞りのように捻って取り外す
- クラウンの根元についた果肉や葉を取り除く

引用元:パイナップルの再生栽培#01|泉南市 - 1週間ほど乾燥させる
- 受け皿に培養土を入れた紙ポットを置く
- クラウンを培養土に差し込む(果肉や葉を取り除いた部分が隠れる程度)
- 受け皿に水を入れ、培養土の表面にも水をかける
- 水切れにならないように気をつけながら太陽に当てる
上手に育てるポイント・注意点
- 気温は20℃以上を推奨(冬場は10℃以上)
- 10℃未満になる時は水やりを控える
- クラウンから果肉や葉を取り除く作業は丁寧に行う(いい加減にすると腐る原因になる)
- 水はけのよい酸性の土を用意する
- 培養土は紙ポッドに満杯に入れるのではなく、15~20ミリほどスペースを空ける
泉南市のホームページに、パイナップルの再生栽培方法が載っています。さらに詳しく知りたい方は、覗いてみてください。
ブロッコリー
グラタンや炒め物など様々な料理に使えるブロッコリーは、水を使った再生栽培のみでも生育できますが、土植えすることによって収穫量が増えます。
【必要なもの】
- わき芽が付いたブロッコリーの芯
- 芯が入る大きさの容器
- 水
さらに、土に植え替える場合は
- プランター
- 鉢底ネットや石
- 培養土
なども必要です。
【手順】
- ブロッコリーの芯を容器に入れ、芯の底が1センチ浸かる程度の水を入れる
- わき芽が増え、3~4センチほどに成長したら収穫する(水耕栽培の場合)
- 土植えは芯に根が出てきたタイミングで植え替え、最初はたっぷりと水をあげる
- その後、1週間は水を控え目にして半日陰で育てる
- ブロッコリーがしっかりと根付いたら、日当たりの良い場所に移動
- 土の表面が乾いたら水をたっぷりあげる
上手に育てるポイント・注意点
- 生育温度は15~20℃。栽培開始は1~4月が好ましい
- 生育環境は、屋内の風通しが良く明るい場所または屋外の日当たりの良い場所
- ブロッコリーは種類によって「わき芽」がでない種類もあるため、選ぶ時は「芽が出そうな兆しがあるもの」「枝ぶりが良く、軸がしっかりしている」「葉が付いている」などを確認する
- 芯は毎日すすぎ、水の入れ替えも行う
- 古くなった葉や枝は取り除く
- 追肥をする場合は、週1を目安にあげる(液肥の場合)
ニンニク
ニンニクは、1個まるごと使う機会が少ない食材のため、「つい使い忘れて発芽してしまった」という経験をしたことがある人も多いのではないでしょうか。そういった時こそ、捨てずに再生栽培を行いましょう。多少時間はかかりますが、再生できます。
【必要なもの】
- ニンニクが入る容器
- プランター
- 鉢底ネットと石
- 培養土
【手順】
- 発芽したニンニクを2~3日水に浸ける(水の量は、お尻の部分が触れる程度)
- 根が生えたら土に植え付ける(7~10センチ間隔で植える)
- 最初に多めに水をあげて、1週間ほど日陰で管理
- 地上に芽が出てきたら(だいたい10日前後)日当たりの良い場所に移動
- 土の表面が乾いたと思ったら水やりをする
- わき芽が出てきたら細い方を抜く(太い方を押さえながら抜く)
- 花芽(ニンニクの芽)が出たら摘み取る
- 葉が2/3ほど枯れ始めたら収穫(6月くらい)
- 掘り起こし、茎の部分を10センチほど残してカットする
- その後、風通しの良い場所で日陰干しする
上手に育てるポイント・注意点
- 生育温度は15~20℃。栽培開始は9月下旬から10月が好ましい
- 生育環境は、屋外の日当たりの良い場所
- ニンニクを発芽させる時は気温が高い時期を避ける
- 追肥は、12月頃と翌年の春頃。有機肥料の場合は2月中旬頃
キャベツ
明治時代頃から食べられていたキャベツは、ビタミンCやカリウム、カルシウムなどを含みます。
【必要なもの】
- キャベツの芯
- 芯を入れる容器
- 水
- 大型プランター
- 培養土(土によっては石も必要)
- 防虫ネット
【手順】
- キャベツの芯の1/4を水に浸す(毎日水の入れ替えを行い、芯の底はすすぐ)
- 個体差もあるが、1週間ほどで葉が生え始める。根も生えてきたら土に植えつける
- さらに、芯の様々なところから葉が生え始める(再生栽培のキャベツは球体にならずに、葉が広がることが多い)
- ある程度大きくなったら収穫
上手に育てるポイント・注意点
- 生育温度は15~20℃。日当たりの良い場所で生育する(夏場は日差しが強いため注意が必要)
- キャベツの芯は手で無理やり取ると成長点を傷つけるため、葉の周りを包丁で切り抜いて取る
- 害虫が付きやすいため防虫ネットなどで対策する
- 水が多いと根腐れを起こすため水はけの良い土を選ぶ
再生栽培とSDGs目標12「つくる責任つかう責任」

最後に、再生栽培とSDGsの関係性を確認していきます。
SDGsとは、2015年9月に開催された国連総会にて、193の加盟国が賛同し決定した国際目標です。地球上で起きている、環境・社会・経済の問題を解決するために、17の目標と169のターゲットが設定されました。このターゲットを2030年までに解決するために、現在、国や企業、個人などが取り組みを進めています。
SDGsの目標達成にも貢献でき、個人も取り組みやすいアクションの1つとして、「再生栽培」があります。なかでも、目標12とは密接に関わっています。
目標12は、私たちが生活していく中で行っている「消費行動」と、消費のもととなるものを作る「生産活動」を持続可能なものにすることを目指す内容となっています。
そのためターゲットも、
- 天然資源の持続可能な管理や効率的な利用の実現
- 廃棄物の発生を予防や、3R(リデュース、リサイクル、リユース)により大幅に削減する
- 化学物質や廃棄物の環境に配慮した管理の実現
- 持続可能な消費と生産体系の移行のために、途上国の科学的・技術的能力の強化を支援
などが挙げられます。
その中で、再生栽培が達成の鍵となるターゲットが【12.3】です。
2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる。
引用元:JAPAN SDGs Action Platform|外務省
【12.3】は、上記の通り食品ロスの削減に関するターゲットです。
農林水産省によると、令和3年度の日本の食品ロス量は523万トン。推計開始以来過去最少となった前年度より、1万トン増加してしまいました。事業と家庭から出る食品ロス量の内訳を見てみると、事業系は前年より+4万トンである297万トン、一方で家庭系食品ロス量は前年度より-3万トンの244万トンとなっています。全体的に見ると増加していますが、家庭の食品ロス量は減っているのです。
この流れに乗り、更なる削減を目指すために、家庭でできるアクションの1つが「再生栽培」です。今まで捨てていた野菜やくだものの種やヘタを、捨てずに再利用することによって、家庭から出るごみの量を減らせます。些細なことのように思えますが、行う人が増えれば増えるほど、大幅な食品ロス量削減につながるのです。
【関連記事】SDGs12「つくる責任つかう責任」|日本の現状と取り組み、問題点、私たちにできること
まとめ
野菜やくだものの種やヘタを、水に浸したり土に埋めたりして育てる再生栽培。食品ロスが問題となっている現代において、家庭でも気軽にできるアクションの1つです。野菜やくだものの種類によっては、数回行えるものもあり節約にもつながるでしょう。
また、成長する過程を観察できるため、子どもの「食育」も兼ねて栽培してみるのも良いかもしれません。豆苗やニンジンのように、手間がかからず簡単に栽培できる種類を選べば、よほどのことがない限り失敗せず収穫できるはずです。
楽しく育てて美味しく食べるだけで、食品ロス量の削減に貢献でき、SDGsの目標達成にもつながる再生栽培をぜひ試してみてください。
〈参考文献〉
SDGs(持続可能な開発目標)|蟹江憲史 著|中公新書
観て楽しい育てて美味しい 野菜の再生栽培|大橋明子(Akiko Ohashi)|株式会社産業編集センター
キッチンからはじめる再生栽培|原 由紀子 監修|ブティック社
コロナ禍の夏休み 子どもたちの自由研究を応援したい! 特設ページ「村上農園 自由研究部」を開設|PRTIMES
2021年もコロナ禍で家庭菜園デビューが続々!約3割がコロナ禍2年目に新たに家庭菜園をスタート!|PRWire
最新の食品ロス量は523万トン、事業系では279万トンに|農林水産省
パイナップルの再生栽培#01|泉南市
再生栽培のコツ|育々研究室-豆苗研究会
消費者向け情報|食品ロスポータルサイト|環境省
この記事を書いた人
スペースシップアース編集部 ライター
スペースシップアース編集部です!
スペースシップアース編集部です!