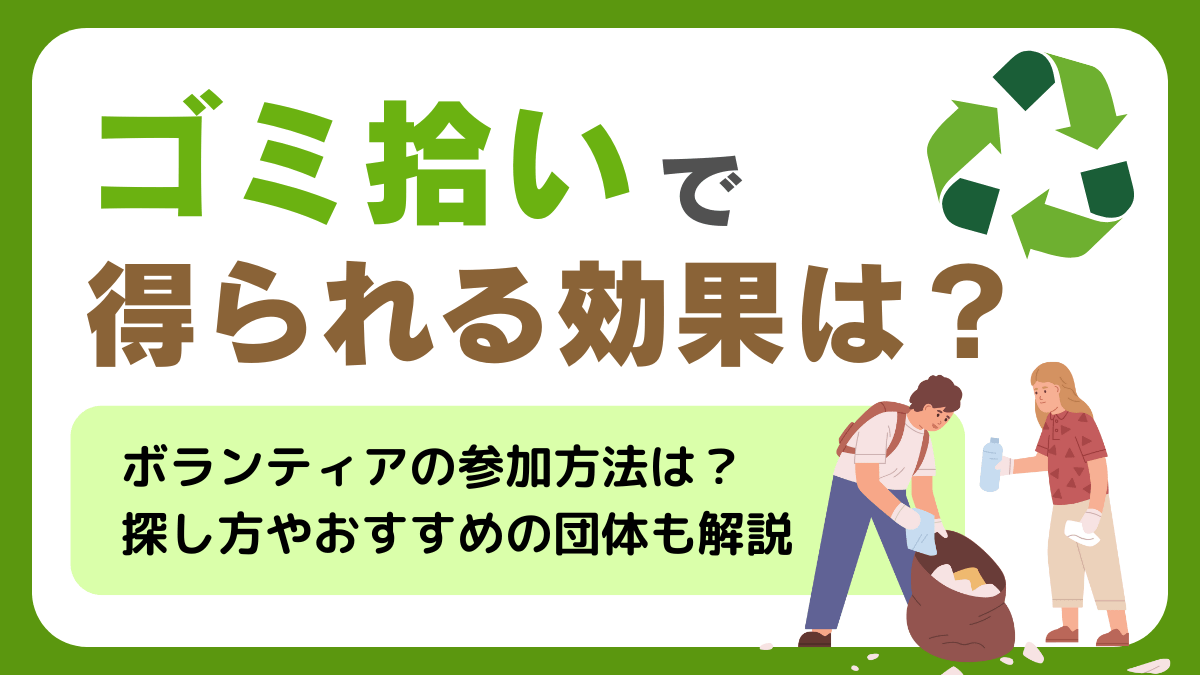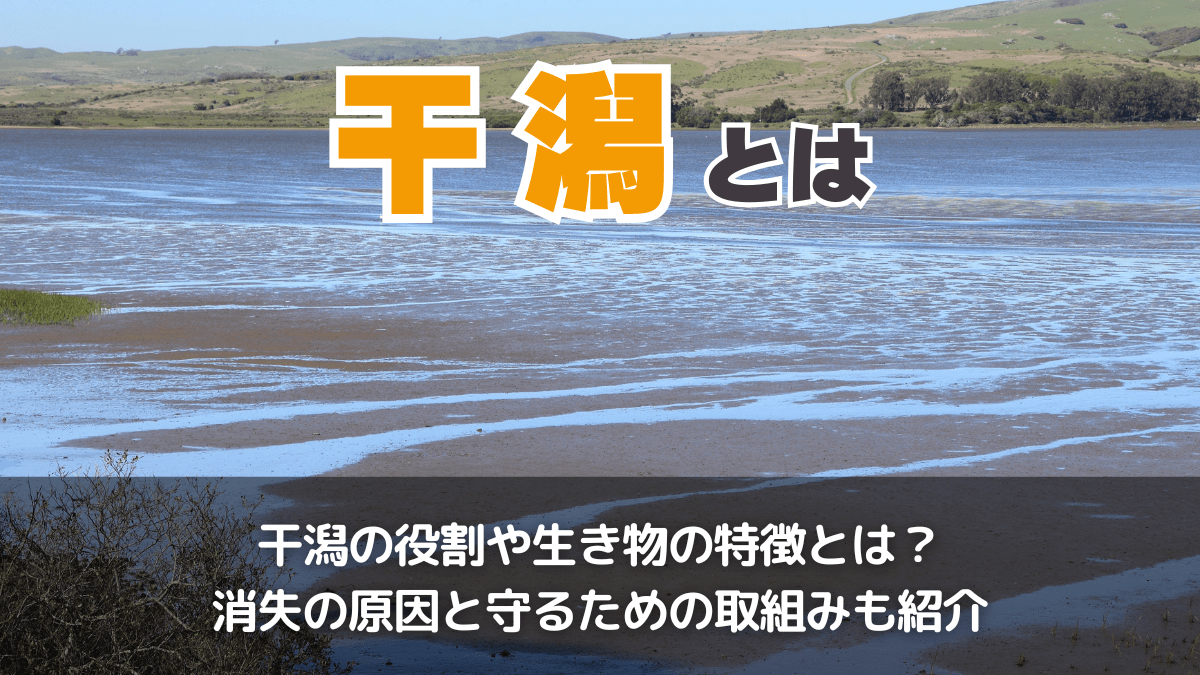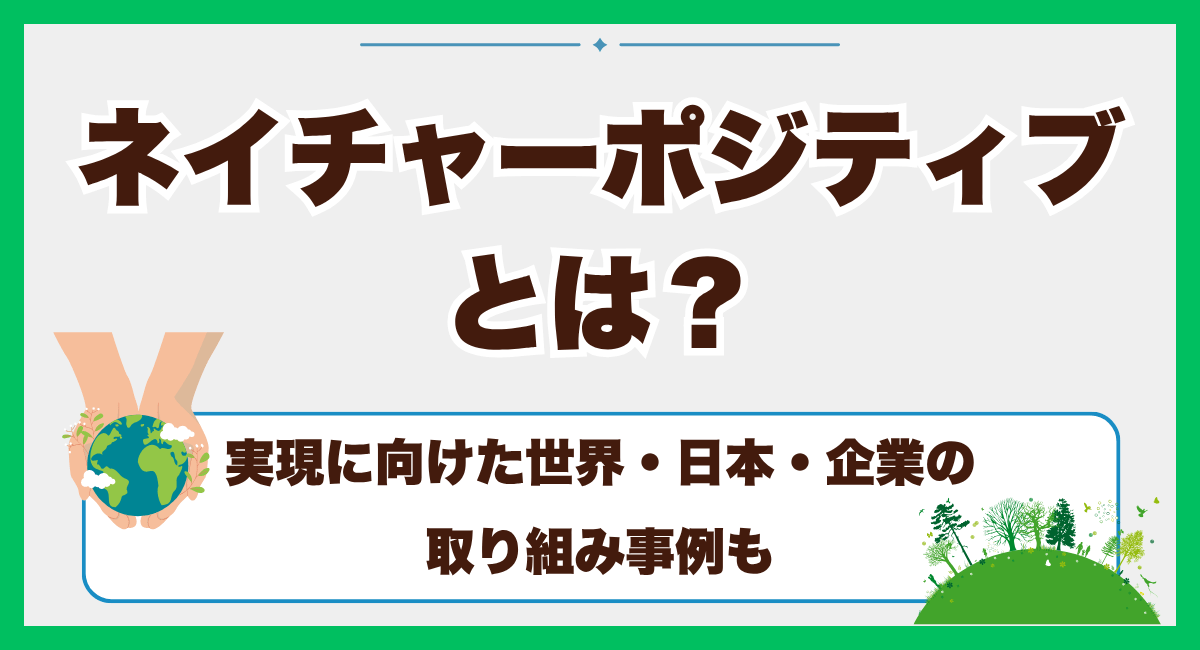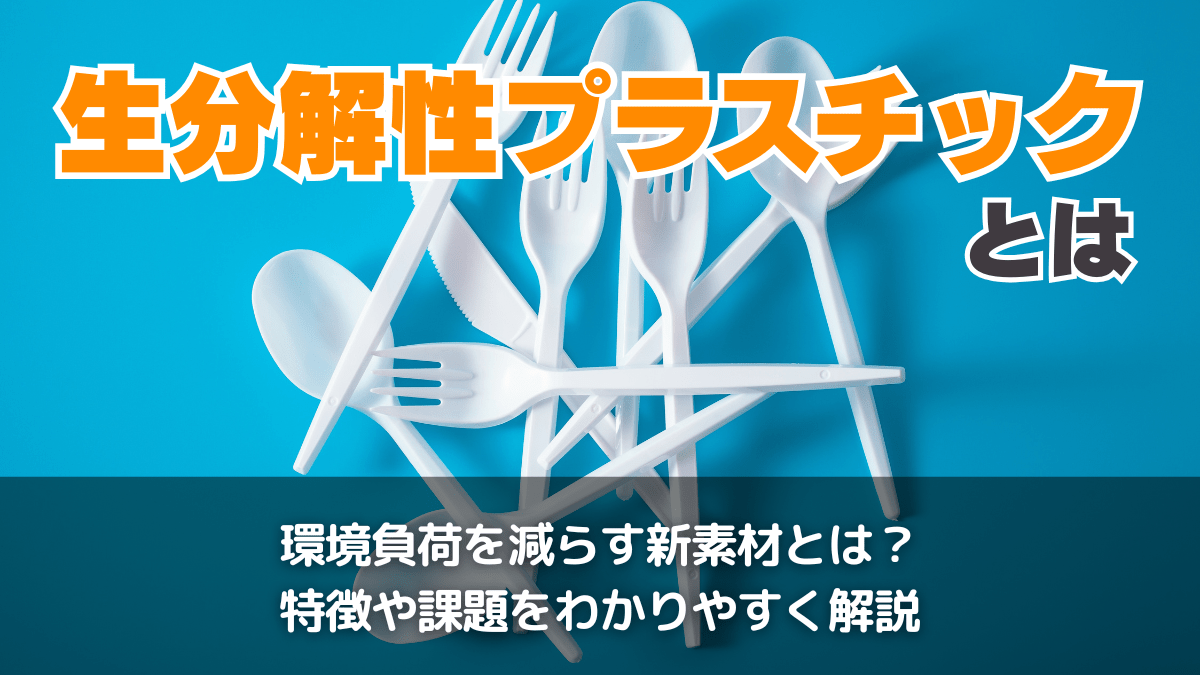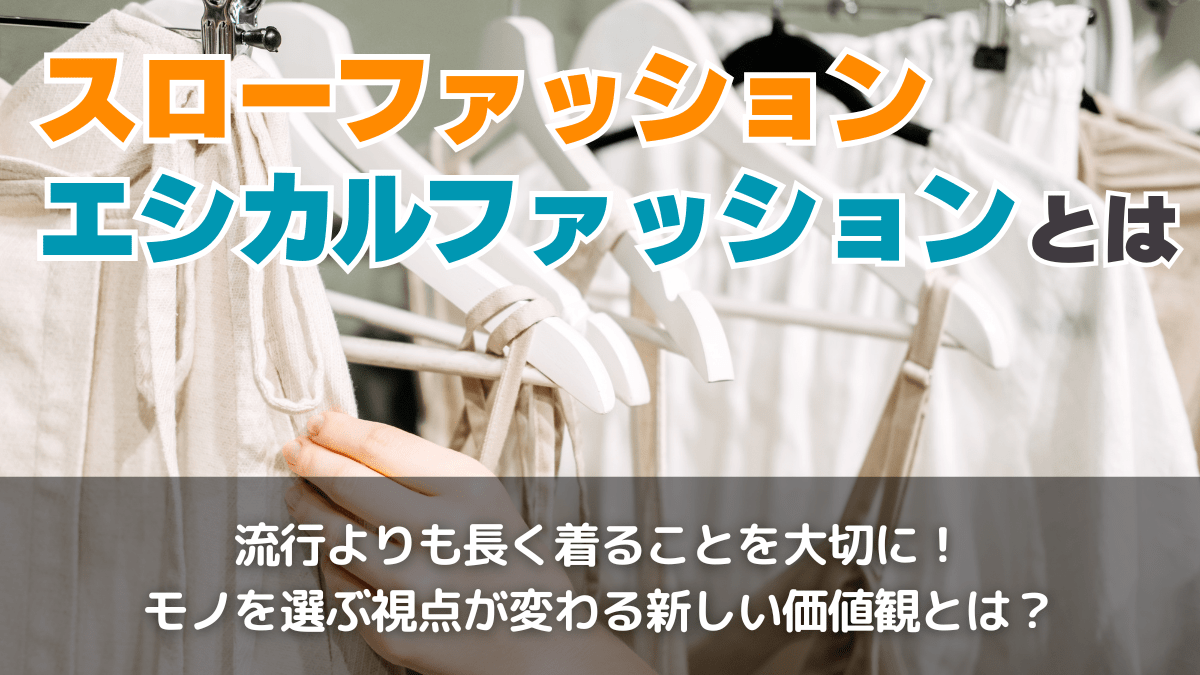マグロやタイなどのお寿司、焼き魚、ムニエルなど、魚料理は美味しいですよね。
しかし近年、「サンマなどの大衆魚が不漁」「全体の漁獲量も年々減少」「乱獲による生態系の減少」などの問題がニュースで報じられるようになり、これらの問題をそのままにしておくと、近い将来、魚が食べられない日が来るかもしれません。
解決に向けて取り組みを進めていかなければならない中で、これからも持続的に魚を食べていくために注目されているのが「未利用魚」の活用です。
本記事では、未利用魚について注目されている理由やサステナブルとの関係などを詳しく解説していきます。また、未利用魚を購入できるサイトやレシピも紹介しているので、ぜひ生活の中に取り入れてみてはいかがでしょうか。
目次
未利用魚とは?読み方は?

未利用魚とは、「サイズが不揃い」「漁獲量が少ない」「鮮度が落ちやすい」などの理由で、市場に出回らずに利用されない魚のことを指します。読み方は「みりようぎょ」です。
未利用魚はどうなる?活用方法は?
これらの未利用魚は、一般的には漁の時点で獲らない、もしくは獲れても逃がすなどの対応がされているそうですが、それでも漁獲されたものについては、ちくわなどに加工される以外にも、肥料や飼料などとして活用されています。
とはいえ、活用しきれないものは廃棄されているのが現状です。正確な数値は出されていないものの、2020年のFAO(国際連合食糧農業機関)の報告から計算すると、日本においては年間100万トンが廃棄されていることになります。
なぜ未利用魚が注目されているのか?
さまざまな原因から未利用魚となってしまうことが分かりました。ではなぜ今、未利用魚の活用が注目されているのでしょうか。その理由を見ていきましょう。
漁獲量が年々減少している
大きな理由として、漁獲量が年々減少していることが挙げられます。
上の図は日本の漁獲量を示しています。1990年をピークに漁獲量が減少していることが分かります。2021年にはさらに減っておよそ319万トンとなりました。
なぜ漁獲量が減っているのかを考えていきましょう。
原因1:乱獲
海の中の生態系は、図のようにさまざまな要素が循環することで成り立っています。このうち食用にしている魚だけを多く獲りすぎてしまうと、生態系バランスが崩れる原因となってしまいます。
実際、FAO(国際連合食糧農業機関)発表の資料によると、乱獲が進んでいることが分かります。
青色のアンダーフィッシュ(まだ余裕がある資源の割合)が年々減少しており、オレンジ色の乱獲の割合が増えています。日本でも、不漁の年は稚魚まで根こそぎ獲ってしまうような漁が行なわれたこともあり、現在において漁獲できる魚の量が少なくなっているのです。
原因2:気候変動
地球温暖化などの気候変動も漁獲量が減っている原因のひとつです。
※図の青丸は各年の平年差を、青の太い実線は5年移動平均値を示す。赤の太い実線は長期変化傾向を示す。
図からも分かるように現在地球温暖化によって、日本近海の水温は上昇傾向にあります。これにより、魚の生育地域にも変化が見られるようになりました。下の図は、マサバの産卵場の変化を表したものです。
1980年から2010年の間に、おおよそ北上してきていることが分かります。また、他にも北海道でブリが豊漁となったり、サワラの分布域が北上したりと、これまででは考えられないような事態が発生するようになりました。
その結果、漁において予測が立てにくくなり、漁獲量も不安定になる可能性が高まることが考えられます。漁獲量が不安定であれば、安定した収入も得られなくなります。現在、漁業人口の高齢化により担い手が減っている中で、稼げないとなれば漁業従事者の増加は期待できません。
これらの背景から、未利用魚を利用することで
- 漁獲量の安定確保
- 漁業の活性化
ができるのではないかと期待が集まっているのです。加えて、近年のサステナブル意識の高まりが、未利用魚活用の追い風となっています。
サステナブル意識の高まりにより、未利用魚の活用が漁業活性化の鍵に
未利用魚を利用することは、少ない資源を最大限に利用し、生態系に負担をかけずに供給を増やすことにつながります。また、使い道がなかった魚から利益が発生することで、収入も増えて漁業経済の活性化にもなります。
とはいえ、未利用魚をどう消費者に伝えていくかが課題でした。その中で近年、SDGsの認知が広まってきたことにより、サステナブルへの意識も高まりつつあります。これまで、おいしくても日の目を見なかった未利用魚を、サステナブルの潮流の中においては、「社会課題の解決になるなら」と試しに食べてみる人も増えるかもしれません。その結果、おいしさに気づいてリピートするようになれば、漁業地域でも新たな販路を確保することができるのです。
未利用魚を活用するための取り組み
では、具体的に未利用魚を活用するためにどのような取り組みが行われているのでしょうか。
認知度を高める工夫
現在の流通では、漁船で獲れた魚をすぐに冷凍できるなど、鮮度を保ったまま消費者に届けるシステムが確立しています。そのため、次に必要なのが多くの人に未利用魚の存在を知ってもらうことです。
そこで、水産庁や自治体など公的機関では消費者の認知度向上に努めています。給食のメニューに取り入れたり、高校や大学と共同で未利用魚を使った特産品を開発したりと、さまざまな取り組みが行なわれています。また、水産庁の補助金制度では約40事業が対象となっており、未利用魚となっている深海魚のせんべいや、小魚のハンバーグなどが開発・販売されています。
未利用魚サブスクも登場

他にも民間では、漁師から直接購入できるサービス・アプリや、サブスクリプションなどが登場するなど、未利用魚の露出を増やそうと努力しています。ここでは2つほど、未利用魚のサブスクリプションサービスを紹介します。
Fishlle!(フィシュル)
Fishlle!(フィシュル)は、福岡発のベンチャー企業が提供するサービスです。下処理済み・下味付きの冷凍パックでの販売です。焼くだけ、解凍するだけですぐに食べられるものばかりなので、忙しい人でも手軽に旬の魚を利用できます。味付けもバリエーション豊かで、着色料・保存料が無添加なのも嬉しいポイントです。骨取り済みなのでお子さんのいるご家庭でも活躍すること間違いなし。魚に関する情報誌も一緒に届くので理解が深まります。
月に1回、6パックおまかせ便で2,940円(税込み、送料別)、他にもコースがあります。
らでぃっしゅぼーや
らでぃっしゅぼーやでは、「海のふぞろいレスキューコース」で未利用魚の販売があります。未利用魚の他、不揃いになってしまった海産物とのセットです。未利用魚は未加工の丸ごとが届きますが、レシピ付きで美味しい食べ方を紹介しているので安心です。魚に関する豆知識も盛り込まれており、理解が深まること間違いなしですよ。
送料込みで3,450円(税込み)。毎週届く「ふぞろいセット」と4週に1回届く「未利用魚レスキューセット」(3〜4匹)が一緒になっています。
サブスクリプション以外にも、
などで、未利用魚の直販もされるようになっているので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。
未利用魚とSDGsの関係
最後に、未利用魚とSDGsの関係を見ておきましょう。
特に目標14「海の豊かさを守ろう」と関係

目標14「海の豊かさを守ろう」では、人間活動による海の汚染を防ぐことや、海洋資源の回復、資源を持続的に利用するための漁の仕方について提言しています。
未利用魚を減らす取り組みは、海洋資源の無駄遣いを防ぐことが期待されます。また、色々な種類の魚を利用することで漁の幅が広がり、マグロなどの人気の魚種に集中せず、海の多様性が守られるでしょう。
【関連記事】SDGs14「海の豊かさを守ろう」現状と課題、日本の取り組み事例、私たちにできること
まとめ
未利用魚が発生してしまう理由として、知られていない種類であることや、毒の扱い、量や大きさによる流通のしづらさなどがありました。
近年はさまざまな要因から漁獲量も年々減少しており、未利用魚の活用は漁業の活性化の鍵として期待されています。
未利用魚を減らす取り組み、活用方法も紹介しました。私たちにできることとしては、産直サイトやサブスクで実際に購入して味わってみたり、理解を深めるたりすることが大切です。海の資源を持続的に利用していくために、行動してみてはいかがでしょうか。
<参考文献>
魚食普及推進センター
魚食普及推進センター:未利用魚・低利用魚とは? 海の資源を上手に食べよう!
特集1 ニッポンの漁!(5):農林水産省
NHK:未利用魚とは 行き場のない魚をサブスクで有効活用
NHK:未利用魚・低利用魚 季節ごとのおすすめ&レシピ
FAO:Towards blue transformation
Fishlle!(フィシュル)
らでぃっしゅぼーや
未利用魚って結局何なの?
三省堂:第36回 【未利用魚】みりようぎょ | ニュースを読む 新四字熟語辞典(小林 肇) | ことばのコラム
この記事を書いた人
スペースシップアース編集部 ライター
スペースシップアース編集部です!
スペースシップアース編集部です!