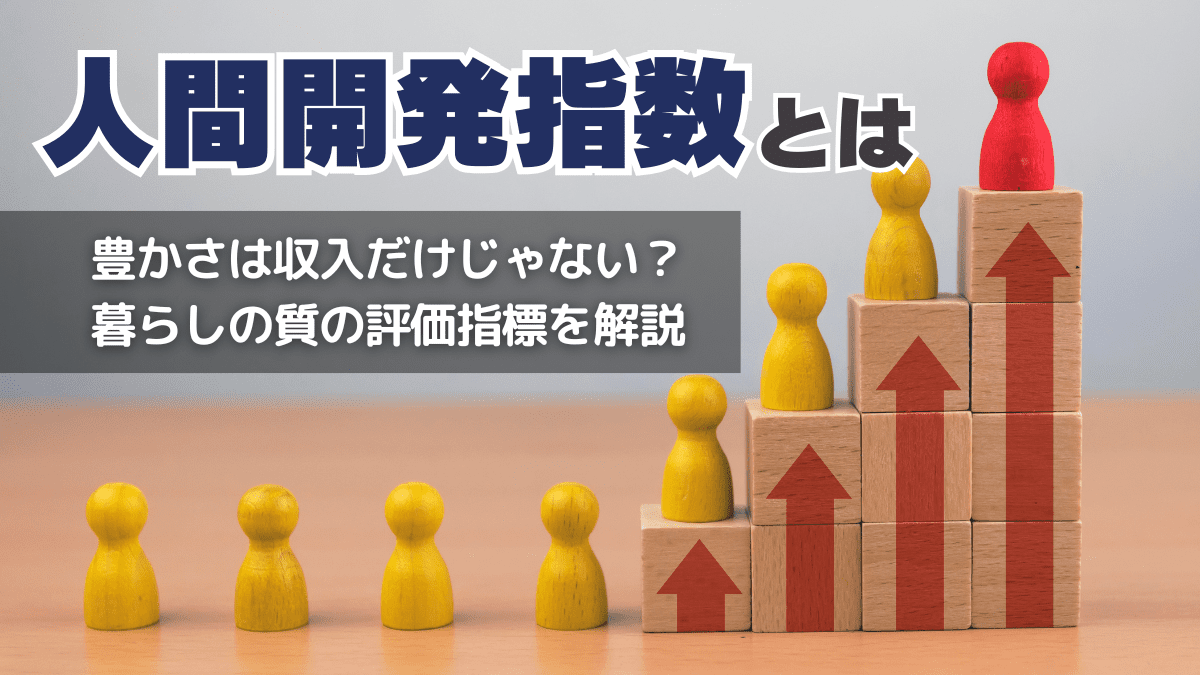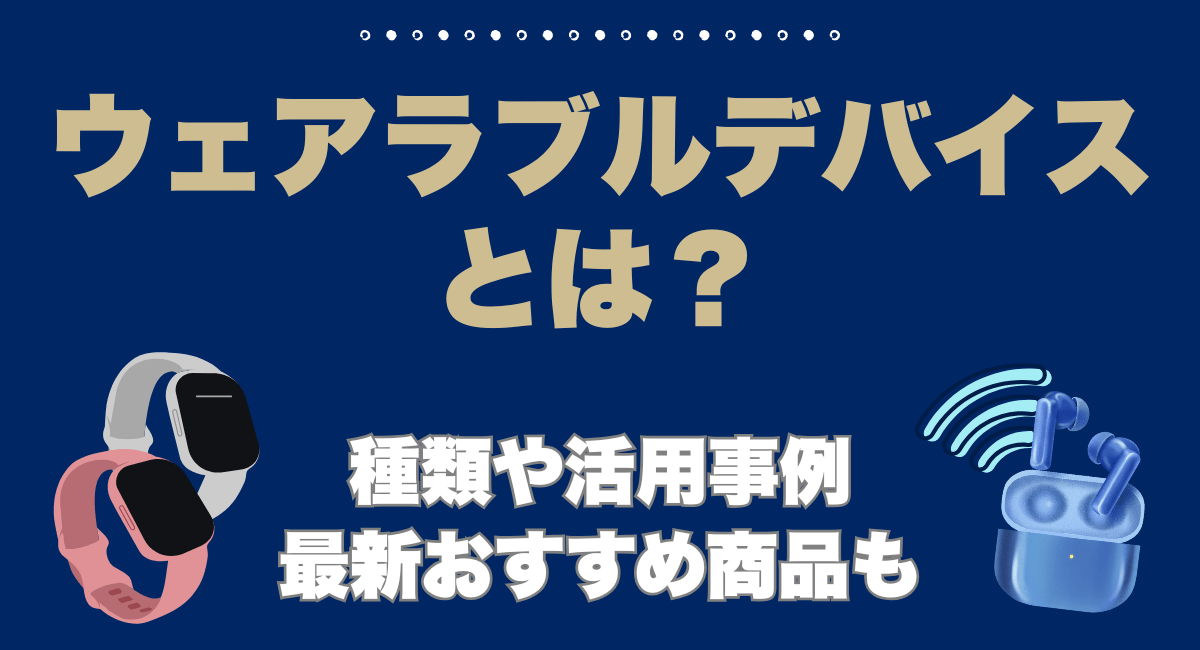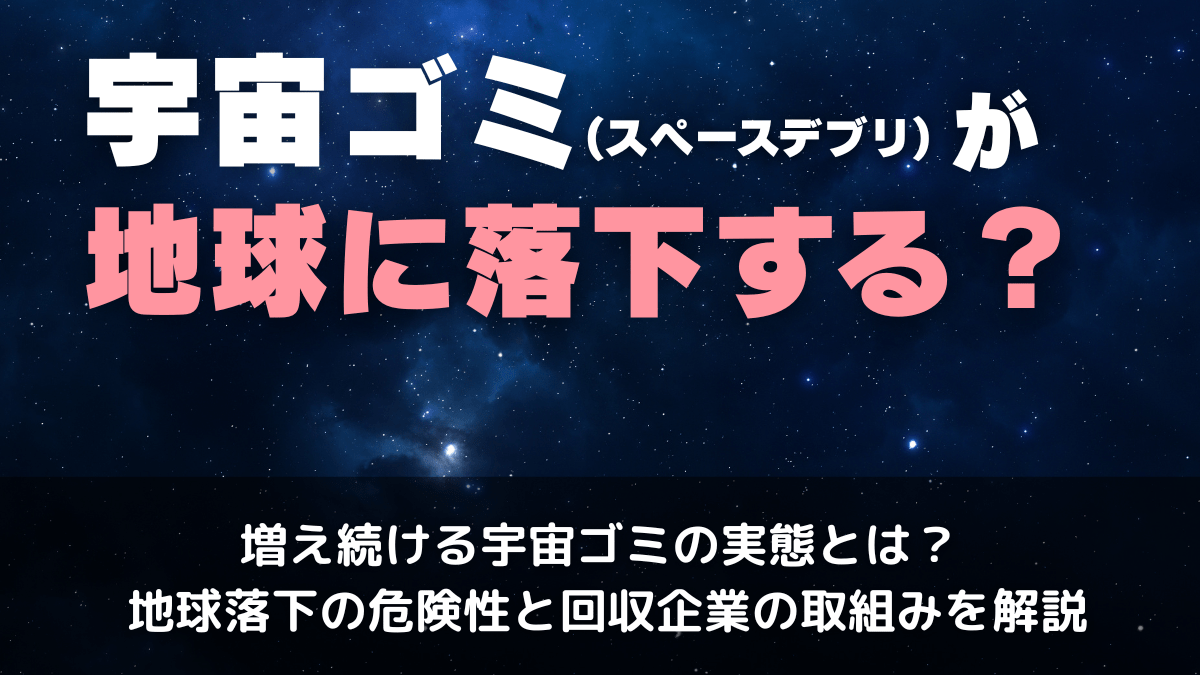インターネットやSNSは、私たちの生活やコミュニケーションを大きく変化させました。
その変化は国や世代を超え、若者や子どもたちの間にもまたたく間に浸透しています。
そんな中、近年問題化しているのがネットいじめの増加です。ネットいじめは今どのようなことになっているのか、なぜ起こるのか、ネットいじめを防ぐにはどんなことをすればいいのか、考えてみましょう。
目次
ネットいじめとは

ネットいじめとは、インターネットでの技術を悪用したいじめ全般で、具体的には、SNSやメッセージアプリ、ゲームアプリなど、インターネット上でのやり取りでの特定の人への中傷や侮辱などを目的に繰り返される行動のことです。
文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校調査」では、ネットいじめを「パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる」ことと定義しています。
ネットいじめは一般的には、主に18歳以下の若年層や学生の間での問題とされています。そのためこの記事でも、ネットいじめは学齢期の子ども〜若者年齢層を対象とします。全年齢に関わるネット上での中傷や侮辱などのトラブルについては、誹謗中傷に関する記事をご覧ください。
ネットいじめの怖さ

ネットいじめは、従来のいじめ(リアルいじめ)の延長線上にあるだけでなく、ネットの特性を反映した独自の問題を抱えています。
広く急速に拡散してしまう
ネットいじめが手に負えないのは、いじめや誹謗中傷が短期間でどこまでも拡散してしまうことです。かつては仲間内だけでとどまっていた情報はSNSの普及によって拡散性が高まり、無関係な外部へも広がりやすくなります。
そうしたネットいじめによる投稿が不特定多数の目に触れてしまえば、最悪の場合被害者当人の個人情報や画像が悪用されたり、犯罪にもつながりかねません。
外部からの発見が困難
ネットいじめは、実態が外部からわからないように行われているケースがほとんどです。
その背景には、児童・生徒のインターネットの利用状況を大人が把握しにくいという問題があります。
また、名前を出さない、呼び名や内容などやりとりが当人たちにしか通じない、発端がはっきりしないなど、加害者や問題の深刻さが表に出にくいことも、ネットいじめを助長させる要因となっています。
逃げ場がない
通常のいじめの場合、別のクラスにする、あるいは転校するなど、加害者と被害者を離すことで一応の収束を見ることがあります。
しかし、ネットいじめは本人がいない所でも時間や場所を問わず行えるため、被害者は逃げ場がありません。加害者は見つかるのを避けるため被害者がいるうちはネットいじめを控えていても、本人がいなくなればばれる心配はないため、さらに増長してしまう危険性もあります。
ネットいじめの具体事例

ネットいじめは年々巧妙になり、その内容も陰湿になっています。その主な手段を具体的な例で紹介していきます。
事例1.学校裏サイトやメールでの悪口・誹謗中傷
初期の頃から行われてきたネットいじめの例としては、メールや学校裏サイト(通学者同士で交流する学校の非公式なサイト)で特定の個人に悪口や誹謗中傷を送るやり方です。
2005年には茨城県の高校に入学した女生徒が、学校裏サイトに自分を中傷する投稿が書き込まれて孤立し、退学を余儀なくされるというケースが起きています。
事例2.LINEでの既読無視による中傷やグループ外し
近年では誰もが連絡手段として活用しているLINEでも、事例1のような悪口や誹謗中傷などによるネットいじめが起きています。特にLINEのグループでは、気に入らない人をグループから強制退会させる「グループ外し」や、退会させた相手の悪口をグループ内で投稿するなどのいじめが少なくありません。
この背景には、LINEで投稿を見たにも関わらず返事をしない「既読無視」「既読スルー」が投稿相手の怒りをかき立て、いじめの原因となるとされています。
事例3.本人になりすましてトラブルを引き起こす
気に入らない相手のアカウントを名乗り、本人になりすまして問題のある投稿を行う事例もあります。
一例として
- 女子高生がプロフィールサイトに援助交際をしているような偽の投稿をでっち上げられ、転校せざるを得なくなった
- 嫌がらせをしたい人の名前を使って他人を中傷するような投稿をする
- 嫌がらせをしたい人の名前を使って他人をLINEのグループから外し、すぐに自分の名前に戻す(LINEのグループ外しは、誰が誰を退会させたかがわかるようになっているため)
などがあります。
こうしたなりすましは、いじめの標的にする児童・生徒を貶めるだけでなく、それ以外の他人をも巻き込むことになるのです。
事例4.娯楽感覚のいじめ動画像視聴・保存や煽り
本人が見られたくない画像や動画を撮影・保存して周囲にばら撒くといった行為も、ネットいじめの一つです。
- いじめられている様子を撮影して視聴する
- 服を脱がせたり、性的な行為を強要して撮影する
- 本人の写真を別画像と合成または加工して投稿する
など、実際のいじめと連動した悪質なやり方が目立ちます。近年は動画がメインのSNSが若年層中心に普及していることもあり、こうした陰湿ないじめ画像を遊び半分で投稿し、仲間内で共有・視聴するというケースも少なくありません。
ネットいじめの現状

インターネットが普及するにつれ、ネットいじめは年を追うごとに増加の一途をたどっています。
文部科学省の統計によれば2006年度は4,883件だったネットいじめは、2022年度には23,920件にまで増え、令和5年度には24,678件にも上ります。
いじめの総認知件数のうち、ネットいじめが占める割合は3.4%と少数です。
しかし、小学校:10,356件(1.8%)/中学校:11,327件(9.2%)/高校:2,724件(15.5%)と、学齢が上がるにつれ、いじめの手段としてネットを使う割合が増えていることがわかります。
ネットいじめの様相が変化
メールやプロフサイト、学校裏サイトなどでの直接的なものが多かった初期のネットいじめは、監視システムやフィルタリングソフトの導入により、グループ内だけで通用する言葉や話題で、特定の個人を公開の場で晒す形で中傷する間接的ないじめに変わっていきました。
LINEやtwitterなどSNSの普及は、こうした傾向に拍車をかけました。ネットいじめはより匿名性が高くなり、加害者の特定がしにくくなったことで、前述の事例のような問題がさらに深刻化しています。
近年の傾向
2015年と2020年の高校生を対象とした調査では、5年間でネットいじめの様相がさらに変化したことが示されています。その主な傾向としては
- 発生率が上昇し、加害者の特定ができなくなっている
- ネットいじめの内容にオンラインゲームの割合が増えている
- 学力上位層にネットいじめの発生率が高くなっている
- 学力が下降した生徒にネットいじめの被害が多くなっている
などの特徴が挙げられています。
ネットいじめが起きる原因

いじめそのものは、インターネットがなくても昔から起きています。その主な原因は嫉妬や恨み、害や不利益を受けたことへの仕返しなどですが、ネットいじめはそれ以外の要因によっても発生し、深刻化していきます。
急速なインターネットの普及とスマートフォンの保持率
ネットいじめが起きる要因として大きいのは、子どもたちの間でのインターネットとスマートフォンの急速な普及です。
日本では令和4年の時点で、
- 中学生の79%、高校生の98%がスマートフォンでインターネットを利用
- 投稿やメッセージの交換はいずれも80〜90%に上る
という状況になっています。
スマートフォンのアプリは心理学的に依存性を高めるように設計されているものが多く、脳への刺激を受けやすい若者は特にスマホやSNSへの依存に陥りやすくなります。
これは日本のみならず世界的に問題視されており、特にSNS依存症はうつ病や神経症などメンタルヘルスへの悪影響が顕著です。そこから他者への攻撃性や自制心の低下などにつながり、ネットいじめに走りやすくなるとされています。

自分の言動への影響に対する無知と無責任
子どもたちの未熟さからくる無知や無自覚も、ネットいじめが起こる原因となります。
子どもの多くは社会経験が乏しいがゆえ、自分の言動が他人や社会に及ぼす影響を自覚も想像できないことがほとんどです。そのため、ふざけ半分や軽い気持ちで行ったいじめで、相手がどれだけ苦しむかということも想像できず、責任の重さも感じません。
誤解を招きやすい書き言葉
メールやLINE、SNSなど、書き言葉が中心でのやり取りの難しさも、ネットいじめに発展しやすい原因です。SNSでの短い文章で、受け手が発信者の意図しない解釈や受け止め方をしたために、口論となったことがある方はよくお分かりでしょう。
また、相手を批判し罵る言葉は口頭よりも文字の方が印象に残りやすく、後で見返すこともあるためネガティブな感情を引き起こしがちです。こうした書き言葉の不用意な使い方が、ネットいじめにつながってしまいます。
匿名性と万能感
SNSの匿名性が高いことも、ネットいじめを引き起こす原因のひとつです。自分だと特定されることがなければ、ネット上で他人を中傷することへの抵抗感は少なくなります。
また、たとえ言ってはいけないことや違法なことでも、注目を集めることで承認欲求を満たされ、万能感を得る人は少なくありません。自分の言動に対する自覚や責任感の薄い子どもなら、なおさらです。
ネットいじめを防止するための具体的な対策

こうしたネットいじめをなくすためには、どのような対策をとればよいのでしょうか。
ここでは、いじめが起きてしまった場合と、事前に起きないための予防策に分けて見ていきたいと思います。
ネットいじめが起きた時の対策
ネットいじめを認識した場合、教職員や保護者は、正確な事実確認と早期発見・早期解決を徹底しましょう。見守る時間は不要です。
対策①証拠の保全と削除要請・事情聴取
対策の最初は、加害者のネット端末を押さえて、いじめの様子や関係するやり取り・動画像などを全て記録し保存することです。これらの証拠がなければ被害者側は裁判での立証が困難になります。
SNSへの投稿の場合は、管理者に対して加害者情報の開示や有害な投稿の削除を要請します。この時には証拠となるスクリーンショットやURLなどの情報が必要です。
合わせて学校側は加害・被害児童や関係者への聞き取りを行います。ここでは当事者への先入観を持たずに、背景や周りの出来事も含めたうえで事実や証拠と照らし、正確な判断に努めることが重要です。
同時に学校側と保護者は、加害生徒を隔離してネット環境を制限し、監視下に置くという対応も必要となります。
対策②学校・教育機関へ対応を求める
次に保護者側は、学校長・教頭・担任または部活顧問など、学校側へ書状を送り、経緯と要求を明確に伝えます。この際には、決して学校を敵対視せず、対応に協力的な教職員を見極めて対応に当たりましょう。
校長や教頭など上の立場の者が非協力的だったり、加害者の謝罪が表面的でしかなかったりなどで対応がうまくいかない場合、さらに上の機関や、外部の機関へ対応を求めます。
具体的には
- 教育委員会
- 文部科学省などの「子ども安全対策支援室」
- 法務省や法務局の人権相談窓口
など、緊急性や事態の深刻さに応じて書状を送付するのが望ましいでしょう。
学校側は被害者の人権を守ることを最優先に対応し、安易に被害者と加害者を対面させるべきではありません。加害生徒に対してはその後の態度や出方を十分に観察した上で、形ばかりの謝罪や反省で終わらせずに、厳格な処分を下す姿勢が重要になります。
対策③警察へ相談する
学校内での対応に限界がある場合は、警察へ捜査を依頼する必要があります。
ただし「いじめがひどいので相談したい」などと言うだけでは、民事不介入を理由に受け付けてもらえないケースも少なくありません。
一方、警察は告訴状や告発を受ければ調書を作成しなければならないため、法律に則った事務的な手続きを行えば受理されます。未成年者でも告訴状の作成や口頭での告訴が可能なので、加害の事実を特定できる証拠と共に手続きを行います。
ネットいじめを起こさない防止策

事前にネットいじめを起こさないためには、普段からの教育が重要になってきます。特に、日本の学校ではインターネットやSNSの使い方を教える教育が十分とは言えないのが現状です。
対策①大人がネットやSNSに精通する
子どもたちがネットでのトラブルに対処できる力を養うには、保護者・教職員自身がSNSやインターネットを十分に使いこなし、正しい使い方や問題点を指導できるようになることが大事です。
また、現場の教職員もSNSを活用することで、子どもの様子やいじめの兆候などを共有できる体制を作ることで、いじめの早期発見・早期解決にも効果を発揮します。
対策②子どもたちのリアルな関係を観察する
保護者・教職員は、常に子どもの様子を注意深く観察し、気を配り続ける必要があります。
ネットいじめはリアルな関係を反映していることが多いため、普段と変わった兆候が見受けられた場合は慎重に対応しなくてはなりません。
保護者は日頃から積極的に子どもと会話することを意識し、子どもが親に相談しやすい環境を作りましょう。
対策③情報コミュニケーションに対するトレーニングを行う
情報教育では、情報通信の仕組みやコミュニケーションが上手くいかなくなる理由、そこからネットいじめが起こる原理などを、コンピュータを使わずに教える方法もあります。
これは主に年齢の低い子どもたちを対象に、実際にネットで大きなトラブルを起こす前に、教師の管理下によって小さな失敗をシミュレーションで経験させるというものです。
これにより、ネットでやってはいけないことやその理由を、身をもって知ることができます。
対策④いじめる側の理屈を突き崩す
いじめ加害者は「いじめられる側にも問題がある」という言い訳をよく行います。
ネットいじめに限らずいじめを未然に防ぐためには、その言い分には正当性がなく、いじめを行なって良い理由などないということを理解させなければなりません。
そのためには教師が加害者の言い訳を聞いた上で、その正当性を突き詰めさせ、自らの間違いに気付かせることが重要です。
ネットいじめに関してよくある疑問

この章では、ネットいじめに関する多くの疑問について特に関心の高いものを取り上げていきます。
ネットいじめが原因で死亡した例もある?
ネットいじめは子どもや若者のメンタルヘルスに負の影響を与えます。被害者は特に強いストレスや不安などがもとで、双極性障害や睡眠障害、神経症などを引き起こし、強い孤立感が自殺や他害を引き起こします。
ネットいじめによる自殺は、日本のみならず、世界各国で大きな社会問題となりつつあります。
規制する法律はないの?
ネットいじめはインターネットにおける誹謗中傷の問題とも地続きであり、同様の民事・刑事罰が適用されます。具体的には
- 侮辱罪…令和4年の刑法等改正で厳罰化
- 名誉毀損罪
- 傷害罪…いじめによる心的外傷後ストレス障害(PTSD)も傷害罪となりうる
- 脅迫罪…身体への危害を告知する、平穏な学校生活ができなくなるよう脅す行為
- 強要罪
などをはじめとする、さまざまな罪状に該当する場合があります。
未成年の場合でもその罪状によって逮捕される可能性があり、家庭裁判所での審判によって
- 保護観察
- 少年院送致
- 児童自立支援施設等送致
- 都道府県知事または児童相談所長送致
といった処分が下され、より重大な事件の場合は検察官へ送致されることになっています。
SNSの利用を禁止すべき?
先日、オーストラリアで16歳未満のSNS利用を禁止する法律が可決されたことが話題となりました。これを受けて、同様に子どものSNS利用制限を検討する国も出ています。
しかし、SNSの普及率がネットいじめや自殺を助長するという因果関係は証明されていません。
むしろSNSやネットに対する経験やリテラシーの不足がネットいじめを深刻化させるという例も多く、SNS禁止をめぐる議論にも賛否が分かれています。
ネットいじめ対策とSDGs

ネットいじめに適切な対策を行うことは、SDGs(持続可能な開発目標)とも関連してきます。
特に大きく関わってくるのが
- 目標4.質の高い教育をみんなに
- 目標16.平和と公正をすべての人に
です。
すべての子どもたちが正しいネットリテラシーを身につけ、安心して学べる環境を作ることで、公正で質の高い教育機会の確保が実現できます。
また、ネット空間も含めたあらゆる場所でのいじめを根絶することで、すべての子どもや若者に平和と公平さをもたらすことになります。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ

インターネットやSNSは便利で楽しい反面、誤った使い方は子どもたちにとって危険で有害なものとなります。小さな言葉が誰かを深く傷つけることがあることを、改めて理解しなければなりません。そのためには、大人が正しいネットやSNSの使い方を教え、子どもたちを注意深く見守りながら正しい使い方を習得できるようにすることが大事です。子どもたち一人ひとりが思いやりのあるネット社会を築いていけるよう、社会全体で手本を示していきましょう。
参考文献・資料
ネットいじめの構造と対処・予防:加納寛子 (編著) 内藤朝雄・西川純・藤川大祐(著)/金子書房,2016年
令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果 本体資料
子供のネットいじめの主な原因や兆候、そして対策を解説 | McAfee Blog
ネットいじめの現状と課題 : 子どもたちの磁場で何が起きているのか / 原清治 – 佛教大学
徐莉/小原一馬,ネットいじめが発生する要因に対する研究 宇都宮大学共同教育学部研究紀要. 第1部 73号
西川友子,金子夢,ネットいじめの実態とその対策 生活文化研究所報告 第48号 山形県公立大学法人学術機関リポジトリ
ネットいじめから子どもを守る–根本原因はリアルと同じ – ZDNET Japan
【事例で学ぶ】学校裏サイトによるネットいじめ~元同級生に慰謝料請求したケース | 弁護士保険の教科書ー弁護士監修ー
ネットいじめ・ 学校裏サイトの現実|相談室だよりだより2008
どこからが誹謗中傷となる?過去の事件・事例をもとに対応や対策例を解説 – Spaceship Earth(スペースシップ・アース)|SDGs・ESGの取り組み事例から私たちにできる情報をすべての人に提供するメディア
大人も陥るかも…スマホ依存症の恐ろしさとは?診断方法や治し方と対策 – Spaceship Earth(スペースシップ・アース)|SDGs・ESGの取り組み事例から私たちにできる情報をすべての人に提供するメディア
いじめは犯罪? 加害者の子どもが問われうる罪と逮捕されうるケース|ベリーベスト法律事務所 大宮オフィス
この記事を書いた人
shishido ライター
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。