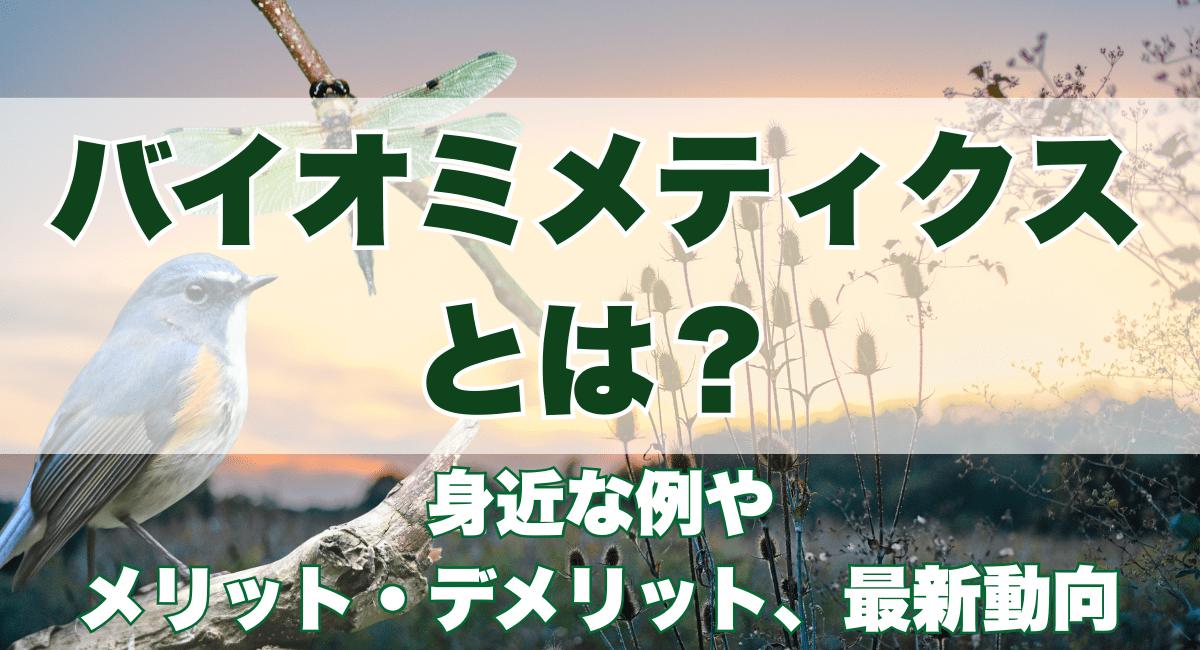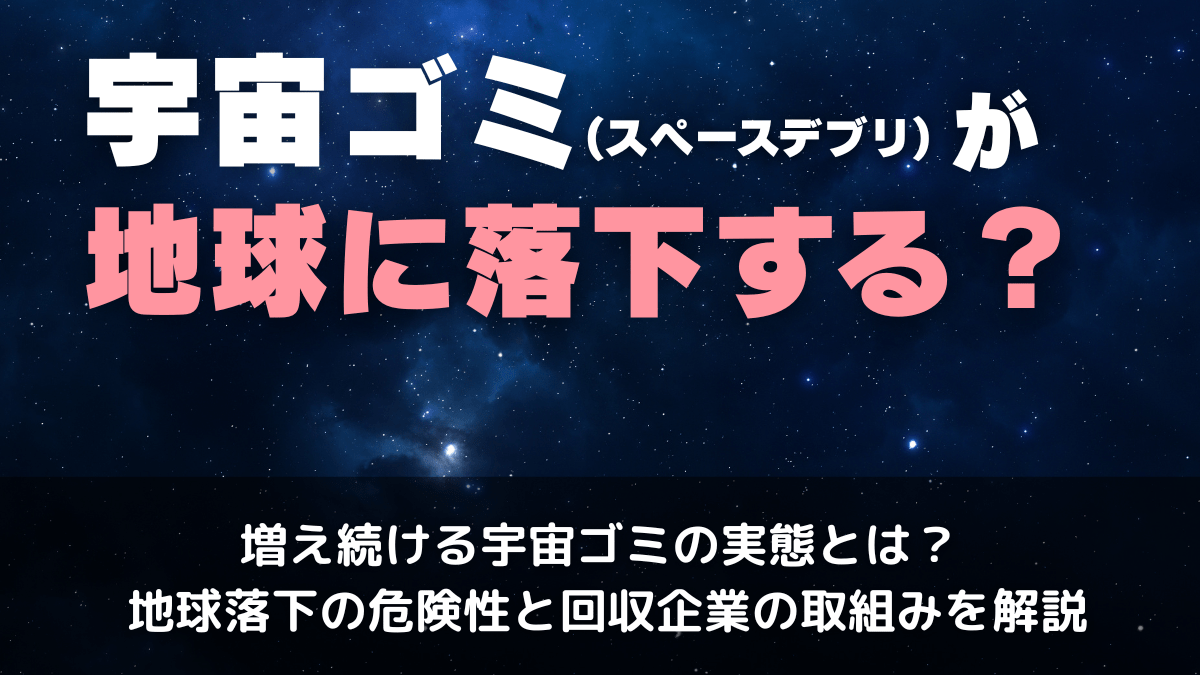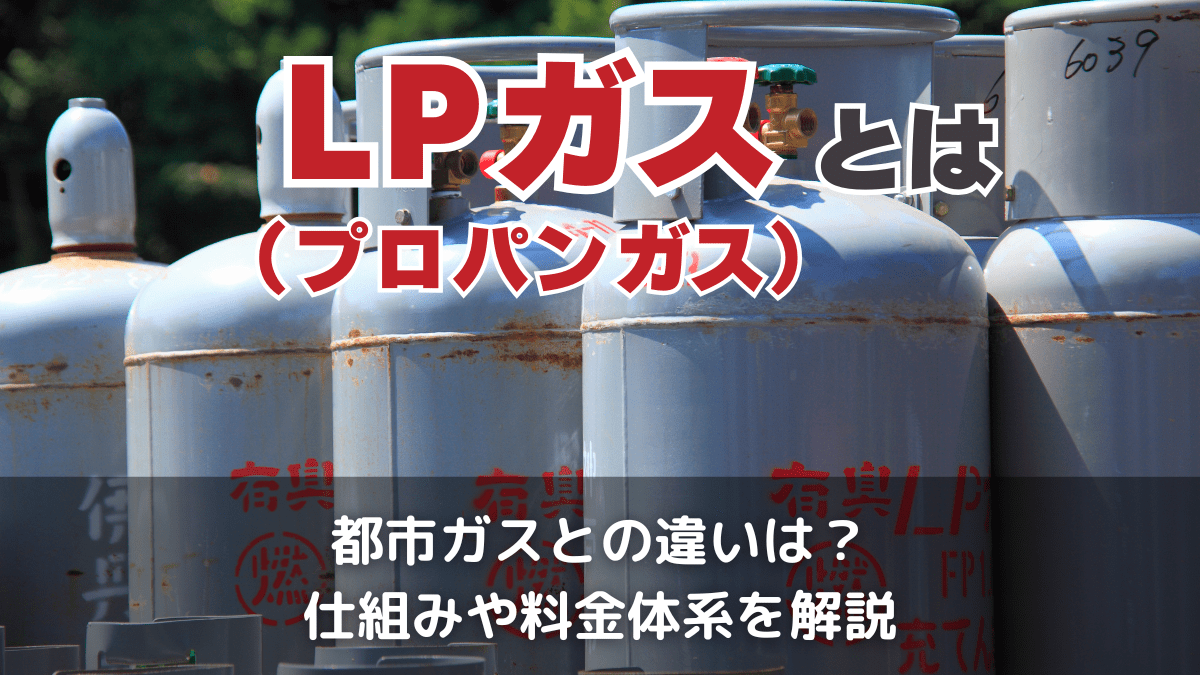株式会社ニッポン手仕事図鑑 藤本稀恵さん 安江和さん インタビュー

藤本稀恵
2023年よりニッポン手仕事図鑑に入社。プランナー/ディレクター

安江和
2024年よりニッポン手仕事図鑑に入社。プランナー/ディレクター
目次
introduction
日本が誇る文化や職人技を、職人へのインタビューとともに紹介していく動画メディア「ニッポン手仕事図鑑」。10分の動画の中に熟練の「手仕事」と職人の想いが凝縮されています。インタビューを続ける中で浮かび上がってきたのは、匠の技と同時に「後継者不足」の現実。同社は、日本の手仕事を真に未来に残すために、職人と職人を目指す若者を繋ぐ「後継者育成事業」にも着手しました。
今回は、同社の藤本稀恵さん、安江和さんに、「ニッポンの手仕事」を未来に残していくための事業の現状や展望を伺いました。
土地の個性を作り出すのは、そこで働く人々
-まずは、事業内容の概略をご紹介ください。
安江さん:
弊社は、日本全国各地の「手仕事」や「産地」の課題解決に向けて、様々な事業を展開しています。各地の手仕事を紹介する動画メディアの運営からスタートしましたが、現在では、その取材過程で知ることになった後継者不足への支援「後継者育成インターンシップ」事業も大きな柱です。さらに、職人さんの商品開発への協力、職人さんそれぞれの課題に応じたサポートとしてSNSやECショップ制作、映像制作などの講座、手仕事・伝統工芸に関するイベントの運営なども手がけています。
-「ニッポン手仕事図鑑」はどのような背景で誕生したのでしょうか?そこには、どんなビジョンや夢があったのですか?
安江さん:
創業者であり編集長の大牧圭吾は、もともと「地方といわれる地域を元気にする」手伝いをしたい、という気持ちが強かったんです。日本自体にも、自分の子どもたちが、将来「日本大好き!」と思えるような国であり続けてほしい、という思いがあり、何か行動をしたいと模索していました。
そんな中、年齢を重ねるごとに、幼いころから親しんでいた故郷長野県の個性や文化が失われていることに気づき、危機感を覚えました。その対応策に考えを巡らせているうち、結局、土地の個性を作り出すのは「そこで働く人々」では?と感じたそうです。そして、そのような人々が注目されることで「土地の個性」を残していける、という考えに至り、「手仕事の紹介」を思い立ったとのことです。
ライティングの仕事もしていたことから、文字媒体のメディアも考えたのですが、やはり職人さんの言葉や想い、作品などをよりリアルに伝えられるのは動画だと定め、2015年に「ニッポンの手仕事を、残していく」をコンセプトとして、動画メディア「ニッポン手仕事図鑑」を立ち上げました。株式会社としての設立は2019年になります。
スター選手ではなく、埋もれている人を取り上げる


-「職人図鑑」や「伝統工芸図鑑」ではなく、あえて「手仕事図鑑」とされたのはなぜでしょうか?御社の「手仕事」の定義も合わせ、お聞かせください。
安江さん:
私たちは、いわゆる「職人」といわれている職業や伝統工芸という分野に限らず、農業、漁業、林業といった一次産業の職業や、街の食堂の料理などまで含め、すべて「手仕事」ととらえています。これは、街の個性や文化を生み出しているのは、そのような方々だと考えているからです。将来的には、様々なジャンルに関わっていきたいですね。
藤本さん:
弊社の「手仕事の定義」ということでは、「ものづくりの仕事」「手を使って何かを生み出す仕事」を「手仕事」と捉えています。ただ、現状では、動画制作のキャパシティがまだ限られており、すべてにフォーカスできていないのが心苦しいところです。
-動画に登場する「手仕事」は、全国多岐にわたり、かつ周知されていないものも多いと感じます。どのようにして出会いを作られてきたのですか?
安江さん:
現在、弊社は都道府県や市区町村などの自治体と事業をさせていただくことが多くなっています。動画などを制作するにあたっても、自治体とまず最初に話し、そこから組合とか工房を紹介していただく場合が多々あります。一連の動画シリーズとは別枠になりますが、自治体のほうからPR動画の作成をご依頼いただくケースもあります。
もともと、誰もが知るスタ―選手を取り上げるより、埋もれていらっしゃる方、スポットライトを浴びる機会を得られていない方を取り上げたいと思っていますので、いろいろな繋がりを通じて探し出す場合もあります。
広告になることを避けるために貫きつづけた自費制作


-動画作成対象が決定してから作品に完結するまでのプロセスを教えてください。
安江さん:
撮影する工房や職人さんが決まってからは、直接職人さんとやりとりさせていただきます。現地で1~2日かけて撮影したあとは、すべてこちらで編集をします。「ニッポン手仕事図鑑」に掲載している動画に関しては、職人さんからこういう内容にしたい、というような意向を伺って作ることはしていません。「日本で一番職人さんを愛するメディア」として、職人さんからお金はいただいていないのですが、その分、職人さん主導の宣伝動画ではなく、「手仕事を残すための映像作り」という一点を目標として完成させます。それが、ずっと自費で作ってきたことの背景です。
-事業をサステナブルなものとするためにも、経済的な基盤は大切なところですが、どのようにして「自費制作」を貫いてきたのですか?
藤本さん:
もともとは、ファストコムという会社の一事業として生まれたのが「ニッポン手仕事図鑑」で、WEB制作や映像制作であげた利益を使っての自費制作でした。大牧がこの事業を立ち上げた時、最初の予算はわずか5万円だったそうです。株式会社として子会社化した現在は、さまざまな事業を手がけていますので、これまでと同様に他の事業であげた利益の一部を映像制作の費用として充てることで、自費制作を貫いています。
-個々の動画、また「ニッポン手仕事図鑑」全体としてどのような成果を感じていますか?
安江さん:
現時点での最新動画で取り上げた「芦屋釜」の例をご紹介します。700年ほど前に福岡県芦屋町で誕生した「芦屋釜」は、茶の湯釜として南北朝時代の貴族に人気でしたが、江戸時代に製作が途絶え、現代の職人さんが復活させた工芸です。
後継者インターンシップを一度行いましたが、知名度が低く、なかなか募集が集まりづらいという問題がありました。その後、映像を作って公開し、2回目のインターンシップの際に再度募集したところ、応募数が倍になっています。やはり、映像での発信は知名度に直接的につながっていきます。


メインの動画シリーズとは異なりますが、Bar KOBOという名称で、職人さん同士がフリートークする動画も発信しています。通常の動画制作でも同様ですが、このような場で職人さんと弊社、職人さん同士、という繋がりができることにより、新しい仕事が生まれることがあるんです。たとえば、とある企業広告で職人さんを紹介する企画で、弊社が職人さんのキャスティングを行いました。このように、これまで培ってきた繋がりから別の企業様との案件に広がり、さらには広告に出演いただいた職人さんの作品の展示販売イベントにまで発展しました。イベント内では職人さんのトークショーも開催しました。
そのような形で、動画が様々な繋がりを生み、そこから伝統工芸に関する新しい仕事をご依頼くださるという循環も発生しています。
「後継者不足の産地」と「職人になりたい若者」を繋ぐ
-小さな伝統工芸で組合も横の繋がりもない場合はなお、「ニッポン手仕事図鑑」は頼もしい存在ですね。ましてや、後継者育成のサポートまでされています。その事業を手がけたきっかけや内容の詳細をご紹介ください。
安江さん:
日本の手仕事をめぐって日本各地をまわる中で、産地や工房を訪れた時に必ず話題になったのが「後継者不足」でした。きわめて深刻な問題でありながら、その課題に取り組んでいる人も企業もなかったんです。そこで、日本の伝統産業を守るために、自分たちが一歩を踏み出そうと考えました。
産地の職人さんは、(職人になりたいという若者はいない)と思いこんでいる場合が多いんです。ですが、職人やものづくりを志す人が通うものづくり系の学校は、全国に140校以上あります。その中には、伝統工芸の職人になりたいと考えている若者もたくさんいます。産地側は人の採用に慣れていないし、学生側はその産地との関係性や繋がりを作ることが難しい。
確かに、伝統工芸は、求人サイトに出てくるような業界ではありません。結局「職人を目指す学生の8割は職人になれずに卒業していく」という話を聞いたこともあります。そのような状況と課題がある中、「後継者不足に悩む産地」と「職人になりたい学生や若者」をマッチングする仲介役として誕生したのが「後継者育成インターンシップ」です。
藤本さん:
インターンシップの募集をする際は、まずものづくり系の学校にポスターを貼らせていただきます。京都には伝統工芸大学校という伝統工芸の技術校がありますし、全国に美術大学、工芸系、美術系専門学校がある中、ものづくりを目指す学生たちがポスターを見て、関心のあるジャンルのインターンシップに応募してくれます。

秋田に樺細工という桜を使った伝統工芸がありますが、その工芸品の商品開発に携われるインターンシップに参加した8人のうち、その以前から樺細工を知っていた学生はわずか1名でした。7名が樺細工を知ったきっかけは、インターンシップのポスターなんです。また、「伝統工芸インターン」という公式ラインを運営していますので、そこから流れてきたものをきっかけに興味を持った、という方々もいますね。
応募してくださる学生のすべてがインターンシップに進めるわけではなく、「エントリーシート」と「オンラインのグループ面接」という2段階の選考プロセスがあります。
採用を目的としたインターンシップの通過者は、それぞれのジャンルで基本的に6名ほどです。通過した参加者は、職人さんの工房で2日間の実習となります。技術はもちろんですが、職人さんとの相性など様々な点を見ますので、時間をかけた面接のような意味もあります。
採用段階の話でいえば、正規雇用もあります。個人事業主でもフルタイムで雇用するパターンがありますし、いきなり正規雇用は難しい、という場合は他のアルバイトなどをしながらという「兼業型」で採用するケースもあります。
-後継者育成という意味で、現時点でどのような成果が見られていますか?
藤本さん:
この3年間で、内定者は50名を超えています。例として、佐賀県武推市で作られている西川登竹細工でのケースを挙げさせていただきます。明治初期から続いてきたこの竹細工ですが、現在、その伝統を受け継ぐ事業者が残りわずかとなっています。この竹細工を残さねばと、佐賀県庁主催の「西川登竹細工の仕事体験インターンシップ」を実施することになりました。
とても熱心にものづくりに取り組む学生が6名参加し、職人さんご夫婦も彼らと対話を重ねる中で、こんなに自分の仕事に興味を持ってくれる若い人々がいるんだ、と驚かれ、結果として「この子だったら職人として、育てていきたい」という出会いが生まれました。そのインターンシップ生は、現在佐賀県に移住し、伝統を受け継いでいます。
もう一つ、日光市主催の「日光彫」インターンシップの例をご紹介します。日光彫は日光の観光資源にもなっている伝統工芸です。その体験教室があるからこそ、小学生の修学旅行先に選ばれたりもしている地域の代表産業です。代表が職人さんたちのご高齢化を課題視され、、後継者を残すためにインターンシップの実施を決意されました。
ただ、フルタイムの雇用は難しいということで兼業型の募集となりましたが、採用となった方は、この4月から飲食店で働きながらすでに日光彫の商品も作っています。先日訪問してみたのですが、しっかりと活躍されていました。
-若い後継者の方々の活躍は頼もしいですね。最後に今後の展望をお聞かせください。
安江さん:
大きく分けて2つあります。1つ目は、「年間100人の後継者を産地に」という目標の達成です。全国各地にはまだまだ様々な産地がありますので、しっかりと後継者を育成していきたいと考えています。
2つ目は、職人さんが「ものづくり」以外の技術を磨き、それを通じてご自身の収入アップを可能にするためのサポートです。例えば、SNSやクラウドファンディング、ECサイトをうまく使っての宣伝や販売などは、「ものづくり」以外での能力が必要となります。そのような得意分野がある職人さんに講師となっていただき講座やスクールを開催すれば、それもまたものづくり以外の収入ですし、イベントのトークショーなどでお話をしていただくことなども、ものづくり以外で収入源となりうる部分だと思っています。そのような知識やスキルをお互いに共有できるオンラインスクールの開催などを企画したいですね。
-誰もが「伝統の技が消えてほしくない」と漠然とは思う中、数々の効果的、具体的な施策に挑まれていることに感動しました。今日は貴重なお話をありがとうございました。
株式会社ニッポンの手仕事図鑑公式HP:https://nippon-teshigoto.jp/
この記事を書いた人
壱岐 梢 ライター
ライティング、詩作、翻訳…様々なかたちで言葉と共に仕事をしています。 この世界に入ったきっかけは、宮沢賢治との出会いでした。彼は究極のSDGs 実践者。大好きな言葉の仕事によって、今SDGsに取り組む皆様をご紹介 できることは、大きな喜びです。
ライティング、詩作、翻訳…様々なかたちで言葉と共に仕事をしています。 この世界に入ったきっかけは、宮沢賢治との出会いでした。彼は究極のSDGs 実践者。大好きな言葉の仕事によって、今SDGsに取り組む皆様をご紹介 できることは、大きな喜びです。