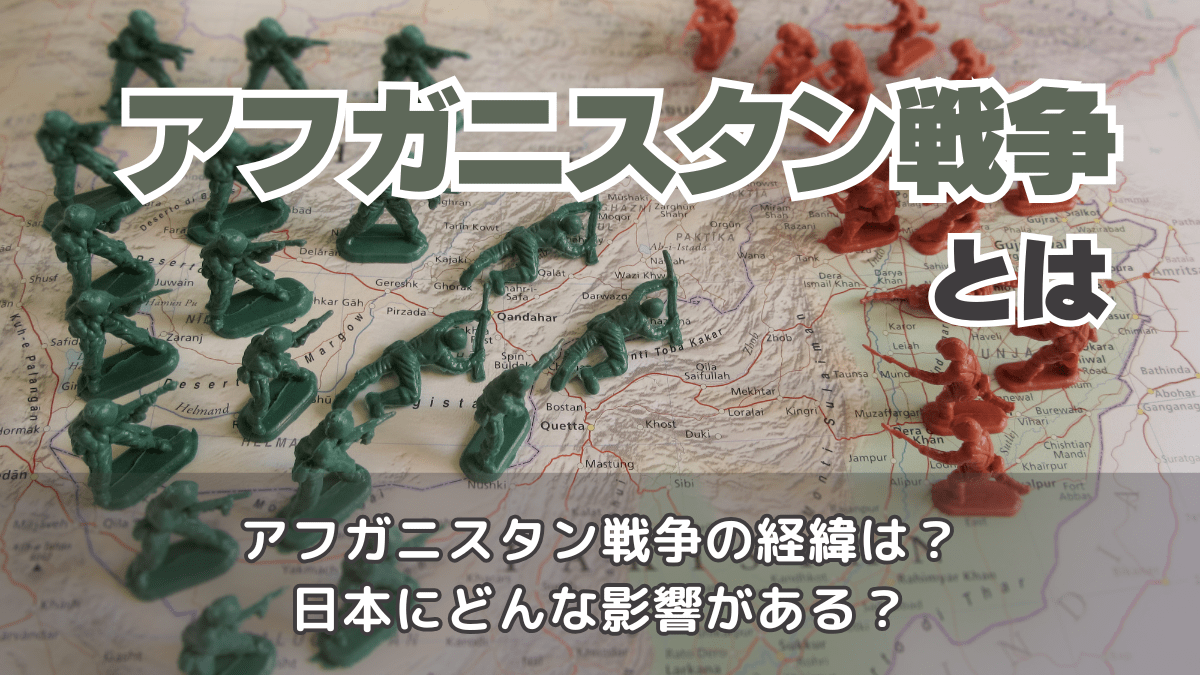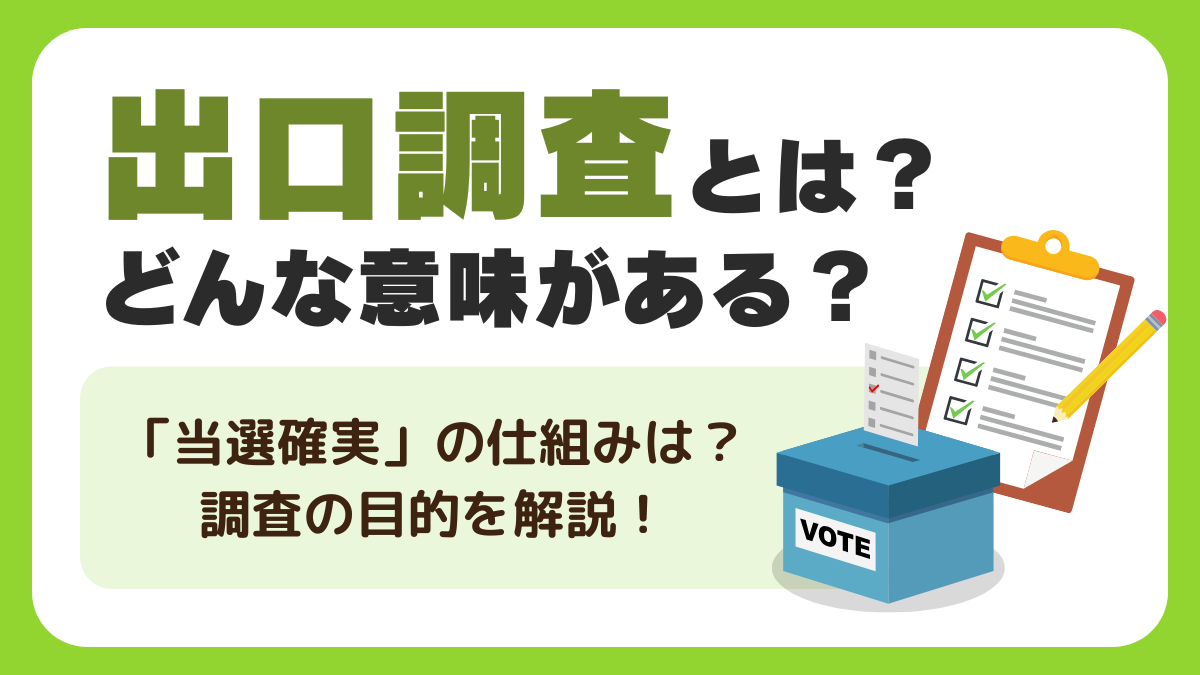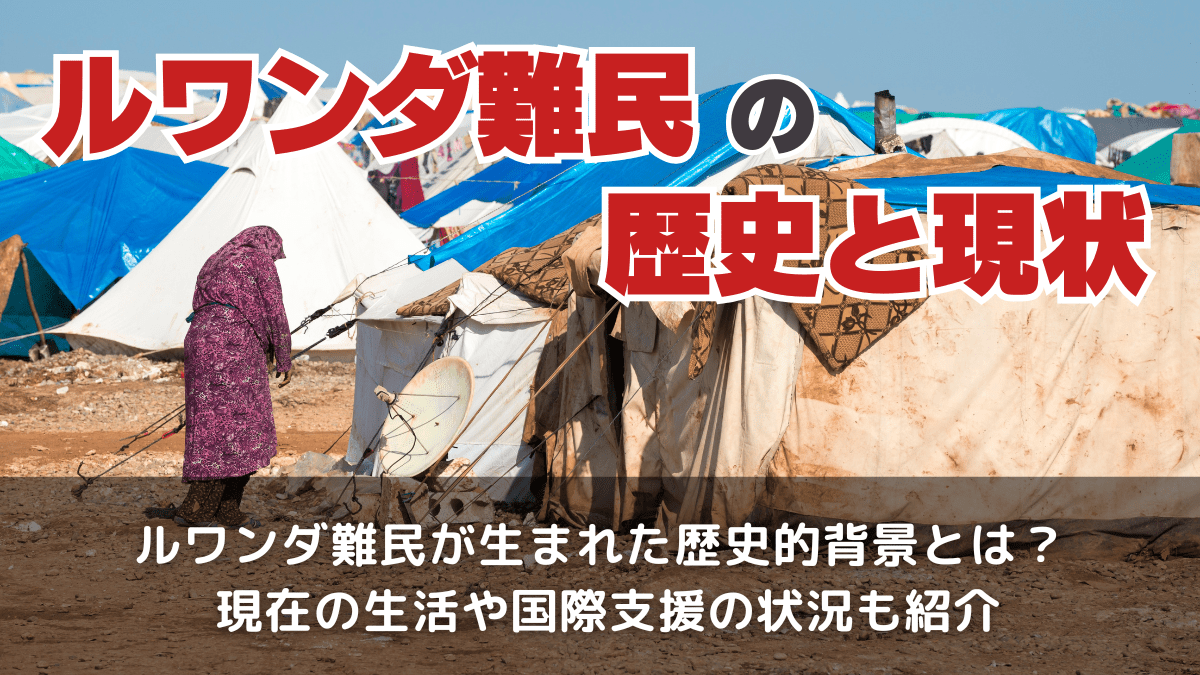1945年8月22日、真っ暗な海を進む一隻の船がありました。船内には、沖縄から疎開してきた学童など多くの疎開民が乗っていました。しかし、彼らは疎開先にたどり着くことができませんでした。
アメリカ軍の魚雷が船体を切り裂き、海は一瞬にして阿鼻叫喚の渦と化したのです。これが、多くの尊い命を奪った「対馬丸事件」です。
なぜ、非武装の民間人を乗せた船が攻撃の対象となったのでしょうか?そこには、戦争の悲惨さとともに、歴史の闇に葬り去られようとした真実が隠されていました。今回は、語り継がれるべき「対馬丸事件」について紹介します。
目次
対馬丸事件とは

対馬丸事件とは、疎開船として那覇から長崎に向かった対馬丸が、アメリカ軍の潜水艦に撃沈された事件のことです*1)。対馬丸は、トカラ列島の悪石島周辺の海域でアメリカ海軍の潜水艦ボーフィン号の魚雷攻撃で撃沈されました。
対馬丸は陸軍が使用した船
1912年に建造された対馬丸は、当初から貨物船として世界中の海を航行し、様々な物資の輸送を行っていました。太平洋戦争が始まった1941年からは日本陸軍の輸送船として使用され、敵の潜水艦による攻撃を何度も切り抜けながら、戦時下での物資輸送を担っていました。
悲劇的な対馬丸事件の直前には、中国の上海から沖縄への兵員輸送任務に就いており、那覇港に停泊していました。この船は、平時から戦時まで、日本の海上輸送を支える重要な役割を果たしていたのです。
事件の経緯
1944年8月21日、対馬丸は疎開する沖縄の人々や学童疎開の児童ら約1,800名を乗せ、長崎を目指し那覇港を出港しました。元は貨物船だった対馬丸は兵員輸送用に改造され、船倉には二段の棚が設置されるなど、大変な過密状態で、蒸し暑く、とても睡眠に適した環境ではありませんでした。
この対馬丸を、アメリカ潜水艦ボーフィン号が上海出発時から標的に定め、執拗に追跡していました。那覇港入港前から追跡を続けていたボーフィン号は、22日早朝、再びその姿を現します。
そして、乗客が就寝中の深夜、ついに攻撃を開始します。対馬丸はわずか10分足らずで沈没してしまいました*3)。
漂流する人々
真夜中、対馬丸はアメリカ軍の魚雷攻撃を受け、一瞬にして海の底へと沈んでいきました。乗船していた人々は、逃げ惑う間もなく暗い海へと投げ出されました。そこは「七島灘」と呼ばれる、流れの速い海域です。さらに、台風が接近していたため、海は荒れ狂い、高い波が容赦なく彼らを襲いました。
海水は冷たく、体力を奪い、吐き気をもよおします。恐怖と寒さで、意識が朦朧とする人もいました。それでも、島影を目指して必死に泳ぎ続ける者、浮遊物にしがみつきながら救助を待つ者、それぞれの方法で生きようとしました。
しかし、漂流が長引くにつれ、体力は限界に達し、希望は次第に絶望へと変わっていきました。そして多くの命が、海の藻屑と消えていったのです*3)。
生存者の救出と遺体の漂着
対馬丸の生存者を最初に見つけたのは、佐世保大村飛行場所属のパイロットたちです。彼らは、木片につかまったり、イカダに乗ったりしている漂流者たちの顔をはっきり見たといいます。その後、パイロットたちは付近で漁を行っていた2隻の船に状況を知らせ、救助を依頼しました*3)。
現場に到着した2隻のカツオ漁船が見たのは、無数の遺体でした。しかし、小さな漁船は遺体を収容できるほどのスペースがなかったため、やむなく、生存者のみを救出します。
対馬丸の撃沈から6日後、奄美大島の北東部の海岸線に多くの遺体が漂着しました。その一方で、21名の生存者が保護され、宇検島の集会場などで手厚く保護されます。
対馬丸事件の被害者数
対馬丸事件の被害者は、以下の通りです。
【対馬丸事件の犠牲者(氏名判別者数)】
| 疎開児童 | 784名 |
| 訓導・世話人 | 30名 |
| 一般疎開者 | 625名 |
| 船員 | 24名 |
| 船舶砲兵隊 | 21名 |
| 合計 | 1,484名 |
対馬丸に乗っていた人は、合計1,788名であったことを考えると、およそ83%が亡くなったことになります*4)。
そもそも疎開とは

学童疎開とは、戦争の状況が悪化する中、国が都市部の国民学校初等科に通う子どもたちを、空襲の被害を受けにくい郊外や農村部に一時的に移住させた措置のことです。目的は、子どもたちの命を守ること、空襲時の混乱を避けること、そして戦意の衰えを防ぐことにありました。
集団疎開によって、子どもたちへの被害を最小限に抑えようとしたのです。子どもたちは見知らぬ土地で生活を送ることになり、家族と離れ離れになる寂しさや不安、生活環境の違いに苦しむことになりました。
学童疎開についてより詳しく見てみましょう。
大都市を中心に実施された
学童疎開の対象となったのは、東京、横浜、川崎、大阪、神戸、名古屋といった大都市を中心に、全国18都市の国民学校初等科3〜6年生でした。
これらの都市は、軍事工場や軍需施設が集中しており、空襲による被害が特に懸念されたためです。1944年から始まった学童疎開では、およそ46万人もの児童が、全国7,000か所の疎開先に集団で生活を送ることとなりました。
沖縄では沖縄戦に備えて学童疎開が実施された
サイパンが陥落した1944年7月、政府は沖縄県知事に非戦闘員(老人・女性・児童など)10万人を本土または台湾に疎開させる命令を出しました。疎開児童の保護者の一部は、軍艦で児童を輸送するよう軍に要請しました。しかし、軍艦が不足していたため、輸送船で疎開することになったのです*3)。
8月以降、学童を含む疎開者を乗せた船は、次々と沖縄から離れていきました。対馬丸もこうした船のうちの一隻です。
【関連記事】学童疎開とは?目的や一日の流れなどをわかりやすく!
対馬丸はなぜ狙われたのか

対馬丸は、上海を出港した段階からアメリカの潜水艦に狙われていました。なぜ、アメリカ軍は輸送船である対馬丸を狙ったのでしょうか。それを理解するには、通商破壊作戦について理解する必要があります。
対馬丸攻撃は通商破壊作戦の一環
アメリカ軍は太平洋戦争中、日本の海上輸送を妨害するため、通商破壊作戦を展開していました。この作戦は、敵国の輸送船を攻撃して物資や人員の移動を阻止するもので、第一次世界大戦でドイツが実施した作戦と同様の戦術でした。
アメリカ軍の潜水艦は、日本の輸送船を次々と撃沈し、日本の物資輸送に大きな打撃を与えました。1944年に起きた対馬丸撃沈事件も、このアメリカ軍による通商破壊作戦の一環として実行されたものでした。
対馬丸の撃沈も、このようなアメリカ軍による通商破壊作戦によって起こった悲劇でした。多くの民間人を乗せていた対馬丸の撃沈は、対馬丸や疎開児童・民間人を狙ったというよりも、通商破壊作戦の一環として遂行されたのです。
太平洋戦争では軍艦以外に多くの船が撃沈された
全日本海員組合が算出した被害総数を見ると、官民の一般汽船や機帆船、漁船など7,240隻が戦争によって沈められています*5)。また、日本殉職船員顕彰会がまとめたデータによると、6万人以上の方が戦死したことがわかります*6)。
このように、アメリカ軍による通商破壊作戦は日本の船と船員に大きなダメージを与えました。その結果、日本国内の流通は滞り、物資の輸送もままならない状況となってしまったのです。
対馬丸事件のその後

対馬丸事件は戦後も長らく、その全容が明らかにされることはありませんでした。事件発生当時、軍の箝口令により、生存者や関係者たちは事件について口を閉ざすことを余儀なくされたからです。ここでは、軍による箝口令や戦後の遺族会の活動について紹介します。
軍の箝口令で口外が禁じられた
第二次世界大戦中に起きた対馬丸撃沈事件は、警察や憲兵による厳しい情報統制の対象となりました*7)。この情報統制は「箝口令」と呼ばれ、事件に関するあらゆる情報の公開や話題にすることが固く禁止されました。
そのため、生存者も事件について語ることができず、正確な死傷者数の把握も困難を極めました。沖縄に残された家族や関係者たちにも、真実は伝えられませんでした。
しかし、疎開先の家族からの便りが途絶えたことなどから、やがて対馬丸の悲劇は人々の知るところとなっていきました。
対馬丸事件後の沖縄
対馬丸撃沈から7か月後の1945年3月末、沖縄戦が始まりました。サイパン島陥落後の日本軍は、米軍の本土進攻を阻止するため、沖縄での防衛態勢を強化しました。牛島満中将が指揮を執る第32軍の約10万人が配備され、健児部隊やひめゆり部隊も組織されました。
米軍の圧倒的な戦力の前に、日本軍は徐々に追い詰められ、6月23日に組織的戦闘が終結するまでの約3か月間、激しい地上戦が展開されました。
この戦いで日本軍は約6万5,000人が戦死し、さらに悲惨なことに、一般住民の犠牲も甚大で、当時の島民約50万人のうち、10万人から15万人もの尊い命が失われました。対馬丸事件後も、多くの沖縄の人々の命が失われたのです*8)。
沖縄戦は、一般市民を巻き込んだ地上戦となった国内唯一の戦闘であり、日本の敗戦を決定づける重要な転換点となりました。
対馬丸記念館が作られた
1954年、対馬丸事件の遺族たちは、犠牲者を慰霊するため小桜の塔を建立しました。この塔は1959年に現在の場所へと移設されています*9)。
2001年、遺族や生存者の高齢化が進む中、対馬丸記念会が設立されました。そして2004年、対馬丸記念館が完成しました。記念館の完成から10年後の2014年には、明仁天皇陛下(現上皇)と美智子皇后陛下がご訪問され、遺族との懇談が行われました。
現在、記念館では犠牲者の名簿や遺影、ランドセルや手紙といった遺品が展示されています。また、船倉内の様子や漂流時の状況を再現した展示、証言映像なども公開されており、事件の記憶を後世に伝える重要な施設となっています*10)。
対馬丸事件に関してよくある疑問
ここからは、対馬丸事件に関するよくある2つの質問についてとりあげます。
何人助かったのか?
対馬丸の生存者数について、正確な数字を知ることは難しい状況です。当時、事件後すぐに情報統制が敷かれ、多くの重要な記録が失われてしまいました。さらに、誰が実際に船に乗っていたのかという乗船者の記録も曖昧な部分が多く、これらの要因により、確かな生存者数を算出することができない状態が続いています。
しかし、対馬丸記念館が、これまでに収集した様々な資料を基に推計した生存者数であれば知ることができます。
【推計された生存者数】
| 漁船・哨戒艇が救助した疎開者 | 177名 |
| 船員・砲兵の生存者 | 82名 |
| 奄美大島に漂着した生存者 | 21名 |
| 合計 | 280名 |
乗船した人数が1,788名であったとすれば、生存率は約15.7%に過ぎなかったことがわかります。対馬丸に乗り込んだ人の7人に1人しか助かりませんでした。
サメにも襲われた?
沈没した船の周辺海域には、多くの遺体とともに生存者たちが漂流していました。その悲惨な状況の中、さらなる恐怖が待ち受けていました。人食いザメが漂流者たちを襲撃していたのです*3)。
また、他の生存者の証言によると、耐えきれなくなったのか、イカダから海に身を投げた老人が、瞬く間にサメに襲われる光景を目撃したということです。
対馬丸事件とSDGs目標16との関わり
対馬丸事件は、多くの学童疎開児童や一般市民が犠牲となった痛ましい悲劇であり、これはSDGs目標16が掲げる「平和と公正をすべての人に」という理念と深く関係しています。戦時中の非戦闘員の犠牲という観点から見ると、この事件は平和の大切さを私たちに強く訴えかけています。
特に現代の戦争は、かつての戦場だけの戦いとは異なり、一般市民を巻き込む残虐な形で展開されます。対馬丸事件でも、罪のない子どもたちや一般市民が犠牲となり、その家族に深い悲しみと喪失感を残しました。さらに、この事件の後に起きた沖縄戦では、県民の5分の1もの人々が命を落とすという甚大な被害が生じました。
このような悲劇は、戦争がなければ決して起きることはありませんでした。戦争は人々の生活基盤を根こそぎ破壊し、その影響は終戦後も長く続きます。対馬丸事件のような悲劇を二度と繰り返さないためには、私たち一人一人が平和の維持に努め、戦争を未然に防ぐための取り組みを続けていく必要があります。
まとめ
今回は対馬丸事件を取り上げました。対馬丸は、アメリカ軍の通商破壊作戦の一環として攻撃されました。戦争の激化に伴い、物資輸送を断つことが目的でした。しかし、多くの民間人を乗せた船を攻撃したことは、戦争の悲惨さを改めて示すものとなりました。
戦後、対馬丸事件は長く箝口令が敷かれ、真相が明らかになりませんでした。しかし、遺族たちの努力により、事件の記憶を後世に伝えるための活動が進められています。2004年には対馬丸記念館が開館し、事件の資料や証言などが展示されています。
対馬丸事件は、戦争がもたらす悲劇と平和の尊さを私たちに教えてくれます。二度とこのような悲劇を繰り返さないために、平和について考え続けることが大切です。
参考文献
*1)共同通信ニュース用語解説「対馬丸事件」
*2)デジタル大辞泉「徴用」
*3)対馬丸記念館「対馬丸事件について」
*4)対馬丸記念館「対馬丸に関する基礎データ」
*5)全日本海員組合「戦没した船と船員の資料館」
*6)日本殉職船員顕彰会「わが国船舶(商船・漁船・機帆船)の被害と戦没船員」
*7)沖縄県公文書館「あの日の沖縄」
*8)山川 日本史小辞典 改定新版「沖縄の戦い」
*9)総務省「小桜の塔」
*10)内閣府「対馬丸平和祈念事業について」
この記事を書いた人
馬場正裕 ライター
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。