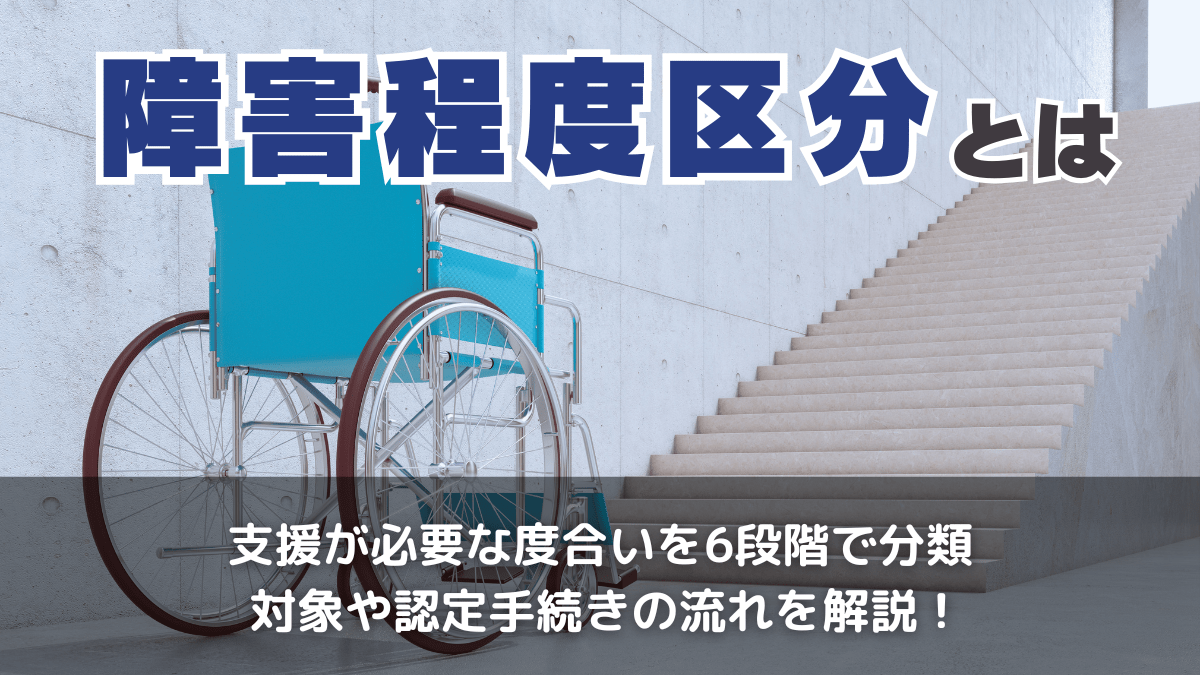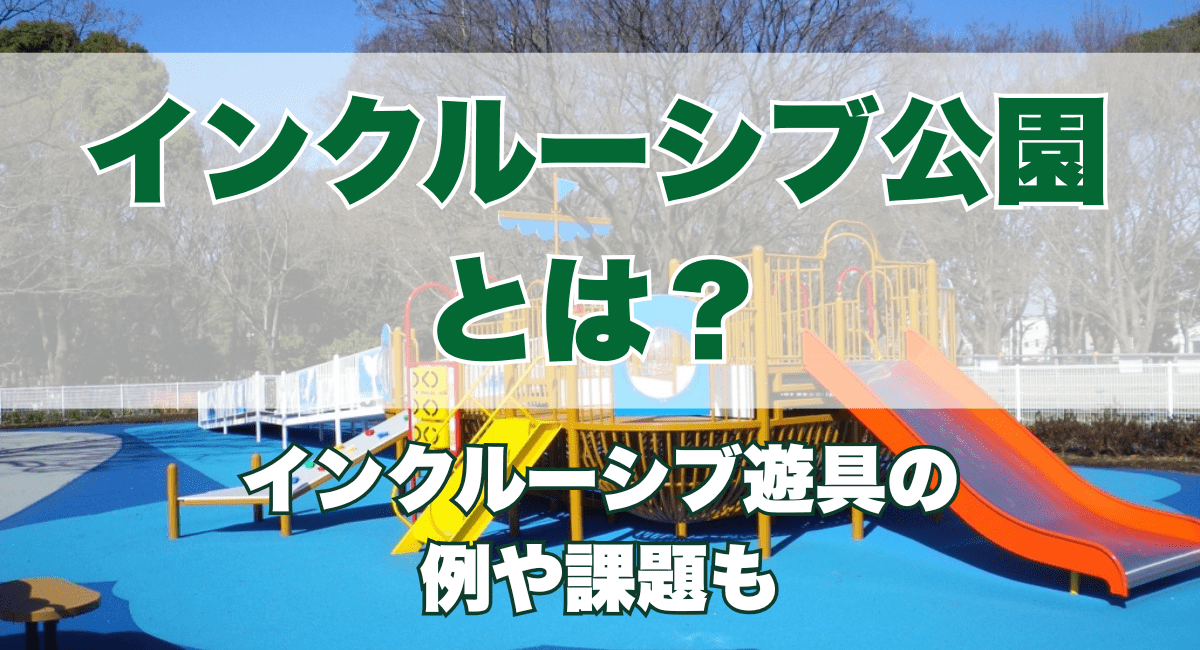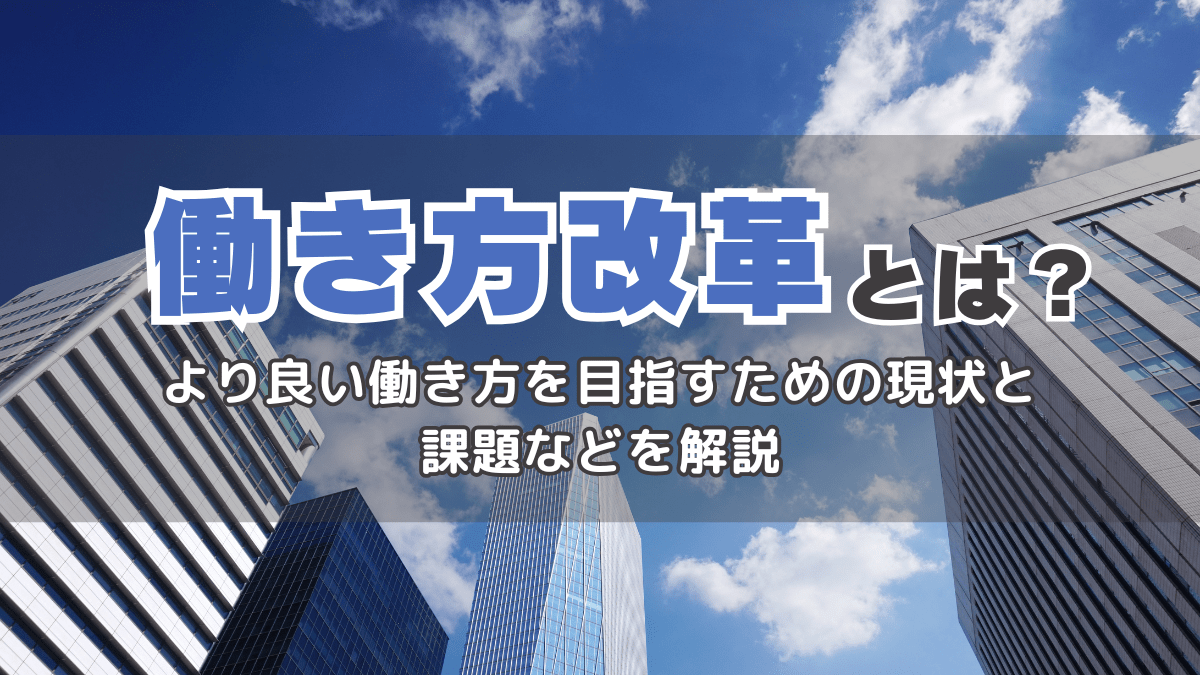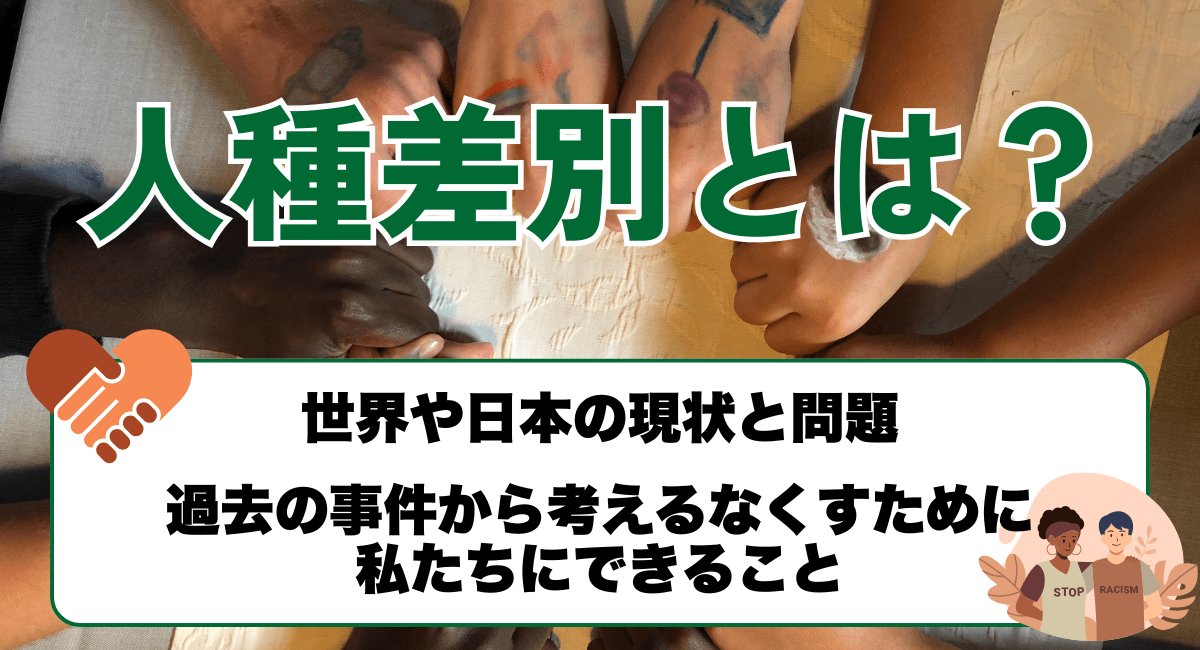今から600年近く前の15世紀前半、ポルトガルで新しいタイプの帆船であるカラベル船が開発されました。ポルトガルやスペインの探検家たちは、このカラベル船にのってアフリカ最南端の喜望峰や大西洋横断を成し遂げたのです。
その後、新しい船の改良が続けられ、遠洋航海で到達できる距離がどんどんと伸びました。そしてついに、ポルトガルの船団は東の果てともいえる日本にたどり着き、鉄砲やキリスト教をもたらすのです。
今回は、大航海時代がなぜ始まったのか、大航海時代にどのような出来事があったのかを中心に解説します。ガマ、コロンブス、マゼランといった有名な航海者についての紹介だけではなく、大航海時代がヨーロッパや日本にもたらした影響についてもまとめています。ぜひ、参考にしてください。
目次
大航海時代とは

大航海時代とは、15世紀から17世紀にかけて、ヨーロッパの国々(特に、スペイン・ポルトガル)が世界規模の航海を行い領域を広げた時期のことです*1)。新航路を開拓することで世界各地の結びつきが強まった半面、ヨーロッパ諸国によるアフリカ・南北アメリカなどの植民地化が進められました。
大航海時代が始まった要因
大航海時代が始まった要因はいくつか考えられます。主な理由は以下のとおりです。
- 香辛料の需要増加
- オスマン帝国の拡大
- 遠洋航海技術の発展
かつて香辛料は、肉の防腐や風味付けに欠かせない貴重な存在でした。中でもヨーロッパで特に需要が高かった胡椒は、インド南西部のマラバール海岸付近が原産とされ、東南アジア各地で栽培されていました。肉を主要な食糧としていたヨーロッパの人々にとって、その味わいを引き立てる香辛料は必要不可欠であり、とりわけ王侯貴族など上流階級の人々から強く求められました。
しかし、ヨーロッパは胡椒の自生地ではなかったため、ヴェネツィア(ベネチア)商人が地中海沿岸やシルクロードを経由して運んできたものを買い付け、ヨーロッパ市場で販売していました(東方貿易)。そのため、胡椒は流通量が限られ、非常に高価な商品でした。
ところが、オスマン帝国が勢力を拡大してヴェネツィアが東地中海で行っていた貿易を圧迫したため香辛料の価格が大幅に上昇します。
15世紀中頃、ポルトガルに三本マストのカラベル船が出現しました。これにより、従来よりも遠方まで航海できるようになります。加えて、羅針盤の技術が発達したことにより、船の正確な位置を割り出せるようになりました。
航海技術が発達した結果、オスマン帝国の領土を避けてインドなど香辛料の原産地にたどり着けるようになりました。こうして、大航海時代が始まる条件が整ったのです。
大航海時代の歴史と流れ【何が起こっていたのか】

大航海時代は15世紀から17世紀までの長い期間に及びます。今回は、大航海時代の主役ともいえるスペインやポルトガルが活躍した15~16世紀の出来事についてまとめます。
【大航海時代の流れ】
| ポルトガル | スペイン | |
|---|---|---|
| 1415年 | エンリケ航海王子がセウタを攻略 | |
| 1488年 | バルトロメウ=ディアスが喜望峰に到達 | |
| 1492年 | コロンブスがサンサルバドル島に到着 | |
| 1494年 | トルデシリャス条約 | |
| 1498年 | ヴァスコ=ダ=ガマがインドのカリカットに到達 | |
| 1500年 | カブラルがブラジルに漂着 | |
| 1501年 | アメリゴ=ヴェスプッチが「新大陸」と命名 | |
| 1510年 | ゴアに総督府を設置 | |
| 1511年 | マラッカを占領 | |
| 1512年 | モルッカ諸島に到達 | |
| 1519~22年 | マゼランの世界一周 | |
| 1521年 | コルテスがアステカ帝国を征服 | |
| 1533年 | ピサロがインカ帝国を征服 | |
| 1543年 | 種子島に漂着 | |
| 1549年 | ザビエルが布教を開始 | |
| 1557年 | マカオの居住権を得る | |
| 1571年 | マニラを建設 | |
ヴァスコ=ダ=ガマのインド到達
イベリア半島西岸にあるポルトガルは、アフリカ西海岸に進出しました。その指揮を執ったのがエンリケ航海王子です。彼は、学者を集めて天文学や地図の研究をさせ、遠洋航海に必要な道具をそろえるなどしたといいます。
15世紀後半、ジョアン2世の治世下でポルトガルのアフリカ探検は大きく進展しました。探検家バルトロメウ・ディアスは、アフリカ大陸最南端に位置し、インド洋へと続く喜望峰に到達しました。
マヌエル1世(在位1495〜1521年)の時代の1496年、喜望峰を回ったヴァスコ=ダ=ガマは、インドのカリカットに到達します。これにより、ポルトガルのインド航路が完成しました。1509年のディウ沖海戦でマムルーク朝に勝利して香辛料貿易を独占します。
その後、ポルトガルはマラッカ王国を滅ぼして東南アジアにも進出し、香料の産地であるモルッカ諸島をも占領します。ポルトガルの船はインド洋から東シナ海まで幅広く活動し、日本近海でも日本の銀や中国の生糸などを扱って莫大な利益を上げました。
コロンブスのアメリカ到達
ポルトガルに後れを取ったスペインは、ポルトガルの東回りとは逆ルートの西回りでインドを目指しました。この西回りでのインド到達を主張したのがコロンブスです。彼は、トスカネリが唱えた「地球球体説」をもとに、西回りでもインドにたどり着くと主張し、スペイン女王イサベルの支援を受けます。
1492年、コロンブスは大西洋を渡り、カリブ海のサンサルバドル島に到達しました。当初、コロンブスはこの新しい土地をインドだと誤解し、そこに住む人々を「インディオ」と名付けました。しかし、その後、アメリゴの探検により、ここがインドではないことが明らかになりました。
コロンブスの新大陸到着後、スペインとポルトガルの間で領有権争いが始まりました。ポルトガルは、非キリスト教世界の征服や貿易独占、異教徒の奴隷化や権利を認めた1455年の教皇教書を持ち出してスペインの主張に反対しました。
教皇アレクサンドル6世は境界線(教皇子午線)を引きましたが、ポルトガルは納得せず、スペインと直接交渉してトルデシリャス条約を結び、両国の勢力圏を決めなおしました。
マゼランの世界一周
1517年、スペイン王カルロス1世はポルトガル人のマゼラン(マガリャンイス)に西回りでの世界一周を命じました。
カール5世は、西回りで香料産地のモルッカ諸島に到達すれば、モルッカ諸島をスペインの領土にできるのではないかと考え、マゼランに世界一周を命じたといわれています。カール5世は南ドイツの豪商であるフッガー家の援助を得て、マゼランの船団を派遣しました。
マゼランの船団は太平洋横断に成功しましたが、マゼラン本人はフィリピンのセブ島付近で現地の首長であるラプラプとの戦いに敗れて戦死してしまいます。生き残った船団は、喜望峰経由でスペインにたどりつき、世界一周を成し遂げました。
スペインによるアメリカ征服
コロンブスの到達後、コンキスタドール(征服者)たちによる中南米の征服が始まりました。1521年、スペインの下級貴族だったコルテスは、わずか400人の部下を率いてアステカ王のモンテズマを捕え、帝国を滅亡に追いやりました。
征服者たちは、エンコミエンダ制という土地制度を実施して植民地支配を強化し、銀の採掘や大農園の経営を行いました。
エンコミエンダ制は、スペイン人によるインディオ虐待の原因になっていると考えた聖職者のラス=カサスは、エンコミエンダ制の撤廃を訴えましたが、実現できませんでした。
大航海時代に関してよくある疑問

ここからは、大航海時代に関してよくある質問を紹介します。
大航海時代は日本でいうと何時代?
大航海時代の頃、日本は室町時代後期(戦国時代)から安土桃山時代でした。コロンブスがアメリカ大陸に到達したころ、初期の戦国武将として知られる北条早雲が小田原城に入城しています。
ポルトガル人が1543年にもたらした鉄砲は、日本の戦争の常識を根本から変える武器となりました。その後、ポルトガル人やスペイン人は日本の戦国大名と貿易(南蛮貿易)を行い、鉄砲で使用する弾薬の原料である硝石などを購入し、銀などを輸出しました。
また、ザビエルによって伝えられたキリスト教は九州を中心に日本各地に広まり、大友宗麟や有馬晴信、大村純忠といったキリシタン大名を生み出します。彼らは後に、天正遣欧使節をローマに送りました。
日本が植民地にならなかった理由
日本が植民地にならなかった理由はいくつか考えられます。最も大きな理由は、ヨーロッパから距離が遠かったからで、大軍を送り込むことが困難であったことがあげられます。
次に、軍事力が高かったことがあげられます。戦国時代から安土桃山時代は、各地の領主が軍勢を保有しており、最新武器である鉄砲なども使っていたことから、スペインやポルトガルの軍事力でも征服するのは困難でした。
加えて、戦国時代の争いの中から織田政権・豊臣政権といった強力な政権が生まれつつあったため、外国勢力による征服はより困難となっていました。
つまり、距離・軍事力・統一政権の形成の3つの要素があったから、日本はスペインやポルトガルなどによる植民地化を免れたといえます。
大航海時代はなぜ重要だったのか
大航海時代は、ヨーロッパに数々の影響をもたらしましたが、なかでも商業革命と価格革命の影響は非常に大きいものがありました。
商業革命とは、ヨーロッパ経済の中心が、イタリア半島などの地中海沿岸地域から、大西洋沿岸に移ったことです。この変化により、ヴェネツィアやジェノヴァ、フィレンツェなどルネサンスを主導したイタリアの都市国家が衰退し、経済の中心はリスボンやアントワープなどに移ってしまいました。
価格革命とは、銀の大量流入によって引き起こされた社会の変化です。ペルーやメキシコといったスペインの植民地や、日本銀などがヨーロッパに流入することで、銀の価格が暴落してしまいました。そのため、貨幣の価値が落ちて物の価値が上がるインフレーションが起き、物価が高騰します。
固定した地代に頼っていた封建貴族は物価上昇によって大打撃を受けてしまいます。なぜなら、収入が増えないにもかかわらず、出費だけが一気に増えてしまったからです。これにより、封建貴族の力が低下してブルジョワジーなどの資本家の力が増大しました。
世界三大航海士は誰?
三大航海士といえば、ヴァスコ=ダ=ガマ、コロンブス、マゼランの3人を挙げる人が多いのではないでしょうか。
ガマは、ポルトガル船団を率いてインドに到達し、オスマン帝国を介さない香辛料貿易を実現しました。コロンブスは、スペインによる中南米支配のきっかけを作り、現地の社会に激変をもたらした人物です。マゼランは、彼自身は亡くなってしまったものの、彼の船団が世界一周を成し遂げたことで、地球が丸いことを実証しました。
いずれの航海者も、未知の海に乗り出して時代を変革させたことは言うまでもありません。しかし、彼らの進出はアフリカやインド、南北アメリカの社会に激変をもたらしました。彼らの功績に光を当てるだけではなく、影の部分にも注目しなければならないのです。
大航海時代とSDGs
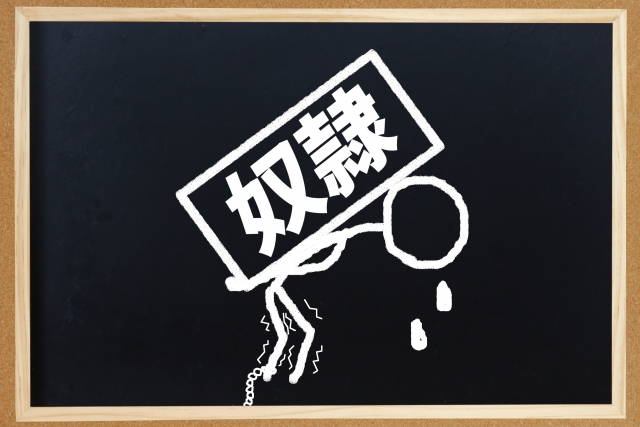
大航海時代は、ヨーロッパにとって世界の発見と拡大をもたらしましたが、その影響は複雑でした。アフリカ、インド、中南米、東南アジアなどの地域では、ヨーロッパの進出により従来の社会構造が崩れ、文化や伝統が脅かされる結果となりました。この時代は、発見と破壊の両面を持ち合わせていたのです。
ここでは、SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」との関わりについてみてみます。
SDGs目標10は、国同士の不平等や国内の不平等の解消を目指す目標です。大航海時代がきっかけで、ヨーロッパ諸国はアフリカや南北アメリカ、東南アジア、東アジアなどを植民地として支配しました。
大航海時代はヨーロッパに大きな富をもたらしました。しかし、支配された国や地域は、本国(ヨーロッパ諸国)の原料供給地となったり、本国製品の市場となったりしたため、産業が育ちにくくなり、経済が立ち行かなくなりました。
大航海時代の先駆者であるコロンブスも、負の側面を含めて再評価されています。大航海時代を「夢と冒険の時代」と捉えるのは、一面的な見方かもしれません。
まとめ
今回は、15〜17世紀にスペインやポルトガルが中心となった大航海時代を紹介しました。大航海時代が始まったきっかけは、香辛料需要の増加、オスマン帝国の拡大、航海技術の発展が主な要因です。
ポルトガルはアフリカ経由でインドに到達し、スペインはコロンブスによるアメリカ大陸到達を果たしました。両国は新航路開拓や植民地獲得を進め、世界貿易の拡大をもたらしました。
一方で、征服された地域では従来の社会構造が大打撃を受け、文化や伝統が脅かされる結果となりました。大航海時代は経済発展と破壊の両面を持ち、現代の国際関係や経済格差にも影響を与えた重要な歴史的出来事だったと言えます。
参考
*1)デジタル大辞泉「大航海時代」
*2)精選版 日本国語大辞典「東方貿易」
*3)デジタル大辞泉「オスマン帝国」
*4)日本大百科全書(ニッポニカ)「エンリケ(航海王子)」
*5)デジタル大辞泉「イサベル」
*6)山川 世界史小辞典 改定新版「トルデシリャス条約」
*7)山川 世界史小辞典 改定新版「カール5世」
*8)改定新版 世界大百科事典「エンコミエンダ」
*9)デジタル大辞泉「天正遣欧使節」
この記事を書いた人
running.freezy ライター