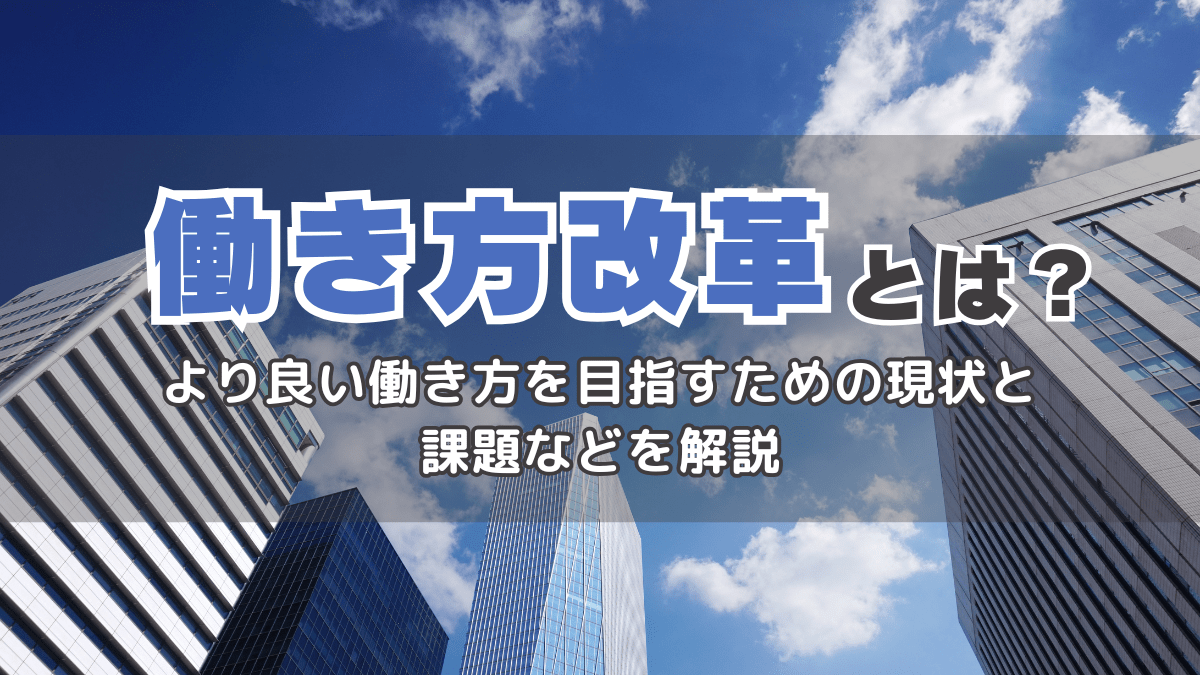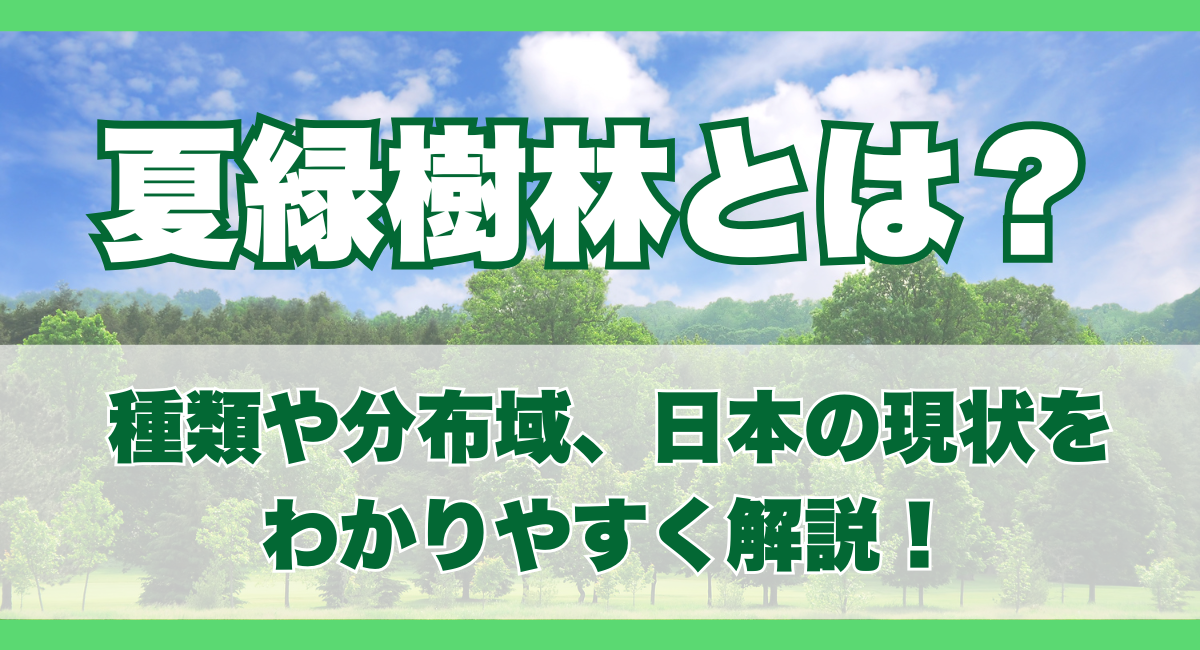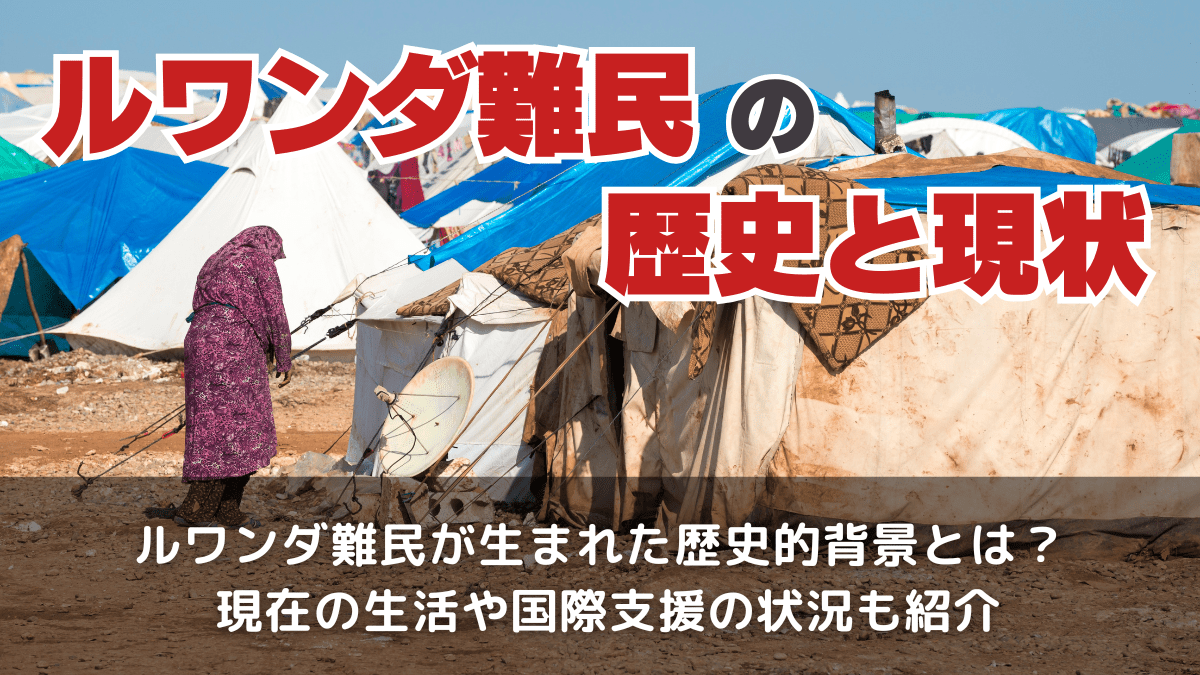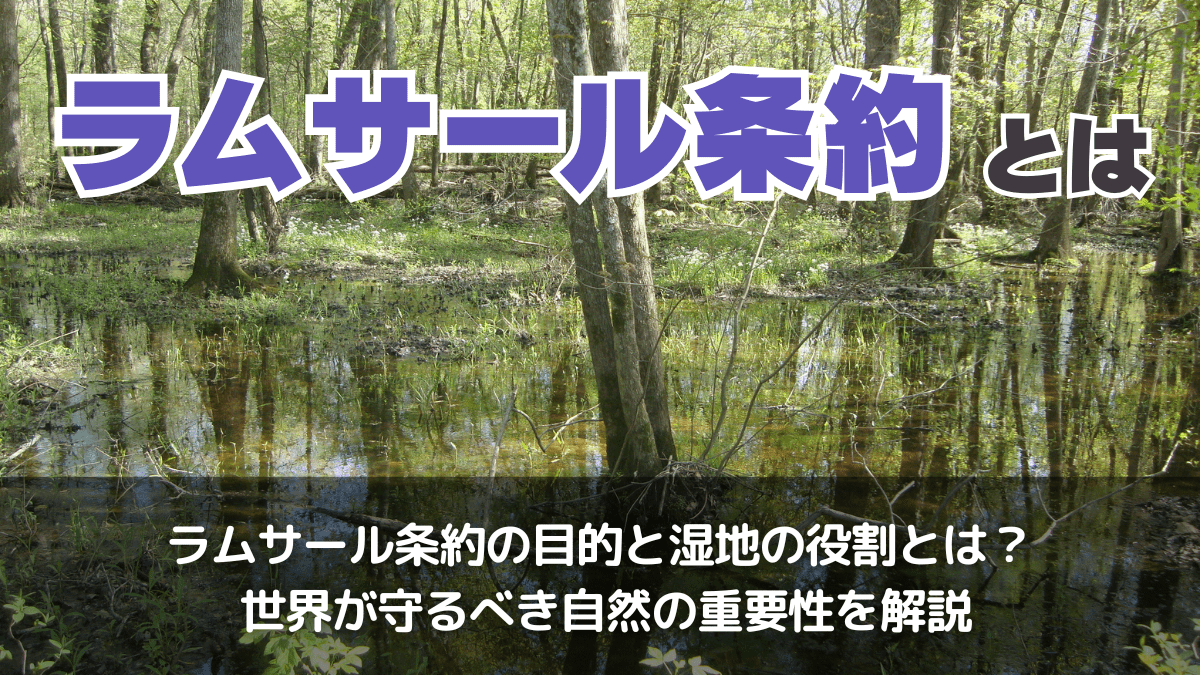「SDGs」という言葉は耳にするものの、具体的な内容がイメージしにくい方も多いでしょう。
本記事では、青森県ならではの自然や文化を活かした取り組みや、地域課題の解決を目指す活動をご紹介します。
青森の未来をより持続可能にするための具体例を知り、一歩踏み出すきっかけになるかもしれません。
さあ、青森県で行われているSDGsの実践を一緒に見ていきましょう!
目次
青森県のSDGs
青森県では、「青森県基本計画『選ばれる青森』への挑戦」(2019~2023年度)の中で、SDGsの理念を取り入れたさまざまな施策を推進しています。
計画の第6章「計画の推進」では、政策分野ごとにSDGs達成を目指した取り組みを展開するだけでなく、市町村や企業・団体への情報発信や普及啓発を通じて、県民の理解促進にも力を入れています。
また、環境、教育、経済、まちづくりといった多岐にわたる分野での先進的な事例を取りまとめた事例集も発行。
これにより、地域での取り組みが共有され、SDGsの輪が広がることでしょう。
青森県は、持続可能な地域づくりを目指し、県全体でSDGsの実現に向けた一歩を踏み出しています。
県内企業の取り組み紹介
では実際にどんな取り組みがされているのでしょうか。
北洋硝子株式会社「持続可能な伝統産業を優れた技術と女性の活躍で」
北洋硝子株式会社は、石塚硝子株式会社の連結グループ子会社であり、ガラス食器の製造販売を行っています。
1949年、青森県青森市に漁業用のガラス製浮玉を製造する工場として創業し、1973年には国内トップの生産高を記録。
しかし、時代の流れに伴い、浮玉の素材がプラスチック製へ移行したことから、事業の方向転換を図り、ガラス成形の技術を活かした工芸品「津軽びいどろ」の生産を開始しました。
具体的な取り組み内容
現在、「津軽びいどろ」は、カラフルで美しい色合いと手作りの温かみを特徴とし、青森県の伝統工芸品として広く知られています。
同社は青森の四季や自然をイメージした100種類以上の独自の色ガラスを用い、インテリア製品やテーブルウェアを製造。
2014年には「四季を感じるハンドメイドガラス」をブランドコンセプトに掲げ、さらなるリブランディングを実施しました。
環境への配慮も重要な取り組みの一つです。
同社は、不要となった漁業用のガラス製浮玉を回収し、網を外し洗浄・粉砕・溶解することで、浮玉由来の自然な青緑色や素朴な風合いを活かしたアップサイクル製品「津軽びいどろ DOUBLE F -UKIDAMA EDITIO-」を製造しています。
この製品は、廃棄の困難さから漁港などに積み上げられ放置された浮玉を原料にすることによって、海洋汚染防止や海岸景観の保護に貢献しています。
ガラス職人が一つひとつ丁寧に仕上げた製品は、ナチュラルな空間にも調和するシンプルで洗練されたデザインが特徴です。
さらに、北洋硝子は伝統工芸士を含むベテランから若手までの職人が活躍する職場です。
特に近年は女性職人も増え、箸置きや一輪挿し等、多様な視点を取り入れたものづくりに取り組んでいます。
同社の活動は、青森の地域産業を盛り上げるだけでなく、環境問題の解決にも寄与するものであり、「今ある資源を無駄にしない」「青森の美しい景色を守る」という想いを体現しています。
北洋硝子はこれからも、「四季」「手作りの温かみ」「地域のストーリー」を大切にし、持続可能な未来を目指して歩み続けます。
北洋硝子株式会社の基本情報
| 名称 | 北洋硝子株式会社 |
| 代表者名 | 壁屋知則 |
| 住所 | 青森市富田4丁目29-13 |
| 電話番号 | 017-782-5183 |
| URL | https://tsugaruvidro.jp/ |
まとめ
今回は、青森県でSDGsに取り組む企業について紹介しました。
青森ならではの自然や文化を活かしながら、持続可能な地域づくりに挑戦する姿勢は、多くの人にとって共感や学びを与えるものです。
不要になった資源を活用し、新たな価値を生み出す取り組みや、伝統工芸を次世代につなぐ努力は、地域に根差したSDGs実践の好例と言えるでしょう。
これをきっかけに、青森県の未来を一緒に考え、SDGsを日々の暮らしに取り入れるヒントを見つけてみませんか?
この記事を書いた人
mochi ライター