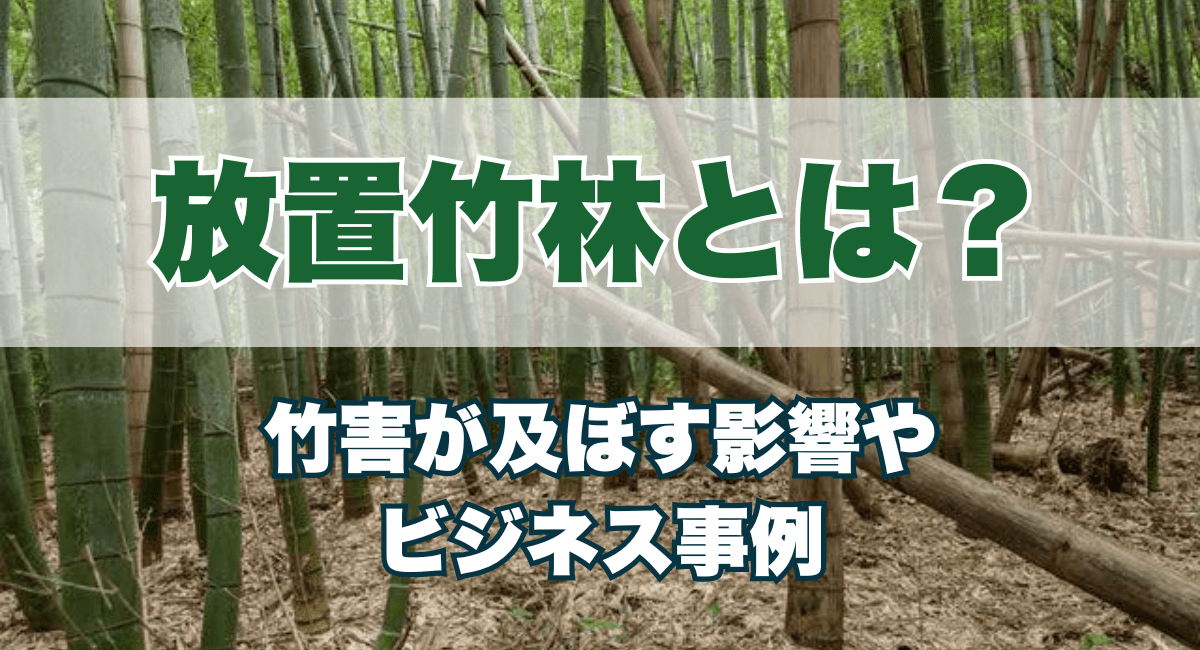
放置竹林とは、持ち主によって計画的に管理されず、竹が生えるがままに放置された竹林のことです。放置竹林の増加は、竹害をもたらしています。放置竹林の日本における現状や発生する原因などをわかりやすく解説。放置竹林の対策や企業が取り組む具体的な活用事例もまとめています。
竹は古くから、建材、日用品、食材など、さまざまな形で私たち日本人の生活を支えてきた植物です。しかし近年、管理されていない竹が増え過ぎる放置竹林が問題化しています。
放置竹林がなぜ増えて、どのような影響を及ぼすのか。その問題を解決するためにどんなことが行われているのか。放置竹林の実態に迫りながら、とるべき対策やビジネスへの活用事例などについても紹介していきたいと思います。
目次
放置竹林とは?竹害とは?読み方も簡単に解説
放置竹林とは、持ち主によって計画的に管理されず、竹が生えるがままに放置された竹林のことです。
竹は生命力や繁殖力が極めて強く、竹稈(幹に当たる部分)が1日で120cm、地下茎も1年で5m伸びた記録もあるほどです。そのため適切な管理がされなくなるとたちまち広範囲に広がり、周囲の植物の植生エリアにも侵食していきます。
やがて放置竹林が他の植物を追いやり、新たな放置竹林を生み出す。これが後述するさまざまな問題を引き起こす元になっているのです。
放置竹林とは?簡単に解説
放置竹林(ほうちちくりん)とは、持ち主によって計画的に管理されず、竹が自然に伸び放題になっている竹林のことです。かつて竹は建材や日用品、食用として需要が高く、伐採や手入れが行われていました。
しかし近年は需要減少や担い手不足により管理が滞り、全国各地で放置竹林が増加しています。この状態が続くと、竹の地下茎が勢いよく広がり、他の植物を駆逐する「竹害」が発生します。
結果として生態系のバランスが崩れ、土砂災害や農地・住宅への被害にもつながります。こうした問題は日本だけでなく海外でも報告されており、原因の一つは人手不足と採算性の低さです。
現在は行政や企業が、放置竹林を資源として活用するビジネスや地域連携の対策に取り組んでいます。
竹害とは?読み方も解説
竹害(ちくがい)とは、竹が過剰に繁殖し、周囲の環境や人間生活に悪影響を及ぼす現象を指します。竹は成長が非常に早く、地下茎で横方向にも広がるため、一度放置すると短期間で大規模に拡大します。
その結果、森林の樹木や草花が光を奪われ枯れ、生態系の多様性が失われます。また、農地や道路、住宅地にまで竹が侵入し、作物の生育不良や建物・インフラへの損傷を引き起こすこともあります。
さらに根の浅さから土壌をしっかりと固定できず、豪雨時に土砂崩れのリスクを高めます。竹害の原因は、竹林の管理放棄、竹需要の減少、担い手不足など複合的です。これに対し、伐採や間引き、竹材のビジネス活用、地域住民の協働などが効果的な対策として進められています。
放置竹林の原因・問題点
なぜ適切に管理されず、放置される竹林が増えてしまうのか。それには以下のような原因があります。
高度経済成長に伴う生活様式の変化
従来、竹は箸やうちわ、かご、食器など、あらゆる日用品、建築資材などに使われてきました。しかし戦後の高度経済成長期に日本人の暮らしが洋風化し、プラスチックや軽金属などの代替製品がそれらにとって変わるようになります。そのために日用品としての竹の利用は激減していきました。
輸入竹の増加
同じ時期に海外からの輸入竹材やタケノコが増えたことも、放置竹林が増加した原因です。
竹は120年に一度花を咲かせ、その後すぐに枯れるという性質を持っています。そしてまさにその時期に当たっていた昭和40年代、国内でマダケが一斉に開花し枯死したことで、竹材の供給が追いつかなくなりました。
結果的に日本の竹材やタケノコは輸入に頼るようになり、竹林が回復した現在でも国産竹材の利用は少ないままです。こうして利用されなくなった竹林は放置され、増えるがままになっています。
竹林所有者の高齢化や後継者不足
放置竹林増加のもう一つの理由は、竹林所有者や竹関連産業従事者の高齢化や後継者不足です。
これは農林水産業全般に共通する問題ですが、竹林管理や竹産業の場合、
- 放置竹林は急な斜面や軽トラックが入れない狭い場所が多く、管理に身体的負担がかかる
- 従来の竹材利用には使用目的に適した竹を選ぶ目利きが必要で、育成に時間がかかる
といった課題を抱えています。
一方で前述のような竹産業の衰退や地方の過疎化は、竹林・竹材の担い手減少と高齢化を招きました。これが放置竹林の増加に拍車をかけているというのが現状です。
生態系の破壊と景観の悪化
放置竹林は、竹が成長し放題になり、地下茎を使って急速に広がります。この過程で、元々そこに生えていた広葉樹や針葉樹、草花などが光や養分を奪われ、次第に枯れてしまいます。その結果、森の多様性が失われ、野鳥や昆虫などの生息環境も大きく変化します。
特に単一種の竹が広範囲を覆うと、四季折々の植生が消え、景観が単調になり、地域の自然美が損なわれます。さらに、季節の変化や紅葉の風景が見られなくなるなど、観光資源としての価値も低下します。
こうした生態系の変化は一度進むと回復が難しく、長期的な自然環境の劣化を招く深刻な問題です。
農地・住宅・インフラへの被害
放置竹林は農地や住宅地、道路周辺にまで拡大し、生活や経済活動に直接的な被害を与えます。農地に竹が侵入すると、作物が十分に光を受けられず、生育不良や収量減少が発生します。
また、竹の根や幹が住宅の基礎や塀、道路舗装を押し上げて損傷させることもあります。竹は根が浅いため、土壌をしっかり固定できず、豪雨時には斜面の土砂崩れリスクを高めます。
さらに、電線や排水設備などインフラにも影響が及び、修繕や管理コストの増加を招きます。これらの被害は放置期間が長いほど深刻化し、後からの除去や修復には多大な時間と費用がかかるため、早期の対策が重要です。
放置竹林問題(竹害)とは
こうした放置竹林の増加は、竹害とも呼ぶべき問題を引き起こすようになりました。では放置竹林が増えることで、どのような問題が起こるのでしょうか。
農林業への支障
一つは農林業への悪影響です。竹は特に低い広葉樹林に侵入しやすく、隣接する森林に侵入して広葉樹のほか、スギやヒノキなどの樹木の根を圧迫し、枯れさせていきます。
また竹林が畑地に近い場合、竹の地下茎が侵入することで野菜や果樹・茶などの栽培に支障をきたすといった問題を引き起こすことにもなります。
また放置竹林が鹿やイノシシなど野生動物の住処になることで近くにある畑が荒らされ、農作物に被害を及ぼすという問題も起きています。
土砂災害の危険性
放置竹林の増加は土砂災害の危険性を高めます。
山や森林では、広葉樹が深く根を張り地下に水を蓄えることでしっかりした地盤を保持しています。しかし放置竹林が増え、竹に侵食されていくことで
- 広葉樹林の深い根がなくなる反面、竹の根は地下50cm程度と浅いため山の地盤が弱くなる
- 竹自身の中に水を貯めるため山の保水力も低下する
- 下流域の川の水枯れや地下水の減少につながる
といった状態になります。これによって起こりやすくなるのは、豪雨が起きた際の斜面崩壊や土砂崩れです。水害が激甚化している近年では、決して軽視できない問題と言えるでしょう。
動植物多様性の低下
竹林の侵食は、山や森林における動植物の多様性を損なう原因ともなります。その理由は
- 竹は上に高く伸びるため森の下層に光が届きにくくなり、多くの植物の成長を阻害
- 竹の地下茎に侵食され広葉樹、スギやヒノキが枯死する
- 竹類が侵入した林では土壌中の根圏の微生物が減少する
などです。この結果、植物だけでなく地表のアリ類、森に棲む動物や鳥類の多様性にも影響を与えることがわかっています。
温暖化防止機能への影響も
放置竹林の増加は地球温暖化対策とも無縁ではありません。
通常の樹木と竹類とでは炭素の蓄積様式に大きな違いがあり、竹類が増え過ぎることで地上部の炭素蓄積量は従来の植生の半分以下になるとも指摘されています。
放置竹林は、竹そのもののCO2の吸収能力も低下させます。モウソウチクの場合1本に3〜5万枚の葉を付けますが、竹藪状態になれば中下段の枝が枯れ、葉の量も減少します。その結果、吸収できるCO2も減ってしまうというわけです。
日本の放置竹林(竹害)の現状
では、そんな放置竹林の現状はいったいどうなっているのでしょうか。
2022年3月末時点で、日本全国の竹林面積はおよそ17万5,000ヘクタール(17億5,000万㎡)とされており、その多くは九州や中国地方など西日本に分布しています。
国内には約600種の竹があるとされますが、その多くはマダケ、ハチク、モウソウチクの3種です。中でも竹稈の伸びが大きいモウソウチクが、放置竹林になりやすいとされます。
日本に放置竹林(竹害)はどのくらいある?
全国の竹林のうち、放置竹林の面積がどのくらいかは正確な把握がされていません。
調査では日本の竹林面積の2/3が管理されていないとも言われており、これらを放置竹林と見なせば約11〜12万ヘクタールが放置竹林ということになります。
さらに竹林と竹が他の森林に25%以上侵入している混交林も含めると、何らかの形で管理されていない竹林面積は実に42万ヘクタールにも上ると推定されています。
放置竹林(竹害)対策が進まない理由
これだけ大きな問題を抱えているにもかかわらず、日本の放置竹林対策は進んでいるとはいえません。そこには以下のような事情があります。
実態の把握が難しい
理由の一つは、竹林の面積や拡大状況を包括的に評価できるデータが乏しく、対策が立てにくいためです。背景には、竹の特性として非常に早く人知れず地中で根を広げていくこと、他の樹木と混交してしまった竹林が増えたことなどがあります。
そのため、2000年以降の放置竹林面積を評価した研究や解析手法は少ないというのが実情です。
竹はしぶとい
2つめの理由は、竹の生命力の強さ、しぶとさです。
竹は地上部を刈っても地下部分が生き残り、翌年以降もまた再生した竹が生えてきます。
新竹の再生度合いは年によって変わり、たとえ刈り払いの翌年に再生竹が減ったとしても、その翌年には一気に増えてしまうこともあるため、油断はできません。
竹林を樹木中心の森林へ変えるには、樹木の成長を阻害する再生竹を何年もかけて伐採しなければならず、継続的な見回りと管理は不可欠となります。
駆除作業の労力やコストが大きい
再生竹のしぶとさは、大きな労力とコストを発生させます。放置竹林は毎年刈り払いをしても、なかなか伐採の効果が実感しにくく、モチベーションの維持も容易ではありません。
また竹は木材より軽いため、伐採作業に関わる生産性が低い割にコストは高くつきがちです。
竹林はトラックが入れない狭い土地や傾斜が急な土地も多く、人件費や機械の搬入出・回収・運搬など、伐採前後のコストはどうしてもかかってしまいます。
海外にもある放置竹林(竹害)の現状
海外でも放置竹林や竹害は報告されており、特に中国や東南アジアでは森林や農地の生態系変化が問題視されています。近年は輸出や観光資源化などビジネス活用の動きも進んでいます。
中国における竹害の発生状況と対策
中国は世界最大級の竹資源国で、特に南部地域では竹林が広範囲に分布しています。しかし近年、一部地域で放置竹林が拡大し、森林の単一化や生態系の変化が問題化しています。
農地への侵入や山地の植生破壊も進み、農業生産や防災機能に悪影響を及ぼしています。対策としては、竹材の計画的な伐採や間引き、地域住民や企業との協働による管理体制強化が進められています。
また、政府は竹の繁殖抑制や外来種との競合調査など科学的手法も導入しています。こうした取り組みにより、竹害を防ぎつつ竹資源の持続可能な利用を図る方向性が模索されています。
東南アジアでの竹林拡大と地域経済への影響
東南アジアでは竹は古くから生活資材や食料として利用されてきましたが、一部地域では放置竹林が急速に拡大しています。特に農村部では耕作放棄地や山林が竹に覆われ、在来植物の減少や土壌保全機能の低下が報告されています。
これにより農作物の収量が減少し、地域経済に影響を与えるケースもあります。また、道路や住宅への侵入によるインフラ被害も見られます。各国では、行政による伐採支援や竹林境界の整備、地域コミュニティによる共同管理などの対策が進められています。
放置竹林対策は単なる環境保全にとどまらず、農業や観光を守るための重要な地域課題となっています。
外で進む竹害防止と管理体制の強化
海外では、竹害防止のために制度面と地域参加型の管理が強化されています。例えば、中国やタイでは竹林の所有者に対して定期的な伐採や境界管理を義務付ける仕組みを導入。
違反した場合には罰則を科す地域もあります。また、行政が専門チームを設置し、竹林分布や成長状況を衛星データで監視する先進的な取り組みも進行中です。さらに、地域住民の参加を促すため、伐採活動を地域イベント化したり、学校教育に竹害防止を組み込む事例もあります。
これらの管理体制強化は、放置竹林を早期に発見・対処し、環境保全と生活の安全を両立させることを目的としています。
放置竹林(竹害)の対策
現在、放置竹林の問題が知られるにつれて、自治体レベルで放置竹林対策に乗り出す動きが高まりつつあります。ここでは現在行われている、放置竹林の主な駆除方法を紹介していきます。
継続的に伐採する
最もポピュラーかつ有効な方法は、継続的、計画的に伐採し続けることです。
竹の生命力がいくら強くても、毎年ひたすら刈り続ければ確実に弱らせることができます。竹の刈り払いを行なった後、広葉樹林を植栽。その後も年2回、7年間竹の刈り払いを継続した場合、ほとんどの現場で竹の駆除に成功しています。皆伐後に全ての地下茎を掘って取り除けば、翌年以降は再生しませんが、コストと労力がかかることが難点です。
除草剤を利用する
もう一つの方法として、除草剤を使った駆除があります。竹用に使われる除草剤にはグリホサート系除草剤と塩素系除草剤が登録されており、
- 竹稈または切り株に一本ずつ注入:手間はかかるが環境に影響が少ない
- 土壌散布:手間がかからないが環境に悪影響
という方法があります。
こうした除草剤の使用で問題となるのは環境への悪影響です。特にグリホサート系の除草剤は、地下茎に移行の危険があるため15m以内のタケノコは採れなくなります。竹稈に注入してふたをするため環境への流出は低く、植物体への影響もないという検証結果はあるものの、できる限り使わない方が良いでしょう。
遮蔽物を埋設する
その他には、地中に遮蔽物を埋め、地下系の侵入を防ぐ方法があります。コンクリートの板、トタンや農業用の畦板などが主に使われ、地下50㎝程度で効果があるとされます。
注意点として、竹の地下茎は先端が尖っていて隙間があれば侵入してしまうため、遮蔽物の継ぎ目は確実に密着させる、溝の底辺部を締め固めるなどの措置が必要となります。
ただ、それでも完全な侵入防止は難しく、その後も見回りや刈り払いは不可欠です。
放置竹林(竹害)を活用したビジネス事例
広がる放置竹林を資源として活用するため、農家や企業などによるさまざまな取り組みが行われています。主なものでも
- 竹炭:堆肥/土壌改良剤/消臭剤/竹酢液
- 竹パウダー:肥料・堆肥/米ぬかと混ぜた漬物のぬか床
- 燃料:薪・混焼燃料
など、その用途は多彩です。ここでは、その他にも放置竹林を活用し、成功しているビジネス事例をいくつか紹介していきましょう。
LOCAL BAMBOO【国産メンマ】
国産の竹を使ったメンマ作りは、日本各地で盛んに行われています。宮崎県延岡市で地元資源を活用した事業を行なっているLOCAL BAMBOOもその一つです。
同社では、地元延岡市の放置竹林問題を解決するため、市内のモウソウチクを使ったメンマの製造・販売に乗り出しました。看板商品となった「延岡メンマ」がひときわ特徴的なのは
- 延岡産の味噌を使った味わいを追求
- トーストやパスタ、アイスに合わせるなど、新しい食べ方をSNSで提案
- 高級感のある洗練されたパッケージデザイン
などの新しい手法によって、メンマそのものにメインの食材として高い付加価値をつけたことです。現在、延岡メンマは宮崎県を中心に20の店舗、10の飲食店で取り扱われています。
エシカルバンブー株式会社【洗濯洗剤】
山口県防府市で事業を展開しているエシカルバンブー株式会社では、地元の竹を活用した洗濯洗剤「バンブークリア」を製造・販売しています。これは、主に県内(周南市、防府市)の放置竹林から伐採された竹が使われており、「竹炭」「竹炭灰」「湧水」の3つだけが原材料という無添加の洗濯洗剤です。
同製品はもともと地元の企業で開発された洗剤がベースとなっており、その事業を継承したエシカルバンブーもまた、地域に根差しながら竹の可能性を追求したものづくり事業を行っています。
株式会社おおいたCELEENA【セルロースナノファイバー】
放置竹林を原料としたセルロースナノファイバー(CNF)の開発を行なっているのが株式会社おおいたCELEENAです。同社では、大分大学理工学部での基礎研究によって生み出された竹由来CNF「CELEENA®」の製造・販売を手がけ、同商品は燃料電池や空気電池用の電極材料として利用されています。
セルロース純度が高く、長さや強度に優れるなど、竹ならではの特性を生かしたCELEENA®は生分解性と皮膚・眼・毒に対する安全性も確認されており、多彩な用途への利用が期待されます。
大和フロンティア【農畜産飼料・肥料】
大和フロンティアは、宮崎県都城市で農畜産業関連事業を中心に展開している企業です。
同社は、価格が高騰するスギのおが屑に代わる新たな畜産飼料として竹に着目。地元の放置竹林の問題を解決する目的とも相まって、竹を飼料や肥料として加工した「笹サイレージ」の研究・開発に乗り出します。
2016年から量産化された笹サイレージは、パウダー状にした竹を糖蜜と混ぜてパッケージし発酵させたもので、
- 牛の枝肉重量の増加、オレイン酸数値の向上、繁殖雌牛へのビタミンA供給、ストレス低減
- 豚舎の臭気対策、臭みのない柔らかい肉質、食肉中脂肪酸含量向上
- 土壌改良(土中の雑菌の繁殖抑制・善玉菌の活性化)による栄養吸収の向上、根の張りや収穫量、生育の向上
など、家畜飼料や農業用有機肥料として低コストで優れた効果を発揮する製品として好評を博しています。
株式会社緑水園【竹するめ】
株式会社緑水園は、鳥取県南部町の緑水湖畔でコテージやバーベキュー場を併設する宿泊施設を経営しています。同社が地域の環境保全活動の一環として、放置竹林の竹を利用して製造・開発したのが「竹するめ」です。
これは、タケノコとしての収穫タイミングを過ぎて2〜3mに伸びたモウソウチクの穂先を湯がいてスライスし、味付けして乾燥させたものです。するめのような食感と深い味わいがお酒のおつまみやおやつに最適として、緑水園のおみやげ売り場や米子空港でも販売されています。
放置竹林(竹害)に関するよくある質問
放置竹林の活用に興味のある方に向けた、よくある疑問を見てみましょう。
放置竹林(竹害)に関する補助金はある?
放置竹林の整備や竹林対策については、林野庁や地方自治体から各種の補助金が交付されています。現在林野庁による「林野庁における竹林整備及び竹材利用に係る対策」で補助の対象となっているのは以下のとおりです。
森林整備事業
人工林内に侵入した竹の伐採・除去、間伐など、周辺の森林に影響を与える竹林の整備を支援するものです。主に自治体や森林所有者、森林組合、森林整備法人など、森林経営計画の認定を受けた者が支援の対象となります。
森林・山村多面的機能発揮対策(地域環境保全タイプのうち「侵入竹除去、竹林整備」)
主に地域住民らによる放置竹林の整備活動全般の取り組みを市町村などの協力で支援するものです。対象となるのは
- 竹や雑草木の伐採・搬出・処理・利用
- 森林調査・見回り、機械の取り扱いや伐採技術などに関する講習
- 活動結果のモニタリング、傷害保険
- 各種刈払機や資材、機器、車両、施設などの購入・賃借料の支援
など多岐にわたり、竹の伐採・除去活動には最大で28.5万円/ヘクタールが補助されます。
事業主体となるのは、地域住民または森林所有者などからなる3名以上の団体、地域の自治会、NPO法人などで、幅広い担い手による活用が期待されます。
森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち林業・木材産業循環成長対策
この対策では、主に森林資源の循環利用のための取り組みを総合的に支援します。
具体的には
- 竹林改良、作業道整備、チッパーや竹割機、竹粉製造機などの機械、乾燥施設やバイオマス利用促進施設など林産物生産基盤の支援
- 林産物生産技術研修や林業技術研修の実施を支援
など、竹材の加工や再造林の低コスト化に向けた取り組みを支援するものです。
こちらは自治体、森林組合、農協、農事組合法人、林業者団体などの事業主体が補助の対象となります。
この他、各地方自治体でも放置竹林対策の一環として竹林整備に対する補助金を交付している都道府県・市町村があります。
詳細は当該自治体へお問い合わせください。
放置竹林がある土地を購入できる?
竹林の購入自体は可能です。放置竹林の処置に困り、売却を検討している土地所有者も少なくありません。ただし、山林や竹林は
- 取引件数が少なく価格変動が激しいため、正確な相場の確認が難しい
- 山林・竹林を扱う不動産会社が少ない
など、一般の不動産と比べ売買のハードルが高くなります。
放置竹林の購入を考えるなら、信頼できる不動産会社に依頼するのが近道です。特に山林・竹林の近くの不動産会社は、林地の取引実績があり、売買に対応できるところも少なくありません。
この他の方法としては、全国の森林組合に相談する方法もあります。
林地の売買を斡旋している地域の森林組合の中には、売却・購入の相談を受けているところもありますので、興味のある方は尋ねてみてはいかがでしょうか。
放置竹林を伐採するにはどこに依頼すればいい?
放置竹林の伐採は、地元の林業組合や造園業者、森林整備を専門とする事業者に依頼するのが一般的です。自治体によっては、竹害対策を請け負う業者の紹介や、補助金を受けられる制度を案内してくれる場合もあります。
依頼先を選ぶ際は、伐採だけでなく、地下茎の除去や再発防止策まで対応できるかを確認することが重要です。また、地形やアクセス状況によって作業方法や費用が変わるため、複数の業者から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。
特に傾斜地や住宅地近くの竹林では安全管理が必要となるため、経験豊富な業者を選ぶことが望まれます。
放置竹林の管理費用はどれくらいかかる?
放置竹林の管理費用は、竹林の面積、竹の密度、地形条件、作業方法によって大きく変動します。一般的には1反(約1,000㎡)あたり数万円から十数万円程度が目安ですが、傾斜地や密生している竹林ではさらに高額になることがあります。
伐採作業だけでなく、地下茎の除去や切り株の処理、処分費用も加わるため、初期費用は想定より高くなる場合があります。さらに、竹は成長が早く、管理を怠ると短期間で再び繁殖するため、年1回〜数回の定期管理が必要です。
長期的な視点で予算を組み、補助金や地域支援制度の活用も検討すると負担を抑えられます。
放置竹林が隣地に越境した場合の責任は?
放置竹林が隣地に越境した場合、民法の規定により、土地所有者は越境した竹の伐採や根の除去に応じる義務が生じる可能性があります。竹の地下茎は地中で広がりやすく、知らぬ間に隣地の地表に芽を出すこともあります。
放置すると、作物の被害や景観の悪化、構造物の損傷といった損害賠償請求の対象になる場合があります。隣地所有者が自ら越境した竹を切除することは可能ですが、トラブルを避けるためには事前に連絡・合意を取ることが望ましいです。
越境を防ぐためには、境界付近の定期的な伐採や防根シートの設置といった予防策が効果的です。
放置竹林対策とSDGs
放置竹林対策は、SDGs(持続可能な開発目標)の複数の目標と関連してきます。
最も関連が深いのが
- 目標15「陸の豊かさを守ろう」
- 目標11「住み続けられるまちづくりを」
- 目標12「つくる責任 つかう責任」
です。目標15では、森林や山地の保全、回復によって生物多様性を強化し、持続可能な利用を確保することなどが掲げられています。竹林の放置が他の森林を侵食することでそうした機能が損なわれないために、日本の農林水産業を挙げてのさらなる対策が求められています。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ
日本人の生活や文化は、古来から竹によって支えられ、発展を遂げてきました。しかし、過去数十年にわたって放置されてきた竹は、私たちの生活基盤となる大地を文字通り足元から突き崩しかねない存在となりつつあります。
資源も燃料も乏しい日本において、山からもたらされる恵みが現在改めて見直されてきています。さまざまな可能性を秘めた竹をより有効に活用するために、放置竹林はいま最も解決されるべき問題の一つと言えるでしょう。
参考文献・資料
竹の利活用推進に向けて:林野庁
森林資源の現況 確報 森林資源の現況(令和4年3月31日現在) |e-Stat 政府統計の総合窓口
広がる竹林をどうしよう?という時に 放置竹林の把握と効率的な駆除技術:鳥居厚志, 上村巧編. — 森林研究・整備機構森林総合研究所関西支所, 2018.
竹林整備と竹材・タケノコ利用のすすめ方 / 全国林業改良普及協会編. — 全国林業改良普及協会, 2014. — (林業改良普及双書 / 全国林業改良普及協会編 ; 176).
「竹害」はどうして起こるのか? 日本の放置竹林の現状と課題|環境とサステナブルを学ぶ BambooRoll STUDY
放置竹林が及ぼす問題は?対策事例も合わせて紹介 | 金沢機工株式会社
野中重之,九州における放置竹林問題と求められる対応方策 タケノコと竹の有用性を踏まえて:地方自治ふくおか/68巻 (2019)
竹林の拡大に関する景観生態学的研究:真鍋 徹, 柴田 昌三, 長谷川 逸人, 伊東 啓太郎 景観生態学 25 (2), 119-135, 2020
農家が教える竹やぶ減らし : かしこく切って、じゃんじゃん活用 / 農文協編. — 農山漁村文化協会, 2021. — (現代農業 ; 2021年10月号別冊).
LOCAL BAMBOO INC.
延岡メンマ – 森を育てるメンマ / NOBEOKA BAMBOO SHOOTS – BAMBOO SHOOTS TO GROW THE FOREST
ethical bamboo
大和フロンティア株式会社|次世代飼肥料「笹サイレージ」
竹するめ – 緑水園
株式会社おおいたCELEENA
林野庁における⽵林整備及び⽵材利⽤に係る対策(令和6年度)
【山林・竹林を売りたい方必見】山林・竹林の売却方法を解説!平均相場・税金・必要書類は?|株式会社torio real estate(トリオリアルエステート) > 不動産査定・売却ブログ
この記事を書いた人
shishido ライター
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。








