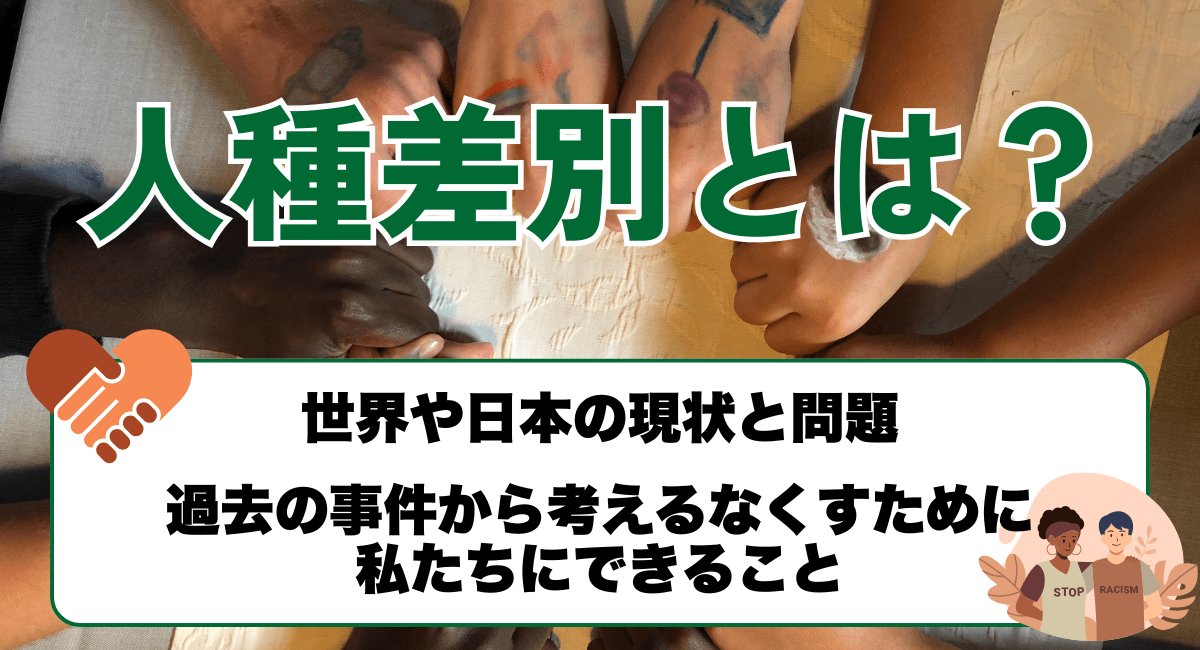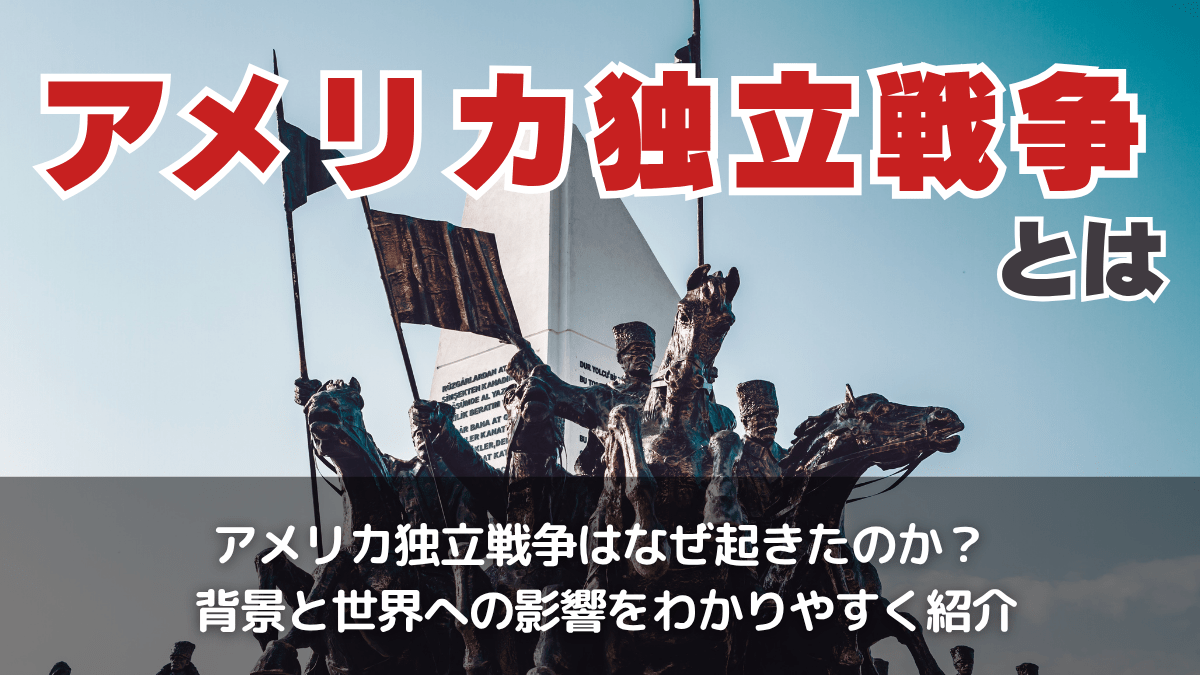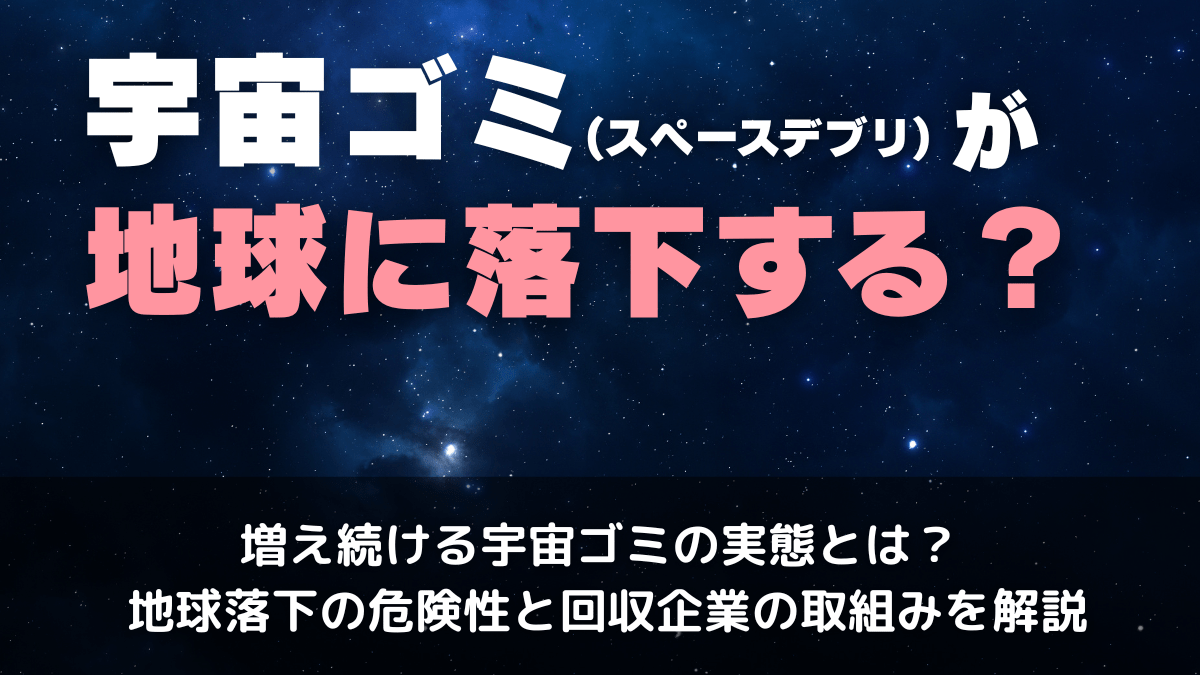鈴木 京子
1999年 舞台・イベント制作会社 有限会社(現株式会社)リアライズを設立。
2001年 同年より国際障害者交流センタービッグ・アイの事業企画に関わる。
2011年 株式会社リアライズ退社、国際障害者交流センター ビッグ・アイ 事業プロデューサー就任。
2018年国際障害者交流センタービッグ・アイ副館長就任。ビッグ・アイの仕事をきっかけに障害のある人が舞台芸術に表現者や鑑賞者として参加できる舞台の企画、制作や全国の劇場・音楽堂等の研修会講師、企画・制作等のコーディネートをおこなう。
特定非営利活動法人CUE-Arts 理事。文化庁・厚生労働省「障害者の芸術活動への支援を推進するための懇談会」委員。大阪府「文化芸術部会」委員。 堺市南区政策会議委員。全国公立文化施設協会コーディネーターほか。著書「インクルーシブ シアターを目指して/障害者差別解消法で劇場はどうかわるか」(ビレッジプレス)
森田 かずよ
俳優・ダンサー。「Performance For All People. CONVEY」主宰。大阪府出身。先天性の障害(二分脊椎症・側湾症)を持って生まれ、18歳より表現の世界へ。自分の身体と向き合い、表現の可能性を日々楽しく考えながら、俳優&ダンサーとして活動している。
ヨコハマ・パラトリエンナーレ、SLOW MOVEMENT、庭劇団ペニノ、日本財団・ユネスコ主催『アジア太平洋障害者芸術祭』(シンガポール・2018)、東京2020パラリンピック開会式など多数の公演やイベントに出演。球体人形作家 井桁裕子氏と共にほぼ等身大である自身の裸体人形を製作、イギリスのメディアアーティストRichard Butchinsと共同製作したものはイギリスのアンリミテッドフェスティバル(2018年)で公開されるなど、様々なアーティストとコラボレーションを行う。
近年は、障害のある人や市民参加のダンス公演の振付や演出、ワークショップ講師やレッスンなどを行う。神戸大学人間発達環境学研究科人間発達専攻博士前期課程修了。
目次
introduction
ビッグ・アイ共働機構が国から委託されて運営する「国際障害者交流センタービッグ・アイ」(大阪府)。障がいのある人に国際交流や芸術・文化活動の場を提供し「完全参加と平等」の実現を図るこのシンボル的施設は、国民一般にも広く開かれています。
今回は、同センターの概要と国際ダンス・ワークショッププロジェクトについてを鈴木京子副館長に伺い、講師参加の森田かずよさんに、ダンスの道を歩くなかでのご自身の変容のプロセス、当事者から見た障がい者と社会の「今」を伺いました。
「ビッグ・アイ」が、障がい者の国際交流と芸術活動の支援として開催する国際ダンス・ワークショッププロジェクト
–まずは、「国際障害者交流センタービッグ・アイ」の概要と役割をご紹介ください。
鈴木さん:
「国際障害者交流センタービッグ・アイ」(「ビッグ・アイ」と表記)は、2001年に設置された国立の身体障害者福祉センターA型施設です。舞台公演ができるホールやリハーサル室などを備え、舞台芸術活動ができる設備を持つ福祉施設は「ビッグ・アイ」だけだと思います。管轄は厚生労働省、管理運営を委託されているのが「ビッグ・アイ共働機構」です。
「ビッグ・アイ」が作られた目的は、「障害者の完全参加と平等」を達成するための、
- 障がい者の国際交流・協力
- 障がい者の芸術・文化の発信
- 全ての障がい者が交流できる拠点
- 大規模災害時の後方支援
この4つの事業を柱として、様々な活動を行っています。


–障がい者へのサポートは、通常どのようなかたちで行われているのでしょうか?
鈴木さん:
基本的には、スタッフの経験やノウハウを活かして、障がいの種別ごとにサポートしています。ただ、たとえ障がいの種別が同じでも、個人の環境や身体的特性などで異なりが生じます。ですから、対象者と双方向で話し合い、どのような環境を作れば対象者の表現活動がしやすくなるか、というところを考えて活動しています。
–2023年8月26∼27日に国際的なダンス・ワークショップが開催されるとのことですが、その目的と内容をお聞かせください。

鈴木さん:
アジア4か国と日本7地域の振付家、障がいのあるダンサーを講師に招いてのダンス・ワークショップ「Breakthrough Journey Dance Camp」は、今年単発の企画ではなく、2019年から始まったプロジェクトのひとつです。

人は、障がいの有無だけではなく、それぞれ違った背景を持っています。このワークショップの目的は、身体、言葉、民族など、様々に違う人々が舞台芸術を通じて交流し、互いの異なりを認め合う、受容しあう、理解しあうことで、共生社会の実現を目指すことにあります。
今年は、多彩な講師陣による5つのプログラムを用意しています。それぞれ定員は20名ですが、障がい者を含む様々な参加者にダンスを楽しんでもらえることと思います。「ビッグ・アイ」だけでなく、どんなところでも、誰もがダンスをしたいと思えばできる環境と場所を作っていかねばなりませんから、いろいろな地域に種をまいていくということも目指しています。

「身体」が違うだけで「特殊」ではなく、問題は「特殊」という考えを持つか持たないか
–ありがとうございました。次に、このワークショップに講師として参加される森田かずよさんにお話を伺わせていただきます。まず、森田さんが持たれている障がいについてお聞かせください。
森田さん:
主としては、二分脊椎症と脊椎側弯症という障がいを持っています。二分脊椎症というのは、先天的に脊椎の一部が欠けている状態です。その損傷部分から下の感覚や運動機能が非常に弱くなっています。
そして、脛骨という足の骨が一本ないので、義足をつけています。また、脊椎側弯症では、身体の背骨がぎゅっと曲がった状態で、肋骨が三本ありません。そのために内臓が圧迫され、機能が弱くなっており、肺活量は普通のだいたい三分の一くらいですね。
–ダンスに出会われる前の森田さんの年月は、どのようなものでしたか?
森田さん:
子どもの頃からダンスをやりたかったわけではないです。普通の女の子として育ってきました。ラッキーなことに、小、中、高校と普通学校に通い続けることもできました。障がいがあることでいじめられもしましたし、いろいろな目にも合ってきました。でも、私は生まれつきこの身体ですから、これが当たり前で、出来ないことはできないし、工夫することで出来ることもあります。「障がい者だから」と思ったことは、そこまで多くなかったと思います。
高校二年生の時、宝塚と音楽座のミュージカルを観て、初めて自分でも踊ってみたい、という気持ちになりました。大学を受験する時に、最初から諦めたくなくて、芸大を受けようと思ったんです。ところが、20年以上前の状況では、障がいによって、受験すらできませんでした。悔しくもありましたし、その時初めて自分は障がい者だと突きつけられた気がしました。もちろん、障がいがあると分かってはいましたが、社会的に障がい者だと強く感じたんです。
そして障がいがあることによって受けた差別以上に、障がいがない人は、障がいのある人が踊ったり表現したりすることを想像すらしないということもわかり、ショックを受けました。
–どのようにしてダンスの道を開拓されたのですか?
森田さん:
受験の扉を閉ざされてからは、様々な試行錯誤をしながら今に至っています。芸術系ではない大学に入り、演劇サークルに所属し、ミュージカルスクールに入れてもらいました。一歩一歩という感じです。健常者だけの世界で障害者が私だけ、その環境でどう自分の存在を認めてもらうか。道のない道を歩いていくような状態でした。
私がダンスを始めた頃は、障害のある人がダンスをする土壌が今ほど整っていなかったので、苦労しましたね。今もなお制度だけでなく、たとえば教える側のダンサーたちも、身体の違う人たちにどうやって教えたらいいか分からないと思います。いろいろなものがまだ育っていませんね。
作品を作るということに関しては、障がいは「特殊」ではないんです。バリアフリー的には特殊かもしれませんが、ダンスに関しては、「身体が違う」だけで「特殊」ではありません。「特殊」という考えを持つか持たないか、です。意識の変革ということが大切です。
障がいをフィルターとしてものの見方を変え、社会を少し違った方向で見る
–ご自身の身体、心と向き合いつつダンスを極めてこられたことと思います。どのようなプロセスだったのでしょうか?
森田さん:
まず、自分の身体を直視できるか?ということが、私の大きな闘いでした。例えば、自分が歩いている、踊っている姿を撮影されたものを抵抗なく観られるか、というようなことです。障がいがない人が大多数を占めている社会に私たちはいるので、私が普段目にする人、というか人間は、整った身体をしています。私の頭の中に刷り込まれている人間の動き方と、私自身の実際の動きはかけ離れていて。まずその祖語に気付くことが大切でした。
自分の動きは、普段見ている人たちの動きと大きく違うということ…それをちゃんと認めて、自分で(自分の動き方はこうで、こういうことができるんだ)というのを把握すること、自分の身体に慣れるということ、自分に何ができるかをちゃんと見るということ、私は、それに結構時間を費やしたような気がします。
–産まれながらの障がいに対して、ネガティブな思いよりも、「何ができるか」というポジティブな挑戦に一直線にいけたのでしょうか?
森田さん:
いえいえ、すぐにはいけてないです。ただ、ネガティブな方に行かなかったのには、理由があります。まず、私はファンキーな母親を持っていて、「私は障がいを持っているあなたの気持ちは絶対にわからない。でも、あなたも、障がい者を産んだ母親の気持ちはわからない」とすごく言われました。そう育てられたんですよ。そこに怒りは産まれなかったですね。
もし、母のお腹の中にいる時に障がいがあることがわかったら、たぶん、産む選択をしなかったと思うんですよ。私、生まれてこなかったと思うんです。実際、私が生まれてからも、
一回は死んでほしいと願ったことがある、って言われたんですよね。それは、特に私の子ども時代は、障がいに対する社会の目も違い、差別も今よりもっとありましたし、障がい児やその家族に対するサポートや情報が少なかったことも理由のひとつだと思います。現実に母は私を愛して育ててくれました。
そんな中、偶然というか、運命的にこの世に生をうけたので、少々のことは受け流せるようになりました。もちろんそのような環境にいられたお陰だとも思います。もちろん時には人と比較してネガティブになることもありますし、社会の仕組みに腹を立ててしまうこともあります。マイノリティーが生きにくいのが現実です。
ただ、私は踊ることによって、それが少しは解消されたんです。障がいのある身体、それぞれの身体にはそれぞれが纏う世界があり、またその身体にしか出せないものがあると知ったからです。ひとつの例ですが、とても速い振付を完璧にそろえることだけが正解ではありません。ダンスも多様な表現があります。身体の違いを生かすこともできます。私が人と違った身体を持ったからこそ、「違う」表現があることを知ることが出来たんだと思います。

–視点が変わって、ご自身に変容が起こったのですね。
森田さん:
自分自身が明らかに変わったと思います。最初は健常の方と一緒にレッスンを受けていたので、自分と他者の身体の比較しかできなかった時もあり、どれだけ頑張ってもあの身体にはなれないんだ、って思ったんです。そこに気づけたのは大きかったですし、だからこそ、自分のやり方を探さねばならないと思えたのは良かった。
ただ、それは障がいごとに違いますし、それは私のやり方だと思ってください。いろいろな方向があるし、その人が何をやりたいか、自分がどの方向に向かいたいか、ということが大事です。
自分の身体の動く範囲で動くことで、ダンスはどこまでも作っていける
–いかに自分を知ることが大事か、ですね。障がいのあるなしに関わらず、すべての人に響くお話だと感じました。シュタイナーが「ダンスは、目が見えなくても、耳が聞こえなくても、四肢が不自由でも、身体があれば踊ることができる最後の芸術」と語ったそうですが、究極の自分との対話だと感じました。森田さんも、ダンスを同様のものと捉えますか?
森田さん:
私は実際に、今カンパニー活動で目の見えない方と一緒にダンスを作っています。その通りだと思います。
また、先日は病院内の支援学校で、重度の障がいがあり、指をほんの少し動かせる子とワークショップをしてきました。私のこれまでのワークショップの切り札では太刀打ちできないと思いました。その子の、かすかな動き(指だけでなく、目線なども)も表現であり、そこを引き出せたらいいなと考えました。
ワークショップ当日、先生とその生徒さんペアで、指の先で会話をするようなダンスに挑戦してもらいました。言葉を発することが出来ない生徒さんでしたが、指を通して先生と心を通い合わせているような、とてもいい時間でした。
指一本を合わせて動くことだけでもダンスになります。普段のスピードの中ではなかなか気づくことが出来ません。でも違う身体に出会い、違う表現に出会うことで、また新しいダンスを発見できました。ダンスの可能性って無限大だと思うのです。

–高齢者でも重い病者でも、その人なりの踊りを踊れるのですね。パラリンピックの開会式で、まさに森田さんは、唯一無二の「森田かずよ」さんのソロダンスを披露されました。その時のお気持ちや、まわりからの反応をお聞かせください。
森田さん:
あの時は精一杯すぎて、自分の置かれた事の重大さがよくわかっていなかったようにも思います。コロナ禍で一番患者数が増えていた時期でしたし、そんな時にあんな大きなイベントをやること自体の是非が私の耳にも届いていました。その中で、自分の体調を崩さず最後まで生ききる、踊りきることだけが、私のすべてでした。
終わってから、とても嬉しい感想をたくさんいただきました。ダンス評論家の方が、「身体が持つ「生」の力を肯定してみせる踊り」※と言ってくださり、やってよかったと思いました。
※TOKYO ART BEAT
踊り/ダンスとオリンピック・パラリンピック(文:武藤大祐) 【シリーズ】オリパラは日本の文化芸術に何を残したのか?(2)
多種多様な障がいのある人が大勢、あの空間にいれたことも本当によかったです。身軽な方だけではなく、あの中には、医療ケアが必要なパフォーマーもいて、本当に多様でした。
「自分以外の人は皆それぞれ違う」という意識を持つ大切さと、自分の特性を社会と共に「価値」として持つ大切さ
–今回の国際ダンス・ワークショップの講師としては、どのような抱負をお持ちですか?
森田さん:
プログラムでは、私にとってレジェンドのようなダンサー・振付家の田畑真希さんと組ませていただくので、勉強させていただく気持ちしかないです。でも楽しみでワクワクしています。
田畑真希さんは健常者の講師ですが、障がいのある人ない人、ダンス経験のある人ない人、様々な方と創作をされていて、尚且つ非常に美しい舞台をつくられる方です。
今回は様々な障がいのある方が参加してくださるので、田畑さんと一緒に、ひとりひとりと向き合って、それぞれの身体の動きに着目したいです。それぞれの身体から発する動きや、日常生活の中にある動きなども組み合わせてダンスを作っていく予定です。
–最後に、鈴木さん、森田さん、それぞれに今後のご展望を伺わせてください。
鈴木さん:
多様な人を受容し、共に生きるための環境をどう創造していくか。その追及につきます。これは、ダンスの世界だけではなく、社会全体に対してでもあります。
この仕事をして24年ほどになりますが、この10年で、障がい者にとっての便利さとかアクセシシビリティなどは劇的に良くなっているのですが、半面、人は皆それぞれ違うもの。それをリスペクトする、認め合うという意識への変容にはまだ遠く感じます。
文化や舞台芸術は、その意識の変容を促すよいコネクターになると思っています。今後も、作品を作ることが目的ではなく、それが観る人や社会にどう伝わっていくかを考えながら舞台作品やワークショップを作っていきたいです。
今、リアルな社会でもネットの中でも、心の痛むことが多々起こっていますよね。人々が少しでも多様な価値を認め、もう少し人の痛みに敏感になれる社会となるために、自分ができることは、多様性や寛容性の気づきにつながる活動を続けていくことだと考えています。
森田さん:
鈴木さんがおっしゃったように、障がい者をめぐる環境は、この10年で大きく前進しました。ただ、当事者が表に出ていくことは増えても、なかなか心の中が伴っていかない状況です。当事者として、自分たちが何を見せたいのか、何をしていきたいのか、ということをもう少し考えていけるといいなと思います。
ダンスをやりたい、ダンスを楽しむ、というのでも全然いいんです。ただ、もし、今後それを続けていきたい、それを生業として生きていきたいと思う人がいるのなら、障がいとは何か?社会の価値観と自分の身体や表現についても、自身で考えられたらいいですね。
ダンスで何をしたいのか、社会と共に、自分の特性をどう「価値」として持っていくか、というところまで繋げていきたいんです。もちろん、障がい者と言われる前に、私たちは一人の人間です。ただ、その中で、せっかく障がい者として生まれてきてしまったので…私たちはそう生まれてきてしまったので、障がい者ということをちゃんと捉え、何ができるかを考えていけたらと思います。
—「ダンス」だけではなく、何にでも置き換えられる気づきをたくさん頂けました。今日はありがとうございました。
国際障害者交流センタービッグ・アイHP:https://www.big-i.jp/
この記事を書いた人
壱岐 梢 ライター
ライティング、詩作、翻訳…様々なかたちで言葉と共に仕事をしています。 この世界に入ったきっかけは、宮沢賢治との出会いでした。彼は究極のSDGs 実践者。大好きな言葉の仕事によって、今SDGsに取り組む皆様をご紹介 できることは、大きな喜びです。
ライティング、詩作、翻訳…様々なかたちで言葉と共に仕事をしています。 この世界に入ったきっかけは、宮沢賢治との出会いでした。彼は究極のSDGs 実践者。大好きな言葉の仕事によって、今SDGsに取り組む皆様をご紹介 できることは、大きな喜びです。