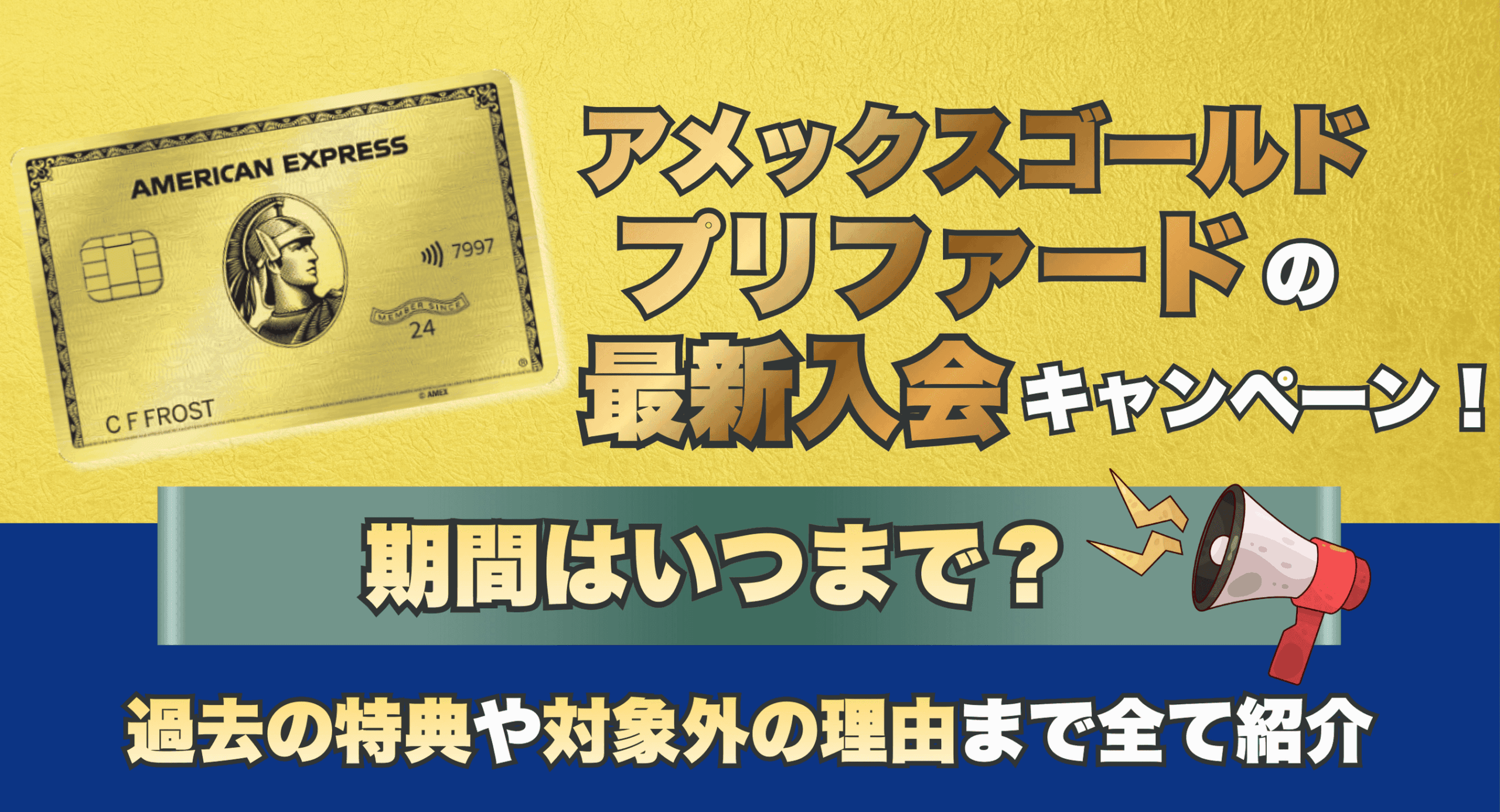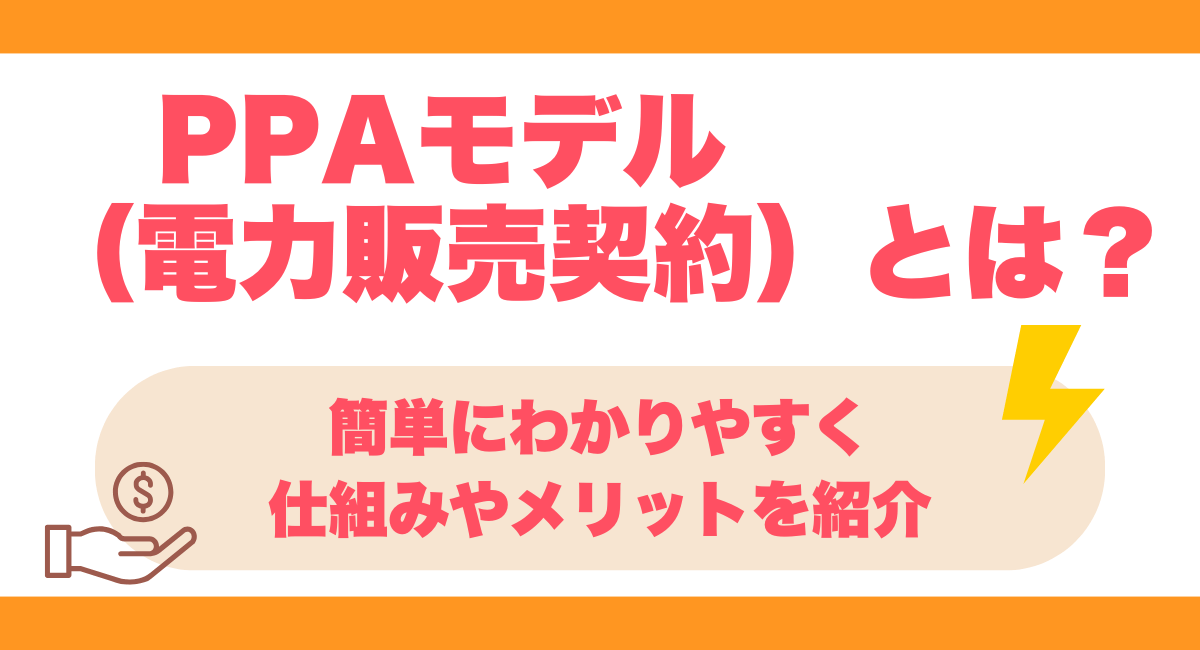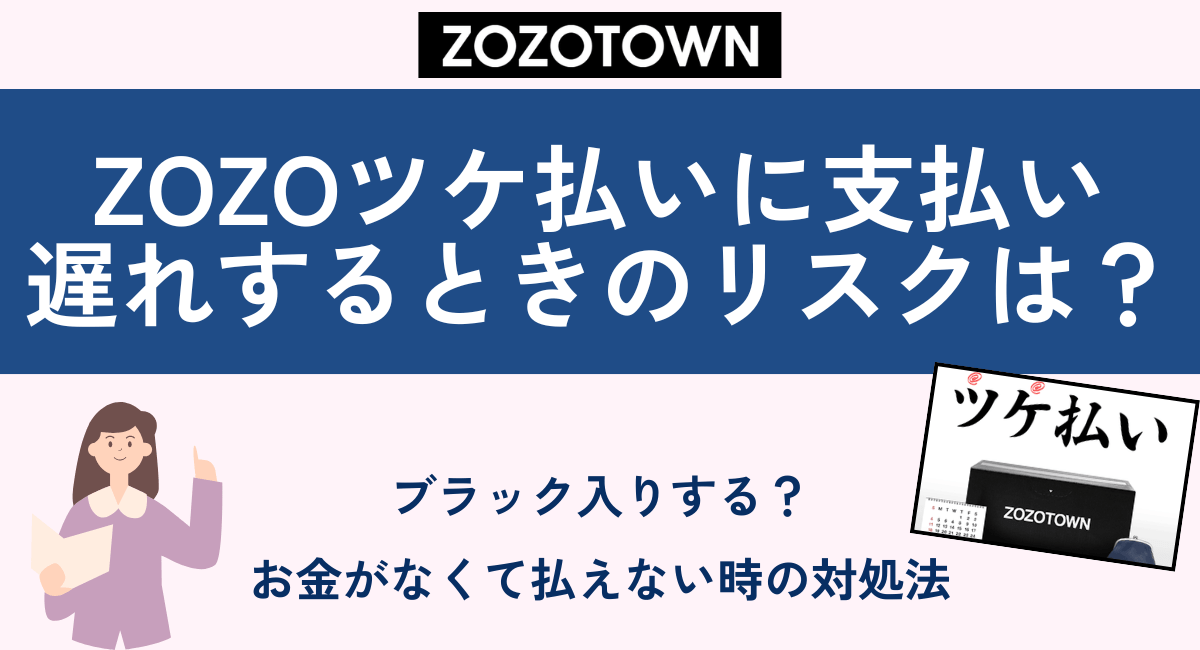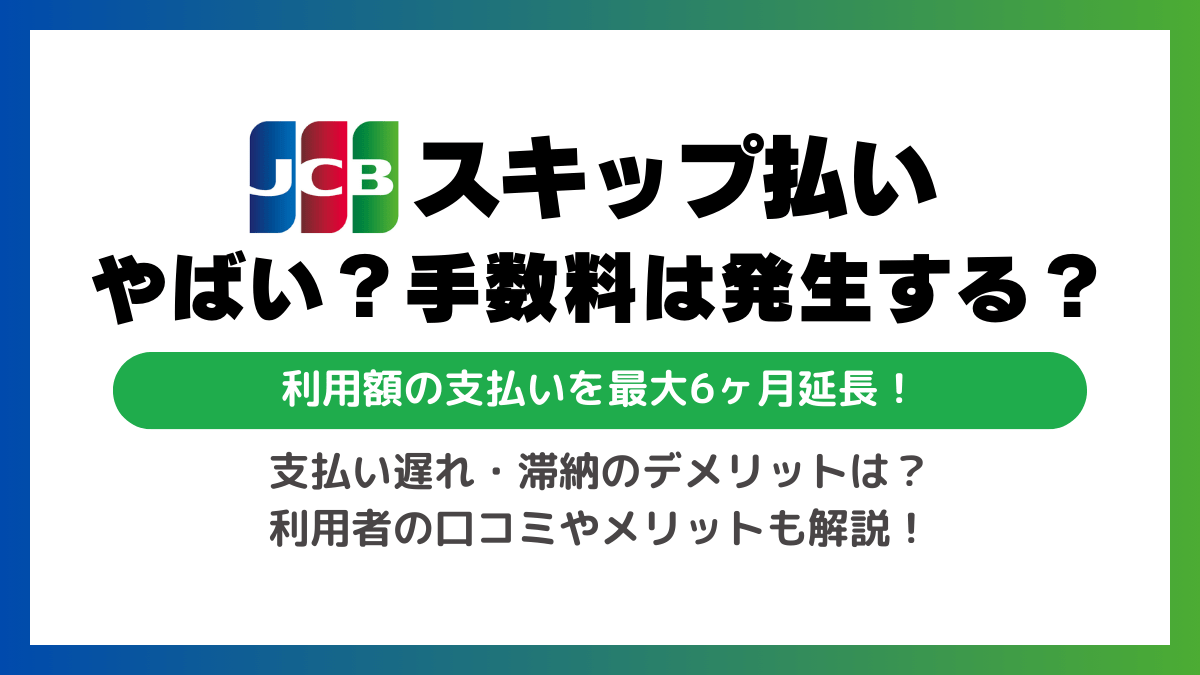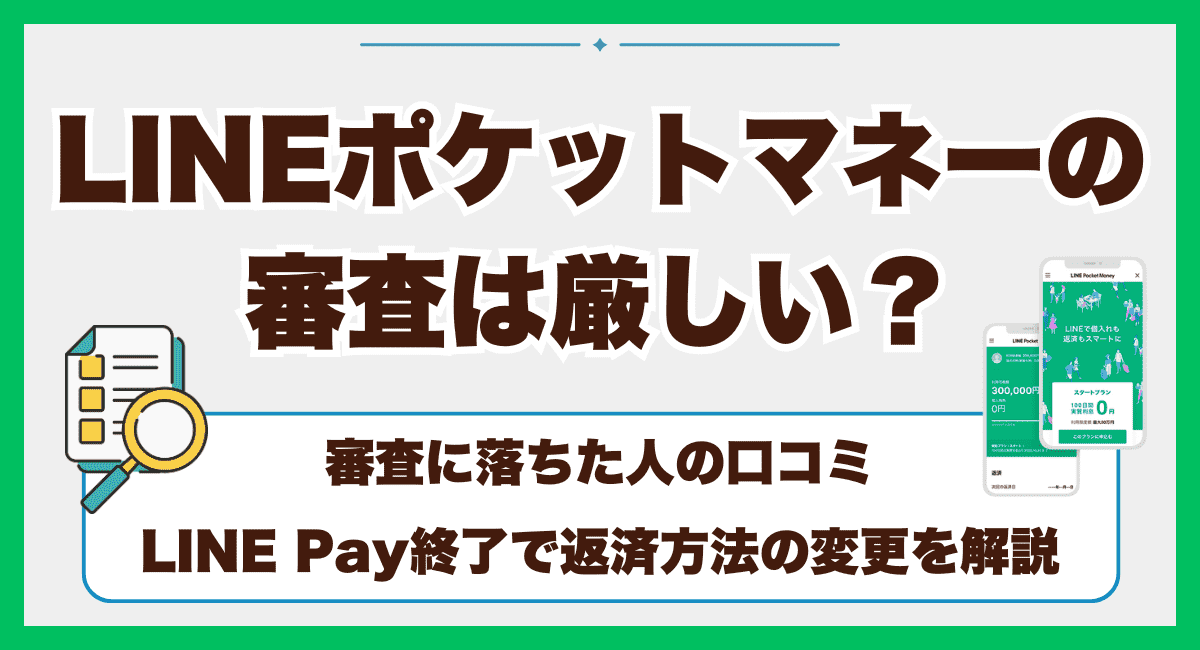環境保全の意識が高いオーストラリアでは、人間と野生動物の共存に力を入れています。
代表的なものが、フレーザー島で行われているディンゴとの共存対策です。
観光客がディンゴに襲われる事故も起きていますが、オーストラリアはディンゴを害獣として駆逐するのではなく、棲み分けることで上手く共存できると考えています。
今回は、フレーザー島が実施するディンゴマネジメントの詳細をご紹介します。
フレーザー島やディンゴの基礎知識も併せて解説するので、この機会にフレーザー島でのエコ活動について理解を深めましょう。
目次
フレーザー島について
クイーンズランド州に位置するフレーザー島は、砂で形成された島です。
1992年には世界遺産に登録されており、島内の大部分がグレート・サンディ国立公園の指定エリアです。
全長は123キロメートル、面積は184,000ヘクタールにも及び、世界最大の砂の島として知られています。
フレーザー島は、2023年にK’gariという名称に変更されました。
先住民であるアボリジニ・Butchulla族の言葉で「楽園」を意味しており、島内には絶滅危惧種の動物が多く生息しています。
ディンゴってどんな動物?
ディンゴは、イヌ科の肉食獣です。
元々はオーストラリアに生息していなかったものの、4,000~8,000年ほど前に南アジアから持ち込まれたと言われています。
その後、オーストラリアでディンゴの個体数が増えたと同時に、他のエリアでディンゴの姿が見られなくなったことから、ディンゴはオーストラリアの固有種として認識されるようになりました。
見た目は犬にそっくりなディンゴですが、気質はオオカミそのもので非常に獰猛です。
体長は平均1メートルほどの中型から大型の個体が多く、オーストラリアの砂漠、海岸、草原をはじめとするさまざまなエリアで生息しています。
3~12頭前後の群れを形成するのが一般的で、主な餌はネズミ、ウサギ、ワラビー、ポッサム、爬虫類、ヤギ、魚、キツネ、猫、鳥類などさまざまです。
フレーザー島のディンゴによる被害
フレーザー島は、ディンゴの代表的な生息地のひとつです。
現代のディンゴはイエイヌとの交配が進んでおり、混血のディンゴが増加傾向にあります。
しかし、フレーザー島のディンゴは純血種の割合が多く、オーストラリア東部で最も純血種に近いディンゴが見られるエリアです。
野生動物としての本能を持ち合わせたディンゴが必然的に多くなることから、フレーザー島ではディンゴによる被害が深刻化しています。
主な被害が、観光客を対象としたものです。
フレーザー島は、毎年50万人近い観光客が訪れる国内有数の観光地です。
観光エリアでの食べ歩きや、大自然の中でキャンプを行う人々も多いことから、食べ物を狙うディンゴが観光客に危害を加えるケースが相次いでいます。
置いていた食べ物を奪われる、荷物や生ゴミを漁られる、コテージのキッチンに入ってくるといった被害のほか、食べ物を持っている観光客がディンゴに直接襲われるといった事故も発生しています。
2001年には小学生がディンゴに襲われて死亡するという痛ましい事故も起きており、フレーザー島は特に観光客への被害防止を大きな課題としているのです。
実際に行われているディンゴマネジメント
フレーザー島では、2018年から2023年にかけてディンゴが人を襲う事故が33件も発生しています。
ディンゴと人間の共存を目指すためにも、オーストラリア政府はフレーザー島でディンゴに関するさまざまな対策を行っています。
以下は、通称・ディンゴマネジメントと呼ばれる対策の詳細です。
ディンゴフェンスの設置
フレーザー島には、5,320㎞にも及ぶフェンスが設置されています。
フェンスを島内に張り巡らすことで、ディンゴと観光客の接触や観光客がディンゴの生息地に立ち入ることを防いでいるのです。
尚、フェンスはディンゴの主な餌場を考慮して設置されているため、ディンゴの狩猟に悪影響はないとされています。
ディンゴへの餌付けの禁止

ディンゴマネジメントで重要なポイントのひとつが、観光客への意識改革です。
犬のような見た目をしているディンゴに対して、観光客は警戒心を解いてしまう傾向にあります。
さらに、細身なディンゴを見て「痩せてしまってかわいそう」「何か餌をあげたい」と考える観光客も多く、食べ物を見たディンゴが興奮して事故に繋がるケースも後を絶ちません。
ディンゴと観光客のふれあいを無くすために、フレーザー島ではディンゴへの餌付けを全面的に禁止しています。
観光客がディンゴに近付くことがないように、啓発活動に力を入れているのです。
フレーザー島では、ディンゴを野生下の環境で自然に生かすことを目的としています。
島内のディンゴは最大で12頭の群れで生息しており、群れの中には地位が低く餌にありつけない個体も存在するのが実情です。
中には飢餓で命を落とすディンゴもいますが、自然界では一般的なこととして捉えられています。
フレーザー島におけるディンゴは、食物連鎖の頂点に立つ生物です。
個体数が増えすぎると生態系が崩れてしまうことから、フレーザー島ではディンゴの淘汰に決して干渉しません。
淘汰は野生下で起こり得る当然のこととして考えられており、ディンゴが適切な個体数を維持するために必要な餌は自然界に十分にあります。
そのため、フレーザー島ではディンゴに対する餌付けを禁止し、ディンゴが自分たちで自然界の餌を狩猟できるように促しているのです。
エコツーリズムの催行

フレーザー島では、インストラクターによるさまざまなエコツーリズムが行われています。
島内を巡りながらフレーザー島の動植物やディンゴの生態について解説しており、ディンゴに関する以下のようなリスク、対処法、注意点も啓発しています。
- ディンゴへの禁止事項(ふれあい、記念撮影、餌付けなど)
- ディンゴと遭遇したときの対処法
- 襲われたときの自己防衛の方法
- 常に大人数で行動すること
- 子どもだけで外を歩かせないこと
- キャンプでの食べ物の保管や処理に気を付けること
- コテージのドアや窓のカギは必ず閉めること
- 食べ歩きをしないこと
フレーザー島では、子どもが襲われる事故が多発しています。
ディンゴが夜間にコテージに忍び込んで寝ている赤ん坊を襲う事故も起きているため、特に子どもや10代の若者に対する注意事項を積極的に伝えています。
エコツーリズムとは地域にある自然の環境や文化・歴史を体験し、学ぶことを目的とした旅行スタイルのこと。
GPSを使ったディンゴのモニタリング
フレーザー島で生息する一部のディンゴには、GPSやカメラ付きの首輪が付けられています。
行動範囲や個体数を把握することで、ディンゴの保護及び人間との接触回避に貢献しています。
ディンゴに関する看板の設置
観光客=食べ物を持っていると考えるディンゴは、観光客のそばに近寄る傾向にあります。
寄ってきたディンゴと記念撮影を試みる観光客が襲われることもあるため、フレーザー島の至る場所にディンゴに関する看板が設置されています。
禁止事項などが記載されており、観光客が常にディンゴに対して警戒心を持つように工夫されているのが特徴です。
リスク評価の更新
フレーザー島では、ディンゴの危険度やリスクを定期的に調査しています。
調査結果は評価表にまとめられ、オーストラリア政府は状況に応じて新たな対策を講じるという仕組みです。
評価の更新を行うことで、ディンゴの状態を正確に把握することに繋がります。
観光客への注意喚起強化を含むさまざまな対策を徹底し、観光客がディンゴに襲われる危険性を最小限に抑えています。
まとめ
フレーザー島は、純血種に近いディンゴが生息している観光地です。
野性的な面が色濃く残っている個体が多く、子どもが襲われる事故も頻発しています。
しかし、オーストラリア政府は、ディンゴを一方的に排除するのではなく、人間と上手く共存させる生き方を模索しています。
観光客とディンゴとの接触を減らすためのさまざまな取り組みを行っており、観光客への啓発活動にも余念がありません。
また、人間による餌付けを禁止することで、ディンゴたちが群れの中でより自然に生きられるように工夫しています。
ディンゴはもちろん、フレーザー島全体の生態系を守るために、オーストラリアでは必要以上に干渉しない野生動物保護を意識しています。
この記事を書いた人
Mahogany_socks ライター
オーストラリアでの大学院留学を経て、現在は現地で動物関係の仕事をしながらwebライターとしても活動中。 仕事を通して培った知識や経験を活かして、野生動物保護やエコ活動に関するコラムをwebで紹介しています。
オーストラリアでの大学院留学を経て、現在は現地で動物関係の仕事をしながらwebライターとしても活動中。 仕事を通して培った知識や経験を活かして、野生動物保護やエコ活動に関するコラムをwebで紹介しています。