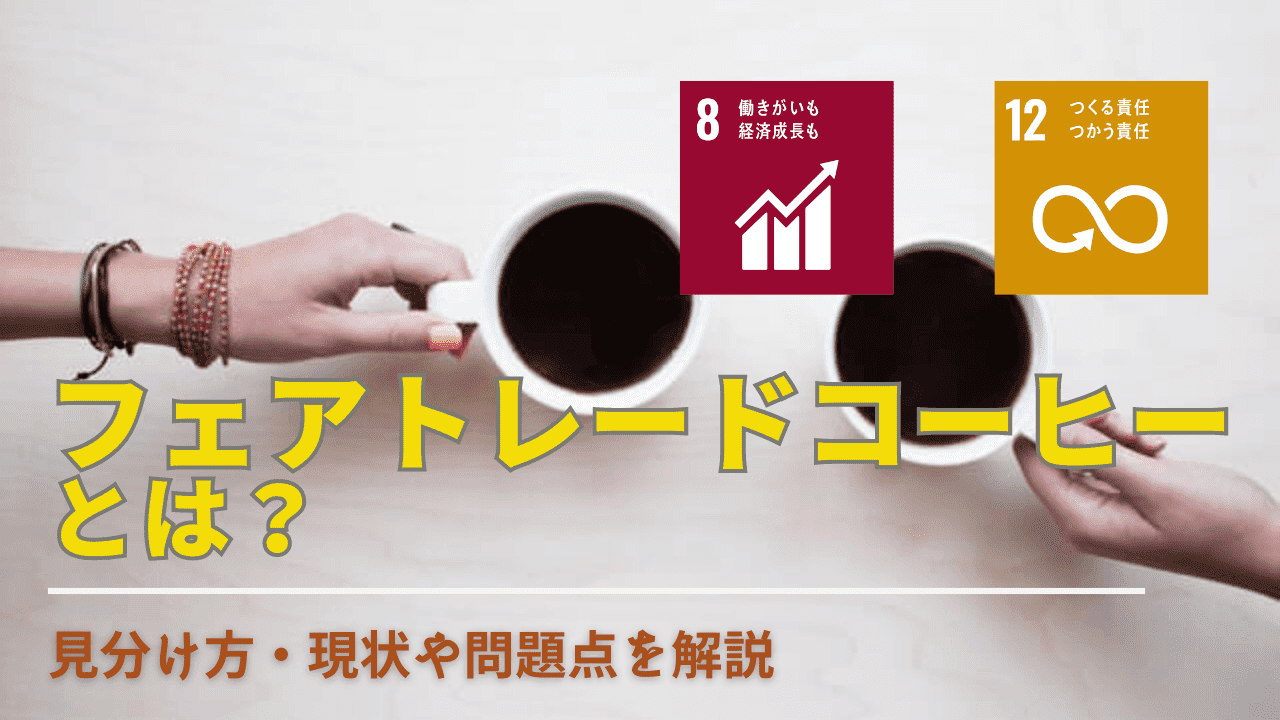
一杯のコーヒーから1日が始まる、という方はたくさんいるでしょう。
ただ、そのコーヒーは、
- 誰によってつくられて
- どんな環境で育てられて
- 人と地球環境にどのような影響を与えているか
を知る機会はなかなかないと思います。
しかし最近では、SDGsへの関心の高まりもあり、生産者や生産方法にも目を向けようという動きが加速しつつあります。
そのためのキーワードは、買い物を通した国際協力を意味する「フェアトレード」。
この記事では、フェアトレードでも特にコーヒーに焦点を当て、詳しく見ていきます。後半では、「ヤマノバコーヒー」代表の山本さんをゲストにお迎えし、フェアトレードコーヒーの本質に迫ります。
目次
フェアトレードコーヒーとは?
フェアトレードコーヒーとは、フェアトレードによって取引されたコーヒーのことです。
そもそもフェアトレードとは何かを簡単に確認しましょう。
そもそもフェアトレードとは
フェアトレードは、以下のように定義されています。
フェアトレードとは、より公正な国際貿易の実現を目指す、対話・透明性・敬意の精神に根 ざした貿易パートナーシップのことを言う。フェアトレードは、とりわけ南(発展途上国) の弱い立場に置かれた生産者や労働者の人々の権利を守り、彼らにより良い取引条件を提供 することによって持続的な発展に寄与するものである。
フェアトレード団体は、消費者の支持のもとに、生産者への支援、人々の意識の向上、そし て従来の国際貿易のルールや貿易慣行を変革するキャンペーンを積極的に推し進める団体で ある。
引用:国際フェアトレード憲章
これまでの生産から消費の流れは、
生産者→仲介業者→貿易業者→企業→店舗→消費者
というものでした。
これだけの流れが生じれば、おのずと生産者に渡る金額は少なくなり、貧困や所得格差が広がる問題がありました。
これに対してフェアトレードは、
生産者→フェアトレード団体→消費者
と、間に入る業者を減らすことでより多くの利益が渡るようになっており、生産者の生活が保障されるようになります。
フェアトレードは作り手にも良くて買い手にも良い
フェアトレードは、生産者だけでなく買い手にも良い影響を与えることも魅力のひとつです。
『フェアトレードビジネスモデルの新たな展開 』(長坂寿久 編著)によると、フェアトレードとは、
- 途上国の人々を幸せを分かち合うこと
- 買い物は選挙の一票と同じに大切で、社会を変える力をもっている
- 途上国の人のことをよく知り、対等につながること
としています。
つまり、フェアトレード製品が、
- どこの国のどんな人がつくったのか
- どんな環境で、どんな思いでつくったのか
- 素材はどのように育てられたのか
- どのような背景でつくられたのか
を私たち消費者が知ることで、生産者と顔を合わせることはないものの、つながることができるのです。
フェアトレードコーヒーのメリット
フェアトレードコーヒーが、公正な取引によるコーヒーであることに加えてもう一つ特徴があります。
それは、人と人、人と地球をつなぐコーヒーだということです。
これはどのような意味なのかもう少し踏み込んで、「生産者への意識」「環境への意識」「格別の味わい」の3つの点から見ていきましょう。
生産者への意識を持てる
フェアトレードコーヒーは、生産者の事情が見えるコーヒーです。一般的にコーヒーは、
- つくる人
- 売る人
- 買う人
の3者がかかわっているにも関わらず、生産地が開発途上国に限られ、消費者は主に先進国に住んでいるため、互いの事情を知る手段は少ないものです。
このような状況の中で、フェアトレードコーヒーが普及することにより、開発途上国でコーヒー生産に携わる人々の貧困問題、社会問題が消費者に伝えられるようになりました。
フェアトレードの認証機関の広がりもあり、生産者への興味関心や問題への意識を持ち始める消費者も増え始めています。
環境への意識を持てる
フェアトレードコーヒーは、自然環境にも配慮しています。
国際フェアトレード基準によると、
- 農薬・薬品の使用削減と適正使用
- 有機栽培の奨励
- 土壌、水源、生物多様性の保全
- 遺伝子組み換え品の禁止など
引用:フェアトレードジャパン 国際フェアトレード基準
と、環境的基準を設けており、
- 保全区域に対する負の影響及び農園・生産区域の内外にあるHCV(保護価値の高い地域)を含む区域内での負の影響の発生を避ける義務
- 湖等周辺の緩衝帯及びHCV区域と生産区域の間の緩衝帯の維持義務
- 不耕作区域でフェアトレード産品の野生採取を行う場合、採取対象となる種の在来生息地での持続可能性と生存性の確保義務など
引用:フォレストパートナーシップ・プラットフォーム
といった生態系保護のための規定もあります。
数ある選択肢の中からフェアトレードコーヒーを選ぶことで、地球環境、生態系保護につながるのです。
格別の味わいを楽しめる
社会問題、地球環境問題について考えさせられるフェアトレードコーヒーですが、適切な品質管理のもとで栽培されるため、味わいも格別です。
国際フェアトレード基準では、
商品代金とは別に支払われるプレミアム(奨励金)を民主的に運用し、組織と地域全体の社会・環境にとって持続可能な発展に取り組む。また付加価値の向上や品質管理への取組みなどを通して生活向上を目指す。
引用:フェアトレードジャパン
と、持続可能な生産を続けるために、品質において生産者が守るべき規定があるため、品質の向上が期待でき、おいしいコーヒーが生まれるのです。
このように、フェアトレードコーヒーは、環境・社会・経済すべての面で恩恵をもたらすコーヒーといえますが、どのように見分ければ良いのでしょうか。
フェアトレードコーヒーの見分け方
お店でフェアトレードコーヒーかを見分ける方法は、
- 認証マーク・ラベルが付いているか
- 上記以外の場合、製品情報が明確かどうか
が挙げられます。1つずつ見ていきましょう。
フェアトレード認証マーク・ラベル
フェアトレードコーヒーには、認証マーク・ラベルが貼られているケースが多く見られます。
フェアトレード認証マーク・ラベルは、
- 団体向けに付けられるもの
- 商品に付けられるもの
の2種類。
1 団体向け「フェアトレード認証マーク」
フェアトレード認証マークは、国際フェアトレード連盟IFATに加盟している団体に付けられるマークです。
IFATは、世界の生産者団体70カ国300団体が加盟する組織で、互いに情報共有しながらフェアトレードを普及しています。
認証を受けるには、IFATが示す9つの基準にクリアする必要があり、認証を受けた団体の製品であれば、間違いなくフェアトレードだという特徴があります。
日本では、ピープル・ツリーと、ネパリ・バザーロがIFATに加盟しています。
2 商品向け「フェアトレードラベル」

フェアトレードラベルは、商品単体に付けられるもので、国際フェアトレードラベル機構FLOが発行するラベルです。
IFAT認証マークとはまったくの別物となります。フェアトレードラベルの特徴は、一般企業の商品にも付与される点です。
認証される基準は、国際フェアトレード基準の3つの原則
- 経済的基準
- 社会的基準
- 環境的基準
のもと、
- 「生産者の対象地域」
- 「生産者基準」
- 「トレーダー(輸入・卸・製造組織)基準」
- 「産品基準」
などを満たした商品に付けられます。※2
フェアトレードコーヒーを購入する場合は、上記2種類のマークを目標に探すと良いでしょう。
しかし、認証マーク・ラベルが貼られていなくてもフェアトレードコーヒーである場合もあります。そのような場合、次のことをポイントに商品選びをすることをおすすめします。
フェアトレード認証ラベルがついていない場合の見分け方
ラベルがついていない場合、商品を取り扱っている企業のHPやパンフレットをチェックしてみましょう。
例えば、
- 生産者がどのような人たちか
- どのような環境で製品が作られているか
- 買い物によってどう社会貢献できるのか
というような、フェアトレードの活動状況を明らかにしているか、活動目的が明確であるかが書かれているか確認することで、フェアトレードコーヒーであるかがわかります。
フェアトレードに興味がある方は、購入前に商品について調べる習慣をつけると良いかもしれません。
「ヤマノバコーヒー」から学ぶ本質的なフェアトレードコーヒー
ここまで読むと、なんとなくはフェアトレードコーヒーのことがわかったものの、
- 本当に外国の農家の人たちの生活を救えているのか
- 言葉の意味どおり、本当にフェアな取引がなされているのか
といった疑問を抱く方もいると思います。
確かに私たちは、現地を訪問して実情を確認することは難しいため、インターネットや書籍の情報でしかフェアトレードコーヒーについて知る術はありません。
もし、実際に足を運ばれた方の体験を知ることができれば、さらにフェアトレードコーヒーを身近に感じられ、日々の買い物でもより意識できるようになるのではないでしょうか。
そこで今回、日本でフェアトレードコーヒーの普及に貢献しておられる「ヤマノバコーヒー」店主の山本喜昭さんに、現地ネパールのお話を伺ってきました。
はじめに、ヤマノバコーヒーをご紹介します。
ヤマノバコーヒーとは
ヤマノバコーヒーは2016年にスタートした、「アウトドアとスローライフのクリエイティブレーベルYAMANOVAが輸入販売しているコーヒーブランド」です。
ヤマノバコーヒーが大切にしていることは、人と自然のつながり。
自然を身近に感じることで、人間にとって大切なチカラを取り戻し、自らの意志で人生のハンドルを握り進んでいく。
そんな生き方を、映像やイベント、コーヒーを通して提案しています。
ヤマノバコーヒーが届けるネパール生まれの「ナマステヒマラヤ」

ヤマノバコーヒーでは、ネパール生まれのフェアトレードコーヒー「ナマステヒマラヤ」を取り扱っています。
ナマステヒマラヤの特徴
ナマステヒマラヤのコーヒー農園は、荒廃した土地に1から植林して森自体を再生し、徹底した管理のもとで自然の森に近い環境で農作物を育てます。
コーヒー豆は樹木の日陰で栽培されゆっくり育ちます。そうすることで種子の密度が上がり、深い香りを持つ良質なコーヒーが生まれます。
他にも、
- 無農薬・化学肥料不使用
農園はアメリカとヨーロッパのオーガニック認証を取得しているため、品質管理が行き届いています。 - すべて手摘みのコーヒー豆
機械を一切入れず、コーヒー豆はすべて手摘みで収穫されます。 - フェアトレード
ナマステヒマラヤのコーヒー農園は、ネパールの女性たちの雇用創出と自立支援に貢献しています。 - 焙煎へのこだわり
日本に届いた生豆は、オーガニックとフェアトレードに特化して焙煎している千葉県のスローコーヒーさんで焙煎されています。 - 在庫を抱えず、食品ロスを防ぐコーヒー
ヤマノバコーヒー は食品ロス削減のために最初から在庫を持たない形となっています。
このように、さまざまなこだわりが詰まっているのが「ナマステヒマラヤ」です。※3

ではここからは会話形式で山本さんのお話を紹介します。
自然を愛する人からコーヒーの魅力を拡めたい。
–山本さんがフェアトレードコーヒーを扱うようになったきっかけを教えてください。
山本さん:
知人からもらったネパールみやげのコーヒーが本当に美味しかったんです。これはぜひ日本に広めたい!と思ったのがきっかけです。
さらに知人に詳しく聞くと、そのコーヒー豆は森林伐採で荒地となった国有地を国から借り上げ、植林によって森を復活させた「森林農法」で栽培されていること、そしてそこで働いている人々は、人権侵害から救い出された女性たちで、雇用の場になっていることを知りました。
そんなすばらしいストーリーを持つコーヒーに惚れ込んだんです。
リーフレットに込められた想い
–ヤマノバコーヒーのリーフレットには、自然の中で、動物と歩きながらコーヒーを楽しんでいるイラストが描かれているのが印象的です。どのような想いが込められていますか。
山本さん:
リーフレットは、コンセプトや私の想いがギュッと詰まっています。私はもともとアウトドアの仕事をしていて、そのご縁で出会ったのがナマステヒマラヤのコーヒーです。
アウトドアコーヒーを拡めることで、社会問題や環境問題にコミットしたい。そのためにも、まずは自然を愛する人たちにこのコーヒーを楽しんでもらい、その輪を広げていきたいという想いを込めています。
現代社会の中で「生きる力」を養う
–リーフレットには、『自然と人の生きるチカラがつながる』というフレーズが描かれています。この言葉の背景を詳しく教えていただけますか。
山本さん:
ヤマノバコーヒーが考える『生きるチカラ』は、人が自然とつながり、自然を身近に感じることで、自らの意思で自らハンドルを握り、人生を進んでいくチカラです。
私は、結果だけでなくプロセスを知ることが、生きる力になると考えています。アウトドアの仕事に関わるようになって、自然の中で遊んだり寄り添って暮らしたりすることで、生きている実感を感じられたんです。
しかし最近は、体験や情報など、調べれば結果がすぐに手に入ってしまう便利な世の中になりましたよね。便利なこと自体は、豊かになるために追求し続けてきた結果なのでいいことです。ただ、便利さと豊かさは必ずしもイコールではないと感じます。
最短最速で結果だけを求めても生きてる実感というか、手応えが薄れてしまうのではないかと。特に自然から離れた東京で暮らしていると顕著に感じるんですよね。
そんな現代だからこそ、生きるチカラの再起動が必要なんじゃないかなと。
フェアトレードの現状や問題点
–ではここからフェアトレードについて質問させてください。フェアトレードは適正な賃金が届くシステムとされていますが、これは本当なのでしょうか?
山本さん:
正直、どのくらいの額がフェアなのかは現地に住んでみないと誰にもわからないんです。
フェアトレードで賃金が届いたとしても、当然、私たちのような便利すぎる生活はできていないはず。
ネパールの社会問題を考える
–ちなみにネパールはどのような場所なのでしょう?
まず、ネパールの社会問題として、女性の地位が低いんです。特に山村部は貧しく、男性でも働き口がない。また、公立学校には適切に教えられる先生がおらず、教育も平等に受けられないところもあると聞きます。
そしてネパールには従来あったカースト制度が残っています。カーストの高い人か、運良く奨学金を得られた人は私立学校に通い、質の高い教育を受けられます。
こう聞くと、カースト制度という言葉にネガティブに聞こえるかもしれませんね。
確かに差別は残りますが、一部のカースト上位の人は下位にいる人たちを支援しようと活動していることもあります。実際、ナマステヒマラヤのコーヒー農園は、傷ついた女性の人権を守るためにカーストの高い人が20年も前に開拓し、女性の人権を守るために始めたプロジェクトです。
誘拐・人身売買で心に傷を負った女性たち
–ではナマステヒマラヤのコーヒー農園ではどのような女性が働いているのでしょうか。
山本さん:
人身売買や誘拐された経験のある女性たちが多く働いています。ネパールでは女性の誘拐や人身売買が後を絶ちません。
仮に助け出されても、普通に社会生活を送れるかというと、古い慣習が残っているため、
汚れた存在と見られてしまい、差別されたりもするようです。
誘拐されるのは、主にカーストの低い少女たちです。貧困であることと、適切な教育を受けていないため正しい情報を得られず、誘拐の被害に遭いやすいのです。
このプロジェクトは、そのような女性たちや障がいを持っている人たちの雇用を支えるための場所なのです。
フェアトレードコーヒーは儲け優先のコーヒーではない
山本さん:
そして、これは女性の自立支援のために作られたプロジェクトですから、儲け優先の農園ではありません。
–プロジェクトによって女性の生活はどう変化したのでしょうか。
山本さん:
それはまだわかりません。ヤマノバコーヒーがスタートして3年が経ったところで一度訪れましたが、その時は農婦のみなさんの作業を見学しただけで、実際にご自宅にお伺いしたわけではないんです。その後、コロナウイルスによるパンデミックが起きたため、現在のご様子は分からない状況です。
そもそも、彼女たちの生活を拉致、人身売買といった、心にも体にも深い深い傷を負っている方々なので、生活に踏み込んだ質問や言葉は、現地の人たちも非常にナーバスになっています。
–他国で暮らす私たちが、フェアトレードのシステムを学ぶと、現地の人たちの生活を支援すると理解されがちですが、その後の生活の変化は、簡単に数値化されるものではないんですね。
山本さん:
そうです。現地の暮らしぶりを知るには、とても長い時間が必要です。
フェアトレードのためのフェアトレードではない。スタート地点に立つきっかけとなるコーヒー農園でありたい
–では、山本さんが考えるフェアトレードとはどのようなものでしょうか?
山本さん:
普通の生活を送るきっかけとなるものです。コーヒー農園は、ネパールの女性が自立できるよう支援したい、と考えたことがきっかけで始めたものです。
確かに賃金も大切ですが、普通に生活できるようになることがフェアトレードが持つ意味なのかなと。
私たちのように、生まれた時から自由な選択肢を持って人生を歩んでいる方ばかりではありません。ネパールの女性の背景を知った時、まず普通の生活をすることがスタートとなります。だから、フェアトレードのためのフェアトレードじゃないんですよ。
–コーヒー農園で働く女性たちにとって、働く場所があるということは、喜びを感じたり、生きるチカラを取り戻すきっかけになることを意味するのでしょうか?
山本さん:
働く喜びを感じているかどうかは、おそらく、その人にしか分からないと思います。切実にお金が必要かもしれませんし、境遇も違います。
–ちなみに現地の女性の方々ってどんな様子なんでしょう?
山本さん:
私がネパールに訪れたときは3〜4名くらいの女性が作業していました。
その時、少しだけ交流をしましたが、『コーヒーもっと採れたらいいね』という話をしました。
フェアトレードコーヒー生産者の実情と今後
–コーヒーをたくさん採るにはどうすればいいのでしょう?
山本さん:
農園面積を拡げていくことですね。農園自体は75ヘクタールと広いんですが、今はまだ一部しか活用していないので拡大したいですね。
–とても広いですね!東京ドームに換算すると約16個分となります。全てが農園になると嬉しいですね。ちなみにどのような作業をされているんですか?
山本さん:
すべて手摘みで行い、熟しているもの熟していないもの様々なので、収穫は長期間にわたります。
作業量が増えるのはだいたい10月から3月の収穫の時期。
その後は、精製して生豆にする作業があります。その後新しい苗を植えるというサイクルです。
すべて手摘みで行い、熟しているもの熟していないもの様々なので、収穫は長期間にわたります。
作業量が増えるのはだいたい10月から3月の収穫の時期。
その後は、精製して生豆にする作業があります。その後新しい苗を植えるというサイクルです。
–では最盛期以外は何か別の仕事をされているんですか?
山本さん:
はっきりとは聞いてはいませんが、コーヒー農園の作業だけですべての生活をまかなっているわけではないと思います。
フェアトレードコーヒーはオーガニック?
–ナマステヒマラヤは化学肥料や農薬を使わずに栽培されていますが、他の農園も同様ですか?
山本さん:
いや、農薬を使っている農園は多いでしょうね。産業的に作っているコーヒーは、売ることを目的とするのが大半なので、外敵を駆除するために薬剤を使っていると思います。
薬剤を使うと土も弱ってくるので、さらに化学肥料を使わざるを得なくなる。
ただ、オーガニックと謳っていなくてもオーガニックで育てている農園はあると思います。そもそも使う必要がない場所だとか、使うお金がなかったりとか理由は様々でしょう。
–自然とオーガニックになるケースもあるんですね。
山本さん:
旧来の栽培って、農薬自体使わず自然任せだったじゃないですか。
そう考えると、オーガニックのためにオーガニックにしているわけじゃないんですよね。
気候変動とコーヒーの密接な関係
–気候変動はコーヒー農園にどのような影響を与えているのですか?
山本さん:
気候変動をこのまま放っておくと美味しいコーヒーが飲めなくなりますね。コーヒーの2050年問題ってご存知ですか?これはあらゆるコーヒー好きの方に伝えたいことです。
消費者はフェアトレード製品を知る上でこのような真実を知っておくことが必要なのかもしれませんね。
フェアトレードコーヒーを選択肢のひとつに
山本さん:
日本では、コーヒーなどのエシカルな商品を消費することくらいしかこれらの問題になかなか向き合うのが難しかったりしますよね。環境問題がコーヒー栽培に与える影響などの理解を深めながら選んでほしいですね。
悲壮感を持ってではなく、コーヒーそのものを楽しんでほしい
–ナマステヒマラヤを頂いた時、こんなにも美味しいコーヒーは生まれて初めてだ!と感動しました。その体験が、フェアトレードコーヒーに出会ったきっかけでもあります。それ以降、私にとってフェアトレードコーヒーは、人に感動を与えるもの、と認識しています。山本さんにとって、フェアトレードコーヒーはどのような存在でしょうか。
山本さん:
嬉しいです。私にとってのフェアトレードコーヒーは、選択を楽しむものです。どうしても「フェアトレードコーヒー」というと、生産者を救わなきゃ‥と悲壮感を持つ方も多い。
また、フェアトレード製品は、お買い物を通じた国際協力と解釈されることが多く、ボランティアや寄付につながるとも思われるかもしれません。結果的にそうなることがフェアトレードですが、コーヒーは人と人をつなげるアイテムであってほしいんですよね。まず一杯のコーヒーを通じて飲む人が幸せだと感じ、その幸福を連鎖させる。これが、フェアトレードコーヒーの存在意義なのではないでしょうか。
そのため、背景にある出来事を知ったあとは、気負ったり悲しんだりせず、「今日はどのフェアトレードコーヒーにしようかな」と楽しんで欲しい。うちだけに限らずフェアトレードコーヒーの選択肢の幅も広がっていますし。
もちろんコンビニコーヒーを買っても良いでしょう。現状を知った上で選ぶことが大切なんです。そこから自由な選択は始まり、生きるチカラとなると思います。
ヤマノバコーヒーが飲める場所
まとめ
ヤマノバコーヒーが考えるフェアトレードコーヒーを伺ってみると、
- 生産者が自立するきっかけとなる存在
- 将来にわたり、ずっと美味しいコーヒーを楽めるよう努力し続ける存在
であることがわかりました。
コーヒーが直面している課題は、気候変動、社会問題、経済問題などがあり、フェアトレードコーヒーを選択肢に入れることは、課題解決を目指すひとつの手段でしょう。
ぜひ普段の買い物から意識して探してみてくださいね。
<参考文献>
※1:フェアトレードビジネスモデルの新たな展開 SDGs時代に向けて
※2:フェアトレードジャパン
※3:ヤマノバコーヒー
※4:国際開発センター 開発の理論と現場をつなぐ
※5:ネパールのカースト社会における観光産業と社会的弱者
この記事を書いた人
スペースシップアース編集部 ライター
スペースシップアース編集部です!
スペースシップアース編集部です!








