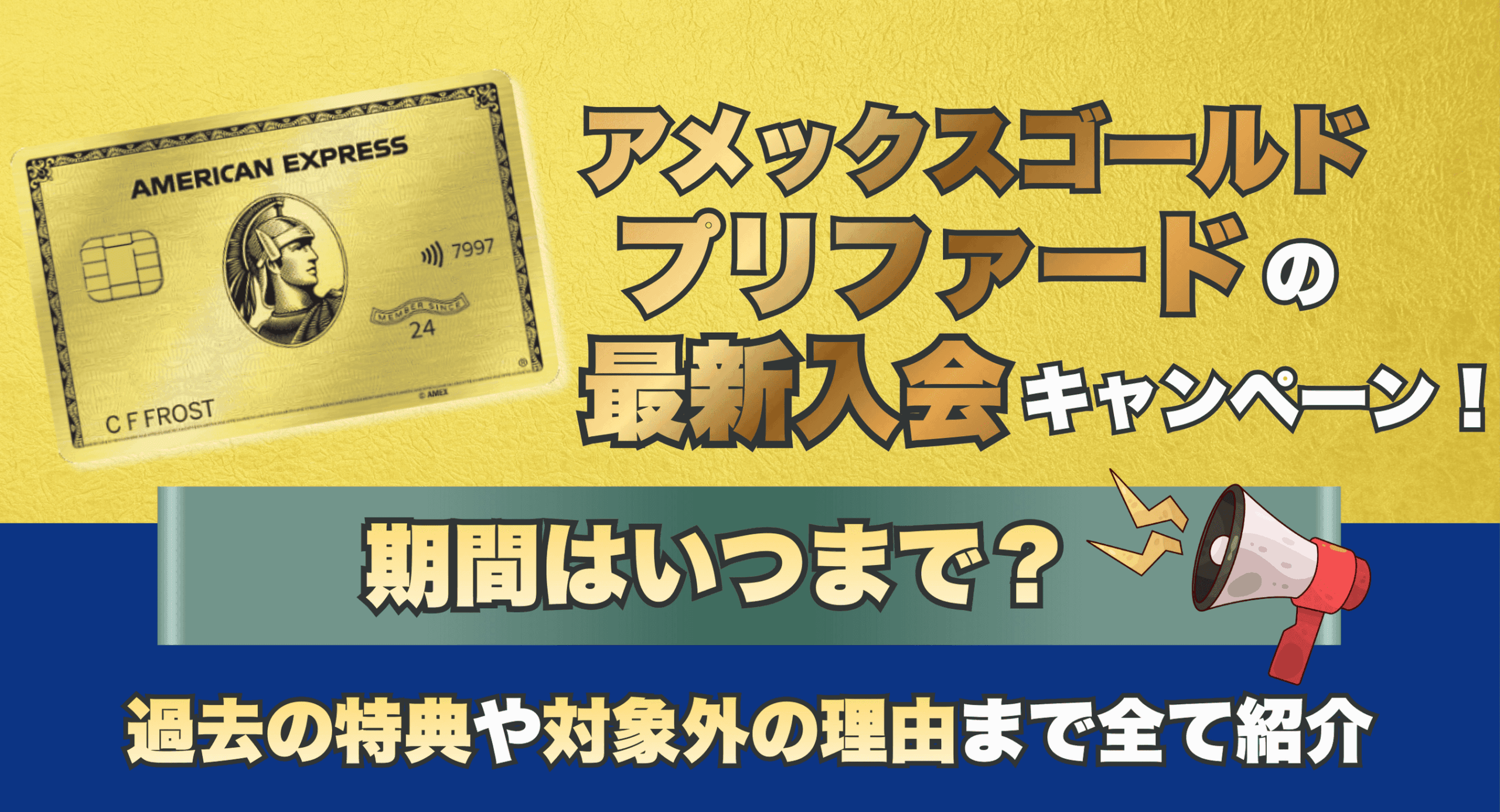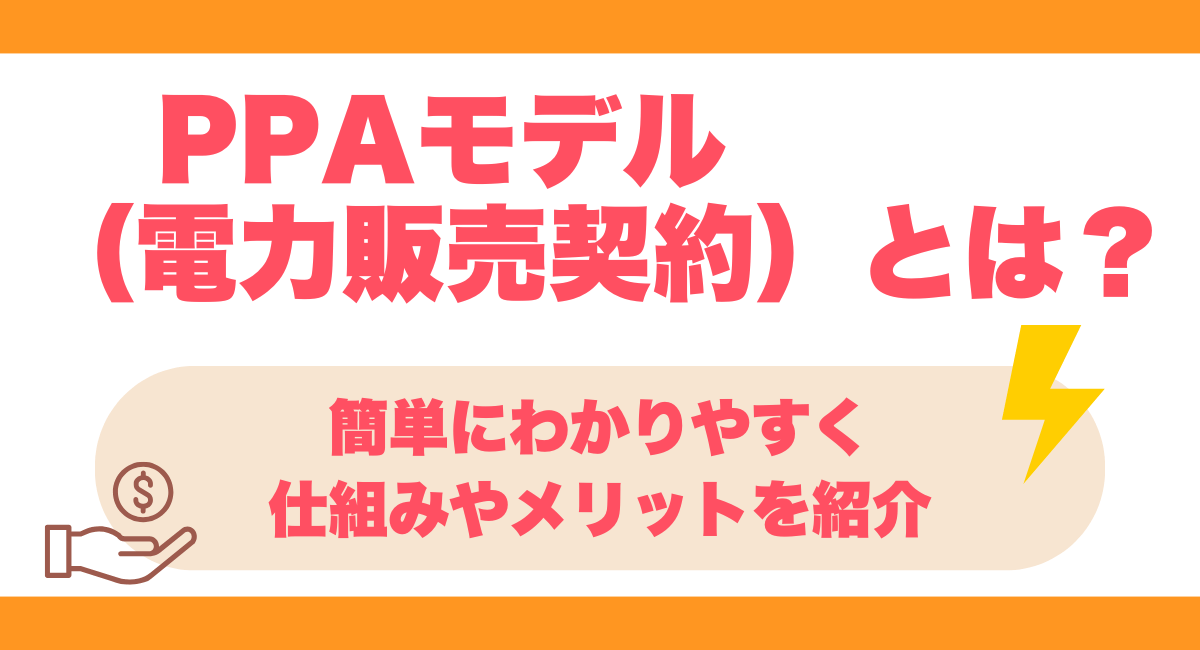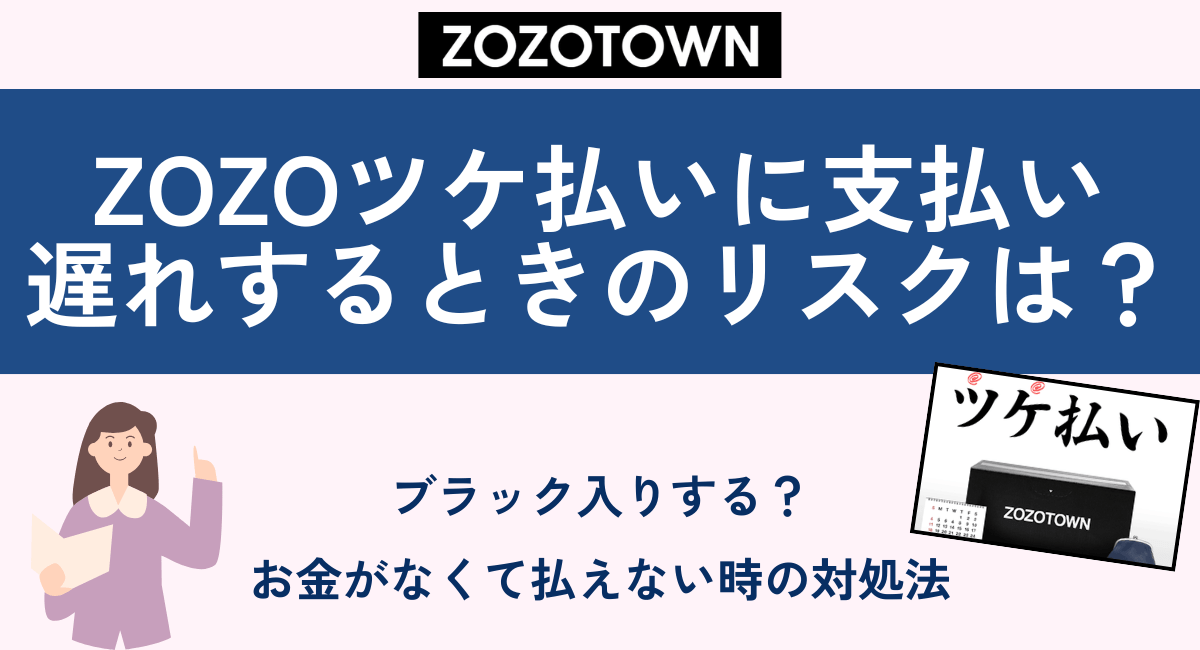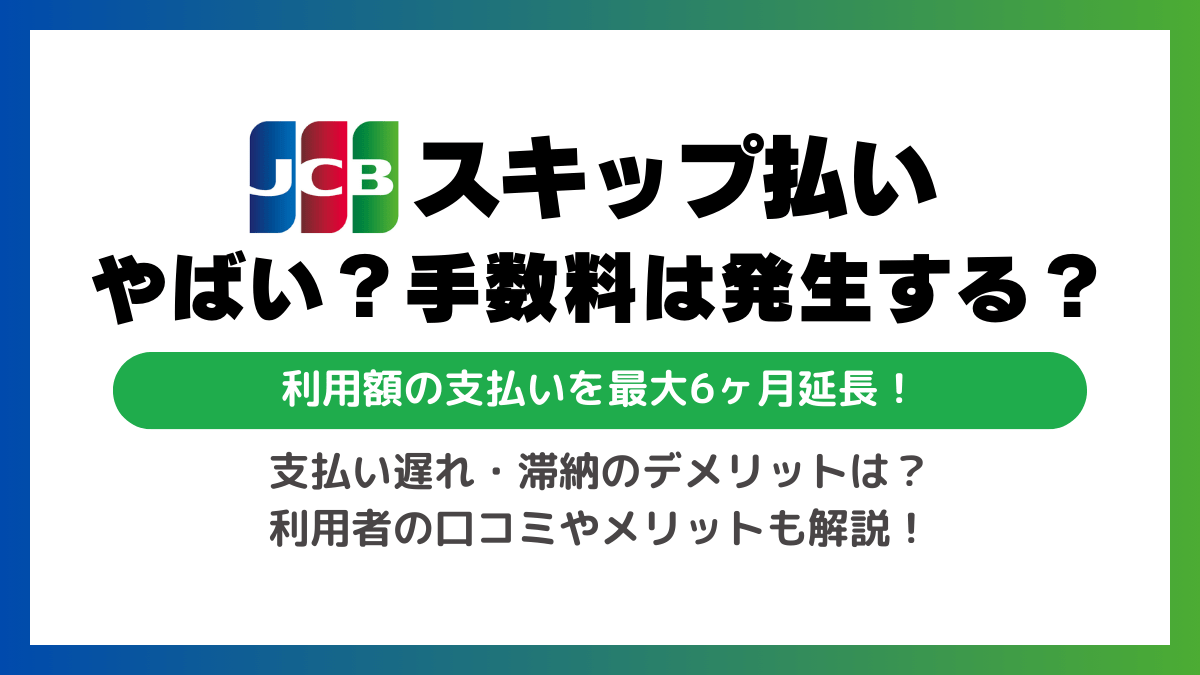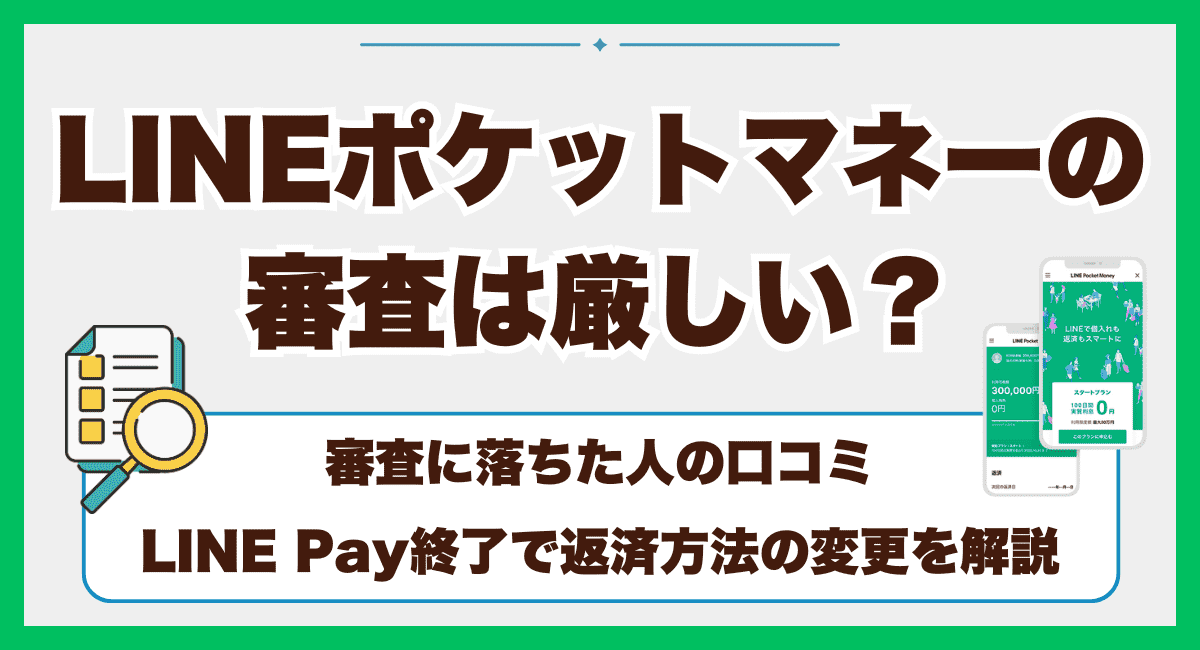現在私たちは、日常的に食べ物を得られることを当然と感じています。しかし、世界的に見ればその安定性は保証されていません。
フードセキュリティはすべての人が安全で栄養のある食料を確保するために重要であり、それは豊かな国も無関係ではありません。フードセキュリティとは何か、世界の現状や解決策について考えていきましょう。
目次
フードセキュリティとは
フードセキュリティとは、世界的な食料安全保障のことを言います。
現在フードセキュリティを表す基本的な考え方は、2009年にFAO(国際食糧農業機関)が開催した「世界食糧安全サミット」での採択に基づいており、
- すべての人がいかなる時にも、彼らの活動的で健康的な生活を営むために必要な食生活のニーズと嗜好に合致した十分かつ安全で、栄養のある食料を物理的にも社会的にも経済的にも入手可能であるときに達成される
という条件を満たすことが、フードセキュリティが保証されているとされています。
食料安全保障との違いは?
フードセキュリティの同義語としては食料安全保障という言葉があります。実際にはどちらも同じ意味として使われることが少なくありません。
農林水産省では、食料安全保障を
- 国内の農業生産の増大を図る
- 輸入及び備蓄を適切に組み合わせ、食料の安定的な供給を確保すること
- 凶作や輸入の途絶など不測の事態が生じた場合にも、国民が最低限度必要とする食料の供給を確保
といった取り組みを進めることで保証される、国民の総合的な食料の安全を確保することであると定義しています。
しかし、こうした日本ほか先進国の食料安全保障は、あくまでも国レベルのものです。
前述の通りFAOが定義するフードセキュリティは世界的な食料安全保障のことであり、世界、国と地域(地理的区分)、地方、自治体、集落、家庭、個人までに至る全体のレベルを包括するものとされています。
食料不足の問題だけではない

フードセキュリティというと、私たちは単純に「食べ物が足りている状態」であると思いがちです。しかし、広義のフードセキュリティはそうした量的な食料需給の問題だけではなく
- 物理的・経済的な入手可能性
- 構造的な貧困問題
- 栄養面に関する問題
- 社会的差別や女性差別など社会全般についての問題
などといった問題をも含んでおり、それらが私たちの食生活や農業にどのような影響を与えるのか、ということなども議論の対象になっています。
フードセキュリティの4つの要素

フードセキュリティを構成する要素には以下の4つがあり、食料政策においてこれらの要素のどれを重視するかは、国や社会によっても異なってきます。
量的充足(Availability)
量的充足とは、十分な量の食料があること、詳しくは「国内生産または輸入によって供給される、適切な品質の食料の十分な量の確保」のことです。食料が不足している国・地域への食料援助もこの供給に含まれます。
量的充足を測る主な指標としては、
- 平均食事エネルギー供給充足度
- 平均食料生産額
- 穀物・根茎類由来の食事、エネルギー供給割合
- たんぱく質供給量平均値
- 動物由来たんぱく質供給量平均値
などがあります。
物理的・経済的入手可能性(Access)

物理的・経済的入手可能性とは食料の手に入れやすさのことであり、「栄養ある適切な食料を獲得するために必要な権原(ある行為への法的根拠)への個人によるアクセス」であるとしています。この要素は、
- 道路全体に占める舗装道路率
- 道路密度・鉄道密度
- 国内総生産
- 国内食料価格指数
- 栄養不足/食料不足蔓延率
- 貧困層の食料支出割合
- 食料不足の深刻度合
といった指標から導き出され、国の経済力によって大きく左右される要素でもあります。
適切な利用(Utilization)
適切な利用とは、その食料を食べることができる状態のことです。主にその国や社会の衛生条件などが関係しており、「栄養的に満足な状態を達成するために、十分な食事、清潔な水、衛生、健康管理を通じた食料の利用」ができるかどうかという、食料・農業部門以外の重要性を示しています。
この要素を測る指標には、
- 改良水資源へのアクセス
- 改良衛生設備へのアクセス
- 消耗性疾患/発育不全/体重不足の5歳未満児の割合
- 体重不足の成人の割合
- 貧血症の妊産婦/5歳未満児の蔓延率
- ビタミンA・ヨウ素欠乏蔓延率
があり、医療や社会インフラの質、普及度合いなどとも大きく関係してきます。
安定性(Stability)
4つ目の安全性とは、必要な食料をいつでも手にすることができることで、「フードセキュリティを確保するために、いかなるときも全世帯、個人が十分な食料にアクセスできること」を意味します。
安定性の要素は、
- 穀物輸入依存率
- 灌漑された耕作地率
- 商品輸出総額に対する食費輸入額の割合
- 政治的安定性、争乱・テロ行動がない状態
- 国内食料価格の不安定性
- 一人当たり食料生産変動性
- 一人当たり食料供給変動性
といった指標から導かれ、量的充実とアクセスの両側面と関連してきます。
さらにFAOでは2020年以降、これら4つの要素に加え、新たに2つの構成要素を追加すべきという提案がなされています。その2つとは、
- エージェンシー(Agency):個人や集団がどのような食品を食べ、生産するか、フードシステムにおいて食品がどのように生産・加工・流通されるのかを決定する権利など、フードシステムやガバナンス形成のプロセスに参加できる権利
- 持続可能性(Sustainability):次世代に向けてフードセキュリティと栄養を生成するための経済的・社会的・環境的基盤を損なうことなく、フードセキュリティと栄養を確保するための長期的なフードシステムの能力
という要素であり、いずれもフードセキュリティを取り巻く背景が複雑化している現状を踏まえて提案されました。2024年の時点では公的に承認されてはいませんが、今後の議論で新しい要素として発展していく可能性はあります。
なぜフードセキュリティが大切なのか
安全な食料の確保と健康な食生活は、私たちすべての人間にとって最優先事項です。
フードセキュリティは、私たちの生命維持のためであると同時に、生きる権利や食事以外での豊かな生活を送る上でも、最も重視するべきものであると言えます。
飢餓の撲滅と「食料への権利」
飢餓の撲滅と栄養不足人口の削減は、フードセキュリティが大切な最大の理由です。
1970年代に初めてフードセキュリティが提唱された際も、背景には1940年代からの飢餓・飢饉による栄養不足人口の増加があります。
現在でも世界では9人に1人が、特にサハラ以南のアフリカ地域では全人口のほぼ4人に1人に当たる23.2%の人々が飢餓に苦しんでいる状態です。
1948年に採択された世界人権宣言では、すべての人々が健康に生きるために十分な食料をいつでも手に入れられる「食料への権利」を、人間の基本的な権利として明記しています。飢餓からの解放は、保障されるべき権利なのです。
人間の安全保障としての要素

フードセキュリティが重要なのは、それが「人間の安全保障」を実現する上で必要とされる要素のひとつであるためです。
人間の安全保障とは、UNDP(国連開発計画)が1994年に提唱した概念であり、
- 恐怖からの自由
- 欠乏からの自由
- 尊厳を持って生きる自由
という、すべての人間にとって基本的な一連の自由を尊重し、保障するために必要な取り組みを示したものです。
そしてこの人間の安全保障を実現するために、経済、食料、健康、環境、個人、コミュニティ、政治という7つの要素が提示され、フードセキュリティは食料の安全を保障するものとして位置付けられました。
「食料への権利」は人が生きるために保障されるべき権利ですが、人間の安全保障は病気や政治的弾圧、犯罪などの脅威から守られるためにも不可欠なものです。フードセキュリティは、人が社会に生きる上でも必要な概念と言えるでしょう。
先進国についての問題
食料へのアクセスに不自由しない先進国にとっても、フードセキュリティの問題と無縁ではいられません。
飢餓と栄養不足に苦しむ国がある一方で、世界の多くの国では成人の肥満の増加による健康への悪影響が深刻化しています。
FAOの推計によると、世界の成人人口に占める肥満人口の割合は2016年には13.2%に上り、実に8人に1人以上と言われています。
その多くを占めているのは、北アメリカ・ヨーロッパやオセアニア、ラテン・アメリカ地域など、食料供給に余裕のある国・地域です。フードセキュリティにおける栄養と健康の保障という面では、極めて憂慮すべきことと言えるでしょう。
そして、次章で述べるような国際情勢の変化によって、世界的な食料供給網が混乱・途絶する危険も無視できません。食の安全を守るためのフードセキュリティは、どれだけ裕福な国であっても常に意識すべき最重要政策なのです。
世界におけるフードセキュリティの現状

フードセキュリティはそれぞれの国・地域の風土や歴史、あるいは政治的状況などさまざまな要素によって成り立っています。では現在、世界におけるフードセキュリティはどのような状況になっているのでしょうか。
三大穀物と大豆の生産を占める大国
世界的なフードセキュリティを支える最も重要な作物は、米・小麦・トウモロコシの三大穀物と大豆です。単位面積当たりの収穫量や栄養価が高い三大穀物は古くから農産物の主流であり続け、現在も世界の農産物の4割を占めています。その生産を支えているのは
- 米:中国/インド
- 小麦:中国/EU/ロシア/インド/ウクライナ/オーストラリア
- トウモロコシ:アメリカ/中国/ブラジル
といった広大な国土を有する大国です。また、大豆は生産量の多くがブラジルとアメリカで占められており、両国への依存が際立っています。
食肉需要と飼料穀物の増加

現代のフードセキュリティを左右する要因は、世界的な食肉需要の高まりと、畜産に必要な飼料作物の需要増加です。
世界の年間食肉消費量を見ると、アメリカを筆頭に南北アメリカ諸国が突出して高く、次いでEU諸国が続きます。一方で、食肉消費が少なかったアジア諸国でも、経済成長に伴って近年高い伸びを見せており、世界的な食肉需要は主食穀物を上回る勢いです。
必然的に家畜の飼料となる作物への需要も高まり、そのほとんどを占めるトウモロコシと大豆の作付面積が特に飛躍的に増加しています。
現在では、世界の多くの国々が飼料穀物の需要を主要生産国からの輸入に頼るようになり、穀物貿易も拡大の一途を辿っています。
国際的なフードセキュリティ格差の拡大
一方で、食料システムの不平等によるフードセキュリティの不安定化は、高所得の国々と下位の国々との格差拡大を生み出しています。
Global Food Security Index 2022の調査によれば、最もフードセキュリティが高い国として挙げられているのはフィンランド、アイルランド、ノルウェー、フランス、オランダなどEU諸国、特に北欧の国々です。
逆にアフリカ諸国、特にサハラ以南の国々や、中東のシリア、イエメンなどはフードセキュリティが低く、2019年以降はその格差がより広がっていると指摘されています。
世界のフードセキュリティを脅かす多くのリスク
そして現在、世界全体におけるフードセキュリティの環境は悪化し、脅かされつつあると言われています。その背景には、
- 輸送ルートの迂回による物流コストの上昇
- 地政学リスクや主要輸出国の食料輸出規制の影響
- ロシアのウクライナ侵攻による小麦や化学肥料の国際的な供給不安
- 新型コロナウイルスの蔓延によるサプライチェーンの混乱
などの出来事が大きく影響しています。
そして、地球温暖化による気候変動の影響も深刻です。近年世界中で頻発する水不足や高温・豪雨などのさまざまな異常気象は、農産物の収量減少や品質の低下、病害虫や疫病の多発など、世界中の食料供給にも影響を及ぼしています。
日本におけるフードセキュリティの現状

では、日本におけるフードセキュリティの現状はどうでしょうか。
前述のGlobal Food Security Index 2022のランキングでは、日本は上位5カ国に次ぐ6位に入っており、世界的には非常に高いフードセキュリティを保っています。
その反面、
- 農業生産者価格(農家が受け取る販売価格)や農業の生産性の低さ
- 鉄分や亜鉛、ビタミンAなど微量栄養素の不足
- 気温上昇や水害のリスク
- 海洋生物多様性の低下
などの指標で課題が指摘されており、持続可能性に難を抱えています。
低い自給率と高い輸入依存
世界的なランクが高いとはいえ、一般的に知られているように食料自給率の面では日本のフードセキュリティは脆弱と言わざるを得ません。2023年度の日本の食料自給率はカロリーベースで38%、一人当たりの国産供給熱量は841kcalにとどまり、いずれも長期的に横ばい、もしくは低下傾向が続いています。特に2020年以降、日本の農産物輸入額は9兆円を超え、トウモロコシや大豆の輸入額は半分をアメリカに依存しているのが現状です。
こうした自給率の低さをもたらしたものは
- 貿易自由化による畜産物の輸入増加
- 小麦や大豆、飼料用作物・肥料などの輸入増加
- 都市化・宅地化による農地面積の減少
- 過疎化や高齢化による農業従事者の激減
- 運搬・流通にかかるエネルギーの輸入依存
などの要因です。これによって日本の農業は次第に力を失い、国内需要の増加を国産ではまかなえずに輸入に依存するようになり、自給率は低下してきました。
日本を襲うフードセキュリティリスク

最近、野菜の価格が高くなったと嘆いている方も少なくないかと思います。キャベツの値段が一時、ひと玉500円を超えたことに象徴されるように、国内における農産物の価格急騰は、フードセキュリティにおける物理的・経済的入手可能性と安全性を脅かすものです。
その背景には、
- 天候不良・猛暑や厳冬などの異常気象
- 洪水や台風の激甚化などの災害の多発
- 輸送コストの増加
- ウクライナ侵攻などによる化学肥料価格の高騰
などがあります。
また、新型コロナウイルスの蔓延、ウクライナ侵攻の影響などでもたらされた畜産飼料価格や燃料費の高騰は、国内畜産業の相次ぐ廃業の原因ともなりました。地政学リスクによる一次産品価格の高騰や供給不安は、日本の食料供給の輸入依存が抱える問題を浮き彫りにしています。
フードセキュリティを達成するためには
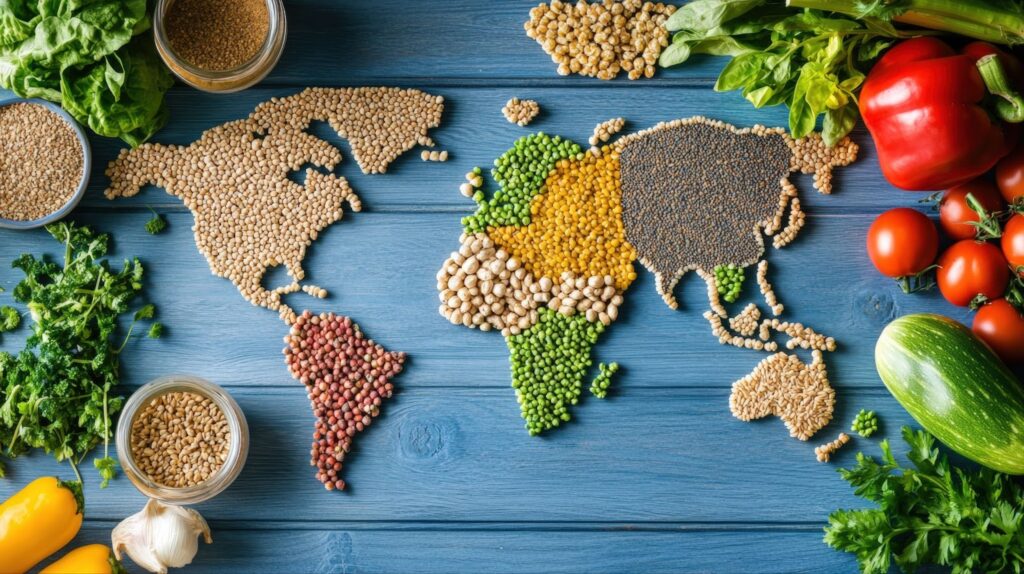
世界的な食料システム、地政学リスクなど、さまざまな問題と向き合わざるを得ない現在、フードセキュリティを達成するために国や世界はどのような対策をとるべきなのか。
また、消費者としての私たちは、フードセキュリティを守るために何ができるのでしょうか。
世界規模での取り組み
世界規模でのフードセキュリティ達成には、国同士の格差や経済・社会状況の改善が必要であり、実現は容易ではありません。国際的に求められる取り組みとして必要なのは、
- 貧困削減と世界経済の安定的成長
- 栄養教育の普及など栄養学的アプローチ
- 不平等・格差是正といった社会学的アプローチ
など、食と農業の分野以外からのさまざまなアプローチが求められます。
アフリカへの食料援助と農業技術開発支援
現在進められている取り組みの一例が、WFP(国連世界食糧計画)による食料の緊急援助と、アフリカの食料自給率向上を目指す農業技術開発援助です。アフリカ諸国が自ら食料を賄えるようになることで、食料輸出国の負担も減って輸入環境を整えられ、世界全体のフードセキュリティ達成にも繋がります。
気候変動対策
その他に進められている取り組みは、気候変動や生物多様性の減少などへの対策です。
具体的な例としては、
- 土壌の有機質や保水力の向上、干ばつと高温に耐えられる農業システムの構築
- 気候変動に強く、環境に優しい持続可能な農法の普及
- 不耕起栽培やアグロフォレストリー、緑肥作物の栽培、化学肥料使用量の削減
などの推進があります。
国内での取り組み

日本でも、国内の食料安全保障を確保するためのさまざまな取り組みが求められています。
激変する国際情勢の大きな変化を受けて、2022年に国・政府は食料・農業・農村基本法の見直しを行いました。政府は現在、そこで言及された課題を踏まえ、
- 農業の持続的な発展:担い手農業者の経営の安定、生産性や付加価値の向上
- 環境負荷低減農業の推進
- 合理的な価格の考慮
- フードバンクなどへの支援拡大
- 輸入先の多様化
- 備蓄体制の整備
などに努めることを明示しています。
消費者に求められる役割
改正食料・農業・農村基本法では、環境との調和や食料安全保障の実現には、消費行動における消費者の役割が重要なポイントであると位置付けています。
具体的には、私たち消費者が、
- 農業体験など消費者による農業参画の意識向上
- 環境負荷の低い食材の購入
- 食品ロス削減:在庫管理や計画的な購入、食べ切り・使い切り
などに取り組むことで農産物生産や消費のあり方に関心を持ち、自分ごととして捉えることが、フードセキュリティの達成につながると期待されています。
フードセキュリティとSDGs

フードセキュリティの確保は、人類すべての存続のために最優先で取り組むべき事案であり、SDGs(持続可能な開発目標)の達成にとっても重視されるべきものです。
目標2「飢餓をゼロに」
フードセキュリティが体現するのは目標2「飢餓をゼロに」です。
「飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を推進する」という目標2の主題と、2.1から2.cまでのすべてのターゲットは、フードセキュリティの概念と符合します。
現在の状況では、2030年までの飢餓の撲滅や、農業生産性の向上、持続可能な食料生産システムの確保などの実現は困難な状況です。一日も早い目標達成に向けて、世界の国々は農業政策や栄養教育、農産物の流通や入手のしやすさなどに一層の対策を講じなければなりません。
目標1「貧困をなくそう」
貧困は、安全な食料を十分に手に入れられない状態でもあります。
アフリカ諸国など飢餓に苦しめられている人々だけでなく、先進国でも貧困のために基本的な食料を入手できず、栄養不足や疾患に苦しめられている人々は少なくありません。貧困を撲滅するためにも、フードセキュリティをすべての層に保障することは不可欠な政策です。
目標10「人や国の不平等をなくそう」
世界的なフードシステムの偏りは、国や地域間の不平等を生み出します。
必要な食料が得られず飢餓に喘ぐ国がある一方、有り余る食料を廃棄し、肥満に苦しむ国がある現状はまさにその典型と言えるでしょう。
さまざまな属性や経済的地位などに関わりなく、すべての人々に安全かつ十分な食料を保障し、社会的、経済的、政治的包摂を実現することは「人間の安全保障」の基本です。
その他にもフードセキュリティは
- 目標3「すべての人に健康と福祉を」
- 目標6「安全な水とトイレを世界中に」
- 目標12「つくる責任 つかう責任」
- 目標13「気候変動に具体的な対策を」
- 目標14「海の豊かさを守ろう」
- 目標15「陸の豊かさを守ろう」
といった、SDGsが掲げるほとんどの目標達成とも深く関連してきます。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ
激しく変化する世界情勢の中、すべての人々がフードセキュリティを確保することの重要性と困難さがより強く認識されるようになっています。日々の食事に不自由しない日本も例外ではなく、アメリカ・ラトガース大学の研究によれば、局地的な核戦争が起きた場合、世界の飢餓人口の3割が日本人になるとも言われています。
フードセキュリティの現状を理解し、その実現に向けて何ができるのか。今こそ私たちはその重要さを実感する時期に来ているのです。
参考文献・資料
図解 知識ゼロからの食料安全保障入門-気候変動 法制度 消費 生産基盤 国際情勢 SDGs;平澤 明彦/阮蔚/小針 美和 著;家の光協会,2024年
食料安全保障とは:農林水産省
FAOの定義(Food Security)|農林水産省
小泉達治 フードセキュリティの国際的潮流から学ぶ 顕在化するリスク・不確実性 農業経済研究 96 (2), 120-134, 2024-09-25
ARDEC60号:国際的なフードセキュリティに関する論点 農林水産政策研究所 上席主任研究官 小泉達治
Global Food Security Index 2022
人間の安全保障 | 国連広報センター
人間の安全保障と国連 | 国連広報センター
【農家向け】野菜高騰の原因と対策|供給と収益の安定化に向けて|新しい農業のカタチをつくるメディア「リプラス」
都市農業の時代 食料安全保障へ 反転攻勢始まる:青山佾 著/一般社団法人全国農業会議所,2023年
この記事を書いた人
shishido ライター
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。