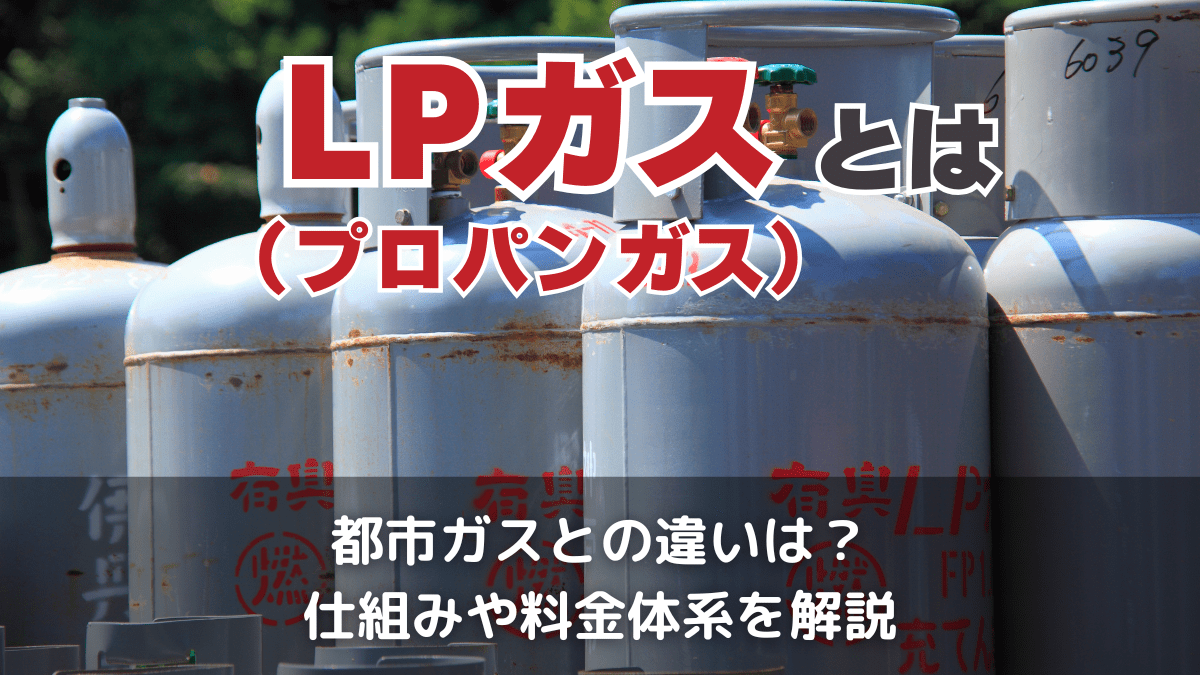名所めぐりの旅行では、ツアーガイドさんが「これは重要文化財〇〇の建物で・・・」や「この仏像は国宝〇〇で・・・」などとよく説明してくれます。「重要文化財」も「国宝」もよく耳にする言葉で、熟語としての意味は、<重要文化財=重要な→文化財>、<国宝=国の→宝>です。
このような言葉が使われると、何か大事なものを説明されていることは分かるのですが、ではいったいどのようなものが重要な文化財、あるいは国宝なのでしょう? 両者の違いはどこにあるのでしょう?そのような疑問が解決するよう、具体例も交えて分かりやすく解説します。
目次
重要文化財とは

まず言葉の意味からみていきましょう。
「文化」を辞書で引くと「人間が自然に手を加えて形成してきた物心両面の成果」とあります。「教養」や「文明」と同じような意味で使われることもあり、どこまでを「文化」というかは、国や研究者によって多少違いがあります。「文化財」とは「文化的価値があると広く認められた国民の財産」と言えます。多くの人が「取っておきたい、と思える文化の形」と言い換えることができます。
では実際には、誰が、どのように、どのような文化財を、「重要」と決めていくのか、整理していきましょう。
文化財の種類
日本では、文化財に関する様々な規定をする「文化財保護法」という法律があり、この法律のもとに文化財が分類されています。文化財保護法では「『文化財』とは、次にあげるものをいう」と、以下の6類型が挙げられています。


引用:文化財保護法 | e-Gov 法令検索及び文化財に関する基礎資料
文化庁や都道府県の教育委員会が調査をしたり、文化審議会で話し合われたりして選定されますが、決定は文部科学大臣が行います。さらに文部科学大臣によって「重要」と指定されたものが「重要文化財」となります。
数値で示されているような基準はありませんが、次のどれかに当たるものとされています。
- 意匠的に優秀なもの
- 技術的に優秀なもの
- 歴史的価値の高いもの
- 学術的価値の高いもの
- 流派的又は地方的特色において顕著なもの
簡単にいうと、デザインも作り方も優れていて、歴史上も学問上も価値が高く、ユニークな点もあるもの、と言えます。
有形文化財
後にお話する「国宝」は、第1類型の有形文化財のうち「重要有形文化財」に選定されたもののうちから指定されます。つまり、重要有形文化財となることが「国宝」への予選通過第1段階と言えます。

有形文化財は大きく「建造物」と「美術工芸品」の2種に分けられます。2024年現在、有形文化財として登録されているもの(登録有形文化財)は14,141件、文部科学大臣が重要文化財として指定したものがさらに2,582件あります。
美術工芸品は、次の7種類に分類されています。
| 1.絵画 2.彫刻 3.工芸品 4.書跡・典籍 ※ 5.古文書 6.考古資料 7.歴史資料 |
※ 文化財分類上は、書跡は書道の優れた作品や墨蹟、典籍とは古くから伝わる本を指す。
中国や西洋で発行されて日本に伝わったものも含む。
無形文化財
「有形」に対して、演劇・音楽・工芸技術等は「無形文化財」になります。
重要無形文化財として指定されたものには、
- 演劇:雅楽・能楽・文楽など
- 音楽:地歌・尺八・筝曲など
- 工芸技術:陶芸・漆芸・手すき和紙などの技術
が挙げられます。
無形文化財にの例について詳しくはこちら
有形と無形の違いと分類
文化財保護法上では、言葉通り<形がある=有形>というだけで分類されるわけではありません。例えば、古墳などの遺跡や天然記念物も形は有りますが、有形文化財ではなく記念物に分類されます。同様に形のある里山は文化的景観、城下町は伝統的建造物群に分類されます。
押さえておきたい点は、有形文化財に分類されるのは、文化財保護法による建造物と7種の美術工芸品に限定されるということです。
国宝とは
姫路城

国宝についても「文化財保護法上は」という視点で話を進める必要があります。
国宝については第27条第2項に次のように記されています。
| 文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。 |
つまり、国宝となるには、まず有形文化財に分類・指定され、次に重要文化財と認定され、さらに「国民の宝」と指定されなければなりません。

人間国宝って?
古典芸能を演じる方や巧みな陶芸技術をされる方が「人間国宝」といわれることがあります。しかしこの呼び名は通称で、文化財保護法上の「国宝」にはあたりません。
では、全部はご紹介できないまでも、代表的な重要文化財・国宝をご紹介しましょう。
重要文化財の例
令和6年12月1日現在

国宝をのぞく重要文化財の総数は、2024(令和6)年現在212349件で、その内建造物は、5,202棟2,351件となっています。
建造物
重要文化財の指定を受けている建造物には多くの種類がありますが、1番多いのは寺社・神舎で、合わせると1,289件に上ります。次に民家や官庁舎が続きます。
地域別にみると、やはり古都である京都・奈良・滋賀に多くあります。
近年の人気スポット:東京駅丸の内本屋
古都である3県に続くのは東京都です。近年リニューアルされた東京駅は、夜のライトアップや近隣の商店街のイルミネーションなどで観光スポットとなっており、外国の方を含む多くの人々が訪れています。
大阪城は国宝?

お城も人気の文化財ですが、有名な大阪城は国宝ではなく重要文化財です。
ほぼ復元されていますが、繰り返し修復される過程で、天守閣など元の形と異なった復元が施されているからです。
国宝として指定されている城郭は、姫路城・松本城・彦根城・松江城・犬山城の5つのみです。重要文化財としては、大阪城や弘前城など44の城郭が指定されています。
ニューフェイス:鞍崎灯台
1番新しく指定された重要文化財に灯台が仲間入りをしました。宮崎県日南市の鞍崎灯台です。九州南部で現存する最古の洋式灯台で、近代海上交通史上、価値が高いと評価され指定を受けました。
美術工芸品
重要文化財に指定されている美術工芸品は約1万点にのぼります。所蔵博物館や美術館が多い東京に多く集まっています。代表的なものを種類別にご紹介しましょう。美術の教科書で見たことが思い起こされませんか。
| 絵画 | 1899 | 尾形光琳作「風神雷神図屏風」 | ・江戸時代・オリジナルといえる俵屋宗達の同絵画は国宝。 |
| 彫刻 | 2593 | 高村光雲作「老猿」 | ・1983(明治26)年シカゴ万博に出品された。 |
| 工芸品 | 2220 | 陣羽織「猩々緋羅紗地違鎌模様」(しょうじょうひらしゃじちがいかまもよう) | ・戦国武将:小早川秀秋所有とされる。 |
| 書跡・典籍 | 1697 | 藤原行成「古今集」の一部 | ・平安時代 |
| 古文書 | 731 | 藤原宣孝「大宰府符」 | ・藤原宣孝は紫式部の夫 |
| 考古資料 | 616 | 遮光器土偶(しゃこうどぐう) | ・縄文時代晩期のもの・宮城県大崎市で出土 |
| 歴史資料 | 232 | 平賀源内作「エレキテル」 | ・平賀家に伝来・現在は郵政博物館に保管 |
画像出典・文引用:国指定文化財等データベース及び東京国立博物館 – コレクション コレクション一覧 名品ギャラリー 館蔵品一覧
国宝の例
厳しい「予選」を通り国宝に指定されたものも、お子さんにもよく知っていると思われるものを中心にご紹介しましょう。これらも歴史や美術の教科書で目にされたことも多いのではないでしょうか。
建造物:231件
| 建造物 | 231 | 東照宮 陽明門 | <江戸時代>東照宮は、陽明門の他・正面唐門・東回廊・東透塀・本殿及び拝殿も国宝に指定されている。 出典・引用:国指定文化財等データベース | |
美術工芸品:計912件
| 美術工芸品 | 絵画 | 166 | キトラ古墳壁画「玄武」 | <飛鳥時代>・奈良県明日香村にある石窟壁画・現存する世界最古の本格的な中国式星図・令和元年に国宝に指定 出典・引用:キトラ古墳とは(文化庁) |
| 彫刻 | 141 | 東大寺万大門金剛力士(仁王)像 | <鎌倉時代>・高さ8.4mという巨大木造彫刻・運慶・快慶作・修復の過程で躰内から多くの経巻や文書が発見された。 出典・引用:南大門 – 東大寺(東大寺) | |
| 工芸品 | 254 | 玉蟲厨子 | <飛鳥時代>・奈良県法隆寺所有・高さ2m33cm・玉虫の羽が使われているので、こう呼ばれる。・凍土な金工や漆工の技術も使われている。 出典・引用:大宝蔵院 | 聖徳宗総本山 法隆寺 | |
| 書跡・典籍 | 235 | 古今和歌集(元永本) | <平安時代>・上下2冊・古今和歌集として唯一の完成版で書体の美しさも評価が高い。・東京国立博物館所蔵 出典・引用:国指定文化財等データベース | |
| 古文書(こもんじょ) | 63 | ポルトガル国印度副王信書 | <桃山時代>・京都府妙法院所有・豊臣秀吉宛・羊皮紙に書かれ、外国からの書状として異色の国宝 出典・引用:| WANDER 国宝 | |
| 考古資料 | 50 | 金印 | <弥生時代>・縦横高さとも2.3cm余り。金が有率約95%・「漢委奴国王」の韻文がある。・福岡市博物館所蔵 出典・引用:金印 | 福岡市博物館 | |
| 歴史資料 | 3 | 伊能忠敬関係資料 | <江戸時代>・初めて測量に基づいた日本地図を作成した伊能忠敬の功績を多面的に伝える資料・千葉県香取市伊能忠敬記念館保管出典・引用:国指定文化財等データベース |
その他のものは、国指定文化財等データベースでご覧いただけます。
文化財の保護とは具体的にどのようなことをするのか
文化財保護法では「保存」と「活用」を文化財保護活動の両輪としています。
つまり
- 保存:文化財を管理、修理するなどして守ること
- 活用:文化財を公開したり、利用したりして社会に生かすこと
が、文化財を保護する大きな2本柱となります。
文化財の保存:管理と修理は大変!
文化財の価値を後世に確実に伝えるために管理・修理を主に担うのは所有者です。
大変なのは
- 素材の劣化が進んでいる
- 修理費用が高額
- 修理技術者が高齢化している
という点です。
国や地方自治体は選定や指定をするだけではなく、費用を補助したり、税制上の優遇を行ったりしていますが、国宝に指定されても補助は85%までです。
費用がかさむ上、勝手に改造、移動、売買が厳しく制限されるため、博物館や公共の施設・団体に管理を任せたいという所有者も少なくありません。
文化財の活用:保存活動との相乗効果をねらって
「公開」はより多くの人と文化財の価値を共有し、理解と関心を高める取り組みです。
美術品に関しては、SNSを利用して公開も広まり、クラウドファンディングのシステムも効果を発揮しつつあります。
建造物については「公開」ばかりではなく、観光対象として地域振興につなげたり、まちづくりの拠点としたりなどの「活用」が期待されています。
また、教育活動との連携も積極的に考えられるようになってきました。修理過程を公開して、子供たちの興味関心を高めたり、文化財に指定された旧家で体験活動を企画したりする活動も見られます。
地域のニーズに合わせた活動を通じて、地域住民に文化財の本来の価値を正しく理解してもらうことができれば、今後の担い手としての意識が高まり、その後の保存活動や地域振興にも繋がります。
集客が進めば保存のための費用も集まり、多くの人の関心が高まって支援に結びつけば保存活動の推進が期待できます。地方自治体が推進の中核となることが望まれます。
参考:「文化財」の保存と活用を推進するための戦略:文化財保護のための資金調達ハンドブック(1)(文化庁)
VI. 文化財保護の望ましいあり方と実現方策(調査総括)(国土交通省)
文化財の総合的な保護を行うための施策について
文化財保護制度の概要(文化庁)
重要文化財の保護とSDGs
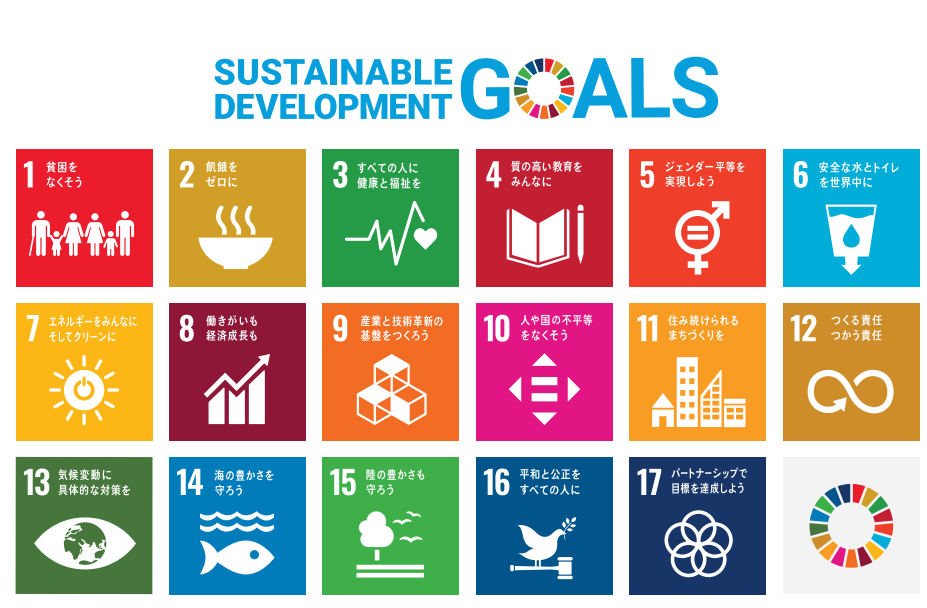
最後に重要文化財の保護とSDGsの関係をみていきましょう。
SDGs目標17のうち最も関わりが深いのは、SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」です。
SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」との関り
目標11には10のターゲットがあり、その4番目に、「世界の文化遺産・自然遺産を保護・保全する取り組みを強化する」と明記されています。
世界遺産は、人類共通のかけがえのない宝物としてユネスコが指定します。これは日本の重要文化財・国宝が指定される意義と同じです。
日本は文化財の活用にスポットを当て、魅力あふれる地域づくりの礎として文化財を活用することが、地域の活性化に寄与するとし、予算面や専門家との連携を支援しています。建造物を観光の拠点にするばかりでなく、コンサートや演劇発表の会場にする試みもされています。美術工芸品の展示も、地域の方々の協力を得て障害のある方も楽しめるようにするなど、工夫されてきています。
文化財を保護する姿は、SDGsの「持続可能」を目指す姿です。
>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから
まとめ
重要文化財・国宝について、種類や例、そして保護活動について解説してきました。
地域活性の要として文化財の保護活動を推進する姿は、持続可能な地域の未来を見据える姿です。
最近は外国からの観光客も多く、オーバーツーリズムも問題になっていますが、地域で協力して正しいマナーで観光してもらおうという活動も見られます。日本の宝・財産として文化財を持続させるという同じ目標に向かう姿です。
地域の文化財を見に足を運ぶことも、私達のできる保護活動の一歩になりそうです。また、居住区以外の観光地を訪れたり、イベントに参加したりすることも、個人の楽しみと重なります。この記事が、旅行好きな方にもそうでない方にも、文化財とその保護により一層の関心を持っていただければ幸いです。
心配な点は、維持・修理にかかる費用です。
言われる清水寺や延暦寺の修復費用は、数十億円に上ります。国や自治体から最大の補助を受けたとしても、所有者の負担額も億に上ります。保護活動費用が大きな課題として残る点を、心に留めておくべきではないでしょうか。
<参考資料・文献>
大仏殿 – 東大寺
国指定文化財等データベース
文化財保護法 | e-Gov 法令検索
文化財に関する基礎資料
勧進帳 | 歌舞伎演目案内 – Kabuki Play Guide –
国宝及び重要文化財(建造物)指定基準
勧進帳 | 歌舞伎演目案内 – Kabuki Play Guide –
重要無形文化財(文化庁)
文化財指定等の件数
東京駅丸ノ内本屋(スポット紹介)|【公式】東京都千代田区の観光情報公式サイト / Visit Chiyoda
大阪城天守閣
国宝・重要文化財(建造物) 最近の指定
東京国立博物館 – コレクション コレクション一覧 名品ギャラリー 館蔵品一覧
キトラ古墳とは(文化庁)
南大門 – 東大寺(東大寺)
大宝蔵院 | 聖徳宗総本山 法隆寺
| WANDER 国宝
金印 | 福岡市博物館
文化財修理現場の現場から 「絵画の保存修理について ―『真正極楽寺所蔵花車図屏風』の修理を例に―」 | 京都市文化観光資源保護財団
公益財団法人 京都古文化 保存協会
「文化財」の保存と活用を推進するための戦略:文化財保護のための資金調達ハンドブック(1)(文化庁)
VI. 文化財保護の望ましいあり方と実現方策(調査総括)(国土交通省)
文化財の総合的な保護を行うための施策について
文化財保護制度の概要(文化庁)
世界遺産とは – 公益社団法人日本ユネスコ協会連盟
e国宝
コトバンク
SDGs:蟹江憲史(中公新書)
この記事を書いた人
くりきんとん ライター
教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。
教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。