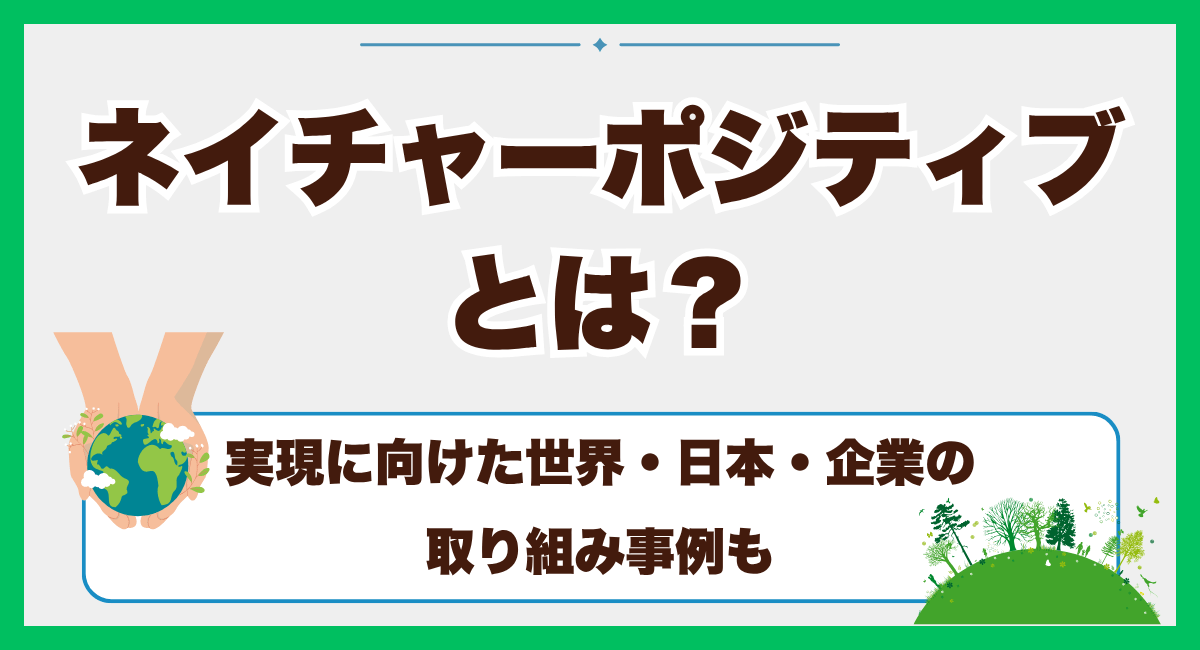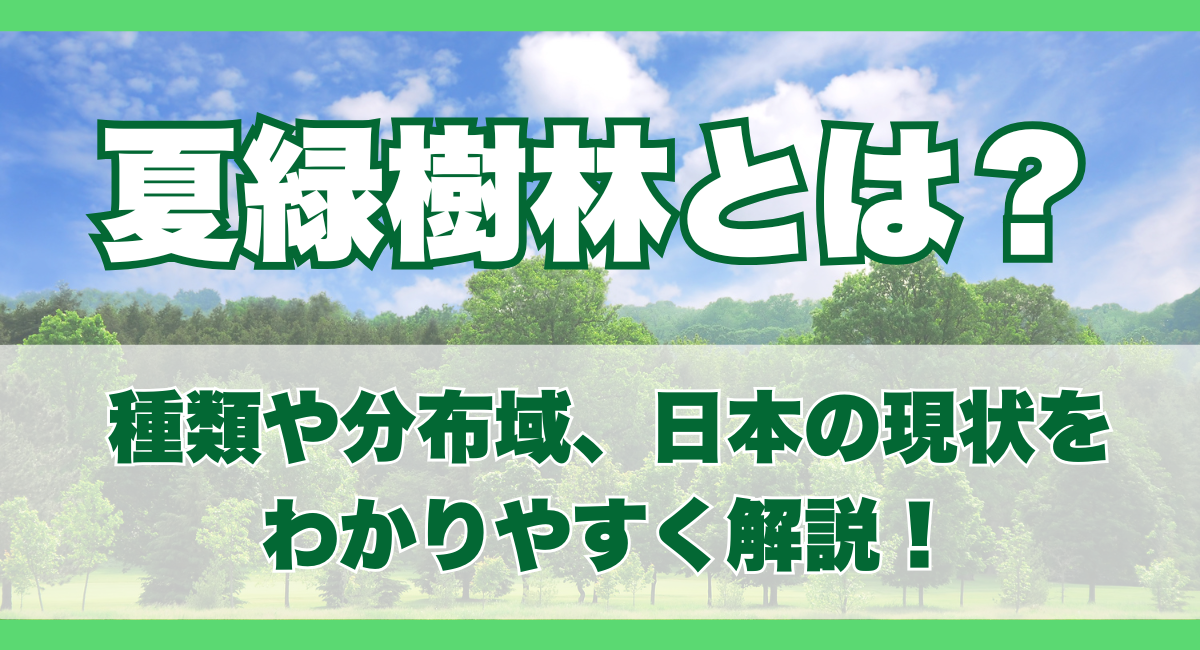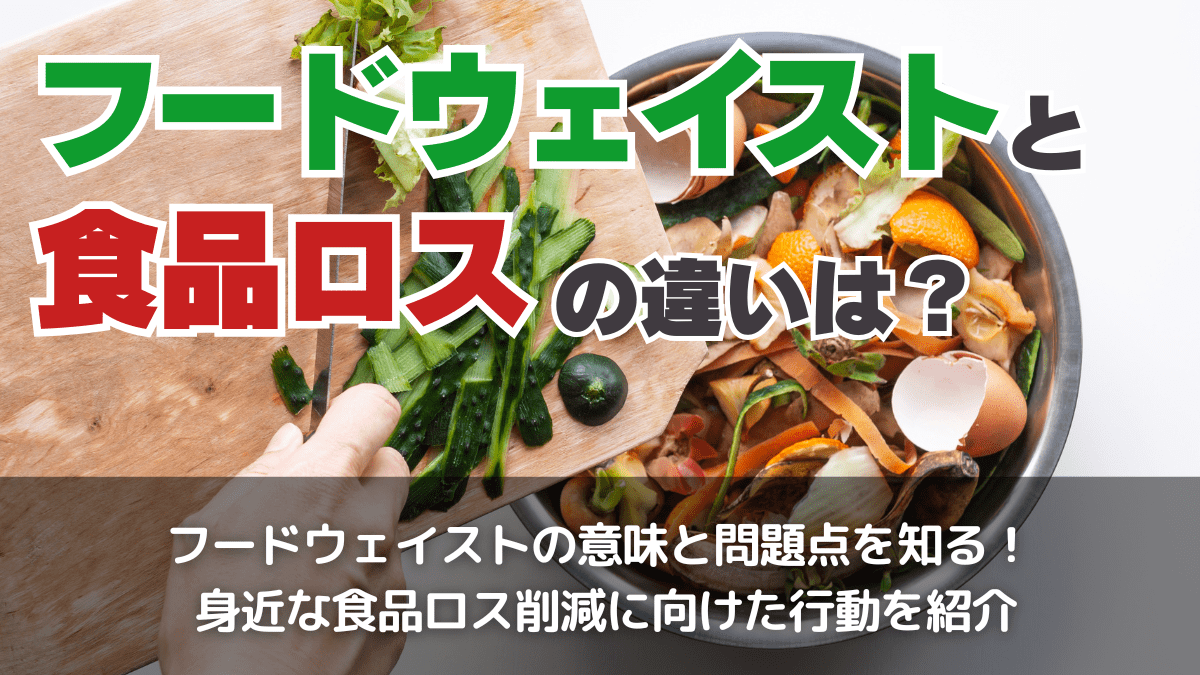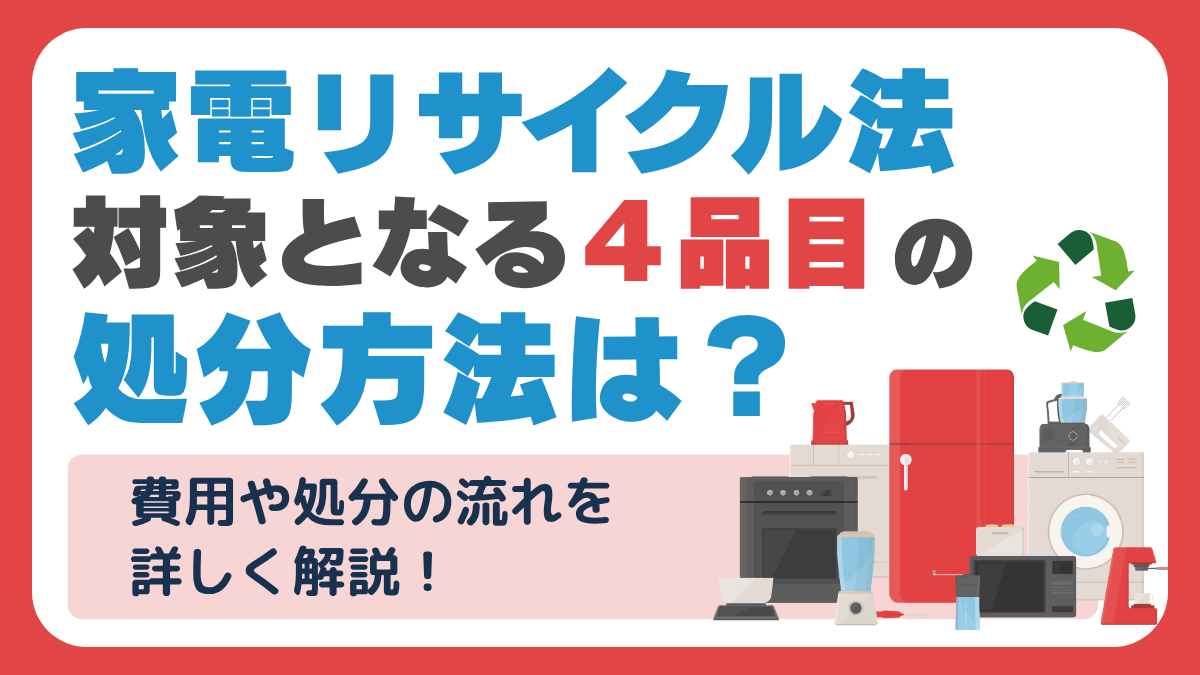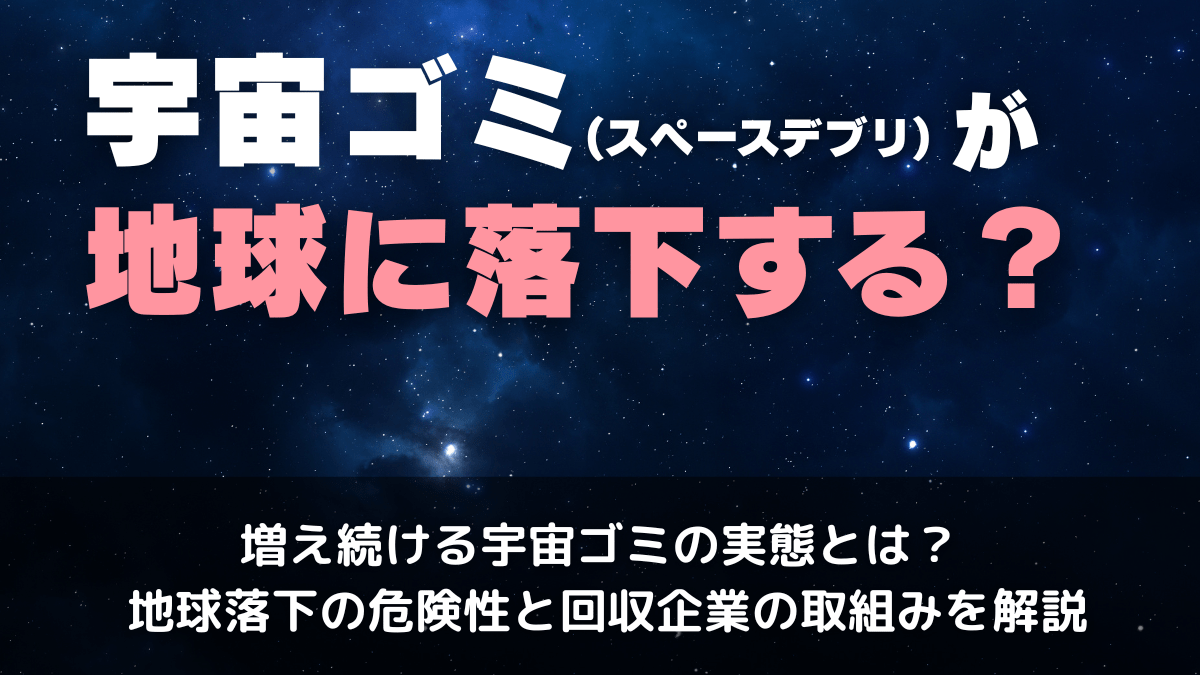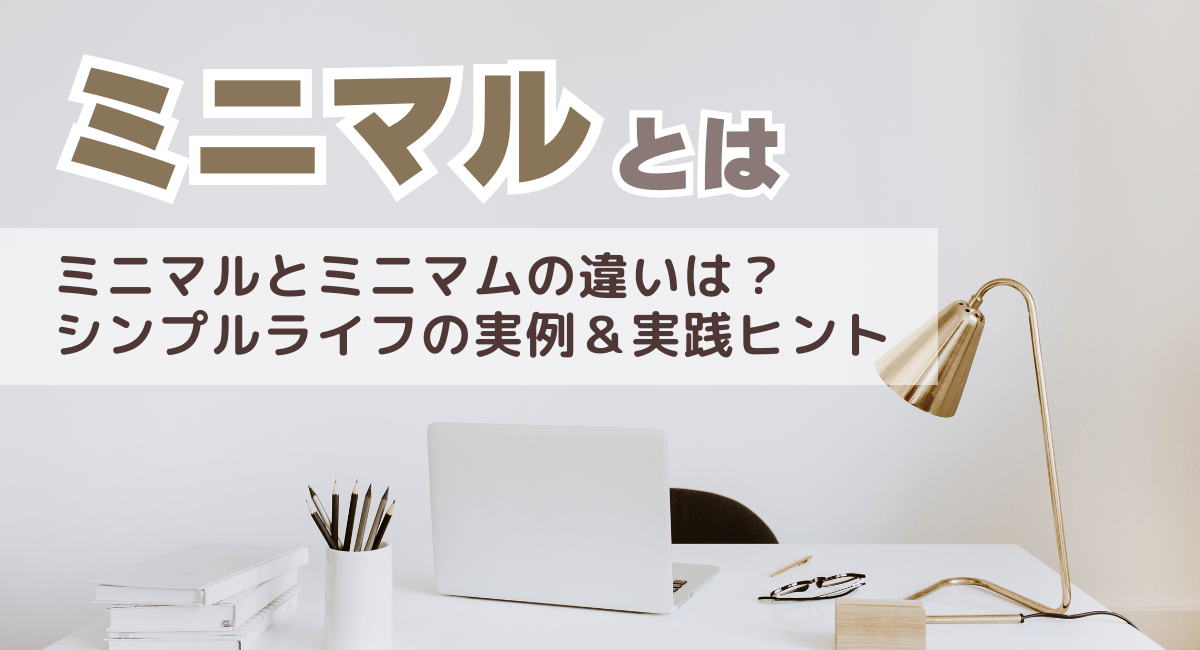
ここ何年かミニマルなライフスタイルが注目されていますが、日本ではもともと、江戸時代から「もったいない精神」で「ひとつのモノを工夫しながら長く使う」という暮らしをしてきました。
しかし、多くのモノが簡単に手に入るようになった今、「ひとつのモノを大切にする」という感覚が薄れてしまい、使い捨てを繰り返すことで廃棄を増やし、地球に大きな負荷をかける結果となっています。
このままでは、廃棄物の焼却で出る二酸化炭素で地球温暖化が進み、気候変動や環境破壊に歯止めがきかなくなってしまいます。
「なぜ、ミニマルと地球環境に関係が?」と思われる方も多いと思います。
この記事ではミニマルの意味と、こちらも最近よく聞くようになったSDGsとの関係、ミニマルなライフスタイルがどういうものなのかを詳しくご紹介します。
最後に実践するためのヒントになる情報もピックアップしているので、ぜひご覧になってみてくださいね。
目次
ミニマムとは?ミニマルが指す意味とは?
「ミニマル」とは必要最小限、可能な限り少ないことを意味します。似た言葉に「ミニマム」「ミニマリスト」がありますが、英語では明確に区別されています。
まずはそれぞれの違いを確認しましょう。
ミニマルとミニマムの違い
ミニマルは、相対的で「量」だけでなく「質」も表している言葉であるのに対し、ミニマムは法律などの決められた範囲内の最小、最小限、最低限定といった意味を持ち、「最小単位」「最小量」など数式、「絶対量」で使われます。
意味
無駄のない、最低限の
使い方
ミニマルな暮らし=最低限必要な家具や衣服で生活すること
意味
最小単位、必要量
使い方
ミニマムチャージ=最低利用料金を指し、例えば飲食店でミニマムチャージが3,000円と設定されている場合、それに満たない金額で飲食したとしても3,000を支払う必要がある。
また、ミニマルな生活をしている人を「minimalist(ミニマリスト)」といいますが、「minimalist」という単語はあってもminimamist(ミニマミスト)という単語は存在しません。
似た単語ですが、ニュアンスは大きくことなるので英語圏で使用する場合には、使い分けに注意が必要です。
ミニマムは英語で何?
ミニマムは、英語だと「minimum」と表記します。ミニマルは「minimal」です。
形容詞・名詞・副詞として使われる言葉で、形容詞なら「最小の・最小限の」という意味になり、名詞なら「最小・最小限」、副詞なら「最小」と訳されます。
ミニマムの反対語・略
ミニマムの反対語(対義語)は「マキシマム」で、英語だと「maximum」と表記します。日本語では「最大・最大限」と訳されます。
マキシマムの略語は「max.」ですが、ミニマムも同じように「min.」と略します。
ミニマルの反対語は「マキシマル」で、ミニマルとミニマムは同じ略語、マキシマムとマキシマルも同じ略語で表記されます。
ミニマルを実践する人がミニマリスト
「ミニマリスト」は「ミニマル」から派生した造語です。ミニマリストは、「必要最小限のモノだけで暮らす人」とされるのが一般的ですが、個人によって必要最小限(ミニマル)の定義は異なり、最小量(ミニマム)が決まっているわけではありません。
例えば、
- 「ソファを持っていたらミニマリストじゃない」
- 「炊飯器を使っていたらミニマリストじゃない」
- 「20着も服を持っていてミニマリストなの?」
などと思われがちですが、重要なのはモノが少ないことや量ではないのです。
大事なのは、「自分にとって必要なモノだけを持ち、豊かに生きる」こと。無駄なモノや事柄をそぎ落とし、自分の好きなモノやしたいことに時間を費やす。これが「ミニマリスト」の生き方と言えるでしょう。
過去や未来に執着せず、現在を生きることで、今自分の必要なモノが見えてきます。ミニマリストの人は、他人と比べず「自分の価値観」を大切にする人が多い傾向にあります。
ミニマムファッション
ミニマムファッションというのは、過度な装飾を省いてシンプルにしたデザインの服やシンプルかつベーシックで機能性が高いアイテムを組み合わせたファッションを表現する言葉です。
ミニマルファッションと形容する場合もあり、ファッションについてはミニマムとミニマルは厳密に分かれていない状態なので、当記事ではミニマムファッションと表記しています。
ミニマムファッションの女性御用達のブランド
ミニマムファッションを楽しむ女性が増えていることもあり、女性向けのブランドの人気も高まる一方です。男性や子供も着用できるポピュラーなブランドから高級ブランドまで揃っています。
ここでは、手が届きやすい価格帯で人気が高い女性向けのブランドを紹介します。
リーズナブルブランド
- ユニクロ
- 無印良品
老若男女問わず着られるファッションが揃っているのがこの2ブランドで、特にユニクロはやや高級なGAPなどのブランドも展開していて、そちらもミニマムファッションが揃っています。
無印商品も、手に入れやすく着やすいという点で長い間人気を保持してきたブランドです。
やや高めのブランド
- グリーンレーベルリラクシング
- レショップ
グリーンレーベルリラクシングは高級ファッションで知られるユナイデットアローズグループの中ではややリーズナブルな価格帯のブランドで、イージーパンツなどが人気です。
レショップは日本で生まれたブランドで、エディフィスのバイヤーである金子忠治さんが立ち上げました。
ミニマルが注目されたきっかけ・背景
ではなぜ最近になってこのような考え方に注目が集まるようになったのでしょうか。
ミニマルが注目された背景には、世界的な経済成長による弊害が挙げられます。大量生産大量消費によって経済は発展してきましたが、その一方で環境問題や不平等な労働環境が問題視されるようになり、人々の考え方がミニマルに変化してきたのです。
順を追って見ていきましょう。
大量生産・大量消費
大量生産・大量消費が生まれたきっかけは産業革命にまで遡ります。産業革命は18世紀のイギリスで起こりました。
産業革命とは、動物の力や風力、水力など自然の力を利用していた農業文明社会から、石炭やガス、石油を利用した工業文明社会に移行した大きな社会の変化のことを指します。さまざまな機械革命により機械化が進み、生産性が向上しました。
日本では民間の綿糸紡績業や鉱山業に機械が導入された1886年(明治19)に日本産業革命が始まったと言われています。その後、1960年には日本は急速な経済成長をとげ、高度経済成長期頃には、大規模な設備投資ができ生産コストを下げることが可能になり、市場には安価な商品が並ぶようになりました。
一方で、価格競争も激しくなり、企業は消費者の動機づけとして安価な新商品を次々と打ち出すようになります。これによりモノを大切にするという意識は薄れ、「壊れたら修理するより買い替える」など、まだ使える状態の商品まで廃棄されるようになりました。
また、
- プラスチック製品、合成樹脂製品、合成繊維の安価な衣類が店頭に並ぶようになった
- 流通がスムーズになり24時間買い物ができるようになった
ことで、消費者の選択肢も増え、気軽に買い物ができるようになり、モノを持つことで豊かさが増したと感じるようになったのです。
しかし、安くて便利なモノが増えた一方で、環境破壊や不平等な労働環境が問題視されるようになりました。
環境破壊
環境破壊とは、環境汚染や人間の活動によって、自然環境が維持できなくなることを指します。大量生産・大量消費による環境破壊は1950年代後半頃から注目されていましたが、本格的に問題視されたのは1990年代初め頃です。
特に問題となっているのが、
の6つです。
地球温暖化
産業が発展し、温室効果ガスの排出量が増えたことで地球の気候システムに変化が起こり、気温が上昇しました。
海洋汚染
海洋汚染の原因は、工場や生活排水、有害物質、海上事故で起こった石油流出などです。また、近年ではプラスチック製品やペットボトルゴミの投棄により海の生態系に大きな影響が出ています。
大気汚染
大気汚染は工場から排出される大気汚染物質と、物流や人流の車の排気ガスなどから排出される場合があります。大気汚染物質は人間の呼吸器に影響を及ぼします。
森林減少
大規模な土地の開拓や過剰な伐採により、世界の森林は急激なスピードで減少しています。森林が減少することも先述した地球温暖化が進む原因と考えられており、さらには生態系のバランスを崩す原因にもなっています。
エネルギー問題
わたしたちの生活を支えている電気やガス。そのエネルギーとなる石炭や石油、天然ガスには限りがあります。このままの使用状況が続けば、近い将来資源が枯渇すると予測されています。
ゴミ問題
一般ごみ、家庭ごみ、不当投棄ゴミ、また災害に関するゴミ、焼却や埋め立てが追いつかないことなどをゴミ問題といいます。また、焼却時には二酸化炭素を排出するため、こちらも温暖化の原因となるのです。
このように、私たちの生活が便利になるにつれて、地球に多大なる負担をかけたことで、さまざまな問題が発生するようになりました。さらには自然環境だけではなく、労働環境にも影響を及ぼすようになったのです。
不平等な労働環境
わたしたちが着ている服がどこで、誰が作っているか考えたことがありますか。
わたしたち消費者は商品を手に取っても、その裏側にある情報を知る機会がなかなかありません。
安価なトレンドの服や、コーヒーや紅茶、チョコレートの原料が作られているのは主に途上国です。途上国の人々は、わたしたちが想像もつかないような低賃金で働かされており、貧困から抜け出せない現状があります。
そのなかで世界的に関心が高まるきっかけとなったのが「ラナプラザの悲劇」です。この事故は2013年4月24日、バングラデシュの首都ダッカにある、銀行やお店、縫製工場が入る8階建ての商業ビルで発生しました。前日にビル使用の警告があったにもかかわらず、オーナーや経営者は従うことなく営業を続けた翌日、ビルが倒壊。死者は1,100人以上、負傷者は2,500人以上。行方不明者は500人以上と被害にあった人数は4,000人を超えています。
のちの調査で、
- ビルが倒壊した理由は大型発電機、ミシンの振動が原因であったこと
- 働いていた女性は日本円にして時給約15円であったこと
といったことが判明しています。
時給15円では1ヶ月どれだけ働いても6,000円程度しか得られず、とても人間らしい暮らしができるとは言えません。
さらに、縫製工場で作られていたのは、世界的なファストファッションブランドの洋服であったことも、大きな話題となりました。
これにより、先進国のアパレルメーカーが、途上国の人々の貧困ゆえに劣悪な環境でも働くしかない状況を利用し、低賃金での長時間労働などを行っていたことが明らかになり、問題視され始めたのです。
ここまで見てきたように、経済成長の裏側には多くの犠牲が払われてきた事実があります。これらの問題を解決するためにも、自分にとって必要なモノだけを持ち、環境に配慮した生活を送るミニマルの実践に注目が集まるようになったのです。
さらには、ラナプラザの悲劇をきっかけに、世界的にミニマルと関係が深いエシカル消費が広まりを見せるようになりました。
参考資料:バブル経済崩壊後の消費者行動
次ではエシカル消費について簡単に見ていきましょう。
エシカル消費とは?
エシカル(ethical)とは英語で、倫理的や道徳的などを意味します。倫理的などというとむずかしく聞こえますが、法的な縛りはなくとも人間の良心に従って行動することと言い換えることができます。
これを踏まえてエシカル消費について考えると、人や地球環境、社会に配慮して、「自分に良くて人にも良いモノを選択する」といった消費行動を心がけることと言えるでしょう。
「人にも良くて自分にも良い」エシカル消費はミニマルと通じる
先述したように、ミニマルな生活をしている人は、「自分にとって必要なモノだけを持ち、豊かに生きる」ことを大切にしています。
例えば衣服では、
- 長く使えて肌にも良いオーガニックコットン製の衣服を選ぶ
- 一時期の流行ではなく、長期間にわたり着れるデザインのものを選ぶ
といった観点から熟慮を重ねて購入に至るのです。
この消費行動はエシカル消費そのもので、
オーガニックコットン
化学肥料を使用していないことで生産者や土壌の健康につながる
長く着れるデザイン
廃棄のサイクルも長くなるのでCO2の削減につながる
など、人にも環境にも悪影響を極力及ぼさない選択と言えます。
つまり、ミニマルな生活を送ることは、自分にも良いことはもちろん、他者にも良い消費行動の実践につながっているのです。
補足:エシカル消費の始まり
ちなみにエシカル消費は、1989年にイギリスで創刊された「エシカルコンシューマー(Ethical Consumer)」という雑誌が始まりだといわれています。この雑誌は、消費者の行動によって企業側にエシカルな製品の生産と提供をしてもらうことを目的とした内容でした。
日本では2015年に消費者庁によって「倫理的消費」調査研究会が設置され、エシカル消費の枠組みが作られました。様々な専門家からヒアリングをし、エシカル消費を広める働きかけをしています。
ミニマルな暮らしを実践する方法
モノを大切にするミニマルなライフスタイルは決してむずかしいものではなく、簡単に取り入れられる方法がたくさんあります。
そこで今後ミニマルを実践していくヒントとなるよう、ミニマリストがどのようなライフスタイルを意識しているのか紹介します。
モノを減らすと大切なモノがわかり、時間の余白も生まれる
まず、多くのミニマリストが実践しているのが不要なモノを捨てることです。
モノが多いと、自分が本当に好きで大切にしたいものが見えてきません。「全部大切だ」と思っていても、いざモノを引っ張り出してみると買ったのを覚えていなかったり、使っていなかったり、壊れていたり…なんてことがあります。
モノは使ってこそ意味を持ちます。そのため、ミニマリストは「とりあえず」や「今使ってないけど、いつか使う」モノを持っていません。これらを手放すことで、本当に大切にしたいモノやことが見えてくるのです。
モノを減らせば時間を有効に使えるようになる
そして、モノが減ることで時間を有効に使えるようになります。
例えば家事時間。すっきりした家は収納に余白があり、片付けがスムーズにできるようになります。これにより片付けのストレスも軽減され、さらにはモノが少ないため、散らかる心配もあまりありません。
時間に余裕ができると、気持ちにも余裕が生まれます。ゆっくりコーヒーを飲む時間や、趣味に費やすこともできるでしょう。これまで時間がなくてできなかったこと実行することが出来るようになりますよ。
無理に捨てる必要はない
とはいえ、モノを無理に捨てる必要はなく、自分自身が好きなモノ、豊かな気持ちになるモノは量に関係なく残しておいてもよいでしょう。また、まだ使えるモノを捨てるのに抵抗のある人もいると思いますし、なにより繰り返しになりますが、廃棄はさまざまな負の側面を持つので極力避けたいところです。そこでおすすめなのが寄付です。
「寄付」と聞くと少し堅苦しいような気もしますよね。しかし、今は気軽に利用できるものもあります。
たとえば「ジモティ」。ジモティは、必要としている人に直接手渡すことが出来るので、ハードルも低く、取りに来てくれることがほとんどなので、梱包などに時間を使う必要もありません。
本来なら粗大ごみ代として費用がかかるところを、無料でモノを減らすことができ、また人の役に立つのでお互いがwin-winな気持ちになれます。
価格を付けることも可能ですが、筆者は「引き取ってもらえるだけでありがたい!」と思っているので、テレビやテレビ台、チェストなどの大型家具も無料で取引しています。無料で提供することで引き取り手もすぐ決まり、引き渡しまでの時間も無駄にかかりません。
他にも、リユース目的で洋服を回収してくれる洋服ポストもおすすめです。洋服ポストは、集まった服を海外マーケットで販売したり、集まった衣類の重量に応じて支援金を環境保全や社会貢献活動団体に寄付しています。

洋服ポストの利用方法は宅配受付と自身で持ち込みの2種類です。宅配受付は365日いつでも可能。(送料は自己負担)
自身で持ち込む場合は、袋ごと渡せるようにする必要があります。東京都と神奈川県の10か所で開設されており、開設場所によって開設日と時間が異なりますので、訪問前に公式サイトにて確認すると良いですね。
筆者は新宿の洋服ポストを利用していますが、新宿リサイクルセンターにあるので、リサイクルの仕分けなども展示しており、正しい知識を得ることが出来ました。みなさん大きな袋いっぱいに服や布団を入れ持ってきていて、意外と利用している人が多くいるもの印象的でした。
まだ着られる服をリサイクルに出すのは勇気がいるものです。しかし、一度やってみると、必要としている人の手にも渡ったり、焼却処分するときにでる二酸化炭素の削減にもなるなど、服に新しい役割を与えられたような気持ちになり、なんだかうれしくなるはずです。ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
食材を無駄にしない管理方法
いつ開けたかわからない乾物、安かったから購入した缶詰、使いこなせなかった調味料…
冷蔵庫や食品庫にそんな食べ物はありませんか?ミニマルに暮らしている人は、
- 管理できる量の食材を購入する
- 食べきれる量の食材を購入する
ため、賞味期限の切れた食品はありません。
食品ロスを出さない生活は、廃棄物を燃やすために出る二酸化炭素を削減するだけでなく、家計にも嬉しい節約にもなります。次ではすぐにできる食材管理方法を紹介します。
食品チェック
まず、賞味期限の切れている食品チェックからはじめましょう。食品チェックは「賞味期限」が目安になるので、服や雑貨などを手放すよりずっと手放しのハードルが低く、時間もかかりません。
すっきり整理された冷蔵庫や食品庫は、あるものが把握しやすく、何を買うべきかチェックしやすくなります。これにより買い物時間の短縮になるうえに、同じものを買ったりするミスも防げます。
ローリングストック
また、ローリングストックもおすすめです。
ローリングストックとは、「防災用に買ってある非常食」を日常的に食べ、食べたら補充する方法です。これにより賞味期限を気にすることなく、備蓄量も一定に保つこともできます。
フードドライブを利用
お祝いやお歳暮をもらったものの、量が多くて消費しきれない、あまり好みではなかったなどの理由で消費できない食べ物もあると思います。
そんなときはフードドライブの利用がおすすめです。フードドライブは、食べきれない食品を持ち寄り、地域の福祉施設や団体に寄付する取り組みです。
- 未開封
- 常温
- 賞味期限が1か月以上あるもの
など団体により条件は異なりますが、全国各地に取り組みが広がっています。
また、最近ではファミリーマートでも「ファミマフードドライブ」として食品の回収をおこなっています。2021年9月現在で500店舗で実施されています。コンビニだと行く機会も多く気負わず行けるので、缶詰1つやお茶など気軽に持っていけますね。近くのファミリーマートが実施しているかぜひチェックしてみてください。

使い捨てではなく、長く使えるものを選ぶ
多くのミニマリストは気に入ったものを長く愛用しています。
今では24時間いつでも買い物ができ、100円でいろんなものが購入できるようになりました。特に買う物がなくてもつい足を運んで、そんなに必要でもないものを買ってしまうことがありますよね。
手ごろだと「100円だしまぁいいか」という気持ちで買ってしまいがちですが、それは本当に必要なものですか?今の生活に不可欠な買い物なのでしょうか?
自分に必要なモノがわかってくると、選ぶ基準も変わってきます。生活するうえで直ちに必要なモノは意外と少ないものです。
安価で買ったものを何度も買い替えるより、しっかり考えて購入することで愛着がわき、生活が豊かだと感じられるようになるでしょう。
また、何度も買い替えることで不要になったものを捨てる=ゴミが発生します。長く使えるモノを購入することは、家の中に入ってくるゴミを増やさずに済みます。小さなゴミは気軽に捨てられるかもしれませんが、家電や粗大ごみとなると捨てるのにも手間とお金がかかります。
ぜひ、購入する前に手放すときのイメージをしてみてください。
レンタルやサブスクリプションを利用しようとはいえ欲しいものは欲しい。と思う時はありますし、試してみないとわからないモノもあります。そんな時は一度レンタルやサブスプリクションを利用してみるのはいかがでしょうか?
今はいろんなものがレンタルでき、そのまま買い取れるサービスもあります。しっかりイメージしたつもりでも、なんとなく使い勝手が悪かったり、家の雰囲気に合ってないなどの不安を解消するのにおすすめです。家電や家具は簡単に買い替えができないので、一度試せると安心感もあります。
例えばsubsclifeは最新の家電を月額500円から利用できます。合わなければ返却もできますし、気に入ったら購入も可能。購入前に試せるため、無駄な出費にも不用品にもなりません。
サスティナブルな商品を選択しよう
また、最近ではサスティナブルな商品も増えています。サスティナブル商品は、地球環境に配慮したものです。包装にも気を遣っており、リサイクルできるものやプラスチックを使用してないものなどもあるため、ゴミの削減を目指せます。最近では専門サイトも登場しているので、買い物の選択肢のひとつとしてチェックしてみてはいかがでしょうか。
他にも工夫ひとつでモノは減らせる
他にも買い方や使い方を工夫することで、モノを増やさずに暮らすことができます。例えば、
など、買う物自体が減れば、家の中をシンプルにできゴミも自然と減っていくでしょう。
ミニマムに関するよくある質問
ミニマムについてネットやSNSに寄せられている質問の一部を紹介します。その回答とあわせてご覧ください。
「ミニマムな会社のビジネス」とは?
ミニマムな会社のビジネスと表現されているのは、一般的にはマイクロ法人です。
マイクロ法人というのは、従業員を雇用せずに会社の代表者1人で事業を行なう会社のことです。個人事業主やフリーランスで仕事をしている人が法人化するとマイクロ法人になります。
マイクロ法人にすることにより税務上のメリットを受けられるため、個人事業主・フリーランスの中にはマイクロ法人を目標にする人が増えています。
ミニマムな生活は大変?
ミニマムな生活は一人暮らしなら問題ありませんが、物を増やしたい家族と生活している場合には大変になります。
生活スタイルや美意識が異なる場合、不要だと思って断捨離したものが家族にとって大切なものだった場合、家族間でトラブルが発生するからです。
ミニマムな生活をしたいという認識が共通している人との生活なら、物が最小限でも心は充実した状態で生活できるでしょう。
ミニマリストに向いている人の特徴は?
ミニマリストに向いているのは、以下の特徴を備えた人です。
- 衝動買いをしないで計画的に物を購入できる
- 不要だと思ったものはすぐに処分できる
- 自分に必要なものを見極められる
この3つに該当する人ならミニマリストとして生活できます。
ミニマルな暮らしとSDGs目標12「つくる責任つかう責任」との関係

ミニマルな暮らしの実践は、最近耳にする機会が増えたSDGsの達成にも関連します。
SDGsとは、Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略で、2015年9月に国連サミット加盟国で採択された国際目標です。2030年までに持続可能でより良い地球を作ることを目指しており、地球上で「誰ひとり残さない」ことを誓った、全世界で積極的に取り組むべき目標です。
また、SDGsには17の目標があり、その目標はさらに細かく169のターゲットに分けられていることも特徴です。
ミニマルな暮らしは、「ひとつのモノを大切に長く使う」ことが一般な考え方であるため、価格ではなく質に焦点を当ててモノを選択する傾向にあります。そのため、
目標10「人や国の不平等をなくそう」
ファストファッションなどの安価な商品を購入しないことで、生産者に適正な金額が渡る
目標13「気候変動に具体的な対策を」
目標14「海の豊かさを守ろう」
目標15「陸の豊かさも守ろう」
大量生産や廃棄を抑制できるためCO2の削減に貢献できる
など、さまざまな目標の達成に貢献できます。そのなかでも特に関係するのが目標12「つくる責任つかう責任」です。
特にSDGs目標12と関係
SDGs目標12は「つくる責任 つかう責任」、持続可能な消費生産形態を確保するとなっています。
SDGs目標12で挙げられる課題のなかのひとつが、食品廃棄や有価物(鉄・アルミ・古紙類・古布類など)などの投棄、無駄な資源の浪費です。
日本国内では年間約600万トンもの食べられるのに捨てられている食べ物があります。また、捨てられている衣類は年間100万トンにもなります。課題の解決のためには、つくる側は
- 少ない資源でより質の良いものを生み出す生産方法
- 今ある資源を活用し、新たな資源を生み出す方法
を考え、つかう側は、
- ひとつのものを長く使う意識を持つ
- エシカル消費を心がける
必要があります。
つまりミニマルの実践は、目標12にぴったりな生活様式であると言えるでしょう。
まとめ
この記事ではミニマルなライフスタイルとSDGsとの関わりをご紹介しました。
今のまま大量生産・大量消費を続けていけば、環境破壊は進み、気候変動による災害も増える一方です、また、いつまでも不平等な労働をしいることでさらなる貧困差が生まれます。
今の快適な地球での暮らしを持続するためには、ひとりひとりのライフスタイルの改善と見直しが必要です。ミニマルな生活をすることは、ただ少ないモノで暮らすだけではなく、地球にやさしい選択をすることです。
今まで、私たちはより多くの物を持つことで豊かさを実感してきました。しかし、たまに多くの情報やモノに振り回され、「しんどいな…」と感じることはありませんか?自分にとって大切なものを丁寧に選別することで、人と比べず自分自身の幸せと向き合うことができます。
過去や未来に執着せず、今をていねいに生きることは持続可能な未来につながるのかもしれません。
この記事を書いた人
スペースシップアース編集部 ライター
スペースシップアース編集部です!
スペースシップアース編集部です!