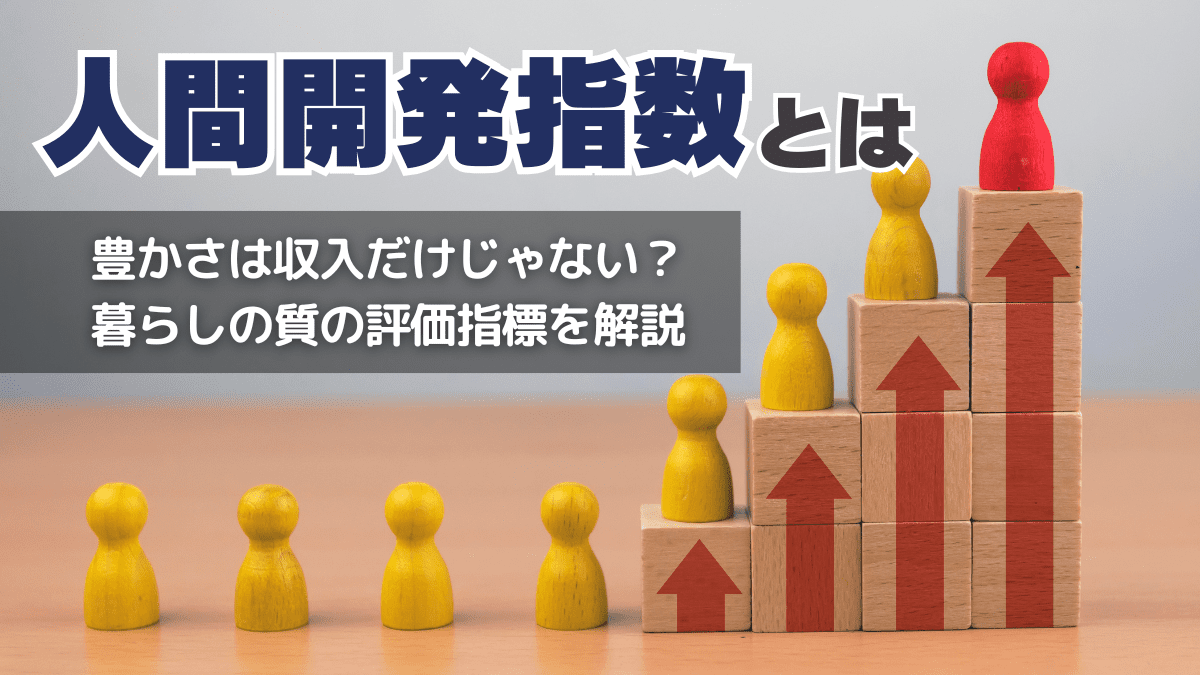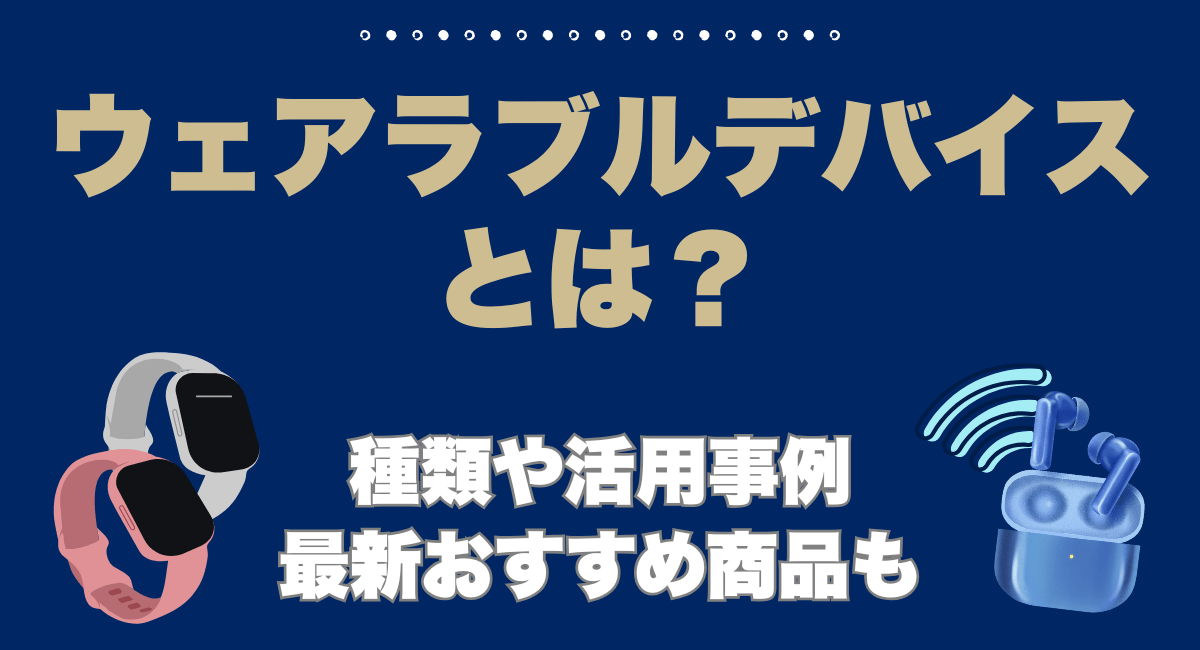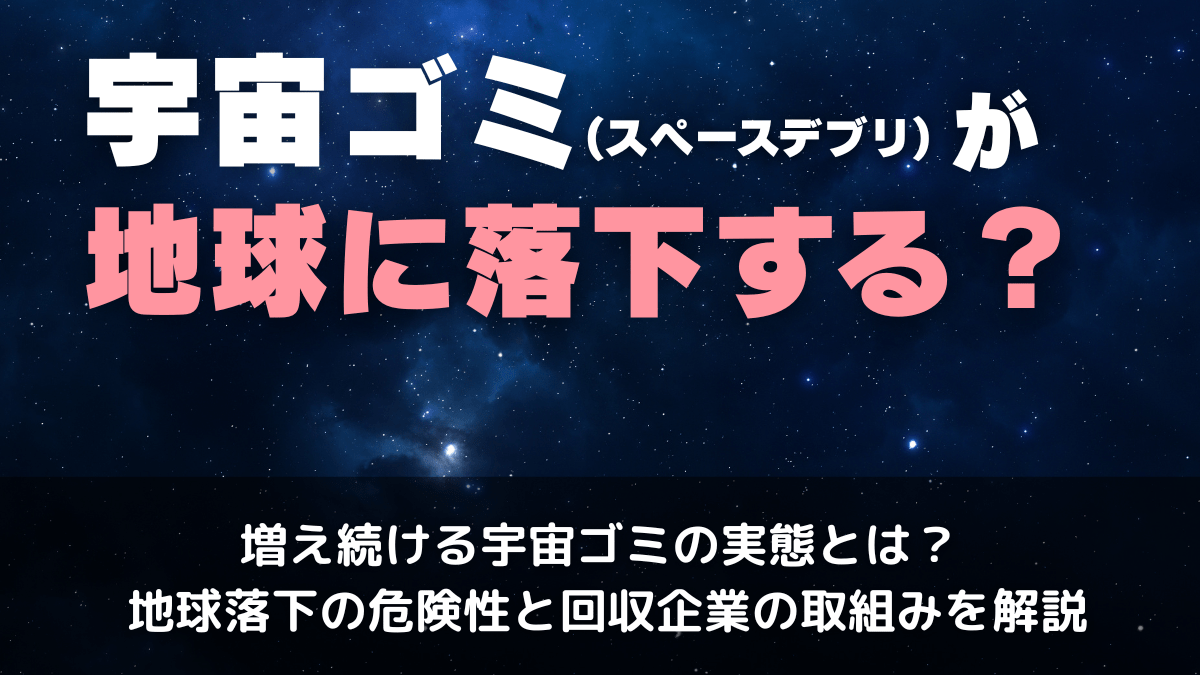1944年夏、戦局の悪化とともに、アメリカ軍による本土空襲が目前に迫っていました。都市に住む多くの子どもたちを守るために行われたのが学童疎開です。見慣れた風景や大切な家族と離れ、慣れない土地での生活は、子供たちにとって期待と不安が入り混じる日々だったでしょう。
当時8歳から12歳だった子どもたちは、見知らぬ土地で友人や先生と寝食を共にしながら、勉強や農作業に励みました。まさに戦争が子どもたちにもたらした過酷な体験といえます。
今回は小中学校の歴史で学ぶ「学童疎開」について、その目的や一日の流れなどを詳しく見ていき、当時の子供たちの生活を紐解いていきます。戦争の影響を大きく受けた子どもたちのことを考えながら、当時の状況を一緒に学んでみましょう。
目次
学童疎開とは
学童疎開とは、戦争の状況が悪くなる中、国が都市部の国民学校初等科に通う子どもたちを、空襲の被害を受けにくい郊外や農村部に一時的に移住させた措置のことです*1)。 子どもたちを戦火から守る「疎開」は日本だけではなく、イギリスやドイツ、ソ連でも実行されました*2)。
目的
学童疎開の目的は、主に以下の3つです。
- 本土空襲から子どもたちの命を守るため
- 空襲時の混乱を避けるため
- 戦意の衰えを防ぐため
サイパン島は日本政府が絶対に守らなければならない重要な防衛拠点と考えていましたが、1944年7月7日に守備隊が全滅し、アメリカ軍に占領されてしまいました。アメリカ軍はこの島に飛行場を整備し、B-29という長距離爆撃機の発着基地として使用し始めました。
B-29はとても航続距離が長く、サイパン島から日本の主要都市のほとんどを爆撃できる範囲にありました。そのため、日本の都市部は深刻な空襲の脅威にさらされることになりました。確実に爆撃から子どもを守るには、都市から避難させるしかなかったのです。
戦争中に都市で空襲があると、人々はパニックになり、あたりは大変な混乱に陥ります。 そこで、子どもたちだけでも安全な田舎に避難させれば、空襲時の混乱を少しでも減らすことができます。 また、大切な子どもたちを空襲から守ることで、人々の戦意が弱まってしまうのを防ぐという狙いもありました。
対象となった児童
学童疎開の対象となったのは、東京都や横浜、川崎、大阪、神戸、名古屋など全国18の都市にいる国民学校初等科の3~6年生の児童*3)です。
縁故疎開と集団疎開の違い
学童疎開は縁故疎開と集団疎開に区分できます。
【縁故疎開と集団疎開の違い】
| 縁故疎開 | 親類や知人を頼って行う疎開*5) |
| 集団疎開 | 学校単位で行う疎開学童疎開というと、集団疎開を指すことが多い*6) |
1944年6月30日に閣議決定された「学童疎開推進要綱」によると、縁故疎開を強力に進める一方、集団疎開は保護者の申請に基づくとしました。
戦局が悪化した1945年3月9日には、「学童疎開強化要綱」が閣議決定され、初等科3年生以上は全員疎開させることとし、1・2年生は縁故疎開と集団疎開を実行するとしたのです*3)。
学童疎開が実施された時期
学童疎開は、1944年8月から始まりました。太平洋戦争が終わる1945年8月15日まで続き、疎開先から子どもたちが完全に帰宅したのは、終戦から3か月後の1945年11月でした*3)。
学童疎開先での生活の様子
学童疎開で親元を離れた子供たちは、どのように過ごしたのでしょうか。ここでは、疎開先での一日の流れと、疎開先での食事について解説します。
一日の流れ
港区教育委員会のサイトに掲載されている氷川国民学校 金剛寺学寮の日課表を見てみましょう。
【1945(昭和20)年4~5月の日課表】
| 6:30 | 起床→洗面・清掃・駆け足 |
| 7:00 | 朝礼・体操 |
| 7:15 | 朝食 |
| 8:10 | 授業:1時間目 |
| 9:10 | 授業:2時間目 |
| 10:00 | 授業:3時間目 |
| 11:00 | 授業:4時間目 |
| 12:20 | 昼食 |
| 13:30 | 作業・運動、耕作 |
| 14:30 | 作業・運動、耕作 |
| 16:30 | 清掃 |
| 17:30 | 夕食 |
| 18:00 | 夜の行事、自習、園芸、散歩 |
| 19:30 | 就寝用意 |
| 20:00 | 消灯 |
| 21:30 | 職員就寝 |
朝の駆け足は、体力をつけるために毎日行っていました。午後の耕作では野菜やサツマイモを作っていたことが記録されています。また、男性の教員が防空壕を作っている様子なども記載されています。
授業が行われたのは、疎開先の寺でした。そのため、地元の学校に合流して授業を受けることはなかったようです。このような状況で、130名ほどの児童と教職員が疎開を行っていました。
学童疎開のメリット
第二次世界大戦中、日本政府は学童疎開を実施しました。この政策には、都市部の子どもたちを空襲の危険から守り、命を救うという大きな意義がありました。学童疎開のメリットについて見てみましょう。
子どもを空襲から守れる
アメリカ軍による日本本土への空襲は1944年から激しさを増していきました。特に、日本の戦意を失わせる目的で、大都市を広範囲にわたって爆撃する作戦が展開され、一般市民の犠牲者が多数出ました。
この時期、地方への疎開が推し進められましたが、すべての人が避難できたわけではありません。疎開が間に合わずに犠牲となった子どもたちがいる一方で、間に合ったことで命をつなぐことができた子どもたちもいました。
太平洋戦争末期の本土空襲では、多くの都市が焼き尽くされ、多数の人々が亡くなりました。この甚大な被害を考えると、疎開は多くの命を救う重要な役割を果たしたと言えます。
学童疎開のデメリット・問題
学童疎開には、子どもたちの命を救ったというメリットだけではなく、いくつかのデメリットがあります。ここでは、学童疎開のデメリットや問題について解説します。
子どもたちの間でいじめなどが起きた
学童疎開により都市部から田舎へ移動してきた児童たちは、地元の子どもたちとの間でいじめの問題に直面することがありました。特に疎開直後は両者の交流が少なく、地元の子どもたちから「疎開っ子」や「青白いっ子」といった差別的な言葉を投げかけられ、休み時間などに集団で囲まれるような嫌がらせを受けることがありました。
教師は事前にそうした事態を予測し、「気にするな」と児童たちに助言していました。そのため、多くの児童は我慢していましたが、中には耐えきれず「気持ち悪い」「喧嘩してみようか」と訴えてくるケースもあったといいます。このように、環境の異なる児童同士の間で軋轢が生じ、いじめという形で表面化していたのです*8)。
親から離れることで子どもの情緒が不安定になった
学童疎開では、親元から離れて生活することを余儀なくされた子どもたちの心の不安定さが様々な形で表れていました。疎開開始から約1週間が経過すると、夕暮れ時に涙を流す児童が現れ始め、疎開先の家族に対して帰宅願望を打ち明ける子どもも出てきました。
また、家族に引き取りを懇願する手紙を書く児童もいました。なかには耐えきれずに宿舎から逃げ出す子どももおり、実際に栃木県足利市から麻布まで2日間かけて徒歩で帰宅した6年生男子の事例も報告されています*9)。
このような子どもたちの行動からは、親との突然の別れが幼い心に大きな動揺を与え、深刻な情緒不安を引き起こしていたことが明らかです。
集団行動で自由がなかった
学童疎開中の児童たちの生活は、朝6時30分の起床から夜8時の消灯まで、すべての時間が細かく管理された集団行動でした。先ほど取り上げた集団疎開の一日を見ると、朝は起床後すぐに洗面や清掃、駆け足といった活動が始まり、朝食までの時間も決められていました。
午前中は4時間の授業を受け、昼食後は作業や運動、耕作などの労働に従事しました。夕方以降も夜の行事や自習などが組み込まれており、子どもたちが自由に過ごせる時間はほとんどありませんでした。
このように、一日中他の児童たちと行動を共にし、自分の意思で行動を選択する余地がない生活を送っていました。特に、通常の学校生活では経験しない農作業などの肉体労働が含まれており、児童たちにとっては精神的にも身体的にも負担の大きい日々だったかもしれません。
学童疎開に関してよくある疑問

ここからは、学童疎開に関するよくある疑問に答えていきます。
食事はどうした?その費用は?
戦時中の学童疎開では、食べ物が極めて不足していました。当時12歳で疎開を体験した八ツ橋さんによると、支給されたご飯にはサツマイモやカボチャが混ぜられていましたが、味は良くなく、量も十分ではありませんでした。
子どもたちは常に空腹に悩まされ、その対策として野山に生える桑の実やホオズキの実を探して食べたり、使わなくなった草鞋を乾燥サツマイモと交換したりしていました。
親が面会に来る際には、お菓子を持ってきてもらうよう手紙でお願いすることもありました。しかし、貴重なお菓子を一人占めしようとして食べ過ぎ、体調を崩してしまうこともあったそうです*10。
このように、疎開児童たちは深刻な食糧不足の中で過ごしており、彼らの証言からは、戦争によってもたらされた食糧難の厳しさを痛感させられます。
子どもたちの食費については、保護者が10円を負担し、それ以外についてはすべて市が負担することになっていました*11)。
疎開先で死亡してしまうこともある?
児童が疎開先に移動する最中や疎開先で亡くなることはありました。移動中の事件として有名なのが「対馬丸事件」です。
また、慣れない環境での生活は、多くの人々、特に体の弱い子供や高齢者にとって過酷なものだったのです。栄養状態が悪化したり、衛生状態の悪い場所で暮らさざるを得なかったりした結果、病気にかかり命を落としてしまう人も少なくありませんでした。
加えて、戦争の影は疎開先にも容赦なく忍び寄り、米軍機の機銃掃射によって犠牲になる人もいました。さらに、避難場所として頼みの綱であった寺院が火災に遭い、逃げ遅れて命を落とすという痛ましい出来事も起こりました。
このように、疎開は決して安穏なものではなく、多くの人々が様々な困難に直面し、命を落とす危険と隣り合わせの逃避行だったのです。
体験談を知りたい
学童疎開を経験した方たちはかなり高齢になっているため、直接話を聞くのは難しくなりつつあります。しかし、各自治体が収集した体験談を、WEB上で閲覧することができます。
【自治体で公開している学童疎開の体験談】
上記以外にも、多数の体験談が公開されています。また、各自治体の歴史(自治体史)に収録されている事例もあるため、そちらを閲覧してもよいでしょう。
学童疎開とSDGs目標4との関わり
学童疎開と「質の高い教育をみんなに」というSDGs目標4は、深い関連性を持っています。戦時中の学童疎開では、空襲から子どもたちの命を守るため、教育の場を都市部から地方へ移す必要がありました。しかし、急遽設けられた学習環境は十分とは言えず、教育の質を維持することは困難でした。
この経験は、SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」を実現することの重要性を私たちに考えさせます。平和な社会の構築には、すべての子どもたちが質の高い教育を平等に受けることができる環境が不可欠です。
現代の日本では、学校に通うことは当たり前の権利として認識されていますが、学童疎開の経験は、この権利がいかに貴重で、守るべきものであるかを示しているのです。戦争という悲劇を繰り返さず、誰もが安心して教育を受けられる平和で持続可能な社会を築いていかなければなりません。
まとめ
今回は、学童疎開について解説しました。学童疎開とは、第二次世界大戦中、都市部の子供たちを空襲から守るため、地方へ集団疎開させたことです。
子供たちの命を守るという大きな目的がありましたが、一方で、生活環境の変化や親元を離れることによる精神的な負担など、様々な問題も引き起こしました。食事も満足に与えられないなど、当時の子供たちは多くの困難に直面しました。
学童疎開は、戦争の悲惨さとともに、平和な社会における教育の重要性を改めて認識させてくれる出来事と言えるでしょう。
参考文献
*1)共同通信ニュース用語解説「学童疎開」
*2)百科事典マイペディア「学童疎開」
*3)日本大百科全書(ニッポニカ)「学童疎開」
*4)文部科学省「一 国民学校令の公布」
*5)デジタル大辞泉「縁故疎開」
*6)デジタル大辞泉「集団疎開」
*7)港区教育委員会「デジタル港区教育史」
*8)中央区「体験記 人間、孤立していてはだめ」
*9)港区教育委員会「(2)集団疎開先でのくらし」
*10)中央区「体験記 つらかった学童疎開」
*11)レファレンス協同データベース「戦時中の学童疎開の経費は、どこの予算枠であり支出額はどうだったのか。また、国・府・市負担、保護者負担などについても知りたい。」
*12)日本大百科全書(ニッポニカ)「対馬丸事件」
この記事を書いた人
馬場正裕 ライター
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。
元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。