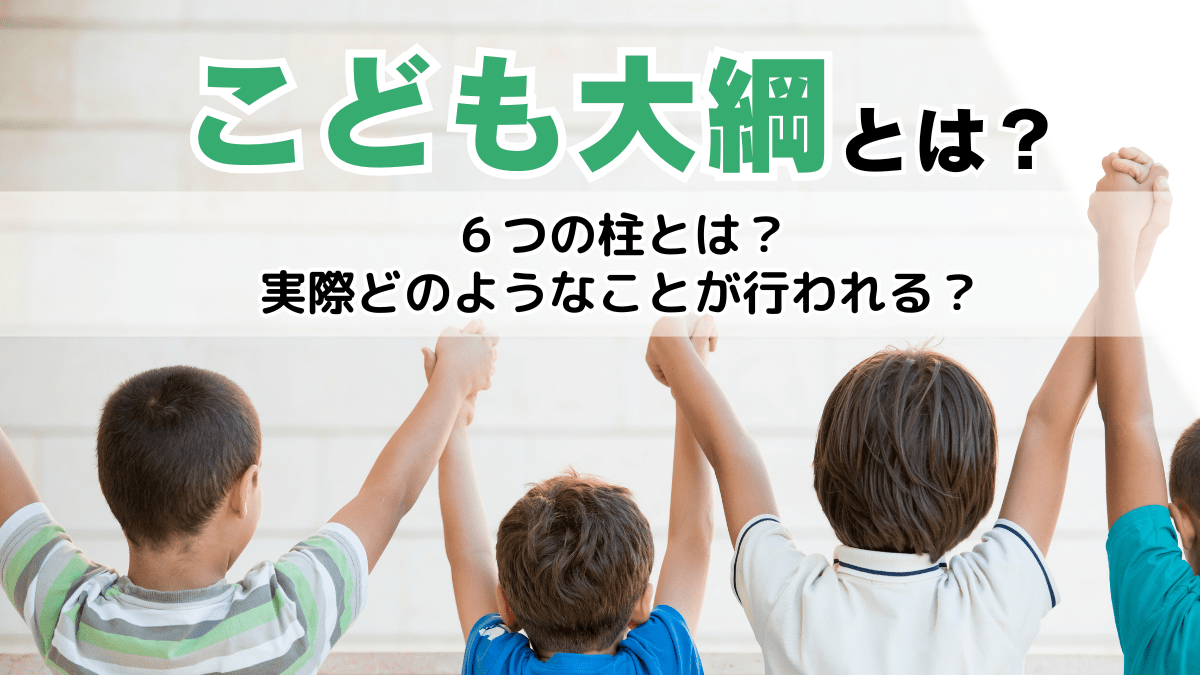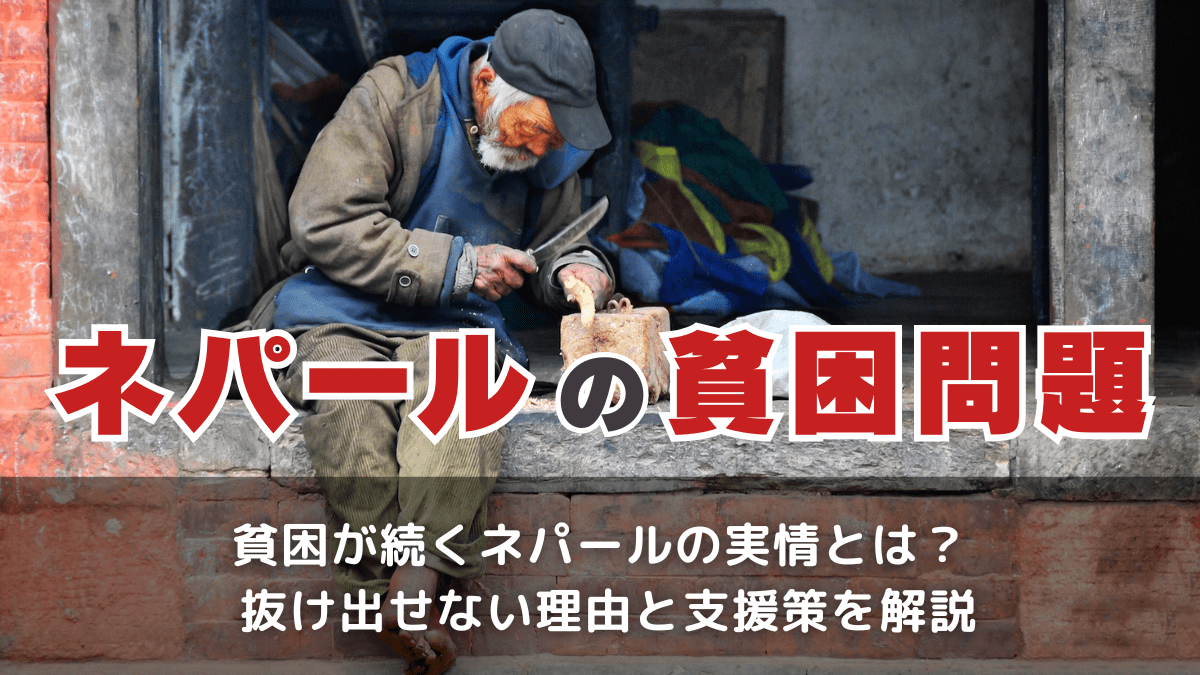「社会的再生産って、なんだか難しそう…」
そう思う方も多いかもしれません。一見難しそうですが、実はあなたの日常生活に深く関わっています。
社会的再生産は、社会の仕組みや価値観が世代を超えて継続的に再生産されるプロセスを指します。社会的再生産について具体例を交えてわかりやすく解説し、社会の仕組みを理解することで、
- あなたがどのように社会から影響を受けているのか
- あなたはどのように社会に影響を与えることができるのか
など、新たな視点を提供します。
目次
社会的再生産とは

社会的再生産とは、社会を維持するために必要な、人々の生活や社会関係を継続的に作り出すプロセスのことです。
社会的再生産は、社会の存続にとって不可欠なプロセスです。社会的再生産がうまく機能しないと、
- 社会の階層の維持
- 格差の拡大
- 社会の不安定化
などの深刻な問題を引き起こす可能性があります。
社会的再生産の3つの要素
社会的再生産は、以下の3つの要素から構成されています。
生産・分配・消費
社会における、物やサービスの生産、分配、消費を継続的に行うことで、社会の経済活動を維持します。
教育・養育・介護
人々の知識やスキル、健康を継続的に向上させることで、社会の人的資源を維持します。
社会関係の維持・強化
人々の相互作用や協力を継続的に促すことで、社会の秩序や安定を維持します。
【日本の環境変化及び、ものづくり現場が目指す方向性】
社会的再生産の在り方は、時代とともに変化していきます。現在も世界は持続可能な社会の構築のために急速な変化の最中にあるのです。
そもそも再生産とは
そもそも再生産とは、あるものが、
- 次世代の存続
- 福祉
- 消失・消耗の補充
- 成長・進化・変化を促す
などのために、新しいものに生まれ変わることです。
例えば、植物や動物は、種や卵から新しい個体を生み出します。これは、生物の種を存続させるための重要な再生産のプロセスです。
文化的再生産との違い
文化的再生産とは、社会や共同体における言語、習慣、伝統、芸術、宗教など、文化的な要素や価値観を維持し、次の世代に伝えていくことを指します。文化的再生産は社会的再生産の一部です。
社会的再生産は、社会や経済の中で行われる活動や努力によって社会の維持や発展を行うことなどの、文化的再生産より広義の人間が行う再生産を指します。
【関連記事】文化的再生産論とは?及ぼす影響や問題点、文化資本についてもわかりやすく解説
社会的再生産は、個人や家族が行うだけでなく、企業や政府、非営利団体など、さまざまな主体が協力して行っています。また、経済活動や環境問題など、さまざまな社会課題と密接に関係しています。
社会的再生産がうまく機能することで、社会は安定し、人々は安心して暮らすことができるのです。次の章では、もう少し詳しく、社会的再生産について確認していきましょう。*1)
具体例を交えて社会的再生産をわかりやすく説明

社会的再生産は主に、
- 労働力の再生産
- 生産手段の再生産
- 経済的再生産
- 文化的再生産
で構成されています。これらの要素が互いにつながり合いながら、社会全体の再生産のプロセスを形成しています。それぞれを具体例を交えながら見ていきましょう。
労働力の再生産
労働力の再生産とは、人々が労働に従事できるようにするために必要な条件を再生産することです。子育てや教育、健康管理などを通じて、人々が労働に必要な知識や能力を身につけ、健康を維持できるようにする活動を指します。具体的には、
- 母親が赤ちゃんを育てる
- 子どもが学校に通って勉強する
- 大人たちが健康診断を受ける
などが、労働力の再生産に含まれます。また、人々が労働に従事できるようにするためには、労働へのモチベーションや、働きがいなどの心理的要因も重要です。
【関連記事】健康経営とは?SDGsとの関係やメリットと企業の取り組み事例を紹介
これからの日本にとって、労働力の再生産は非常に重要かつ大きな課題です。少子高齢化やデジタル化の影響で、現代の社会に必要とされる人材は高度経済成長期から様変わりしました。
高度経済成長期には、大量生産や労働力の需要が高まり、単純作業やルーティン業務に長けた人材が求められていましたが、
- クリティカルシンキング:情報の洞察力や分析力を持ち、論理的に考える能力
- コミュニケーション能力:他者との円滑なコミュニケーションができる能力
- クリエイティビティ(創造性)::新しいアイデアや解決策を生み出す力
- グローバルマインドセット(国際的な視野):情報技術を活用し、デジタルツールやプログラミング言語を使った仕事ができる能力
などが、これからの社会には求められています。
【これからの日本に求められる人材】
生産手段の再生産
生産手段の再生産とは、人々が労働するために必要な物や道具を再生産することです。農業や工業、建設などを通じて、食料や衣服、住居などの生産に必要な物や道具を生産する活動を指します。具体的には、
- 農家が種をまいて収穫する
- 工場で機械を製造する
- 建築業者が家を建てる
などが、生産手段の再生産に含まれます。物理的な道具だけでなく、知識や技術も生産手段として考えます。
【日本の製造業に起きている変化】
生産力の再生産の面でも、日本は持続可能な社会に向けて大きく変わりつつあります。
- 自動化
- デジタル化
- グローバル化
- AI
- サステナビリティ
などの要因で、製造業では生産プロセスが大きく変化し、サービス業ではオンラインやAIを活用した新しいサービスが普及しています。
経済的再生産
経済的再生産とは、社会の経済活動全体を再生産することです。生産、流通、消費の3つの過程を通じて、社会が継続的に存続するために必要な物やサービスを生産・配分・消費する活動を指します。具体的には、
- 農家が作物を栽培する
- 工場で製品を製造する
- 商店が商品を販売する
- 消費者が商品を購入する
などが、経済的再生産に含まれます。経済的再生産は、経済活動を通じて人々の生活を豊かにし、社会を安定させることも重要な目的です。
経済的再生産の面でも、世界は急激で予測の難しい変化の中にあります。
- 気候変動
- 経済成長の鈍化
- グローバル化
- デジタル化
- 格差の拡大
などに影響され、世界的なインフレ※や政策金利の上昇が起きています。日本はインフレや政策金利※の上昇の点では比較的安定を保っていますが、それとは別に少子高齢化や賃金上昇率の鈍化などの大きな課題があります。
【世界の消費者物価指数※と政策金利の推移】
【日本の将来人口の予測】
今後、日本の社会的再生産における、さまざまな課題を解決するために、
- 包摂的な社会:すべての人々が平等に機会を享受し、尊重される社会
- 持続可能な経済成長:環境に優しい経済活動を推進
- 教育の充実:すべての人々が適切な教育を受ける機会を持つ
- 社会的な共有と協力:企業、個人も社会全体の利益を追求する
- 多様性と包容性:異なる人々や文化、価値観を尊重し、受け入れる社会
などを実現する取り組みが必要です。
文化的再生産
先述した文化的再生産の具体例としては、
- 学校で学ぶ
- 伝統的な行事を受け継ぐ
- 芸術鑑賞や音楽鑑賞を楽しむ
- 宗教を信仰する
などが、含まれます。文化的再生産では、人々の価値観やルールを形成し、社会の秩序を維持することも重要な役割です。
社会的再生産の概念を通じて、私たちの日常生活がいかに社会全体のシステムとつながっているかを理解することができます。個々の行動が集まって大きな流れを作り出し、それがまた私たちひとりひとりに影響を与えている、この循環性が社会的再生産の本質であり、社会を動かす大きな力なのです。*2)
資本主義以前の社会における社会的再生産

資本主義が誕生する以前、人々はどのように生活し、社会はどのように機能していたのでしょうか。そして、資本主義が登場した後、その構造はどのように変化したのでしょうか。
ここでは、資本主義以前の社会と資本主義以後の社会における社会的再生産の違いについて探っていきます。
資本主義とは
資本主義は、生産手段が私有され、利益追求が中心となる経済システムです。このシステムでは、物を作るための道具や設備を持っている人が、他の人を雇って働かせ、働く人は、自分の力を商品として売ります。資本主義は、市場経済と競争を基盤としており、他者との競争に勝つために、より良い商品やサービスを提供することで、利益を最大化することを目指します。
資本主義以前の社会における社会的再生産
資本主義以前の社会では、社会的再生産は共同体や家族単位で行われていました。例えば、農業社会では、農民たちが共同で農作業を行い、家族、集団単位で協力して食料を生産しました。
また、世界の多くの地域で、宗教は社会的再生産の重要な役割を果たしていました。宗教により、社会の秩序を維持したり、人々は働く意欲を得たりし、また文化の継承や社会の一体感の形成の役割も果たしていました。
現代の社会的再生産と課題
現代の社会では、資本主義の進展により、社会的再生産の責任が個人から国家や市場へと移行しています。教育や医療などの社会的なサービスは、国家や市場によって提供されることが一般的になりました。
しかし、資本主義の中での再生産のあり方には課題も存在します。格差の拡大や環境問題など、社会的再生産の公平性や持続可能性についての懸念が高まっています。
【日本の目指す新しい資本主義】
このように、資本主義以前の社会では、社会的再生産は現在よりも小さな単位で行われていました。現代の社会では、国家や市場が教育や医療などのサービスを提供していますが、公平性や持続可能性に課題があります。
これからの社会の発展には、より公正で持続可能な社会的再生産のあり方が求められています。次の章では、現在日本の社会的再生産に起きている「個人化」について探っていきましょう。*3)
社会的再生産と個人化について
資本主義以前の社会では、社会的再生産は、家族や共同体のメンバーが互いに助け合うことで行われていました。そのため、個人は社会に強く依存し、独自の価値観や生き方を持つことは困難でした。
しかし、時代とともに社会的再生産のあり方は変化し、個人化の流れが進んでいます。ここでは、社会的再生産の個人化について解説します。
社会的再生産の個人化
社会的再生産の個人化とは、社会における階層や格差が、個人の努力や選択によって決定されるようになることです。以前は、家族や地域の人々が大切なことやルールを教えてくれる役割を担っていました。しかし現代では、テレビやインターネットなどのメディアがとても影響力を持っています。
具体的には、SNSやWebサイトを通じて、個人が自発的に情報を取り入れ、自分の価値観やライフスタイルを形成していくことを指します。以前ほど家族からの強制はなくなり、個人の選択の自由が大きくなったことが個人化の背景にあると考えられています。
このことから、わたしたちひとりひとりが主体的に社会のルールを学び、自分の中に取り入れる必要があります。
【人生100年時代の社会人に必要な基礎力】
社会的再生産の個人化の課題と求められるもの
社会的再生産の個人化は、個人の努力や選択が、社会における地位や収入を決定する上でより重要な役割を果たすようになることです。そのため、社会の活性化につながる一方で、
- 格差の拡大:努力や選択の機会に恵まれた人々が有利になり、格差が拡大する
- 社会の分断:努力や選択ができない人々が疎外感や孤立感を抱きやすく、社会の分断につながる
などの問題を引き起こす可能性もあります。
【社会的再生産(人的資本)のための3つの視点と5つの共通要素】
このような社会的再生産の個人化における課題を解決するために、
- 格差の是正:努力や選択の機会に恵まれない人々に対する支援を強化
- 社会の包容性:多様な価値観や生き方を認める社会を構築
などの取り組みが必要です。
【コロナ後に求められる社会像】
社会的再生産と個人化は、相互に影響し合う関係にあります。社会的再生産が個人化を促進し、個人化が社会的再生産を変容させます。
時代の変化に取り残されないために、常に新しい情報や知識を得られる環境を整え、新たな挑戦を続けることが大切です。この次は、社会的再生産とSDGsがどのようにつながっているかを確認しましょう。*4)
社会的再生産とSDGsの関係

社会的再生産は、SDGsの目標達成に向けた重要な手段となります。たとえば、SDGs目標1「貧困をなくそう」を達成するためには、貧困層の支援や格差の是正が必要です。
社会的再生産は、このような課題に取り組むための活動や政策を支援し、実現に向けた具体的な行動を促す役割を担っています。社会的再生産がうまく機能することで、以下のSDGs目標の達成につながります。
- SDGs目標1「貧困をなくそう」
- SDGs目標2「飢餓をゼロに」
- SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」
- SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」
- SDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」
- SDGs目標8「働きがいも経済成長も」
- SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」
- SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」
- SDGs目標16「平和と公正をすべての人に」
【日本・世界の抱える課題と社会のニーズ】
これらのSDGs目標は、社会的再生産がうまく機能することで、大きく達成に近づきます。また、現代の社会的再生産には、SDGs(持続可能な開発目標)が欠かせない存在であるとも考えることができます。
つまり、社会的再生産がうまく機能することで、SDGsの目指す誰もが豊かで幸せに暮らせる持続可能な社会を実現することができるのです。*5)
まとめ

社会的再生産は、社会を維持するために不可欠なものです。責任ある社会人の一員として、社会的再生産についての知識を深めてください。
社会的再生産は、
- 少子高齢化
- グローバル化
- デジタル化
などにより、担い手や環境が変化しています。これらの変化に対応するために、社会的再生産に関する新しい考え方や制度が必要とされています。
そして、社会人として働き、生活を送ることであなたも常に社会的再生産を支える存在です。私たちひとりひとりも、社会的再生産のプロセスの変化に対応して、新しいスキルを習得したり、仕事や生活のスタイルを変化させたりしていくことが重要です。
社会的再生産にさらに貢献するために、できることはたくさんあります。
- 家庭や地域で、子どもや高齢者を支える
- 社会的サービスやジェンダー平等の推進に取り組む
- 持続可能な社会づくりに貢献する
- 家族の絆を大切にする
- 新しい時代に適応するためのスキルを身につける
など、持続可能でより良い社会や環境のためになる多くの活動が、社会的再生産を支えます。あなたも社会の一員として、あなたの特性や関心を活かした、あなたにできることを見つけ、活躍することで社会を活気づけましょう。
個人主義が進む中、価値観の多様化や地域のつながりの希薄化が起きています。それでも、互いを思いやる心や環境を大切にする精神など、人間社会にいつの時代でも必要なものは次世代に確実に受け継いでいきたいものです。
また、自動化やAI技術の進歩、少子高齢化により、私たちひとりひとりに求められるスキルや知識は変化しています。日本の社会的再生産を今後も支えるために、どのような人材が必要とされているかを理解し、生涯にわたって学び、成長し続けることを目指しましょう!
<参考・引用文献>
*1)社会的再生産とは
経済産業省『第2節 人手不足が進む中での生産性向上の実現に向け、「現場力」を再構築する「経営力」の重要性』
文化的再生産論とは?及ぼす影響や問題点、文化資本についてもわかりやすく解説
清水 亮『文化資本と社会階層-文化的再生産論の日本的展開に向けて』
高木 幸二郎『資本主義的再生産の前提の問題について』
高木 彰『社会的総資本の再生産過程と再生産表式分析』
農林水産省『ピエール・ブルデュー著「禁じられた再生産」ー経済的支配の象徴的側面についてー』
三輪 哲『新規開業における世代間再生産と社会的ネットワークの影響』
経済産業省『文化資本経営促進に関する調査研究事業 成果報告書』(2022年3月)
経済産業省『製造業を巡る動向と今後の課題』(2021年9月)
経済産業省『人生100年時代の社会人基礎力について』(2018年2月)
経済産業省『新しい健康社会の実現』(2023年3月)
経済産業省『未来人材ビジョン』(2022年5月)
経済産業省『事務局説明資料』(2021年5月)
経済産業省『健康経営の推進について』(2022年6月)
*2)具体例を交えて社会的再生産をわかりやすく説明
健康経営とは?SDGsとの関係やメリットと企業の取り組み事例を紹介
経済産業省『事務局説明資料』(2021年12月)
経済産業省『製造業を巡る現状と政策課題~Connected Industriesの深化~』(2018年3月)
経済産業省『「経済産業政策の新機軸」の進捗状況と今後の進め方について』(2022年11月)
経済産業省『2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について』(2018年9月)
申 琪榮『社会的再生産理論(SRT)を手かがりに読み解くコロナ禍』(2022年)
今野 晃『現代社会の再生産』
和田豊『社会的再生産における生産的労働と非生産的労働(1991年)
伊藤 武『マルクスの再生産論の論理』(2003年1月)
経済産業省『METI Journal 戦後日本経済の変遷くっきり。通商白書のキーワードを大解剖』(2023年7月)
*3)資本主義以前の社会における社会的再生産
経済産業省『数理資本主義の時代~数学パワーが世界を変える~』
経済産業省『経済産業政策の新機軸~6月総会での議論を踏まえた方向性~』(2021年8月)
首相官邸『新しい資本主義』
内閣府『第2章 持続的発展のための条件 序 明治以来の日本の経済』(2000年7月)
政府広報オンライン『新しい資本主義の実現に向けて』
*4)社会的再生産と個人化について
経済産業省『人生100年時代の社会人基礎力について』p.3(2018年2月)
経済産業省『未来人材ビジョン』p.53(2022年5月)
総務省『「誰一人取り残さない」デジタル化の実現に向けて』
正村 俊之『リスク・機能分化・個人化 ベック理論とルーマン理論との対話』(2016年)
澁澤 透『社会の「個人化」と教育学的発達研究の課題-人格発達論と自己形成論との架橋-』(2011年)
青木 紀『「見えない」貧困と不平等ーその世代的再生産』(2004年)
香川大学経済学部『政治経済学I––1. 政治経済学の対象と方法––』
落合 恵美子『第1章 1970 年代以降の人口政策とその結果―アジアにおけるケア
の脱家族化を中心に』
*5)社会的再生産とSDGs
経済産業省『SDGs』
経済産業省『「新産業構造ビジョン」⼀⼈ひとりの、世界の課題を解決する⽇本の未来』p.11(2017年5月)
この記事を書いた人
松本 淳和 ライター
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。
生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。